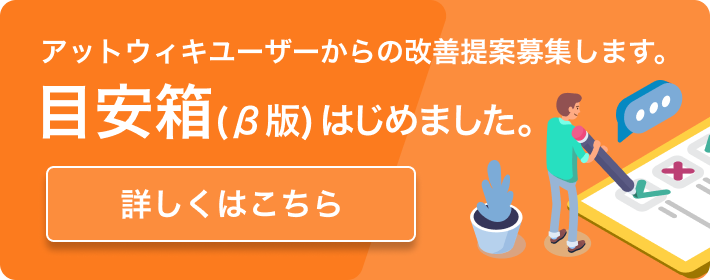ここ・・・どこだろう。
目覚めたところはビルの屋上。なぜか俺は、灰色のコンクリートの上で目を覚ました。
ぼやける視界に飛び込んでくるのは、どんより曇った空の色だけだ。
とりあえず体を起こし、まだ寝ぼけたままの頭を二、三回かいてから、俺は自分の今の状況を考え始めた。
確か昨日、学校で遅くまで部活をしていて、家へ帰って、宿題やって、風呂入って、飯食って・・・
いつもと同じような生活を送って、それから自宅の自分の部屋のベットで眠りについた・・・はずだ。
ならなぜ、俺はこんなとこにいるんだろう。
少なくとも俺は夢遊病なわけではないし、ビルの上で寝る趣味もない。だいたいここはどこなんだ。
俺は次から次へとわいてくる疑問を頭から消滅させた。
こういうときはあせらず騒がず、冷静に今自分のおかれている状況を見極めるのが先決だ。
とりあえず情報を集めようと、俺は立ち上がってビルの手すりのところまで行き、そこに身をあずけるようにして外を眺めてみた。
手すりの下には、今自分が立っているビルに良く似た灰色のビルが数多く立ち並んでいた。
典型的な都会の風景といったところだろうか。いかにも環境の悪そうな場所である。
しかし、そこにはいつも見慣れているのとはどこか違う、違和感を感じさせる何かがあった。
中途半端に薄汚れたビル、あちこちに止められている車、申し訳なさそうにその身を潜めている街路樹達。
何か、何かが足りない。
「・・・?」
人だ。
この街には人がいない。道路の上を歩いていないのはもちろん、ビルの窓からどの部屋をのぞいても似たような風景が連なっているだけだ。
無論、そのおかげで街は不気味に静まりかえっており、俺の立てた音と時折聞こえる風の音以外に、ここには音は存在しない。
少し気味が悪くなってきた。とにかくここから抜け出さなければ。しかしどうやって?
考えが袋小路に入ってしまいそうになったとき、たまたま振りむいた俺の視界に人影が映った。
いつからいたのかはわからないが、そいつは俺の背後のビルの屋上から見下ろすようにこちらを眺めているようだった。
光が逆光になっていて良くはわからないが、すらっとした体型や細くたれた尻尾が垣間見える辺り、ギコ族のAAらしい。
「お~い」
こちらに気づいていないのだろうかと思った俺は、手を振って大きな声で呼びかけてみた。
こちらの呼びかけに気づいたのだろう、向こうは体の向きを変え、一歩二歩とこちらに近づいてくる。
その時、俺の背中を何か電撃のようなものが走った。形容するのなら、嫌な予感という感じだろう。
あの人影が振り返ったとき、左手の辺りが太陽の光の反射によって一瞬鋭く光ったのだ。
その影が・・・俺の見間違えでなければだが・・・ナイフのようなものに見えたのだが。
俺の思考が別の方へと捕らわれている間に、人影はビルの縁へと昇っていた。
そして。
一瞬、影が消えたかと思った時には、もう人影は俺の目の前にいた。
人影の正体は青い皮膚に、スマートな体つきのギコだった。
その左手には、俺の頭のてっぺんから腰の辺りまではありそうな大剣が光に反射して鋭い光を放っていた。
ギコはその顔に生気のない笑みを浮かべたまま、ゆっくりと歩み寄ってくる。
間違いなくおかしい。こいつは狂っている。ギコの顔に浮かべられた笑みが、俺の第六感から恐怖を感じさせ、体の動きを奪っていく。
気づくと俺は、ゆっくりと後ろに下がり始めていた。だが、狭いビルの屋上だ。下がれる距離などたかが知れていた。
すぐにフェンスと背中が接触する。
金属のきしむ音と、突然の背中の妙な圧迫感に一瞬目をそらしたのがいけなかった。
視線を戻したときにはすでに大剣が振りかぶられており、手で体をかばうことも、声をあげることすらできないまま俺の体は―――
「―――っ・・・!?」
少年はベッドから飛び起きた。両手を使って自分の体をくまなく調べてみたが、どこにも切り傷らしきものは見つからない。
一通り確認し終わると、彼は目を閉じて破裂しそうなほど早い鼓動を沈めるために、そっと深呼吸を繰り返した。
彼の名前はリオ・レジタンス。近くの都立高校に通う、ごく平凡な高校生である。
部活は野球部、勉強は中の下といったところだろうか。
ちょっと変わったところといえば、黄色の毛並みを持つギコ族なのだが口のパーツがД(でー)ではなく-(ハイフン)が使われていて、どこか一般的なギ コよりは落ち着いた雰囲気があるところぐらいだろう。
そんなリオの悩みは、よく悪夢を見ることだ。
初めて見たのは中学生のときだった。その時は、朝起きたら大体の事を忘れてしまっていて、悪夢のことなど少しも記憶に残らなかった。
しかし次第に悪夢を見る頻度が増え、悪夢の内容もより現実的なものへと変化していった。
悪夢の内容はいつも決まっていて、どんよりと曇った人っこ一人いない街の中で、自分に良く似たギコに襲われる・・・というものである。
医者やカウンセリングを受けてみたりしたが、特に深刻な悩みがあるわけでもなくいたって健康な体なので、せいぜい不眠症とでも診断されるのが 関の山だった。
リオはだいぶ落ち着いてきたのを見計らって、冷や汗でぐっしょりとぬれた布団から這い出した。
よく見ればパジャマまでぐっしょりぬれている。これじゃ下着も湿っているだろう。気持ち悪いわけだよ、とリオは思った。
「リオ、大丈夫?またうなされていたみたいだけど・・・」
声のほうへと向いてみると、部屋の扉を半分開けて中を覗き込んでいた彼の母親らしき人物が立っている。
かわいらしいエプロンが小柄な体に良く似合う、モナー族の女性だ。
「うん、大丈夫」
リオは母親に背を向けると湿ったパジャマを脱ぎ捨てて、着慣れた制服に袖を通した。
まだ体には汗が少し残っていたものの、制服のひんやりした感触は不快感を取り除くには十分だった。
母親はリオが制服のボタンをとめているところにやってきて、まだ心配そうな声で聞いてきた。
「ホントに大丈夫?具合でも悪いの?」
「大丈夫だって。また少し、変な夢を見ただけだよ」
「また悪夢にうなされてたの?カウンセリングに行ったほうがいいんじゃないの?」
「いいっていいって、時々見るだけなんだから。それより朝飯用意しといて」
リオはまだ不安そうな母親を入り口から追い出し、ドアを閉めた。
いつものように布団をたたみ、パジャマを片付け、昨日のうちに用意しておいたかばんの中を確認する。
一通り中を確認し終わって、ふとカレンダーに目をやった。
今日の日付は21をさしていた。目線をゆっくり左に動かしていく。
・・・・・20・・・・・・・・19・・・・・・・・・18。リオは思わず息を飲み込んだ。
この前悪夢を見たのは18日、たった3日しか空いていない。明らかに悪夢を見る頻度が多くなっている。
始めは追われるだけだったのに、最近は殺されそうになることもしばしばだ。
これには、リオも恐怖と不安を感じずにはいられなかった。
「・・・いったいなんだって言うんだよ・・・」
リオは独り言のようにぼやくと、ゆっくりと下へと降りていった。
台所から漂うトーストの香ばしい香りが、少しだけ不安を取り除いてくれた。
結局この日もいつもと同じような学校生活で、リオも昼休みを終える頃には、悪夢のことなどすっかり忘れていた。
この日もいつもと同じように終わるものだと思っていた。
だがこの日が、リオにとって運命を変えるものになるとは、リオには知るよしもなかった。
午後五時。耳に慣れたチャイムの音が風に乗って聞こえてくる。夕焼けが赤々と染まり、カラスが何匹か飛び去っていくのが見えた。
彼の高校は定時制があるので、全日制の生徒は五時に帰るのが基本となっている。
グラウンドを見ると、まだ数人の一年がせわしなくトンボを動かしていた。
俺にもあんな時代があったな、などとリオが感慨深く眺めていたところ、
「リオ君、なにしてるの?」
ふと声をかけられ、振り向くとリオと同じ制服に身を包んだ女の子が立っていた。
彼女は、同じクラスのシィナ。リオの中学時代の幼馴染で、野球部のマネージャーを務めている。
成績優秀で性格もよく、そんな彼女には男女を問わず友人が多かった。
リオは、そんな彼女にほのかな恋心を抱いていた。
「いや、昔は俺も雑用してたなぁって考えててさ」
リオがほんのり赤くなってしまった頬を隠すように顔をそむけながら言うと、シィナはその横に歩み寄ってグラウンドを覗き込んだ。
「懐かしいね。リオ君、頑張ってたもんね。私も一年のときは失敗ばっかりだったなぁ・・・」
シィナは頭を軽くこぶしで叩くと、いたずらがばれた小さな子供のようにちょろっと舌を出して笑った。
こういうあどけないしぐさが、彼女のファンを増やしていることに気づいていない。
「でも今は立派なマネージャーだよ。みんな、シィナのおかげですごく助かるって言ってる」
「ありがとう。じゃあリオ君も、試合のほうでしっかり恩返ししてよね?」
「わかってるよ」
「あっ、ちょっと待ってて」
かばんを背負いなおし、帰ろうとしていたリオの両足をシィナが止めた。
「一緒にかえろ?途中までだけどさ」
いつもと同じ通学路も、二人で帰ってみると違うように感じる。
シィナとリオの二人は、近くの商店街を歩いていた。商店街といっても、ほそぼそとやっている店が多いので買い物客の数はまばらだ。
周囲の人のざわめきよりひときわ大きく響くシィナの高い声。歩いている人たちが、ちらほら二人を不思議そうに眺めてくるので、リオはなんだか気恥ずかしい。
(もしかしたら、カップルみたいに見えてるのかも・・・)
ついそんなことを考えて、リオは頬の筋肉が緩んでくるのを必死でこらえていた。
「ちょっとリオ君、私の話聞いてる?」
ふとシィナに視線を戻すと、彼女はほほをむくれさせながらリオの顔を覗きこんでいた。
「あぁごめん。ちょっと他のこと考えてて」
「もう、すぐに上の空になっちゃうんだから」
リオが言い訳しながら謝ると、彼女はすねたようにそっぽを向いて先に行ってしまった。
慌てて後を追いかけて、彼女の肩を叩く。
「ごめんごめん、ちゃんと聞くからさ。で、何の話?」
「・・・うん」
彼女は振り向いてリオの顔を見つめると、少しためらいがちに言った。
「あのさぁ、リオ君てなんか悩みとかある?」
「へっ?」
甘いことで埋め尽くされていたリオの脳は、突然の意外な質問に一瞬戸惑った。
「なんかさ、最近学校来るときくらい顔してるでしょ?それに授業中も居眠りばっかりしてるし、何かあったのかなって」
ああ、そういうことか。リオの脳はようやく質問の意図を理解した。同時に少しがっかりした。
だいたい学校で居眠りすることが悩みと関係あるのか?と突っ込みたい気分だったが、優等生の彼女にはそれがわからないんだろう。
「別に何もないよ。ただ最近少し夜更かししてて」
「ふ~ん。まぁないならいいんだけどさ」
リオはとりあえず適当なことを言って茶を濁しておいた。
実は悪夢を見るんだなんて言ったりしたら、おせっかいな彼女のことだ、市内の病院じゅうを引きずりまわされるに違いない。
そんな彼女は疑うそぶりを少しも見せず、リオに振り返って言った。
「なにか悩みとかあったらいってね。私でよければ相談にのるよ」
「うん。いろいろとありがとう」
「いいのいいの。選手のサポートはマネージャーの義務ですから!」
彼女は大げさに敬礼のポーズをとると、その白い歯をみせて笑った。
結局そんな感じで話題は学校のことへと流れていき、気がつけば二人の帰り道の分岐点へとついていた。
「じゃあ、私こっちだから。また明日学校でね」
彼女はおおげさに手を振ると、その小柄の体を闇の中へと消していった。
彼女の姿はすぐに見えなくなる。気づけば空は闇に包まれており、辺りは目をよく凝らさなければ見えないほどに暗くなっていた。
「楽しい時間とは、あっという間に過ぎるもんだよな・・・」
リオは独り言のようにそっとつぶやくと、自宅がある方向へと足を進めた。
とっとっとっ・・・
しばらくの間、リオの靴が発する規則的な音だけがそこを支配する。そのうちにリオは何か違和感を感じ始めた。
目線を右は左へと流す。いつもと変わらない帰り道なのだが、視界に生き物が入らない。
門限を過ぎてしまい急いで帰る子供達や、ふざけあいながら帰る他校の生徒達、買い物帰りの井戸端会議を楽しむおばさんたち、いつもごく自然に見ているものがそこにはなかった。
リオは次第に不安になってきた。その状況が、いつも見ている悪夢とあまりにも似すぎていたからだ。
次第に歩みを速める。心臓の音がまじかに聞こえ、冷や汗が背中から吹き出ているのがわかった。
「早くここを出なくちゃ・・・」
リオはっと息を呑み、突然歩みを止めた。思わず自分の口から漏れた言葉が、今朝自分を苦しめた悪夢と酷似していたからだ。
(この次はどうなんだっけ・・・)
リオは頭を抱えた。考えまいと思えば思うほど、次から次へと脳裏に悪夢の内容が映し出されていく。
そうだ。この次は後ろを振り向くんだ。
(馬鹿っ・・・)
意識しないよう考えたが、そのときにはもう遅すぎた。
リオはもうすでに、誰かが後ろをつけてきているように感じてしまっていた。
まるで刃物を突きつけられたかのように動くことができない。足に鉛がついたかのように動かない。
好奇心と恐怖心が渦巻いて、リオは後ろを向かずにはいられなくなった。
覚悟を決めて両目をつぶり、後ろを振りむくと両目の緊張をゆっくりと解いていった。
「・・・・・」
しばらくの静寂。
リオの目に映ったのは自分によく似たあの悪夢の登場人物ではなく、一匹のフサギコだった。
お世辞にも綺麗とはいえない濃い茶色の毛皮にに身を包まれたフサギコは、毛皮の下に垣間見える二つの緑色の目でリオを見返していた。
「え・・・えへへ・・・・・」
リオはとりあえず愛想笑いをしてみた。フサギコは表情を変えることもせず、そんなリオの様子を黙って見つめていた。
フサギコのさめた態度が、余計にリオをますます恥ずかしくさせていった。
「ごめんなさいっ!なんでもないんです!」
リオは謝罪の言葉を大声で叫びながら、真っ赤になった顔を背けて走り出そうとした時だった。
「ちょっと待て」
地面の下のほうから聞こえたのかと錯覚するような、低く重みのある声を背中から浴びせられたリオは、思わず歩みを止め振り返っていた。
当然、この辺りには二人しかおらず、発生源はフサギコであることは明白だ。
「あの・・・なにか用ですか・・・・・?」
呼び止めておきながら何の行動をおこそうともしないフサギコに、リオはおずおずと尋ねてみる。
当のフサギコといえば、リオの顔や体をまるでなめるような視線で眺めているだけだ。
リオがいい加減逃げ出そうかと思案をめぐらせ始めたところで、ようやくフサギコは口を開いた。
「リオ・レジタンス。高校二年生。身長175cm、体重58kg。両親と三人暮らしで、都立モナー高校に通っている。間違いはないか?」
「なっ・・・・・」
リオは頭を殴られたように感じた。見ず知らずの他人、今日始めて会ったはずの人物に、自分のことを詳細に言われてしまった。とっさのことに頭が真っ白になり、何も考えられなくなる。
「間違いはないか、と聞いている」
リオの様子を少しも気にもかけずに、フサギコは続ける。リオはまだショックから立ち直れず、口をパクパクと開閉することしかできない。
「肯定、と取ってよさそうだな」
フサギコは自分の毛皮に手を突っ込み、何かを探すように動かしながらリオへと距離をつめた。
リオは目の前の現実が信じられず、身を翻して逃げることもフサギコに抵抗することもせずに、その目の端に涙を浮かべ、立ち尽くしていた。
フサギコは、お互いの息が相手の体へと触れ合うところまで距離をつめる。
「・・・あんた・・・・・いったい誰なんだよ・・・・」
真っ白な頭から、かろうじてリオは声を絞り出した。だがフサギコは、おびえて震えるような声で発せられた質問には答えず、代わりに言った。
「お前を拘束させてもらう」
腹部に圧迫感、閃光、少し遅れて雷撃の音。
辺りがまた静寂に戻ったときにはリオにすでに意識はなく、かすかに痙攣しながらその場に倒れ伏していた。
フサギコはリオを見下ろし、スタンガンを自分の毛皮の中へと戻した。
それからゆっくりとかがみこみ、リオに意識がないことを確認すると背中に乗せて持ち上げた。
右手の毛皮を探る。不規則に生えたフサ毛の中から、黒光りした通信機らしきものを引っ張り出すと、変わらぬ低い声で言った。
「リオ・レジタンスの身柄を拘束した。任務完了だ。これより帰還する」
フサギコが言い終わると同時に二人の体を白い光が包み込んだ。
次の瞬間にはひときわ大きな光が放たれ、光が収まって辺りに静寂が戻る頃には二人の姿はどこにもなかった。
さっきまでリオが持っていたバッグだけが、闇に支配された道の上に横たわっていた。