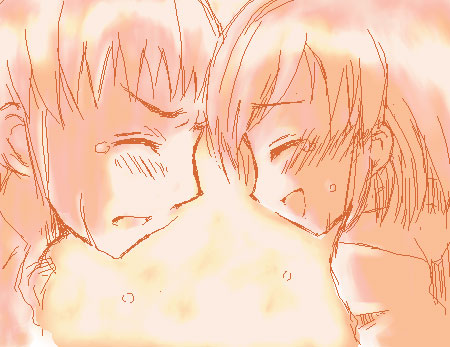一日が終わる二十四時。窓から見える世界は暗闇に包まれていた。
俺は今日という日に、主に、涼宮ハルヒよって作り出された、我が身に降り注がれる疲労感を一掃させるべく、いつもよりかは少し、早めに就寝しようと考えて、布団の中に入ろうとする行動を始めようとした、今、まさに、
「ブーッ、ブーッ」
ベットの上にある携帯が、小刻みに震えだす。
誰だよ、こんな夜中に。迷惑な野郎だ。きっと電話を掛けてきた相手も、俺の精神を不快にさせる人物に違いない。例えば?…古泉とか古泉とか古泉とか。
そしてもしも、この電話の相手が朝比奈さんだった場合、俺は、そこの窓から喜んで飛び降りようじゃないか。誰あろう朝比奈さんをあの年中ニヤケ面の不可思議超能力機関の一員なんぞと同じ扱いにしてしまったのだ。…やべ、あいつの顔思い出したら腹立ってきた。
それにだ、この電話の相手が朝比奈さんだったのなら、それは素直に喜ぶべき事だ。一日の終わりに、朝比奈ボイスが聞けるという事なのだから、俺の鼓膜もさぞ嬉しかろう。
そんな妄想を繰り返している内に、5コール目に入った着信音。
あわててディスプレイを見る。そこには古泉以上に、俺を不快にさせる名前が記されていた。
深い溜息を吐きながら、渋々電話に出る。
「なんだよ」
「お久しぶりなのです。」
そんなにお久しぶりでもねえだろうよ。俺の記憶が正しいのなら一ヶ月程前に、佐々木と、天秤領域女と、あの忌々しい未来人と、お前とで、茶店で会話を交わしていたはずだぜ。さっさと抹消させたい記憶ではあるが。
電話の相手は橘京子だった。
「相変わらず口が悪い人ですね。」
普段の俺はそうでもないさ。多分、話し相手によるんだと思うな。
「…段々声を聞いてるのも不快になってきたので、手早く用件を伝えようと思います」
ああ、そうしてくれ。俺がそう言うと、橘京子は手元にある台本を読むかのようにこう喋りだした。
「明日の午前九時に市民プールに集合です。持ち物はプールバッグ、お金は、まあそこら辺はご勝手に。ではさようなら。」
コホン…。ちょっと待ってくれよ。さすがの俺も、これは引き止めるね。橘京子よ、理由くらい述べてくれ。何をする気だ?そこには誰がいるんだ?お前だけなのか?集合場所と持参品あたりで予測すれば、何をするかくらいは大体わかるが。お前が俺を呼び出す理由が抜けてるじゃねーかよ。
そこまで俺が言ってやると橘京子は、溜息交じりにこう言い放つ。
「相変わらず、面倒臭い人ですね」
手に持っている携帯をそこの窓から思いっきり遠投してやりたくなる衝動に駆られるが、それは理性で止めておく。怒りに身を委ねるのは良くない事だ。それにしても、会話手段が電話で良かったな橘。流石に電話だと、俺はお前を殴れない。
「面倒臭い人ではありましたが、か弱い女の子を殴ろうとするような人だとは思っていませんでした。」
本当にか弱い女の子は、か弱い女の子を誘拐したりはしないさ。そもそもそれはお前が勝手に俺の人柄を決め付けているだけだろう。俺は限度を超えるほど腹が立ったら、例え女でも容赦しないさ。多分な。
次の瞬間、橘は呆れ返ったような声色で俺に反論する。
「嘘ばっかり。あたしの知っている貴方はそんな事しません」、と。
俺は言い返す。お前に俺の何がわかるんだろうな?と。
すると橘京子はそろそろ面倒臭くなったのか、はたまた興味が無くなったのか、それとも、俺との電話以外に、手早く用件を済ませなければならない「何か」が橘京子の身の回りで生じたのか。理由はまったくわからないが、橘京子は既にめちゃくちゃになりかけている本題を、まとめようとし始めていた。
「まぁその話は良いです。とりあえず理由を話します。」
その後、だらだらと橘京子は俺を誘う理由を話し出した。
とりあえず簡単に説明しよう。俺が橘に呼び出された理由を。
ずばり、『二人で市民プールに泳ぎに行こうぜ!』みたいな内容だったのだ。しかしそれは橘京子とでは無い。俺と、そしてもう一人は佐々木とで、だ。メンバーは佐々木と俺のみ。とりあえず、それを聞いてホッとする。あの忌々しい未来人野郎と、誘拐女の顔は見ずに済んだからな。
「私がいなくて、残念ですか?」と、受話器からは笑えない冗談が聞こえてきたので
「ご冗談を」と、俺は一応紳士的に返答しておいた。
いやしかし、古きからの親友と二人きりでプールとは、なかなか青春じゃないか。うむ。
だがしかし、それならお前じゃなくて佐々木が直接俺に電話すれば良いんじゃないのか?なぜお前が俺を誘うんだ?と、俺は至極当然な疑問を橘京子にぶつける。
返って来た答えはこうだ。
「それは佐々木さんからの私に対するお願いなのです。貴方みたいな人にはわからないでしょうけど、佐々木さんはああ見えて意外と乙女なんです。しかも恥ずかしがり屋なのです。佐々木さんが何を恥ずかしがっているのかは私にもよくわかりませんが、とにかくあの人は恥ずかしくて貴方に電話出来ないそうです。つまり、そういう事なのです。」
…いや、俺には意味がちっーともわからないんだが。
「貴方は本当に乙女心がわからない人ですね…。佐々木さんは新しいビキニを買ったのです!だから貴方と二人でプールに行きたいそうです。ではこれで、さようなら!」
一方的に電話を切られた。佐々木がビキニ?あの貧乳が…。…いや、ここは皆まで言わないでおこう。これ以上言ってしまうと謎の訪問者が俺の命を奪いに来そうだ。
まぁ、誰あろう佐々木の頼みとなれば、しょうがない。それに明日はどうせ暇であったし、その暇をどう潰そうかと考えていたくらいだからな。
部屋の中は心地良い夜の沈黙に満たされている。現在の時刻二十五時。そして明日の待ち合わせ時間は午前九時。起きれるだろうか?多分、遅刻はなくても佐々木より遅くなるのは間違いないだろうと思う。
それでは、佐々木をあまり待たせないように、今日はもう寝ますかね。おやすみシャミ。腹に乗るな。
「にゃ~」
耳に張り付くような蝉の鳴き声。見てると吸い込まれそうな青い空。
そしてそこに位置する入道雲。どこからか鳴り響く風鈴の音。カンカン照りの太陽。
激しく飛び散る水しぶき。25mもある水溜り。そしてそこに浸かっている年齢一桁台達。
その中を、隠れるように浸かっているいるのは、先ほどからニコニコと何がそんなに嬉しいのかよくわからないが、不気味な笑みを浮かべている神様第二候補者と、どこにでもいる平凡な地球人。まさしくこの俺である。
俺は与えられた、ある程度の描写説明という役割をとりあえず終えたので、一言言わせてもらう事にしようかな。
「 なんで俺はこんな所にいるんだったっけか 」
バタバタ。という擬音の後に、どこからともなく返答が俺の耳に入ってくる。
「理由なんて、あって無いようなものさ」
いや、嘘をつくな、嘘を。
確か俺がここに呼ばれた理由は、このプールでビキニ鑑賞会が開催されているからだと聞いたのだが。…しかし、佐々木よ。なかなか似合ってるんじゃないか?うん。
佐々木の細く美しい体の大事な部分を守っているのは、なんと、紐の水着である。色は明るいオレンジで、今日の太陽のように、夏らしく、正直、めちゃくちゃ似合っている。
貧乳…、いや、微乳ながらも、スレンダーで美曲線を描いている佐々木の体は、まさにモデルのそれと、ほぼ変わらない。いや、本物のモデルさんを見た事は無いが、多分佐々木の体も、勝るとも劣らないくらいであろう。モデルっつってもピンキリだしよ。
佐々木を見つめてみる。佐々木は必死で浮き輪に掴まりながら、これまた嬉しそうな表情で前髪をかき上げ、空を眺めていた。
「キミのおかげで、とても充実した一日になりそうだ。今日はありがとう」
佐々木はニコリと微笑んで、そう言った。いつもの『くっくっ』というような、特徴的な微笑み方では無い。心底俺に感謝しているような、そんな仕草だった。
「別に。感謝されるような事は俺はしていない。自慢じゃねぇけど、結構暇なんだよ、これでも」
「宇宙人や超能力者を知人に持つキミでも、暇があると言うのかい?それは意外だね」
今度は、いつものように、佐々木は「くっくっ」と、実におかしいと言うように。右手で口元を隠すように笑う。
…その瞬間だった。佐々木が必死で掴んでいる浮き輪が、ひっくり返りそうになる。佐々木は「うわっ」、と、実にらしくない焦り方をする。ジタバタしながら、必死に浮き輪を掴んで、離さない。
―――そう、実は佐々木は、カナヅチなのだ。
思い返すと中学時代、こいつの数少ない不得意科目には、「水泳」があった。
あまりにも泳げない佐々木を見て、体育教師に、「佐々木、お前は水泳には出なくて良いぞ」とまで言われていたくらいだった。佐々木は毎回面白いように溺れては、最後は保健室に連れて行かれるのでな。
だが、根はとんでもないくらい負けず嫌いの佐々木は、一度クロール25mのタイムを測定するときに、急にプールサイドにあるベンチから飛び出し、「私、いきます。」と、突然名乗り出て、案の定5mも持たずに溺れていた事があった。
その時俺は無意識的に一目散に佐々木にクロールで駆け寄り、抱きかかえて保健室まで連れて行った挙句、体育終了後、クラス中から温かい目で見られたという思い出がある。
まぁ佐々木には悪いが、俺にとっちゃそんな事も、今となってはすっかり良い思い出なのさ。
思い出話を終えると、佐々木は恥ずかしそうに呟く。
「よくもまぁキミは…そんな憎たらしい記憶を脳裏の片隅に放置しておけるね…」
おいおいそうは言うがな佐々木。お前にとっては憎たらしくても、俺にとっては良い思い出なんだってば、本当に。なかなか叶わない努力をしているお前は輝いていたぞ?お前はカナヅチの天才だ。あの溺れっぷりは…悪いが、見ていて腹を抱えてしまう程笑った。足の届く所なんだから死にはしないってのによぉ。
佐々木は悔しそうに、そして恥ずかしそうに、顔を赤らめる。
「…もしかしなくてもキミは僕を馬鹿しているようだね」
そう言い終えてから佐々木は表情を覆うように、浮き輪に顔をうずめた。かなりご立腹の様子。
ちょっとした冗談だよ。ジョークジョーク。ごめんな?…おい。佐々木。こっちを向け。
俺が慰めていると、佐々木は、『リベンジしてやる。』と言わんばかりの、サドっぽい笑みを俺に静かに向ける。
「はぁ~…それじゃあ僕もキョンのとびっきりの黒歴史を誰かに暴露してしまおうかな~?」
お、脅しかよ!くそっ。あの事はさっさと忘れろよ!っていうか、謝ってるんだから潔く許せ!それに、そもそも俺はお前を馬鹿にした訳じゃないんだぞ。俺は『そんな佐々木も可愛かったな~』っと言ってるだけだ。だから…な?許せ。
「溺れてる僕が可愛いはずないだろっ!あんなに醜いポーズなんだから!」
…いやまぁ、確かに、溺れてるときのお前は悲惨だった。目も当てられないくらいで、同情すらした。描写するのも怖いくらいだ。あんな動きが人間に出来たとはな。と言うか、どうやったらあんなに醜い姿で溺れられるんだ?…と、思いはしたが、口にはしないでおく。そんな事を言おうものなら、佐々木の堪忍袋は大震災を起こすところだ。
…だがな佐々木。俺が言いたいのは、苦手な事に挑戦して努力するお前の姿に俺は感動したんだ。あの醜いポーズで溺れてしまっても、別に良いじゃないか。佐々木。そういうのもマニアは喜ぶもんなんだぞ?
「………………」
佐々木は口元を水面に沈めて、ブクブクさせながら、かなり恨めしそうな目でジトーッと俺を見つめる。
「やっぱりキョンは僕の事を馬鹿にしてるんじゃないか……」
てな事を言われてしまった。だから違うんだ、佐々木。冗談だよ冗談。そう言いながら佐々木の頭を、俺はなるべく優しく撫でる。…そうすると佐々木は、また口元を水中に入れて、空気を出してブクブクさせる。相変わらず、いじめ甲斐のある奴だ。まったく。
まあ、いつもは逆に、俺がいじめられる場面ばかりなのだが、舞台がプールという事だと別だ。「水泳」という検索ワードで調べると、佐々木の面白話然り、赤面話は、それこそ永遠と出てくる。
なんせ俺は一昨年の夏、佐々木の水泳弱点克服の為に、佐々木と共にこの市民プールに何度も通っていた事があるのだ。…まあ、案の定、佐々木の水泳技術が上がる事は無く、俺のクロールに磨きが懸かるばかりであった。しかも佐々木は、毎回のように溺れ、そしてこの市民プールで、あの怖いくらい醜いポーズを、周りにいる子供達に披露しては爆笑されるだけだった。
その後の帰り道に、悔しさと恥ずかしさで、今にも泣き出しそうな佐々木を慰めるのには骨が折れたが、まぁそれも今となっては良い思い出さ。
「…キミは僕の理解して欲しい部分は少しも触れないでおきながら…僕の理解して欲しくない部分はこれ以上ないくらい理解しているような…嫌味な人間だね」
やべ、ちょっと怒ってる。しょうがないな。宥めてやるか。っというかなんだよ?理解して欲しい部分って。
「い、色々あるのだよ。僕くらいの年頃の女性にはね。まあキミに理解出来るはずもないだろう」
必死に浮き輪に掴まりながらいじける佐々木は、悪いが少し、滑稽だった。
ってか、お前は女であって女じゃないようなモンだろ。自分の事を呼ぶ際も、「僕」だしさ。心は男だよな。
…と、俺は慰めるつもりで、もちろん冗談半分で、そう言い放った、のだが。この場面でこの言葉は、史上最悪のNGワードだった事を、俺は次の瞬間に思い知らされる事となるのだ。
…佐々木が浸かっている水面が、プルプルと振動しているのがすぐにわかった。
なんだなんだ?そう思って俺は佐々木の顔を覗き込む。…完全に涙目で、耳が真っ赤だ。
必死で浮き輪を掴んでいる佐々木のその拳は、これまたプルプルと震えている。
どうやら俺は、『親友』を、完全に怒らせちまったらしい。
「もうキョンなんて知らない…!」
珍しく、佐々木が怒りを露にしているという事で唖然としている俺の顔に、顔を真っ赤に染めながら瞳に涙を浮かべる佐々木は、そう言い放った。佐々木は水中で、プイッと俺に背を向けて、バタ足で必死にプールサイドへ向かっていく。おいおいおい、これはちょっと本格的にまずい空気だぞ。佐々木をここまで怒らせたのは、初めてかもしれない。
「おい佐々木っ!」俺は必死にバタ足して、しかもなかなか進まない佐々木の背中に、そう叫んだ。
返答はない。振り返ってもくれない。
―――そこで事件は起きた。
「きゃあっ!」
という、甲高い声がプール全体に響く。
クロール25mの競争をしていた子供達が…!なんと浮き輪無しではこの水中の世界を生きてはいけない女、佐々木にぶつかってしまったのである。「まずい!」、と俺は、咄嗟に思った。 溺れた佐々木を助ける事だけならイアン・ソープともなかなかの勝負が出来る事で有名になれる、かもしれない俺が、クロールで出陣。
だが、時すでに遅し。
いつかのシーンが俺の脳裏で鮮明にフラッシュバックしていた。
佐々木は大方の予想通り、見事にあの、「怖いくらい醜い姿」。を、久々にこの市民プールで披露して見せたのだ。
「なんだよー。お姉ちゃん気持ち悪いよー」
…という、佐々木にぶつかった子供達の声も、遥か遠くに聞こえる。俺の背筋は、ただただ。冷たく凍り付いていた。そして、額からは嫌な汗がどんどん出てくる。俺の指先が、恐怖により震えている。…このあと俺は、佐々木にどんな仕打ちを受けるのだろう?と、想像しただけで、俺の全身は細かく震える。
「もう終わった…」。そう、自然と呟いている自分に気づく。これは決して大袈裟の事では無い。佐々木という人間を怒らせたらどうなるのか。そんなこと、想像したくもなかった。
ここら辺で俺は、「ハッ!」となる。そうだ、後の事はとにかく謝れば良い。なんなら土下座でも、靴の裏でも舐めてやる。でも今はそうじゃない。今はとにかく、佐々木を助けなければ!勝負だイアン・ソープ!俺のクロールに酔いしれろ!
―――そして俺は、年齢一桁台達の脇を駆け抜け、いつかのように佐々木の下に賭け付け、そして抱きかかえ救出したのだった。
―――そんな事があってから、もう一時間は経っているかな。
俺は今、この世の冷酷さと無情さを、その身をもって痛感していた。
「…………………。」
今しがた帰路を歩く佐々木の背中は、未だ怒りを物語っていた。俺より前方を早足で歩く佐々木の存在が、やけに怖い。そして冷たい。「どうしたものか」と、悩んでいる暇は,俺には無いのだ。とにかく謝らなければ。そう思って俺は佐々木に向かって、何度も謝ってはいる。
「佐々木…さっきは本当に悪かった…恥かかせてしまって…」
返答はもちろん、
「…………………。」
やはり、長い沈黙しか返ってこない。長門にだって話しかけたら、もう少しくらいリアクションをくれるだろうによ。
不意に、向かい風が吹く。佐々木が身に纏っている白いスカートが揺れる。見えそうで見えな…ではなくてだな…。さて、どうしたものか。と俺は、茜色に染まりあがってく空を見上げ、思う。さすがにあそこまで怒らせてしまってはなぁ。
あの事件があってから、佐々木は無言で更衣室に向かい、そして更衣室から出てきた。しかも、無言でだ。会話どころか、そもそも俺は未だに佐々木の顔もまともに見れちゃいない。佐々木はずーっと俯いて、地面を見ている。前髪で眼が隠れていて、それが異様に怖い。
佐々木はただ黙って自宅に向かう道を歩く。淡々と。そして俺はそれに付いていく。俺は先ほど二本購入したコーヒーを、佐々木に一本手渡し、そこから会話を広げよう!…という、なんとも古臭い作戦に出てみたものの、駄目だった。受け取ってもくれない。
だが俺はまだ、最終兵器を隠し持っているのだ。これさえ使えば、どんな状態でも佐々木を一発で上機嫌にさせる。そんな凄い兵器が、な。
…それを発揮するには、今はちょうど良い場面であろう。よし、行くか。
「佐々木、手を貸してくれ。」
そう言っても、貸してはくれない。そればかりか、振り向いてもくれない。ピクリと反応すらしないのだ。だが、俺はこんな事も想定内さ。
俺は小走りで佐々木の隣まで行く。やっと佐々木の表情が目に入った。なるほど、かなり落ち込んでいるな。
次の瞬間、俺は佐々木の手を、強引に奪い取った。
「あんまり早く歩かないでくれよ。見失うかもしれないだろ?」
俺は今自分が出来る限り、飛びっきりの笑顔で、佐々木に告げる。だが佐々木の返答は、
「…………………。」
相変わらず、沈黙である。だが表情は見る限り、まだむくれているはいるが、頬には桜色が灯っていた。
昔、岡本に言われた事があるのだ。佐々木と少し、すれ違いがあった時、俺は相談相手に岡本を選び、そして、岡本は快く俺の相談に乗ってくれた。
そんなある日、岡本は得意げに言った。『そういうときはね、ササッキーの手を、こう、強引に握ってしまえば良いんだよ!』…とのアドバイスを、な。ちなみにササッキーってのは、佐々木のあだ名だ。
そして俺はその翌日あたりに、半信半疑で佐々木に対して実行してみた。『強引に手を握る』という行為を。
まあこれが。ズバリ的中のナイス采配だった訳なのだ。
手を握ってしまうと、すぐに佐々木は上機嫌になった。理由は今でもよく知らん。もしかして俺の超能力か?とも思ったが、首を振ってすぐに否定する。「んな馬鹿な」と。
…だが、これは列記とした事実なのだ。本当に、俺が手を握って優しく謝るだけで、佐々木はどんな喧嘩の後でも、すぐに機嫌を良くする。手を繋いだだけでだぜ?やっぱり、少し変わった奴なんだなー。と、俺は改めて思わされる訳だ。
しかし、佐々木と手を繋いでいると、やはり男として、何だか俺まで少し変な気分になってくる。それもそのはず、佐々木の手は小さくて、綺麗で、そして触り心地がとてつもなく良いので、俺もどうしようもなく興奮してしまうのだった。
…まあそんな昔話はどこか隅にでも置いておいて、俺は、「佐々木」と、呼びかける。まあ、もちろん、返答はない。
だか俺は言う。俺は続ける。手を握って、今も少し顔を赤らめている佐々木の横顔に、俺は言う。
「最後はあんなになっちまったけど…」
佐々木は、未だ沈黙。口を堅く閉ざしている。意地でも喋らないつもりらしい。
俺は、先ほどの笑顔を大きく上回る、今日一番の笑顔を向けて、佐々木に言い放った。
「今日は楽しかったよ。誘ってくれてありがとな、佐々木」
ついでに、お前の水着姿もめちゃくちゃ似合っていたしな。と、俺は続けて、佐々木の頭に手を置く。柔らかい髪質だ。その髪から、少し香る、甘い匂い。そんな佐々木の頭を、俺は優しく撫でる。
佐々木の顔は、笑えるほど赤かった。
そして同時に、とても悔しそうだった。
…これで俺の事を、佐々木に許してもらえなければ、俺はもう最悪土下座をするしかねぇな、と。
まさに、そう思いかけた時だった。
「キミって奴は…」
と、佐々木はモジモジしながらも、やっと口を開いてくれたのだ。
だが、やはりそこには少し恥ずかしさがあるのか、俺と目を合わせてはくれない。俺は昨晩の橘京子との電話のやり取りを思い出す。佐々木は乙女で、しかも恥ずかしがり屋らしいな。
そのせいなのだろうか、顔はまだ赤い。
だかそれも、今にも沈みそうな夕日のせいかもしれないな。と俺は勝手に思っていた。
「キミは本当にずるい奴だよ」
それはそれは。すまないね。
「そろそろ僕の頭の上に置いている手をどけてくれないかな?」
おっと。すまない。ずっと撫でていたようだ。…ふふ。なんだ?どうした佐々木、顔が赤いぞ?
「あ、…あんまり女性はからかわない方が良いと思うぞ?キミの為に言っているんだ」
別に自覚は無いのだが、まあすみませんね。…それにしてもだ、佐々木、今日は楽しかったな。
「とても…とても恥ずかしかったよ。僕はね」
でもまあ、それも含めて、ちょっとは楽しかっただろ?久しぶりにあのポーズもとれた事だし。観衆の注目を集めた事だしさ。
「ばか。」
バカですまないね。
「…キミには少しお灸が必要のようだね」
そう言い終えてすぐに、佐々木は急に俺の腕に体全体を傾けてきた。と思ったら、俺の腕に佐々木の腕が絡まってくる。俗に言う、腕を絡めてきたのだ。そして、佐々木の何か二つの柔らかい物が、俺の腕に僅かに当たっている。…ほんとーに、僅かにな。ほんの少しだけだ。
…っというか、佐々木。重いぞ?歩きにくいし。
「うるさいうるさい。黙りたまえ。これは今日のキミに対する、罰だ。よくも僕に恥をかかせてくれたね?」
罰を与えてるにしては、なんかお前も楽しそうだな。
「くっくっ…気のせいじゃないか?あるいはキミの脳内でおきている勝手な妄想だとか」
そんな佐々木の言葉を聞いて、俺達は笑いあった。
確かにあまり会えないとは言え、俺は今でもお前の親友だぜ?お前が本当に楽しそうにしてるか、否かなんてのは、俺にはまさに手に取るようにわかるさ。
そこまで俺が言うと、佐々木は先ほどまでの様子とは、まるで正反対に、とてつもなく上機嫌そうな笑みを見せてから、
「悪かったね。白状しようか。そうさ、僕は今凄く楽しいよ。とても憎たらしい、キョンという名の悪戯坊主を、僕が今成敗している所だからね」
そう言って、堪え切れなかったのか、珍しく佐々木は口元に手を置いて、腹を抱えて大爆笑してた。俺もそれにつられて、ついつい吹き出してしまう。男女の高校生が道路の真ん中で、腕を組み、寄り添いあい、体を密着させながら、爆笑しているような所を、道行くおばさん達は迷惑そうに、或いは温かい眼差しを向けながら見つめてくる。だが俺はそんな事も気にせず、佐々木と笑い合っていた。
…心から、岡本には感謝しておこう。訳わからんくらい上機嫌だな。佐々木よ。
そんな佐々木を見ていると俺だって、少なからず嬉しいような、そんな気持ちが湧いてくるってもんだ。こんな時間が愛しい。心からそう思う。
なぁ佐々木。たまにで良いから、連絡くれよな?そんで、こうやってまた遊ぼうぜ。
「ばか。それは僕の台詞だろう?僕は毎日だってキミと会いたたがっているのだよ。それに男性のキミから連絡をくれるのが、世間一般的な常識なんじゃないかな?…それにだね、今日は僕が誘ったんだから、次の約束は、キョン。キミが僕を誘うのが、道理としては正しい。と、僕は思うのだけれど?」
いや、…お前が誘ったというか、俺は橘に誘われたんだけどな。
「そ、それは言わない約束だろう…」
そう言われて佐々木にコツンと頭を叩かれた。…おい佐々木、人を叩いておいて微笑むとは何事だ。
俺がそう言うと佐々木は、心底楽しそうに、しかし、少しだけ、物哀しそうに、話出した。
「いやぁね、キミとの時間は本当に充実していて…それ故に…僕の心の中に、やり場の無い 寂しさが芽生えてしまう程だよ」
やたらと、佐々木の声が沈んでいくのがわかった。
寂しいさが芽生える?楽しいのに、寂しいのか?不思議な奴だな。と俺は言う。
すると佐々木は俺を見上げて、心底呆れ返った様子で、呟く。
「本当にキミは乙女心のわからない奴だなぁ…」
…その台詞なら、昨晩忌々しい女超能力者に聞かされたところだよ。
「つまりだ、キョン。よく聞きたまえ。僕はだね、これほどまでに、キミといる時間が充実しているからこそ、僕は、キミと会っていない時間が余計に寂しく、中身の無い物になってしまうと、それが哀しいと、僕は言っているのだよ。わかったな?僕の乙女心がキミにも」
佐々木は、今にも泣き出しそうな表情を浮かべていた。だが、それは見ない振りをしておこう。負けず嫌いなこいつの事だ。指摘したらまた機嫌を悪くするだろう。
俺は佐々木の問いには返答せずにいた。しかし、その代わりと言うように、佐々木を少し抱き寄せる。相変わらず俺の右腕には、佐々木の全体重が掛かっている。信じられないくらい軽い。こいつは普段何食ってんだ?と不安になるほどだ。
ふと、気づくと、蝉の音が少し遠くに…。そして入道雲は、夕日の仕業で、茜色染まっている。俺は、この世でもっとも、美しい風景を眼にしているのかもしれない。…そうだ。もうそろそろ本格的に、秋になっていくんだなと、思わされる。…一昨年の、中学三年時の、この季節は、俺は何をしていたかな?多分、塾と学校に追われながらも、でも、それなりに楽しくやっていたんだろう。…なぜなら、俺の隣にはずっと、佐々木がいたからな。
今となっては、過去になってしまった、あの頃を思い出しながら、「ふぅ」と、俺は一つ息を吐く。
―――今にも泣き出しそうな親友に向かって、俺は一言、言ってやる事にした。
「電話くらいなら、いつでも受け付けてるから。なんかあったらいつでも電話してこいよ」
と、早口で言い放つ。佐々木の表情は、なんだか呆気にとられていたようで、口がポカンと開いていた。そして俺の言葉の意味を理解した瞬間、佐々木は、面白いくらいにあわてるのだ。あたふたしている様子の佐々木を見て、俺は少し、幸せの中に隠れている、込み上げてくる感情に気づく。目頭が、少し熱い。
…不味いな、これは佐々木には隠し通さなければ。
「珍しいね。キミは電話による会話手段を、面倒臭いと豪語して避けていたじゃないか。僕の記憶違いか…?」
ぐすっ。と、俺は涙を隠す。そして平静を装い、返答する。
「確かにどうでもいい奴との会話なんて、電話じゃなくても極力したくないさ。だかな、逆に、お前となら、さ。話してても最高に面白いし、だから…お前だけは、俺に遠慮なんてしないでくれ。」
…そこまで俺が言い終えると、うん。まぁ、なんと言うか…俺は、胸の奥底から込み上げて来る感情に、…涙腺が、負けてしまったのだ。目頭がカーッと熱くなり、そして次の瞬間、俺の瞼からは大粒の涙が零れ出てしまう。…制御したい。でも、そう思う度に、涙の粒は大きくなる。
俺はついに、声を漏らして泣いてしまう。そこで佐々木はやっと、俺が泣いている事に気づいたらしい。
ふと見た佐々木の表情は、今日一番のサディズムスマイル。悪戯娘が、「良いものを見つけた!」というかのように、それはそれは嬉しそうに、「ニヤリ」と微笑んだのだ。…くそ!やばい!見つかってしまった!
「…泣いているね?」
と、佐々木は小さく呟く。そして次の瞬間、「うふふっ」と、あの個性的な笑い方では無く、別の笑い声が聞こえてくる。くそっ、心底俺は悔しくなる。佐々木のような悪戯娘の前で泣いたりするのは、この世で最もやってはいけない事の一つに、間違いなくランクインするだろう。
「…わ゛るいがよ゛っ…」
と、俺は涙のせいで、上手く返答出来無いが、それでも言う。「悪いかよ?」と言ったつもりが、酷く声が震えてしまう。だが佐々木は俺の言葉を理解し、そして、返答してくれる。
「全然、悪くない。むしろ、うん。僕は今、とても嬉しいよ。この際はっきり言ってしまうとさ、正直、凄く不安だったんだぞ?この春キミとたまたま駅前で出会うまで、『キミは僕の事を完全に忘却しきっているのではないか』と思っていたし、まあ、その他色々な感情に取り巻かれて、僕はとても不安だったんだよ?…キミのせいでね」
佐々木は、思い出しながら話をしているような、そんな口調だった。とても慎重に、佐々木は言葉を選んでいる。選んで、選んで、絞って、切り捨てて、そして、とても大切に、大事そうに、選んだ言葉を佐々木は声に出す。すると、佐々木が放つその言葉は、まるで命を持つかのように俺の耳に、脳に、全身に、染み込んでくる。心地良かった。この瞬間が。
「でも、目に見える現実として、キミはこうして僕と、今ある時間を共有して、感極まって泣き出してしまうほどにキミは、僕と共にいる事に感動してくれている。これほど、僕にとって幸せな事は無いんだ。…キョン。本当だよ?…僕は、今…そう……とても……っ……」
そこまで佐々木は言うと、話すのを止めた。というより、話すことが出来なかった。次の瞬間、俺の耳に響くのは、佐々木の泣き声だった。
とても深く、弱々しく、とても…とても綺麗な涙だった。佐々木は声も出さずに、だが、俺とは比べようもならないくらいの、大粒の涙を流していた。その涙は、留まる事を知らず、佐々木の大きな瞳から、止め処なく零れだしてくる。
―――色んな想いが、そこにはあったのだ。そして、それよりも多くの不安を、佐々木はきっと、その小さい背中に背負っていた。
俺は佐々木の涙を見て、とても深く、後悔する。なんでだよ。なんで、俺はもっと早く、佐々木に会えなかったのだろう。こいつがこんなに不安になってしまう前に、電話でもして、会ってしまわなかったのだろうと、後悔する。ハルヒ達と出会ってからも、俺は決して佐々木を忘れていた訳では無い。時々思い出し、「あの頃もあの頃で楽しかった」と、嘆く程度ではあったが、だか、それでも俺は佐々木を忘れたりはしなかった。
佐々木の瞼から零れ落ちる涙を、夕日は照らし出す。茜色の涙。
俺は佐々木の頬を伝うその涙を、指で優しく拭い取る。佐々木の頬は温かかった。
少し時間も経つと、佐々木は、気持ち的にも落ち着いたのか、呼吸も一定のリズムを保ち始めた。だがまだ、哀しい余韻を残すかのように、少し、嗚咽をあげている。
夕暮れの茜色が、やけに切なく、俺達二人の影を映し出す。
佐々木は、必死に声を絞り出し、消え入りそうな声色ではあったが、確かに、俺に向けて言葉を発していた。
「僕はもう、不安になったりはしないよ」
その声に、その言葉に対し、俺は強く頷く。お前を不安にさせるなんて事は、俺がさせない。もう二度と、だ。
俺は佐々木と目を合わせて、そう宣言する。佐々木は、目に少し涙を浮かべながら、またも頬を赤く染める。
「うむ。頼んだよ。次、僕が涙を流したりしたら、それはキミのせいだからな?わかっているね?僕の大切な、キョン」
はいはい。わかっておりますとも。ええ、よぉくこの身に言い聞かせておきますとも。
俺と佐々木はまた、笑い合った。
もう二度と、哀しい涙を流したりはしないように。
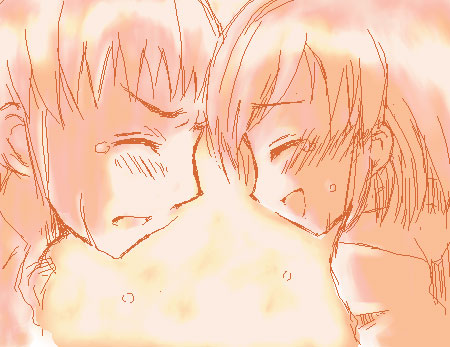
最終更新:2008年01月06日 18:55