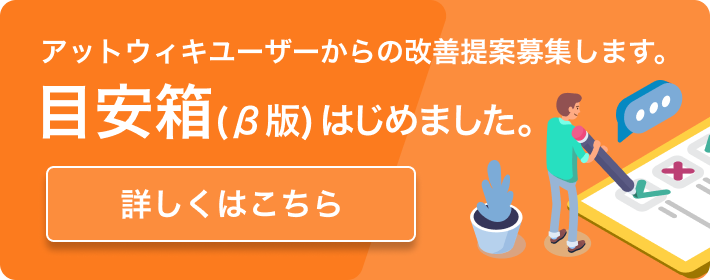(1)
詩歌藩国はまことに小さな国である。
極北の海に浮かぶ島がその国土である。
森は深く山は高い。氷雪に閉ざされた霊峰が島を南北に横たわる。15のターンを経たが、この山脈は変わらない。その威容も人々の想いも。
この島は海底火山を有し、地熱を生んだ。おかげで自然は厳しさだけでなく恵みも与えた。土は肥え、果実がなる。鳥が啄ばみ、落ちたものを地上の生き物が食べる。
過酷に見えるこの島にも、命は生きている。
森は深く山は高い。氷雪に閉ざされた霊峰が島を南北に横たわる。15のターンを経たが、この山脈は変わらない。その威容も人々の想いも。
この島は海底火山を有し、地熱を生んだ。おかげで自然は厳しさだけでなく恵みも与えた。土は肥え、果実がなる。鳥が啄ばみ、落ちたものを地上の生き物が食べる。
過酷に見えるこの島にも、命は生きている。
詩歌藩国はまことに静かな国である。
人もいるが、町の数は少ない。
行き来は殆どが徒歩である。騒音を生む技術が主要なものになっていない。
国中が音に包まれることなど滅多にない。思い当たるのは春先の雪崩、それと音楽。
けれど音楽院は王都のみにある。
他の街で夜毎音を奏でても、国を包みはしないだろう。
なぜなら雪がこの国を包むから。
行き来は殆どが徒歩である。騒音を生む技術が主要なものになっていない。
国中が音に包まれることなど滅多にない。思い当たるのは春先の雪崩、それと音楽。
けれど音楽院は王都のみにある。
他の街で夜毎音を奏でても、国を包みはしないだろう。
なぜなら雪がこの国を包むから。
詩歌藩国はまことに寒い国である。
一年の大半が冬である。短い夏や春以外、雪化粧は落ちない。
木の葉の雨が止めば、粉雪が散る。
湖水は薄氷が張っていく。
草花が霜を溶かす頃、吐く息の色を知る。
日暮れの色を眼にすれば、短日の意味を知る。
霜の花が芽吹くのは、冴ゆる月下の夜のこと。寒造りの酒を飲み、窓辺に思う。
今が春の隣だと。
木の葉の雨が止めば、粉雪が散る。
湖水は薄氷が張っていく。
草花が霜を溶かす頃、吐く息の色を知る。
日暮れの色を眼にすれば、短日の意味を知る。
霜の花が芽吹くのは、冴ゆる月下の夜のこと。寒造りの酒を飲み、窓辺に思う。
今が春の隣だと。
これまでずっとこうであった。幾度かの騒乱を除けば。
けれど、この年の春。少々具合が違うらしい。
けれど、この年の春。少々具合が違うらしい。
この年の春、詩歌藩国は騒がしい。
このまことに小さな国が、華開こうとしていた。
音楽祭が、始まる。
(2)
開催の口火を切る栄誉は、浮遊島が得た。夜明け前のことである。
夜空が星と月の輝きを手放していく。空が深い蒼から白へと移ろうとしていた。
浮遊島の中央部には、神殿がある。
石柱が並び立つ石畳の一本道が伸びている。螺旋を描く吹き抜けの神殿である。周囲にはヘビイチゴが群生している。解け残った雪の下からは赤い実が姿を見せていた。
石柱が並び立つ石畳の一本道が伸びている。螺旋を描く吹き抜けの神殿である。周囲にはヘビイチゴが群生している。解け残った雪の下からは赤い実が姿を見せていた。
それは蛇神を崇める場所であった。
凍てつく寒さをもたらすと言われた神を人々は恐れていた。だから、崇めた。
畏怖の念を込めて。
凍てつく寒さをもたらすと言われた神を人々は恐れていた。だから、崇めた。
畏怖の念を込めて。
かつては、そうだった。だが、今は違う。蛇神は変わった。
いや、蛇神を崇める国民が変わったのだ。
いや、蛇神を崇める国民が変わったのだ。
蛇神様の神官団、総勢150名が整然と神殿内部の螺旋回廊に並んでいる。
彼らは吹き抜けの下にある凍った水盤を取り囲んでいた。視線は、水盤の中央部に置かれた石像に注がれている。
美しい少女の上半身に蛇の下半身を有していた。
彼らは吹き抜けの下にある凍った水盤を取り囲んでいた。視線は、水盤の中央部に置かれた石像に注がれている。
美しい少女の上半身に蛇の下半身を有していた。
それは恐ろしい神と伝えられた蛇神のイメージとはかけ離れていた。この遺跡が発見された当初、神官団は面食らった。
だが、今になって思う。
あの関西弁の神様は昔こんなに美形だったのか、っていうか性別まで変わってないかと。
あの関西弁の神様は昔こんなに美形だったのか、っていうか性別まで変わってないかと。
斉唱が始まった。
回廊の下から順に声が広がり、空にのぼっていく。加わる歌声の数に比例して、螺旋の壁に反響する声も大きくなる。
回廊の下から順に声が広がり、空にのぼっていく。加わる歌声の数に比例して、螺旋の壁に反響する声も大きくなる。
歌は冬の終わりを懸命に告げていた。
雪解けで水量が増した滝の轟音。
草の若葉が雪を押しのけ芽吹く姿。
落ちる鹿の角が立てる乾いた音。
雪解けで水量が増した滝の轟音。
草の若葉が雪を押しのけ芽吹く姿。
落ちる鹿の角が立てる乾いた音。
その150の心は、願っていた。
冬の寒さを土中で過ごす、関西弁の神様との再会を。
冬の寒さを土中で過ごす、関西弁の神様との再会を。
この国の誰よりも早く、春の到来を告げたかった。
ともに喜びを分かち合う為に。
ともに喜びを分かち合う為に。
蛇神様、はやく起きてくださいよ。
年の若い神殿楽師見習いが、丸く切り抜かれた空を見上げた。見習いになって日は浅かったが、心は立派な楽師であった。学生の頃から抱いていた願いを今も忘れてはいない。
絶対スイングしてくださいよ、ウィングバイパー様。
(3)
「ようこそ、詩歌藩国へ。」
もう何度言ったか分からない台詞を、入国審査官は言った。
いい加減舌がつりそうだと思う。
いい加減舌がつりそうだと思う。
そっと目の前にいる東国人観光客から視線を外し、彼の後ろを見る。
列が出来ていた。驚くべきことに最後尾が見えない。
最近観光客が増えたと思っていたが、これはあんまりではないかと思う。今日一日俺はトイレに立てないのではないか。
列が出来ていた。驚くべきことに最後尾が見えない。
最近観光客が増えたと思っていたが、これはあんまりではないかと思う。今日一日俺はトイレに立てないのではないか。
音楽祭当日早朝、エンリル空港は混雑していた。いや、大混雑していた。
燃料を馬鹿に食う航空機はこの国で殆ど使われていない。だから空港自体も随分こじんまりした規模である。目の前の現実と当初の予定が全くかみ合っていなかった。
「お預かりした検疫検査の結果と所持品検査の結果はいずれも問題ありません。貴方の入国を許可致します。」
もう何度押したか分からない判子を、入国審査官は書類に押し当てた。
いい加減手がつりそうだと思う。
ついこの間まで確かにあったのんびりした職場はどこにいったんだろう。
いい加減手がつりそうだと思う。
ついこの間まで確かにあったのんびりした職場はどこにいったんだろう。
「ここを抜けるとシーカヤック交通網が御利用できます。サファイアラグーンのホテルに直行したいのでしたら是非どうぞ。体力に余裕がおありでしたら水竜の背に乗ってみてください。大変楽しい船旅になるでしょう。・・・・えぇ、そうです、ソットヴォーチェです。水竜達が音楽祭の間だけなら手伝うよと言ってくれまして。」
もう何度見たか分からない東国人観光客の驚いた顔を、入国審査官は見た。
西国人観光客よりは控えめなリアクションだなぁと思う。
西国人観光客よりは控えめなリアクションだなぁと思う。
「・・・まったく、ありがたいことです。シーカヤックだけじゃとても手が足りなくて。音楽祭が終わったら、ソット達もくたくたになってるでしょうね。なにか労いのご褒美でもあげないと」
入国審査官はにこりと微笑んだ。
自分だけが忙しいのではないと思い出した。
今日は全力で動く日だと思った。業務が終われば楽しい時間が待っているのだ。
うまい酒とメシと音楽が俺を待っている。
自分だけが忙しいのではないと思い出した。
今日は全力で動く日だと思った。業務が終われば楽しい時間が待っているのだ。
うまい酒とメシと音楽が俺を待っている。
「では、良い音楽祭を。節度を失せず良き想い出が生まれることを。」
「はー、なんとも壮観ですねー」
駒地真子は頬に潮風を受けていた。
水竜の背に、彼女は立っている。薄く青みがかった白の短髪が揺れ、子供らしさの残る顔が微笑んでいる。
水竜の背に、彼女は立っている。薄く青みがかった白の短髪が揺れ、子供らしさの残る顔が微笑んでいる。
<そうですね、爽快です>
駒地の足元で幼い水竜が答える。声は出していない。聞こえるのはドラゴンシンパシーと呼ばれる人々だけである。
「いやー、それにしても恐ろしい。こんなにおいしいものが溢れているとは」
リンゴ飴を舐めながら、花陵が言う。
長い髪をお団子に編んだ女性が、両手にそれぞれリンゴ飴と蜂蜜飴の刺さった棒を握っていた。白い髪が陽光に映えた。
長い髪をお団子に編んだ女性が、両手にそれぞれリンゴ飴と蜂蜜飴の刺さった棒を握っていた。白い髪が陽光に映えた。
「あ、駒地さん。いる?ソットちゃんも。」
「いや、いい。見てるだけで十分。」
<ご好意だけ頂いておきます。>
「いや、いい。見てるだけで十分。」
<ご好意だけ頂いておきます。>
即座に反応する一人と一匹。残念、おいしいのにと花陵は再び舐め始めた。
<そういえば、あのバンダナの人は今日一緒ではないのですか?>
「あ、森さん?うん、夕方までやることあるって」
<そうですか>
「あ、森さん?うん、夕方までやることあるって」
<そうですか>
簡素な返事だが明らかに残念そうな子供の水竜。無意識だろうが大変かわいらしい。
駒地真子、視線を落とす。しゃがみこみ、たまらずぎゅーっ。
「駒地さん、次私も。」
花陵・駒地両名、撃沈。
(4)
シーカヤックと呼ばれる船がある。
この島を流れる地下水路を行き来する際に用いられ、サイズは大小様々である。最近ではもっぱら観光客を乗せている。
この島を流れる地下水路を行き来する際に用いられ、サイズは大小様々である。最近ではもっぱら観光客を乗せている。
音楽祭当日の朝、シーカヤック交通網はフル回転している。
最初漕ぎ手の中には往復した数を競う者達がいた。けれど、すぐにそのことは話題に挙がらなくなった。数えるのが馬鹿らしくなったらしい。
今は一刻も早く音楽祭に参加したいと頭で考えていたのだろう。
エンリル空港に戻る時、遠くから聞こえる楽しげな音楽を名残惜し
そうに聞いていた。
最初漕ぎ手の中には往復した数を競う者達がいた。けれど、すぐにそのことは話題に挙がらなくなった。数えるのが馬鹿らしくなったらしい。
今は一刻も早く音楽祭に参加したいと頭で考えていたのだろう。
エンリル空港に戻る時、遠くから聞こえる楽しげな音楽を名残惜し
そうに聞いていた。
どの船も目的地は殆ど同じであった。
サファイアラグーンの入り口である。
サファイアラグーンの入り口である。
サファイアラグーンとは島の潟湖である。
観光客が主な拠点としている。露天温泉とホテルがあるからだ。
観光客が主な拠点としている。露天温泉とホテルがあるからだ。
普段は「静かな湖畔でのんびり」がキャッチフレーズだが、今日だけは違う。
いたるところに楽団の姿が見える。格好からして地元民が楽器を持ち出して作ったものだが、その技術は眼を見張るものであった。
いたるところに楽団の姿が見える。格好からして地元民が楽器を持ち出して作ったものだが、その技術は眼を見張るものであった。
難なくアドリブとアレンジを加えセッションしている。アルトリコーダーにハープ、ギターにヴァイオリン、サックスにホルン。手にする楽器には統一感がまるでない。
強弱のつけ方が非常にうまい。楽器で感情表現をしていることが素人にも分かった。
強弱のつけ方が非常にうまい。楽器で感情表現をしていることが素人にも分かった。
それは素朴で切実な歓喜であった。
最後の一麦を刈り取った時から爆発していたそれが、もてる技術の全てを駆使させていた。
音楽は止まず、メロディーは春風にのっていた。
最後の一麦を刈り取った時から爆発していたそれが、もてる技術の全てを駆使させていた。
音楽は止まず、メロディーは春風にのっていた。
活気溢れるラグーンを、見下ろせる場所がある。
そこに一体の石像があった。巨大である。足元からだと顔は見えないだろう。積雪と春雨で像は黒くなっていた。野晒しであったけれど、みすぼらしくはない。
そこに一体の石像があった。巨大である。足元からだと顔は見えないだろう。積雪と春雨で像は黒くなっていた。野晒しであったけれど、みすぼらしくはない。
それはただの石像であったが、この国の友人である。詩歌藩国王犬シィが過去に雄々しく吠えたのは彼女の為だけである。
遠くから眺めれば、分かったかもしれない。彼女はどこか嬉しそうに微笑んでいた。
その視線の先に、収穫を終えた春の大地があった。
その視線の先に、収穫を終えた春の大地があった。
(5)
「ビール、追加の樽が届きましたーっ!蜂蜜酒の追加はもう少しかかりますーっ」
日が真上に見えた頃、亀神殿の神官団2000人は忙殺されている。
春風祭と音楽祭が近いせいか、訪れる人の数が予想を大きく超えていた。
空の樽が山を成そうとしている。前庭にはささやかな出店が出されている。その裏では荒い息を吐いた神官が何人も腰を下ろしていた。出店に前もって置かれていた酒樽はとうの昔に空である。急遽ビール工場から追加をお願いし、神殿の地下深くから蜂蜜酒の樽を運び出していた。
春風祭と音楽祭が近いせいか、訪れる人の数が予想を大きく超えていた。
空の樽が山を成そうとしている。前庭にはささやかな出店が出されている。その裏では荒い息を吐いた神官が何人も腰を下ろしていた。出店に前もって置かれていた酒樽はとうの昔に空である。急遽ビール工場から追加をお願いし、神殿の地下深くから蜂蜜酒の樽を運び出していた。
声の主は、美女である。
北国人ではない、肌の色は薄い小麦色である。栗毛の髪をポニーテールにし、大きな両目はエメラルドの瞳を収めている。
背は、昔に比べれば少し伸びた。
北国人ではない、肌の色は薄い小麦色である。栗毛の髪をポニーテールにし、大きな両目はエメラルドの瞳を収めている。
背は、昔に比べれば少し伸びた。
「アルティニさーん、少し休んでください。働きっぱなしでしょう?ここはまかせてください。」
「ありがとうございます、それじゃお願いします。」
「こちらこそ、お手伝いありがとうございました。音楽祭、楽しんできてください。」
「ありがとうございます、それじゃお願いします。」
「こちらこそ、お手伝いありがとうございました。音楽祭、楽しんできてください。」
若い神官に後を任せ、アルティニは出店から離れた。
朝からずっとだったから体が硬くなっている。大きく伸びをして、溜まっていた息を一気に吐き出す。体が軽くなった気がした。さて、とりあえず街に行こう。
朝からずっとだったから体が硬くなっている。大きく伸びをして、溜まっていた息を一気に吐き出す。体が軽くなった気がした。さて、とりあえず街に行こう。
歩き出すと、すぐに顔見知りから声をかけられた。出店のおじさんおにいさんおねえさんおばさん、神官の人達、楽器職人のおじさん、何度も何度も。
神殿を出る頃には両手一杯に食べ物を抱えていた。後ろからリュートの優しい旋律が聞こえた。あれは多分マルク先生だな。
刈り終えた畑とラズライトラインが目の前の景色だった。
少し歩けば街が見えてくるだろう。
街でもきっと声をかけられるだろうなと思った。酒場の店主に常連達、八百屋のおばさん、魚屋のおじさん。他にもたくさんいるなと驚く。
随分顔見知りが増えたものだ。
少し歩けば街が見えてくるだろう。
街でもきっと声をかけられるだろうなと思った。酒場の店主に常連達、八百屋のおばさん、魚屋のおじさん。他にもたくさんいるなと驚く。
随分顔見知りが増えたものだ。
まったく、あの人はどこいったんだろう。
頭の隅で、無造作に髪をしばり前髪で目の見えない男を思い出した。
まぁ、そのうち帰ってくるか。その時に聞けばいいや。
頭の隅で、無造作に髪をしばり前髪で目の見えない男を思い出した。
まぁ、そのうち帰ってくるか。その時に聞けばいいや。
音符の形をした蜂蜜飴を舐めながら、足は王都イリューシアへ向いていく。
(6)
王都イリューシアは、人に溢れている。
真上に輝く太陽が、ようやく傾きはじめていた。雪解けに濡れた屋根が光り輝いている。舗装された地面は黒く濡れているが水溜りはひとつもない。
真上に輝く太陽が、ようやく傾きはじめていた。雪解けに濡れた屋根が光り輝いている。舗装された地面は黒く濡れているが水溜りはひとつもない。
道のいたるところに楽団の姿が見える。
演奏する人達は大別して2種類。音楽院の制服を着ているものとそうでないもの。
制服組は今コンサートホールで演奏している者以外は街に繰り出し楽器を好きに演奏している。自分の出番がくれば、コンサートホールに行くだろう。
手にする楽器に関連性が多少みられる。小規模でも役割分担を気にしてしまうのは音楽院での教育が染み付いているからだろう。洗練された技術が感情変化をより繊細に表現している。
演奏する人達は大別して2種類。音楽院の制服を着ているものとそうでないもの。
制服組は今コンサートホールで演奏している者以外は街に繰り出し楽器を好きに演奏している。自分の出番がくれば、コンサートホールに行くだろう。
手にする楽器に関連性が多少みられる。小規模でも役割分担を気にしてしまうのは音楽院での教育が染み付いているからだろう。洗練された技術が感情変化をより繊細に表現している。
学生以外の楽団もかなりの数いる。
手にする楽器には関連性がまるでない。見物客はこれで音楽になるのかと最初は心配したが、すぐに杞憂だとわかった。
脈々と受け継がれてきた音楽を見事なアドリブで演奏していく。込められた感情は素朴だが大きな喜びであった。
手にする楽器には関連性がまるでない。見物客はこれで音楽になるのかと最初は心配したが、すぐに杞憂だとわかった。
脈々と受け継がれてきた音楽を見事なアドリブで演奏していく。込められた感情は素朴だが大きな喜びであった。
制服組の楽団のひとつが音楽院東棟玄関付近に陣取っている。
「あれ、ロレーラ。アネッテは?」
ディーノ・ベッテンドルフが尋ねた。
年は20を超えた位のモヒカン男である。ギターの弦を調整している。ベストの下に着ているワイシャツの袖を肘あたりまで折り上げていた。
年は20を超えた位のモヒカン男である。ギターの弦を調整している。ベストの下に着ているワイシャツの袖を肘あたりまで折り上げていた。
「バレエ科で出演中。」
ロレーラと呼ばれた女性が答えた。
高い背に長く伸ばした白雪色の髪。かわいいというより格好いいといわれそうな人物である。
年はまだ若いが外見から年上に見られがちだろう。モヒカン男と同じとスラックス。袖はまくっていないが、アームベルトをつけている。
ハープの弦を優しく撫で、ため息をひとつ。どうやらアネッテという人物がいないことに不満らしい。
高い背に長く伸ばした白雪色の髪。かわいいというより格好いいといわれそうな人物である。
年はまだ若いが外見から年上に見られがちだろう。モヒカン男と同じとスラックス。袖はまくっていないが、アームベルトをつけている。
ハープの弦を優しく撫で、ため息をひとつ。どうやらアネッテという人物がいないことに不満らしい。
「じゃ、曲はダンス抜きのやつか。」
メガネをかけた青年がキーボードをいじりながらつぶやく。
トゥーサン・プーサン、彼がこのバンド結成の張本人にして作曲担当である。ブレザーが大変よく似合っている。
トゥーサン・プーサン、彼がこのバンド結成の張本人にして作曲担当である。ブレザーが大変よく似合っている。
「何でもいいからさっさとやろう。ホールでの演奏だけじゃ全然足りないんだ。」
「トマス、燃えていますね。いい演奏になりそうです。」
「トマス、燃えていますね。いい演奏になりそうです。」
やる気迸る目付きが悪い金髪の少年に先程から終始笑顔の青年が答えた。少年、トマス・オルディアレスの手にはフィドル、青年、マシュー・ウィングフィールドの手にはマンドリンがある。二人はトゥーサンと同じ、ブレザーにスラックス。
「じゃ、やるか。」
キーボードの低音から、その曲は始まった。
時間が引き延ばされているような、音色。それは、かすかな音をたて、燃える暖炉の薪。
ハープの響きが重なった、穏やかに。それは、家に流れるくつろぎの時間。
主旋律が移った。ギターの弦が、一本ずつはじかれる。テンポは、ロッキングチェアの揺れるスピード。近づく春に、心躍らせる若者。それを静かに眺める老人。
キーボードが高音に移った。フィドル、マンドリンが軽快さを演出する。それは、団欒のなかで響く笑い声。
時間が引き延ばされているような、音色。それは、かすかな音をたて、燃える暖炉の薪。
ハープの響きが重なった、穏やかに。それは、家に流れるくつろぎの時間。
主旋律が移った。ギターの弦が、一本ずつはじかれる。テンポは、ロッキングチェアの揺れるスピード。近づく春に、心躍らせる若者。それを静かに眺める老人。
キーボードが高音に移った。フィドル、マンドリンが軽快さを演出する。それは、団欒のなかで響く笑い声。
「んー、やっぱり明るさが足りないかな」
演奏を終えた後、トゥーサンが不満げに言った。
「ダンスが無いんだ、パンチが足りない選曲になるのはしょうがないさ」
ディーノの言葉にロレーンが頷く。早くアネッテ来ないかなと思ったが口には出さなかった。
「しょうがない、なぁんということでしょうっ!!それが私の生徒の言葉とはっ!!」
五人の頭上から、声が降ってきた。見上げると、屋上に人影が五つ。
声の主は、男であった。
年は20代後半、ウェーブのかかった髪に細身で中性的な顔立ち。ロレーラの顔色が驚愕に染まる。顔に見覚えがあった。
トビアス・コルッカ、彼女が属する声楽科の名物講師である。
年は20代後半、ウェーブのかかった髪に細身で中性的な顔立ち。ロレーラの顔色が驚愕に染まる。顔に見覚えがあった。
トビアス・コルッカ、彼女が属する声楽科の名物講師である。
「そうですね、あまり褒められた態度とは言い難い。」
また別の声が降ってきた。
よくとおる女性の声である。今度はトゥーサンの顔が凍りついた。原因は声の主、長身長髪の女性、セルマ・ライネ。彼が身を置く作詞科の名物講師である。
よくとおる女性の声である。今度はトゥーサンの顔が凍りついた。原因は声の主、長身長髪の女性、セルマ・ライネ。彼が身を置く作詞科の名物講師である。
「トマスッ、アンタ祭りだからって気の抜けた演奏してんじゃないわよっ!!もっとエネルギッシュにっ!!」
若い女性の怒鳴り声である。苦い顔をしたのは、トマス。この声には聞き覚えがあった、嫌というほどに。
ソフィア・レトネン、楽器演奏科の講師である。短い白髪、手にはハープをもっている。
ソフィア・レトネン、楽器演奏科の講師である。短い白髪、手にはハープをもっている。
「まぁ、言ってわかるってもんじゃねぇだろ。」
「何事も実践ですよ、ソフィア」
「何事も実践ですよ、ソフィア」
なだめすかす二つの声。トマスの表情がますます苦々しくなった。
パーヴォ・ヤルヴェ、筋骨隆々の顎鬚男。ギターのネックを握り締めている。
アルベルト・ユーティライネン、ひょろりとやせた長身の男。フルートがきらりと光った。
パーヴォ・ヤルヴェ、筋骨隆々の顎鬚男。ギターのネックを握り締めている。
アルベルト・ユーティライネン、ひょろりとやせた長身の男。フルートがきらりと光った。
「「「「「講師の実力、魅せてくれるわっ!!!!!」」」」」
「あの人らは、大人なんだか、子供なんだか・・・・・。」
音楽院東棟工房室の中、禿頭白髪のリペア科講師セヴェリ・ハルトネンの嘆息が響いた。
(7)
バイオエタノールプラントの白壁がオレンジに染まる。
蒼海に沈み往く太陽が最も鮮烈に陽光を焼き付けていた。気づけば、空の彼方に月が姿を見せている。春の月は淡くおぼろげであった。
蒼海に沈み往く太陽が最も鮮烈に陽光を焼き付けていた。気づけば、空の彼方に月が姿を見せている。春の月は淡くおぼろげであった。
「地熱の影響か、逢魔ヶ刻に陽炎が見えやがる。」
管理棟の小さな窓から、主任は外を眺めていた。
燃料不足で暖がとれずに凍えた昔を遠くに感じた。あの頃じゃ考えられないな、この平和は。
燃料不足で暖がとれずに凍えた昔を遠くに感じた。あの頃じゃ考えられないな、この平和は。
「おい、今日は音楽祭だろ。ここは俺に任せていって来いよ。他の奴らも行ってるんだから。」
「何言ってるんですか、燃料生成に使う海藻利用の構想を練らなきゃいけないんですよ?私が休んでる暇なんてないんです。」
「何言ってるんですか、燃料生成に使う海藻利用の構想を練らなきゃいけないんですよ?私が休んでる暇なんてないんです。」
答えたのは、硬い表情の若者である。専門書と論文のコピーが山を成していた。首からIDカードをぶら下げてる。
(昔の俺も、こんなに頑固だったんだろうか)
燃料生成の研究に没頭していた頃の自分を思い出そうとしたが、何一つ浮かばなかった。
そういえば随分酒も飲んでないな。元々俺って飲む酒造ってたのに。
そういえば随分酒も飲んでないな。元々俺って飲む酒造ってたのに。
「・・・・一区切りついたら、付き合え。久々に飲みたくなった。」
「はー、しょうがないですね。一杯だけですよ、おかわりなしで。どうせまた戻ってくるんですから」
「はー、しょうがないですね。一杯だけですよ、おかわりなしで。どうせまた戻ってくるんですから」
なんとも厳しい後輩だとため息をつこうとした。けれど、思い直すことにした。
なんとも頼もしい後輩だ。
(8)
その場に居る誰もが、天上に光る星々が孤独ではないと今日思った。
夜闇に沈む姿がずっと寂しそうだった。大海にポツンと浮かぶこの国も。
だが、そうではない。
今ならそう言える。隣を見れば見知った顔も見知らぬ顔もあった。
詩歌藩国音楽祭、最後の幕が開こうとしていた。
使用される楽器、人員共に過去最大数を誇る。楽器演奏科と総合科の学生、講師陣、全てが楽器を手にしている。
これまで繰り広げられていた大騒ぎが、嘘のようである。静謐が過ぎ、聴衆の背がぞくりと揺れた。演者達の手にうっすらと汗がにじむ。酒の酔いなど、とうに抜けていた。
これまで繰り広げられていた大騒ぎが、嘘のようである。静謐が過ぎ、聴衆の背がぞくりと揺れた。演者達の手にうっすらと汗がにじむ。酒の酔いなど、とうに抜けていた。
最後の演者が、整然と並ぶ演者達の前に現われた。
詩歌が誇る二人の摂政が一人、竜宮・司・ヒメリアス・ドラグゥーンである。
最後の空席、グランドピアノが埋まった。メガネをくいと押し上げる。
指揮台に立つ初老の男が、指揮棒を高く突き上げた。今まさに振り下ろされんとする一本の棒を、誰もが注視していた。
指揮台に立つ初老の男が、指揮棒を高く突き上げた。今まさに振り下ろされんとする一本の棒を、誰もが注視していた。
第一幕、開始。
音が奏でたのは、魂との再会であった。
始まりは、ピアノの緩やかな独奏。スピードは、歩くような速さで。
二人の男と一機が緑の森を抜ける。落ち葉を踏み、銀の森を故郷にもつ彼は言った。
ここは、死の森だと。湿っていて、暖かいけど、どこか冷たいと。
曲調、急転。ヴァイオリンの鋭利な音が平穏を切り裂く。
それは、突然の別離。
それは、突然の別離。
何十ものヴァイオリンはつのる不安、緊張を次々にえがきだす。
シンバルの爆発でピアノのリズムは急上昇。トランペットの音が高らかに響く。
透明な絶望。薄氷の上を無我夢中で走り抜ける必死さであった。
透明な絶望。薄氷の上を無我夢中で走り抜ける必死さであった。
涙を流しながら見上げた空が、青かった。広く、穏やかだった。
それが、無性に悔しかった。
それが、無性に悔しかった。
曲調は再び穏やかに。チェロ、トロンボーンが低く深い音を編みこむ。
男は気づく、もはや救いはないのだと。
深い失意と悔恨の中、彼は出会う。運命の少年と。
トランペット、ホルン、トロンボーン、チューバが告げた、信じがたい奇跡を。
ヴァイオリン、チェロ、ヴィオラ、コントラバスが告げた、再会の喝采を。
シンバルの爆発で全ての音が止む。
そして、流れ出すのはピアノの静かな音色。
スピードは、歩くような速さで。
手をつなぎ、歩くような。
最後の一音が止んだ。耳が痛くなるような一拍の静寂、そして。
耳が痛くなるような喝采が、惜しみなく、演者達に向けられた。
(9)
「いやー、なかなか良かった。竜宮摂政、ピアノもイケるのか。」
「だな、昼間のアレとはまた違う愛だった」
「だな、昼間のアレとはまた違う愛だった」
「昼間のアレって・・・あぁ、水着の君のお相手か」
「あんなにストレートな愛の歌は滅多に聴けないよな」
「いや、ほんと。アツかったアツかった。」
張りつめた緊張が消え、そこかしこから感想が漏れ聞こえてくる。
舞台にも動きがあった。
グランドピアノが舞台から姿を消す。聴衆の間で興奮が止んだ頃、楽器の音合わせが厳かに始まった。
まず、フルート、クラリネット、サックス、オーボエ。
次にトランペット、ホルン、トロンボーン、チューバが続く。
ヴァイオリン、チェロ、コントラバス、ギター、ハープが加わった。
最後はシンバルを初めとした打楽器。
舞台にも動きがあった。
グランドピアノが舞台から姿を消す。聴衆の間で興奮が止んだ頃、楽器の音合わせが厳かに始まった。
まず、フルート、クラリネット、サックス、オーボエ。
次にトランペット、ホルン、トロンボーン、チューバが続く。
ヴァイオリン、チェロ、コントラバス、ギター、ハープが加わった。
最後はシンバルを初めとした打楽器。
静寂が戻る。今か今かと待ちわびる、次の音楽を。
最後の演者が姿を現す。
詩歌が誇る最後の摂政、星月典子である。
一歩進む度、新雪を思わせる白銀の長い髪が揺れる。手には深い光沢を放つヴァイオリン。
指揮台の横に立ち、構えた。
指揮台の横に立ち、構えた。
そして、指揮が始まる。
第二幕、開始。
音が奏でたのは、友との別れと再会であった。
始まりは鮮烈に。一斉に弓は天を突き、弦が揺れた。
トランペット、トロンボーンが吹き鳴らされる。思わず踊りだしそうなリズム。フルート、クラリネットがさらに華やかさを演出する。
それは、聖夜の宴。
華やかさと荘厳さ。チェロやコントラバス、ホルン、チューバ、サックスが加わる。
重く響く低音が手を取り合う。
それはまるで舞踏。見慣れぬ姿をする友。手を伸ばし、彼女は掴む。彼らの手を。
けれど、宴は終わる。
旅立ちと共に。華やかさは消え、残るは荘厳さ。
ハープの音色だけが優しい。静かに、別れを惜しむように。
そして、打楽器の爆発。
ついに別れの時。ヴァイオリン、ギターが加わった。全ての音が高まっていく。
重ねあった一つの手と二つの前脚が離れていく。雄大な音楽が生まれる。
強い意思がそこにみえた。また会おう、いつの日か。
音が急に止む。
ヴァイオリンの独奏だけが残った。
ただ一人、激しくけれど美しい音色が続く。それは、友を想う心だった。
たった一つの音が止むかと思ったその時に、ヴァイオリンの音が幾十にも増えた。
それまで控えていた楽器達も続々と鳴る。演奏は最高潮に。
それは、沸き立つ喜び。
ぶつける相手は、遠くに見えるあの友達。
見慣れぬ姿の友達に。
一斉に全ての音が消えた。直後に爆発した喝采。
肩で息をする星月の顔は満面の笑みだった。
(10)
やっと、帰ってきた。
藩王九音・詩歌は舞台に続く一本道を歩いていた。
薄暗く狭い通路である。
本来広かったが、大小様々な楽器ケースがそこかしこに置かれていた。
雑然と積まれて出来たその山を見て、少し緊張する。
本来広かったが、大小様々な楽器ケースがそこかしこに置かれていた。
雑然と積まれて出来たその山を見て、少し緊張する。
これに声楽科と総合科のコーラスも加わるのか、すごい数だな。
舞台に上がり、その数に圧倒される。
どこをみても人だらけだった。まず演奏者の数に驚き、次に聴衆の数に眼を見張る。
雰囲気に飲まれそうだったが、人々の表情を見てほっとした。大人も子供も期待に目を輝かし、口元から笑みがこぼれている。
どこをみても人だらけだった。まず演奏者の数に驚き、次に聴衆の数に眼を見張る。
雰囲気に飲まれそうだったが、人々の表情を見てほっとした。大人も子供も期待に目を輝かし、口元から笑みがこぼれている。
さて、名残惜しいがフィナーレといこう。
音が奏でたのは、笑顔との再会だった。
一音のズレもなく、歌と演奏は始まった。
曲目が分かった聴衆から、一瞬の大歓声が湧く。
それは壮大な夜明け、眩しくてとても直視できないような。
ヴァイオリンの清廉さをフルート、クラリネット、木琴の音色が包み込む。
チェロ・コントラバス・ギターの低音がしっかりと音楽を支えている。
ヴァイオリンが描くのは長い長い毎日。
いくつもの苦悩に頭を抱える日々。人々の手、その温もりを知る度に深まる悩み。
歌う詩歌に無数の手拍子、前からも後ろからも。
そして、ワンシーンが終わるその瞬間に流水の如く滑り出すハープの音色。最高のリズムで鳴る打楽器。
ファンファーレのように高らかに鳴り始めるトランペット、トロンボーン、ホルン、チューバの音。ヴァイオリンの音色が次第に駆け上がっていく。
だが、思う。心から。
この無数の手が、自分を支えたのだと。万里の道を行く勇気を、与えたのだと。
詩歌は伝う汗を散らし、歌った。
言葉に出来ない無限の感謝を、一片でも伝える為に。
それにコーラスが答える、盛大に。
初雷の如く、時に春風の如く。
最後の大演奏を惜しむように、数百の楽器達は絢爛豪華に謳う。
山が笑い、崩れ行く氷雪の如く。
最後の大団円。
図ったかの如く、背後のラズライトラインに巨大な水柱が同時にいくつも上がった。
図ったかの如く、背後のラズライトラインに巨大な水柱が同時にいくつも上がった。
聴衆は圧倒され、言葉にならない。オーケストラの面々は、イタズラっ子のように笑っている。
静かな湖面を貫き、夜空に伸びる白い柱。その陰から黒い巨体が次々と浮かび、派手な水飛沫と共に沈んだ。
それは、ささやかな企て。水竜達とオーケストラの贈り物だった。
九音・詩歌は歌い続けた。
内心の驚きは隠し通せたが、喜びは隠せなかった。
内心の驚きは隠し通せたが、喜びは隠せなかった。
この祭りが、人だけのものではなかったと安心できたのはこの時である。
指揮棒が勢い良く下ろされた瞬間、音楽は唐突に止んだ。寸分の狂いもない。
詩歌は汗を拭うこともなく空を見上げ、思った。
ありがとう、みんな。
空に穴が開きそうな拍手喝采の中、藩王九音・詩歌は恭しく頭を下げた。
(終)
文:士具馬 鶏鶴
▲back 音楽祭開催について