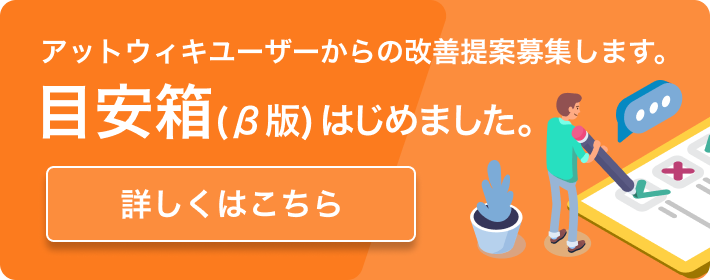薄暗い廊下を、複数の人間が駆けていた。そのほとんどは白衣に身を包んだ研究員らしき者だったが、先頭を行く一人だけは流行の服に半端な長さの金髪をなびかせる少年だった。その少年へ、白衣の一人――少年とは親子程度の歳の差に見える――が反響する靴音に負けない程度の声を出して話しかける。
「ギィ君、時間が無いから簡潔に話そう。ガーディアンAIには君が戦った“紅剣”ララエルの他に、柔と剛の技を使い鉄壁の守りを誇る“深緑両刃”マー・エモナ、圧倒的な俊敏性を武器とする“変移閃影”#2、そして複数行動で相手を地の果てまで追い詰める“長躯兵団”エイトソルジャーズがいる。“紅剣”と渡り合った君とはいえ、そいつらに出会った場合はまず逃げることを考えた方がいいだろう。奴らは倒したとしても、自分の支配するエリア内にいる限りバックアップデータから何度でも再生することができるからな」
ギィと呼ばれた少年は答えない。喋る体力も惜しいのか、正面を向いたまま軽く頷いて走り続ける。目指す先は、さっきまで彼がいた機械仕掛けの夢の中。人に在らざる者が振るう紅き剣と戦い、そして大切な人を残してきてしまった場所。
「君はこのままさっきの部屋に戻り、カプセルに入って待機していてくれ。話を聞く限りではシィラが仮想空間とこちらを結ぶ地点に防壁を張ってしまったようだが、それは私達が何とかしてみよう。それと、『向こう』へログインしたら最後、『こちら側』から君のサポートをすることはほぼ不可能だ。ほとんどのシステムは奴らに制御権を奪われるか破壊されているからな。それだけは覚悟しておいてくれ」
やはり無言で頷く少年。そんなやりとりが終わったところで道が通路と階段の二手に分かれる。集団の大半は横にそれて階段を駆け上がり、少年とそれに続くよう指示を受けた数人の白衣だけがそのまま真っ直ぐ通路を進む。ほどなくして直進組は突き当たりに位置する部屋に入り、少年が無数に並ぶカプセルの中で唯一開いてるものへとその身を滑り込ませる。それを確認した白衣の一人が少年の体へ無数のコード類を接続し、もう一人は操作盤に張り付いて指を躍らせる。やがてカプセルのシャッターと少年の瞳が同時に閉じてゆき、それを見守る数人の頭上で「ALL GREEN」のランプが灯る。
決戦の始まりだった。
◆ ◆ ◆
――その頃、この世に在らざる偽りの街の中で。
この状況を打破するために、自分の置かれている状態を冷静に確認してみようと思う。
自分は今、列車の最後尾、それも屋根の上という場所に片手で必死にぶら下がっている。顔をちょっと下に向ければそこには高速で流れ去っていくレールがあり、正面に向ければ数メートル先にさっきまで握っていた剣が突き刺さっている。そしてそのさらに手前、つまりは自分の正面数十センチという場所に、深緑の光を携えた白い影がいつでも自分を叩き落せる体勢で立ちふさがっている。
そもそも何でこんな状況になっているのか。そんなものは簡単だ。街中を歩いていたらこの白いやつに突然襲われて、駅に逃げ込んだら丁度列車が出発するところだったので乗り込んで、それでもギリギリで追いつかれたので腹をくくって屋上に誘い込んで一騎打ちを挑んで――結果、このザマである。油断していた、とは少し違う。突然の出来事に動転してしまい、幼少の頃より叩き込まれてきた戦う際の心構えその他色々を完全に失念してしまっていた。こんな状態になってようやく思い出したところで、一体どうなるというのだろうか。
「……被験者番号002、人間名ギサルフ。お前に一つだけ問わねばならないことがある。答えよ」
いきなり頭上から降ってきた言葉にそれまでの思考が強制終了され、意識が目の前の状況に集中される。声の主は無表情と手に掲げた深緑のダブルセイバーを微動だにさせず、かすかに目線だけで後方を見て言葉を続けた。
「あの剣、この世界の物ではないな。どこで手に入れたのか、答えよ」
こういう場合、適当なことを並べて時間を稼いだ方がいいんだろう。しかし自分はそういったことがかなり苦手だ。そこまで考えた時点ですでに口の方が先に動いてしまっている。
「んなこと言われても、駅に入った時たまたま隠すように置いてあったのを見つけてそのまま持ってただけだ。詳しいことは知らねーよ。それより、質問に答えた分こっちからも聞かせてもらうぞ。お前は……何者だ!」
吠えるような声にも全く怯むことなく、すぐに平坦な口調で答えが返ってきた。
「我、ガーディアンが一角“深緑両刃”マー・エモナ。我の在る理由すなわち、“人間”の破壊」
直後、深緑の光が列車の屋根を叩きつけるように動き、その軌道上が爆ぜた。
「ぬおっ!」
とっさに両手を離して斬撃を回避、同時に両足で窓を蹴破って列車の中へ転がり落ちるように逃げ込む。降り注ぐガラス片が全身に細かな傷を作り出すが、この程度の痛みはとりあえず無視。一挙動で立ち上がって体勢を立て直し、今の会話を反芻する。被験者、この世界、人間……どういう意味か詳しいことは分からないが、どうやら自分が今いるこの世界は普通のものではないようだ。
そこまで考えたところで、マー・エモナと名乗った白き両刃使いが天井を突き破って降りてきた。無表情のまま問答無用で振り回される攻撃を避けながら、奥へと逃げ――ない。吊り革にぶらさがって挑発し、攻撃を誘う。上段に振られた一撃をさすがに回避しきれず茶色の毛と鮮血が若干飛び散ったが、狙い通り。今の攻撃で抉り取られた天井から、鈍い銀色の輝きを放つ剣が降ってきた。すぐにこちらの意図を見抜いた相手からの斬撃が飛んでくるが、こちらが剣を取る方が一瞬早い。細かい破片で傷だらけの腕には負荷が大きいが、何とかこらえて防御に成功。そのまま相手の武器を弾き返し、続けざまに跳躍。一気に斬りかかる。
「人間とは、愚かな生命体だ。何故正面から我に向かうことの無意味さに気づかない?」
まるでこちらの動きが分かっているように、マー・エモナは完璧な防御を繰り出してくる。わざと力を抜いていた自分の体は、弾かれて一気に後方、列車の連結部まで吹き飛んだ。こうなれば今更こちらの狙いに気づいても、もう遅い。
「へへっ、無意味じゃないんだなー、これが」
腕に走る激痛を堪え、大きな円を描くように連結部を一閃。
地下鉄路線のど真中に、ボロボロの列車一両と乗客一名だけが取り残された。
――運命に試されし者達が、集いつつあった。
◆ ◆ ◆
再び目を開けると、すでに『向こう』へ着いていた。薄暗い研究室もそれを照らす無機質なライトも目を閉じる前最後に見た半透明のシャッターもそこには存在せず、夕焼けと夜の色が混じりあった中途半端な色の空だけが、文字通り上下左右どこまでも続いていた。ふと気づいて自分の体をあちこち触ってみると、手に伝わる感触はやはり人間のものではない。黄色の体に大きな耳と尻尾が付いていて、二足歩行なのが改めて考えるとちょっとおかしい気がするがそれは紛れも無い猫の体。遠い昔に自分と彼女が考えた落書きの中の一匹を流用して、この世界で自分にあてがわれた姿。さっきまでと違う姿のはずなのに違和感がほとんど無いというのが、かえって変な感じだ。
そこまで考えたところで、少年――今は猫の――ギィは顔を上げ、正面を見据えた。ただ空の色だけが流れる無の空間に突然、透明な色をした一直線の道が作られていく。その様子はどちらかというと新しく作られていくというより、映像を巻き戻しているように見えた。道の構成は数秒で終わり、間髪入れずに突き当たりの空間で揺らぎのようなものが発生し、そこで迷彩を施されていた漆黒の壁を登場させる。一瞬のうちに塗り替えられた景色を見つめるギィの前に今度は半透明のパネルのようなものが出現し、そこに短いメッセージが刻まれる。
『私達にできるのはここまでだ』
ギィは一瞬だけパネルを見つめ、すぐに走り出した。そして走りながら同時に“力”をイメージする。それは自らを取り巻き流れる水。すなわち全てを包み守る無限の蒼。そして大切な人のために振るわれるべきもの。少しずつ右腕に質量が集まるのを感じ、さらに強く願う。
「シィラアアアアァァァ!」
右手に生じた蒼の剣を握り締め、力任せに叩きつける。その一撃で目前に迫っていた漆黒の壁に亀裂が走り、さらに返す刃で直撃を受けた部分が粉々に砕け散る。間髪置かずにその穴に飛び込み、そして――
――紅き剣の一閃が、視界を切り裂いた。
◆ ◆ ◆
夕日の煌きが夜の闇へと姿を変え始めている。長く伸びた影はだんだんとその輪郭を失い、世界を覆い始めた黒に同調していく。変わらないのは吹き付けるビル風の冷たさと、周囲に満ちる重苦しい雰囲気だけ。狂った街の片隅にある小さなビルの屋上で、彼らはただ待ち続ける。偽られた世界を、再び真実で照らす光を。己の無力を嘆きつつ、祈ることしかできない自分達を呪いながら。
「ボク達、どうなっちゃうのかなぁ…」
「まあまあボンさんよ、そうクヨクヨなさんな。心配しなくてもなるようになるんじゃネーノ?」
「ネノー、あんたは楽観しすぎ。もっと危機感持ちなさいよ…」
「レモナサマ、現在、全テニオイテ予測不可能ナ状況ニアリマスガ、何ガアッテモ皆サマヲオ守リスルノガワタクシノ任務。デスカラ、ドウカ涙ヲオ止メニナッテクダサイ」
「…………」
ただ、待ち続ける。
◆ ◆ ◆
とっさに上半身を引いて攻撃を避けたギィに、紅い剣は少しも休むことなく次々と斬撃を叩き込む。横に、縦に、時には背後や頭上から嵐の如く連撃が繰り出され、しかしそれでもなお、蒼の剣を操るギィはその過ぎ去る光のような太刀筋の全てを的確に見切り、隣に倒れる今は桃色の猫の姿をした少女を守り抜いていた。
「くく…ははははっ!」
突然、紅い剣の使い手、暴走したこの世界のガーディアン“紅剣”ララエルが笑い声を上げた。子供じみた、高い声だった。振りかざす剣の勢いだけは変えずに、嘲笑うような笑顔を浮かべながら紫色の狂った猫は言葉を続ける。
「人間って、何考えてるのか本当に分からないね。マスターはここまで何もしなかったから大人しく殺されてくれると思ったのに反撃してくるし、止めを刺そうとしたら今度は逃げたはずの君が戻ってくるし……馬鹿じゃないの?」
対峙するギィは何も答えない。ただほんの少しだけ顔に怒りの表情が表れ、剣にかける力が増した。今まで防戦一方だった動きを変えて横一線に渾身の一撃を放ち、防御の姿勢をとったララエルを数メートル吹き飛ばす。相手が驚いたような顔をした一瞬の隙に跳躍して距離を戻し、さらに追撃をかける。完全に立場が逆転していた。しかしそれでも、紅い剣は笑って言う。
「ははっ、怒ったかい? 感情に流されるなんて、やっぱり人の心なんて不完全で不安定だ…。心の力なんて僕は認めない。心なんて、なければいいんだ。だから……死ねっ!」
瞬間、紅い剣の表面が炎のように揺らめき、爆ぜた。
「なっ…!」
とっさに防御姿勢をとったギィの体を、真紅の波動が貫いていく。全身を駆け巡る衝撃波は次々に裂傷となり、生じた暴風が崩れかけた体勢のギィを宙に持ち上げ吹き飛ばす。そのまま背後にそびえる漆黒の壁まで吹き飛ばされたギィは、意識が途切れそうな痛みをこらえて立ち上がろうとし、そこで眼前にまで迫った笑顔があるのに気づいた。蟻を踏み潰して優越感に浸る子供のような、無邪気ゆえに残虐な笑みだった。
「……これで、終わりだ」
呆然とするギィの目の前で紅い剣が振り上げられ、心臓のように鼓動する。そして――
――蒼に輝く一筋の光が、剣を掲げたララエルの腕を貫いた。
「はぁ、はぁ、ララエル、お願いだからもうやめて……!」
目を覚ましたこの世界の“マスター”シィラが光の弓矢を構え、ギィとララエルを見つめていた。言葉こそしっかりしていたが顔は青ざめて呼吸も乱れ、澄んだ瞳からは今にも涙がこぼれてきそうだった。
「マスター……」
対するララエルは先ほどまでの邪悪な笑みから一転、何か大切なものを失くしてしまったような哀しい目で本来自分が仕えるべき者の名を呟いた。一瞬の後、腕に残る傷と目の前に倒れる黄色の猫を一瞥してから漆黒の壁に背を向け、街の方角へ跳躍しながら去っていった。
最後に小さく一言、「南十字で待つよ」とだけ言って。
◆ ◆ ◆
なあ、兄者。
「ん? どうした」
さっきの赤い奴、放っておいても大丈夫なのか? さっきは妹者の不意討ちで撃退できたけど、あの程度の傷ならバックアップからすぐに再生できるし、何度も同じ手は通用しないぞ。何か他に策でもあるのか?
「ああ、それなら心配無い。あの拳銃型クラッシュプログラムには俺の特製ウイルスが仕込んであるからな」
ウイルス? それは初耳だぞ。
「そういえば教えてなかったな。あのウイルスは打ち込まれると偽の情報を流し込んで対象のソフトの“本来の部品”に化けるんだ。そしてバスティングソフトやデータの初期化による削除から逃れ、少しずつだが確実に内部から全体を変化させ、破壊する。まあ、人間で言うところの肥満みたいなものだな。違和感無く、しかし確実に全身を蝕む…そんなウイルスというわけだ」
ほお、それで、そのウイルスはどこをどう破壊していくよう設計されてるんだ?
「…………」
おい、兄者、聞こえてるのか?
「……そこまでは、分からん。事前にどの部分が何を司っているかまで調べ切れなかったから、ウイルスが目標とする箇所とそこをどのように改変するかはほとんどランダムに設定してある」
相変わらず兄者は詰めが甘いな。今回の作戦は最初からそうだ。めぼしいデータ盗んだらすぐ逃げる予定だったのに出口を調べてなかったなんて言い出すし、主力になるはずの剣型とトラック型のプログラムは転送先を間違えた上に誰かが使ってるみたいだし、切り札の特製ウイルスは未完成……どうしたものかね。
「うるさい。今ちょうどデータをまとめて今後の行動を考えてるとこだ。お前はバイクに後部座席とサイドカーの増設でもしてろ。あとそろそろ妹者のこと起こしとけ」
了解。やれやれ、今回ばかりは本当に死ぬかもな。
「……弟者、一つだけ言っておく」
いきなりどうした、兄者。遺言だったら聞きたくないぞ。
「――この世に、母者のゲンコツより強いものなんて無いさ」
……それもそうだな。
◆ ◆ ◆
「どうして……どうして戻ってきたのっ……!」
ララエルが去った後、シィラは傷だらけのまま壁によりかかるギィに駆け寄り、両目から溢れる涙も拭わず開口一番そう言った。数秒の間があってようやくギィが反応を示し、かすかに唇を上下させる。
「…とえ……しても………かえ……のために…」
「え?」
「……行け、たとえ困難に直面しても。戦え、自分が信じる者のために――1年前、くらいかな。君がいなくなって途方に暮れてた時、道でたまたますれ違った占い師に言われたんだ。……シィラ、オレのいる場所は、君の隣だ。だから、君がここにいる限り、逃げ出したりなんかしない」
なんとか一息でそこまで言って、黄色い猫は笑った。
それを見た桃色の猫も、寂しげに笑った。
日が沈み、世界が夕焼けの色を失う。その空いた空間を新たに支配するのは、濃厚な漆黒の闇。この先に潜む脅威がそのまま具現化したような、どこまでも続く黒の世界。
そんな世界の中心、全てが黒い中でなお存在感を保ってそびえ立つビル街へ向かい、ギィとシィラの二人――今は二匹――は歩を進めていた。全てに決着をつけるため。そして今度こそ二人で真実の世界へ帰るために。
「何でだ……?」
不意にギィが立ち止まり、後ろへ振り返る。そこにあるのはたった今渡り終えた巨大なつり橋。最初にこの世界から出ようとした時にも歩き、初めてあの“紅剣”ララエルと戦った場所だ。
「壊れて、なかった……」
あの時、つり橋の塔部分から飛び降りる形で奇襲を仕掛けてきたララエルによって橋の一部に大穴ができたはずなのだ。しかし、今渡ってきたそれにはどんなに注意深く見つめても穴どころか傷の一つも見当たらない。まるで、橋を丸ごと全部新品に取り替えたようだった。「あ、あのね、ギィ、それは……」
そのまま思慮にふけってしまいそうなギィの様子に気づき、慌ててシィラが説明を始める。それによると、どうやらこの世界は定期的にベースとなる夢を見ている彼女から世界のイメージを受信し、それを直接上書きすることによって破損箇所の修復・構成の維持を行っているらしい。
「この程度なら何ともないけれど、例えばビルが数本まとめて消えたりしたら、イメージの送受信時にその誤差で生じるエラーが負荷になって私はしばらく動けなくなっちゃうの。一応覚えておいて」
そう最後に付け足して説明は終わり、二人は再び歩き始めた。
最初の目的地は目前にそびえ立つビル街の一角。シィラがマスターにのみ受信可能な最上級の秘匿通信をそこから受け取ったらしい。通信の内容は、おそらく極限まで通信時間を抑えるためだろうが「help」の一言のみ。もちろん罠である可能性も十分にあるが、いきなりララエルを追うにしても危険が高く、これに賭けるしかなかった。
自然と、二人の足取りは速くなる。
◆ ◆ ◆
「うわあああ! オーギリさん、もっと速く! 追いつかれちゃうよ!」
「お、落ち着いてイワン君! ま、まだ大丈夫……」
ああもう、言ってる自分が落ち着いてないじゃないか。落ち着け落ち着け落ち着け自分。落ち着いて今の状況を一から整理するんだ。
ええと、僕の名前はオーギリ。オニギリみたいな顔をしてるけれど、だからこういう名前というわけじゃない……と思う。何故かその辺は記憶が曖昧だ。どう言えばいんだろう、まるで“夢の中で自分じゃない誰かになっている”ような、そんな感じだ。
トラックの荷台に乗っている茶髪に青い服の人はイワン君。フルネームはとても長くて「イー・なんたら・なんたら・ワン」って言うらしいけれど、他の人からは呼びやすいようにイワンって呼ばれているそうだ。それで僕もそうしている。さっきから半分パニックになっているのがちょっと心配だけれど、正直僕も何がどうなっているのかさっぱり分からなくて混乱してるのでそれはしょうがないかもしれない。
そしてサイドミラー越しに見えるのが、この混乱の大元。白っぽい体はやけに等身が高くて、おまけにほとんど無表情。手足に光で出来たような車輪を使っているのと、背中からやはり光のようなプロペラを使っているのと、直接走っているのと合計三体。僕達は今、このなんだか気持ち悪い連中に追われている。
事の始まりは確かまだ日が沈む前…ってことはもうずいぶん逃げてることになる。街を歩いていたらイワン君と会って意気投合して、色々他愛も無い話をしながら道を進んでたら裏路地に隠すようにして今乗っているこのトラックがあったのを偶然見つけて、誰のだろうかと思ってたらいきなりこいつらが追いかけてきたから仕方なくトラックに乗って逃げて、それからずっと逃げっぱなし。
うう、僕達が何をしたっていうんだ。そりゃあ、このトラックは盗んだようなものだけどその前からこいつらは追いかけてきてるわけで……あああ!
神様、もしいるのなら助けてください。
『――あー、聞こえるか? 聞こえたら返事しろ』
「だだだだ、誰っ!?」
「だっ、誰です! 一体どこから……」
『まあ落ち着け。そのトラックには通信機が備えてある。ハンドルの右にあるエアコンの送風口っぽいのがそうだ。俺は今、それを通して声を送っている。分かったか?』
言われた場所を見てみたら、たしかにエアコンの送風口らしきものがあった。そばについている数個の小さなボタンが本当はそんなものじゃないと訴えている。いきなり声が聞こえてきて僕もイワン君もかなり驚いたけれど、これで謎は解けた。でも……
「えっと……それで、あなた、誰ですか?」
通信機のことを説明してくれたから、多分このトラックの持ち主なんだろう。でも普通、送風口に偽装した通信機をトラックにつけたりなんてしない。おかしい。怪しい。信用できない。もしかしたら今後ろから追いかけてきてる連中の仲間かもしれない。もし本当にそうだったらすごくまずいような……
『うむ、この状況では疑われても仕方ないな。信じてもらえないかもしれんが、俺達は味方だ。名前はわけあって明かせないから、とりあえず“兄者”と呼んでくれ。あ、ちょっと失礼――弟者、まだ“侵食剣”の座標はトレースできないか?』
「あの! 兄者に弟者ってもしかして……」
どう返せばいいか悩む僕が結論を出すより早く、イワン君が口を開いた。どうやらこの人達について心当たりがあるらしい。それなら会話はイワン君に任せて、僕は運転に集中した方が良さそうだ。
『じゃ、そっちは任せたぞ――で、何かな。続けたまえ、イワン君とやら』
「……ちょっと前に噂で聞いたことがあるんです。自分たちのことを“兄者”とか“弟者”とかって呼ぶ以外に素性不明、世界中のあらゆる情報を盗み出して裏で売りさばく天才ハッカー兄弟がいるって。まさか、でも……」
なるほど、そういうことならこの状況もある程度は納得できる。途中で聞こえた意味不明な単語、“侵食剣”というのが唯一分からないが、それはこの際置いておこう。でも、それでもこの人達の真意が分からない。世界中に敵のいるハッカーが、どうしてこんな堂々と登場してきたのだろうか。このトラックに大事な何かがあるにしても、僕達を助ける理由にはならないはずだ。むしろ目撃者を消そうとするはず。イワン君が最後に言葉を濁したのもそう思ってのことだろう。何がどうなって……
『うむ、正解だ。不思議に思っているだろう、世界的な犯罪者が自分の仕事道具を見た者を助けているのだからな。――まあ、何と言うか、俺達の仕事は命を奪うことじゃない、ってだけだ。それではこれより、そのトラックに搭載してある武装について説明する。生きて帰ろうぜ、兄弟』
まあ、この際すがれるものにはすがっておいた方がいいみたい。
◆ ◆ ◆
「マスター、オ待チシテオリマシタ」
天を目指しながら互いの高さを競うようにそびえ立つビルの一つ、その屋上にたどり着いたギィとシィラを待っていたのはガーディアンの罠などではなく、全く予想していなかった者達の存在だった。
「えっと、このちっこいのがジェンディスタ、あんたらがそっちから順にレモナさん、ボン、ネノーか。よし、覚えた」
周囲を常闇が覆う中でこのビルの屋上だけは世界から切り離されたように明るく、お互いの顔をはっきりと認識することができた。シィラ以外に初めて出会う他の人間ということで多少戸惑うギィの足元、顔だけの小さい身体でぴょんぴょんと跳ねているのはプレイヤーガイド専門のAI、ジェンディスタ(と本人から説明を受けた)。彼がまだ使用可能な管理者としての権限を駆使して世界の定義を改変し、結果としてこの場所は外からは絶対に認識できないようになっているらしい。
人間型に近い姿をして長い金髪をなびかせているのが女性プレイヤーのレモナ、その奥でずっと怯えた顔をしている水色のネコ型がボンで、正反対に「どうにかなるさ」と言わんばかりの顔でにやけているのはネノー。彼らはプレイヤーの安全を最優先して反乱行動に加担しなかったジェンディスタと最初に出会うことができた、幸運な者達だった。そして、非力であるがゆえにこうして隠れることしかできない、不運な者達であった。
「うまく説明できないけれど、“知る”ことと“感じる”ことは違うんだと思うんだ。ここは夢だから思い通りに力を出せます、ってジェンディスタさんに言われても、ボク達にはできなかったよ……」
「悔しいけれど、ボンの言う通りね。だから、お願い。私達を助けて」
「分かりました、皆さんのことは何としてでも無事にもとの世界へ戻します。……こんなことになってしまって申し訳ありません」
一通りお互いの状況を確認し、いよいよ脱出作戦が練られることになった。問題はどこからどのようにして脱出するか。シィラとジェンディスタの持つ情報を総合すると、この世界から元の世界へ戻るための正規のルートは全部で三つ。一つはギィが最初に脱出した街の外。これは現実だけでなく外界のネットワークに直結しているらしく、万が一反乱側AIが使用して外界に逃げるようなことになったら取り返しがつかなくなる。距離的な問題と展開中の防壁を取り払うリスクを考えるとこれは使えない。次に、四つのエリアに区切られた街の各エリア中心部に設置してある転送装置。距離的には最短だが、ジェンディスタからもたらされた情報によるとこれはすでに各エリアのガーディアン達によって破壊されていて使えないらしい。最後は各エリアを街の中心で一つに繋ぐ“南十字星通り”という名の大通り。ここの転送装置はガーディアンとは別に、世界の基本的なパラメータ――重力や空気抵抗といった類の情報――を司る専用のAIが制御しており、有事の際はそのAIとマスター以外誰も触れることすらできないようになっているらしい。これを使うのが、一番確実に思われた。
「やっぱり、それしかないわね。でも……」
「あいつとだけは、どうやっても正面からぶつかることになるだろうな。…全部向こうの計算どおりか」
ここにたどり着く前、最強のガーディアンと戦ったギィとシィラは、彼の口からこう聞いたのだ。
――南十字で待つよ――
このまま進めば、確実にララエルと戦うことになる。それどころか最悪の場合、等距離にあるそれぞれのエリアから他のガーディアンが集結する危険性もある。分の悪い博打だった。
「……ジェンディスタ、少し作戦を変えます。私とギィは先行して南十字通りに向かい、ララエルと交戦。その間、あなたは皆さんと共に他のプレイヤーの救助にあたってください」
ギィとジェンディスタは素直に頷いた。非力な者を三人も抱えた状態でララエルと戦えば、こちらの負けは見えている。それなら離れ離れになる危険を冒してでも、それぞれに可能なことをこなした方がいい。全滅を避けるためにはこの方法が一番なのだ。だが。
「ま、待ってよ! 助けてくれるって言ったじゃないか、なのに、なんでまたボク達だけで……」
それを理解できない者は、絶対に出てくる。
怯える顔をさらに恐怖で歪ませ、ボンがシィラの提案に食って掛かる。
「い、嫌だよそんなの…やっと、やっと助けてくれる人に会えたのに……こんなの…ないよ……うっ…」
怖くて、苦しくて、悲しい、叫び。
シィラとギィは申し訳なさそうに顔を伏せ、レモナは何か言おうとして失敗する。こうする他に無い、なんてことは彼だって言わなくても分かっているのだ。ただ、どうしようもなく怖いだけ。あふれ出す感情とそれを制御できない自分への混乱が生み出す、涙の無限連鎖。
「っ……うぅ……いや…だ……」
「……なあ、ちょっと面貸せよ」
今までの会話に興味を示さずずっと外を眺めていたネノーが、いつの間にかボンの真横に立っていた。ボンは彼が自分に向けて放った言葉に気づくことなくただ泣き続け、それを確認した男の顔からにやけた表情が消える。
――次の瞬間、人が殴られて吹っ飛ぶ音が響き渡った。
「ちょっと、ネノー! それはいくらなんでもやりすぎ…」
「あんたは黙ってろ」
抗議の声を上げたレモナを、冷たい台詞が一蹴した。
完全に怯えきっているボンの視線を正面から受けながら、殴った本人はさらに冷たい声を出して言葉を綴る。
「お前なぁ、さっきから黙って聞いてりゃ甘ったれやがって。いい加減頭に来るんだよ。いいか? 弱いのも、怖いのも、お前だけなわけねーだろ。オレだって、本当は…怖いのに……無理して、笑って……やってんのに…お前は……」
そこまで言って、ネノーは皆に背を向けた。彼の足元に水滴が落ちていく。
「……ごめんなさい、ネノーさん、それに皆さん。まだ、何も終わってないんですよね。なのに、ボクは……」
「おっと、それ以上は言うな。また泣かれたらたまったもんじゃねーっての」
もう元に戻ったにやけ顔が、縮こまるボンを明るい口調でなだめる。遠目からその光景を眺めるレモナにとっては、ジェンディスタと出会ってからの数時間で何度も見た姿だった。対照的な二人だが、こうやって釣り合えばきっと最後まで何とかなる。彼女にはそう思えた。
この世に在らざる夢の街
そこに住まうは悪魔と天使
迷い込む者光を探し
必ず還るとここに誓う
再び出会う約束の地は
南十字の交わる先
◆ ◆ ◆
本来の姿より一両分短くなった列車は、だからといって特に運行に支障をきたした様子もなく動き続け次の駅へと無事到着した。
駅員の一人も無く全く動作していない改札を通って外に出ると、はるか彼方では太陽がその輝きの半分以上を地に埋めようとしているところだった。
「さて、と。どうするかな」
誰に言うでもなく、被験者番号002・ギサルフは呟く。
彼はまだ、この世界の真実に気づいていない。現実世界においては有名な剣道場の跡取りで、そこに通っている昔からの親友ギィには負けた事が無い――などということは思い出せず、せいぜい肉体に染み付いた武術の感覚が生きている程度。どうやっても常識の範囲に縛られた動きしかできず、今の彼の力を支えているのは偶然見つけて手に入れた謎の大剣一本だけだった。
「そもそもここがどこなのか分からないもんなぁ。誰か人見つけて……うおっ!」
いつの間にか、背後に一人の少女(一匹の猫という認識をするのは、夢を自覚している者だけだ)が立っていた。一切の音や気配を伴わず、まるで突然現れたように彼女はそこにいた。体色は赤で、何故か左肩に大きな傷がある。とっさに身をひねって剣を構えたギサルフの反応とは逆に警戒や殺気の類はまるで感じられず、ただ無防備な姿勢のまま虚ろな目で相手のことを見ていた。
「…お前、何者だ」
少しも隙を見せようとせず、射殺すような目で高圧的に問いかける。
数秒置いて、弱弱しい少女そのものな声で返事があった。
「アタシは……第二世代型ガーディアンの…“変移閃影”#2……人間――お前が、道に迷っているようだったから……来た…」
「っ!」
聞き取りづらい言葉の中に含まれていた一つの単語に、ギサルフは戦慄した。ガーディアン。先ほど戦ったあの圧倒的な力を誇る冷酷な両刃使いも、自らをそう表した。とてもそうは見えないが、仮に目の前の少女がそうだとすればこの状況は非常に危険だ。先ほどは列車の中という状況で逃げに集中したから何とかなったが、今はそうはいかない。何かで距離を稼ぎ逃走することは不可能な上、ならば戦って勝てるかといえばそうでもない。どんな芸当をやってのけたのかは分からないが、相手は一切の音や気配を伴うことなくこちらの背後をとることができるのだ。一対一の戦いにおいて、これほど一方的なハンデは無い。
「何故……武器を、構える…? アタシは…プレイヤーのサポートも…兼ねているんだ……脅さなくても、管理に支障が出ない範囲なら…質問に答えるぞ……」
「なっ…そ、そんな手に…乗るわけ……ああもう!」
あまりに儚げな相手の反応に、いちいち頭の隅で策略を巡らせながら剣を向けるのが馬鹿らしくなってきた。よくよく考えたら、本当に攻撃の意思があるならとっくにそうしているはずなのだ。あの両刃使いと同等の力があるならば、こんな小細工をして油断させる必要も無い。空いている方の手でがしがしと頭をかきながら、ならどう話を切り出したらよいものかと考える。
「……じゃあさ、一通り教えてくれよ。ガーディアンだのプレイヤーだの、何のことだかさっぱりだ…」
「分かった。本当は…データ比較のために教えないつもりだったけれど…結果的に混乱させてしまったし…マスターも…この方針に少し反対してたから……話そう」
予想以上にすんなりと話は進み、長い長い説明が始まった。
「“変移閃影”#2が知る限りの」情報の全てをギサルフが理解した頃には、もう完全に日が落ちて周囲は暗黒に閉ざされていた。二人は今、一つだけ明かりの灯った街灯の下、ビルの壁にもたれて座っている。本来は全ての街灯が灯って明るさを保つはずなのだがどうやら故障らしい、と#2の説明。これじゃあ暗すぎると文句を言うギサルフに、だったらと彼女は一番近くにあった街灯を管理者権限で直接起動し、それからそこで話を続けているのだった。
「あのシィラがお前のマスター、ねえ。それにギィのやつも参加してるのか」
「マスターと、知り合いなのか?」
「一応な。俺とギィが仲良くって、ギィとシィラが仲良くって。それでよく小さい頃から一緒に遊んだりしてたんだ。あいつらよく髪伸ばしてる俺のことフサフサ野郎って呼んで面白がってたんだけど、ここでもか…」
そう言って、ギサルフは自分の腕を見つめる。彼の姿――長毛の猫型は、今この世界にいるプレイヤー及びAIの中で唯一のものらしい。思わず深いため息をつき、「ところで」と話を戻す。
「お前…その肩の傷、どうしたんだ?」
「……えっ?」
返ってきた反応は予想外のものだった。何のことだか分からないといった顔でギサルフを見つめ、彼が指差した方向に首を傾けてみる。そして、目を見開いた。どうやら彼女は、本当に今の今まで自分の左肩にある大きな傷に気づかなかったらしい。
「いつの…間に…? でも、これなら…多分、バックアップにアクセスして…修復できると思う」
そう言って、彼女は目を閉じてひざまずくような姿勢をとる。
(エリア管制システムへアクセスを開始…成功。現在のアクセスポイントから到達可能な位置に存在するガーディアンAI用バックアップを検索……発見。ダウンロード開始……終了。インストール開始………エラー! 損傷箇所の認識に失敗。ダウンロードしたデータを破棄、全プロセスを強制終了)
「……駄目だ。うまくいかない。何故かは分からないけれど…この傷が、傷として認識されてない」
立ち上がった#2は、そう言って首を横に振った。その顔には少なからず困惑の色が浮かんでいる。
ギサルフはそんな彼女になんと言うべきか逡巡し――直後、ほとんど本能的に感じた風の音に向かって剣をはらい、背後に迫った深緑のダブルセイバーを寸前で弾き返した。
不意討ちをかわされたガーディアン“深緑両刃”マー・エモナは、それ以上追撃しようとはせず一歩下がって防御の姿勢をとる。対峙するギサルフも続けて踏み込むようなことはせず、か細い少女を空いている手でかばうようにしながら相手との距離を置く。
「そういえば、まだ聞いてなかったな。なんでこいつは、俺のこと殺そうとするんだ?」
「あ…エモナ……なんで…このエリアに…」
「“変移閃影”#2、何故その人間を殺さないのだ。口調も普段と異なるな。何があった?」
それぞれの疑問に答える者も無く、数秒の静寂。
それを打ち破ったのは、剣のぶつかる甲高い音。
◆ ◆ ◆
「ねえ、ジェンディスタ。私達以外のプレイヤーって今どこにいるの?」
「ハイ、レモナサマ。ワタクシ達ガ現在ムカッテイルエリアデ常ニ移動シテイル方ガ二名、ソノ隣ノエリアニ三名、エリア移動用ノ列車型輸送装置ヲ使用シテイテ詳細不明ナ方ガ一名デス。モットモ、コチラノ動向ヲガーディアンニ気ヅカレナイヨウ古いログノミニアクセスシテイルノデ現在ハ違ウ場所ニイル可能性モアリマスガ」
ギィ、シィラと別れたレモナ、ネノー、ボンの“一般人”三人は、ジェンディスタの作り出す特殊な障壁――有事の際にプレイヤーを守るためのもので、外部からは透明に見える上物理的な衝撃に対してもほぼ完璧な防御力という優れものだ――に包まれながら残りのプレイヤーを探して闇の街を歩いている。彼らの周辺を明るく照らし出す障壁は半径三メートルほどの円形で、さきほど屋上で展開していたものに比べるとかなり小さい。ジェンディスタに言わせると常に移動に合わせて展開範囲を変えるのは負荷が大きく、これで限界らしい。
「この近くに二人いるのね。でも、常に移動してるってどういうこと?」
「ソレハワタクシモヨク分カリマセン。速度ヲミル限リ、ガーディアン“長躯兵団”カラ逃ゲ回ッテイルモノト思ワレマスガ、コノエリアニソレホドノ速度ヲ出スコトガデキル装置ハ存在シナイハズ…」
そう言ってジェンディスタは困ったような顔をする。この小さなAIは、人間と遜色ない感情表現が実に得意だった。
本人の説明によれば彼は他のAIよりも後に生まれた「第二世代型」と呼ばれるタイプで、プレイヤーとの交流を前提により人間らしい感情と思考を持つように設計されているらしい。下された命令もただ受け入れるのではなく独自に持つ基準に当てはめて考え、結果が理不尽なものになると判断したら従わない。だから彼は今、こうして人々を守るべく動いている。暴走した仲間達に敵意すら覚えながら。
それから数分。変化は唐突にやってきた。
全員がほぼ同時に気づいたのは、はるか後方から聞こえてくる爆音。空気を震わせながら響く何かのエンジンらしき音に、時折タイヤの擦れる音が混じる。音は瞬く間に大きくなり、一際大きい急ブレーキの音に振り向いた時には――そこにバイクが一台止まっていた。
赤と黒で塗られたボディに、少量の排気を出しながら低くうなるエンジン。ハンドルを握るのはレモナ達と同じような猫の姿をした緑色の青年で、後部座席にはやはり同じような姿をした青い青年がノートパソコンを片手に座っている。バイクの左側にはサイドカーが取り付けられていて、乗っているのは何故か人間そのままの姿をした少女。短くまとめた薄桃混じりの黒髪に、桃色の服と濃緑のズボン。どういう訳か、可愛らしい外見にとことん不釣合いな黒い拳銃を握っている。
突然の事態に、誰も何も言えなかった。
とにかく状況を見極めようと、ジェンディスタは一人思考を開始する。いきなり障壁を取り払って話しかけるには、彼らは怪しすぎる。
まず、その外見。青年二人は最初からプレイヤー用の容姿として用意されている姿なのだが、少女の姿は人間そのまま。こうするには、システムの深部にアクセスして直接データを改ざんするしかない。ガーディアン達に探知されるのを覚悟で最新のプレイヤー管理情報にアクセスし、そこで一人分の容姿情報の改ざんと、三人分の経歴情報の破壊を確認する。おそらくは機密情報目当てのハッカーか何かなのだろう。
そして今この状況において最大の問題点は、彼らが
ガーディアンですら感知できないこの障壁とその中にいる自分達を真っ直ぐに見つめているということは即ち、向こうが障壁を無効化する何らかの技術を持っているということ。あの少女が腕を少し上げて引き金に指をかければ、誰かの血が飛ぶことは避けられない。こうなれば相打ちしてでも――
「おい兄者、やっぱ警戒されてるぞ。俺ら」
「あー、そのー、まー、なんだ。俺らは別に怪しい者じゃないっても怪しさ満点なわけで確かに不正アクセスで色々いじらせてもらったけどお前らを殺すとかそういうことは一切考えてないしむしろ脱出に協力したいからそこそこ丈夫なその障壁取り払ってまずは情報交換といきませんか、みたいなつもりで近づいたわけなんだが…」
「あにじゃー、それ全っ然説明になってない気がする」
コンマ数秒で進行するジェンディスタの高速思考に気づく様子もなく、三人はやけに気の抜けた会話を始める。緊張感ゼロで展開されるあーだこーだの論争はいつの間にかただの兄弟喧嘩にすりかわり、ようやく我に返ったレモナの
「あのっ」
という一言がなければ、多分永遠に続いていた。
◆ ◆ ◆
闇に包まれた街の大通りに、黒い世界を切り裂いて進む光が二つ。
そのうち一つはバイクのもの。赤と黒のボディに二人がまたがり、左側面のサイドカーにもう一人。
もう一つは軽トラックのもの。暗闇でも目立つ白い車体で、広々とした荷台には積荷ではなくいくつもの人影を乗せている。
「それで、これからどうするんですか?」
トラックの運転手、オニギリ頭をした青年が不満げに口を開く。
ガーディアンの一角“長躯兵団”に追い回されること数時間、トラックに備え付けられていた通信機から聞こえる声を頼りに追撃を振り切って指定された場所に行ってみれば、そこにいたのは声の主の他に自分達と同じような状況らしい人々が他にも三人。とりあえず全員荷台に乗ってもらってバイクと共に再び走り出したのが15分ほど前のことで、まだ互いの自己紹介くらいしかしていない。けっこう命がけのはずなのにこんな調子でいいのかと、彼オーギリはため息をつく。
「んー、その小さいのが言うには脱出地点に待ち伏せてるやつがいるらしいから、別働隊が何とかしてくれるまで俺らは逃げ続けるしかないだろうな。イワン、各人に武器を渡しとけ。取り出し方は覚えてるな」
「あ、はい」
バイクのハンドルを握る青年――兄者とだけ名乗った。自称天才ハッカー一家の長男らしい――の指示を受け、トラックの荷台に座る中の一人、イワンと呼ばれた茶髪の青年が床に手を触れる。すると触れた部分から計算機のようなボタン配置の操作盤がせり上がり、「パスワード入力」の文字が表示される。イワンがそこへ少々迷いながら十六桁の数字列を打ち込み、「認証」の表示。
「はい、好きなの選んで。使いやすさはどれも一緒だよ。ここは夢とプログラムの世界だし」
新しく荷台の住人となった三人と一体から驚きの視線を受けながら、荷台の中央から大きな箱がせり上がる。その中にクレーンゲームの景品よろしく大量にぶら下がっているのは、様々な種類の銃器一式。片手で扱える小さな拳銃から、本来ならとても生身では撃てないであろう大型ガトリングまで揃っている。
「す、すごい…」
手近な拳銃を握り締め、少年――姿は水色の猫――ボンが感嘆の声を上げる。今までずっと無力感に打ちのめされてきた彼にとって、目の前にある武器の山は希望の光そのものなのだろう。
そんな彼の肩をポンと叩きながら、隣で小機関銃を手にした青年、ネノーがおどけた調子で話しかける。
「場合によっちゃ、これから派手な撃ち合いだ。びびんじゃねーぞ?」
「はいっ!」
振り返りながら発したその言葉に、これまで見せてきた臆病な様子は無い。
(なんだ…ただの泣き虫かと思ってたけど、やればできる子なんじゃない。これなら、何とかなるかな)
格好つけて二挺拳銃にしてみたレモナが、二人の様子を見て顔をほころばせる。圧倒的な絶望の中にあってもなお失われない、友情の輝き。それがある限り自分達は負けたりしないと、彼女は確信できた。
「あにじゃー、お客さんみたいだよー。皆さんも気をつけてー」
バイクのサイドカーに乗り込む人間の姿をした少女――やはり本名ではなく、妹者とだけ名乗った――が、やけに気の抜けた声で敵襲を告げる。しかし声の調子とは正反対にその顔は引き締まっており、彼女の構える銃はすでに、並んで走るトラックとバイクの後方数百メートル先、見えるか見えないかの位置にいる三体の巨人、“長躯兵団”エイトソルジャーズを正確に照準している。
「よーし、総員戦闘準備。小さいの、お前はナビゲーターを頼む。トラックの方にしまってあるデータ類も自由に使って構わん」
「了解シマシタ。…ソレニシテモ、ヨクコレダケノ機密データヲ盗ミ出シタモノデスネ」
兄者からの指示を受けたジェンディスタの周囲に無数の半透明なディスプレイが展開され、現在地を示すマップデータからガーディアンの詳細な戦闘能力まで様々な情報が表示される。これが全て不正アクセスで盗まれたものだという事実に驚きと呆れの表情を作りながら、小さなAIが解析を開始する。
その様子を横目で確認し、バイクの運転手は自身のすぐ後ろ、先ほどからずっとノートパソコンと格闘する弟に声をかける。
「弟者、“侵食剣”の方は?」
弟者と呼ばれた青年が、顔を上げずに答える。
「通信を安定させるまであと数分、ってとこだな。しかし持ち主は色々大変なことになってるみたいだから、話ができるのはもうちょっと後かもしれん。兄者お手製ウイルスのせいで味方が増えそうなのはいい誤算だが」
どういう意味だ、と質問が返ってくる前に、兄の考えていることを正確に汲み取った弟がパソコン画面を差し出して表示されたデータを見せる。兄者はバイクの進行方向に向けた顔を逸らさず、視界の隅で差し出された情報を器用に見つめる。数秒して、その顔にかすかな笑みが浮かんだ。
「なるほど、上出来だ。…オーギリ、速度上げるからしっかり続け!」
夜の街に、無数の銃声と二つのエンジン音が響き渡った。
◆ ◆ ◆
斜め上から振り下ろされた大剣が、軌道を予知していたかのように現れた光の刃に阻まれる。
「無駄だと、何度言えば理解できるのだ」
深緑色に輝くダブルセイバーで大剣の動きを封じ込めるマー・エモナが言う。その顔は相変わらずの無表情で、全力で振り下ろされた一撃を受け止めながらも眉一つ動かそうとしない。
鍔迫り合いのまま対峙するギサルフは、そんな相手から放たれた抑揚のない言葉を沈黙で弾き返す。
そのまま硬直すること数秒。せめぎ合う力が臨界に達し、互いに武器を弾いて距離を置く。着地と同時に双方駆け出し、何度目かの金属音が鳴り響く。
(――戦力分析完了。“
ひたすらに正面からの力押しをしてくるギサルフに対しやはり正面から受け止めていたエモナが、突如としてその動きを変えた。
真横に構えて剣を受け止めていたダブルセイバーを前後と上下に半回転させ、相手の攻撃を払いのけると同時に地面に突き立てて棒高跳びのように跳躍。そのまま背後に回りこんで振り向きざまに斬撃を叩き込み、防御されても一切動作を止めることなく武器の衝突地点を軸として再び背後に潜り込む。
「なっ…このぉ!」
驚愕と焦りで、ギサルフの顔が歪んだ。突然始まった相手の猛反撃に、思考と体が追いつけない。剣を振るってもすでに相手の姿は無く、背後で必殺の一撃を繰り出す体勢にある。強引に体を回転させて間一髪防御をすれば、今までとは比較にならない相手の力に全身の関節が悲鳴を上げる。痛みが声に変わるよりも速く、相手は再び自分の背後。
これがガーディアンの、この世界において最強の存在たる者達の持つ、埋めようの無い絶対的な力の差なのだと、“ただの人間”が理解したその瞬間。
深緑の輝きが、大剣を握るギサルフの右腕を貫いて生えていた。
「――言ったはずだ。“人間”がいくら足掻こうと、我には勝てぬ」
引き戻された刃の緑に、紅い血の色が降り注ぐ。
激痛と、それ以上に悔しさのこみ上げた顔をしながら少年が倒れる。これだけは離すまいと剣を握る手が、傷口から湧き上がる血に染まった。うつぶせに倒れたまま何かを言おうとして、その口からも血が流れ出す。それらはアスファルトの黒に染み込み、彼の周囲を紅く切り取っていく。
遠のいていく意識の中で少年が、無慈悲な足音と振り上げられた刃が風を切る音を聞いた時。
(――目標座標特定。成功率91%、起動容認。“変移”起動)
「やめろっ、エモナ!」
ギサルフに守られるようにして呆然と事の成り行きを見ていた#2が、相対距離を無視して両刃の前に立ち塞がった。怒りの表情を露にした彼女の両腕には、投擲ナイフを模した赤い光が宿る。
「やっと思い出した。計画に反対したせいで強制命令コマンドを埋められたこと。我を失って人間に襲い掛かったら、反撃でウィルスらしきものを打ち込まれたこと。そのせいでコマンドが解除されたこと。やっと、アタシの意思を、思い出した」
対峙する相手を睨みつけたまま、一つずつ確認するように言葉を繋ぐ。
刹那、赤い姿が揺らめいた。
(“変移”起動準備。“閃影の舞”開始)
常軌を逸する速度でエモナに近接した#2が、逆手に構えたナイフを振るう。その一撃が当然のように緑の刃に受け止められ、それでも彼女は動きを止めない。武器を弾いて跳躍し、同時にもう片方のナイフを真横に投げる。投げられたナイフは目前のビルに突き刺さる直前に突如として姿を消し、速度を保ったままエモナの背中に突き刺さる位置に再び現れた。着地を終えた#2がそれと挟み撃ちにする形で再び疾走からの攻撃を繰り出し、
(“
長さを半分に減じることで二本に分裂した深緑のダブルセイバーに、阻まれた。
「無駄だ。貴様の強制座標置換能力“変移”では、我が守りを貫くことなどできぬ。しかも貴様――」
一回転して前後からの攻撃を弾き飛ばし、今度はエモナが反撃を開始する。相手の防御を嘲笑うような、巧みで一分の隙も無い無慈悲な連撃。この状況で無理に反撃を繰り出すことがどれだけ危険かを十分に知っている、そして先ほどの光景から改めて理解した#2はひたすらに耐え、逃げ回る。今だ血を流し続ける少年から少しでも相手を遠ざける目的と、そしてもう一つ。
「――手加減しているだろう。人間の味方を気取っておきながら、それでも我らと敵対するのを嫌っているのだろう?」
「……っ!」
図星を突かれ、怒りの一色に染められていた顔が歪んだ。
その一瞬の隙を逃すこと無く、深緑の刃が踊りかかる。二本を一本に統合して、下段から渾身の切り払い。交差させて防御の姿勢をとった赤いナイフが一瞬で砕け散り、なお失われない斬撃の勢いがその持ち主をビルの壁まで吹き飛ばす。衝突の衝撃は壁に大きな傷を生み、舞い上がった粉塵の白が夜闇を切り裂く。
ダメージを示す無数のエラーを#2が思考の隅に確認した時、冷酷な仮面はすでに眼前。
少女の顔が今度は恐怖に歪み、それを見下すエモナは攻撃せずに武器を消し、口を開いた。
「貴様は、自らの名の意味を忘れたわけではあるまい。“一段上の性能を持つ第二世代型”として暫定的に付けられていた名を、貴様は「一度名付けられた以上はその名に誇りを持ちたい」と言って変更しなかった。そして、この様だ。貴様の持つ“心”とやらは、迷いと躊躇い以外に何をもたらした。我らに仇なし、それでいて仲間でいようとするなど、不可能だと分かっていて何故やめようとしない」
淡々とした口調ながらも明らかに侮蔑と非難の意思が込められた、それでいて現実的な矛盾の指摘。これに明確な答えを返さないことには、ガーディアンとして、世界を守護する限りなく完璧な存在として君臨することなどできない。そのことを全て理解していて、しかし問いかけられた少女は。
「アタシは……アタシは………」
答えることが、できなかった。
とにかく何か言葉を発しようとして、そこから思考回路が原因不明のループに陥る。混乱などという生易しい言葉では表現しきれない、入り乱れた感情と理性の矛盾による思考の大爆発。無数のエラーが全身を駆け巡り、今更のように左肩の傷が認識されて疼きだす。四肢から伝わる感触が曖昧になり、視界は歪んで聴覚にも異常をきたす。絶望に埋め尽くされたその顔は、人間以上に人間らしい。
そのままうずくまってしまった#2を見て、マー・エモナは、確固たる意思を持つ者は、言った。
「やはり貴様は、出来損ないだ。迷って何をすることも叶わぬ者に、“#2”などという名を名乗る資格は無い。――消えろ」
掲げられた白い腕に、深緑の光が灯る。それはすぐダブルブレードの形へと凝固し、確かな質量を帯びる。両手を使って振りかぶり、少しの躊躇いも見せずに一閃。