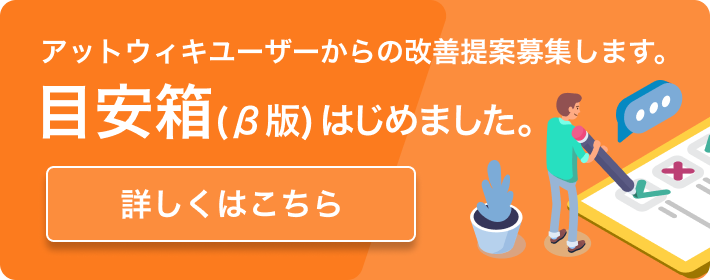・プロローグ・
とても深い、まどろみの中にいた。
視点がぼやけて、定まらない。
ただ、自分の前に誰かが立っているのだけは見えた。
「キミが七人目ですか…今、この場で消しておきましょうかね?」
目の前にいる誰かはそう言って、僕の前に膝をついた。
ああ…僕は殺されるのか。
どうせ意識も朦朧としているのだ、殺すなら今のうちに殺してくれ…
僕はそう思った。
「いや…まだ早いですね。もう少し…時間が必要になります」
誰かはそう言って、僕の頭に手を置いた。
「その代わりと言ってはなんですが…キミの大切なものを貰います」
大切なもの?
何だろう。
「いつかはキミに返さなければならないですが…これを貰っておかないと、こっちが困るんですよ…」
置かれた手が、不思議な光を放つ。
「さようなら、哀れな守り人よ」
そこで、僕の意識は途切れた。
気づくと、僕は一軒のアパートに居たんだ。
ポジビリティという自分の名前以外の…全ての記憶を失って。
・第1話・「五月蠅い散歩」
僕は散歩が嫌いだ。
昨日、静かな住宅街をぶらついていると、僕の隣をカップルが通り過ぎていった。
二人はとても幸せそうに会話をしていた。
きっと僕以外の人から見ても、そう見えただろう。
でもその時僕の耳には、彼らの幸せそうな会話とは違う会話が聞こえてきた。
『まったく、いつまでこんな男とくっついていなくちゃならないのかしら?』
『この女、ウザいんだよな。いくら建前上の恋人とはいえ、こんな女じゃなくてももっといい女が居ただろうに…
何でこんな奴捕まえちまったんだ、俺…』
『あー…本当こいつといると疲れるわ。さっさと別れたい』
『誰かいい女紹介してくれねぇかなー…』
僕はまたか、とため息をついた。
僕には、人の心を読めるという不思議な力が生まれつき備わっている。
とは言ってもその力は最近使えるようになったばかりだが。
おまけにその力は簡単にコントロール出来るものではないらしく、
おかげで僕の頭には絶えず色々な人間の感情や思惑が渦を巻いて押し寄せてくる。
その勢いに耐えきれず、道端でうずくまってしまう時も何度かあった。
だから僕は余程のことがなければ滅多に外へは出ない。
自分を痛めつける結果になるだけだ。
でもなぜか今日は自然と足が外へと向いた。
そして僕の足は勝手に歩みを進めていく。
どこへ行こうとしているのか、僕にもわからない。
誰かに呼ばれているかのように、僕の足は止まることを知らなかった。
しばらく歩いて、僕は街の大通りに出た。
ここは簡素な住宅街と違って、沢山の人が歩いている。
すると、僕の頭の中で沢山の声が騒ぎ立て始めた。
どれが誰のものか、わからない。
それは大声もあれば小声もある。
ピーチクパーチクと、まるで鳴くことしか知らない愚かな鳥のようだ。
それらの声はいつものように渦を巻いて、僕の頭をかき乱す。
例えるなら、何か硬い物で頭を叩かれ続けているような…そんな感じ。
(あー…、五月蠅い…)
僕は頭を抱えながら壁を伝うようにして歩き、路地裏に逃げ込んだ。
ここなら、少しぐらいはこの五月蠅い「声」をやり過ごせるだろう。
そう思ったからだった。
でも表通りの声は路地裏まで流れ込んで来て、僕の頭の中で大合唱を始める。
こうなってしまうと、もう駄目だ。
僕の頭は混乱して、身動きひとつとれなくなってしまう。
僕は情けなくその場にへたり込んだ。
この状態になると、家に帰ることすら困難になる。
歩くことが出来ないからだ。
(参ったな…路地裏で一夜を明かすなんて何年ぶりだろう)
その時の僕は完全に家に帰ることを諦めていた。
「彼」の「声」が聞こえる、その時までは。
・第2話・「望み叶える者」
「こんなところで何してるモナ?」
突然かけられた声に、僕はゆっくりと頭を上げた。
見ると、僕の目の前に一人の男が立っていて、僕を見下ろしていた。
「こんな誰も来ない寂れたところに座ってても、何も良いことないモナよ」
どこかのほほんとした、そんな口調で彼は言った。
確かに良いことなんかないけど…本当の理由を話しても、信じて貰えないだろうな。
「あ…はい、そうなんですけど…」
適当に相槌を打って誤魔化しながら、僕は改めて彼を見た。
その肌は抜けるように白く、どこまでも黒く染め上げられたスーツが逆に映えて見える。
黒いスーツの上に羽織るのは、古ぼけた薄手の長いコート。
のほほんとした口調に違わず、垂れ下がった穏やかな細い目。
丸く柔らかそうな顔は、彼の優しさを表しているようだった。
「…聞こえるモナか?」
不意に、彼が訊いてきた。
「え?」
「キミは人の心の声が『聞こえる』はずモナ。
じゃなきゃ、あんな路地裏でうずくまるなんてことはしないモナ。『聞こえる』者の特徴モナよ」
これは驚いた。
僕の力のことを知っている人がいたなんて。
僕は頷いて、尋ね返した。
「確かに僕は人の心の声が聞こえます。でも、貴方はどうしてそのことを知っているんですか? 貴方も僕と同じなんですか?」
「う~ん、同じだけど…微妙に違うモナね」
彼は笑顔を崩すことなく答えた。
「同じだけど…違う…?」
「そうモナ。キミは沢山の人達の心の声が聞こえるのが五月蠅くて、耐えきれなくなってここにいたんじゃないのかモナ?」
「…はい、そうです。もう本当に五月蠅くて…」
「その力…コントロール出来たら嬉しいモナ?」
「ええ、そりゃもう」
僕がため息混じりに答えると、彼はその笑みを深くした。
「なら、モナがその願い…叶えてあげてもいいモナよ」
「えっ?! ほ、本当ですか?!」
僕は驚いて彼を見た。
彼は大きく頷いて言う。
「モナは、嘘はつかない主義モナ。
キミのその力をコントロール出来るようにして、さらに強くしてあげられるモナよ」
「強くなるのはともかく、コントロールするのは出来るようになりたいです!!
お願いです、僕の力をコントロール出来るようにして下さい!!!」
僕は頭を下げた。
もうこの力のせいで悩むこともなくなる。
そう考えただけで僕の胸は踊った。
「良いモナよ。でもその代わり、条件があるモナ」
「条件? 何ですか?」
僕が訊くと、彼は怪しく微笑んだ。
「モナの組織『Sevence Sign』に入って欲しいモナ」
・第3話・「小さなオフィスと二人の男」
「組織…?」
僕は固まった。
組織と聞くと、あまり良い印象はない。
刑事ドラマの見過ぎだと言われるかもしれないが、
僕の中で「組織」という言葉の位置づけは、かなりヤバいところにある。
「別に変な組織じゃないモナよ。…まぁ、確かに普通の組織ではないけど」
「それを一般的には『変な組織』って言うんじゃないですか?」
「う~ん、そうモナね。じゃあ変な組織モナ」
「そんなあっさり言われてもなぁ…」
僕は頭を掻きながら尋ねた。
「…僕を組織に入れてどうするつもりなんですか?」
すると彼は辺りを見渡して、答えた。
「…ここじゃ言えないモナ。ちょっとモナについて来て欲しいモナけど…いいモナ?」
「いいですが…その前に、名前を教えてくれませんか? 僕はポジビリティっていいます」
「ポジビリティ君モナね。モナの名前はモナーっていうモナ。
こう見えても、一応組織の創設者でリーダーやってるモナ。さ、行くモナよ」
僕はモナーさんの後について歩き出した。
いつの間にか辺りはすっかり夜が更けていた。
モナーさんが僕を連れて来たのは、あるビルの一室だった。
「さ、入ってモナ」
僕は促されるままに中に入った。
中は、何の変哲もない小さなオフィス。
誰もいない…いや、二人居た。
「モナー、お帰り。そっちは? お客様かい?」
一人は丸く黒い瞳と黄色い肌を持つ、とぼけたように笑った口元の男。
楽しそうに笑う口元が彼の人柄の良さを伺わせる。
「お前が客を連れて来るなんて珍しいな」
もう一人は全身真っ青で、蒼く澄んだ目をした男だ。
どこか硬派な表情は生まれつきなのだろうか。
モナーさんは僕を二人の前へ連れて来ると、嬉しそうに言った。
「モララー、ギコ、ただいまモナ。『七つの刻印』の最後の一人を連れて来たモナよ」
(…『七つの刻印』?)
僕はモナーさんの言っていることが分からず、頭を捻った。
モナーさんの言葉に、二人の顔色が変わる。
「…へぇ、それはまた豪華なお客様だこと」
「で? そいつは何の能力持ってるんだ?」
「彼は『人の心が聞こえる』んだモナ。
でもまだ能力のコントロールが上手くいかなくて、困ってるみたいだから、何とかしてあげようとここに連れて来たモナ」
そう言うとモナーさんは二人のいるテーブルまで歩いて行った。
僕も慌ててその後に続く。
「ポジビリティ君、紹介するモナ。黄色い方がモララーで、青い方がギコっていうモナ」
「あ、どうも初めまして…ポジビリティっていいます…」
しどろもどろになりながらも僕が挨拶すると、二人は軽く会釈してくれた。
「さてと、コーヒーでも飲みながらマターリするモナ」
「あの~、モナーさん…」
とにかく今は詳細が知りたい。
「『七つの刻印』って何ですか? あと僕に詳しい説明を…」
「ああ、ごめんモナ。今から説明するモナ」
・第4話・「七つの刻印」
モナーさんは僕をソファーへ座るよう促し、自分も向かい側に座った。
僕の隣にはモララーさんが座り、モナーさんの隣にはギコさんが座る。
「さて、まずこの組織がどういったものか簡単に説明するモナ。
この組織『Sevence・Sign』は6人のメンバーだけで構成されている組織モナ。
そしてそのメンバーは全員…『神々の刻印』の守人の子孫なんだモナ」
「『神々の刻印』…?」
モナーさんは大きく頷いた。
「そうモナ。『神々の刻印』は神が生み出した特殊な刻印で、強大な力が秘められているんだモナ。
刻印は全部で七つあって、それぞれに力が封印されているモナ」
「でもよ、神って奴は臆病者でな。刻印の力が悪事に使われないようにと、七人の守人に刻印を託したんだと。
自分で管理すりゃいいのに…無責任な奴だよ、神も」
ギコさんがため息混じりに言うと、モララーさんが言った。
「ギコ、そんなこと言うとまた『あいつ』に封印かけられるぞ?」
「ちっ…わかってるよ。『あいつ』にだけは逆らえねーからな…」
「まぁまぁ、二人とも。話を戻すモナよ?」
モナーさんは笑顔で話を断ち切ると、再び話し始めた。
「『神々の刻印』は代々守人の手によって守られ、守人の家系にのみ伝えられていったモナ。その刻印は今も受け継がれているモナ」
「…え、ということはまさか…」
全てを悟った僕に、モナーさんは嬉しそうに言った。
「察しがいいモナね。そう、モナもモララーもギコも『神々の刻印』を守る守人の子孫。
そして…キミも『神々の刻印』を受け継ぐ守人の子孫なんだモナ」
「僕が…ですか?」
「そうモナ。キミは選ばれた人種モナよ」
僕は耳を疑った。
そんな話、今まで聞かされたことなどなかった。
僕は能力が発動する前までは、本当に普通のAAとして生きて来た。
…少なくとも、記憶を失う前までは。
それなのに…何で急に…しかも今更…。
「選ばれた人種、ねぇ…少し言い方が大袈裟なんじゃないの? モナー。
そんな言い方しちゃ、ポジビリティ…君だっけ? 彼も驚くだろうに」
「でも事実モナ。彼にもわかって貰わないといけないモナ」
「あの…一つ質問していいですか?」
僕は恐る恐る尋ねた。
「僕が『神々の刻印』を持つ守人の子孫という証拠は何かあるんですか?」
「あるモナよ」
モナーさんはあっさりと答えた。
「キミの左耳の付け根のあたり。その辺に変な紋様があるはずモナ。それが刻印。
嘘だと思うなら、そこに鏡があるから確認してみるといいモナ」
言われて、僕は鏡の前に立って自分の耳をよく見た。
…本当だ。
僕の左耳の付け根の辺りに、小さいが奇妙な紋様が刻まれていた。
人間の耳たぶのような模様に十字が引かれ、十字の真ん中に黒い丸がついている。
その周りを、大きな丸が囲んでいる…そんな紋様だ。
いつの間についたのだろう。
普段自分の耳なんてまじまじと見ないから、全然気が付かなかった。
「わかったモナか? キミは『神々の刻印』を受け継ぐ者として、組織に入らなければならないモナよ。
嫌とは言えない。キミはそのためにこの世に生まれたのだから」
モナーさんの言葉が、僕の心に深く突き刺さった。
・第5話・「残りの3人」
「キミ、ご両親はどうしているモナ? 兄弟とかはいるモナ?」
何も言えなくなってしまった僕に、モナーさんが訊いてきた。
「…わかりません。僕、記憶を失くしているんです」
僕がそう言うとモナーさんは少し眉をひそめたが、そのことについて問いつめることはしなかった。
「そうモナか。キミは何歳モナ?」
「正確にはわからないですが…多分21歳くらいです」
「仕事とかはしてるモナか?」
「いえ…記憶がないせいで、ことごとくクビになりましたよ」
僕が答えると、モナーさんはうんうんと頷いて言った。
「文句なしの合格点モナ。キミにご両親が居たり、キミが仕事やってたりしたら
色々と手配が必要だったモナけど…これなら何もしなくていいモナね」
「あの…ところで僕は組織に…」
バンッ!!
その時、オフィスのドアがやや乱暴に開けられた。
入って来たのは気性の荒そうな女性(…かな、多分)と、十字の髪止めをした金髪の女性、
そしてタバコをくわえた、物静かな男だった。
「あ、つーちゃんにレモナ、フーンもお帰りモナ」
「随分遅かったね。せっかくコーヒー淹れておいたのに冷めちゃったからな!」
「その様子じゃ、仕事に手間取ったか?」
モナーさん達が口々に言いながら三人を出迎える。
すると気性の荒そうな女性がピリピリした声で言う。
「オレノ仕事ヲ見ヤガッタ奴ガ居テヨ!! ムカツクカラミンチニシテ来タンダガ、
マダ怒リガ収マリャシナイゼ!! アヒャー!!!」
(ミ、ミンチ?!)
あまりの過激な表現の仕方に、僕は竦み上がった。
その言葉に嘘はないのだろう、彼女の両手は血で溢れている。
「困ったわよ、つーちゃんったら周りの人をみんな切り刻んじゃうんだもの。
後始末が大変だったわー。ま、今回はフーン君が居てくれたからそれなりに楽だったけど」
金髪の女性が髪を整えながら言う。
彼女の身体にも少しだが血の跡がこびりついていた。
「…おい、ところでそこに座ってる奴はなんだ? 客か?」
物静かそうな男がくわえ直したタバコに火をつけながら言った。
彼の身体には血の跡は見あたらない。
…いや、汚れひとつついていないと言った方が正しいだろう。
「ああ、彼はポジビリティ君。『神々の刻印』の最後の一人モナよ」
モナーさんが言うと、三人の顔色が変わった。
『神々の刻印』がこの組織に集まることは、やっぱり何か深い意味があるのだろうか。
「あ、そうだポジビリティ君…長いからポジ君って呼ぶモナね。
メンバーも全員揃ったことだし、改めて自己紹介させて貰うモナ」
「あの…僕の力をコントロール出来るようにはしてくれるんですよね…?」
「勿論モナ。そんなに焦らなくても大丈夫モナよ。後でちゃんとやってあげるモナ。だってキミはもうこの組織に入らざるを得ないから」
あっけに取られる僕に、モララーさんが首を振りながら言った。
「諦めた方がいいよ、ポジ君。モナーは最初からキミを組織に入れるつもりで連れて来た。
それに、『刻印』の力が覚醒した以上…もうキミは普通の生活は出来ない」
僕は何も言えなかった。
・第6話・「Member&Codename」
「さてと…まずはモナから。さっきも言ったけど名前はモナー。年は23。
この組織の創設者でリーダーやってるモナ。持ってる刻印は『変化』の刻印モナ」
「変化?」
首をかしげる僕に、ギコさんが説明してくれる。
「…刻印にはそれぞれ名前がある。能力にちなんでつけられたものだ。
モナーの場合は『変化』の刻印…すなわち奴はありとあらゆるものに変身出来るのさ」
するとモナーさんは笑顔で付け加えた。
「全部とはいかないモナよ。一度見たものになら何でもなれるけど」
「似たようなもんだろ…」
「でも違うモナ。あ、モナ達にはコードネームがあって、モナから順番に1,2…と数えていくモナ。
ちなみにモナは『1st Sign』モナ。さて、次はモララー。コーヒー飲むのは後にするモナよ」
モナーさんに言われて、モララーさんがコーヒーのカップを口から離した。
「僕はモララー。年は24。この組織では主にモナーの相方や代理をやってるよ。
何せナンバー2だからな! 持ってる刻印は『自然』の刻印。
これは自然界に存在するエレメント…要するに魔力の塊みたいなものを吸収し、操る力を持った刻印なんだ。
コードネームは『2nd Sign』。よろしく! さ、次はギコの番だからな!」
言われたギコさんはちょうどコーヒーを口に運ぼうとしていたところだった。
あまりに良すぎるタイミングに、ギコさんが少し顔をしかめたのが見えた。
「俺はギコ。年は24。一応組織ではナンバー3ってことになってるが…
モララーがナンバー2なら、俺の方がナンバー2に相応しいと思うのが正直なところだ。
コードネームは『3rd Sign』。持ってる刻印は『武器』の刻印だ。これは…言うより見た方が早いな」
そう言うとギコさんはさっき置いたコーヒーのカップを手に持った。
すると、彼の手の甲に不気味な紋様が浮かび上がり――――
次の瞬間、コーヒーカップは短剣に変わっていた。
「この刻印の力は、触れたものを武器に変える。
俺のイメージがそのまま具現化するから、ほぼ俺の思うがままに武器が精製出来るということだ」
「アヒャヒャ、相変ワラズ便利ナ能力ダナ! ジャア、次ハオレノ番ダ」
気性の荒そうな女性が血にまみれた手を拭きながら言った。
「オレノ名前ハ、つー。年ハ…多分23。コードネームハ『4th Sign』ダ。
オレノ持ッテル刻印ハ『切断』ノ刻印ッテ言ッテナ…オレノ意志デ自分ノ指ガ鉤爪ニナル。
コノ鉤爪ニ切レネェモンハネェ。アルナラオ目ニカカリタイモンダナ」
そう言ったつーさんの指が伸び、一瞬で鉤爪と化した。
思わず息を呑む僕に、金髪の女性が僕に囁いた。
「つーちゃんは性別不明種なの。そのことを気にしているから、あまり性別については触れないであげて。
じゃないとものすごく怒るのよ、つーちゃんは…」
僕は頷いた。
つーさんを怒らせたら、僕は一瞬でミンチにされてしまうだろう。
それだけは勘弁だった。
女性は僕が頷いたのを確認すると、にっこり笑って自己紹介を始めた。
「さて、次は私かしら? 私はレモナ。年は22、コードネームは『5th Sign』よ。
この組織には愛しのモナー君に誘われたから入ったのv 持ってる刻印は『鋼鉄』の刻印で、これは私の身体を鋼鉄に変える上、
少しだけなら自分の身体を武器に変えられるのよ。ま、モナー君やギコ君までとはいかないけどね」
「レモナ、もう一つ言い忘れてることがあるんじゃねーのか」
レモナさんの後ろから、物静かな男が言った。
「お前がネカマだってことをよ」
「え、え?! ネ…ネカマって…まさか…」
「レモナはネカマ。元は男なんだよ」
さらっと言ったモララーさんに、僕は思わず絶句した。
レモナさんが大声でがなりたてる。
「う、五月蠅いわね!! そんなことどうだっていいじゃないのよ!!
私はモナー君に愛されるなら女になったって構わないと思ったからなったんだもの!!」
「そうモナよ、フーンにモララー。今のレモナはとても綺麗モナ。それだけで十分だとモナは思うモナ」
モナーさんはレモナさんの髪を手で梳きながら、やんわりと言った。
その一言でレモナさんはすっかり機嫌が良くなったらしく、胸を張って言う。
「ほら、モナー君だってそう言ってくれてるでしょう?! フーン、次はあんたよ!!」
「ちっ…わかったよ、面倒臭ぇな…」
物静かな男がタバコを灰皿に置いた。
「俺はフーン。年は25だ。コードネームは『6th Sign』。
持つ刻印は『速度』の刻印だ。恐らく俺の力が一番ややこしいだろうから説明しておくが…
この力は動くもの全ての動く速度を自在にコントロール出来るものだ。
遅くしたり速くしたり…全て俺の思った通りの速度になる…俺がこの目で見たものはな」
そう言ってフーンさんは糸のように細い目を少しだけ開けた。
途端、僕は痺れたように身体が動かなくなった。
フーンさんの真っ暗な瞳の奥に、奇妙な目のような紋様が描かれていた。
それが刻印だということはすぐにわかったけれど、刻印の目に見つめられ、僕は身動き一つ取れなかった。
まるで、あの目に縛られているかのように。
「フーン、いい加減目を閉じろ。ポジがビビってるぞ」
ギコさんに言われ、フーンさんが目を閉じると、僕の金縛りは解けた。
「じゃあ、最後はポジ君に自己紹介して貰うモナ」
モナーさんに言われ、僕は慌ててソファーから立ち上がった。
「は、はい! ええと…名前はポジビリティです。
年は多分21で、今日モナーさんに連れられてここに来ました。
刻印の名前は…まだわからないですけど、人の心の声が聞こえるっていう力があるみたいです。どうぞよろしく…」
最後の方は自分でも驚くほど小さな声だった。
他のメンバーの人に比べて、僕の力が酷くちっぽけに感じたからだ。
「ふーん、お前だけ戦闘型じゃないんだな」
「人の心が読めるってことは…私の心は読めるかしら?」
「いえ…今は特に…あれっ?」
レモナさんに言われて、僕は初めて気が付いた。
モナーさんに会った時から、僕の力が勝手に発動していないことに。
「ふふ、キミの力はまだ弱くて不安定モナ。だからちょっとモナの力でキミの力を制御させて貰ってたモナ」
「え…でも、モナーさんの力は変身することじゃあ…?」
「あいつは特別なんだよ」
ギコさんが言う。
「モナーの一族は全ての守人を束ねる存在として、神に任命されたんだと。その時に、刻印とは別の力を与えられたらしい」
「何だよモナーばっかり…神もセコいんだからな!」
「まぁまぁ、お喋りはその辺にして…ポジ君」
「は、はい」
モナーさんが僕を手招きした。
僕が言われるままに彼に近寄ると、彼の白い手が僕の刻印に触れた。
僕は驚いて後ずさりしようとしたが、彼に止められた。
「キミの願いを叶えてあげるモナ。いいからそのままおとなしくしてるモナよ。すぐに終わるし、痛いとか痒いとかもないモナ」
「痛イトカ痒イッテ、医者ジャネェンダカラヨ…」
つーさんのさりげないツッコミも、モナーさんは得意の笑顔でかわした。
・第7話・「力・覚醒」
モナーさんの指が、僕の刻印の上を滑るように動いている。
「ちょっと失礼するモナ…ここモナね」
指が止まったところで、モナーさんは刻印を覆うように手を広げた。
僕の視点からではよく見えないが、彼の手から光が漏れているのを感じた。
僕の刻印が発する光が漏れたものなのか、彼が発しているのかはわからないが、不思議な温かみが伝わってくる。
「…はい、これで完了モナ」
そう言ってモナーさんは手を離した。
「え、これで終わりですか?」
「そうモナ。もうキミは自分の力を自由に操れるモナ」
「操るって、どういう風に…?」
「簡単モナ。心の中を見たい人を思い浮かべるだけでいいモナ。練習も兼ねて、早速やってみるといいモナ」
僕は静かに息を吸い、精神を研ぎ澄ました。
試しに、目の前にいるモララーさんを思い浮かべてみる。
「…あ、聞こえる…」
モララーさんの考えていること全てが、一気に頭の中に流れ込んで来る。
でもそれは今までのような五月蠅いものではなくて。
とても自然に、僕の中にひとつの「情報」として流れてきた。
「誰の心を読んだモナ?」
「…モララーさんです」
「え?! 僕の心読んだの?!」
「丁度いい、奴が何を考えてるのか教えろ、ポジ!」
ギコさんが僕に迫って来る。
「あ、ええと…『早くコーヒー飲みたい』って…」
勢いに押されて僕が答えると、ギコさんはつまらなさそうに言った。
「何だ、そんな下らねぇこと考えてたのかよ」
「な、何だよ! 僕が無類のコーヒー好きだって知ってるくせに!」
「…どうやら、異常はないみたいモナね」
モナーさんが笑顔で頷きながら言う。
「…あ、はい」
「今日から君は晴れてこの組織の一員…君のコードネームは『7th Sign』モナ。ここが今日から君の家、君の帰る場所モナよ」
「あの…荷物とかは…」
「それなら心配ないモナ。住所さえ教えてくれれば、モナが運んでおいてあげるモナ。…あ、そうだ。肝心なことを話していなかったモナね」
モナーさんはもう一度ソファに座り、他のメンバーにも座るよう促した。
「この組織は、ある目的のために活動をしているモナ」
「ある活動…ですか?」
「まぁ、僕らも一応それなりに仕事はしてるんだよ」
モララーさんが全員分のコーヒーを淹れ直しながら言った。
彼がコーヒーのカップを全員に配り終えたのを確認して、モナーさんが続きを話す。
「さっき、『刻印』は全部で七つあるって話をしたモナよね?」
「はい」
「でも、本当は八つあるモナ」
「え? 七つじゃないんですか?」
思わず首をかしげた僕に、ギコさんが言った。
「その『八つ目の刻印』を見つけ出すのが俺達の仕事だ」
・第8話・「追う者と追われる者」
ある高層ビルの屋上。
そこに、一人の少女が街を見下ろすように立っていた。
傍らには巨大な犬が座っている。
「…ねぇ、ぞぬ」
少女は犬に呼びかけた。
ぞぬ、と呼ばれた巨大な犬はその大きな顔を少女に向ける。
「私を追い回して、一体どうするつもりなのかしらね」
少女の顔には疲労の色が見えた。
「…疲れたけど…でも私は勝たなくちゃいけない。自由を手に入れるために」
少女はそう言ってぞぬの頭に飛び乗った。
同時に背後から聞こえてくる、沢山の人間の走る靴音。
「また来た。…ぞぬ、逃げるよ」
その声を合図に、ぞぬは地面を蹴る。
普通ならそのまま落ちてしまうところだが――――
「居たか?!」
「いや、居ない! 下の奴らからも連絡なしだ!!」
「クソ、また逃げられたか!!」
数分遅れて現れた黒服の男達は、悔しそうに唇を噛んだ。
「ウフフ…ねぇ、ぞぬ…見て。私達を捜してるのよ」
少女が楽しそうに微笑む先には、沢山の黒服の姿。
彼女は耳で羽ばたき宙を舞うぞぬの上から、さっきまで自分が居たビルを見下ろしていた。
「私は絶対逃げ切ってみせるわ。この力は誰にも渡さない」
その目に宿るは、決意の光。
「…行こう、ぞぬ。長居は無用よ」
少女の命令で、ぞぬは大きな羽ばたきと共に闇に消えた。
「…女の子…ですか?」
「そうモナ。八つ目の刻印を持っているのは、『しぃ』という名前の女の子モナ。
彼女は愛犬のぞぬと行動を共にし、街から街を逃げ回っているモナ。
モナ達の目的は刻印を持つ彼女を『保護』して、彼女の刻印を狙う連中から彼女を守ることなんだモナ」
モナーさんの話では、その「しぃ」という女の子が八つ目の刻印を持っていて、
彼女は刻印の力を狙う連中に追われる日々を送っているという。
「…でも、そこまで彼女の素性が割れているなら、どうして彼女をなかなか保護出来ないんですか?」
僕が訊くと、モナーさんは困ったような顔で言った。
「彼女は幼い頃から刻印の力を持っているということだけで、様々な人間に狙われ、逃げ延びながら生きてきたモナ。
…そのせいか…彼女は人を信じることが出来なくなってしまったんだモナ。
だから、モナ達が手を差し伸べても…その手を取ろうとしない」
「おまけに、最近彼女は刻印の力を使って姿を眩ましながら行動するようになって…。
それでも何とか情報を集めて彼女を見つけ出すんだけど…まるで話を聞いてくれないの」
レモナさんも言う。
「僕らの仕事は簡単なように見えて簡単じゃないんだ。だからこそ、この組織をモナーが立ち上げたわけだしね」
「そうなんですか…」
「アイツ、最近特ニ逃ゲルノガ上手クナッテナ。オレデモ捕マエランネェンダゼ」
「お前はすばしっこいのをウリにしてるからな。ムカつくのはわかるが、今度会ったら間違っても、殺すなんてことはするなよ?」
イライラした様子のつーさんを、ギコさんが宥める。
つーさんはワカッテルヨ、とだけ答えて乱暴にカップを口に運んだ。
「…それより、モナー。そのガキについてのことだが…」
今まで話を黙って聞いていただけのフーンさんが、口を挟んだ。
「タカラのところの組織がさっき、奴とニアミスをしたらしいという情報が入った。
情報が正しければ、まだこの辺りにいるかもしれないが…どうする?」
カップがテーブルに置かれ、モナーさんが振り返る。
「…この街は、彼女にとって好都合モナ。これだけ大きな街だと、身を隠せる場所が多いからモナね。
だから、すぐに街を離れる可能性は低いモナ。明日にでもまた捜索に行って貰うことになると思うモナけど…あ、そうだ」
モナーさんは僕に向き直ると、笑顔で言った。
「明日の仕事、ポジ君にも参加して貰うモナ♪」
「えぇぇぇぇ?!」
突然の提案に、僕は頭の中が真っ白になった。
・第9話・「叫び」
…翌日。
僕はギコさんやモララーさんと一緒に、街の真ん中にある巨大なビルの屋上に来ていた。
モナーさんに言われた「仕事」をするためだ。
昨日この話を持ちかけられた僕は、突然のことに頭が混乱した。
『え、え、え、でっ、ででででもぼっ、僕なんかっ、ぜんqあwせdfrtふじこlp』
『大丈夫モナよ。簡単な仕事だし、何かあってもモララーやギコが守ってくれるモナ。でも、一応…護身用の銃ぐらいは渡しておくモナね』
『安心しなよ、ポジ君。ギコはともかく、組織ナンバー2の僕がいる限り、
君が生命の危機に晒されることはないんだからな!!』
『…ともかく、は余計だ。いいか、ポジ。お前はもうこの組織のメンバーの一員。
今回は初任務だから仕方ないが、人に守られるばかりでなく、自分の身は自分で守れるように努力はしろよ。
俺達もお前を完全に守りきれる保証はないぞゴルァ』
『は、はい…がんがります…』
それが昨日の話。
僕の記念すべき(?)初任務は、昨日教えて貰った「八つ目の刻印」を持つ女の子、
「しぃ」ちゃんを捜し出し、接触を図ること。
そして出来るなら、彼女を組織に連れて帰ること。
…まぁ、昨日のレモナさんの話からすると、後者は相当難しそうだけど。
そこでまず、彼女が昨日現れたというビルで手がかりを掴もうというわけだ。
勿論、僕の能力を使って。
「モナーが言うには、お前の能力は相手の『気』を強く感じる場所ほど効果があるらしい。
当然相手が目の前に居れば効果は抜群だが、今回の場合はそうはいかない。
そういう時は、相手の『気』が強い場所で能力を使えばそれなりに効果はあるそうだ。例えば、その相手が一度訪れた場所とかな」
「…で、ここに来たんですね」
「その通り♪ せっかく便利な能力持ってるんだから、有効活用するっきゃないからな! と、いうことで宜しくポジ君」
「はい…とりあえずやれるだけやってみます…」
僕は目を閉じた。
昨日みたいに深呼吸して、彼女の顔を思い浮かべる。
(会ったことないからあくまで想像だけど…)
辛い。
辛い辛い辛い辛い。
どうして?
どうして私だけが…
滝のように、勢いよく。
聞こえてくる、彼女の声。
これは彼女の本音なのだろう。
憎い。
憎い憎い憎い憎い。
私を追う奴らが憎い。
こんな刻印生み出した神が憎い。
叫ぶような、喘ぐような悲痛な響きに、聞いている僕も正直辛くなってきた。
でも、聞かないと。
これは仕事なんだ、任務なんだ。
僕は必死に精神を集中させた。
だから私は
復讐するの。
復讐…?
誰に?
この刻印を作った神様?
それとも、彼女を追う連中?
これは私にしか出来ないの。
自由を手に入れ、あいつに復讐する。
今日はあいつは現れるかしら。
13日の金曜日、誰もいないあの孤独な海に。
絶対に仕留めてみせるわ。
私の力は、そのためにあるのだから。
…この力は…誰にも渡さない。
「っ!!!」
…コノチカラハ、ダレニモワタサナイ。
そう言った彼女の声があまりにも恐ろしい声だったので、僕は思わず目を開けた。
息が荒く、脂汗をかいているのが自分でもわかる。
頭が痛い。
目の前がぐらぐらして…
「おい、ポジ! 大丈夫か?!」
思わず崩れかけた僕の身体をギコさんが支えてくれた。
「…あ、ギコさん…すみません…」
「能力を行使しすぎたか? 体力の消耗が激しい」
「ポジ君は真面目だからねー。仕事熱心なのは偉いけど、無理はしない方がいいよ。
能力の扱いに慣れるまでは、刻印の力に身体がついていかないから。少しそこに座って休んでれば? 気休めにはなると思うよ」
「はい…わかりました」
僕は床に座って、少し休むことにした。
「で、何か手がかりになりそうなことは聞こえた?」
モララーさんの言葉に僕は頷き、さっき聞こえたことを話した。
しぃちゃんの本音の叫び。
復讐を考えている相手がいること。
彼女はそのために刻印の力を使っていること。
そして、その相手が13日の金曜日、『海』に現れることを願っていること。
「海…か。ギコ、この街の港ってどこだっけ?」
「港って、ラウンジ港のことか? そこならここからはそう遠くないぞゴルァ」
「よし、まずはポジ君の回復を待って、ラウンジ港に向かおうか。
彼の聞いた声によると、彼女はそこに現れるかもしれないそうだからね」
「わかった。モナーに連絡する」
そう言うとギコさんは携帯を取り出し、組織と連絡を取り始めた。
モララーさんは僕の隣に座り、目の前の景色を眺めている。
「あの…すみませんモララーさん…僕のせいで、仕事を進めるのが遅れてしまって…」
「ん? 別にいいよ。僕はどちらかといえば、のんびり仕事をするのが好きなタイプだし。あいつはどうだか知らないけど」
彼の指が、ギコさんを指し示す。
「大丈夫。僕もギコもキミが刻印の力に慣れてないってことはわかってるから、
そんなに僕らに気を遣わなくていいからな。気楽に行こう、気楽に」
「あ、ありがとうございます…」
僕は無意識に深々と頭を下げていた。
やがて連絡が終わったらしいギコさんが、モララーさんと少し距離をとって座った。
「出来れば日が沈む前に帰って来いってさ。レモナの特製ディナーが冷めるからだと」
「そっか。レモナの料理の味は格別だからな。よし、夕方までには終わらせようか。ポジ君、身体の方はもう大丈夫?」
「あ、はい。あれも多分一時的なものだと思いますし」
「よし、じゃあぼちぼち行くとしますか。でも本当に無理だったら言った方がいいよ。人間、やせ我慢が一番良くないんだからな」
「お前もだろ、モララー」
僕はゆっくりと立ち上がり、傾きかかった太陽を見つめた。
あの陽が落ちる前に、仕事を終わらせる。
そう心に決め、僕達はビルを後にした。
第10話:「宿敵」
「…やれやれ、モナーさんのところにも厄介な人が来たものですね」
ある組織の本部ビル最上階。
幹部だけが入ることを許されたこの部屋で、タカラは大きなため息をついた。
「しかも今回は彼とモララーさん、おまけにギコ先輩までついていると来た。
これじゃあ迂闊に手は出せないですかねぇ…困りましたねぇ…」
口はそう言ってはいたが、タカラの表情は相変わらず笑ったままであった。
そこへ、彼の横に立っている女性が口を挟む。
「…本当ハ、困ッテナイデショウ? タカラサン」
「あ、バレました?」
悪戯がバレた子供のように、タカラは舌を出して笑った。
そんな彼に対して女性は何も言わず、表情も硬いままだ。
「わかりました、わかりましたから…無言でこっちを睨むのはやめて下さいよ、でぃさん。で、どうしましょうか? 誰かいますかねぇ?」
「今デシタラ、ウララーサンガ暇デスネ。アトハ山崎サンモ…ソレグライデスケド」
「そうですか。じゃあ僕からおながいしておきます」
タカラはそう言って、窓から外へと視線を移した。
「そう簡単にはいかせませんよ…先輩」
ラウンジ港。
様々な国や街の人々が集うこの港では、人の足が絶えることはない。
ただ…13日の金曜日を除いては。
「どうして13日の金曜日は誰も人がいなくなるんですか?」
「昔から、縁起が悪い日だって言われててな。その日にこの港に来ると、船が沈んだり溺れて氏んだりするんだと。
特にここら一体に住んでる住民には、その迷信を信じている連中が多い。
そしてそのことを港にやって来る他の街や国の連中に言いふらしちまってよ。
迷信は全世界を駆け巡り、世界中でその迷信を知らない者は居なくなった。だから、13日の金曜日は港に誰も来ないんだ」
今日は、13日の金曜日。
ギコさんの言った通り、ラウンジ港には誰も居ない。
様々な大きさの船が、波に静かに揺れているだけだ。
「この日だけは、港から人が消える。それを狙って、しぃは復讐したい相手がここに来ることを望んだんだろうな。
もし、しぃがその『相手』を頃そうと企んでいるのだとしたら…こんなに好都合な環境はない」
「そうだね。人っ子一人いない港…目撃者の数も減らせる上、これだけ土地の面積が広いと何かあっても対応はしやすいし。
彼女にとっても、僕らにとっても好都合だからな」
僕らにとっても…?
もしかして…
少し気になった僕は、恐る恐る尋ねた。
「それって…相手と戦うことになったとしても…ってことですか?」
「その通りだよ、ポジ君。…伏せてっ!」
モララーさんが僕の頭を地面に押さえつけた瞬間。
ドゴォッ!!
何かが爆発するような大きな音がすぐ上から聞こえて、僕は思わず目を閉じた。
その後も、何度か小さな爆発音がして。
びくびくしながら目を開けると、モララーさんが僕を庇うように立って上を見上げていた。
「ポジ君、大丈夫? 怪我は?」
「あ、大丈夫です…」
「そっか。ま、僕のシールドは宇宙一だからな」
ふと見ると、彼の周りを強い風の流れが守るように覆っていた。
勿論、僕も含めてだが。
「え…あの、これって」
「前に言っただろ? 僕は自然界のエレメントを操る力を持っているってさ。
これは『風』のエレメントを集めて作った防御壁ってワケ」
そう言って笑ったモララーさんの胸元に、刻印が浮かび上がっているのが見えた。
雫の形をした模様の周りからオーラが出ているような模様が描かれた刻印だ。
「無駄話はそれくらいにしとけ、モララー」
「わかってるよ。で? さっきの攻撃はしぃちゃんの仕業?」
「いや…別の香具師だ。気配が明らかに違う。これは恐らく…」
「へぇ、勘がいいな。流石はこっちの頭領が『先輩』と呼んで尊敬するだけはある」
「…どうです? 今の花火は気に入って頂けましたかな?」
屋根の上から現れたのは、二人組の男だった。
一人はモララーさんによく似た外見の、紫色の肌を持つ男。
耳元に一周ぐるりと赤い線が引かれている。
もう一人は黄緑色の肌を持ち、何となくモナーさんに似てはいるが…彼には鼻と口がない。
唯一ある二つの目が、薄気味悪く笑っていた。
「…久しぶりだな、ウララー…と山崎だったっけ」
「オマエモナー。…っと、これはお前んとこの頭領の代名詞だったか」
「お前らが出てくるとは、タカラの奴は相当焦ってるのか?」
「フフ、答える筋合いはありませんね。もし知りたいのでしたら…」
山崎はない筈の口でそう言うと、どこからともなく大きな鎌を取り出す。
ウララーもニヤリと口元だけで笑い、背中から真っ黒な翼を生やして飛び立った。
彼の手に握られているのは、漆黒の槍。
「我々を倒すことです」
港に、緊張が走る。
僕は不安と緊張で押しつぶされそうになりながら、震える足で何とか立っていた。
日は既に傾き始め、まもなく夜が顔を見せようとしている。
「…あ~あ、仕方ないな。レモナの出来たて熱々ディナーはお預けかぁ」
「まだそうと決まったわけじゃねぇぞゴルァ。さっさと終わらせればいいだけの話だ」
「ま、そうなんだけど。でも正直面倒臭いんだよな~…」
とぼけた調子で言うモララーさんの手のひらに、吸い寄せられるように水が集まる。
足下に落ちていた石をギコさんが拾い上げると、手の甲の刻印が輝き…
その石はたちまち中くらいの大きさの剣に変わった。
「あ、そうだポジ君。銃の撃ち方わかる?」
「え…はい、わかります。昨日、モナーさんに一通り教わったので…」
「うん、それなら心配ないね。キミはまだ戦闘には不慣れだから…僕らの手助けしろとは言わないけど、
いざという時はそれで自分の身を守るんだ。いい?」
「は、はい!!」
僕は慌てて頷く。
するとギコさんが僕を手招きして呼んだ。
「いいか、ポジ。お前の能力は確かに戦闘向きじゃない。だが…使い方によっては
相手にとって戦闘でも脅威となる能力だ。そのことを考えて行動してみろ」
「…はい、わかりました。やってみます」
「作戦会議は終わりましたか?」
山崎が鎌を構えて尋ねる。
「ああ。悪いが、熱々のディナーが待ってるんだ。手っ取り早く終わらせて貰う」
「そうはいかないな。これからお前達がオレ等のディナーになるんだから」
「そういうことは、僕らを倒してから言うんだな。ウララー」
「ではお喋りはその辺で…参りますよ!!」
山崎の言葉で、向こうが屋根の上から飛び降りて来るのが見えた。
僕は手の汗で銃を落としそうになりながらも、必死に銃のグリップを握りしめていた。
第11話:「油断大敵」
ウララーがモララーさんに、山崎はギコさんに向かっていく。
僕は二人の戦いを見守る一方、いつ自分が襲われても対応出来るように、常に視線を四方八方へと巡らせていた。
「ほらほら、どうした?! 避けてばっかりじゃ、俺は倒せないぜ!!」
「…全く、僕が肉弾戦派じゃないってことぐらいわかってるくせに…これだから厨房は」
ウララーの繰り出す槍をかわしながら、ため息をつきつつモララーさんが言う。
「わかってるからこそ、そこを狙うんだよ! 相手に勝つためには当然の戦略だろ?!」
「まぁ、確かにお前の理論はわからなくもないよ。いや…むしろ、模範的な理論だね」
「珍しいな、お前が俺を褒めることなんて今までなかったじゃないか」
「あれ? そうだったっけ? …でも、ウララー…」
モララーさんの手に集まっていた水の塊が、段々と大きくなっていく。
「…模範的だからこそ…その理論には限界があるんだからな」
彼の口元が吊り上がる。
水の塊はうねりながら天高く昇り、今や竜巻のようになっていた。
「…来い」
ゴパァッ!!!
モララーさんが命じると同時に、水流の竜巻が姿を変え…巨大な水竜になった。
水竜はモララーさんの手から生えているように伸び上がり、ウララーに牙を剥いている。
「へぇ、なかなか面白いもん見せてくれるじゃん…」
「さっき、素敵な花火を見せて貰ったからな。これはそのお返しだよ」
「なら…出された礼は100倍にして返さないとな!!」
ウララーは天高く舞い、槍の先端を水竜に向けた。
一方、ギコさんは石から生み出した剣を振るい、山崎と戦っていた。
山崎の大きな鎌と、ギコさんの中型の剣が何度もぶつかり火花を散らす。
「ほほう、なかなかの腕の持ち主ですね。流石は我がリーダーが尊敬する人物」
「あいつに尊敬されるのは悪くはないが…俺達の邪魔をするのは頂けねぇなゴルァ」
「それは仕方のないことでしょう。貴方達の目的が有り続ける限り、
私達が貴方達の敵となるのは必然なのですから。それがリーダーのお考えです」
「そうか…あいつとは出来るなら仲良くやっていきたいと思っていたが…
タカラがそういうつもりならどうしようもないな。
なら、俺も手加減するのはやめにしよう。…ここからは本気で行く」
そう言ったギコさんの目の色が深みを増した。
綺麗な蒼が、どす黒い蒼へと変わっていく。
ボッ!!!
途端、ギコさんの周りの空気が変わった。
彼を中心に空気が渦を巻き、吹き上げるように昇っていく。
手に握られた剣は、いつのまにか禍々しいほどの黒いオーラを纏っていた。
「さて…続けるかゴルァ」
「…本領発揮といったところですか…望むところですよ」
そんなギコさんにも山崎は表情一つ変えず、鎌を振り上げた。
…正直、目が追いつかない。
どっちに気を配ったらいいのか、わからない。
大きな水の竜を従え、ウララーと対峙するモララーさん。
全身から禍々しいオーラを放ち、山崎の攻撃を受けるギコさん。
…どっちを見ていればいいんだろう。
僕はなるべく四人から遠ざかって、それぞれの戦いがよく見えるようにした。
「はぁぁぁぁっ!!」
漆黒の槍を携え、ウララーがモララーさんに突っ込んでいく。
その進撃を阻むのは、水竜。
口からいくつもの水の弾を吐き出し、彼の動きを止める。
「…チッ、やっぱりそう来るかよ!」
「単純に攻撃しても無駄なんだからな。それぐらいお前もわかってるだろ?」
「なら、その竜から海の藻屑にしてやるぜ!!」
ウララーの槍の先端が、奇妙に変形していく。
やがて、槍の刃は怪物の頭を模した形になった。
「行け!」
ウララーが叫ぶと、怪物の口から木の枝のようなものが一斉に生えてきた。
枝は水竜に巻き付き、水竜の全身を覆う水を吸い上げ始める。
思わぬ反撃に、水竜が悲鳴を上げた。
「竜っつったって、所詮は水で出来た作りものだろ?
だったら、竜を作り上げている水そのものを消してしまえばいい」
「へぇ、考えたなお前も」
「いつまでもお前に『考えなさ杉』って言われるのは癪なんでね」
得意げな笑みを浮かべるウララーに、モララーさんは頭を掻いた。
「全く…その勇ましさだけはお前のいいところなんだけどな」
ギコさんの方はというと、目にも止まらぬスピードで山崎に走り寄り、剣を振るっていた。
そしてそれを鎌で受け止めながら、時折流れるような反撃を見せる山崎。
二人の実力は、まさに互角だった。
「フフ、刻印の力も大したことないのですね…私すら倒せないようでは、
リーダーに会ったら、すぐにあぼーんされてしまいますよ?」
「タカラか…確かに奴はかなりの実力を持っている。モナーに引けを取らないほどのな。
だが…奴を育てたのは俺だ。お前ごとき、すぐに蹴散らしてやるぜゴルァ」
「言いますね…ならば、その実力とくと見せて頂こうではありませんか!」
山崎が鎌を振り上げ、一気に振り下ろした。
狙いは、ギコさんの首。
だが、それよりも素早い動きでギコさんは鎌の一撃をかわすと、次の瞬間には山崎の背後にぴたりとついていた。
「…な…!!」
「手抜きするのは、意外に疲れるもんだな…まぁいい、これで仕舞いだ!
とても深い、まどろみの中にいた。
視点がぼやけて、定まらない。
ただ、自分の前に誰かが立っているのだけは見えた。
「キミが七人目ですか…今、この場で消しておきましょうかね?」
目の前にいる誰かはそう言って、僕の前に膝をついた。
ああ…僕は殺されるのか。
どうせ意識も朦朧としているのだ、殺すなら今のうちに殺してくれ…
僕はそう思った。
「いや…まだ早いですね。もう少し…時間が必要になります」
誰かはそう言って、僕の頭に手を置いた。
「その代わりと言ってはなんですが…キミの大切なものを貰います」
大切なもの?
何だろう。
「いつかはキミに返さなければならないですが…これを貰っておかないと、こっちが困るんですよ…」
置かれた手が、不思議な光を放つ。
「さようなら、哀れな守り人よ」
そこで、僕の意識は途切れた。
気づくと、僕は一軒のアパートに居たんだ。
ポジビリティという自分の名前以外の…全ての記憶を失って。
・第1話・「五月蠅い散歩」
僕は散歩が嫌いだ。
昨日、静かな住宅街をぶらついていると、僕の隣をカップルが通り過ぎていった。
二人はとても幸せそうに会話をしていた。
きっと僕以外の人から見ても、そう見えただろう。
でもその時僕の耳には、彼らの幸せそうな会話とは違う会話が聞こえてきた。
『まったく、いつまでこんな男とくっついていなくちゃならないのかしら?』
『この女、ウザいんだよな。いくら建前上の恋人とはいえ、こんな女じゃなくてももっといい女が居ただろうに…
何でこんな奴捕まえちまったんだ、俺…』
『あー…本当こいつといると疲れるわ。さっさと別れたい』
『誰かいい女紹介してくれねぇかなー…』
僕はまたか、とため息をついた。
僕には、人の心を読めるという不思議な力が生まれつき備わっている。
とは言ってもその力は最近使えるようになったばかりだが。
おまけにその力は簡単にコントロール出来るものではないらしく、
おかげで僕の頭には絶えず色々な人間の感情や思惑が渦を巻いて押し寄せてくる。
その勢いに耐えきれず、道端でうずくまってしまう時も何度かあった。
だから僕は余程のことがなければ滅多に外へは出ない。
自分を痛めつける結果になるだけだ。
でもなぜか今日は自然と足が外へと向いた。
そして僕の足は勝手に歩みを進めていく。
どこへ行こうとしているのか、僕にもわからない。
誰かに呼ばれているかのように、僕の足は止まることを知らなかった。
しばらく歩いて、僕は街の大通りに出た。
ここは簡素な住宅街と違って、沢山の人が歩いている。
すると、僕の頭の中で沢山の声が騒ぎ立て始めた。
どれが誰のものか、わからない。
それは大声もあれば小声もある。
ピーチクパーチクと、まるで鳴くことしか知らない愚かな鳥のようだ。
それらの声はいつものように渦を巻いて、僕の頭をかき乱す。
例えるなら、何か硬い物で頭を叩かれ続けているような…そんな感じ。
(あー…、五月蠅い…)
僕は頭を抱えながら壁を伝うようにして歩き、路地裏に逃げ込んだ。
ここなら、少しぐらいはこの五月蠅い「声」をやり過ごせるだろう。
そう思ったからだった。
でも表通りの声は路地裏まで流れ込んで来て、僕の頭の中で大合唱を始める。
こうなってしまうと、もう駄目だ。
僕の頭は混乱して、身動きひとつとれなくなってしまう。
僕は情けなくその場にへたり込んだ。
この状態になると、家に帰ることすら困難になる。
歩くことが出来ないからだ。
(参ったな…路地裏で一夜を明かすなんて何年ぶりだろう)
その時の僕は完全に家に帰ることを諦めていた。
「彼」の「声」が聞こえる、その時までは。
・第2話・「望み叶える者」
「こんなところで何してるモナ?」
突然かけられた声に、僕はゆっくりと頭を上げた。
見ると、僕の目の前に一人の男が立っていて、僕を見下ろしていた。
「こんな誰も来ない寂れたところに座ってても、何も良いことないモナよ」
どこかのほほんとした、そんな口調で彼は言った。
確かに良いことなんかないけど…本当の理由を話しても、信じて貰えないだろうな。
「あ…はい、そうなんですけど…」
適当に相槌を打って誤魔化しながら、僕は改めて彼を見た。
その肌は抜けるように白く、どこまでも黒く染め上げられたスーツが逆に映えて見える。
黒いスーツの上に羽織るのは、古ぼけた薄手の長いコート。
のほほんとした口調に違わず、垂れ下がった穏やかな細い目。
丸く柔らかそうな顔は、彼の優しさを表しているようだった。
「…聞こえるモナか?」
不意に、彼が訊いてきた。
「え?」
「キミは人の心の声が『聞こえる』はずモナ。
じゃなきゃ、あんな路地裏でうずくまるなんてことはしないモナ。『聞こえる』者の特徴モナよ」
これは驚いた。
僕の力のことを知っている人がいたなんて。
僕は頷いて、尋ね返した。
「確かに僕は人の心の声が聞こえます。でも、貴方はどうしてそのことを知っているんですか? 貴方も僕と同じなんですか?」
「う~ん、同じだけど…微妙に違うモナね」
彼は笑顔を崩すことなく答えた。
「同じだけど…違う…?」
「そうモナ。キミは沢山の人達の心の声が聞こえるのが五月蠅くて、耐えきれなくなってここにいたんじゃないのかモナ?」
「…はい、そうです。もう本当に五月蠅くて…」
「その力…コントロール出来たら嬉しいモナ?」
「ええ、そりゃもう」
僕がため息混じりに答えると、彼はその笑みを深くした。
「なら、モナがその願い…叶えてあげてもいいモナよ」
「えっ?! ほ、本当ですか?!」
僕は驚いて彼を見た。
彼は大きく頷いて言う。
「モナは、嘘はつかない主義モナ。
キミのその力をコントロール出来るようにして、さらに強くしてあげられるモナよ」
「強くなるのはともかく、コントロールするのは出来るようになりたいです!!
お願いです、僕の力をコントロール出来るようにして下さい!!!」
僕は頭を下げた。
もうこの力のせいで悩むこともなくなる。
そう考えただけで僕の胸は踊った。
「良いモナよ。でもその代わり、条件があるモナ」
「条件? 何ですか?」
僕が訊くと、彼は怪しく微笑んだ。
「モナの組織『Sevence Sign』に入って欲しいモナ」
・第3話・「小さなオフィスと二人の男」
「組織…?」
僕は固まった。
組織と聞くと、あまり良い印象はない。
刑事ドラマの見過ぎだと言われるかもしれないが、
僕の中で「組織」という言葉の位置づけは、かなりヤバいところにある。
「別に変な組織じゃないモナよ。…まぁ、確かに普通の組織ではないけど」
「それを一般的には『変な組織』って言うんじゃないですか?」
「う~ん、そうモナね。じゃあ変な組織モナ」
「そんなあっさり言われてもなぁ…」
僕は頭を掻きながら尋ねた。
「…僕を組織に入れてどうするつもりなんですか?」
すると彼は辺りを見渡して、答えた。
「…ここじゃ言えないモナ。ちょっとモナについて来て欲しいモナけど…いいモナ?」
「いいですが…その前に、名前を教えてくれませんか? 僕はポジビリティっていいます」
「ポジビリティ君モナね。モナの名前はモナーっていうモナ。
こう見えても、一応組織の創設者でリーダーやってるモナ。さ、行くモナよ」
僕はモナーさんの後について歩き出した。
いつの間にか辺りはすっかり夜が更けていた。
モナーさんが僕を連れて来たのは、あるビルの一室だった。
「さ、入ってモナ」
僕は促されるままに中に入った。
中は、何の変哲もない小さなオフィス。
誰もいない…いや、二人居た。
「モナー、お帰り。そっちは? お客様かい?」
一人は丸く黒い瞳と黄色い肌を持つ、とぼけたように笑った口元の男。
楽しそうに笑う口元が彼の人柄の良さを伺わせる。
「お前が客を連れて来るなんて珍しいな」
もう一人は全身真っ青で、蒼く澄んだ目をした男だ。
どこか硬派な表情は生まれつきなのだろうか。
モナーさんは僕を二人の前へ連れて来ると、嬉しそうに言った。
「モララー、ギコ、ただいまモナ。『七つの刻印』の最後の一人を連れて来たモナよ」
(…『七つの刻印』?)
僕はモナーさんの言っていることが分からず、頭を捻った。
モナーさんの言葉に、二人の顔色が変わる。
「…へぇ、それはまた豪華なお客様だこと」
「で? そいつは何の能力持ってるんだ?」
「彼は『人の心が聞こえる』んだモナ。
でもまだ能力のコントロールが上手くいかなくて、困ってるみたいだから、何とかしてあげようとここに連れて来たモナ」
そう言うとモナーさんは二人のいるテーブルまで歩いて行った。
僕も慌ててその後に続く。
「ポジビリティ君、紹介するモナ。黄色い方がモララーで、青い方がギコっていうモナ」
「あ、どうも初めまして…ポジビリティっていいます…」
しどろもどろになりながらも僕が挨拶すると、二人は軽く会釈してくれた。
「さてと、コーヒーでも飲みながらマターリするモナ」
「あの~、モナーさん…」
とにかく今は詳細が知りたい。
「『七つの刻印』って何ですか? あと僕に詳しい説明を…」
「ああ、ごめんモナ。今から説明するモナ」
・第4話・「七つの刻印」
モナーさんは僕をソファーへ座るよう促し、自分も向かい側に座った。
僕の隣にはモララーさんが座り、モナーさんの隣にはギコさんが座る。
「さて、まずこの組織がどういったものか簡単に説明するモナ。
この組織『Sevence・Sign』は6人のメンバーだけで構成されている組織モナ。
そしてそのメンバーは全員…『神々の刻印』の守人の子孫なんだモナ」
「『神々の刻印』…?」
モナーさんは大きく頷いた。
「そうモナ。『神々の刻印』は神が生み出した特殊な刻印で、強大な力が秘められているんだモナ。
刻印は全部で七つあって、それぞれに力が封印されているモナ」
「でもよ、神って奴は臆病者でな。刻印の力が悪事に使われないようにと、七人の守人に刻印を託したんだと。
自分で管理すりゃいいのに…無責任な奴だよ、神も」
ギコさんがため息混じりに言うと、モララーさんが言った。
「ギコ、そんなこと言うとまた『あいつ』に封印かけられるぞ?」
「ちっ…わかってるよ。『あいつ』にだけは逆らえねーからな…」
「まぁまぁ、二人とも。話を戻すモナよ?」
モナーさんは笑顔で話を断ち切ると、再び話し始めた。
「『神々の刻印』は代々守人の手によって守られ、守人の家系にのみ伝えられていったモナ。その刻印は今も受け継がれているモナ」
「…え、ということはまさか…」
全てを悟った僕に、モナーさんは嬉しそうに言った。
「察しがいいモナね。そう、モナもモララーもギコも『神々の刻印』を守る守人の子孫。
そして…キミも『神々の刻印』を受け継ぐ守人の子孫なんだモナ」
「僕が…ですか?」
「そうモナ。キミは選ばれた人種モナよ」
僕は耳を疑った。
そんな話、今まで聞かされたことなどなかった。
僕は能力が発動する前までは、本当に普通のAAとして生きて来た。
…少なくとも、記憶を失う前までは。
それなのに…何で急に…しかも今更…。
「選ばれた人種、ねぇ…少し言い方が大袈裟なんじゃないの? モナー。
そんな言い方しちゃ、ポジビリティ…君だっけ? 彼も驚くだろうに」
「でも事実モナ。彼にもわかって貰わないといけないモナ」
「あの…一つ質問していいですか?」
僕は恐る恐る尋ねた。
「僕が『神々の刻印』を持つ守人の子孫という証拠は何かあるんですか?」
「あるモナよ」
モナーさんはあっさりと答えた。
「キミの左耳の付け根のあたり。その辺に変な紋様があるはずモナ。それが刻印。
嘘だと思うなら、そこに鏡があるから確認してみるといいモナ」
言われて、僕は鏡の前に立って自分の耳をよく見た。
…本当だ。
僕の左耳の付け根の辺りに、小さいが奇妙な紋様が刻まれていた。
人間の耳たぶのような模様に十字が引かれ、十字の真ん中に黒い丸がついている。
その周りを、大きな丸が囲んでいる…そんな紋様だ。
いつの間についたのだろう。
普段自分の耳なんてまじまじと見ないから、全然気が付かなかった。
「わかったモナか? キミは『神々の刻印』を受け継ぐ者として、組織に入らなければならないモナよ。
嫌とは言えない。キミはそのためにこの世に生まれたのだから」
モナーさんの言葉が、僕の心に深く突き刺さった。
・第5話・「残りの3人」
「キミ、ご両親はどうしているモナ? 兄弟とかはいるモナ?」
何も言えなくなってしまった僕に、モナーさんが訊いてきた。
「…わかりません。僕、記憶を失くしているんです」
僕がそう言うとモナーさんは少し眉をひそめたが、そのことについて問いつめることはしなかった。
「そうモナか。キミは何歳モナ?」
「正確にはわからないですが…多分21歳くらいです」
「仕事とかはしてるモナか?」
「いえ…記憶がないせいで、ことごとくクビになりましたよ」
僕が答えると、モナーさんはうんうんと頷いて言った。
「文句なしの合格点モナ。キミにご両親が居たり、キミが仕事やってたりしたら
色々と手配が必要だったモナけど…これなら何もしなくていいモナね」
「あの…ところで僕は組織に…」
バンッ!!
その時、オフィスのドアがやや乱暴に開けられた。
入って来たのは気性の荒そうな女性(…かな、多分)と、十字の髪止めをした金髪の女性、
そしてタバコをくわえた、物静かな男だった。
「あ、つーちゃんにレモナ、フーンもお帰りモナ」
「随分遅かったね。せっかくコーヒー淹れておいたのに冷めちゃったからな!」
「その様子じゃ、仕事に手間取ったか?」
モナーさん達が口々に言いながら三人を出迎える。
すると気性の荒そうな女性がピリピリした声で言う。
「オレノ仕事ヲ見ヤガッタ奴ガ居テヨ!! ムカツクカラミンチニシテ来タンダガ、
マダ怒リガ収マリャシナイゼ!! アヒャー!!!」
(ミ、ミンチ?!)
あまりの過激な表現の仕方に、僕は竦み上がった。
その言葉に嘘はないのだろう、彼女の両手は血で溢れている。
「困ったわよ、つーちゃんったら周りの人をみんな切り刻んじゃうんだもの。
後始末が大変だったわー。ま、今回はフーン君が居てくれたからそれなりに楽だったけど」
金髪の女性が髪を整えながら言う。
彼女の身体にも少しだが血の跡がこびりついていた。
「…おい、ところでそこに座ってる奴はなんだ? 客か?」
物静かそうな男がくわえ直したタバコに火をつけながら言った。
彼の身体には血の跡は見あたらない。
…いや、汚れひとつついていないと言った方が正しいだろう。
「ああ、彼はポジビリティ君。『神々の刻印』の最後の一人モナよ」
モナーさんが言うと、三人の顔色が変わった。
『神々の刻印』がこの組織に集まることは、やっぱり何か深い意味があるのだろうか。
「あ、そうだポジビリティ君…長いからポジ君って呼ぶモナね。
メンバーも全員揃ったことだし、改めて自己紹介させて貰うモナ」
「あの…僕の力をコントロール出来るようにはしてくれるんですよね…?」
「勿論モナ。そんなに焦らなくても大丈夫モナよ。後でちゃんとやってあげるモナ。だってキミはもうこの組織に入らざるを得ないから」
あっけに取られる僕に、モララーさんが首を振りながら言った。
「諦めた方がいいよ、ポジ君。モナーは最初からキミを組織に入れるつもりで連れて来た。
それに、『刻印』の力が覚醒した以上…もうキミは普通の生活は出来ない」
僕は何も言えなかった。
・第6話・「Member&Codename」
「さてと…まずはモナから。さっきも言ったけど名前はモナー。年は23。
この組織の創設者でリーダーやってるモナ。持ってる刻印は『変化』の刻印モナ」
「変化?」
首をかしげる僕に、ギコさんが説明してくれる。
「…刻印にはそれぞれ名前がある。能力にちなんでつけられたものだ。
モナーの場合は『変化』の刻印…すなわち奴はありとあらゆるものに変身出来るのさ」
するとモナーさんは笑顔で付け加えた。
「全部とはいかないモナよ。一度見たものになら何でもなれるけど」
「似たようなもんだろ…」
「でも違うモナ。あ、モナ達にはコードネームがあって、モナから順番に1,2…と数えていくモナ。
ちなみにモナは『1st Sign』モナ。さて、次はモララー。コーヒー飲むのは後にするモナよ」
モナーさんに言われて、モララーさんがコーヒーのカップを口から離した。
「僕はモララー。年は24。この組織では主にモナーの相方や代理をやってるよ。
何せナンバー2だからな! 持ってる刻印は『自然』の刻印。
これは自然界に存在するエレメント…要するに魔力の塊みたいなものを吸収し、操る力を持った刻印なんだ。
コードネームは『2nd Sign』。よろしく! さ、次はギコの番だからな!」
言われたギコさんはちょうどコーヒーを口に運ぼうとしていたところだった。
あまりに良すぎるタイミングに、ギコさんが少し顔をしかめたのが見えた。
「俺はギコ。年は24。一応組織ではナンバー3ってことになってるが…
モララーがナンバー2なら、俺の方がナンバー2に相応しいと思うのが正直なところだ。
コードネームは『3rd Sign』。持ってる刻印は『武器』の刻印だ。これは…言うより見た方が早いな」
そう言うとギコさんはさっき置いたコーヒーのカップを手に持った。
すると、彼の手の甲に不気味な紋様が浮かび上がり――――
次の瞬間、コーヒーカップは短剣に変わっていた。
「この刻印の力は、触れたものを武器に変える。
俺のイメージがそのまま具現化するから、ほぼ俺の思うがままに武器が精製出来るということだ」
「アヒャヒャ、相変ワラズ便利ナ能力ダナ! ジャア、次ハオレノ番ダ」
気性の荒そうな女性が血にまみれた手を拭きながら言った。
「オレノ名前ハ、つー。年ハ…多分23。コードネームハ『4th Sign』ダ。
オレノ持ッテル刻印ハ『切断』ノ刻印ッテ言ッテナ…オレノ意志デ自分ノ指ガ鉤爪ニナル。
コノ鉤爪ニ切レネェモンハネェ。アルナラオ目ニカカリタイモンダナ」
そう言ったつーさんの指が伸び、一瞬で鉤爪と化した。
思わず息を呑む僕に、金髪の女性が僕に囁いた。
「つーちゃんは性別不明種なの。そのことを気にしているから、あまり性別については触れないであげて。
じゃないとものすごく怒るのよ、つーちゃんは…」
僕は頷いた。
つーさんを怒らせたら、僕は一瞬でミンチにされてしまうだろう。
それだけは勘弁だった。
女性は僕が頷いたのを確認すると、にっこり笑って自己紹介を始めた。
「さて、次は私かしら? 私はレモナ。年は22、コードネームは『5th Sign』よ。
この組織には愛しのモナー君に誘われたから入ったのv 持ってる刻印は『鋼鉄』の刻印で、これは私の身体を鋼鉄に変える上、
少しだけなら自分の身体を武器に変えられるのよ。ま、モナー君やギコ君までとはいかないけどね」
「レモナ、もう一つ言い忘れてることがあるんじゃねーのか」
レモナさんの後ろから、物静かな男が言った。
「お前がネカマだってことをよ」
「え、え?! ネ…ネカマって…まさか…」
「レモナはネカマ。元は男なんだよ」
さらっと言ったモララーさんに、僕は思わず絶句した。
レモナさんが大声でがなりたてる。
「う、五月蠅いわね!! そんなことどうだっていいじゃないのよ!!
私はモナー君に愛されるなら女になったって構わないと思ったからなったんだもの!!」
「そうモナよ、フーンにモララー。今のレモナはとても綺麗モナ。それだけで十分だとモナは思うモナ」
モナーさんはレモナさんの髪を手で梳きながら、やんわりと言った。
その一言でレモナさんはすっかり機嫌が良くなったらしく、胸を張って言う。
「ほら、モナー君だってそう言ってくれてるでしょう?! フーン、次はあんたよ!!」
「ちっ…わかったよ、面倒臭ぇな…」
物静かな男がタバコを灰皿に置いた。
「俺はフーン。年は25だ。コードネームは『6th Sign』。
持つ刻印は『速度』の刻印だ。恐らく俺の力が一番ややこしいだろうから説明しておくが…
この力は動くもの全ての動く速度を自在にコントロール出来るものだ。
遅くしたり速くしたり…全て俺の思った通りの速度になる…俺がこの目で見たものはな」
そう言ってフーンさんは糸のように細い目を少しだけ開けた。
途端、僕は痺れたように身体が動かなくなった。
フーンさんの真っ暗な瞳の奥に、奇妙な目のような紋様が描かれていた。
それが刻印だということはすぐにわかったけれど、刻印の目に見つめられ、僕は身動き一つ取れなかった。
まるで、あの目に縛られているかのように。
「フーン、いい加減目を閉じろ。ポジがビビってるぞ」
ギコさんに言われ、フーンさんが目を閉じると、僕の金縛りは解けた。
「じゃあ、最後はポジ君に自己紹介して貰うモナ」
モナーさんに言われ、僕は慌ててソファーから立ち上がった。
「は、はい! ええと…名前はポジビリティです。
年は多分21で、今日モナーさんに連れられてここに来ました。
刻印の名前は…まだわからないですけど、人の心の声が聞こえるっていう力があるみたいです。どうぞよろしく…」
最後の方は自分でも驚くほど小さな声だった。
他のメンバーの人に比べて、僕の力が酷くちっぽけに感じたからだ。
「ふーん、お前だけ戦闘型じゃないんだな」
「人の心が読めるってことは…私の心は読めるかしら?」
「いえ…今は特に…あれっ?」
レモナさんに言われて、僕は初めて気が付いた。
モナーさんに会った時から、僕の力が勝手に発動していないことに。
「ふふ、キミの力はまだ弱くて不安定モナ。だからちょっとモナの力でキミの力を制御させて貰ってたモナ」
「え…でも、モナーさんの力は変身することじゃあ…?」
「あいつは特別なんだよ」
ギコさんが言う。
「モナーの一族は全ての守人を束ねる存在として、神に任命されたんだと。その時に、刻印とは別の力を与えられたらしい」
「何だよモナーばっかり…神もセコいんだからな!」
「まぁまぁ、お喋りはその辺にして…ポジ君」
「は、はい」
モナーさんが僕を手招きした。
僕が言われるままに彼に近寄ると、彼の白い手が僕の刻印に触れた。
僕は驚いて後ずさりしようとしたが、彼に止められた。
「キミの願いを叶えてあげるモナ。いいからそのままおとなしくしてるモナよ。すぐに終わるし、痛いとか痒いとかもないモナ」
「痛イトカ痒イッテ、医者ジャネェンダカラヨ…」
つーさんのさりげないツッコミも、モナーさんは得意の笑顔でかわした。
・第7話・「力・覚醒」
モナーさんの指が、僕の刻印の上を滑るように動いている。
「ちょっと失礼するモナ…ここモナね」
指が止まったところで、モナーさんは刻印を覆うように手を広げた。
僕の視点からではよく見えないが、彼の手から光が漏れているのを感じた。
僕の刻印が発する光が漏れたものなのか、彼が発しているのかはわからないが、不思議な温かみが伝わってくる。
「…はい、これで完了モナ」
そう言ってモナーさんは手を離した。
「え、これで終わりですか?」
「そうモナ。もうキミは自分の力を自由に操れるモナ」
「操るって、どういう風に…?」
「簡単モナ。心の中を見たい人を思い浮かべるだけでいいモナ。練習も兼ねて、早速やってみるといいモナ」
僕は静かに息を吸い、精神を研ぎ澄ました。
試しに、目の前にいるモララーさんを思い浮かべてみる。
「…あ、聞こえる…」
モララーさんの考えていること全てが、一気に頭の中に流れ込んで来る。
でもそれは今までのような五月蠅いものではなくて。
とても自然に、僕の中にひとつの「情報」として流れてきた。
「誰の心を読んだモナ?」
「…モララーさんです」
「え?! 僕の心読んだの?!」
「丁度いい、奴が何を考えてるのか教えろ、ポジ!」
ギコさんが僕に迫って来る。
「あ、ええと…『早くコーヒー飲みたい』って…」
勢いに押されて僕が答えると、ギコさんはつまらなさそうに言った。
「何だ、そんな下らねぇこと考えてたのかよ」
「な、何だよ! 僕が無類のコーヒー好きだって知ってるくせに!」
「…どうやら、異常はないみたいモナね」
モナーさんが笑顔で頷きながら言う。
「…あ、はい」
「今日から君は晴れてこの組織の一員…君のコードネームは『7th Sign』モナ。ここが今日から君の家、君の帰る場所モナよ」
「あの…荷物とかは…」
「それなら心配ないモナ。住所さえ教えてくれれば、モナが運んでおいてあげるモナ。…あ、そうだ。肝心なことを話していなかったモナね」
モナーさんはもう一度ソファに座り、他のメンバーにも座るよう促した。
「この組織は、ある目的のために活動をしているモナ」
「ある活動…ですか?」
「まぁ、僕らも一応それなりに仕事はしてるんだよ」
モララーさんが全員分のコーヒーを淹れ直しながら言った。
彼がコーヒーのカップを全員に配り終えたのを確認して、モナーさんが続きを話す。
「さっき、『刻印』は全部で七つあるって話をしたモナよね?」
「はい」
「でも、本当は八つあるモナ」
「え? 七つじゃないんですか?」
思わず首をかしげた僕に、ギコさんが言った。
「その『八つ目の刻印』を見つけ出すのが俺達の仕事だ」
・第8話・「追う者と追われる者」
ある高層ビルの屋上。
そこに、一人の少女が街を見下ろすように立っていた。
傍らには巨大な犬が座っている。
「…ねぇ、ぞぬ」
少女は犬に呼びかけた。
ぞぬ、と呼ばれた巨大な犬はその大きな顔を少女に向ける。
「私を追い回して、一体どうするつもりなのかしらね」
少女の顔には疲労の色が見えた。
「…疲れたけど…でも私は勝たなくちゃいけない。自由を手に入れるために」
少女はそう言ってぞぬの頭に飛び乗った。
同時に背後から聞こえてくる、沢山の人間の走る靴音。
「また来た。…ぞぬ、逃げるよ」
その声を合図に、ぞぬは地面を蹴る。
普通ならそのまま落ちてしまうところだが――――
「居たか?!」
「いや、居ない! 下の奴らからも連絡なしだ!!」
「クソ、また逃げられたか!!」
数分遅れて現れた黒服の男達は、悔しそうに唇を噛んだ。
「ウフフ…ねぇ、ぞぬ…見て。私達を捜してるのよ」
少女が楽しそうに微笑む先には、沢山の黒服の姿。
彼女は耳で羽ばたき宙を舞うぞぬの上から、さっきまで自分が居たビルを見下ろしていた。
「私は絶対逃げ切ってみせるわ。この力は誰にも渡さない」
その目に宿るは、決意の光。
「…行こう、ぞぬ。長居は無用よ」
少女の命令で、ぞぬは大きな羽ばたきと共に闇に消えた。
「…女の子…ですか?」
「そうモナ。八つ目の刻印を持っているのは、『しぃ』という名前の女の子モナ。
彼女は愛犬のぞぬと行動を共にし、街から街を逃げ回っているモナ。
モナ達の目的は刻印を持つ彼女を『保護』して、彼女の刻印を狙う連中から彼女を守ることなんだモナ」
モナーさんの話では、その「しぃ」という女の子が八つ目の刻印を持っていて、
彼女は刻印の力を狙う連中に追われる日々を送っているという。
「…でも、そこまで彼女の素性が割れているなら、どうして彼女をなかなか保護出来ないんですか?」
僕が訊くと、モナーさんは困ったような顔で言った。
「彼女は幼い頃から刻印の力を持っているということだけで、様々な人間に狙われ、逃げ延びながら生きてきたモナ。
…そのせいか…彼女は人を信じることが出来なくなってしまったんだモナ。
だから、モナ達が手を差し伸べても…その手を取ろうとしない」
「おまけに、最近彼女は刻印の力を使って姿を眩ましながら行動するようになって…。
それでも何とか情報を集めて彼女を見つけ出すんだけど…まるで話を聞いてくれないの」
レモナさんも言う。
「僕らの仕事は簡単なように見えて簡単じゃないんだ。だからこそ、この組織をモナーが立ち上げたわけだしね」
「そうなんですか…」
「アイツ、最近特ニ逃ゲルノガ上手クナッテナ。オレデモ捕マエランネェンダゼ」
「お前はすばしっこいのをウリにしてるからな。ムカつくのはわかるが、今度会ったら間違っても、殺すなんてことはするなよ?」
イライラした様子のつーさんを、ギコさんが宥める。
つーさんはワカッテルヨ、とだけ答えて乱暴にカップを口に運んだ。
「…それより、モナー。そのガキについてのことだが…」
今まで話を黙って聞いていただけのフーンさんが、口を挟んだ。
「タカラのところの組織がさっき、奴とニアミスをしたらしいという情報が入った。
情報が正しければ、まだこの辺りにいるかもしれないが…どうする?」
カップがテーブルに置かれ、モナーさんが振り返る。
「…この街は、彼女にとって好都合モナ。これだけ大きな街だと、身を隠せる場所が多いからモナね。
だから、すぐに街を離れる可能性は低いモナ。明日にでもまた捜索に行って貰うことになると思うモナけど…あ、そうだ」
モナーさんは僕に向き直ると、笑顔で言った。
「明日の仕事、ポジ君にも参加して貰うモナ♪」
「えぇぇぇぇ?!」
突然の提案に、僕は頭の中が真っ白になった。
・第9話・「叫び」
…翌日。
僕はギコさんやモララーさんと一緒に、街の真ん中にある巨大なビルの屋上に来ていた。
モナーさんに言われた「仕事」をするためだ。
昨日この話を持ちかけられた僕は、突然のことに頭が混乱した。
『え、え、え、でっ、ででででもぼっ、僕なんかっ、ぜんqあwせdfrtふじこlp』
『大丈夫モナよ。簡単な仕事だし、何かあってもモララーやギコが守ってくれるモナ。でも、一応…護身用の銃ぐらいは渡しておくモナね』
『安心しなよ、ポジ君。ギコはともかく、組織ナンバー2の僕がいる限り、
君が生命の危機に晒されることはないんだからな!!』
『…ともかく、は余計だ。いいか、ポジ。お前はもうこの組織のメンバーの一員。
今回は初任務だから仕方ないが、人に守られるばかりでなく、自分の身は自分で守れるように努力はしろよ。
俺達もお前を完全に守りきれる保証はないぞゴルァ』
『は、はい…がんがります…』
それが昨日の話。
僕の記念すべき(?)初任務は、昨日教えて貰った「八つ目の刻印」を持つ女の子、
「しぃ」ちゃんを捜し出し、接触を図ること。
そして出来るなら、彼女を組織に連れて帰ること。
…まぁ、昨日のレモナさんの話からすると、後者は相当難しそうだけど。
そこでまず、彼女が昨日現れたというビルで手がかりを掴もうというわけだ。
勿論、僕の能力を使って。
「モナーが言うには、お前の能力は相手の『気』を強く感じる場所ほど効果があるらしい。
当然相手が目の前に居れば効果は抜群だが、今回の場合はそうはいかない。
そういう時は、相手の『気』が強い場所で能力を使えばそれなりに効果はあるそうだ。例えば、その相手が一度訪れた場所とかな」
「…で、ここに来たんですね」
「その通り♪ せっかく便利な能力持ってるんだから、有効活用するっきゃないからな! と、いうことで宜しくポジ君」
「はい…とりあえずやれるだけやってみます…」
僕は目を閉じた。
昨日みたいに深呼吸して、彼女の顔を思い浮かべる。
(会ったことないからあくまで想像だけど…)
辛い。
辛い辛い辛い辛い。
どうして?
どうして私だけが…
滝のように、勢いよく。
聞こえてくる、彼女の声。
これは彼女の本音なのだろう。
憎い。
憎い憎い憎い憎い。
私を追う奴らが憎い。
こんな刻印生み出した神が憎い。
叫ぶような、喘ぐような悲痛な響きに、聞いている僕も正直辛くなってきた。
でも、聞かないと。
これは仕事なんだ、任務なんだ。
僕は必死に精神を集中させた。
だから私は
復讐するの。
復讐…?
誰に?
この刻印を作った神様?
それとも、彼女を追う連中?
これは私にしか出来ないの。
自由を手に入れ、あいつに復讐する。
今日はあいつは現れるかしら。
13日の金曜日、誰もいないあの孤独な海に。
絶対に仕留めてみせるわ。
私の力は、そのためにあるのだから。
…この力は…誰にも渡さない。
「っ!!!」
…コノチカラハ、ダレニモワタサナイ。
そう言った彼女の声があまりにも恐ろしい声だったので、僕は思わず目を開けた。
息が荒く、脂汗をかいているのが自分でもわかる。
頭が痛い。
目の前がぐらぐらして…
「おい、ポジ! 大丈夫か?!」
思わず崩れかけた僕の身体をギコさんが支えてくれた。
「…あ、ギコさん…すみません…」
「能力を行使しすぎたか? 体力の消耗が激しい」
「ポジ君は真面目だからねー。仕事熱心なのは偉いけど、無理はしない方がいいよ。
能力の扱いに慣れるまでは、刻印の力に身体がついていかないから。少しそこに座って休んでれば? 気休めにはなると思うよ」
「はい…わかりました」
僕は床に座って、少し休むことにした。
「で、何か手がかりになりそうなことは聞こえた?」
モララーさんの言葉に僕は頷き、さっき聞こえたことを話した。
しぃちゃんの本音の叫び。
復讐を考えている相手がいること。
彼女はそのために刻印の力を使っていること。
そして、その相手が13日の金曜日、『海』に現れることを願っていること。
「海…か。ギコ、この街の港ってどこだっけ?」
「港って、ラウンジ港のことか? そこならここからはそう遠くないぞゴルァ」
「よし、まずはポジ君の回復を待って、ラウンジ港に向かおうか。
彼の聞いた声によると、彼女はそこに現れるかもしれないそうだからね」
「わかった。モナーに連絡する」
そう言うとギコさんは携帯を取り出し、組織と連絡を取り始めた。
モララーさんは僕の隣に座り、目の前の景色を眺めている。
「あの…すみませんモララーさん…僕のせいで、仕事を進めるのが遅れてしまって…」
「ん? 別にいいよ。僕はどちらかといえば、のんびり仕事をするのが好きなタイプだし。あいつはどうだか知らないけど」
彼の指が、ギコさんを指し示す。
「大丈夫。僕もギコもキミが刻印の力に慣れてないってことはわかってるから、
そんなに僕らに気を遣わなくていいからな。気楽に行こう、気楽に」
「あ、ありがとうございます…」
僕は無意識に深々と頭を下げていた。
やがて連絡が終わったらしいギコさんが、モララーさんと少し距離をとって座った。
「出来れば日が沈む前に帰って来いってさ。レモナの特製ディナーが冷めるからだと」
「そっか。レモナの料理の味は格別だからな。よし、夕方までには終わらせようか。ポジ君、身体の方はもう大丈夫?」
「あ、はい。あれも多分一時的なものだと思いますし」
「よし、じゃあぼちぼち行くとしますか。でも本当に無理だったら言った方がいいよ。人間、やせ我慢が一番良くないんだからな」
「お前もだろ、モララー」
僕はゆっくりと立ち上がり、傾きかかった太陽を見つめた。
あの陽が落ちる前に、仕事を終わらせる。
そう心に決め、僕達はビルを後にした。
第10話:「宿敵」
「…やれやれ、モナーさんのところにも厄介な人が来たものですね」
ある組織の本部ビル最上階。
幹部だけが入ることを許されたこの部屋で、タカラは大きなため息をついた。
「しかも今回は彼とモララーさん、おまけにギコ先輩までついていると来た。
これじゃあ迂闊に手は出せないですかねぇ…困りましたねぇ…」
口はそう言ってはいたが、タカラの表情は相変わらず笑ったままであった。
そこへ、彼の横に立っている女性が口を挟む。
「…本当ハ、困ッテナイデショウ? タカラサン」
「あ、バレました?」
悪戯がバレた子供のように、タカラは舌を出して笑った。
そんな彼に対して女性は何も言わず、表情も硬いままだ。
「わかりました、わかりましたから…無言でこっちを睨むのはやめて下さいよ、でぃさん。で、どうしましょうか? 誰かいますかねぇ?」
「今デシタラ、ウララーサンガ暇デスネ。アトハ山崎サンモ…ソレグライデスケド」
「そうですか。じゃあ僕からおながいしておきます」
タカラはそう言って、窓から外へと視線を移した。
「そう簡単にはいかせませんよ…先輩」
ラウンジ港。
様々な国や街の人々が集うこの港では、人の足が絶えることはない。
ただ…13日の金曜日を除いては。
「どうして13日の金曜日は誰も人がいなくなるんですか?」
「昔から、縁起が悪い日だって言われててな。その日にこの港に来ると、船が沈んだり溺れて氏んだりするんだと。
特にここら一体に住んでる住民には、その迷信を信じている連中が多い。
そしてそのことを港にやって来る他の街や国の連中に言いふらしちまってよ。
迷信は全世界を駆け巡り、世界中でその迷信を知らない者は居なくなった。だから、13日の金曜日は港に誰も来ないんだ」
今日は、13日の金曜日。
ギコさんの言った通り、ラウンジ港には誰も居ない。
様々な大きさの船が、波に静かに揺れているだけだ。
「この日だけは、港から人が消える。それを狙って、しぃは復讐したい相手がここに来ることを望んだんだろうな。
もし、しぃがその『相手』を頃そうと企んでいるのだとしたら…こんなに好都合な環境はない」
「そうだね。人っ子一人いない港…目撃者の数も減らせる上、これだけ土地の面積が広いと何かあっても対応はしやすいし。
彼女にとっても、僕らにとっても好都合だからな」
僕らにとっても…?
もしかして…
少し気になった僕は、恐る恐る尋ねた。
「それって…相手と戦うことになったとしても…ってことですか?」
「その通りだよ、ポジ君。…伏せてっ!」
モララーさんが僕の頭を地面に押さえつけた瞬間。
ドゴォッ!!
何かが爆発するような大きな音がすぐ上から聞こえて、僕は思わず目を閉じた。
その後も、何度か小さな爆発音がして。
びくびくしながら目を開けると、モララーさんが僕を庇うように立って上を見上げていた。
「ポジ君、大丈夫? 怪我は?」
「あ、大丈夫です…」
「そっか。ま、僕のシールドは宇宙一だからな」
ふと見ると、彼の周りを強い風の流れが守るように覆っていた。
勿論、僕も含めてだが。
「え…あの、これって」
「前に言っただろ? 僕は自然界のエレメントを操る力を持っているってさ。
これは『風』のエレメントを集めて作った防御壁ってワケ」
そう言って笑ったモララーさんの胸元に、刻印が浮かび上がっているのが見えた。
雫の形をした模様の周りからオーラが出ているような模様が描かれた刻印だ。
「無駄話はそれくらいにしとけ、モララー」
「わかってるよ。で? さっきの攻撃はしぃちゃんの仕業?」
「いや…別の香具師だ。気配が明らかに違う。これは恐らく…」
「へぇ、勘がいいな。流石はこっちの頭領が『先輩』と呼んで尊敬するだけはある」
「…どうです? 今の花火は気に入って頂けましたかな?」
屋根の上から現れたのは、二人組の男だった。
一人はモララーさんによく似た外見の、紫色の肌を持つ男。
耳元に一周ぐるりと赤い線が引かれている。
もう一人は黄緑色の肌を持ち、何となくモナーさんに似てはいるが…彼には鼻と口がない。
唯一ある二つの目が、薄気味悪く笑っていた。
「…久しぶりだな、ウララー…と山崎だったっけ」
「オマエモナー。…っと、これはお前んとこの頭領の代名詞だったか」
「お前らが出てくるとは、タカラの奴は相当焦ってるのか?」
「フフ、答える筋合いはありませんね。もし知りたいのでしたら…」
山崎はない筈の口でそう言うと、どこからともなく大きな鎌を取り出す。
ウララーもニヤリと口元だけで笑い、背中から真っ黒な翼を生やして飛び立った。
彼の手に握られているのは、漆黒の槍。
「我々を倒すことです」
港に、緊張が走る。
僕は不安と緊張で押しつぶされそうになりながら、震える足で何とか立っていた。
日は既に傾き始め、まもなく夜が顔を見せようとしている。
「…あ~あ、仕方ないな。レモナの出来たて熱々ディナーはお預けかぁ」
「まだそうと決まったわけじゃねぇぞゴルァ。さっさと終わらせればいいだけの話だ」
「ま、そうなんだけど。でも正直面倒臭いんだよな~…」
とぼけた調子で言うモララーさんの手のひらに、吸い寄せられるように水が集まる。
足下に落ちていた石をギコさんが拾い上げると、手の甲の刻印が輝き…
その石はたちまち中くらいの大きさの剣に変わった。
「あ、そうだポジ君。銃の撃ち方わかる?」
「え…はい、わかります。昨日、モナーさんに一通り教わったので…」
「うん、それなら心配ないね。キミはまだ戦闘には不慣れだから…僕らの手助けしろとは言わないけど、
いざという時はそれで自分の身を守るんだ。いい?」
「は、はい!!」
僕は慌てて頷く。
するとギコさんが僕を手招きして呼んだ。
「いいか、ポジ。お前の能力は確かに戦闘向きじゃない。だが…使い方によっては
相手にとって戦闘でも脅威となる能力だ。そのことを考えて行動してみろ」
「…はい、わかりました。やってみます」
「作戦会議は終わりましたか?」
山崎が鎌を構えて尋ねる。
「ああ。悪いが、熱々のディナーが待ってるんだ。手っ取り早く終わらせて貰う」
「そうはいかないな。これからお前達がオレ等のディナーになるんだから」
「そういうことは、僕らを倒してから言うんだな。ウララー」
「ではお喋りはその辺で…参りますよ!!」
山崎の言葉で、向こうが屋根の上から飛び降りて来るのが見えた。
僕は手の汗で銃を落としそうになりながらも、必死に銃のグリップを握りしめていた。
第11話:「油断大敵」
ウララーがモララーさんに、山崎はギコさんに向かっていく。
僕は二人の戦いを見守る一方、いつ自分が襲われても対応出来るように、常に視線を四方八方へと巡らせていた。
「ほらほら、どうした?! 避けてばっかりじゃ、俺は倒せないぜ!!」
「…全く、僕が肉弾戦派じゃないってことぐらいわかってるくせに…これだから厨房は」
ウララーの繰り出す槍をかわしながら、ため息をつきつつモララーさんが言う。
「わかってるからこそ、そこを狙うんだよ! 相手に勝つためには当然の戦略だろ?!」
「まぁ、確かにお前の理論はわからなくもないよ。いや…むしろ、模範的な理論だね」
「珍しいな、お前が俺を褒めることなんて今までなかったじゃないか」
「あれ? そうだったっけ? …でも、ウララー…」
モララーさんの手に集まっていた水の塊が、段々と大きくなっていく。
「…模範的だからこそ…その理論には限界があるんだからな」
彼の口元が吊り上がる。
水の塊はうねりながら天高く昇り、今や竜巻のようになっていた。
「…来い」
ゴパァッ!!!
モララーさんが命じると同時に、水流の竜巻が姿を変え…巨大な水竜になった。
水竜はモララーさんの手から生えているように伸び上がり、ウララーに牙を剥いている。
「へぇ、なかなか面白いもん見せてくれるじゃん…」
「さっき、素敵な花火を見せて貰ったからな。これはそのお返しだよ」
「なら…出された礼は100倍にして返さないとな!!」
ウララーは天高く舞い、槍の先端を水竜に向けた。
一方、ギコさんは石から生み出した剣を振るい、山崎と戦っていた。
山崎の大きな鎌と、ギコさんの中型の剣が何度もぶつかり火花を散らす。
「ほほう、なかなかの腕の持ち主ですね。流石は我がリーダーが尊敬する人物」
「あいつに尊敬されるのは悪くはないが…俺達の邪魔をするのは頂けねぇなゴルァ」
「それは仕方のないことでしょう。貴方達の目的が有り続ける限り、
私達が貴方達の敵となるのは必然なのですから。それがリーダーのお考えです」
「そうか…あいつとは出来るなら仲良くやっていきたいと思っていたが…
タカラがそういうつもりならどうしようもないな。
なら、俺も手加減するのはやめにしよう。…ここからは本気で行く」
そう言ったギコさんの目の色が深みを増した。
綺麗な蒼が、どす黒い蒼へと変わっていく。
ボッ!!!
途端、ギコさんの周りの空気が変わった。
彼を中心に空気が渦を巻き、吹き上げるように昇っていく。
手に握られた剣は、いつのまにか禍々しいほどの黒いオーラを纏っていた。
「さて…続けるかゴルァ」
「…本領発揮といったところですか…望むところですよ」
そんなギコさんにも山崎は表情一つ変えず、鎌を振り上げた。
…正直、目が追いつかない。
どっちに気を配ったらいいのか、わからない。
大きな水の竜を従え、ウララーと対峙するモララーさん。
全身から禍々しいオーラを放ち、山崎の攻撃を受けるギコさん。
…どっちを見ていればいいんだろう。
僕はなるべく四人から遠ざかって、それぞれの戦いがよく見えるようにした。
「はぁぁぁぁっ!!」
漆黒の槍を携え、ウララーがモララーさんに突っ込んでいく。
その進撃を阻むのは、水竜。
口からいくつもの水の弾を吐き出し、彼の動きを止める。
「…チッ、やっぱりそう来るかよ!」
「単純に攻撃しても無駄なんだからな。それぐらいお前もわかってるだろ?」
「なら、その竜から海の藻屑にしてやるぜ!!」
ウララーの槍の先端が、奇妙に変形していく。
やがて、槍の刃は怪物の頭を模した形になった。
「行け!」
ウララーが叫ぶと、怪物の口から木の枝のようなものが一斉に生えてきた。
枝は水竜に巻き付き、水竜の全身を覆う水を吸い上げ始める。
思わぬ反撃に、水竜が悲鳴を上げた。
「竜っつったって、所詮は水で出来た作りものだろ?
だったら、竜を作り上げている水そのものを消してしまえばいい」
「へぇ、考えたなお前も」
「いつまでもお前に『考えなさ杉』って言われるのは癪なんでね」
得意げな笑みを浮かべるウララーに、モララーさんは頭を掻いた。
「全く…その勇ましさだけはお前のいいところなんだけどな」
ギコさんの方はというと、目にも止まらぬスピードで山崎に走り寄り、剣を振るっていた。
そしてそれを鎌で受け止めながら、時折流れるような反撃を見せる山崎。
二人の実力は、まさに互角だった。
「フフ、刻印の力も大したことないのですね…私すら倒せないようでは、
リーダーに会ったら、すぐにあぼーんされてしまいますよ?」
「タカラか…確かに奴はかなりの実力を持っている。モナーに引けを取らないほどのな。
だが…奴を育てたのは俺だ。お前ごとき、すぐに蹴散らしてやるぜゴルァ」
「言いますね…ならば、その実力とくと見せて頂こうではありませんか!」
山崎が鎌を振り上げ、一気に振り下ろした。
狙いは、ギコさんの首。
だが、それよりも素早い動きでギコさんは鎌の一撃をかわすと、次の瞬間には山崎の背後にぴたりとついていた。
「…な…!!」
「手抜きするのは、意外に疲れるもんだな…まぁいい、これで仕舞いだ!