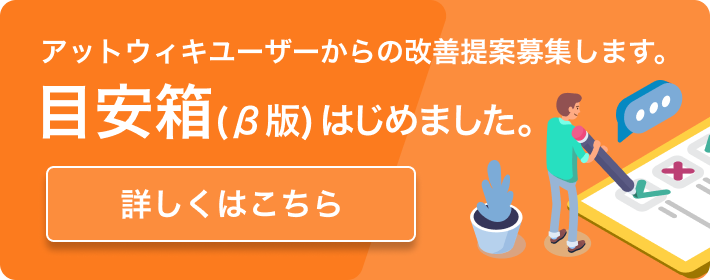盲雨
メクラアメ メクラアメ
愛した男が帰らない
奥方は雨に寄り道
学生は蛙に騙された
娘は雨から出たくない
想い人のすべてを攫うは
憎らしや
* * * *
空気がまとわりつくような、そんな夜だった。
湿気を含んだ空気に線香の煙が立ち上る。休む間もない雨音を縫って、住職の低い読経が響いていた。
ここ数週間休むことなく続いた雨で、町の外れにあった溜池が溢れた。用水路につながっている水門が泥で詰まって、水抜きの役割を果たしていなかったからだ。
晴れ間を選んで若い男達が池の泥をさらった。
――――最初は木かと思ったんですよ。
「彼」をすくい上げた男は血の気の失せた顔で呟いたという。
「池の底から白骨死体で出てきたんでしょ? ギコ君。」
葬式の終わり、雨音に紛れた噂話が聞こえる。
「どうもそうらしいんですよ。行方不明になってからもう三年。」
「恐ろしいことになったものだ…」
部屋の隅で囁かれる噂話は、当然俺の耳にも入っていた。そして、勿論
「つーちゃん!お兄さんのこと、その、あの、大変だったな。」
俺のすぐ隣で、喪主のつーが肩を落としていた。当然囁き声も彼女の耳に入っていることだろう。
彼女は心持ち青ざめ、組んだ指をじっと見つめているだけだ。
いつもピンと伸びている背筋も、引き締まった目許も、笑みを浮かべている口元も、全てが陰鬱な悲しみで覆われている。
囁き声の主は決まり悪そうに彼女を横目で見ていた。
「俺、何て言っていいか…。」
「《メクラアメ》だ」
「え?」
「兄貴だよ。あの時もひでぇ雨が降ってた。メクラアメに攫われたんだ。」
唇を殆ど動かさず、うめくように彼女は呟いた。
組んだ指に力が込められて真っ白になる。
目の縁に見る見るうちに涙が溜まり、唇が引きつるようにわなないた瞬間に、零れた。
「あの女が兄貴をたぶらかしてあの世に連れてっちまったんだ!」
「つ、つーちゃ…」
「あんなに『つれてかないで』って…頼んだのに…!」
彼女は大きくよろけ、支えた俺の肩に額を当てて泣きわめいた。
支えた彼女の肩は驚くほどに細くて、しゃくり上げるたびに震えている。今すぐにでも壊れてしまいそうなほどに。
葬儀に訪れた友人達も、手伝いにきたのーちゃんも、皆、可哀想な喪主…死者の妹を見つめていた。
「つーちゃん…」
俺は支える腕に少し力を込めた。
あの池さらいで、つーちゃんの兄貴…ギコさんの骨が出てきたのが数日前。
何故池の底で死んでいたのかは解らない。
ギコさんは三年前から行方不明になっており、家は妹のつーちゃんが一人で守っていた。
――――メクラアメに攫われたんだ。
盲雨は、引き裂かれた男女が 迷って抜けられなくなる雨だと言われている。
暗闇から消えたかたわれが相手を呼ぶ。
そしてそれに応えると、応えた方は”向こう側”へ行って、
二度と帰ってこないそうだ。
「……。」
ああ。彼女は。
お兄さんのこと大好きだったんだな…。
俺の肩の上で泣き続ける彼女の顔を見て、俺は目眩がした。
彼女の流している涙は、彼女の為でも、勿論俺の為でもなく、彼女の兄貴の為に。
彼女が好きなのは、多分俺じゃなかった。
だけど、俺はつーちゃんが好きだった。
気が、おかしくなるほどに。
それを突きつけられたようで、俺は…。
―――― ザアアアアアアアア…。
「おや、雨が強くなってきましたね…」
「私たちはそろそろ…」
私はそう言って腰を上げた。
目の前で喪主である妹御が泣き崩れている。
それを支えている彼女の友人であるフサ君も、何かに憑かれたかのような陰鬱な目で、仏壇を睨み付けていた。
非常に気まずい空気を、線香の香りと雨の音が更に際立たせていて…。
―――― このままだと私も連れて行かれそうだ。
横を見ると、友人のモナーも苦い顔をしている。
葬式というのは、嫌だ。全てが重くまとわりついて、境界が曖昧に惚けてしまいそうになる。
「ああ、モナーはんもモララーはんも、雨が強ぅなってますさかいに、お気をつけて。」
葬式の手伝いをしていたのーが玄関口まで見送りに来て、言った。
奥の部屋ではまだすすり泣く声が聞こえていた。
外は闇に包まれて、雨音だけが響いている。
線香の香りの代わりに、泥臭い匂いが鼻先をかすめた。
「…それにしても、良く降りますね。」
前を行くモナーに声をかける。
「そうですね。じとじとじめじめして、食べ物も腐りやすいし薄暗いし、」
モナーは歩く速度を私にあわせながら、すこし間をおいた。
「…僕たちも気をつけないと攫われちゃうかな」
雨音が少し大きくなったような気がした。
雨の夜道は明かりがない。
油断すると隣にいるのがモナーなのか、誰なのか、解らなくなってしまう。
「盲雨《メクラアメ》なんてのはね、要するに人の心の惑いを例えたものなんですよ」
私の隣の闇が口をきく。モナーの輪郭はぼやけて、もう声しか聞こえない。
「”迷わない”と思っていれば捕まらないものです」
「またまた」
私はかろうじて合いの手を入れた。
メクラアメ。メクラアメなんて…。
―――― 兄貴はメクラアメに…
「そもそもウチらは盲雨なんて見た事無いじゃないですか。」
私は闇夜で薄く笑った。
そうだ、私はそんな雨には未だ遭ったことがない。
どのような物かなどとも考えたことも。
それは普通の雨なのか。例えば今、夜空を濡らしているこの雨の様な…?
「もしかしたら本当に雨が人を攫うのかもしれませんよ」
クック、と喉で笑うような声が隣の闇から聞こえた。
「ギコ君を攫ったのは果たして誰なんでしょうねぇ…」
―――― シトシトシトシト…
目の前で彼女は目を赤く腫らし、肩を落として座っていた。
参列者も手伝いの人も殆どが帰り、今、彼女の家には俺とのーちゃんの3人だけだ。
「…つーちゃん。」
俺は出来る限り優しく彼女に声をかける。
「もしつーちゃんが辛くなかったら、話訊いてもいいか。」
彼女はどろりと疲れた瞳を俺に向けた。
「…『あの女』のあたりか。」
「…、そう。」
俺は彼女の瞳を見返しながら頷いた。
――――あの女が兄貴をたぶらかして
あの時確かにそう泣き叫んだ。つーちゃんは興奮していて声は不明瞭だったけれど、俺が聞き違えるはずはないんだ。
彼女は俺の視線から逃れるように、膝の上に置いた指先に視線を落とした。
瞳が潤んでいる。
「…俺が話すと長ーぞ。」
「いいよ。一晩中でも、聞くから。」
俺は自分に言い聞かすように言って、彼女の顔をのぞき込んだ。
時間は惜しくない。彼女の話が聞けるのなら。
彼女の、伏せた瞳からはらはらと涙がこぼれて、頬を伝っていく。
「オレは、あの女が、憎い。ひでぇこといっぱい考えてる。きっと、オレのこと、見捨てたくなる…」
「ならない!!」
俺は思わず声を張り上げ、彼女の方に膝をつめた。
弾かれたように彼女は顔を上げて、涙がパラパラと空を舞った。
―――― 雨粒のようだ。
「俺が」
俺は彼女の指に手を伸ばす。
「俺がつーちゃんを見捨てるわけないだろ…」
呟きながら、す、と彼女の指に自分の指を重ねて
――――バシィ!!!
俺は呆然と彼女の顔を見つめた。
彼女は自分の指を握りしめ、怯えた瞳で俺を見ている。
「………やめろ、気持ち悪い」
青ざめた顔で、震える唇で、彼女は言い放った。
それは悲しみと言うより、驚きと言うよりも、
―――― 強い嫌悪。
…ああ。
やっぱりつーちゃんが好きなのは俺じゃないのか。
俺は自分の指先を見つめる。
やめてくれ。そんな瞳は…俺には耐えられない。
俺は、俺はつーちゃんが好きなのに。
つーちゃんしか俺の心にはいないのに。
お前の心にいるのは、誰なんだ?
自分の手の先にある、彼女の細い膝。
小さく震えていて…。
……いかんいかん。
俺はぶるぶるっと首を振った。
一瞬よぎった強い憎悪。それを振り払うように。
「悪かった。続きを聞かせてくれよ。」
彼女は震える肩を抱きながら、俺を見返した。
―――― シトシトシトシト…
ああ、雨がまだ降っている。
オレは雨が嫌いなのに。雨は悲しいから嫌いなのに。
オレはフサを撲ってしまった指をさすり、口を開いた。
…雨の記憶。
「……兄貴は、生きていた頃、近所の後家さんと出来ていたんだ…」
その女の旦那は死んでたのかどうかわかんなかった。いなくなっただけだったから。
兄貴が勝手に後家さんだって決めつけたんだ。
兄貴は毎日決まって彼女の家に行って、庭いじりをしている彼女を眺めていたんだ…。
『学生さん。さっきからご覧になってるみたいですけど、何か御用かしら?』
『え? あ、ああ違うっす。庭です。庭を見ていたんです。』
兄貴はしどろもどろになって、後家さんから目をそらした。
日差しが降りそそぐ、手入れの行き届いた庭。
『…綺麗だなと思って。』
兄貴はやっとの事でそう取り繕ったそうだ。
もちろん、庭なんて見ちゃいない。見ていたのは後家さんさ。
『若いのに庭が好きなんて珍しいひとね…。』
後家さんは微笑みながらそう返したそうだ。
その人は、かなり年上だったんだと思う。兄貴には関係なかったんだろうけど。
それから兄貴は、晴れた日には女の庭に通い詰めていた。
雨の日は…。
『ありゃあ絶対未亡人だ!』
居間で座り込み、兄貴はでかい独り言を呟いていた。
じっとりとした嫌な雨が2~3日続いていて、その間兄貴はあの女の家にも行けず、ずっとオレと一緒にいた。
『アヒャ、馬鹿兄貴がトチ狂いやがったな』
オレは兄貴にお茶を出しながらせせら笑い、兄貴の口まねをする。
『ああ、今日は災難だ。何故雨が降る。彼女の庭へ行けない……ってか』
『何で解るんだ』
兄貴がむっとして振り返った。全く反応が子供じみている。
オレは笑い出したくなるのを堪えて、澄ました顔で続けた。
『一昨日も同じ事言ってたぞ』
兄貴は口をゆがめて、オレの淹れた茶を一口飲んだ。
オレは兄貴のすぐ隣に腰を下ろして顔をのぞき込む。兄貴の隣はオレの定位置だ。誰にも譲らない。
ここは兄貴に一番近しい奴が座るべきなんだ。
兄貴はちらちらとこちらを伺い、口を開いた。
『だってよ。何もない庭に行くなんておかしいじゃねえか。』
兄貴は湯飲みを持ったままそう反論する。
ああ。それならば雨がずっと降っていればいい。オレは幾度となく思っていた事を考える。
この世は雨に包まれて。そしてその中はオレと兄貴だけ。
そう、雨の日、兄貴はオレだけの物だから。
『兄貴は庭が好きなんだろ?庭だけ見に行けよ。』
そんな考えなどおくびにも出さずにオレは言う。
あの女なんかに会いにいかなくったってオレが居るんだ。
兄貴はお茶を飲み干し、渋い顔をしてオレから顔を逸らした。
『あんまり余計なこと言わすなよ…』
オレは兄貴の背中にもたれかかる。頬に兄貴の体温が伝わってくる。
雨の日に、あんな女なんか入るスキはない。
『目を覚ませ。相手は人妻だぞ。』
もたれかかった先から見上げた、兄貴の顔のライン。
むっと唇をつきだして考え事をしている。きっと、あの女のことだ。
オレは少し腹立たしくなった。今日は雨なのに。あんな女はいないのに。
オレは兄貴のことしか考えてないのに。
『大体旦那だって本当に死んでんのか??』
注意をこちらへ向けようと無理矢理話しかけた。
女の事なんて考えるな。今ここに女は居ないんだ。今ここにはオレしか居ないんだよ。
兄貴は目線をちらっとこちらへ投げかける。
『そう、そこなんだ。俺は彼女にそこんとこを尋ねた』
そのまま兄貴は上の空になってしまった。
目線は、兄貴自身の足。でもそんなものきっと見えてない。
兄貴が見ているのは、
―――― あの人は盲雨に捕まってしまったわ。…他に誰か忘れられない人が居たのね。
―――― でも、私まだあの人のことを好きなの……内緒よ
『何黙ってんだよ!尋ねてどうなったんだ?』
オレは視線を邪魔したくて兄貴の身体を揺すった。
『……。』
早く聞かせろ、とさらにせっつく。
兄貴は足から空の湯飲みにかろうじて視線を上げ、また足先に視線を戻した。
『…分かんなかったよ。俺が余計好きになっただけだ。』
違う。
オレが聞きたいのはそんな台詞じゃ…。
『この際間男になろうが構わねえ』
兄貴はそれきり黙り込んで、じっと床を睨んでいた。
オレは兄貴の肩に頬を寄せる。
…実を言うとあの女のことは知ってた。旦那が行方不明のままになってることも。
だから高をくくっていたんだ。
”ウブな兄貴が、いつまでも間男なんて続けていられるはずがない”
”最後はオレの処へ戻るしかないんだ”、って。
間男ったって、可愛いもんだ。 想いも打ち明けられずに柵越しに喋るだけだったんだから。
それも、晴れの日だけ。
どうしたってオレの方が多くの時間を、濃密な時間を、共有出来るんだ。
…だがオレの予想は外れた。
『しぃさん。俺、あなたのことが好きなんだ。俺みたいな若造じゃ駄目ですか?』
ある日、兄貴はとうとう柵を越えようと彼女に打ち明けたんだ。
『……私がまだ夫を愛しているって、伝えましたよね?』
後家さんは兄貴から顔を逸らして、
『聞きました。いいんですそれでも』
そして、いつからかな。
兄貴が柵を越えてさ。
ますます気がおかしくなって。
どうも、外じゃなくて応接間にも通されてたみたいなんだ。
―――― サァアァァァァァ……
…皮肉なもんだ。
その頃になると兄貴は雨の日ばかり選んで出かけるようになった。
(雨の日は兄貴はオレの物だったのに)
人目に付かないようにさ。
オレはそんな兄貴が死ぬほど憎かったよ。
(兄貴が晴れの日を楽しみにしてたように)
(オレだって雨の日が楽しみだったんだ)
(兄貴はいつだってオレを見てくれない)
なあ、解るか。
(家にはいつもいる筈の兄貴が居ない)
雨が降る度にオレは夕飯の具を減らして買うんだ。
(オレはいつもいつも兄貴の事だけを考えているのに)
買い物籠に自分一人の飯しか入ってないってのは侘びしいぞ。
(オレの周りは薄暗い薄暗い雨ばかり)
そしてその度にオレは兄貴の姿を懸想するんだ。
(ざああ、ざああ)
今 部屋のどこに居るんだろう。
(どんなこと考えてるんだろう。)
あの女はどう応えているんだろう。
(どんな声出してるんだろう…兄貴は?女は?)
何やってるんだアイツら。
(笑い死にそうだから訊かねぇけど)
もしかしたらそれで愛を貫いてるつもりなのか?
薄い雨の幕に、妄想が映る。
ああいやだ、そんなものは見たくないんだ。
雨の音に包まれた応接室、
ソファの軋む音、
兄貴の背中、
そして、
(お気に召さないの?それではこうしてみたら如何)
笑いを含んだ女の声。
ソファの軋む音、
兄貴の背中、
雨の音、
雨の音、
雨の音
オレは雨の中座り込み、じっと雨の幕を見つめる。
『ま、悪くねぇかもな。それも。』
ふいに笑いがこみ上げる。
雨の幕に映る妄想。幻覚。
でも多分それが、現実なんだ。
……呪われろ。
ざああ、ざあああ、ざあああああ。
――――ザアァァァァァァァァァァ…
その日もオレは一人分の飯を準備して、一人で食事をしていた。
雨は強い。今日も兄貴はあの女の所へ行ったのだろう…オレを置いて。
あの幻想が頭をもたげてきそうになって、オレは無理矢理飯を飲み込んだ。
ばたん。
戸が開く音。
皿から視線を上げると、兄貴がずぶ濡れでフラフラと部屋に入ってきていた。
『…つー、つー。……しぃがいないんだ。知らないか。』
兄貴は雨に打たれて真っ青になっていた。
いや、兄貴を真っ青にさせているのは雨なんかじゃない。
―――― あの女。
『知らねぇな。そんな不愉快な名前の女は。』
オレは飯を飲み下しながら答えた。
雨が激しく屋根にたたき付けられて、俺の声は兄貴に届かない。
『しぃが俺に何も言わないで家を空けるはずがないんだ…。』
兄貴はふらふらと戸口に戻る。
背中もぐっしょりと濡れていて、兄貴が歩いた後は水たまりが出来ていた。
『何があったんだ…。』
兄貴が呟くと同時に戸が閉まった。
その日は土砂降りだった。
事情は飲み込めないが”何かあったらしい”と言うことは解る。
オレはあの女の為に体を濡らす気がサラサラ無かったんで、そのまま家で兄貴が帰ってくるのを待ってた。
水浸しになった廊下を見つめ、雨の中をかけずり回って居るであろう兄貴の姿を思い浮かべる。
『いなくなったのかあの女。どこかで八つ裂きにでもされてんじゃねーか』
ずたずたに切り裂かれたあの女を夢想する。
感慨が湧く前に、雨音にうち消された。
――――ザアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
雨は一層、酷い。
ガラスが水で覆われて外も見られない。
耳を澄ますと、雨音に紛れて兄貴の声が聞こえる、気がした。
ざあああああああああああああ
『しぃ!!!』
ざあああああああああああああ
『しぃどこだ!!!』
ざあああああああああああああ
『しぃ!!』
ざあああああああああああああ
(兄貴も馬鹿だろ。)
オレは、狂ったように降り続ける雨音を聞きながら、兄貴が作った水たまりを雑巾で拭った。
(あんなに取り乱しちゃってら。)
雨水は酷く冷たい。それも気にならないほどに乱れているというのか。
(ああいうのを”亡者みてーな面”っていうんだろうな)
よりどころのない酷く不安げな。そして酷く悲しそうな。
ざあああああああああああああ
可哀想に。
ざあああああああああああああ
(…オレが居なくなってもあんな顔すんのかな)
ざあああああああああああああああああああああ
すげぇ怖くなったから、その時のオレは考えるのをやめた。
―――― しぃがいないんだ
虚ろな目、真っ白になった顔、わなないた唇。
あれは、自分の半身を奪われると感じた恐怖の顔だ。
狂っている雨は、夜中中降り続いていた。
オレは眠りながら兄貴を待つ。
兄貴はまだ夜の雨の中を彷徨って居るんだろう。
オレは布団に入って、兄貴のことを考えないようにして、眠った。
考えると、またあの幻想を見るような気がしたから。
おかしいな。昔は、雨が待ち遠しくて仕方なかったはずなのに。
雨が降るだけで、落ち着いて眠る事も出来ない。
…ばたん。
戸が開く音でオレは目を覚ました。
相変わらず、雨が降っている。
よろよろと廊下を歩く足音。
『おっと、それ以上動くなよ。また床を濡らされちゃかなわねえ』
オレは顔だけ兄貴に向けていった。
兄貴は俺の声や顔なんて聞こえてないし見えてない。
全身ずぶ濡れで、それでも震えてなくて、ただただ呆然とそこに立っていた。
オレは起きあがり、用意したバスタオルで兄貴の体を拭いた。
兄貴は為されるがまま、身体も冷え切ったままタオルにくるまっている。
『おかえり、兄貴。』
夜が明けていたように思う。
兄貴は帰ってきた。
でも女は帰ってこなかった。
―――― シトシトシト…
執念深く雨が降っている。
俺は彼女の次の言葉を待った。
「なぁフサ。」
彼女は指先を見つめたまま俺の名前を呼んだ。
「正気と基地外の違いってどこにあると思う?」
独り言の様に彼女は呟く。
「俺の答えが必要なのか?」
「ああ。」
指先を見つめたままだ。俺の方を見てはくれない。
「そうだな…」
俺は彼女を見つめ、彼女の過去を見つめ、言葉を撰ぶ。
「戻って来れるか来れないかの違いなんじゃないか。」
そう、自分の心の中から。甘い幻想の中から。
雨の中で溶け出した境界線の向こうから…。
「そもそも生きている間、一度も狂わずに人生を終える人間なんているのか?」
俺は彼女を見つめたまま言う。
雨はしとしとと降り続いていて、僅か空気を震わせている。
―――― 俺の言葉は、つーちゃんに届いているのかな。
「酷く曖昧だと思うんだ、そう言うの。」
俺の言葉が終わると同時に、後ろで聞いていたのーちゃんが立ち上がった。
「つーさん、フサさん。茶ぁ淹れましょか。」
のーちゃんは俺とつーちゃんの顔を見比べながら、柔らかい声で言った。
「…二人ともお疲れですやろ。」
「お、おう。」
つーちゃんが照れたように顔を上げた。
「悪いね。」
「いえ、お安いご用ですわ。」
のーちゃんはにっこり微笑んで俺達…特につーちゃんの顔を注視した。
俺もつーちゃんを見つめる。
俺の答えへの返答は、あるのだろうか。無いのかもしれない。
彼女へ言葉は届いたのだろうか。
「それよりも…いらん口出しですけど。」
のーちゃんが笑顔を引っ込めて、つーちゃんに言った。
「今の話は町の衆には言わん方がええ。」
柔らかい声には変わりなくても、のーちゃんには珍しく厳しい口調だった。
「男と女の沙汰ですし、元々どないな事があってもおかしゅうないとは思います。
…せやけど、根も葉もない噂が好きな連中もおる。気いつけて下さいね。」
のーちゃんはつーちゃんの目をのぞき込んで、噛んで含むように言った。
彼女の言う通りだった。
もしこの話が外に漏れたらと思うと気分が悪くなる。
噂話はスキャンダラスで、悪意があるもの程あっという間に広がってしまうものだ。
…事実、ギコさんの異様な死に様は葬式の前に外に漏れていた。
のーちゃんは、す、と立ち上がり、湯飲みを持って台所へ向かっていった。
残された、俺と、彼女と、雨音。
絶えること無い雨音は、ふたりで居ても心細くなると言うのに。
独りで居たらどんなに寂しいことだろう。
―――― サァァァァァァ…
バス停は幾分か明るかった。
つーさんの家を出て、30分ほど歩いただろうか。
輪郭はハッキリと見える。闇は盲雨などでなく、モナーだった。
「ギコ君……自殺なんでしょうか。それとも殺されたんですかね?」
私は一緒に待つモナーに話しかける。
バスはまだ来ない。雨は少しだけ弱まったような気がする。
「気になる所だけど今は何とも言えないね。まあ、フサ君が後で何か教えてくれるんじゃない?」
そうだろうか。
つーさんを支える彼の姿が浮かんだ。
聞き出すことはあっても、私たちに話してくれるだろうか。
「…僕なんかは椎名夫妻の事件を思い出すけどなぁ。」
モナーは雨を見つめながら呟いた。
「椎名夫妻の事件ってあれですか。夫婦二人揃って行方不明になったっていう。」
その事件なら私も知っている。
モナーは振り向きもせず雨を見つめたまま、頷いた。
「そう。正確にはタイムラグがあってね。」
雨が、また少し強くなったような気がした。
強い闇がモナーの顔を覆い隠そうとしている。
水はさらりとしているのに、何と粘っこく見えることだろう。
「奥さんが四年前。旦那さんはもう六年も前になるか。」
雨に隠されたモナーが呟く。
「奥さんが行方不明になった後に椎名氏の遺体が見つかったんだが、
奥さんのしぃさんの方はまだ行方が掴めていないんだ。」
その人も雨に攫われたというのか?
「美しい人だった。生きてらっしゃるといいが……。」
バスの光が、雨の中を切り裂いた。
―――― シトシトシト…
雨の音にも少しだけ慣れたような気がする。
俺はお茶に口を付け、息を吐いた。
のーちゃんの淹れてくれたお茶は少しだけ俺の心をほぐしてくれたようだ。
暖かくて良い香りの液体は、体だけでなく心にも染みこんでくる。
「茶と茶菓子のおかわりもありますんで、おかわり欲しゅうなったら言うてや。」
相変わらず柔らかい声でのーちゃんは言う。
つーちゃんは無表情で湯飲みを包み込んでいる。湯飲みの中をじっと見つめていた彼女の、唇の端が、不意に、くぅ、と上がった。
それが笑顔…自嘲からくる笑みだと、俺はすぐに解った。
迷惑をかけている…とでも思っているのだろうか。
「つーちゃ…」
「のーの茶は美味ぇな!お茶請けにも合うぞ。」
俺の言葉は彼女自身の声で遮られてしまった。
場違いに明るい、いつもの彼女の声。
「オレと組んで料理屋とかどうよ。」
俺に声をかけさせないようにしている様だ。
「アホ言うたらあきませんわ~。お上手でんなぁ」
「いや、マジだぞ!オレとお前とで『肉茶屋』とか、受けるんじゃねーか。」
照れたように笑うのーちゃんに、つーちゃんは明るく答えた。
声も表情も明るいけれど、いつもの彼女のようだけれど。
そう、目の端や、口元、指先。
いつもの様に振る舞っていても、彼女の端々は訴えているのに。
悲しい、寂しい、泣きたい、って。
(つーちゃん。無理に笑うこと無いんだ。)
それなのに、明るく振る舞うなんて。
今まで話してくれた過去を忘れたいのか?
「そうだな。フサ、お前はカーペット用に毛だけよこせ。オレ様が綺麗に刈り尽くしてやるぞ。」
つーちゃんは俺に向き直って言い放つ。
ああ。やっぱり目許が暗い。
(泣きたいんだったら俺が抱きしめてやるから。)
そう、俺が。兄貴なんかじゃなく、俺が。
「返事しろ!」
笑いながら…いいや、笑顔なんかじゃない。口をゆがめて、つーちゃんは俺を小突くフリをする。
俺は返事を忘れて彼女を見つめた。
ああ。痛ましいよ。無理をしている彼女を見ているのは。
そりゃあ、つーちゃんが俺以外の男に惚れていたのは憎いよ。
俺じゃお兄さんの代わりにはなれない。
だけど…。
「イヤ、俺はこのフサフサが命だから。刈られると困るから!」
「オレ様に敵うと思ってんのかよ!」
いつものやりとり。いつもの彼女。
そう、明るくて、でもそれだけでなくて、俺は、彼女が。
俺以外の誰かに惚れていたとしても、俺がその人に一生敵わなくても。
彼女が俺の事なんて見ていなくても…。
そんなことで離れられるんだったら、俺だってこんなに苦しんだりしない。
「ありがとな。お前ら。」
つーちゃんは不意に目を伏せた。
「オレみてーな基地外のためによ。」
溜息と一緒に、独り言のように呟く。
基地外?戻ってこられないと言うことか?
それなら、彼女がそうなら、戻ってこられないのなら…。
「つーさんは基地外やないですわ!!」
のーちゃんの強い口調につーちゃんは顔を上げる。
「つーちゃんが基地外なら俺も基地外だよ」
そう、俺も、もう、戻れないんだよ。
雨で溶けだした向こう側から。
のーちゃんは青ざめて唇を噛み、俺とつーちゃんを交互に見やった。
「一度くらい本物の基地外になってみるさ。……おかしいか?」
そう、彼女と同じになれるのなら。
それも悪くないんだ。
―――― サァァァァァァァァァァ…
フサの言葉に、のーは青ざめたままオレ達を見ていた。
「ちょっとフサさん、基地外とか洒落にならんからやめて下さいよ。」
「俺は大真面目だよ?その方が救われることだって世の中にはあるんだからさ。」
フサは難しそうな顔で、のーじゃなく俺を見つめて言う。
ああ。なんだろう、フサの目は。何処かで見た事があるような気がする…。
オレはフサの目から逃れたくて、目をそらす。
のーはまだ何か言いたげな表情をしていた。
「兄貴といた頃は基地外とかそんなことどうでも良かったな…」
オレはのーの発言を邪魔するように口を開いた。
あの頃は基地外だなんてどうでも良かった。
ただ兄貴と居られれば、それで。
「話、してもいいか?」
二人は口を閉ざし、オレを見る。
ああ。雨音が少し大きくなった。
オレは、雨音に、兄貴の姿を思い浮かべる。
あの女が居なくなってから、兄貴は酷く落ちこんだ。
女が自分に何も言わずに消えたのが信じられなかったみたいでな。
オレの前では何も言わなかったけど、朝から晩まであの女の事考えてた。
廃人だったな。アレは。
『兄貴、飯こぼれてるぞ。』
オレがそう声をかけても、兄貴は虚空を見つめたまま。
パンくずがボロボロと兄貴の胸元を汚していた。
『兄貴!』
オレが手を伸ばして布巾を渡そうとしても、兄貴は気づかない。
ずっと虚空を見つめたまま。
記憶の中のあの女を…。
『こぼれてるっつってんだろうが!!人の話聞いてんのかよ!?』
オレは仕方なく兄貴の零した跡を拭いてやる。
オレの指が触れて初めて、兄貴は飯を零した事を…いや、オレが目の前にいる事に気づいた。
『へ?あ、悪ぃ。聞いてなかった。…ご馳走さん…。』
兄貴は上の空で立ち上がる。
ふらふらと戸口に向かう最中、小さな声であの女の名前を呼んだのを、オレは聞き逃さなかった。
あの女は消えてなお兄貴の頭の中を占領している。
兄貴はあの女ばかり見て、オレのことなんて。
目の前にいるのに。隣にいるのに。誰よりも長い間、オレは、兄貴を、思ってきたのに。
『オレは無視かよ!この糞馬鹿兄貴!!』
オレは湯飲みを戸口に向かって投げつける。
戸口から出ていった兄貴にむかって。兄貴を独占するあの女にむかって。
あの女のせいだ。
あの女が兄貴を惑わしてるんだ。
オレだけの兄貴だったのに。
あの雨の日からずっと、兄貴はオレを見てくれない!
粉々になった湯飲みの欠片が、日差しを受けて、ぎらり、と歪む。
…外はイヤになるくらい晴れていた。
ギコは土手の上を上の空で歩く。
『どうしちまったんだろうなあ。俺。』
頭の中は彼女の事でいっぱいだ。
妹のつーの言葉も、俺は聞き取れなかった…。
なあギコよ、そろそろ正気に戻らないか。
晴れ渡った空の中。頭の中の俺が語りかけてくる。
しぃが消えた理由だって、お前には解っているじゃないか。
彼女が多分戻ってこないこともさ。
あとはお前がそれを認めてやれば、済む話さ──。
俺は空から目をそらして、足下を見つめた。
少し汚れた胸元。ああ、つーをまた怒らせてしまった。
『たいへんだー』
前方から聞いた事のある声が迫っていて、ギコは顔を上げた。
町民のモナーが真っ青になってこちらへ駆けてくる。
『何かあったのか?』
『おおごとだ。早く警察呼ばないと。』
俺が声をかけると、モナーは真っ青のまま俺に言い放った。
『椎名さんの死体が裏山の森から出てきたんだ。』
…”椎名”?
俺の脳裏に浮かぶ、良く晴れた、あの庭。
柵の向こう側の婦人。
美しい笑顔、優しい声。
もしかして
大変だ、と叫びながら町の方へ行くモナーにそれ以上言葉をかける事も出来ずに、俺は走り出していた。
裏山の森。
死体。
椎名。
まさか、まさか。
目の前に町民の人だかりが迫っていた。
ざわざわと遠巻きに。目をそらす事も出来ない人の群れ。
『ひでえ。』
『もっと臭うかと思ったけど意外とそうでもないね?』
『あれは骨を喰った虫けらの匂いだろ。』
『何故こんな所に死体が……。』
人の群は口々に囁き合う。
その声は不愉快に空気を震わせて、俺はその振動を乱すように人の群に分け入った。
『どいてくれ!!知ってる人かもしれないんだ』
椎名と言う名前。
どうか、いや、死体でも良い。行方を…。
俺の前に、群で隠された死体が晒される。
『きみ、椎名さんと知り合いなのか?』
群の一人が口を利いた。
『”この人はやっぱり椎名さんだと思う?”』
目の前の人。
いや、人と言うにはあまりにも…。
『誰だ?この骨は?』
すっかり肉がそげ落ちた、木片のような死体。
かろうじてボロのような着物を纏っている物の、所々身体のパーツがこぼれ落ちて、これでは一体誰なのかすら…。
『着物に名前が刺繍してあったんだ。ほら、二年前に行方不明になった椎名氏だよ。そんな感じしないか?』
群の声で、不愉快な振動がまた始まる。
他人事の、憶測。
『……悪いが旦那の方は面識がねえ。俺はてっきり奥さんかと……。』
俺は死体から目がそらせないまま、うめく。
ああ。俺が会いたいのは旦那なんかじゃない。
彼女はどこへ行ってしまったんだ。死体でも、なんでもいいんだ。彼女に、一目…。
ざわ、ざわわ、ざわわわ。
『なあ、そう言えば椎名さんの奥さんも最近行方しれずなんだよな』
『うん。僕もその噂聞いた。』
『あの旦那、浮気してたんだろ?』
『そんな噂もあったね。』
『この状況で考えられる事ってそんなにないぞ。』
噂、噂、噂。彼女の姿が噂で縁取られて、曖昧にぼやけていく。
『まさか奥さんが旦那さんを殺してそのまま逃げたんじゃ…。』
その言葉が妙にクリアに、俺の耳に入ってきた。
目の前が、歪む。
音が…。
ざあああああああああああああ
これは、雨音?
『おい』
俺の口が独りでに動く。
『誰だ今喋った奴。取り消せよ。』
違う。彼女は。そんな人じゃない。
――――…でも、私まだあの人のことを好きなの……内緒よ。
あの人は、そう、心から。
『お前か?あ?お前か?』
俺は声の主の胸ぐらにつかみかかった。
ギリギリとシャツをねじ上げる。
『く、苦しい…』
『しぃがそんな酷い真似するわけないだろ!!』
そうだ、彼女は旦那さんを愛していたんだ。
俺なんて、初めから
『しぃは……しぃは……!!』
俺に胸を締められて、男は苦しそうにもがき、咳き込んだ。
『そういう君こそ、人様の奥方を呼び捨てにして何様のつもりだ!?
君と奥さんは一体どううい関係だったんだね!?』
男の蔑むような視線。
青ざめた群、噂、憶測、不愉快な振動。
ざわ、ざわざわ…。
俺は声高に叫べない。
俺は初めから、あのひとには…
『……別に大した関係じゃねえよ。ただ、あの人は清らかだった。』
俺なんかが触れたらいけないくらいに。
…だから、俺はあの人が。
『それだけは言っておくぞ。』
蔑みの視線と、噂話から逃れるように、俺はその場からそっと離れた。
空は晴れている。
俺は口の中で彼女の名前を呼んだ。
世間から隠れるようにして、他人の女を愛して、何になると言うのか。
叫んではいけないことなのだ。
俺はこの心を人に叫んではならない。
(ああ。あの雨の日。)
(雨の日が待ち遠しい。)
俺は現実に引き戻される空恐ろしさの中で、逃げるように彼女の側で過ごした日々を思い出す。
(雨の中。俺は、彼女と共に。)
『兄貴、飯こぼれてるぞ』
幻想の中、つーの声が聞こえる。
『兄貴!』
俺を呼んでいる…?
『……。』
俺は、ふ、と隣を見た。
『戻って来いよ…。』
つーが震える声で俺に訴える。
強気につり上がっていた瞳から、液体がはらはらとこぼれて…。
『うお!?何で泣いてんだお前?』
『わからないのか?本当にわからないのか?』
つーは俺に縋り付く。
ぼろぼろと溢れる涙を拭う事もなく。
『あの女はもう帰ってこねえよ!いい加減、目ぇ覚ませ、馬鹿兄貴。』
つーの口からこぼれる現実。
俺が彷徨う妄想の中。
俺の頬を伝い落ちる雨粒か、
つーの頬を伝い落ちる涙か、
どちらが現実か、
狂ったように繰り返す
永遠にこの日常が繰り返される
街の人たちが居て
つーが居て
そして
―――― ザアアアアアアアアアア…
その日も、あの女が消えた日みたいに酷い雨だった。
オレは高熱を出して、一日うなされていたんだ。
『お前が風邪なんて珍しいな。』
すぐ隣でオレを看病し続けていた兄貴の顔が、ぼんやり見えた。
兄貴の声を、雨音が邪魔をする。
『薬、買ってくるか?』
『…行かないで』
オレは夢中で兄貴の手に縋り付く。
雨は嫌だ。
こんな雨の日は嫌だ。
雨は…。
『兄ちゃんここにいて…外、雨降ってる…』
熱に浮かされて声が震える。
背筋を悪寒がゾクゾクと駆け抜けていった。
熱だけのせいじゃない。
雨音が、雨音がオレを不安にする。
『お願い…』
オレは兄貴の手を精一杯握りしめた。
見つめているつもりなのに、兄貴の顔がぼやけてしまう。
そんなオレを見て、兄貴は可笑しそうに笑った。
『何必死になってんだよ。大丈夫だって。二・三日もすりゃ治るだろ。』
そうじゃない…。そうじゃないんだよ…。
嫌なんだ。雨は。雨が降ると兄貴はあの女に取り憑かれてしまう。
『いいから心配しないで寝てろ。な。』
兄貴は優しくオレの頭を撫でる。
兄貴、今はオレだけを見てくれてるのか…?
『――――うなされてんだよ。お前は。ほうら、早く寝ちまえ。』
オレは手の力を少し緩める。
兄貴の掌。兄貴の声。
ゆっくりと熱が意識をむしばんでいく。
『そう。いい子だ。よし…』
兄貴の声が遠くなっていく。
なのに。なのになんで。
雨音だけは耳元で…。
ああ。雨は嫌だ。兄貴があの女を思い出す。
オレを見てくれなくなるから…。
ざあ、ざああ、ざあああ…
『なぁ、つーよ。お前だけには憶えておいて欲しいんだ。』
遠くで兄貴の声が聞こえる。
『兄ちゃんはさ、誰にも言えなかったけどあの奥さんを本当に大切に思っていたんだ。』
『でも俺だけは知っている。』
兄貴の掌…嫌だ、嫌だ、離さないで。
『あの奥さんは行方不明になったけど、たぶんもう生きていないだろう。』
近くにいて。あの女の事なんて…。
『あの奥さんはメクラアメに誘われて旦那の所へ逝っちまったのさ。』
雨…メクラアメ。
あの日も酷い雨だった。
人を誘う雨。愛しい人を連れ去る雨。
雨は嫌だ。雨は兄ちゃんをオレから取ってしまうから…。
『最後まで俺と旦那との板ばさみで苦しんでいた。
でも、待っていてもあの世から人は来ないから奥さんは仕方なく俺を側に置いた。
オレはそれで良かったんだ。』
そんな話は聞きたくないんだ。
違うんだ。兄貴、オレはただ…。
『お前はずいぶん怒ってたみたいだけどさ。いつか、解ってくれよな。』
違う。
オレはただ怒ってただけじゃなくて。
オレだけを見て欲しくて。
あの女の事なんか…!
『奥さんもきっと旦那とうまくやってるし、化けて出たりはしねえだろうさ。』
あの女が化けて出るんじゃないんだ…。
兄貴、兄貴は今でもあの女を…?
『薬買ってくるから大人しく寝てろよ。』
嫌だ、いやだ。行かないで。
近くにいて。今日は雨の日だよ。
あの女に…。
兄ちゃん…。
――――…ザアアアアアアア…
雨を進む兄ちゃんの後ろ姿。
激しくたたき付ける雨は、真っ黒なカーテンのようだ。
ざああああああああああああああああああああ
兄ちゃん。兄ちゃん戻ってきて。
雨は嫌だよ。この雨は…。
ざああああああああああああああああああああ
闇の中で兄ちゃんは振り返る。
そう、そのまま戻ってきて、兄ちゃん…。
―――― …学生さん。
ざああああああああああああああああああああ
どこを見ているの、オレの所へ帰ってきてよ…。
ああ そこは
兄ちゃん…。
あの女に
ざああああああああああああああああああああ
『…!』
オレは布団の中で目が覚めた。
汗でぐっしょりと布団が濡れてしまっている。
頭はクラクラとしたままだ。熱が上がったのかも知れない。
オレはガバリと起きあがって部屋中を見回した。
居ない。
『…兄貴。』
家の中は気配も、音もない。
あるのは
―――― ザアアアアアアアアア…
オレは布団から這い出ようとする。
身体中に熱が駆けめぐって、足が言う事を聞かない。
身体が壊れたように震え出す。
寒い。怖い。雨が。雨が。
『…まだ帰ってこねえのかよ。』
声が出ない。
寒い。雨音がオレを壊しに来る。
『…こんな日に…外に出るからだ。雨は嫌なんだよ。怖くなるから。』
たたき付けるような雨。
あの日と同じ。あの女が消えた日と同じ。
兄貴。
兄貴は。
―――― あの奥さんはメクラアメに誘われて旦那の所へ逝っちまったのさ。
雨…。
メクラアメ。
片割れを連れ去る雨。
暗闇。
あの女が消えた日と同じ…。
兄貴は居ない。
『オレが「苦しい」って言ってるんだ!こんな日ぐらい側にいてくれよ!』
雨音をかき消すように叫ぶ。
ああ 苦しい。胸がつぶれてしまいそうだ。
喉の奥から塩辛い液体がこみ上げる。
熱が身体中を浮き立たせる。
兄貴。兄貴。
どこにいっちまったんだ。
あの女が あの女が…!
『オレを置いて行くなああああああああああああああああああ!!!』
ザアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
オレの叫び声は、強くなった雨音にかき消されて、届かなかった。
結局、次の日になっても、その次の日も、兄貴は帰ってこなかった。
傘だけだ。残ってたのは。
オレはそれで何が起きたのか理解したよ。
―――― シトシトシト…
つーちゃんが語り終えても、しばらくは口をきけるような空気ではなかった。
のーちゃんはつーちゃんを見つめながら、ゆっくりと瞬きをした。
つーちゃんの頬は、はらはらこぼれる涙で濡れている。
雨音に、兄貴を思っているのか。
「つーちゃん、ありがとう。話してくれて。」
俺が声をかけると、彼女は両手で顔を覆ってうつむいた。
肩が小刻みに震えている。
ああ。良いんだよ。無理をしないで。泣きたいだけ泣けば良いんだ。
俺がいくらでも抱きしめてやるから…。
「今晩、一人で大丈夫か? 雨降ってるけど。」
ビクリ、と肩が震えて、彼女は顔を上げた。
「オレは大丈夫だよ!何を今更…」
さっきまでとはうって変わって、明るい声で彼女は言う。
つーさん、とのーちゃんが小さく呼ぶのを遮るように、彼女は明るい笑顔で続けた。
「この三年間、オレはずっと一人暮らしだったんだぜ?」
嘘だ。
つーちゃんは一人なんかじゃなかったんだろう。
この三年間、ずっと兄貴を待ち続けていたんだろう。
頬に残った涙が、てらてらと輝いている。
「帰れよ。気持ちだけ貰っといてやるからよ。」
つーちゃんはそう言いながら俺達を急かした。
彼女に撲たれた指先が、しくり、と痛む。
痛ましいよ。今日からは、本当に、一人きりなのに。
つーちゃんは玄関に立った時には、もう元通りの顔になっていた。
「じゃあな。気をつけて帰れよ。」
いつも通りの声で彼女が言う。
もしかしたら一人になりたかったのかも知れない。
逆に一人になるのが怖かったかもしれない。
俺は、つーちゃんの気持ちがどちらなのか読みとる事が出来なかった。
つーちゃんの姿を痛々しいと思いながら、俺はその晩、つーちゃんの家を後にした。
―――― サァァァアァァァァ…
俺は迷う。
陰気な雨がいつまでも降り続いて、俺を妄想の中に誘っている気がする。
雨の夜道は暗い。
すぐ目の前の闇が、まるで映画のスクリーンのように、俺の妄想を映し出す。
つーちゃんをそっと抱きしめる。
泣かないで。悲しまないで。
自分だけ向こうに行かないで…。
甘く甘く、そして頭を締め付ける妄想。
もう誰もいないじゃないか。
二人で、閉ざされた世界で狂わないか。
つーちゃんの心の中には誰が居るんだろう。
俺ではない、誰か。
それともお前はまだ
存在のない男を愛しているのか?
つーちゃんの兄貴。
メクラアメに攫われた兄貴。
つーちゃんを最後まで見ようとしなかった男。
死んだ男を?
彼女の心に俺は居ない。
彼女の兄が彼女を見なかったように
彼女もまた俺を見ていない
ああ。雨の幕がゆらゆら揺れて、妄想が掻き消える
消えないで、現実になって
「…さん、フサさん!」
掻き消えた妄想の先から、のーちゃんの声がした。
すぐ隣の闇から、傘を差しだして、俺の顔を覗いている。
「何や、怖い顔しとりますなぁ…。気ぃつけんと道に迷いまっせ。」
雨音にとけこむような、柔らかな声。
ああ。駄目なんだのーちゃん。俺はもう
のーちゃんの背後の雨が揺れる。
ふわりと立ち上がる妄想。
お前が居なければ俺にとって この世は闇。
ゆらゆら揺れる雨間をぬって、少し明るいバス停についても、俺の妄想は雨に支配されていた。
「……ほな、うちはこれで。」
「ああ。」
のーちゃんを乗せたバスが遠ざかる。
闇がひたひたと辺りをむしばんでいる。
さああ、さあああ…
薄暗い、薄暗い、雨。
立ち上がったまま消えない妄想。
目をこらしてバスの時刻表をのぞき込む。
本当に俺はこのまま帰っていいのか?
(雨はまだ止みそうもない)
正気に戻るべきか?
(つーちゃんは一人で泣いているんだろうか)
たとえ正気に戻ったところで首輪のように締め付けてくる想いをどうしようもないんじゃないのか?
(俺は彼女の事しか考えられないのに)
雨が誘う妄想の世界から逃れられないんじゃないのか?
(兄貴を思う彼女も彼女を思う俺も)
背後の雨がさわさわと揺れている。
俺を誘っているのか?それとも
彼女を迎えに行こうとしているのか?
俺はゆっくりと彼女の家に足を向けた。
ぱしゃ、ぱしゃと足下の水が跳ねる。
その音で雨をかき消すように、俺はいつの間にか走っていた。
ぼんやりと明かりが近づいてくる。
「つーちゃん!つーちゃん勝手に戻ってごめん。」
玄関は開いていた。
俺は戸口で彼女に向かって声をかける。
返事の代わりに、雨音が響いていた。
「上がるよ。」
薄暗い部屋。
線香の香り、じっとりと重い空気。
雨音がそれを何倍にも重くしている。
つーちゃんは部屋の中、布団も敷かずに眠り込んでいた。
俺は彼女にそっと近づき、のぞき込む。
――――骨壺…?ギコさんの骨か。
彼女は白い小さな壺を抱きかかえるように眠っている。
「つーちゃん、風邪ひくから。…つーちゃん。」
低い声でささやきかける。
彼女は目を覚ます気配もなかった。ただ、壺を抱きしめて眠り続ける。
目許に涙の粒が光っていた。
泣きながら、眠ってしまったのだろうか。
「…。」
俺は彼女の隣に身を横たえて、そっと抱き寄せた。
彼女の肌はすこしだけ冷たい。それを温めるように、身を寄せる。
悲しげに沈んだ目許。きらきらと光る雫。
俺はそっと目を閉じて、彼女に頬を寄せた。
―――― つーちゃん。
彼女の肌は冷たい。
―――― もう一人で眠るの止せよ。
ああ。痛々しいんだ。つーちゃん。
―――― つーちゃんの心にはギコさんが一緒に眠ってるのかも知れないけれど、
雨音が強くなっていく。
―――― 俺にはつーちゃんが独りぼっちに見えるんだ。
それは幻?現実?
俺が側にいるの、わかるか?
雨音が聴こえるかい?
つーちゃん、つーちゃんは俺を許してくれるか?
自分がまともかも解らなくなっている俺を───────俺を
―――― ザアアアアアアア…
いつの間にか眠り込んでいたようだ。
ぼんやりとした暗闇。
隣に確かに感じる体温。
ああ。一人じゃないんだ。
『……奥さんもきっと旦那とうまくやってるし、化けてでたりはしねえだろうさ。』
ああ。一人じゃない…。隣に居てくれるから…。
『薬買ってくるから大人しく寝てろよ。』
いやだ、いやだ、いかないで。はなれないで。ああ…。
「!」
冷や水をかぶったように目が覚める。
薄暗い部屋。
たたき付けるような雨音。
そう、あの日と、同じ。
隣に感じる体温は…。
「…あ……」
声が震える。
ああ。離れないで。
なんで。何でフサが?いや、そんなことより…。
「…にいちゃん…!」
声が震える。あの日と同じ。
震えた叫び声で目が覚める。
線の細い彼女の肩。たたき付けるような雨音。
掌の中でごとりと動く壺。
壊れたように震える彼女。
ああ。壺が。
兄ちゃんはもういない。
そうだ。
兄貴は骨になってしまった。
飛び起きる。
ぽろぽろとこぼれる彼女の涙。
壊れたように震えて…雨音がその上に…。
いやだ。
そんなのいやだ。
骨になったなんてイヤだ。
置いていってしまうなんていやだ。
もたれかかった先から見上げた彼の顔のライン。
掌。声。
後ろ姿…。
「兄貴。何処行っちゃったんだ。」
声を張り上げる。
雨音が。ああ。雨音が。
あの日と同じなんだ。
闇に向かって叫ぶ彼女。
「あの日」を思い出しているのか?
「こんな、こんな骨…。」
違う、こんなのは兄貴じゃないんだ。
兄貴は、兄貴は
「 兄貴…!! 」
がしゃん、と壺を放り出す。
蓋が外れて中から灰褐色の粉がこぼれた。
こんな粉じゃない。兄貴はこんな粉じゃない。
兄貴はこんな壺に入ってなんかない。
兄貴は、兄貴は。
「つーちゃん!」
放り出された壺からギコさんの骨がこぼれだした。
死者の骨。
彼女を最後まで見なかった男の。
雨に攫われた…。
兄貴は雨の中に居るんだ……!!
壺を省みず彼女は雨に飛び出していく。
たたき付けるような雨の所為で、外は真っ黒なカーテンを引いたようだ。
禍々しい。
ああ。駄目だ。あの雨は駄目だ。
「つーちゃん何処行くんだ!」
傘を取りながら彼女の名前を呼ぶ。
「つーちゃん!つーちゃん…!」
俺の声は届かないのか?
雨
メクラアメ メクラアメ
愛した男が帰らない
奥方は雨に寄り道
学生は蛙に騙された
娘は雨から出たくない
想い人のすべてを攫うは
憎らしや
* * * *
空気がまとわりつくような、そんな夜だった。
湿気を含んだ空気に線香の煙が立ち上る。休む間もない雨音を縫って、住職の低い読経が響いていた。
ここ数週間休むことなく続いた雨で、町の外れにあった溜池が溢れた。用水路につながっている水門が泥で詰まって、水抜きの役割を果たしていなかったからだ。
晴れ間を選んで若い男達が池の泥をさらった。
――――最初は木かと思ったんですよ。
「彼」をすくい上げた男は血の気の失せた顔で呟いたという。
「池の底から白骨死体で出てきたんでしょ? ギコ君。」
葬式の終わり、雨音に紛れた噂話が聞こえる。
「どうもそうらしいんですよ。行方不明になってからもう三年。」
「恐ろしいことになったものだ…」
部屋の隅で囁かれる噂話は、当然俺の耳にも入っていた。そして、勿論
「つーちゃん!お兄さんのこと、その、あの、大変だったな。」
俺のすぐ隣で、喪主のつーが肩を落としていた。当然囁き声も彼女の耳に入っていることだろう。
彼女は心持ち青ざめ、組んだ指をじっと見つめているだけだ。
いつもピンと伸びている背筋も、引き締まった目許も、笑みを浮かべている口元も、全てが陰鬱な悲しみで覆われている。
囁き声の主は決まり悪そうに彼女を横目で見ていた。
「俺、何て言っていいか…。」
「《メクラアメ》だ」
「え?」
「兄貴だよ。あの時もひでぇ雨が降ってた。メクラアメに攫われたんだ。」
唇を殆ど動かさず、うめくように彼女は呟いた。
組んだ指に力が込められて真っ白になる。
目の縁に見る見るうちに涙が溜まり、唇が引きつるようにわなないた瞬間に、零れた。
「あの女が兄貴をたぶらかしてあの世に連れてっちまったんだ!」
「つ、つーちゃ…」
「あんなに『つれてかないで』って…頼んだのに…!」
彼女は大きくよろけ、支えた俺の肩に額を当てて泣きわめいた。
支えた彼女の肩は驚くほどに細くて、しゃくり上げるたびに震えている。今すぐにでも壊れてしまいそうなほどに。
葬儀に訪れた友人達も、手伝いにきたのーちゃんも、皆、可哀想な喪主…死者の妹を見つめていた。
「つーちゃん…」
俺は支える腕に少し力を込めた。
あの池さらいで、つーちゃんの兄貴…ギコさんの骨が出てきたのが数日前。
何故池の底で死んでいたのかは解らない。
ギコさんは三年前から行方不明になっており、家は妹のつーちゃんが一人で守っていた。
――――メクラアメに攫われたんだ。
盲雨は、引き裂かれた男女が 迷って抜けられなくなる雨だと言われている。
暗闇から消えたかたわれが相手を呼ぶ。
そしてそれに応えると、応えた方は”向こう側”へ行って、
二度と帰ってこないそうだ。
「……。」
ああ。彼女は。
お兄さんのこと大好きだったんだな…。
俺の肩の上で泣き続ける彼女の顔を見て、俺は目眩がした。
彼女の流している涙は、彼女の為でも、勿論俺の為でもなく、彼女の兄貴の為に。
彼女が好きなのは、多分俺じゃなかった。
だけど、俺はつーちゃんが好きだった。
気が、おかしくなるほどに。
それを突きつけられたようで、俺は…。
―――― ザアアアアアアアア…。
「おや、雨が強くなってきましたね…」
「私たちはそろそろ…」
私はそう言って腰を上げた。
目の前で喪主である妹御が泣き崩れている。
それを支えている彼女の友人であるフサ君も、何かに憑かれたかのような陰鬱な目で、仏壇を睨み付けていた。
非常に気まずい空気を、線香の香りと雨の音が更に際立たせていて…。
―――― このままだと私も連れて行かれそうだ。
横を見ると、友人のモナーも苦い顔をしている。
葬式というのは、嫌だ。全てが重くまとわりついて、境界が曖昧に惚けてしまいそうになる。
「ああ、モナーはんもモララーはんも、雨が強ぅなってますさかいに、お気をつけて。」
葬式の手伝いをしていたのーが玄関口まで見送りに来て、言った。
奥の部屋ではまだすすり泣く声が聞こえていた。
外は闇に包まれて、雨音だけが響いている。
線香の香りの代わりに、泥臭い匂いが鼻先をかすめた。
「…それにしても、良く降りますね。」
前を行くモナーに声をかける。
「そうですね。じとじとじめじめして、食べ物も腐りやすいし薄暗いし、」
モナーは歩く速度を私にあわせながら、すこし間をおいた。
「…僕たちも気をつけないと攫われちゃうかな」
雨音が少し大きくなったような気がした。
雨の夜道は明かりがない。
油断すると隣にいるのがモナーなのか、誰なのか、解らなくなってしまう。
「盲雨《メクラアメ》なんてのはね、要するに人の心の惑いを例えたものなんですよ」
私の隣の闇が口をきく。モナーの輪郭はぼやけて、もう声しか聞こえない。
「”迷わない”と思っていれば捕まらないものです」
「またまた」
私はかろうじて合いの手を入れた。
メクラアメ。メクラアメなんて…。
―――― 兄貴はメクラアメに…
「そもそもウチらは盲雨なんて見た事無いじゃないですか。」
私は闇夜で薄く笑った。
そうだ、私はそんな雨には未だ遭ったことがない。
どのような物かなどとも考えたことも。
それは普通の雨なのか。例えば今、夜空を濡らしているこの雨の様な…?
「もしかしたら本当に雨が人を攫うのかもしれませんよ」
クック、と喉で笑うような声が隣の闇から聞こえた。
「ギコ君を攫ったのは果たして誰なんでしょうねぇ…」
―――― シトシトシトシト…
目の前で彼女は目を赤く腫らし、肩を落として座っていた。
参列者も手伝いの人も殆どが帰り、今、彼女の家には俺とのーちゃんの3人だけだ。
「…つーちゃん。」
俺は出来る限り優しく彼女に声をかける。
「もしつーちゃんが辛くなかったら、話訊いてもいいか。」
彼女はどろりと疲れた瞳を俺に向けた。
「…『あの女』のあたりか。」
「…、そう。」
俺は彼女の瞳を見返しながら頷いた。
――――あの女が兄貴をたぶらかして
あの時確かにそう泣き叫んだ。つーちゃんは興奮していて声は不明瞭だったけれど、俺が聞き違えるはずはないんだ。
彼女は俺の視線から逃れるように、膝の上に置いた指先に視線を落とした。
瞳が潤んでいる。
「…俺が話すと長ーぞ。」
「いいよ。一晩中でも、聞くから。」
俺は自分に言い聞かすように言って、彼女の顔をのぞき込んだ。
時間は惜しくない。彼女の話が聞けるのなら。
彼女の、伏せた瞳からはらはらと涙がこぼれて、頬を伝っていく。
「オレは、あの女が、憎い。ひでぇこといっぱい考えてる。きっと、オレのこと、見捨てたくなる…」
「ならない!!」
俺は思わず声を張り上げ、彼女の方に膝をつめた。
弾かれたように彼女は顔を上げて、涙がパラパラと空を舞った。
―――― 雨粒のようだ。
「俺が」
俺は彼女の指に手を伸ばす。
「俺がつーちゃんを見捨てるわけないだろ…」
呟きながら、す、と彼女の指に自分の指を重ねて
――――バシィ!!!
俺は呆然と彼女の顔を見つめた。
彼女は自分の指を握りしめ、怯えた瞳で俺を見ている。
「………やめろ、気持ち悪い」
青ざめた顔で、震える唇で、彼女は言い放った。
それは悲しみと言うより、驚きと言うよりも、
―――― 強い嫌悪。
…ああ。
やっぱりつーちゃんが好きなのは俺じゃないのか。
俺は自分の指先を見つめる。
やめてくれ。そんな瞳は…俺には耐えられない。
俺は、俺はつーちゃんが好きなのに。
つーちゃんしか俺の心にはいないのに。
お前の心にいるのは、誰なんだ?
自分の手の先にある、彼女の細い膝。
小さく震えていて…。
……いかんいかん。
俺はぶるぶるっと首を振った。
一瞬よぎった強い憎悪。それを振り払うように。
「悪かった。続きを聞かせてくれよ。」
彼女は震える肩を抱きながら、俺を見返した。
―――― シトシトシトシト…
ああ、雨がまだ降っている。
オレは雨が嫌いなのに。雨は悲しいから嫌いなのに。
オレはフサを撲ってしまった指をさすり、口を開いた。
…雨の記憶。
「……兄貴は、生きていた頃、近所の後家さんと出来ていたんだ…」
その女の旦那は死んでたのかどうかわかんなかった。いなくなっただけだったから。
兄貴が勝手に後家さんだって決めつけたんだ。
兄貴は毎日決まって彼女の家に行って、庭いじりをしている彼女を眺めていたんだ…。
『学生さん。さっきからご覧になってるみたいですけど、何か御用かしら?』
『え? あ、ああ違うっす。庭です。庭を見ていたんです。』
兄貴はしどろもどろになって、後家さんから目をそらした。
日差しが降りそそぐ、手入れの行き届いた庭。
『…綺麗だなと思って。』
兄貴はやっとの事でそう取り繕ったそうだ。
もちろん、庭なんて見ちゃいない。見ていたのは後家さんさ。
『若いのに庭が好きなんて珍しいひとね…。』
後家さんは微笑みながらそう返したそうだ。
その人は、かなり年上だったんだと思う。兄貴には関係なかったんだろうけど。
それから兄貴は、晴れた日には女の庭に通い詰めていた。
雨の日は…。
『ありゃあ絶対未亡人だ!』
居間で座り込み、兄貴はでかい独り言を呟いていた。
じっとりとした嫌な雨が2~3日続いていて、その間兄貴はあの女の家にも行けず、ずっとオレと一緒にいた。
『アヒャ、馬鹿兄貴がトチ狂いやがったな』
オレは兄貴にお茶を出しながらせせら笑い、兄貴の口まねをする。
『ああ、今日は災難だ。何故雨が降る。彼女の庭へ行けない……ってか』
『何で解るんだ』
兄貴がむっとして振り返った。全く反応が子供じみている。
オレは笑い出したくなるのを堪えて、澄ました顔で続けた。
『一昨日も同じ事言ってたぞ』
兄貴は口をゆがめて、オレの淹れた茶を一口飲んだ。
オレは兄貴のすぐ隣に腰を下ろして顔をのぞき込む。兄貴の隣はオレの定位置だ。誰にも譲らない。
ここは兄貴に一番近しい奴が座るべきなんだ。
兄貴はちらちらとこちらを伺い、口を開いた。
『だってよ。何もない庭に行くなんておかしいじゃねえか。』
兄貴は湯飲みを持ったままそう反論する。
ああ。それならば雨がずっと降っていればいい。オレは幾度となく思っていた事を考える。
この世は雨に包まれて。そしてその中はオレと兄貴だけ。
そう、雨の日、兄貴はオレだけの物だから。
『兄貴は庭が好きなんだろ?庭だけ見に行けよ。』
そんな考えなどおくびにも出さずにオレは言う。
あの女なんかに会いにいかなくったってオレが居るんだ。
兄貴はお茶を飲み干し、渋い顔をしてオレから顔を逸らした。
『あんまり余計なこと言わすなよ…』
オレは兄貴の背中にもたれかかる。頬に兄貴の体温が伝わってくる。
雨の日に、あんな女なんか入るスキはない。
『目を覚ませ。相手は人妻だぞ。』
もたれかかった先から見上げた、兄貴の顔のライン。
むっと唇をつきだして考え事をしている。きっと、あの女のことだ。
オレは少し腹立たしくなった。今日は雨なのに。あんな女はいないのに。
オレは兄貴のことしか考えてないのに。
『大体旦那だって本当に死んでんのか??』
注意をこちらへ向けようと無理矢理話しかけた。
女の事なんて考えるな。今ここに女は居ないんだ。今ここにはオレしか居ないんだよ。
兄貴は目線をちらっとこちらへ投げかける。
『そう、そこなんだ。俺は彼女にそこんとこを尋ねた』
そのまま兄貴は上の空になってしまった。
目線は、兄貴自身の足。でもそんなものきっと見えてない。
兄貴が見ているのは、
―――― あの人は盲雨に捕まってしまったわ。…他に誰か忘れられない人が居たのね。
―――― でも、私まだあの人のことを好きなの……内緒よ
『何黙ってんだよ!尋ねてどうなったんだ?』
オレは視線を邪魔したくて兄貴の身体を揺すった。
『……。』
早く聞かせろ、とさらにせっつく。
兄貴は足から空の湯飲みにかろうじて視線を上げ、また足先に視線を戻した。
『…分かんなかったよ。俺が余計好きになっただけだ。』
違う。
オレが聞きたいのはそんな台詞じゃ…。
『この際間男になろうが構わねえ』
兄貴はそれきり黙り込んで、じっと床を睨んでいた。
オレは兄貴の肩に頬を寄せる。
…実を言うとあの女のことは知ってた。旦那が行方不明のままになってることも。
だから高をくくっていたんだ。
”ウブな兄貴が、いつまでも間男なんて続けていられるはずがない”
”最後はオレの処へ戻るしかないんだ”、って。
間男ったって、可愛いもんだ。 想いも打ち明けられずに柵越しに喋るだけだったんだから。
それも、晴れの日だけ。
どうしたってオレの方が多くの時間を、濃密な時間を、共有出来るんだ。
…だがオレの予想は外れた。
『しぃさん。俺、あなたのことが好きなんだ。俺みたいな若造じゃ駄目ですか?』
ある日、兄貴はとうとう柵を越えようと彼女に打ち明けたんだ。
『……私がまだ夫を愛しているって、伝えましたよね?』
後家さんは兄貴から顔を逸らして、
『聞きました。いいんですそれでも』
そして、いつからかな。
兄貴が柵を越えてさ。
ますます気がおかしくなって。
どうも、外じゃなくて応接間にも通されてたみたいなんだ。
―――― サァアァァァァァ……
…皮肉なもんだ。
その頃になると兄貴は雨の日ばかり選んで出かけるようになった。
(雨の日は兄貴はオレの物だったのに)
人目に付かないようにさ。
オレはそんな兄貴が死ぬほど憎かったよ。
(兄貴が晴れの日を楽しみにしてたように)
(オレだって雨の日が楽しみだったんだ)
(兄貴はいつだってオレを見てくれない)
なあ、解るか。
(家にはいつもいる筈の兄貴が居ない)
雨が降る度にオレは夕飯の具を減らして買うんだ。
(オレはいつもいつも兄貴の事だけを考えているのに)
買い物籠に自分一人の飯しか入ってないってのは侘びしいぞ。
(オレの周りは薄暗い薄暗い雨ばかり)
そしてその度にオレは兄貴の姿を懸想するんだ。
(ざああ、ざああ)
今 部屋のどこに居るんだろう。
(どんなこと考えてるんだろう。)
あの女はどう応えているんだろう。
(どんな声出してるんだろう…兄貴は?女は?)
何やってるんだアイツら。
(笑い死にそうだから訊かねぇけど)
もしかしたらそれで愛を貫いてるつもりなのか?
薄い雨の幕に、妄想が映る。
ああいやだ、そんなものは見たくないんだ。
雨の音に包まれた応接室、
ソファの軋む音、
兄貴の背中、
そして、
(お気に召さないの?それではこうしてみたら如何)
笑いを含んだ女の声。
ソファの軋む音、
兄貴の背中、
雨の音、
雨の音、
雨の音
オレは雨の中座り込み、じっと雨の幕を見つめる。
『ま、悪くねぇかもな。それも。』
ふいに笑いがこみ上げる。
雨の幕に映る妄想。幻覚。
でも多分それが、現実なんだ。
……呪われろ。
ざああ、ざあああ、ざあああああ。
――――ザアァァァァァァァァァァ…
その日もオレは一人分の飯を準備して、一人で食事をしていた。
雨は強い。今日も兄貴はあの女の所へ行ったのだろう…オレを置いて。
あの幻想が頭をもたげてきそうになって、オレは無理矢理飯を飲み込んだ。
ばたん。
戸が開く音。
皿から視線を上げると、兄貴がずぶ濡れでフラフラと部屋に入ってきていた。
『…つー、つー。……しぃがいないんだ。知らないか。』
兄貴は雨に打たれて真っ青になっていた。
いや、兄貴を真っ青にさせているのは雨なんかじゃない。
―――― あの女。
『知らねぇな。そんな不愉快な名前の女は。』
オレは飯を飲み下しながら答えた。
雨が激しく屋根にたたき付けられて、俺の声は兄貴に届かない。
『しぃが俺に何も言わないで家を空けるはずがないんだ…。』
兄貴はふらふらと戸口に戻る。
背中もぐっしょりと濡れていて、兄貴が歩いた後は水たまりが出来ていた。
『何があったんだ…。』
兄貴が呟くと同時に戸が閉まった。
その日は土砂降りだった。
事情は飲み込めないが”何かあったらしい”と言うことは解る。
オレはあの女の為に体を濡らす気がサラサラ無かったんで、そのまま家で兄貴が帰ってくるのを待ってた。
水浸しになった廊下を見つめ、雨の中をかけずり回って居るであろう兄貴の姿を思い浮かべる。
『いなくなったのかあの女。どこかで八つ裂きにでもされてんじゃねーか』
ずたずたに切り裂かれたあの女を夢想する。
感慨が湧く前に、雨音にうち消された。
――――ザアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
雨は一層、酷い。
ガラスが水で覆われて外も見られない。
耳を澄ますと、雨音に紛れて兄貴の声が聞こえる、気がした。
ざあああああああああああああ
『しぃ!!!』
ざあああああああああああああ
『しぃどこだ!!!』
ざあああああああああああああ
『しぃ!!』
ざあああああああああああああ
(兄貴も馬鹿だろ。)
オレは、狂ったように降り続ける雨音を聞きながら、兄貴が作った水たまりを雑巾で拭った。
(あんなに取り乱しちゃってら。)
雨水は酷く冷たい。それも気にならないほどに乱れているというのか。
(ああいうのを”亡者みてーな面”っていうんだろうな)
よりどころのない酷く不安げな。そして酷く悲しそうな。
ざあああああああああああああ
可哀想に。
ざあああああああああああああ
(…オレが居なくなってもあんな顔すんのかな)
ざあああああああああああああああああああああ
すげぇ怖くなったから、その時のオレは考えるのをやめた。
―――― しぃがいないんだ
虚ろな目、真っ白になった顔、わなないた唇。
あれは、自分の半身を奪われると感じた恐怖の顔だ。
狂っている雨は、夜中中降り続いていた。
オレは眠りながら兄貴を待つ。
兄貴はまだ夜の雨の中を彷徨って居るんだろう。
オレは布団に入って、兄貴のことを考えないようにして、眠った。
考えると、またあの幻想を見るような気がしたから。
おかしいな。昔は、雨が待ち遠しくて仕方なかったはずなのに。
雨が降るだけで、落ち着いて眠る事も出来ない。
…ばたん。
戸が開く音でオレは目を覚ました。
相変わらず、雨が降っている。
よろよろと廊下を歩く足音。
『おっと、それ以上動くなよ。また床を濡らされちゃかなわねえ』
オレは顔だけ兄貴に向けていった。
兄貴は俺の声や顔なんて聞こえてないし見えてない。
全身ずぶ濡れで、それでも震えてなくて、ただただ呆然とそこに立っていた。
オレは起きあがり、用意したバスタオルで兄貴の体を拭いた。
兄貴は為されるがまま、身体も冷え切ったままタオルにくるまっている。
『おかえり、兄貴。』
夜が明けていたように思う。
兄貴は帰ってきた。
でも女は帰ってこなかった。
―――― シトシトシト…
執念深く雨が降っている。
俺は彼女の次の言葉を待った。
「なぁフサ。」
彼女は指先を見つめたまま俺の名前を呼んだ。
「正気と基地外の違いってどこにあると思う?」
独り言の様に彼女は呟く。
「俺の答えが必要なのか?」
「ああ。」
指先を見つめたままだ。俺の方を見てはくれない。
「そうだな…」
俺は彼女を見つめ、彼女の過去を見つめ、言葉を撰ぶ。
「戻って来れるか来れないかの違いなんじゃないか。」
そう、自分の心の中から。甘い幻想の中から。
雨の中で溶け出した境界線の向こうから…。
「そもそも生きている間、一度も狂わずに人生を終える人間なんているのか?」
俺は彼女を見つめたまま言う。
雨はしとしとと降り続いていて、僅か空気を震わせている。
―――― 俺の言葉は、つーちゃんに届いているのかな。
「酷く曖昧だと思うんだ、そう言うの。」
俺の言葉が終わると同時に、後ろで聞いていたのーちゃんが立ち上がった。
「つーさん、フサさん。茶ぁ淹れましょか。」
のーちゃんは俺とつーちゃんの顔を見比べながら、柔らかい声で言った。
「…二人ともお疲れですやろ。」
「お、おう。」
つーちゃんが照れたように顔を上げた。
「悪いね。」
「いえ、お安いご用ですわ。」
のーちゃんはにっこり微笑んで俺達…特につーちゃんの顔を注視した。
俺もつーちゃんを見つめる。
俺の答えへの返答は、あるのだろうか。無いのかもしれない。
彼女へ言葉は届いたのだろうか。
「それよりも…いらん口出しですけど。」
のーちゃんが笑顔を引っ込めて、つーちゃんに言った。
「今の話は町の衆には言わん方がええ。」
柔らかい声には変わりなくても、のーちゃんには珍しく厳しい口調だった。
「男と女の沙汰ですし、元々どないな事があってもおかしゅうないとは思います。
…せやけど、根も葉もない噂が好きな連中もおる。気いつけて下さいね。」
のーちゃんはつーちゃんの目をのぞき込んで、噛んで含むように言った。
彼女の言う通りだった。
もしこの話が外に漏れたらと思うと気分が悪くなる。
噂話はスキャンダラスで、悪意があるもの程あっという間に広がってしまうものだ。
…事実、ギコさんの異様な死に様は葬式の前に外に漏れていた。
のーちゃんは、す、と立ち上がり、湯飲みを持って台所へ向かっていった。
残された、俺と、彼女と、雨音。
絶えること無い雨音は、ふたりで居ても心細くなると言うのに。
独りで居たらどんなに寂しいことだろう。
―――― サァァァァァァ…
バス停は幾分か明るかった。
つーさんの家を出て、30分ほど歩いただろうか。
輪郭はハッキリと見える。闇は盲雨などでなく、モナーだった。
「ギコ君……自殺なんでしょうか。それとも殺されたんですかね?」
私は一緒に待つモナーに話しかける。
バスはまだ来ない。雨は少しだけ弱まったような気がする。
「気になる所だけど今は何とも言えないね。まあ、フサ君が後で何か教えてくれるんじゃない?」
そうだろうか。
つーさんを支える彼の姿が浮かんだ。
聞き出すことはあっても、私たちに話してくれるだろうか。
「…僕なんかは椎名夫妻の事件を思い出すけどなぁ。」
モナーは雨を見つめながら呟いた。
「椎名夫妻の事件ってあれですか。夫婦二人揃って行方不明になったっていう。」
その事件なら私も知っている。
モナーは振り向きもせず雨を見つめたまま、頷いた。
「そう。正確にはタイムラグがあってね。」
雨が、また少し強くなったような気がした。
強い闇がモナーの顔を覆い隠そうとしている。
水はさらりとしているのに、何と粘っこく見えることだろう。
「奥さんが四年前。旦那さんはもう六年も前になるか。」
雨に隠されたモナーが呟く。
「奥さんが行方不明になった後に椎名氏の遺体が見つかったんだが、
奥さんのしぃさんの方はまだ行方が掴めていないんだ。」
その人も雨に攫われたというのか?
「美しい人だった。生きてらっしゃるといいが……。」
バスの光が、雨の中を切り裂いた。
―――― シトシトシト…
雨の音にも少しだけ慣れたような気がする。
俺はお茶に口を付け、息を吐いた。
のーちゃんの淹れてくれたお茶は少しだけ俺の心をほぐしてくれたようだ。
暖かくて良い香りの液体は、体だけでなく心にも染みこんでくる。
「茶と茶菓子のおかわりもありますんで、おかわり欲しゅうなったら言うてや。」
相変わらず柔らかい声でのーちゃんは言う。
つーちゃんは無表情で湯飲みを包み込んでいる。湯飲みの中をじっと見つめていた彼女の、唇の端が、不意に、くぅ、と上がった。
それが笑顔…自嘲からくる笑みだと、俺はすぐに解った。
迷惑をかけている…とでも思っているのだろうか。
「つーちゃ…」
「のーの茶は美味ぇな!お茶請けにも合うぞ。」
俺の言葉は彼女自身の声で遮られてしまった。
場違いに明るい、いつもの彼女の声。
「オレと組んで料理屋とかどうよ。」
俺に声をかけさせないようにしている様だ。
「アホ言うたらあきませんわ~。お上手でんなぁ」
「いや、マジだぞ!オレとお前とで『肉茶屋』とか、受けるんじゃねーか。」
照れたように笑うのーちゃんに、つーちゃんは明るく答えた。
声も表情も明るいけれど、いつもの彼女のようだけれど。
そう、目の端や、口元、指先。
いつもの様に振る舞っていても、彼女の端々は訴えているのに。
悲しい、寂しい、泣きたい、って。
(つーちゃん。無理に笑うこと無いんだ。)
それなのに、明るく振る舞うなんて。
今まで話してくれた過去を忘れたいのか?
「そうだな。フサ、お前はカーペット用に毛だけよこせ。オレ様が綺麗に刈り尽くしてやるぞ。」
つーちゃんは俺に向き直って言い放つ。
ああ。やっぱり目許が暗い。
(泣きたいんだったら俺が抱きしめてやるから。)
そう、俺が。兄貴なんかじゃなく、俺が。
「返事しろ!」
笑いながら…いいや、笑顔なんかじゃない。口をゆがめて、つーちゃんは俺を小突くフリをする。
俺は返事を忘れて彼女を見つめた。
ああ。痛ましいよ。無理をしている彼女を見ているのは。
そりゃあ、つーちゃんが俺以外の男に惚れていたのは憎いよ。
俺じゃお兄さんの代わりにはなれない。
だけど…。
「イヤ、俺はこのフサフサが命だから。刈られると困るから!」
「オレ様に敵うと思ってんのかよ!」
いつものやりとり。いつもの彼女。
そう、明るくて、でもそれだけでなくて、俺は、彼女が。
俺以外の誰かに惚れていたとしても、俺がその人に一生敵わなくても。
彼女が俺の事なんて見ていなくても…。
そんなことで離れられるんだったら、俺だってこんなに苦しんだりしない。
「ありがとな。お前ら。」
つーちゃんは不意に目を伏せた。
「オレみてーな基地外のためによ。」
溜息と一緒に、独り言のように呟く。
基地外?戻ってこられないと言うことか?
それなら、彼女がそうなら、戻ってこられないのなら…。
「つーさんは基地外やないですわ!!」
のーちゃんの強い口調につーちゃんは顔を上げる。
「つーちゃんが基地外なら俺も基地外だよ」
そう、俺も、もう、戻れないんだよ。
雨で溶けだした向こう側から。
のーちゃんは青ざめて唇を噛み、俺とつーちゃんを交互に見やった。
「一度くらい本物の基地外になってみるさ。……おかしいか?」
そう、彼女と同じになれるのなら。
それも悪くないんだ。
―――― サァァァァァァァァァァ…
フサの言葉に、のーは青ざめたままオレ達を見ていた。
「ちょっとフサさん、基地外とか洒落にならんからやめて下さいよ。」
「俺は大真面目だよ?その方が救われることだって世の中にはあるんだからさ。」
フサは難しそうな顔で、のーじゃなく俺を見つめて言う。
ああ。なんだろう、フサの目は。何処かで見た事があるような気がする…。
オレはフサの目から逃れたくて、目をそらす。
のーはまだ何か言いたげな表情をしていた。
「兄貴といた頃は基地外とかそんなことどうでも良かったな…」
オレはのーの発言を邪魔するように口を開いた。
あの頃は基地外だなんてどうでも良かった。
ただ兄貴と居られれば、それで。
「話、してもいいか?」
二人は口を閉ざし、オレを見る。
ああ。雨音が少し大きくなった。
オレは、雨音に、兄貴の姿を思い浮かべる。
あの女が居なくなってから、兄貴は酷く落ちこんだ。
女が自分に何も言わずに消えたのが信じられなかったみたいでな。
オレの前では何も言わなかったけど、朝から晩まであの女の事考えてた。
廃人だったな。アレは。
『兄貴、飯こぼれてるぞ。』
オレがそう声をかけても、兄貴は虚空を見つめたまま。
パンくずがボロボロと兄貴の胸元を汚していた。
『兄貴!』
オレが手を伸ばして布巾を渡そうとしても、兄貴は気づかない。
ずっと虚空を見つめたまま。
記憶の中のあの女を…。
『こぼれてるっつってんだろうが!!人の話聞いてんのかよ!?』
オレは仕方なく兄貴の零した跡を拭いてやる。
オレの指が触れて初めて、兄貴は飯を零した事を…いや、オレが目の前にいる事に気づいた。
『へ?あ、悪ぃ。聞いてなかった。…ご馳走さん…。』
兄貴は上の空で立ち上がる。
ふらふらと戸口に向かう最中、小さな声であの女の名前を呼んだのを、オレは聞き逃さなかった。
あの女は消えてなお兄貴の頭の中を占領している。
兄貴はあの女ばかり見て、オレのことなんて。
目の前にいるのに。隣にいるのに。誰よりも長い間、オレは、兄貴を、思ってきたのに。
『オレは無視かよ!この糞馬鹿兄貴!!』
オレは湯飲みを戸口に向かって投げつける。
戸口から出ていった兄貴にむかって。兄貴を独占するあの女にむかって。
あの女のせいだ。
あの女が兄貴を惑わしてるんだ。
オレだけの兄貴だったのに。
あの雨の日からずっと、兄貴はオレを見てくれない!
粉々になった湯飲みの欠片が、日差しを受けて、ぎらり、と歪む。
…外はイヤになるくらい晴れていた。
ギコは土手の上を上の空で歩く。
『どうしちまったんだろうなあ。俺。』
頭の中は彼女の事でいっぱいだ。
妹のつーの言葉も、俺は聞き取れなかった…。
なあギコよ、そろそろ正気に戻らないか。
晴れ渡った空の中。頭の中の俺が語りかけてくる。
しぃが消えた理由だって、お前には解っているじゃないか。
彼女が多分戻ってこないこともさ。
あとはお前がそれを認めてやれば、済む話さ──。
俺は空から目をそらして、足下を見つめた。
少し汚れた胸元。ああ、つーをまた怒らせてしまった。
『たいへんだー』
前方から聞いた事のある声が迫っていて、ギコは顔を上げた。
町民のモナーが真っ青になってこちらへ駆けてくる。
『何かあったのか?』
『おおごとだ。早く警察呼ばないと。』
俺が声をかけると、モナーは真っ青のまま俺に言い放った。
『椎名さんの死体が裏山の森から出てきたんだ。』
…”椎名”?
俺の脳裏に浮かぶ、良く晴れた、あの庭。
柵の向こう側の婦人。
美しい笑顔、優しい声。
もしかして
大変だ、と叫びながら町の方へ行くモナーにそれ以上言葉をかける事も出来ずに、俺は走り出していた。
裏山の森。
死体。
椎名。
まさか、まさか。
目の前に町民の人だかりが迫っていた。
ざわざわと遠巻きに。目をそらす事も出来ない人の群れ。
『ひでえ。』
『もっと臭うかと思ったけど意外とそうでもないね?』
『あれは骨を喰った虫けらの匂いだろ。』
『何故こんな所に死体が……。』
人の群は口々に囁き合う。
その声は不愉快に空気を震わせて、俺はその振動を乱すように人の群に分け入った。
『どいてくれ!!知ってる人かもしれないんだ』
椎名と言う名前。
どうか、いや、死体でも良い。行方を…。
俺の前に、群で隠された死体が晒される。
『きみ、椎名さんと知り合いなのか?』
群の一人が口を利いた。
『”この人はやっぱり椎名さんだと思う?”』
目の前の人。
いや、人と言うにはあまりにも…。
『誰だ?この骨は?』
すっかり肉がそげ落ちた、木片のような死体。
かろうじてボロのような着物を纏っている物の、所々身体のパーツがこぼれ落ちて、これでは一体誰なのかすら…。
『着物に名前が刺繍してあったんだ。ほら、二年前に行方不明になった椎名氏だよ。そんな感じしないか?』
群の声で、不愉快な振動がまた始まる。
他人事の、憶測。
『……悪いが旦那の方は面識がねえ。俺はてっきり奥さんかと……。』
俺は死体から目がそらせないまま、うめく。
ああ。俺が会いたいのは旦那なんかじゃない。
彼女はどこへ行ってしまったんだ。死体でも、なんでもいいんだ。彼女に、一目…。
ざわ、ざわわ、ざわわわ。
『なあ、そう言えば椎名さんの奥さんも最近行方しれずなんだよな』
『うん。僕もその噂聞いた。』
『あの旦那、浮気してたんだろ?』
『そんな噂もあったね。』
『この状況で考えられる事ってそんなにないぞ。』
噂、噂、噂。彼女の姿が噂で縁取られて、曖昧にぼやけていく。
『まさか奥さんが旦那さんを殺してそのまま逃げたんじゃ…。』
その言葉が妙にクリアに、俺の耳に入ってきた。
目の前が、歪む。
音が…。
ざあああああああああああああ
これは、雨音?
『おい』
俺の口が独りでに動く。
『誰だ今喋った奴。取り消せよ。』
違う。彼女は。そんな人じゃない。
――――…でも、私まだあの人のことを好きなの……内緒よ。
あの人は、そう、心から。
『お前か?あ?お前か?』
俺は声の主の胸ぐらにつかみかかった。
ギリギリとシャツをねじ上げる。
『く、苦しい…』
『しぃがそんな酷い真似するわけないだろ!!』
そうだ、彼女は旦那さんを愛していたんだ。
俺なんて、初めから
『しぃは……しぃは……!!』
俺に胸を締められて、男は苦しそうにもがき、咳き込んだ。
『そういう君こそ、人様の奥方を呼び捨てにして何様のつもりだ!?
君と奥さんは一体どううい関係だったんだね!?』
男の蔑むような視線。
青ざめた群、噂、憶測、不愉快な振動。
ざわ、ざわざわ…。
俺は声高に叫べない。
俺は初めから、あのひとには…
『……別に大した関係じゃねえよ。ただ、あの人は清らかだった。』
俺なんかが触れたらいけないくらいに。
…だから、俺はあの人が。
『それだけは言っておくぞ。』
蔑みの視線と、噂話から逃れるように、俺はその場からそっと離れた。
空は晴れている。
俺は口の中で彼女の名前を呼んだ。
世間から隠れるようにして、他人の女を愛して、何になると言うのか。
叫んではいけないことなのだ。
俺はこの心を人に叫んではならない。
(ああ。あの雨の日。)
(雨の日が待ち遠しい。)
俺は現実に引き戻される空恐ろしさの中で、逃げるように彼女の側で過ごした日々を思い出す。
(雨の中。俺は、彼女と共に。)
『兄貴、飯こぼれてるぞ』
幻想の中、つーの声が聞こえる。
『兄貴!』
俺を呼んでいる…?
『……。』
俺は、ふ、と隣を見た。
『戻って来いよ…。』
つーが震える声で俺に訴える。
強気につり上がっていた瞳から、液体がはらはらとこぼれて…。
『うお!?何で泣いてんだお前?』
『わからないのか?本当にわからないのか?』
つーは俺に縋り付く。
ぼろぼろと溢れる涙を拭う事もなく。
『あの女はもう帰ってこねえよ!いい加減、目ぇ覚ませ、馬鹿兄貴。』
つーの口からこぼれる現実。
俺が彷徨う妄想の中。
俺の頬を伝い落ちる雨粒か、
つーの頬を伝い落ちる涙か、
どちらが現実か、
狂ったように繰り返す
永遠にこの日常が繰り返される
街の人たちが居て
つーが居て
そして
―――― ザアアアアアアアアアア…
その日も、あの女が消えた日みたいに酷い雨だった。
オレは高熱を出して、一日うなされていたんだ。
『お前が風邪なんて珍しいな。』
すぐ隣でオレを看病し続けていた兄貴の顔が、ぼんやり見えた。
兄貴の声を、雨音が邪魔をする。
『薬、買ってくるか?』
『…行かないで』
オレは夢中で兄貴の手に縋り付く。
雨は嫌だ。
こんな雨の日は嫌だ。
雨は…。
『兄ちゃんここにいて…外、雨降ってる…』
熱に浮かされて声が震える。
背筋を悪寒がゾクゾクと駆け抜けていった。
熱だけのせいじゃない。
雨音が、雨音がオレを不安にする。
『お願い…』
オレは兄貴の手を精一杯握りしめた。
見つめているつもりなのに、兄貴の顔がぼやけてしまう。
そんなオレを見て、兄貴は可笑しそうに笑った。
『何必死になってんだよ。大丈夫だって。二・三日もすりゃ治るだろ。』
そうじゃない…。そうじゃないんだよ…。
嫌なんだ。雨は。雨が降ると兄貴はあの女に取り憑かれてしまう。
『いいから心配しないで寝てろ。な。』
兄貴は優しくオレの頭を撫でる。
兄貴、今はオレだけを見てくれてるのか…?
『――――うなされてんだよ。お前は。ほうら、早く寝ちまえ。』
オレは手の力を少し緩める。
兄貴の掌。兄貴の声。
ゆっくりと熱が意識をむしばんでいく。
『そう。いい子だ。よし…』
兄貴の声が遠くなっていく。
なのに。なのになんで。
雨音だけは耳元で…。
ああ。雨は嫌だ。兄貴があの女を思い出す。
オレを見てくれなくなるから…。
ざあ、ざああ、ざあああ…
『なぁ、つーよ。お前だけには憶えておいて欲しいんだ。』
遠くで兄貴の声が聞こえる。
『兄ちゃんはさ、誰にも言えなかったけどあの奥さんを本当に大切に思っていたんだ。』
『でも俺だけは知っている。』
兄貴の掌…嫌だ、嫌だ、離さないで。
『あの奥さんは行方不明になったけど、たぶんもう生きていないだろう。』
近くにいて。あの女の事なんて…。
『あの奥さんはメクラアメに誘われて旦那の所へ逝っちまったのさ。』
雨…メクラアメ。
あの日も酷い雨だった。
人を誘う雨。愛しい人を連れ去る雨。
雨は嫌だ。雨は兄ちゃんをオレから取ってしまうから…。
『最後まで俺と旦那との板ばさみで苦しんでいた。
でも、待っていてもあの世から人は来ないから奥さんは仕方なく俺を側に置いた。
オレはそれで良かったんだ。』
そんな話は聞きたくないんだ。
違うんだ。兄貴、オレはただ…。
『お前はずいぶん怒ってたみたいだけどさ。いつか、解ってくれよな。』
違う。
オレはただ怒ってただけじゃなくて。
オレだけを見て欲しくて。
あの女の事なんか…!
『奥さんもきっと旦那とうまくやってるし、化けて出たりはしねえだろうさ。』
あの女が化けて出るんじゃないんだ…。
兄貴、兄貴は今でもあの女を…?
『薬買ってくるから大人しく寝てろよ。』
嫌だ、いやだ。行かないで。
近くにいて。今日は雨の日だよ。
あの女に…。
兄ちゃん…。
――――…ザアアアアアアア…
雨を進む兄ちゃんの後ろ姿。
激しくたたき付ける雨は、真っ黒なカーテンのようだ。
ざああああああああああああああああああああ
兄ちゃん。兄ちゃん戻ってきて。
雨は嫌だよ。この雨は…。
ざああああああああああああああああああああ
闇の中で兄ちゃんは振り返る。
そう、そのまま戻ってきて、兄ちゃん…。
―――― …学生さん。
ざああああああああああああああああああああ
どこを見ているの、オレの所へ帰ってきてよ…。
ああ そこは
兄ちゃん…。
あの女に
ざああああああああああああああああああああ
『…!』
オレは布団の中で目が覚めた。
汗でぐっしょりと布団が濡れてしまっている。
頭はクラクラとしたままだ。熱が上がったのかも知れない。
オレはガバリと起きあがって部屋中を見回した。
居ない。
『…兄貴。』
家の中は気配も、音もない。
あるのは
―――― ザアアアアアアアアア…
オレは布団から這い出ようとする。
身体中に熱が駆けめぐって、足が言う事を聞かない。
身体が壊れたように震え出す。
寒い。怖い。雨が。雨が。
『…まだ帰ってこねえのかよ。』
声が出ない。
寒い。雨音がオレを壊しに来る。
『…こんな日に…外に出るからだ。雨は嫌なんだよ。怖くなるから。』
たたき付けるような雨。
あの日と同じ。あの女が消えた日と同じ。
兄貴。
兄貴は。
―――― あの奥さんはメクラアメに誘われて旦那の所へ逝っちまったのさ。
雨…。
メクラアメ。
片割れを連れ去る雨。
暗闇。
あの女が消えた日と同じ…。
兄貴は居ない。
『オレが「苦しい」って言ってるんだ!こんな日ぐらい側にいてくれよ!』
雨音をかき消すように叫ぶ。
ああ 苦しい。胸がつぶれてしまいそうだ。
喉の奥から塩辛い液体がこみ上げる。
熱が身体中を浮き立たせる。
兄貴。兄貴。
どこにいっちまったんだ。
あの女が あの女が…!
『オレを置いて行くなああああああああああああああああああ!!!』
ザアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアアア
オレの叫び声は、強くなった雨音にかき消されて、届かなかった。
結局、次の日になっても、その次の日も、兄貴は帰ってこなかった。
傘だけだ。残ってたのは。
オレはそれで何が起きたのか理解したよ。
―――― シトシトシト…
つーちゃんが語り終えても、しばらくは口をきけるような空気ではなかった。
のーちゃんはつーちゃんを見つめながら、ゆっくりと瞬きをした。
つーちゃんの頬は、はらはらこぼれる涙で濡れている。
雨音に、兄貴を思っているのか。
「つーちゃん、ありがとう。話してくれて。」
俺が声をかけると、彼女は両手で顔を覆ってうつむいた。
肩が小刻みに震えている。
ああ。良いんだよ。無理をしないで。泣きたいだけ泣けば良いんだ。
俺がいくらでも抱きしめてやるから…。
「今晩、一人で大丈夫か? 雨降ってるけど。」
ビクリ、と肩が震えて、彼女は顔を上げた。
「オレは大丈夫だよ!何を今更…」
さっきまでとはうって変わって、明るい声で彼女は言う。
つーさん、とのーちゃんが小さく呼ぶのを遮るように、彼女は明るい笑顔で続けた。
「この三年間、オレはずっと一人暮らしだったんだぜ?」
嘘だ。
つーちゃんは一人なんかじゃなかったんだろう。
この三年間、ずっと兄貴を待ち続けていたんだろう。
頬に残った涙が、てらてらと輝いている。
「帰れよ。気持ちだけ貰っといてやるからよ。」
つーちゃんはそう言いながら俺達を急かした。
彼女に撲たれた指先が、しくり、と痛む。
痛ましいよ。今日からは、本当に、一人きりなのに。
つーちゃんは玄関に立った時には、もう元通りの顔になっていた。
「じゃあな。気をつけて帰れよ。」
いつも通りの声で彼女が言う。
もしかしたら一人になりたかったのかも知れない。
逆に一人になるのが怖かったかもしれない。
俺は、つーちゃんの気持ちがどちらなのか読みとる事が出来なかった。
つーちゃんの姿を痛々しいと思いながら、俺はその晩、つーちゃんの家を後にした。
―――― サァァァアァァァァ…
俺は迷う。
陰気な雨がいつまでも降り続いて、俺を妄想の中に誘っている気がする。
雨の夜道は暗い。
すぐ目の前の闇が、まるで映画のスクリーンのように、俺の妄想を映し出す。
つーちゃんをそっと抱きしめる。
泣かないで。悲しまないで。
自分だけ向こうに行かないで…。
甘く甘く、そして頭を締め付ける妄想。
もう誰もいないじゃないか。
二人で、閉ざされた世界で狂わないか。
つーちゃんの心の中には誰が居るんだろう。
俺ではない、誰か。
それともお前はまだ
存在のない男を愛しているのか?
つーちゃんの兄貴。
メクラアメに攫われた兄貴。
つーちゃんを最後まで見ようとしなかった男。
死んだ男を?
彼女の心に俺は居ない。
彼女の兄が彼女を見なかったように
彼女もまた俺を見ていない
ああ。雨の幕がゆらゆら揺れて、妄想が掻き消える
消えないで、現実になって
「…さん、フサさん!」
掻き消えた妄想の先から、のーちゃんの声がした。
すぐ隣の闇から、傘を差しだして、俺の顔を覗いている。
「何や、怖い顔しとりますなぁ…。気ぃつけんと道に迷いまっせ。」
雨音にとけこむような、柔らかな声。
ああ。駄目なんだのーちゃん。俺はもう
のーちゃんの背後の雨が揺れる。
ふわりと立ち上がる妄想。
お前が居なければ俺にとって この世は闇。
ゆらゆら揺れる雨間をぬって、少し明るいバス停についても、俺の妄想は雨に支配されていた。
「……ほな、うちはこれで。」
「ああ。」
のーちゃんを乗せたバスが遠ざかる。
闇がひたひたと辺りをむしばんでいる。
さああ、さあああ…
薄暗い、薄暗い、雨。
立ち上がったまま消えない妄想。
目をこらしてバスの時刻表をのぞき込む。
本当に俺はこのまま帰っていいのか?
(雨はまだ止みそうもない)
正気に戻るべきか?
(つーちゃんは一人で泣いているんだろうか)
たとえ正気に戻ったところで首輪のように締め付けてくる想いをどうしようもないんじゃないのか?
(俺は彼女の事しか考えられないのに)
雨が誘う妄想の世界から逃れられないんじゃないのか?
(兄貴を思う彼女も彼女を思う俺も)
背後の雨がさわさわと揺れている。
俺を誘っているのか?それとも
彼女を迎えに行こうとしているのか?
俺はゆっくりと彼女の家に足を向けた。
ぱしゃ、ぱしゃと足下の水が跳ねる。
その音で雨をかき消すように、俺はいつの間にか走っていた。
ぼんやりと明かりが近づいてくる。
「つーちゃん!つーちゃん勝手に戻ってごめん。」
玄関は開いていた。
俺は戸口で彼女に向かって声をかける。
返事の代わりに、雨音が響いていた。
「上がるよ。」
薄暗い部屋。
線香の香り、じっとりと重い空気。
雨音がそれを何倍にも重くしている。
つーちゃんは部屋の中、布団も敷かずに眠り込んでいた。
俺は彼女にそっと近づき、のぞき込む。
――――骨壺…?ギコさんの骨か。
彼女は白い小さな壺を抱きかかえるように眠っている。
「つーちゃん、風邪ひくから。…つーちゃん。」
低い声でささやきかける。
彼女は目を覚ます気配もなかった。ただ、壺を抱きしめて眠り続ける。
目許に涙の粒が光っていた。
泣きながら、眠ってしまったのだろうか。
「…。」
俺は彼女の隣に身を横たえて、そっと抱き寄せた。
彼女の肌はすこしだけ冷たい。それを温めるように、身を寄せる。
悲しげに沈んだ目許。きらきらと光る雫。
俺はそっと目を閉じて、彼女に頬を寄せた。
―――― つーちゃん。
彼女の肌は冷たい。
―――― もう一人で眠るの止せよ。
ああ。痛々しいんだ。つーちゃん。
―――― つーちゃんの心にはギコさんが一緒に眠ってるのかも知れないけれど、
雨音が強くなっていく。
―――― 俺にはつーちゃんが独りぼっちに見えるんだ。
それは幻?現実?
俺が側にいるの、わかるか?
雨音が聴こえるかい?
つーちゃん、つーちゃんは俺を許してくれるか?
自分がまともかも解らなくなっている俺を───────俺を
―――― ザアアアアアアア…
いつの間にか眠り込んでいたようだ。
ぼんやりとした暗闇。
隣に確かに感じる体温。
ああ。一人じゃないんだ。
『……奥さんもきっと旦那とうまくやってるし、化けてでたりはしねえだろうさ。』
ああ。一人じゃない…。隣に居てくれるから…。
『薬買ってくるから大人しく寝てろよ。』
いやだ、いやだ、いかないで。はなれないで。ああ…。
「!」
冷や水をかぶったように目が覚める。
薄暗い部屋。
たたき付けるような雨音。
そう、あの日と、同じ。
隣に感じる体温は…。
「…あ……」
声が震える。
ああ。離れないで。
なんで。何でフサが?いや、そんなことより…。
「…にいちゃん…!」
声が震える。あの日と同じ。
震えた叫び声で目が覚める。
線の細い彼女の肩。たたき付けるような雨音。
掌の中でごとりと動く壺。
壊れたように震える彼女。
ああ。壺が。
兄ちゃんはもういない。
そうだ。
兄貴は骨になってしまった。
飛び起きる。
ぽろぽろとこぼれる彼女の涙。
壊れたように震えて…雨音がその上に…。
いやだ。
そんなのいやだ。
骨になったなんてイヤだ。
置いていってしまうなんていやだ。
もたれかかった先から見上げた彼の顔のライン。
掌。声。
後ろ姿…。
「兄貴。何処行っちゃったんだ。」
声を張り上げる。
雨音が。ああ。雨音が。
あの日と同じなんだ。
闇に向かって叫ぶ彼女。
「あの日」を思い出しているのか?
「こんな、こんな骨…。」
違う、こんなのは兄貴じゃないんだ。
兄貴は、兄貴は
「 兄貴…!! 」
がしゃん、と壺を放り出す。
蓋が外れて中から灰褐色の粉がこぼれた。
こんな粉じゃない。兄貴はこんな粉じゃない。
兄貴はこんな壺に入ってなんかない。
兄貴は、兄貴は。
「つーちゃん!」
放り出された壺からギコさんの骨がこぼれだした。
死者の骨。
彼女を最後まで見なかった男の。
雨に攫われた…。
兄貴は雨の中に居るんだ……!!
壺を省みず彼女は雨に飛び出していく。
たたき付けるような雨の所為で、外は真っ黒なカーテンを引いたようだ。
禍々しい。
ああ。駄目だ。あの雨は駄目だ。
「つーちゃん何処行くんだ!」
傘を取りながら彼女の名前を呼ぶ。
「つーちゃん!つーちゃん…!」
俺の声は届かないのか?
雨