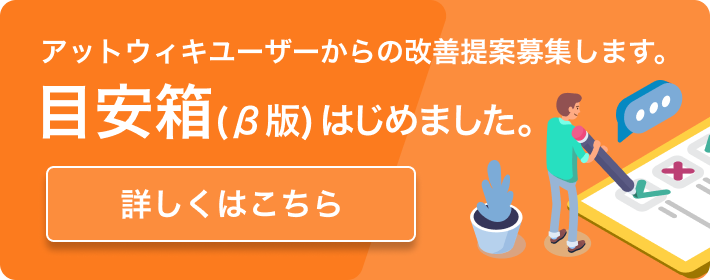0:発端 beginning
それは突然訪れた。
ある日、世界からモナーたちが消えた。
正確に言えば『オマエ・モナー』を基本とする、八頭身及び六頭身などを含めたモナー族が姿を消したのだった。
それも、『モナー』を名前に持つAAだけが。
何か、得体の知れないものが、あの胸焼けを起こしそうな、全てに平和を与える笑みをこの世界から消し去ってしまったのだった。
1:困惑 perplexity
ある日突然起こったその出来事に、八頭身本家次男の八ギコは戸惑いを隠せずにいた。
かつてこの世界でこんな出来事があっただろうか?
先日、不意に気づいたときには八モナーの姿は消えていた。
覚えている、彼があの間の抜けた声で意味も無くラルクを語っていたのを。
それが、今では遠い昔のようで。
不意に肩をたたかれた。
「ギコ兄」
「……フーンか」
この同居人は相変わらずすました顔をしている。
何故だか、むしゃくしゃする。くそ。これもみんな兄貴がいなくなったからだ。
意味も無く、八フーンを睨みつけた。
「気づいたか?――今日、モラ兄まで消えた。街にいるモララー族も、全員だ」
「…………っ!」
「このままだとギコ兄が消える日も来るかもしれないな」
八フーンは煙草に火をつけ、その紫煙をゆっくりと肺に流し込む。
「……あの騒動のときでさえも、こんなことは無かったのにな」
あの騒動とは、かつてギコやモナーが企業に囚われかけたときのことである。
それは、関係が薄い八頭身や六頭身にまで被害が及んだものの、すぐに事態は回復を見せた。
新しく『タカラ』がAAとして生まれ、今ではもうこの世界にすっかりなじんでいる。
しかし、今の事態はそれとはまた違う様相をなしていた。
どこかが、おかしくなってきている。
「……よく考えれば、珍しいな。お前、大体こういうときは俺やモララー、兄貴にも何も言わずに動いてるってのに……どんな風が吹いたんだか」
「手を打ちたいのは山々なんですがね……どっかの過保護の馬鹿が、ショックが大きすぎて使い物にならねえんだよ」
ああそうだろうな、と八ギコは納得した。彼は子供たちに何かがあったら、すぐに行動を起こすかしばらく動けないかどちらかだろう、と推測できたからだ。
「それはそうと。ギコ兄、ちょっと付き合ってくれない?」
「何だゴルァ」
「いろいろ、ね。ああ、しぃやつーも呼んできて欲しい」
「……パシリじゃねえかゴルァ」
「まあそうともいう」
――まあとにかくちょっとそこまでだからいいだろう?
八フーンはそういって、策士の笑みを浮かべた。
※
部屋の中に、ぽつんと星型の髪飾りが落ちている。
八ネーノはそれを手にとって、消えた子供のことを思っていた。
星シーンや>>1もさすがにこの事態を知って混乱した。しぃと一緒にどうにか落ち着きを取り戻したのは先ほどのことだ。
困惑と、奇妙な恐怖。痛いほどの寂しさ。
かつての自分はこんな感情を抱いたことがあっただろうか。
誰かの小さな手が、背中を叩いた。
「……元気出して」
「モラはきっとすぐに帰って来るんじゃネーノ?」
「チョットドコカニ出カケテイルダケヨ。落チ込マナイデ」
「皆……」
子供たちが、一生懸命に自分を励ましてくれる。自分達も不安でたまらないだろうに。
――俺がしっかりしなくちゃ駄目なんじゃネーノ。
「――うん。そうなんじゃネーノ。ごめんな心配かけて」
わしわし、と子供たちの頭を撫で回す。――もう一人の子供がいないことが心に僅かな細波を生む。
あの子を探しに行かなければ。俺はあの子の保護者なんだから。
そう決意したとき、不意に玄関からの涼やかな音が耳に入った。
誰か人が来たのか。こんなときに、いったい何なんだ。
「はーい、どなた……と」
「だいぶ元気そうで何よりだが」
半分ほど開けたドアを、来客は無理やりこじ開ける。
「いよう」
「ノーネじゃネーノ。どうしたんだよ」
「ガキたちは八シーンに任せてちょっと顔出し願いたいんだが……どうだい」
「どんな御用で旦那」
「お前の家族に関わる用事。断ることは許さないノーネ」
この大人が関わっているとろくなことにはならない。
そのことは知っていたが、断る気にはならなかった。
2:謀略 stratagem
「これで全員だな」
八フーンが人数を数えて言った。
集まったのはいずれも八頭身の、ギコ、しぃ、つー、ネーノ、ノーネの5人。
「全員っていっても随分少人数なんだな」
「大人数いたって動けないのならいる理由が無い。それにあまり大人数で動いたら逆に眼を引くことになるからな」
八フーンは八ギコの問いに答えながら携帯電話をいじる。誰かと連絡を取っているようだ。
何度かのバイブレーションの音の後、
「じゃ、こっちだ」
※
着いたところは街外れのビルの中。
今にも崩れそうなその建物のバリケードを破り、不法侵入を果たす。
どちらにせよ人通りも無いこの場所は、秘密の会合に最も適した場所だった。
中は真っ暗なわけではなく、ところどころから光が漏れている。窓が割れているのか、建物の壁自体に問題があるのかまでははっきりしない。
八フーンはその中を迷い無く進んでいった。後ろから仲間達がそれを追いかける。
未だに彼の意図ははっきりしない。八ノーネは何か知らされているようだが、自分達に教えるつもりは毛頭無いようだ。
八ネーノは少し腑に落ちずに、それでも後を付いていった。
錆付いた音を立ててドアが開く。
「随分遅かったですね。迷ってたんですか」
「この場ですり身になりたいというなら別に躊躇しませんが何か?」
「相変わらずですねえあなたも」
目だけが笑っている、八頭身のAA。
「おいフーン!そいつ山崎じゃねえかゴルァ!なに考えてやがる」
「いたってまともですが?」
「そういう意味じゃない。そいつは『荒らし』だろ。今この状況で一番問題を起こす存在だ。どうして奴がここにいる?」
「心外ですね。僕はいつでも荒らしをしているわけじゃない。なにせこの状況を把握して、それでも荒らしをして何になるというのですか」
「アヒャヒャヒャ!全クダナ。ソレニフーンダッテ何モ考エズニ山崎ト手ヲ組ンダワケジャネエダロ?タダノ馬鹿ジャネエンダカラ」
「……ま、取り敢えず話を聞こうじゃネーノ?決めるのはそれからでも遅くない、そうだろフーン?」
八ネーノの言葉に、彼はただ口の端を吊り上げた。
それを皮切りに、八ノーネから言葉が出た。
「……『荒らし』故の特殊性を利用しようってハラか?」
「まあそんなところだ。流石、年寄りは話が早くて助かる」
「…………『荒らし』の特殊性?」
聞いた事のない言葉に、今度は山崎から答えが返ってきた。
「あなたたち普通のAAと、僕達のような『荒らし』のAA、その違いは何だと思いますか?」
「うー……ん?基本的には何も違わないように思えるけど」
「『荒らし』のAAは、どのスレにも――やや悪意的な意味合いが加わりますが――出現できるということです。つまり、板やスレによって存在を制限されることが無い」
「ソレハ変ヨ。荒ラシヲスレバ皆カラタタカレルモノ。コレハ存在ヲ制限スルコトニナルデショウ?」
「その発言をした『名無し』が叩かれることはあれど、僕達AAのみに関していえば自由です。更にスレを自由に行き来できるのは『荒らし』だけに持たされた能力のようです。――さて、この能力を使って何が出来るでしょうか?」
「……まさか、消えたモナーやモララーを探し出すことが出来る?」
いってから、八ギコは信じられないといった表情で考え込んだ。もしくは彼の能力を知ったうえでも、手を組みたくないという思いが強いのかもしれない。
「それで手を組んだってこと?俺にはそれだけで全てが終るとは思えないけど」
「正確に言えば探し出すことは出来ないかもしれないというのが事実なので、この事件が解決するわけではありません」
「?」
「……ま、口で説明するのはややこしいですね」
山崎はそういって八フーンのほうをちらりと見る。彼が勝手にしろ、と言いたげに首を振ると、笑顔を更に深めた。
「では始めましょうか。全部で6人ですね?それでは」
山崎はぱちんと指を鳴らした。
床に入っていたひび割れの、ちょうど円になっている線部分だけが発光する。
「お連れいたしましょう。世界をつなぐ狭間の世界へ」
視界が闇へと反転した。
≪the another side #1≫
「わーん。ここはどこなんだよ!俺はラルクのライブに行った筈だったのにぃ!!ここから出せぇ!!」
がしゃんがしゃんがしゃんがしゃん。
八モナー――正真正銘八頭身一家長男である――が、閉じ込められている檻を両手で力いっぱい揺さぶった。
檻は壊れない。八頭身の力をもってしても壊せないとは、どれほど頑丈な檻なのだろうか。
しかし八モナーはそんなことは気にしない。壊せなくてもそれでも頑張る。それがラルク魂。
そしていくら魂を語った所で物質の硬度が変わるわけでもない。
「うー。酷いやみんな。兄さんを独りにしてえ。きっとおいしいものを食べに行っているに違いないんだ。特にフーン!あいつだ。あいつがきっと実行犯だ!よおし、帰ったらお仕置きしちゃうぞ!」
「それは無いですね。彼はそんなことをするような人じゃありませんし」
いきなり後ろからかけられた声に大袈裟に驚いて、八モナーはゆっくりと振り返った。
「始めまして。八頭身モナー(裏)です」
自分と全く同じ顔。
「…………っっっっっ!!!!!どどどどど」
「大丈夫ですよドッペルゲンガーじゃありませんから。僕とあなたは同じモナー族です。だから同じ顔なんですよ」
「は、あ……」
「ああ、どうして同じ顔が二人、ここに居るのか、ということですか。それは僕にも判じかねますね。ただ僕がいるスレとあなたがいるスレでは雰囲気というか、八頭身モナーの役割が違うからでしょうか」
「役割?」
「あなたはどちらかといえばお笑い担当。ギャグ専門。どちらかといえば上層スレの住人。僕は反対にシリアス専門。主に地下スレにいます。――ここまで性格が違うのだから、別人だと考える方が正しいでしょう?」
「んんん?うーん……なんとなく解ったような気がするけど……」
――そうか。きっとラルクってことなんだな。うんそうだ。そうに違いない。
自分なりの(間違った)結論で思考を一回リセットさせると、改めて自分の疑問を口に出した。
「じゃあ、なんであなたと俺とが同じ場所にいるんでしょう?今の説明だと、俺とあなたとは同じスレにいるのはおかしいはずです。なのに今、同じ場所にいる。これって?」
「それは解りません。ただ、ここに連れてきた誰かの思惑なのは確かなようですよ?」
「誰か?やっぱり誰かいるんですね。誰なんでしょう」
「さあ。まあ、しばらくゆっくり過ごしましょう。果報は寝て待てとか、急がば回れとか言うことですし。ね」
確かに何もやることが無いのは確かである。
八モナー(裏)は柔和な笑顔で相手の二の句を妨げた。
3:召喚 summons #1
「……こんなことになるとは聞いてないぞ山崎」
「そりゃ僕も言ってませんもん。当たり前ですよ」
暗転した後、八頭身たちはトンネルのような光る空間を落ちていっていた。
いや、それは昇っていっているのかもしれない。それとも横に飛んでいるのかもしれない。上下の区別が無いこの空間ではどうにも表現しがたい感覚である。
「聞いてないって、いったい何を聞いてたんだよ」
「モナ兄を探す手伝いをすること。それに協力者がいること。確実性は高かったし、特に損をするような条件でもなかったから、構わんと思って引き受けた」
「条件?」
「お前らを呼んでくること。ひとりだと面倒だからノーネにも手伝ってもらった」
「じゃあ、どうしてそんなに怒ってるんだよ。珍しいんじゃネーノ?」
「……今日は『セーラーフーン劇場版』の放送日だ」
「…………」
「…………録画しそびッた……」
あえてノーコメントである。ついでに顔もそむけてみる。八フーン族の考えることは想像の範疇を軽々飛び越えていく。
とにかく今は、これからどこにたどり着くのかが問題である。
「もうすぐですよ。着いたら殴るでも蹴るでもしてくれてけっこうですから、今はおとなしくしてくださいね。命の保障は出来かねますから」
山崎の言葉に暴れる気も失せた。とにかく、床があるところに着いたら狂犬組の恐ろしさを見せてやる。
そう決意して、八ネーノは流れに身体を任せる。
こうなったらなるようになれだ。何が起きても基本的にはいいんじゃネーノ?
※
突然床が現れた。気が付けばそこに立っていた。
相変わらず回りは不思議な光が飛び交っているが、なぜか目に煩いわけではない。
ただ、自分という存在がこの場にふさわしくないような、そんな気になってきていた。
「いわれた通りお連れしましたよ。ぼるじょあはまだのようですね」
「もう着いたYO。山崎の方が早かったNE」
声がすると同時にもう一人の『荒らし』――ぼるじょあが姿を現した。彼は三頭身の姿だ。
そしてぼるじょあの後ろに、何人かの三頭身が姿を現す。
その姿は――ギコ、しぃ、つー、フーン、ネーノ、ノーネ。
奇遇にも八頭身たちと同じメンバーがそろっていた。
「やはりそちらでもその6人ですか……」
「『コネクター』の言うとおりだYO。まあ、これで僕らの仕事は終わりだNE」
「いやはやまったく、お疲れ様です。山崎君、ぼるじょあくん」
ここに居る、知っているもの以外の声がした。
見れば、何故先ほど気づかなかったのだろう、円卓と三人の風変わりなAAが座っていた。
一人は、八頭身の、恐らくモナー系の種族で、目に幾重にも包帯を巻き、燕尾服を着て紅茶か何かを啜っている。山崎たちに声をかけたのは恐らく彼だ。
もう一人は三頭身で、通常一つきりの耳朶が同じところから二つ生えている畸形(きけい)。だが向かって右の耳はどうしたのか、その姿を見せることは無く、代わりに金属板が頭蓋に沿ってそこを覆っていた。マントのようなものを羽織り、同様に紅茶を啜っている。モナー系の種族のように見えるが、ギコ系の種族特有の長い尾が二本生えていた。
最後の一人は六頭身、顔つきだけならフーン族で、それでいて向かって右目に、縦に切られたような傷跡を残している。そして彼は拘束服でいて器用にノートパソコンを操っているのだった。
それは見かけにも――
「――――兄者か?」
「否定する。私はあくまでもこの姿を借りているだけだ。必要なら変えるが」
兄者もどきが硬い返事を返した。しかも目線すらこちらには向けない。
――これは流石家というよりフーンの腹違いの兄弟か何かって言われた方が納得するんじゃネーノ。
八ネーノの心の思いはあえて口に出されることは無い。
「『コネクター』。失礼でしょう。ちゃんと挨拶ぐらいしたらいかがです」
「何だ。もうそろったのか。それならそうと早く言え」
そして戸惑っている大勢に向かって、
「席に掛けたまえ。適当で良い。説明が長くなりそうだからそのつもりでいるように」
「……だいぶ偉そうだなあんたは」
「偉そうじゃない。偉いんだ」
誰かが発したそんな呟きに平然と答える。ここまでだと寧ろすがすがしい。
有無を言わせぬ声に、皆がぱらぱらと席に着くと、目を隠した八頭身が話を始めた。
「どうも、始めまして、皆さん。私達は今回の事態を重く見て皆さんに集まっていただきました。だから何をするかというのはもはや決まっています」
そういって彼は一呼吸置いて、
「――皆さんには、僕らの手足になっていただきます」
よく通る声をしていた。
※
「納得できねえなあ」
そういったのは三ギコだ。思えば八頭身たちが(一部を除いて)どこか恐縮している中で、三頭身たちはどこか落ち着いた雰囲気を保っている。
「手足になれだと?今回の事態というのは恐らく――モナーたちが消えたことにあるんだろうが。俺たちに十分な説明もなしに手足扱いは無いんじゃねえのか?」
「ギコの言うことに一理有りじゃネーノ。第一、あんた達はいったい誰なんじゃネーノ?」
そういわれて3人は少なくとも戸惑ったようだ。
数秒の沈黙の後、口を開いたのは六頭身の彼だった。
「……我々は概念を象徴させた人格だ」
聞きなれない単語の連続に、思わず全員からハテナマークが飛び出る。
「あそこの畸形は『クリエイター』。物語を作る者たちの概念の象徴。よく『ネタ』とか『ネ申』という言葉で表されるものを実体化させたものと考えて良い。
八頭身は『ウォッチャー』。物語を見る者たちの概念の象徴。閲覧者の総合意思とも表現できるが、ニュアンスが変わってくるためにここでは『観察者(ウォッチャー)』としておく。
私は『コネクター』。作品と閲覧者を繋ぐものの概念の象徴。解りやすく例えれば回線のようなものだ。
――我々が何なのか。これがその質問の回答になるな?」
「……異議無しじゃネーノ」
「次は恐らく、『何故手足にならなくてはいけないのか』だろうな。
――我々ではこの問題に干渉できないからだ。我々はあくまでも『概念』でしかない。実際にこの問題を解決できるのは貴殿等だけだ。我々ができるのはそれを手助けすることのみ」
怒涛のように並べられていく言葉をその場で理解しているものは少ない。
その中で、三フーンがプ、と吹き出した。
「フーン……。だいぶ偉そうなことをいっていたわりには何も出来ないということですか。それで手足になれだと?
――――ふざけるな!」
「そうだ。我々には何も出来ない。だから貴殿等を呼び出すのに山崎たちを使わざるを得なかった。しかし、こう考えていただきたい。――我々が干渉せねばと思うほど、事態は切迫しているのだ、と」
「…………」
「まあ、その点は軽く無視する。異議は聞かん。もし受け入れられない場合は……消えたAAたちは戻ってこないだろうな」
「脅す気か」
「順当に想像した結果だ。我々には何も出来ないのだから」
我々についてこう考えてくれても良いだろうな、と『コネクター』は呟く。
「むしろ神だと」
「「うわあむかつく」」
「文句は小声で言いたまえギコ氏等」
三ギコ・八ギコの両方から出た言葉にさらりと突っ込みをいれつつ、
「それより本題だ。今ここにいるメンバーに、ある力を解放する」
そういった瞬間から、『コネクター』の手はものすごい速度でキーボードの上を滑り出した。
≪PROGRAM NORMAL カラ SPECIAL ニ CHANGE:EFFECT Lv.1 カラ Lv.2 マデ EXTENSION ……PROGRAM RUNNING!≫
3:召喚 summons #2
ふー、と八フーンが紫煙を吐き出した。
「……何も変わらないぞゴルァ」
「ははは。三頭身ギコさん、ちょっと良いですか?」
「何だゴルァ?」
「山崎君に、『逝って良し』、やっていただけますか」
「僕にですか!勘弁してくだ……」
「解ったぞ」
軽く引き受けて、やや後ずさりする山崎に向かい、懇親の力を込めて、
「≪逝って良し≫!!」
「ぐはぅ!!」
衝撃波による轟音と、山崎が弧を描いて吹っ飛んでいくのが見えた。
皆が驚きに声を呑む。あのつーたちですら何を言うべきか言葉を失ったままだ。
「見ての通り、貴殿等の決め台詞に反応して発動する。有り体に言えば『魔法』だな。全てについて説明するのは面倒だから各自で発見してくれ」
「そんな適当な……」
「……ま、良いんじゃネーノ?」
「なるほど……確かに手助け、だな。それ以上に言うことは無い」
納得する三頭身。
「そういえば、山崎たちの『荒らしの特殊性』だったか、あれも同じような原理なのか」
「彼等の力はむしろ私の力に近い。スレとスレの間を繋ぐのだから」
『コネクター』に言われて、軽く疑問に思っていたことが解消する。
ふいに、『クリエイター』が口を開いた。
「私からも、皆さんに渡さなければならないものがあります」
言うと、小さな手の中から、淡く発光している糸を取り出した。
「これを、皆さんに結びます。原型が同じAA同士で手を出してください」
言われ、それぞれが手を差し出す。
糸はその手に触れると、先がとけるように手のひらに吸い込まれていった。そうやって二人ずつ結ばれていく。
「だから同じAAが集まったわけか」
「で、これでいったいどうするんだ?」
「無論二人ペアで行動してもらうため。さっきの力は、同じ種族が集まっていると相乗効果でより強いものになる。一人ひとりで行動してもらうよりこちらの方が些か都合が良い」
「フーン。まあどちらにしろ――俺たちに何をやらせるつもりだ?」
「それは……」
突然、空間が歪んだ。
床や、テーブルや、そのほかさまざまなものがぐにゃりと歪んでいく。
そして風船がはじけるような音とともに、その空間に裂け目が生まれた。
裂け目の先は、漆黒の闇。
「――まずい、この空間がばれたのか!」
「山崎君、ぼるじょあくん、それぞれ解っていますね!」
「あいYOー」
「大丈夫です」
その闇の中から、触手じみた物が溢れてきた。しかもそれはまっしぐらにフーンたち、そして『コネクター』に向かっている。
あわててそれをよけながら、『コネクター』は叫ぶ。
「――そうか、次の獲物はフーン族か!全く油断した……おい、準備はいいな!!」
「「了解!」」
山崎とぼるじょあの返事を聞いているのかいないのか、再びその指はキーボードをなめていく。
≪COMMAND 転送 STAND BY...FIRST:GIKO_TWO_WATCHER_BOLJORE SECOND:FUUN_NENO_CONNECTOR THIRD:C_NONE_CREATER_YAMAZAKI ……PROGRAM RUNNING!≫
「説明している時間は無い。取り敢えず転送する。≪接続(connect)!≫」
彼の言葉が終わるやいなや、先ほど、この場所に来る前に体験した感覚が全身を襲う。
「本当に乱暴だな……」
「まあ仕方ねーな。時間は確かに――無い」
「さて皆さん、喋っていると舌を噛みますよ――」
重々しく世界がひしゃげた音を立てたとき、彼等はその場から姿を消していた。
※
その頃、街からはほとんどのモナー系AAが姿を消してしまっていた。
八マララーは特に何をするでもなく、道を歩いていた。
「はあ……モナ兄さんも、モララー兄さんもいなくなってしまった……ギコ兄さんやフーンさんたちは帰ってこないし、フサ君はカバディだし、ヒッキーやジエンはいつも通り……僕、どうしたらいいんだろう」
先生スレを動かすことは出来ない。出演者が消えてしまったのもあるし、監督やADの殆どは姿を消してしまった。
手持ち無沙汰にもほどがある。
それでも何故だか足はスタジオの方へと進んでいく。
そして、先生スレの撮影スタジオの扉を開けた。
「今日はー。って誰もいるわけが……っ!」
八マララーは目を見張った。
恐らく、監督が。
ADが。
カメラマンが。
モナー族、モララー族、フーン族の三頭身たちの顔に、丸い仮面のようなものが張り付いている。
顔の輪郭に沿って丸く削られただけの板に、目の部分だけがくりぬかれている。
荒っぽい作りであるそれは、だがぴったりと、その顔にくっついていた。
「……み、皆さん……仮面舞踏会でも……?そんなわけ、無いですよね……」
そしてその問いかけに答えずに、彼等はただそこに存在している。
――尋常ではない。
恐怖に似た戦慄が、ゆっくりと八マララーに浸透していった。
※
一方、八ネーノの自宅では、八シーンが子供を元気付けようと奮闘していた。
すっかり子供たちは意気消沈してしまっていて、いつも振り回される立場の彼はその様子に戸惑いを隠せなかった。
「……大丈夫だよ……ネーノも、モラも、すぐに帰ってくるから……」
「じゃあ、いつ帰ってくるか教えて欲しいんじゃネーノ!」
「……そ、れは……」
「……答えて欲しいんじゃネーノ……」
>>1は、むしろ答えを期待していないような様相で、暗く沈んだ空を見上げた。
もうすぐ、雨が降ってくるかもしれなかった。
そのとき、ふいに扉の開く音が聞こえた。
「ネーノ?もしかして……モラじゃネーノ!」
「……本当!」
「チョット行ッテミルワネ」
しぃが玄関に向かおうと足を速め――
すぐに、止めた。
「どうしたんじゃネーノ?」
「……しぃちゃん?どうしたの?ネーノじゃ……っ」
訝しげに思った八シーンがしぃの視線の先に目をやり、声を失った。
星のステッキを持った三頭身。
ここまでなら、いつもの星モラと一緒だった。
しかし、八シーンの声を奪ったのはその顔に張り付いた仮面。
くりぬかれた二つの眼は、無表情な中に、一種の違和感を生み出していた。
「……モラ、なの……?」
星シーンが近づいていく。しかしその足も途中で止まった。
いつも無表情な彼が珍しく、泣きそうな顔をして、
「……モラじゃない……誰?…………誰!?」
誰もその言葉に答えるものはいない。
×××注意×××
この先には、グロテスクな表現が含まれています(虐殺スレの表現のため)。
生温いとはいえど残虐表現に抵抗のある方は回れ右です。
4:犠牲 sacrifice
そのスレにたどり着いたのはギコとつー、ぼるじょあと『ウォッチャー』だった。
辺りは野原が続き、遠くには山が雄大な姿を広げている。
先ほどとはうって変わって平和な風景である。
「おいぼるじょあ……ここはどこなんだよ」
「それは僕にもわからないYO。あの騒ぎだもNO。けどdat落ちしたスレじゃないNE」
「アヒャヒャヒャ!役ニ立タネエナアオイ!」
三つーは笑いながら八つーの身体をよじ登って天辺までたどり着くとようやく満足したようだった。
三ギコも同様に八ギコの頭によじ登って出来るだけ遠くを見ようと試みる。
「八ギコ。お前せっかく八頭身なんだから何とかならねえのか」
「八頭身っつったって見えないもんは見えませんって、ギコさん」
「ソウイエバヨオ、『ウォッチャー』ダッケ?オ前ニハ解ラナイノカ?」
「うーん、見たことはあるんですがねえ……と、あそこに誰かいますね」
「え?」
言われ、指差した方に目を凝らすと、確かに誰かの姿があった。
よく見えないが、ギコ族かしぃ族らしいことはわかった。
「行ってみるぞ。走れ八ギコ!」
「はいはいー」
「俺タチモ行クゾ!」
「ワッカリマシタツーサン!」
走り出す八頭身の足は速い。
その後ろをぼるじょあと『ウォッチャー』が追う。
「……ねえ『ウォッチャー』。今気づいたんだけDO……」
「……この臭いには、出来るだけ近づきたくないんですが……仕方ないですね」
わずかに残る、くすんだ灰の臭い。
※
「……これは……!」
ギコたちは立ち尽くした。
そこは大きな広場だった。
その広場一帯に、死体の山が築かれている。
一部は手足をもぎ取られ、一部は臓物を引き摺り出され、一部は形すら残らず、一部はぶすぶすと煙を吐き出していた。
「……『虐殺スレ』か!」
「噂ニハ聞イテイタガ……ソレ以上ダナ」
「ヒデエナ……」
鼻につく焼けた肉の臭いのせいか、酸っぱいものがこみ上げてくる。
八ギコも三ギコも、ここにしぃがいなくてよかった、と心の中で呟いた。
八つーはやや職人じみた目で辺りを見回した。そしてあることに気づく。
「オイギコ……ヤバクナイカ?コレ」
「そりゃ見た目以上にヤバイだろ」
「ソウイウ意味ジャナイ。ヨク見ロ……得物ガヒトツモネエゾ」
「なに…………?」
「更ニ言ウガ俺タチハギコ系AAダ。後ロ姿ハシイソックリ」
「…………」
「イツ刺サレテモオカシクネエナ」
不敵な笑顔を見せる。
八ギコは呆れた顔でそれを受け止める。
「楽しそうなのはまあ良いが……さっき見つけたしぃ族はどこだ?」
「サアナア……ツーカボルジョアタチハドコダ?」
改めて周りを見渡す。どうやら二人は置いてきてしまったようだ。
すると、八ギコの足元で誰かが名前を呼んだ。
「ギコ君」
「ん?」
「ギコ君ヨネ?」
「ああ」
返事をすれば、どこにいたのか、続々としぃたちが姿を現す。
「ギコ君」「ギコ君」「ダッコシヨ」「ダッコ」「ハニャーン」「マターリシヨウヨ」「マターリ」「ギコ君」「ギコ君」「ギコ君」「ギコ君」
ギコの名を呼びながら集まってくる無数のしぃたち。
彼女達はゆっくりと、しかし力を込めて八ギコにしがみついてくる。
恐らく目標は三ギコ。
「うわあああああ!!」
「ににに逃げるぞ八ギコ!」
このままでは押し倒されてしまうし、そのまま潰されかねない。
どうにか八頭身の力をもってしぃたちを振り払い、そのまま脱兎のごとく逃げ出した。
その後をしぃたちも追いかけていく。
それをつーたちが呆然と見送った後、タイミングを見計らったかのようにぼるじょあたちが追い付いてきた。
「あるぇ?ギコたちはどうしたNO?」
「シイタチニ追イカケラレテイッチマッタヨ」
「おやおや……なるほど、『虐殺スレ』でしたか。これは予想外」
「ソレニシテモ、アノシイタチハイッタイドウシタンダ?アリャ普通ノシイジャネエヨ」
「…………ここが『しぃ虐スレ』だからよ」
振り返れば、小さなしぃがそこに座っていた。
ちぎりとられたのか、片耳で、尾が鉤のように曲がってしまっている。それでも彼女はまともな『しぃ』だった。
「アヒャ?アンタハギコヲ追ッカケナクテイイノカヨ?」
「私は良いわ……あまり足が動かないのよ」
「そういえばしぃなのに全角で喋れるんだNE。めずらC」
「…………オマエ、バグナンダナ。タマニミカケルガ……ヨリニヨッテコノスレカ……イヤ、コノスレダカラ、カ」
「ツーサン、ナニカシッテルンデ?」
「アノナ。虐殺スレノシイハ普通、イマギコヲ追ッカケテイッタミテエナシイバッカリナンダ。マトモナシイノホウガバグナンダ」
「……?」
「……その方が、虐殺しやすいでしょう?そういうことです」
『ウォッチャー』の言葉に、八つーは瞠目した。
「チョットマテヨ!ココノスレノシイハ皆……『殺サレルタメニ作ラレタシイ』ッテコトカ!」
「その通りです」
「『殺ス為』ニ、ワザト普通ノシイヨリ脆カッタリ、アアヤッテスグニ子供ガ出来ルヨウニシテル。頭モ弄ッテチョットオカシクナッテル。ダカラココニイルシイハバグ。歴トシタ、ナ」
「……例え普通のしぃが生まれても、この世界ではすぐにおかしくなってしまう。いっそ普通じゃない方がましだもの」
「…………ダカラ俺ハオ前等ガ嫌イナンダ!!」
三つーが吐き捨てるように言い放った。八つーは驚いて頭の上を見上げる。
「タダ弱イカラッテ言ッテ、何モシナイノハ自分達ダロ!誰カニ助ケヲ求メルダケデ!何ガマターリダ!馬鹿カ!」
「ツーサン、幾ラ何デモ言イ過ギダ」
「ケドッ……ケド、タダ無力ダカラ何モシナイノカ!脆イカラ何モシナイナンテ……逃ゲテルダケダ!」
「……逃げたくて逃げてるわけじゃないYO。多分NE」
ひとり冷静に、そういったのはぼるじょあだ。
三つーは、憎らしいのか後ろめたいのか、そんな表情で彼を見やる。
「僕らは、そのスレの設定からは逃れられない。たとえモナーやモララーでもNE。それがAAなんだと思うYO」
「……ドウシテ」
「そこでは『そうあるように』求められるからじゃないNO?僕だって元は荒らしじゃないC。ただ、『そうあるように』求められたから、今の僕は荒らし。そういうことじゃないNO?」
「…………」
「けど、つーが怒るのも仕方ないC。ここにギコが来なかったら多分ああいう風にはならなかったんじゃないかNA?」
「ソリャマタドウイウコトダ?」
「つまりですね」
遠くで誰かが走り回る音が聞こえる。それ以外に雑音は無い。
「ここに居るべき『虐殺者』……モララーがいなくなってしまった。そして存在しないはずのギコがやってきてしまった。そのために」
これが平和なのかもしれない。けれどこれは、これでは――
「この空間の、秩序が崩れてしまっている。――そういうことでしょう?」
しぃはうなだれた。
5:悲哀 lament
自分がどこにいるのか判らないのはこちらも同様だった。
ここに飛ばされたのはネーノ、フーン、『コネクター』だった。
無論、空気は剣呑そのものだ。
「……おい、あんた」
「コネクター」
「……『コネクター』、ここはどこなんだ」
「知らん。そんなことを考えてる余裕も無かったな。すまん」
「はっ。『接続者(コネクター)』が聞いて呆れるな」
「その言葉そのまま返す。お前もフーン族だろ。折角ある頭を使おうという気にはならんのか」
「…………………………………………」
「ま、ま、ま。取り敢えず落ち着くんじゃネーノ?」
「そうなんじゃネーノ。喧嘩してても始まらないんじゃネーノ」
「フーン。そういうネーノさんはこの状況を打開できる妙案があるとでも?」
「…………八ネーノは」
「……ネノさんに無いんなら俺にも無いんじゃネーノ」
「プ」
「プ」
「プ」
険悪だが他人を嘲笑するときには妙に馬が合っている。
「……何だかひたすらムカつくんじゃネーノ」
「ネノさん、多分怒ってもあいつらにゃ勝てませんて」
まあじゃれ合うのはこれくらいにして、と三フーンが煙草を取り出しながら総括する。
今いる所は崩れかけた建物の中だった。しかし、先ほど八頭身たちが集まった場所とは違って、やけに埃っぽい。
「まずここがどこかを見極めるのが先決、か。おい後輩、何かあるか」
「取り敢えずここから出た方が良いな。これじゃあいつ崩れたっておかしくない」
「……それもそうか。閉じ込められているわけではないようだし」
「――それはやめておいた方が良い」
『コネクター』の指が滑らかにノートパソコンの上を撫ぜていく。
画面には幾つかのウィンドウが開かれ、英語や数列が無数に流れていっている。
それらに目を通しながらの発言は、少々フーンたちの癇に障ったようだ。
「どうしてそう言い切れる?お前にはこの場所すらわからないんだろう?」
「そうだ。場所まではわからない。だがこのスレが何のスレか確かめるのにそれほど時間はかからない」
つまり――と切り出した所までで彼の発言は爆音によって遮られた。
ガラスの嵌っていない窓から衝撃波に乗って砂礫が飛んでくる。
咄嗟に床に伏せてそれをやり過ごしてから、彼は言葉を続けた。
「……ここは、『戦争スレ』だ」
遠くに聞こえる音は恐らく、銃声。
※
とにかく外に出ようというのには賛成だ、と三ネーノは提言した。
「むしろこんな所にいた方が危ないんじゃネーノ。建物の下敷きになる可能性も高いし、第一敵だと思われて殺られるのが関の山じゃネーノ」
「……問題は出てからどこに行くか、か。この調子じゃ非戦闘地域を探す暇なんかなさそうだしな」
「ここから東に2キロほどで戦闘が終わった地域があるぞ」
「フーン……ってどうしてあんたは知ってるんだ」
「だからあんたではなく『コネクター』だと何度……。このスレについての情報を引き出した。私は『接続者』だからな」
そういって、少し前に同じ言葉を言った相手に皮肉った笑みを向ける。
やっぱりこの野郎好きにはなれん、と銜え煙草の八フーンをなだめるのは八ネーノの役目だ。
「取り敢えず、行ってみようじゃネーノ。せっかくの『カミサマ』のお言葉、だろ?」
「フーン……これで死んだら笑い話だな」
「全くそうじゃネーノ」
とにかく、ここにいる悪党の意見は一致した。
※
『コネクター』の指し示した座標には、木々が鬱蒼と茂っていて、ゲリラ戦にはもってこいの場所だった。
所々から硝煙のにおいがする。それと僅かな人の気配。
どこか心霊スポットじみた、じっとりとした嫌な感じに、三ネーノは溜息を吐く。
「ネノさん?疲れたんスか?」
「いや、何だか嫌ーな感じがするんじゃネーノ……」
「フーン。そりゃそこらへんにいろいろいるからだろ」
「いろいろ……?」
「いろいろ。」
「…………え?」
「無駄言吐くな。場所が割れる」
種々の疑問は残れど、『コネクター』に言われては口を閉じる以外に出来ない。
ふと、八ネーノが指さずに、目線だけで方角を伝えると、
「……誰か、いる」
全員に緊張が走る。彼等はまだ、自分の言葉にどんな力があるのか解らない。ゆえに、彼らの唯一の攻撃手段は拳のみだ。
まずは八頭身たちが動く。伊達に狂犬と呼ばれていたわけではない。音を立てないように慎重に、出来るだけ近づく。
そこにいる『誰か』たちの話し声を聞き、会心したかのように口の端を歪めると、指で『こっちに来い』と合図を出す。
「……大丈夫じゃネーノ?」
「まあ、大丈夫でなくてもいざとなったら奴らを囮にして」
「悪だな」
取り敢えず合流してみればその理由は簡単に解るのだ。
「奴さん、ひとりらしい」
「フーン……戦場なのに、か」
「囮じゃネーノ?」
「否。どーもその理由ってやつが、『コネクター』、あんた関連だ」
「……成る程、な」
一言そう呟くと、『コネクター』は気配も消さず、堂々とその『誰か』の所に歩いていく。
皆はその行為に驚きを隠せずにいたが、何か策があるのだろうと止めることはしない。
『コネクター』はそのまま、その人物に、実に気さくに話しかけた。
「……どうも」
「……民間人、か」
「戦争は終わったようだな」
「終わった、か。確かにこの状況を見れば終わったといってもおかしくは無い。全く、おかしなことにな……」
「……私を攻撃したりはしないのだな」
「私をただの一兵卒と一緒にされては困る。これでも大尉で、中隊長だ。身分のある身で、軽率なことは出来ない」
「明らかに怪しい人間だとわかっていても?」
「まさかみすみす殺されるために私の前に現れたわけではあるまい?」
「成る程」
会話の中に含みを持たせつつ、それでも和やかに二人の会話は続いていく。
待っている方は穏やかではない。
しかしそれを知らずか――いや、知っていてむしろ楽しんでいるのだろう――『コネクター』の目はこちらを向かない。向けない。
「……あの野郎、いつまで話し込んでるんだ」
「なかなか意気投合してるじゃネーノ。その前に意気投合してどうするんじゃネーノ」
「もしかすると……武器か?」
「フーン。成る程な。それなら取り入った方がやりやすいか」
而して後に『コネクター』の目がこちらを向いた。口の動きが『来い』と言っている。
そのまま『誰か』と一緒に歩き出してしまう『コネクター』を追いかけて、4人は文句を言いながらも木々の間を駆け抜けた。
※
ついたところは恐らく基地なのだろう。野戦のためのプレハブのような建物の中に通された。
そこからしばらく歩き、開けられた扉の中には銃器の類が所狭しと並んでいる。
「ここにあるものはもう必要の無いものだ。勝手に使うといい」
「こりゃ……また、凄いんじゃネーノ?」
「必要が無い、とは……どういうことで?」
「戦う必要が無くなった、ってことだろ。原因は……モナーやモララーが消えたことに関係がある、か」
八フーンが銃をいじりながら確認のように大尉の方を見ると、彼は硬い表情で頷いた。
「……我々はもともとモナー族とモララー族の連合軍と戦っていたのだ。それが突然、敵軍が姿を消した。この戦いは不戦勝で終わった、というわけだ」
「その割には嬉しそうに見えないんじゃネーノ。寧ろ辛そうに見える」
「――そりゃ、戦争そのものが終わったわけじゃないからな」
八フーンに続き、更に三フーンが言葉を続ける。
「戦争が終わって一息ついたり、喜んだりするのは全部お偉い方だけだ。かたや兵士の戦争は終わらない――」
「――我々はまた戦いの準備をしなくてはならない。戦争が始まれば前線に出なくてはならない。今日笑いあった戦友が明日肉塊になるかもしれない。いつも、いつも、『戦いが終わった』と思っているのは上の人間と、戦争の実態を知らないものたち――」
大尉はゆっくり目を伏せた。彼の瞼の裏に、何が映っているのか。
言葉を止めた大尉に代わって、『コネクター』が口を開く。
「……戦いの最中にいる者たちにとって、戦争は『終わる』ものではない。終わってもなお『続く』ものだ。――時に彼らの夢の中で、メディアの中で、彼らの思い出の中で、戦争は終わらない。戦うことこそが彼らの存在理由になるのだから。まして、だ」
『コネクター』の左目が僅かに引き攣る。
「『戦争スレ』の住民に、戦い無き時間など訪れるわけが無い。秩序が――崩れてしまう」
――このスレは、戦争スレ。
――この世界の秩序は『戦争が続くこと』そのもの。
それに気が付いて、ネーノたちは少し悲しくなった。
6:後悔 remorse
「――皆さん、大丈夫ですか?」
澄んだ声で目を開けた。
八ノーネはぼんやりと霞む目で周りを見やる。すぐそばに三ノーネ。少し離れた所に、既に目を覚ましているしぃたち。それに山崎と、声の主である『クリエイター』。
「……ここは何処だ?」
「恐らく地下スレの一つだとは思うのですが……詳しくは解りません。山崎さん……解りますか」
「すぐにはちょっと判別つけがたいですね。少々席を外します」
山崎は言うやいなや瞬間に姿を消した。これが『荒らし』の本領か。
八ノーネはぐるりと周りを見渡した。そしてある違和感に気づく。
――余りにも、何も無さ過ぎる。
会話も、荒らしも、何も無さ過ぎる。
「珍しいノーネ。ここまで何も無いのは」
「立て逃げされたスレみたいですから……ほとんど流れは止まってますね」
「丁度良い――『クリエイター』、さっき『コネクター』が言っていた、『魔法』について説明願いたいんだが、良いかね」
「……まあ、あの説明で理解しろというのが無理な話でしょうから……」
畸形は苦笑しながら地面に手をついた。それをゆっくり引き上げると、僅かに遅れて地面から棒のようなものが伸びて、丁度良い長さで切れた。それを手に持って、
「実際に『魔法』を使うとこういったことが出来ます。しかし、皆さんの『魔法』にはあらかじめ制限がなされています。それが『科白を言わなければならない』ということです」
「ジャア、ギコ君ダッタラソレガ『逝ってよし』ニナルノネ」
「はい。ギコさんの言葉には『衝撃』の意味が込められています。だから相手に衝撃を与えることが出来る」
「……つまり、他の連中に同じ力はもたらされない?」
「そういうことになります。大雑把に分けると『攻撃型』と『守備型』に分けられます。しぃさんたちは治癒の力、ノーネさんたちには防御の力があるはずです」
三ノーネは手を開いたり閉じたりを繰り返している。どこと無く子供のようで面白い。
三しぃははたと気が付いたように問いかけた。
「思ッタノダケド……山崎君ハドウシテ科白ヲ言ワナクテモアアシテ力ヲ使エルノ?ソレトモモトモトカラ使エルノ?」
「もともと使える、というのが正しいです。山崎さんや、他のAAの中にもそういった設定がある方がいます。モララーさんはスレの中でそういう設定があるはずですし、三頭身しぃさん、あなたも使えるでしょう?」
「エ?」
「≪httpレーザー≫ですよ。あれは本来ちびしぃの頃しか使えないという制限があるのですが……いまはその制限はありません。三頭身しぃさんでも使えますよ」
『クリエイター』は造った棒を更に変形させながら微笑んだ。
三しぃは信じられないといった顔をして自身の手を覗き込んだ。しぃ族の中にどんな制約があるのか知らないが、本来あるはずの無いことが有り得るといわれたときの反応としてはこんなものなのかもしれない。
ふいに、閑散としたスレの中から大声があがった。
「……誰かいるのか?」
「叫び声なノーネ……誰か捕まりかけているのかもしれないノーネ」
先ほどの闇色の怪を思い出して、一同はその誰かを探してスレの中を駆けた。
隠れる場所が少ないはずなのになぜか見つからない。
『クリエイター』だけがそれを傍観して、手の中の棒を細く長い指揮棒のようなものに変形させていた。
「どうしたんですか皆さん?」
「うわっ!」
突然山崎が顔を出した。驚いて立ち止まる。
「いきなり出てくるな!心臓に悪いだろうが」
「そりゃどうもすみません。ところで皆さん、走り回ってどうしたんですか?」
「誰かがいるんだ。このスレに。見かけなかったか」
「……そんなわけ無いでしょう。僕らじゃないんですから」
「は?」
「ここには初めから誰もいないんですよ?スレとスレの間を移動できるのは『荒らし』だけなんですよ?ぼるじょあか『コネクター』たちでもない限り、そんなことは出来ません」
そこまで聞いて、ノーネたちは顔を見合わせた。
空耳――というわけではあるまい。大勢が聞いている。
ではいったい誰が?
「山崎さん、他にもいるんです。スレとスレの間を移動できるのは」
「……それこそ初耳ですね。どなたですか」
「多分――」
『クリエイター』は棒を振った。
棒の軌跡が煌いて、扉の形を作る。
持っていないほうの手を押すように前に突き出すと、音も無くその扉は開いていった。
開いた扉から、つんのめるように男が飛び出してきた。
手にはノートパソコン。フーン族の顔をした彼は、まさしく、
「――兄者サン!」
「あ――」
その顔は普段と違い、恐怖によって歪んでいる。
脱力したように座り込んだ彼の肩に手を置き、八ノーネは静かに、
「――どうした。話してみろ。ん?」
「あ……っ、う……」
何度も何度も呼気を飲み込み、震えを抑えるように手をぎゅっと握りこんで、
「おと……弟者が、弟者が……連れて行かれた!」
『クリエイター』の表情が固まる。しぃたちも息を呑んだ。
「いきなり、何だか解らないものが出てきて……俺には何も出来なかった。何も出来なかった!」
ぽろぽろと、涙が地面をぬらす。
「俺は、弟者の、兄なのに……何も出来なかった!」
兄者はただ泣いていた。
誰も、何も言うことが出来なかった。
責めることも、慰めることも出来ぬ。
兄者はただ泣いていた。
※
「――彼が、スレを移動できるAAですか」
「はい。彼は――彼らは『ウォッチャー』の性質を持っていますから」
「成る程……出演者であり閲覧者でもある、ということですか」
山崎は得心して彼を見やる。フーン族の彼は落ち着きこそ取り戻したものの、落胆は抑えようが無い。
誰の顔も見ようとはしない。ただ、地面と自分の手を見つめている。
その僅かに先に、ノートパソコンが一つ。
「………………言っておくが、誰もお前を責められんぞ」
八ノーネは語りかける。
「だが優しい言葉をかけてやれるわけじゃない。かけようとも思わん。それでもまだ泣いているつもりか?」
「…………」
「お前と同じ状況になったとき、他人を助けられるかと問われれば、出来ないだろうよ。だがな、この後どう動くか、はお前次第だ」
「……俺、次第」
「どうする。ここで何もせずに泣いている意気地無しになるか。それとも弟を助けに行くか。前者ならこのままお前をほっぽらかして俺たちは進む。後者なら――協力できる」
兄者は微動だにしなかった。ゆっくりと、幾度か瞬きを繰り返す。
「俺は……」
「うん?」
「……解らない。俺は、俺が、どうしたらいいのか解らない」
兄者の手が、ノートパソコンに触れる。
「俺が知っているのは、これを使うこと、ブラクラを踏むこと、それぐらいしか知らない。俺になにができるのかも解らない」
「じゃあ、どうするんだ。決めてみろ?」
「……いま、一人でいるのは、いやだ」
僅かだが彼の身体は震えている。
「いまは、ひとりには、なりたくない……できるなら、弟者も、助けたい……」
「……そうか」
八ノーネはそう言ったきりだった。
しぃたちは戸惑いを隠せない。『クリエイター』も難しい顔をして黙ってしまった。
――そして、その時、兄者の背中についていた黒いごみのようなものが、有機的な動きで体内に潜り込んでいくのに気づいたものは誰一人としていなかったのだった――。
≪the another side #2≫
「うーん……いったい、ここはどこなんでしょうか。参ったな、今日は愛しのハニーとディトの約束が……」
薄暗い闇の中で、八モララーはひとりごちた。
目の前には結構な太さの金棒が均等な幅で並んでいる。これでは外には出られまい。
兄が消えたことと関係がありそうだ、と腕を組んだ。
「どちらにしろ、この状況では何も出来ませんね……外に出られなければ何も……」
「じゃあ外に出れたら協力してもらえるね?」
聞こえてきた声に、あわててそちらを振り向く。
いたのは、楽しげに笑っている三モララー。
「モ……モララーさん!モララーさんもいたんですね」
「まあね。状況は君とそれほど変わらない。いつの間にかここにいたんだよ」
三モララーは檻の端で、なにやらごそごそと手を動かしている。
「どういう理由があってかは知らないが、私をここに閉じ込めた罪は重いね。誰であっても」
「あのー……何をしてらっしゃるんですか?」
「ピッキングだよ」
「はあ?」
「こういうときに一芸があるといろいろ便利でね。靴の裏に針金を仕込んで置いたんだよ」
成る程、三モララーは器用に手を曲げて鍵穴をいじっている。
呆れながらも感心しつつ、八モララーは自分の閉じ込められている折を見渡す。そして、
「モギャー」
「……ジャスティスマスター?どうしてこんな所に……、まさか」
八モララーは身体を竦めた。ジャスティスマスターのいる所には、どこからか厄介な副産物が訪れる。
あれが現れては余計に面倒だ。出来れ
それは突然訪れた。
ある日、世界からモナーたちが消えた。
正確に言えば『オマエ・モナー』を基本とする、八頭身及び六頭身などを含めたモナー族が姿を消したのだった。
それも、『モナー』を名前に持つAAだけが。
何か、得体の知れないものが、あの胸焼けを起こしそうな、全てに平和を与える笑みをこの世界から消し去ってしまったのだった。
1:困惑 perplexity
ある日突然起こったその出来事に、八頭身本家次男の八ギコは戸惑いを隠せずにいた。
かつてこの世界でこんな出来事があっただろうか?
先日、不意に気づいたときには八モナーの姿は消えていた。
覚えている、彼があの間の抜けた声で意味も無くラルクを語っていたのを。
それが、今では遠い昔のようで。
不意に肩をたたかれた。
「ギコ兄」
「……フーンか」
この同居人は相変わらずすました顔をしている。
何故だか、むしゃくしゃする。くそ。これもみんな兄貴がいなくなったからだ。
意味も無く、八フーンを睨みつけた。
「気づいたか?――今日、モラ兄まで消えた。街にいるモララー族も、全員だ」
「…………っ!」
「このままだとギコ兄が消える日も来るかもしれないな」
八フーンは煙草に火をつけ、その紫煙をゆっくりと肺に流し込む。
「……あの騒動のときでさえも、こんなことは無かったのにな」
あの騒動とは、かつてギコやモナーが企業に囚われかけたときのことである。
それは、関係が薄い八頭身や六頭身にまで被害が及んだものの、すぐに事態は回復を見せた。
新しく『タカラ』がAAとして生まれ、今ではもうこの世界にすっかりなじんでいる。
しかし、今の事態はそれとはまた違う様相をなしていた。
どこかが、おかしくなってきている。
「……よく考えれば、珍しいな。お前、大体こういうときは俺やモララー、兄貴にも何も言わずに動いてるってのに……どんな風が吹いたんだか」
「手を打ちたいのは山々なんですがね……どっかの過保護の馬鹿が、ショックが大きすぎて使い物にならねえんだよ」
ああそうだろうな、と八ギコは納得した。彼は子供たちに何かがあったら、すぐに行動を起こすかしばらく動けないかどちらかだろう、と推測できたからだ。
「それはそうと。ギコ兄、ちょっと付き合ってくれない?」
「何だゴルァ」
「いろいろ、ね。ああ、しぃやつーも呼んできて欲しい」
「……パシリじゃねえかゴルァ」
「まあそうともいう」
――まあとにかくちょっとそこまでだからいいだろう?
八フーンはそういって、策士の笑みを浮かべた。
※
部屋の中に、ぽつんと星型の髪飾りが落ちている。
八ネーノはそれを手にとって、消えた子供のことを思っていた。
星シーンや>>1もさすがにこの事態を知って混乱した。しぃと一緒にどうにか落ち着きを取り戻したのは先ほどのことだ。
困惑と、奇妙な恐怖。痛いほどの寂しさ。
かつての自分はこんな感情を抱いたことがあっただろうか。
誰かの小さな手が、背中を叩いた。
「……元気出して」
「モラはきっとすぐに帰って来るんじゃネーノ?」
「チョットドコカニ出カケテイルダケヨ。落チ込マナイデ」
「皆……」
子供たちが、一生懸命に自分を励ましてくれる。自分達も不安でたまらないだろうに。
――俺がしっかりしなくちゃ駄目なんじゃネーノ。
「――うん。そうなんじゃネーノ。ごめんな心配かけて」
わしわし、と子供たちの頭を撫で回す。――もう一人の子供がいないことが心に僅かな細波を生む。
あの子を探しに行かなければ。俺はあの子の保護者なんだから。
そう決意したとき、不意に玄関からの涼やかな音が耳に入った。
誰か人が来たのか。こんなときに、いったい何なんだ。
「はーい、どなた……と」
「だいぶ元気そうで何よりだが」
半分ほど開けたドアを、来客は無理やりこじ開ける。
「いよう」
「ノーネじゃネーノ。どうしたんだよ」
「ガキたちは八シーンに任せてちょっと顔出し願いたいんだが……どうだい」
「どんな御用で旦那」
「お前の家族に関わる用事。断ることは許さないノーネ」
この大人が関わっているとろくなことにはならない。
そのことは知っていたが、断る気にはならなかった。
2:謀略 stratagem
「これで全員だな」
八フーンが人数を数えて言った。
集まったのはいずれも八頭身の、ギコ、しぃ、つー、ネーノ、ノーネの5人。
「全員っていっても随分少人数なんだな」
「大人数いたって動けないのならいる理由が無い。それにあまり大人数で動いたら逆に眼を引くことになるからな」
八フーンは八ギコの問いに答えながら携帯電話をいじる。誰かと連絡を取っているようだ。
何度かのバイブレーションの音の後、
「じゃ、こっちだ」
※
着いたところは街外れのビルの中。
今にも崩れそうなその建物のバリケードを破り、不法侵入を果たす。
どちらにせよ人通りも無いこの場所は、秘密の会合に最も適した場所だった。
中は真っ暗なわけではなく、ところどころから光が漏れている。窓が割れているのか、建物の壁自体に問題があるのかまでははっきりしない。
八フーンはその中を迷い無く進んでいった。後ろから仲間達がそれを追いかける。
未だに彼の意図ははっきりしない。八ノーネは何か知らされているようだが、自分達に教えるつもりは毛頭無いようだ。
八ネーノは少し腑に落ちずに、それでも後を付いていった。
錆付いた音を立ててドアが開く。
「随分遅かったですね。迷ってたんですか」
「この場ですり身になりたいというなら別に躊躇しませんが何か?」
「相変わらずですねえあなたも」
目だけが笑っている、八頭身のAA。
「おいフーン!そいつ山崎じゃねえかゴルァ!なに考えてやがる」
「いたってまともですが?」
「そういう意味じゃない。そいつは『荒らし』だろ。今この状況で一番問題を起こす存在だ。どうして奴がここにいる?」
「心外ですね。僕はいつでも荒らしをしているわけじゃない。なにせこの状況を把握して、それでも荒らしをして何になるというのですか」
「アヒャヒャヒャ!全クダナ。ソレニフーンダッテ何モ考エズニ山崎ト手ヲ組ンダワケジャネエダロ?タダノ馬鹿ジャネエンダカラ」
「……ま、取り敢えず話を聞こうじゃネーノ?決めるのはそれからでも遅くない、そうだろフーン?」
八ネーノの言葉に、彼はただ口の端を吊り上げた。
それを皮切りに、八ノーネから言葉が出た。
「……『荒らし』故の特殊性を利用しようってハラか?」
「まあそんなところだ。流石、年寄りは話が早くて助かる」
「…………『荒らし』の特殊性?」
聞いた事のない言葉に、今度は山崎から答えが返ってきた。
「あなたたち普通のAAと、僕達のような『荒らし』のAA、その違いは何だと思いますか?」
「うー……ん?基本的には何も違わないように思えるけど」
「『荒らし』のAAは、どのスレにも――やや悪意的な意味合いが加わりますが――出現できるということです。つまり、板やスレによって存在を制限されることが無い」
「ソレハ変ヨ。荒ラシヲスレバ皆カラタタカレルモノ。コレハ存在ヲ制限スルコトニナルデショウ?」
「その発言をした『名無し』が叩かれることはあれど、僕達AAのみに関していえば自由です。更にスレを自由に行き来できるのは『荒らし』だけに持たされた能力のようです。――さて、この能力を使って何が出来るでしょうか?」
「……まさか、消えたモナーやモララーを探し出すことが出来る?」
いってから、八ギコは信じられないといった表情で考え込んだ。もしくは彼の能力を知ったうえでも、手を組みたくないという思いが強いのかもしれない。
「それで手を組んだってこと?俺にはそれだけで全てが終るとは思えないけど」
「正確に言えば探し出すことは出来ないかもしれないというのが事実なので、この事件が解決するわけではありません」
「?」
「……ま、口で説明するのはややこしいですね」
山崎はそういって八フーンのほうをちらりと見る。彼が勝手にしろ、と言いたげに首を振ると、笑顔を更に深めた。
「では始めましょうか。全部で6人ですね?それでは」
山崎はぱちんと指を鳴らした。
床に入っていたひび割れの、ちょうど円になっている線部分だけが発光する。
「お連れいたしましょう。世界をつなぐ狭間の世界へ」
視界が闇へと反転した。
≪the another side #1≫
「わーん。ここはどこなんだよ!俺はラルクのライブに行った筈だったのにぃ!!ここから出せぇ!!」
がしゃんがしゃんがしゃんがしゃん。
八モナー――正真正銘八頭身一家長男である――が、閉じ込められている檻を両手で力いっぱい揺さぶった。
檻は壊れない。八頭身の力をもってしても壊せないとは、どれほど頑丈な檻なのだろうか。
しかし八モナーはそんなことは気にしない。壊せなくてもそれでも頑張る。それがラルク魂。
そしていくら魂を語った所で物質の硬度が変わるわけでもない。
「うー。酷いやみんな。兄さんを独りにしてえ。きっとおいしいものを食べに行っているに違いないんだ。特にフーン!あいつだ。あいつがきっと実行犯だ!よおし、帰ったらお仕置きしちゃうぞ!」
「それは無いですね。彼はそんなことをするような人じゃありませんし」
いきなり後ろからかけられた声に大袈裟に驚いて、八モナーはゆっくりと振り返った。
「始めまして。八頭身モナー(裏)です」
自分と全く同じ顔。
「…………っっっっっ!!!!!どどどどど」
「大丈夫ですよドッペルゲンガーじゃありませんから。僕とあなたは同じモナー族です。だから同じ顔なんですよ」
「は、あ……」
「ああ、どうして同じ顔が二人、ここに居るのか、ということですか。それは僕にも判じかねますね。ただ僕がいるスレとあなたがいるスレでは雰囲気というか、八頭身モナーの役割が違うからでしょうか」
「役割?」
「あなたはどちらかといえばお笑い担当。ギャグ専門。どちらかといえば上層スレの住人。僕は反対にシリアス専門。主に地下スレにいます。――ここまで性格が違うのだから、別人だと考える方が正しいでしょう?」
「んんん?うーん……なんとなく解ったような気がするけど……」
――そうか。きっとラルクってことなんだな。うんそうだ。そうに違いない。
自分なりの(間違った)結論で思考を一回リセットさせると、改めて自分の疑問を口に出した。
「じゃあ、なんであなたと俺とが同じ場所にいるんでしょう?今の説明だと、俺とあなたとは同じスレにいるのはおかしいはずです。なのに今、同じ場所にいる。これって?」
「それは解りません。ただ、ここに連れてきた誰かの思惑なのは確かなようですよ?」
「誰か?やっぱり誰かいるんですね。誰なんでしょう」
「さあ。まあ、しばらくゆっくり過ごしましょう。果報は寝て待てとか、急がば回れとか言うことですし。ね」
確かに何もやることが無いのは確かである。
八モナー(裏)は柔和な笑顔で相手の二の句を妨げた。
3:召喚 summons #1
「……こんなことになるとは聞いてないぞ山崎」
「そりゃ僕も言ってませんもん。当たり前ですよ」
暗転した後、八頭身たちはトンネルのような光る空間を落ちていっていた。
いや、それは昇っていっているのかもしれない。それとも横に飛んでいるのかもしれない。上下の区別が無いこの空間ではどうにも表現しがたい感覚である。
「聞いてないって、いったい何を聞いてたんだよ」
「モナ兄を探す手伝いをすること。それに協力者がいること。確実性は高かったし、特に損をするような条件でもなかったから、構わんと思って引き受けた」
「条件?」
「お前らを呼んでくること。ひとりだと面倒だからノーネにも手伝ってもらった」
「じゃあ、どうしてそんなに怒ってるんだよ。珍しいんじゃネーノ?」
「……今日は『セーラーフーン劇場版』の放送日だ」
「…………」
「…………録画しそびッた……」
あえてノーコメントである。ついでに顔もそむけてみる。八フーン族の考えることは想像の範疇を軽々飛び越えていく。
とにかく今は、これからどこにたどり着くのかが問題である。
「もうすぐですよ。着いたら殴るでも蹴るでもしてくれてけっこうですから、今はおとなしくしてくださいね。命の保障は出来かねますから」
山崎の言葉に暴れる気も失せた。とにかく、床があるところに着いたら狂犬組の恐ろしさを見せてやる。
そう決意して、八ネーノは流れに身体を任せる。
こうなったらなるようになれだ。何が起きても基本的にはいいんじゃネーノ?
※
突然床が現れた。気が付けばそこに立っていた。
相変わらず回りは不思議な光が飛び交っているが、なぜか目に煩いわけではない。
ただ、自分という存在がこの場にふさわしくないような、そんな気になってきていた。
「いわれた通りお連れしましたよ。ぼるじょあはまだのようですね」
「もう着いたYO。山崎の方が早かったNE」
声がすると同時にもう一人の『荒らし』――ぼるじょあが姿を現した。彼は三頭身の姿だ。
そしてぼるじょあの後ろに、何人かの三頭身が姿を現す。
その姿は――ギコ、しぃ、つー、フーン、ネーノ、ノーネ。
奇遇にも八頭身たちと同じメンバーがそろっていた。
「やはりそちらでもその6人ですか……」
「『コネクター』の言うとおりだYO。まあ、これで僕らの仕事は終わりだNE」
「いやはやまったく、お疲れ様です。山崎君、ぼるじょあくん」
ここに居る、知っているもの以外の声がした。
見れば、何故先ほど気づかなかったのだろう、円卓と三人の風変わりなAAが座っていた。
一人は、八頭身の、恐らくモナー系の種族で、目に幾重にも包帯を巻き、燕尾服を着て紅茶か何かを啜っている。山崎たちに声をかけたのは恐らく彼だ。
もう一人は三頭身で、通常一つきりの耳朶が同じところから二つ生えている畸形(きけい)。だが向かって右の耳はどうしたのか、その姿を見せることは無く、代わりに金属板が頭蓋に沿ってそこを覆っていた。マントのようなものを羽織り、同様に紅茶を啜っている。モナー系の種族のように見えるが、ギコ系の種族特有の長い尾が二本生えていた。
最後の一人は六頭身、顔つきだけならフーン族で、それでいて向かって右目に、縦に切られたような傷跡を残している。そして彼は拘束服でいて器用にノートパソコンを操っているのだった。
それは見かけにも――
「――――兄者か?」
「否定する。私はあくまでもこの姿を借りているだけだ。必要なら変えるが」
兄者もどきが硬い返事を返した。しかも目線すらこちらには向けない。
――これは流石家というよりフーンの腹違いの兄弟か何かって言われた方が納得するんじゃネーノ。
八ネーノの心の思いはあえて口に出されることは無い。
「『コネクター』。失礼でしょう。ちゃんと挨拶ぐらいしたらいかがです」
「何だ。もうそろったのか。それならそうと早く言え」
そして戸惑っている大勢に向かって、
「席に掛けたまえ。適当で良い。説明が長くなりそうだからそのつもりでいるように」
「……だいぶ偉そうだなあんたは」
「偉そうじゃない。偉いんだ」
誰かが発したそんな呟きに平然と答える。ここまでだと寧ろすがすがしい。
有無を言わせぬ声に、皆がぱらぱらと席に着くと、目を隠した八頭身が話を始めた。
「どうも、始めまして、皆さん。私達は今回の事態を重く見て皆さんに集まっていただきました。だから何をするかというのはもはや決まっています」
そういって彼は一呼吸置いて、
「――皆さんには、僕らの手足になっていただきます」
よく通る声をしていた。
※
「納得できねえなあ」
そういったのは三ギコだ。思えば八頭身たちが(一部を除いて)どこか恐縮している中で、三頭身たちはどこか落ち着いた雰囲気を保っている。
「手足になれだと?今回の事態というのは恐らく――モナーたちが消えたことにあるんだろうが。俺たちに十分な説明もなしに手足扱いは無いんじゃねえのか?」
「ギコの言うことに一理有りじゃネーノ。第一、あんた達はいったい誰なんじゃネーノ?」
そういわれて3人は少なくとも戸惑ったようだ。
数秒の沈黙の後、口を開いたのは六頭身の彼だった。
「……我々は概念を象徴させた人格だ」
聞きなれない単語の連続に、思わず全員からハテナマークが飛び出る。
「あそこの畸形は『クリエイター』。物語を作る者たちの概念の象徴。よく『ネタ』とか『ネ申』という言葉で表されるものを実体化させたものと考えて良い。
八頭身は『ウォッチャー』。物語を見る者たちの概念の象徴。閲覧者の総合意思とも表現できるが、ニュアンスが変わってくるためにここでは『観察者(ウォッチャー)』としておく。
私は『コネクター』。作品と閲覧者を繋ぐものの概念の象徴。解りやすく例えれば回線のようなものだ。
――我々が何なのか。これがその質問の回答になるな?」
「……異議無しじゃネーノ」
「次は恐らく、『何故手足にならなくてはいけないのか』だろうな。
――我々ではこの問題に干渉できないからだ。我々はあくまでも『概念』でしかない。実際にこの問題を解決できるのは貴殿等だけだ。我々ができるのはそれを手助けすることのみ」
怒涛のように並べられていく言葉をその場で理解しているものは少ない。
その中で、三フーンがプ、と吹き出した。
「フーン……。だいぶ偉そうなことをいっていたわりには何も出来ないということですか。それで手足になれだと?
――――ふざけるな!」
「そうだ。我々には何も出来ない。だから貴殿等を呼び出すのに山崎たちを使わざるを得なかった。しかし、こう考えていただきたい。――我々が干渉せねばと思うほど、事態は切迫しているのだ、と」
「…………」
「まあ、その点は軽く無視する。異議は聞かん。もし受け入れられない場合は……消えたAAたちは戻ってこないだろうな」
「脅す気か」
「順当に想像した結果だ。我々には何も出来ないのだから」
我々についてこう考えてくれても良いだろうな、と『コネクター』は呟く。
「むしろ神だと」
「「うわあむかつく」」
「文句は小声で言いたまえギコ氏等」
三ギコ・八ギコの両方から出た言葉にさらりと突っ込みをいれつつ、
「それより本題だ。今ここにいるメンバーに、ある力を解放する」
そういった瞬間から、『コネクター』の手はものすごい速度でキーボードの上を滑り出した。
≪PROGRAM NORMAL カラ SPECIAL ニ CHANGE:EFFECT Lv.1 カラ Lv.2 マデ EXTENSION ……PROGRAM RUNNING!≫
3:召喚 summons #2
ふー、と八フーンが紫煙を吐き出した。
「……何も変わらないぞゴルァ」
「ははは。三頭身ギコさん、ちょっと良いですか?」
「何だゴルァ?」
「山崎君に、『逝って良し』、やっていただけますか」
「僕にですか!勘弁してくだ……」
「解ったぞ」
軽く引き受けて、やや後ずさりする山崎に向かい、懇親の力を込めて、
「≪逝って良し≫!!」
「ぐはぅ!!」
衝撃波による轟音と、山崎が弧を描いて吹っ飛んでいくのが見えた。
皆が驚きに声を呑む。あのつーたちですら何を言うべきか言葉を失ったままだ。
「見ての通り、貴殿等の決め台詞に反応して発動する。有り体に言えば『魔法』だな。全てについて説明するのは面倒だから各自で発見してくれ」
「そんな適当な……」
「……ま、良いんじゃネーノ?」
「なるほど……確かに手助け、だな。それ以上に言うことは無い」
納得する三頭身。
「そういえば、山崎たちの『荒らしの特殊性』だったか、あれも同じような原理なのか」
「彼等の力はむしろ私の力に近い。スレとスレの間を繋ぐのだから」
『コネクター』に言われて、軽く疑問に思っていたことが解消する。
ふいに、『クリエイター』が口を開いた。
「私からも、皆さんに渡さなければならないものがあります」
言うと、小さな手の中から、淡く発光している糸を取り出した。
「これを、皆さんに結びます。原型が同じAA同士で手を出してください」
言われ、それぞれが手を差し出す。
糸はその手に触れると、先がとけるように手のひらに吸い込まれていった。そうやって二人ずつ結ばれていく。
「だから同じAAが集まったわけか」
「で、これでいったいどうするんだ?」
「無論二人ペアで行動してもらうため。さっきの力は、同じ種族が集まっていると相乗効果でより強いものになる。一人ひとりで行動してもらうよりこちらの方が些か都合が良い」
「フーン。まあどちらにしろ――俺たちに何をやらせるつもりだ?」
「それは……」
突然、空間が歪んだ。
床や、テーブルや、そのほかさまざまなものがぐにゃりと歪んでいく。
そして風船がはじけるような音とともに、その空間に裂け目が生まれた。
裂け目の先は、漆黒の闇。
「――まずい、この空間がばれたのか!」
「山崎君、ぼるじょあくん、それぞれ解っていますね!」
「あいYOー」
「大丈夫です」
その闇の中から、触手じみた物が溢れてきた。しかもそれはまっしぐらにフーンたち、そして『コネクター』に向かっている。
あわててそれをよけながら、『コネクター』は叫ぶ。
「――そうか、次の獲物はフーン族か!全く油断した……おい、準備はいいな!!」
「「了解!」」
山崎とぼるじょあの返事を聞いているのかいないのか、再びその指はキーボードをなめていく。
≪COMMAND 転送 STAND BY...FIRST:GIKO_TWO_WATCHER_BOLJORE SECOND:FUUN_NENO_CONNECTOR THIRD:C_NONE_CREATER_YAMAZAKI ……PROGRAM RUNNING!≫
「説明している時間は無い。取り敢えず転送する。≪接続(connect)!≫」
彼の言葉が終わるやいなや、先ほど、この場所に来る前に体験した感覚が全身を襲う。
「本当に乱暴だな……」
「まあ仕方ねーな。時間は確かに――無い」
「さて皆さん、喋っていると舌を噛みますよ――」
重々しく世界がひしゃげた音を立てたとき、彼等はその場から姿を消していた。
※
その頃、街からはほとんどのモナー系AAが姿を消してしまっていた。
八マララーは特に何をするでもなく、道を歩いていた。
「はあ……モナ兄さんも、モララー兄さんもいなくなってしまった……ギコ兄さんやフーンさんたちは帰ってこないし、フサ君はカバディだし、ヒッキーやジエンはいつも通り……僕、どうしたらいいんだろう」
先生スレを動かすことは出来ない。出演者が消えてしまったのもあるし、監督やADの殆どは姿を消してしまった。
手持ち無沙汰にもほどがある。
それでも何故だか足はスタジオの方へと進んでいく。
そして、先生スレの撮影スタジオの扉を開けた。
「今日はー。って誰もいるわけが……っ!」
八マララーは目を見張った。
恐らく、監督が。
ADが。
カメラマンが。
モナー族、モララー族、フーン族の三頭身たちの顔に、丸い仮面のようなものが張り付いている。
顔の輪郭に沿って丸く削られただけの板に、目の部分だけがくりぬかれている。
荒っぽい作りであるそれは、だがぴったりと、その顔にくっついていた。
「……み、皆さん……仮面舞踏会でも……?そんなわけ、無いですよね……」
そしてその問いかけに答えずに、彼等はただそこに存在している。
――尋常ではない。
恐怖に似た戦慄が、ゆっくりと八マララーに浸透していった。
※
一方、八ネーノの自宅では、八シーンが子供を元気付けようと奮闘していた。
すっかり子供たちは意気消沈してしまっていて、いつも振り回される立場の彼はその様子に戸惑いを隠せなかった。
「……大丈夫だよ……ネーノも、モラも、すぐに帰ってくるから……」
「じゃあ、いつ帰ってくるか教えて欲しいんじゃネーノ!」
「……そ、れは……」
「……答えて欲しいんじゃネーノ……」
>>1は、むしろ答えを期待していないような様相で、暗く沈んだ空を見上げた。
もうすぐ、雨が降ってくるかもしれなかった。
そのとき、ふいに扉の開く音が聞こえた。
「ネーノ?もしかして……モラじゃネーノ!」
「……本当!」
「チョット行ッテミルワネ」
しぃが玄関に向かおうと足を速め――
すぐに、止めた。
「どうしたんじゃネーノ?」
「……しぃちゃん?どうしたの?ネーノじゃ……っ」
訝しげに思った八シーンがしぃの視線の先に目をやり、声を失った。
星のステッキを持った三頭身。
ここまでなら、いつもの星モラと一緒だった。
しかし、八シーンの声を奪ったのはその顔に張り付いた仮面。
くりぬかれた二つの眼は、無表情な中に、一種の違和感を生み出していた。
「……モラ、なの……?」
星シーンが近づいていく。しかしその足も途中で止まった。
いつも無表情な彼が珍しく、泣きそうな顔をして、
「……モラじゃない……誰?…………誰!?」
誰もその言葉に答えるものはいない。
×××注意×××
この先には、グロテスクな表現が含まれています(虐殺スレの表現のため)。
生温いとはいえど残虐表現に抵抗のある方は回れ右です。
4:犠牲 sacrifice
そのスレにたどり着いたのはギコとつー、ぼるじょあと『ウォッチャー』だった。
辺りは野原が続き、遠くには山が雄大な姿を広げている。
先ほどとはうって変わって平和な風景である。
「おいぼるじょあ……ここはどこなんだよ」
「それは僕にもわからないYO。あの騒ぎだもNO。けどdat落ちしたスレじゃないNE」
「アヒャヒャヒャ!役ニ立タネエナアオイ!」
三つーは笑いながら八つーの身体をよじ登って天辺までたどり着くとようやく満足したようだった。
三ギコも同様に八ギコの頭によじ登って出来るだけ遠くを見ようと試みる。
「八ギコ。お前せっかく八頭身なんだから何とかならねえのか」
「八頭身っつったって見えないもんは見えませんって、ギコさん」
「ソウイエバヨオ、『ウォッチャー』ダッケ?オ前ニハ解ラナイノカ?」
「うーん、見たことはあるんですがねえ……と、あそこに誰かいますね」
「え?」
言われ、指差した方に目を凝らすと、確かに誰かの姿があった。
よく見えないが、ギコ族かしぃ族らしいことはわかった。
「行ってみるぞ。走れ八ギコ!」
「はいはいー」
「俺タチモ行クゾ!」
「ワッカリマシタツーサン!」
走り出す八頭身の足は速い。
その後ろをぼるじょあと『ウォッチャー』が追う。
「……ねえ『ウォッチャー』。今気づいたんだけDO……」
「……この臭いには、出来るだけ近づきたくないんですが……仕方ないですね」
わずかに残る、くすんだ灰の臭い。
※
「……これは……!」
ギコたちは立ち尽くした。
そこは大きな広場だった。
その広場一帯に、死体の山が築かれている。
一部は手足をもぎ取られ、一部は臓物を引き摺り出され、一部は形すら残らず、一部はぶすぶすと煙を吐き出していた。
「……『虐殺スレ』か!」
「噂ニハ聞イテイタガ……ソレ以上ダナ」
「ヒデエナ……」
鼻につく焼けた肉の臭いのせいか、酸っぱいものがこみ上げてくる。
八ギコも三ギコも、ここにしぃがいなくてよかった、と心の中で呟いた。
八つーはやや職人じみた目で辺りを見回した。そしてあることに気づく。
「オイギコ……ヤバクナイカ?コレ」
「そりゃ見た目以上にヤバイだろ」
「ソウイウ意味ジャナイ。ヨク見ロ……得物ガヒトツモネエゾ」
「なに…………?」
「更ニ言ウガ俺タチハギコ系AAダ。後ロ姿ハシイソックリ」
「…………」
「イツ刺サレテモオカシクネエナ」
不敵な笑顔を見せる。
八ギコは呆れた顔でそれを受け止める。
「楽しそうなのはまあ良いが……さっき見つけたしぃ族はどこだ?」
「サアナア……ツーカボルジョアタチハドコダ?」
改めて周りを見渡す。どうやら二人は置いてきてしまったようだ。
すると、八ギコの足元で誰かが名前を呼んだ。
「ギコ君」
「ん?」
「ギコ君ヨネ?」
「ああ」
返事をすれば、どこにいたのか、続々としぃたちが姿を現す。
「ギコ君」「ギコ君」「ダッコシヨ」「ダッコ」「ハニャーン」「マターリシヨウヨ」「マターリ」「ギコ君」「ギコ君」「ギコ君」「ギコ君」
ギコの名を呼びながら集まってくる無数のしぃたち。
彼女達はゆっくりと、しかし力を込めて八ギコにしがみついてくる。
恐らく目標は三ギコ。
「うわあああああ!!」
「ににに逃げるぞ八ギコ!」
このままでは押し倒されてしまうし、そのまま潰されかねない。
どうにか八頭身の力をもってしぃたちを振り払い、そのまま脱兎のごとく逃げ出した。
その後をしぃたちも追いかけていく。
それをつーたちが呆然と見送った後、タイミングを見計らったかのようにぼるじょあたちが追い付いてきた。
「あるぇ?ギコたちはどうしたNO?」
「シイタチニ追イカケラレテイッチマッタヨ」
「おやおや……なるほど、『虐殺スレ』でしたか。これは予想外」
「ソレニシテモ、アノシイタチハイッタイドウシタンダ?アリャ普通ノシイジャネエヨ」
「…………ここが『しぃ虐スレ』だからよ」
振り返れば、小さなしぃがそこに座っていた。
ちぎりとられたのか、片耳で、尾が鉤のように曲がってしまっている。それでも彼女はまともな『しぃ』だった。
「アヒャ?アンタハギコヲ追ッカケナクテイイノカヨ?」
「私は良いわ……あまり足が動かないのよ」
「そういえばしぃなのに全角で喋れるんだNE。めずらC」
「…………オマエ、バグナンダナ。タマニミカケルガ……ヨリニヨッテコノスレカ……イヤ、コノスレダカラ、カ」
「ツーサン、ナニカシッテルンデ?」
「アノナ。虐殺スレノシイハ普通、イマギコヲ追ッカケテイッタミテエナシイバッカリナンダ。マトモナシイノホウガバグナンダ」
「……?」
「……その方が、虐殺しやすいでしょう?そういうことです」
『ウォッチャー』の言葉に、八つーは瞠目した。
「チョットマテヨ!ココノスレノシイハ皆……『殺サレルタメニ作ラレタシイ』ッテコトカ!」
「その通りです」
「『殺ス為』ニ、ワザト普通ノシイヨリ脆カッタリ、アアヤッテスグニ子供ガ出来ルヨウニシテル。頭モ弄ッテチョットオカシクナッテル。ダカラココニイルシイハバグ。歴トシタ、ナ」
「……例え普通のしぃが生まれても、この世界ではすぐにおかしくなってしまう。いっそ普通じゃない方がましだもの」
「…………ダカラ俺ハオ前等ガ嫌イナンダ!!」
三つーが吐き捨てるように言い放った。八つーは驚いて頭の上を見上げる。
「タダ弱イカラッテ言ッテ、何モシナイノハ自分達ダロ!誰カニ助ケヲ求メルダケデ!何ガマターリダ!馬鹿カ!」
「ツーサン、幾ラ何デモ言イ過ギダ」
「ケドッ……ケド、タダ無力ダカラ何モシナイノカ!脆イカラ何モシナイナンテ……逃ゲテルダケダ!」
「……逃げたくて逃げてるわけじゃないYO。多分NE」
ひとり冷静に、そういったのはぼるじょあだ。
三つーは、憎らしいのか後ろめたいのか、そんな表情で彼を見やる。
「僕らは、そのスレの設定からは逃れられない。たとえモナーやモララーでもNE。それがAAなんだと思うYO」
「……ドウシテ」
「そこでは『そうあるように』求められるからじゃないNO?僕だって元は荒らしじゃないC。ただ、『そうあるように』求められたから、今の僕は荒らし。そういうことじゃないNO?」
「…………」
「けど、つーが怒るのも仕方ないC。ここにギコが来なかったら多分ああいう風にはならなかったんじゃないかNA?」
「ソリャマタドウイウコトダ?」
「つまりですね」
遠くで誰かが走り回る音が聞こえる。それ以外に雑音は無い。
「ここに居るべき『虐殺者』……モララーがいなくなってしまった。そして存在しないはずのギコがやってきてしまった。そのために」
これが平和なのかもしれない。けれどこれは、これでは――
「この空間の、秩序が崩れてしまっている。――そういうことでしょう?」
しぃはうなだれた。
5:悲哀 lament
自分がどこにいるのか判らないのはこちらも同様だった。
ここに飛ばされたのはネーノ、フーン、『コネクター』だった。
無論、空気は剣呑そのものだ。
「……おい、あんた」
「コネクター」
「……『コネクター』、ここはどこなんだ」
「知らん。そんなことを考えてる余裕も無かったな。すまん」
「はっ。『接続者(コネクター)』が聞いて呆れるな」
「その言葉そのまま返す。お前もフーン族だろ。折角ある頭を使おうという気にはならんのか」
「…………………………………………」
「ま、ま、ま。取り敢えず落ち着くんじゃネーノ?」
「そうなんじゃネーノ。喧嘩してても始まらないんじゃネーノ」
「フーン。そういうネーノさんはこの状況を打開できる妙案があるとでも?」
「…………八ネーノは」
「……ネノさんに無いんなら俺にも無いんじゃネーノ」
「プ」
「プ」
「プ」
険悪だが他人を嘲笑するときには妙に馬が合っている。
「……何だかひたすらムカつくんじゃネーノ」
「ネノさん、多分怒ってもあいつらにゃ勝てませんて」
まあじゃれ合うのはこれくらいにして、と三フーンが煙草を取り出しながら総括する。
今いる所は崩れかけた建物の中だった。しかし、先ほど八頭身たちが集まった場所とは違って、やけに埃っぽい。
「まずここがどこかを見極めるのが先決、か。おい後輩、何かあるか」
「取り敢えずここから出た方が良いな。これじゃあいつ崩れたっておかしくない」
「……それもそうか。閉じ込められているわけではないようだし」
「――それはやめておいた方が良い」
『コネクター』の指が滑らかにノートパソコンの上を撫ぜていく。
画面には幾つかのウィンドウが開かれ、英語や数列が無数に流れていっている。
それらに目を通しながらの発言は、少々フーンたちの癇に障ったようだ。
「どうしてそう言い切れる?お前にはこの場所すらわからないんだろう?」
「そうだ。場所まではわからない。だがこのスレが何のスレか確かめるのにそれほど時間はかからない」
つまり――と切り出した所までで彼の発言は爆音によって遮られた。
ガラスの嵌っていない窓から衝撃波に乗って砂礫が飛んでくる。
咄嗟に床に伏せてそれをやり過ごしてから、彼は言葉を続けた。
「……ここは、『戦争スレ』だ」
遠くに聞こえる音は恐らく、銃声。
※
とにかく外に出ようというのには賛成だ、と三ネーノは提言した。
「むしろこんな所にいた方が危ないんじゃネーノ。建物の下敷きになる可能性も高いし、第一敵だと思われて殺られるのが関の山じゃネーノ」
「……問題は出てからどこに行くか、か。この調子じゃ非戦闘地域を探す暇なんかなさそうだしな」
「ここから東に2キロほどで戦闘が終わった地域があるぞ」
「フーン……ってどうしてあんたは知ってるんだ」
「だからあんたではなく『コネクター』だと何度……。このスレについての情報を引き出した。私は『接続者』だからな」
そういって、少し前に同じ言葉を言った相手に皮肉った笑みを向ける。
やっぱりこの野郎好きにはなれん、と銜え煙草の八フーンをなだめるのは八ネーノの役目だ。
「取り敢えず、行ってみようじゃネーノ。せっかくの『カミサマ』のお言葉、だろ?」
「フーン……これで死んだら笑い話だな」
「全くそうじゃネーノ」
とにかく、ここにいる悪党の意見は一致した。
※
『コネクター』の指し示した座標には、木々が鬱蒼と茂っていて、ゲリラ戦にはもってこいの場所だった。
所々から硝煙のにおいがする。それと僅かな人の気配。
どこか心霊スポットじみた、じっとりとした嫌な感じに、三ネーノは溜息を吐く。
「ネノさん?疲れたんスか?」
「いや、何だか嫌ーな感じがするんじゃネーノ……」
「フーン。そりゃそこらへんにいろいろいるからだろ」
「いろいろ……?」
「いろいろ。」
「…………え?」
「無駄言吐くな。場所が割れる」
種々の疑問は残れど、『コネクター』に言われては口を閉じる以外に出来ない。
ふと、八ネーノが指さずに、目線だけで方角を伝えると、
「……誰か、いる」
全員に緊張が走る。彼等はまだ、自分の言葉にどんな力があるのか解らない。ゆえに、彼らの唯一の攻撃手段は拳のみだ。
まずは八頭身たちが動く。伊達に狂犬と呼ばれていたわけではない。音を立てないように慎重に、出来るだけ近づく。
そこにいる『誰か』たちの話し声を聞き、会心したかのように口の端を歪めると、指で『こっちに来い』と合図を出す。
「……大丈夫じゃネーノ?」
「まあ、大丈夫でなくてもいざとなったら奴らを囮にして」
「悪だな」
取り敢えず合流してみればその理由は簡単に解るのだ。
「奴さん、ひとりらしい」
「フーン……戦場なのに、か」
「囮じゃネーノ?」
「否。どーもその理由ってやつが、『コネクター』、あんた関連だ」
「……成る程、な」
一言そう呟くと、『コネクター』は気配も消さず、堂々とその『誰か』の所に歩いていく。
皆はその行為に驚きを隠せずにいたが、何か策があるのだろうと止めることはしない。
『コネクター』はそのまま、その人物に、実に気さくに話しかけた。
「……どうも」
「……民間人、か」
「戦争は終わったようだな」
「終わった、か。確かにこの状況を見れば終わったといってもおかしくは無い。全く、おかしなことにな……」
「……私を攻撃したりはしないのだな」
「私をただの一兵卒と一緒にされては困る。これでも大尉で、中隊長だ。身分のある身で、軽率なことは出来ない」
「明らかに怪しい人間だとわかっていても?」
「まさかみすみす殺されるために私の前に現れたわけではあるまい?」
「成る程」
会話の中に含みを持たせつつ、それでも和やかに二人の会話は続いていく。
待っている方は穏やかではない。
しかしそれを知らずか――いや、知っていてむしろ楽しんでいるのだろう――『コネクター』の目はこちらを向かない。向けない。
「……あの野郎、いつまで話し込んでるんだ」
「なかなか意気投合してるじゃネーノ。その前に意気投合してどうするんじゃネーノ」
「もしかすると……武器か?」
「フーン。成る程な。それなら取り入った方がやりやすいか」
而して後に『コネクター』の目がこちらを向いた。口の動きが『来い』と言っている。
そのまま『誰か』と一緒に歩き出してしまう『コネクター』を追いかけて、4人は文句を言いながらも木々の間を駆け抜けた。
※
ついたところは恐らく基地なのだろう。野戦のためのプレハブのような建物の中に通された。
そこからしばらく歩き、開けられた扉の中には銃器の類が所狭しと並んでいる。
「ここにあるものはもう必要の無いものだ。勝手に使うといい」
「こりゃ……また、凄いんじゃネーノ?」
「必要が無い、とは……どういうことで?」
「戦う必要が無くなった、ってことだろ。原因は……モナーやモララーが消えたことに関係がある、か」
八フーンが銃をいじりながら確認のように大尉の方を見ると、彼は硬い表情で頷いた。
「……我々はもともとモナー族とモララー族の連合軍と戦っていたのだ。それが突然、敵軍が姿を消した。この戦いは不戦勝で終わった、というわけだ」
「その割には嬉しそうに見えないんじゃネーノ。寧ろ辛そうに見える」
「――そりゃ、戦争そのものが終わったわけじゃないからな」
八フーンに続き、更に三フーンが言葉を続ける。
「戦争が終わって一息ついたり、喜んだりするのは全部お偉い方だけだ。かたや兵士の戦争は終わらない――」
「――我々はまた戦いの準備をしなくてはならない。戦争が始まれば前線に出なくてはならない。今日笑いあった戦友が明日肉塊になるかもしれない。いつも、いつも、『戦いが終わった』と思っているのは上の人間と、戦争の実態を知らないものたち――」
大尉はゆっくり目を伏せた。彼の瞼の裏に、何が映っているのか。
言葉を止めた大尉に代わって、『コネクター』が口を開く。
「……戦いの最中にいる者たちにとって、戦争は『終わる』ものではない。終わってもなお『続く』ものだ。――時に彼らの夢の中で、メディアの中で、彼らの思い出の中で、戦争は終わらない。戦うことこそが彼らの存在理由になるのだから。まして、だ」
『コネクター』の左目が僅かに引き攣る。
「『戦争スレ』の住民に、戦い無き時間など訪れるわけが無い。秩序が――崩れてしまう」
――このスレは、戦争スレ。
――この世界の秩序は『戦争が続くこと』そのもの。
それに気が付いて、ネーノたちは少し悲しくなった。
6:後悔 remorse
「――皆さん、大丈夫ですか?」
澄んだ声で目を開けた。
八ノーネはぼんやりと霞む目で周りを見やる。すぐそばに三ノーネ。少し離れた所に、既に目を覚ましているしぃたち。それに山崎と、声の主である『クリエイター』。
「……ここは何処だ?」
「恐らく地下スレの一つだとは思うのですが……詳しくは解りません。山崎さん……解りますか」
「すぐにはちょっと判別つけがたいですね。少々席を外します」
山崎は言うやいなや瞬間に姿を消した。これが『荒らし』の本領か。
八ノーネはぐるりと周りを見渡した。そしてある違和感に気づく。
――余りにも、何も無さ過ぎる。
会話も、荒らしも、何も無さ過ぎる。
「珍しいノーネ。ここまで何も無いのは」
「立て逃げされたスレみたいですから……ほとんど流れは止まってますね」
「丁度良い――『クリエイター』、さっき『コネクター』が言っていた、『魔法』について説明願いたいんだが、良いかね」
「……まあ、あの説明で理解しろというのが無理な話でしょうから……」
畸形は苦笑しながら地面に手をついた。それをゆっくり引き上げると、僅かに遅れて地面から棒のようなものが伸びて、丁度良い長さで切れた。それを手に持って、
「実際に『魔法』を使うとこういったことが出来ます。しかし、皆さんの『魔法』にはあらかじめ制限がなされています。それが『科白を言わなければならない』ということです」
「ジャア、ギコ君ダッタラソレガ『逝ってよし』ニナルノネ」
「はい。ギコさんの言葉には『衝撃』の意味が込められています。だから相手に衝撃を与えることが出来る」
「……つまり、他の連中に同じ力はもたらされない?」
「そういうことになります。大雑把に分けると『攻撃型』と『守備型』に分けられます。しぃさんたちは治癒の力、ノーネさんたちには防御の力があるはずです」
三ノーネは手を開いたり閉じたりを繰り返している。どこと無く子供のようで面白い。
三しぃははたと気が付いたように問いかけた。
「思ッタノダケド……山崎君ハドウシテ科白ヲ言ワナクテモアアシテ力ヲ使エルノ?ソレトモモトモトカラ使エルノ?」
「もともと使える、というのが正しいです。山崎さんや、他のAAの中にもそういった設定がある方がいます。モララーさんはスレの中でそういう設定があるはずですし、三頭身しぃさん、あなたも使えるでしょう?」
「エ?」
「≪httpレーザー≫ですよ。あれは本来ちびしぃの頃しか使えないという制限があるのですが……いまはその制限はありません。三頭身しぃさんでも使えますよ」
『クリエイター』は造った棒を更に変形させながら微笑んだ。
三しぃは信じられないといった顔をして自身の手を覗き込んだ。しぃ族の中にどんな制約があるのか知らないが、本来あるはずの無いことが有り得るといわれたときの反応としてはこんなものなのかもしれない。
ふいに、閑散としたスレの中から大声があがった。
「……誰かいるのか?」
「叫び声なノーネ……誰か捕まりかけているのかもしれないノーネ」
先ほどの闇色の怪を思い出して、一同はその誰かを探してスレの中を駆けた。
隠れる場所が少ないはずなのになぜか見つからない。
『クリエイター』だけがそれを傍観して、手の中の棒を細く長い指揮棒のようなものに変形させていた。
「どうしたんですか皆さん?」
「うわっ!」
突然山崎が顔を出した。驚いて立ち止まる。
「いきなり出てくるな!心臓に悪いだろうが」
「そりゃどうもすみません。ところで皆さん、走り回ってどうしたんですか?」
「誰かがいるんだ。このスレに。見かけなかったか」
「……そんなわけ無いでしょう。僕らじゃないんですから」
「は?」
「ここには初めから誰もいないんですよ?スレとスレの間を移動できるのは『荒らし』だけなんですよ?ぼるじょあか『コネクター』たちでもない限り、そんなことは出来ません」
そこまで聞いて、ノーネたちは顔を見合わせた。
空耳――というわけではあるまい。大勢が聞いている。
ではいったい誰が?
「山崎さん、他にもいるんです。スレとスレの間を移動できるのは」
「……それこそ初耳ですね。どなたですか」
「多分――」
『クリエイター』は棒を振った。
棒の軌跡が煌いて、扉の形を作る。
持っていないほうの手を押すように前に突き出すと、音も無くその扉は開いていった。
開いた扉から、つんのめるように男が飛び出してきた。
手にはノートパソコン。フーン族の顔をした彼は、まさしく、
「――兄者サン!」
「あ――」
その顔は普段と違い、恐怖によって歪んでいる。
脱力したように座り込んだ彼の肩に手を置き、八ノーネは静かに、
「――どうした。話してみろ。ん?」
「あ……っ、う……」
何度も何度も呼気を飲み込み、震えを抑えるように手をぎゅっと握りこんで、
「おと……弟者が、弟者が……連れて行かれた!」
『クリエイター』の表情が固まる。しぃたちも息を呑んだ。
「いきなり、何だか解らないものが出てきて……俺には何も出来なかった。何も出来なかった!」
ぽろぽろと、涙が地面をぬらす。
「俺は、弟者の、兄なのに……何も出来なかった!」
兄者はただ泣いていた。
誰も、何も言うことが出来なかった。
責めることも、慰めることも出来ぬ。
兄者はただ泣いていた。
※
「――彼が、スレを移動できるAAですか」
「はい。彼は――彼らは『ウォッチャー』の性質を持っていますから」
「成る程……出演者であり閲覧者でもある、ということですか」
山崎は得心して彼を見やる。フーン族の彼は落ち着きこそ取り戻したものの、落胆は抑えようが無い。
誰の顔も見ようとはしない。ただ、地面と自分の手を見つめている。
その僅かに先に、ノートパソコンが一つ。
「………………言っておくが、誰もお前を責められんぞ」
八ノーネは語りかける。
「だが優しい言葉をかけてやれるわけじゃない。かけようとも思わん。それでもまだ泣いているつもりか?」
「…………」
「お前と同じ状況になったとき、他人を助けられるかと問われれば、出来ないだろうよ。だがな、この後どう動くか、はお前次第だ」
「……俺、次第」
「どうする。ここで何もせずに泣いている意気地無しになるか。それとも弟を助けに行くか。前者ならこのままお前をほっぽらかして俺たちは進む。後者なら――協力できる」
兄者は微動だにしなかった。ゆっくりと、幾度か瞬きを繰り返す。
「俺は……」
「うん?」
「……解らない。俺は、俺が、どうしたらいいのか解らない」
兄者の手が、ノートパソコンに触れる。
「俺が知っているのは、これを使うこと、ブラクラを踏むこと、それぐらいしか知らない。俺になにができるのかも解らない」
「じゃあ、どうするんだ。決めてみろ?」
「……いま、一人でいるのは、いやだ」
僅かだが彼の身体は震えている。
「いまは、ひとりには、なりたくない……できるなら、弟者も、助けたい……」
「……そうか」
八ノーネはそう言ったきりだった。
しぃたちは戸惑いを隠せない。『クリエイター』も難しい顔をして黙ってしまった。
――そして、その時、兄者の背中についていた黒いごみのようなものが、有機的な動きで体内に潜り込んでいくのに気づいたものは誰一人としていなかったのだった――。
≪the another side #2≫
「うーん……いったい、ここはどこなんでしょうか。参ったな、今日は愛しのハニーとディトの約束が……」
薄暗い闇の中で、八モララーはひとりごちた。
目の前には結構な太さの金棒が均等な幅で並んでいる。これでは外には出られまい。
兄が消えたことと関係がありそうだ、と腕を組んだ。
「どちらにしろ、この状況では何も出来ませんね……外に出られなければ何も……」
「じゃあ外に出れたら協力してもらえるね?」
聞こえてきた声に、あわててそちらを振り向く。
いたのは、楽しげに笑っている三モララー。
「モ……モララーさん!モララーさんもいたんですね」
「まあね。状況は君とそれほど変わらない。いつの間にかここにいたんだよ」
三モララーは檻の端で、なにやらごそごそと手を動かしている。
「どういう理由があってかは知らないが、私をここに閉じ込めた罪は重いね。誰であっても」
「あのー……何をしてらっしゃるんですか?」
「ピッキングだよ」
「はあ?」
「こういうときに一芸があるといろいろ便利でね。靴の裏に針金を仕込んで置いたんだよ」
成る程、三モララーは器用に手を曲げて鍵穴をいじっている。
呆れながらも感心しつつ、八モララーは自分の閉じ込められている折を見渡す。そして、
「モギャー」
「……ジャスティスマスター?どうしてこんな所に……、まさか」
八モララーは身体を竦めた。ジャスティスマスターのいる所には、どこからか厄介な副産物が訪れる。
あれが現れては余計に面倒だ。出来れ