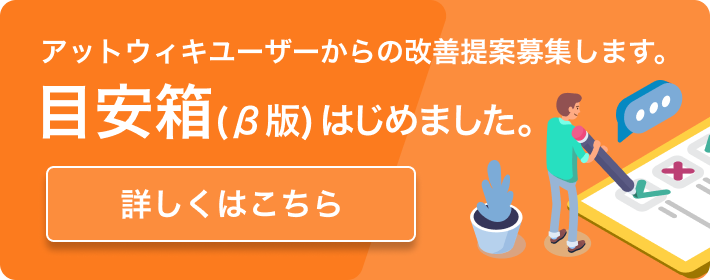【前スレ】
http://town.s96.xrea.com/cgi-bin/long/anthologys.cgi?action=html2&key=20051011232803
【保管庫】
小説板のログ置き場(ログ丸ごと)→http://omaemona.flop.jp/mona/long/30.html
持知の自サイト(編集済みログ)→http://kugatu.fc2web.com/septemberalbum/index/index.html(ページ未完成…スマソ)
自サイトの過去ログ保管ページはまだ出来てないです…出来るまで小説板のログ置き場の方を利用して下さい。
【関連スレ】
「銀の街と黒の空」→http://town.s96.xrea.com/cgi-bin/long/anthologys.cgi?action=html2&key=20060101230038
遂に2スレ目。これからもよろしくですよ。
以下何事もなかったかのように再開↓
第19話:「暗闇の光」
暗闇に、誰かが立っている。
…誰だろう?
――――キミか。
ああ、僕はこの人を知っている。
でも…誰だっけ?
――――とは言っても、キミはボクのことを覚えていないと思うけどね。
足下からゆっくりと、光が差していく。
その人の、姿を照らし出す。
―――――まぁ、そんなことは今のキミにとったらどうでもいいことなのかな。
闇が、晴れた。
目の前に立っていたのは、
『とりあえず…久しぶりだね、ポジビリティ君』
黒いマントに身を包んだ、片耳のモナー族だった。
左耳はもげてなくなっており、唯一残っている右耳には包帯が乱雑に巻かれている。
「…貴方は…誰ですか…?」
僕は辛うじてそれだけ聞くことが出来た。
この質問に、彼は変に言葉を濁すことなく簡潔に答えた。
『ん? それは名前のことかい? 名前なら、一応ダウト・レイジという立派な名前があるよ』
彼はやけに誇らしげだった。
それだけ、このダウト・レイジという名前を気に入っているのだろうか。
『他に何か聞きたいことは?』
「あ、ええと…ここはどこなんですか…?」
『ここ? ここはキミの意識の深淵だ』
「意識…?」
僕の意識は、こんなに不確かで真っ暗な存在だっただろうか?
『そうだ。今のキミは、大耳の鍵の力によって意識を永遠に封印される途中なんだよ。
本来ならそのままキミは意識の暗闇に溺れて氏んでいくところなんだろうけども、
それは困るから、ボクがキミの沈みかけの意識を一時的に止めた。今が、その「止まっている」状態なんだ』
ダウト・レイジは大真面目な顔でそう言った。
僕は、ただ目を瞬かせるしかなかった。
「…氏ねない、ですって?」
シーンが問い返す。
モナーは自分の頭から引っこ抜いたナイフを手の上で弄びながら、笑顔で頷いた。
「そうモナ。モナはこう見えても、結構危険なことをしてきたモナ。
そりゃもう、普通のAAだったら軽く氏ぬぐらいの危ないことを色々と」
その頃を思い出しているのか、懐かしむような顔でモナーは語る。
「…でも、モナは氏ななかった。いや、氏ぬことが出来なかったんだモナ。
それが最初は自分にとって都合のいいことだと思っていたモナ」
弄んでいた手の中のナイフは、いつの間にか綺麗さっぱり消えていた。
その跡すら、残さずに。
それでもモナーは、まるで空気を掴んで転がしているかのように弄ぶ手を止めなかった。
「氏ねば、もう何もすることは出来なくなる。だから、モナは氏ぬことを恐れていたモナ。
だから、この『氏なない肉体』というものはとても有り難いものだ…そう思ったモナ」
「…モナー、もうそれ以上は言うな」
モララーがモナーの弄ぶ手を掴んで制するが、モナーはその手を振り払うと続けた。
「だけど、それは氏ぬことよりも恐ろしいことだったモナ。
永遠に生き続けなければならないというのは、今だかつてない孤独を味わうことと同じモナ」
「孤独? ソレガ何デ怖インダヨ?」
不思議そうに問うアヒャに、モナーは酷く哀れむような視線を向けた。
「…仲の良い友人が出来ても、大好きな妹が生まれても、いずれはモナより先に氏んでしまう運命モナ。
例え世界が滅んでも、モナは氏ぬことが出来ない。それは…とても悲しいことだし、同時に寂しいことでもあるモナ」
「なるほど、独りきりになるのを恐れていると言うことですね」
「そうモナ。だからモナは…自分があまり好きじゃないモナ」
モナーは左腕を大きく振った。
すると、腕が一瞬のうちに変形し、恐ろしい魔物が腕に住み着いたような格好になった。
「…独りにならないために、モナは生きている。そう考えながらじゃないと、とてもやっていけるような状態ではないモナよ。
…キミ達にはわからないと思うモナけど」
モナーの声は、とても悲しそうだった。
今まで見たこともない彼の姿に、誰もが息を呑んだ…その瞬間。
「…だから、モナはキミ達を頃すモナ」
先程までの切なげな表情はどこへ消えたのか。
モナーの口の両端が一気に吊り上がり、醜悪な笑みへと変わる。
同時に腕の魔物が牙を剥いて伸び上がり、二人に襲いかかった。
「おっと…」
「…フェイントカヨ! マッタク、姑息ナ手ヲ使ウモンダナ!」
二人は魔物の攻撃を後ろに飛んでかわすと、アヒャがシーンを庇うような形で前に立ち、ナイフを無数に出現させて放つ。
どすどすどすっ、と鈍い音がしてナイフが魔物に突き刺さり、モナーにも刺さる。
だが、彼の表情は変わらない。
「さて…そろそろ飽きてきたから、一気に始末するモナ」
モナーがにやり、と歪んだ笑みを浮かべた。
「…ちょ、ちょっと待って下さいよ。要するに今、僕はビデオでいう一時停止みたいな状態になってるってことですか?」
『うん、まぁ平たく言えばそんな感じだね。とは言っても「一時停止」だから、出来れば早いところキミに決めて貰わないといけないんだ』
「何をですか?」
混乱する中、僕が尋ねるとダウト・レイジは答えた。
『勿論、キミはこの後どうするかだ。このまま暗闇に墜ちて氏ぬのがいいならそうする。
ボクとしては困るけど、キミが望むなら仕方のないことだと思って諦める。
でも氏にたくないなら、それなりの対処はしてあげようと思ってるんだが』
「氏にたくなんかないですよ!! 何言ってるんですか!!」
僕は即答していた。
記憶のないまま氏ぬなんて、僕は絶対に嫌だった。
それに…組織の皆さんに、まだ満足に恩返しも出来ていないのに。
『…そうか、わかった。でも、これには条件がある』
「何ですか? 僕に出来る範囲のことでなら何でも…」
『なに、別に難しいことじゃないさ。ちょっと、キミに昔のことを見て貰いたいだけだよ』
「昔のこと…?」
ダウト・レイジは不思議な微笑みを浮かべた。
『そう、昔の…思い出みたいなものさ。キミにとってはほんの一瞬に過ぎないけどね』
つい、と彼が指を動かす。
すると、真っ暗だった空間の一部が何かに引っ張られるようにして、抜け落ちた。
丸く空いた穴からは、暖かな光が漏れ出している。
『今からここで見たことを、忘れるも思い出すもキミ次第だ。じゃあ、また後で』
「え?! あ、ちょっと!!!」
叫んだ時にはもう遅く、僕の視界は光に塞がれて真っ白になってしまった。
「…どうなってんだ…?」
大耳は目の前の「ありえない」状況を見つめて、ぽつりと呟いた。
「何で、これ以上鍵が回らねぇんだよ…!?」
ポジの後頭部には、しっかりとマスター・キーの先端部分が埋め込まれている。
あとは、それを音がするまで回せば「封印完了」となるはずであった。
だが、途中まで回したところで突然鍵が回らなくなってしまったのだ。
いくら力を入れて回しても、鍵はうんともすんとも言わない。
「何だこいつ…?! 何しやがったんだ…?!」
「そんな乱暴に振り回したりしてっから、言うこと聞かなくなっちまったんじゃねぇか?」
「んなわけねーだろ!! 今までもちゃんとメンテは頻繁にしてたんだぜ!!」
「デモヨ…」
つーが指さして言った。
「ポジノ意識モ、無イミタイダゼ…?」
鍵の先端が差し込まれたままのポジは、目を見開いたままぴくりとも動かない。
だが鍵が完全に回されていない以上、少なくとも意識を封印されてはいないだろう。
それが唯一の救いだった。
「きっとポジ君も頑張ってるのよ…。封印されまいと、必死になってるのよ…!!」
レモナが鋼鉄の拳をさらに硬いものにして叫ぶ。
「なら、ここで俺達が何とかしてやるってのが筋ってところか?」
「ソウダナ。ソウデモシネェト、オレ達ノメンツガネェモンナ」
フーンもつーも頷いた。
焦ったのは大耳だ。
自分が予測していた展開が、多少ではあるが狂ったのだ。
「くそ…!! 一旦ここは解除するしかねぇのか…!!」
大耳は仕方なく鍵を解除方向に回そうとして…
「…あれ」
「今度は何だよ」
「…封印が解除出来なくなってる…」
鍵は中途半端に回されたまま、完全に固定されていたのだった。
第20話:「昇り詰める者の恐怖」
Sevence Sign本部。
一人留守番を任されたギコは、今日の夕飯のことをぼんやりと考えながら、虚ろな目でテレビを見ていた。
「…今日はレモナが出ちまってるからな…。かといって俺は料理苦手だし…」
メンバーが早く帰って来るのは稀だ。
モナーはいつも割と早い方だが、今日は行くところが行くところだけに、遅れることは確実であろうとギコは踏んでいた。
「それにしてもモララーから聞いた時は驚いたぜ…。まさかいきなり『Fakers』の本部に乗り込むなんてな。
話をしに行くだけだとは言っていたが…タカラのことだ、そう簡単に自分のもとまで通させはしないだろう。…さて…」
ギコはテレビのスイッチを切り、立ち上がって奥の部屋へと向かった。
一番奥にある扉を開けると、その先にはやや長い廊下がある。
その廊下をしばらく歩き、見えて来たのはまた扉。
重い鉄で出来たその扉には、いくつも厳重に鍵がかけられている。
「…全く、モナーもここまですることないだろうによ」
言いながら、刻印の刻まれた片手を扉に押し当てる。
すると、刻印が音もなく輝き…その手が扉にずぶりと吸い込まれた。
「刻印所有者はどっちにしろこの扉抜けられるし…しぃの存在がある今になって、こいつを狙う香具師なんているとは思えねぇな」
そのままどんどん身体も吸い込まれていき…やがて彼は扉を『通り抜けた』。
通り抜けた先は、真っ暗な部屋。
常人なら目が慣れるまでかなりの時間を要するだろう。
ギコは部屋の真ん中に灯っている電気スタンドの僅かな明かりを見つけると、そこに向けて声をかけた。
「おい、ジエン。今晩は何が食いたい?」
明かりの下で、一匹のAAが本を読んでいた。
よく見ると、彼の周りには沢山の本が散らばっており、足の踏み場もない程だ。
ジエンと呼ばれたそのAAは、ギコの声に顔を上げた。
「…その様子じゃ、レモナは仕事で居ないんだ?」
「ああ。ポジを任務に連れて行くようにモナーから言われてな。つーとフーンも一緒に出払っちまってるよ。
今、本部に残ってるのは俺とお前だけだ」
「モナーまで居ないって珍しいね」
ジエンは読んでいた本にしおりを挟んで閉じると、ギコを手招きした。
ギコはそれに従い、本を踏まないよう、器用に歩いて近寄って行く。
「ところで、ボクはまだその『ポジ君』に会ってないんだけど」
「ああ、悪いな。モナーがなかなか許可を出さなくてよ」
「そんなにお気に入りなの?」
「お気に入りかどうかは知らんが…いや…まぁ、気に入られてはいるだろうな」
ギコはモララーに次ぐ組織のナンバー3と言われているが、それは正直ほとんど飾りのようなもので、
組織のトップであるモナーのことをそれほど知っているわけではない。
そのことは当然、ギコもわかっている。
それでいてナンバー2の座を狙っているものだから、いつもモララーにからかわれているのだ。
「それよりジエン…お前本ばかり読んで疲れないのか?」
「疲れる? 冗談はよしてよ。こんな面白いもの、読んでいて疲れるわけないじゃん」
「いや、面白いって言ったらそうなんだろうが…」
ジエンは、この真っ暗な部屋で一日中本を読み続けている。
それ以外にすることがないと言ってしまえばおしまいだが、何よりもジエンは本を読むことが大好きなのだった。
その影響だろうか、彼はいつの間にか全角で会話をすることが出来るようになっていた。
彼は特に物語が大好きで、沢山の愛読書を持っているほどだ。
よく見ると、床に散らばっている本には皆、しおりが挟まっている。
「ん? お前『山奥のしぃ先生』は前に読み終わったんじゃなかったか?」
足下に落ちていた本を拾い上げギコが言うと、ジエンは本へと再び目を戻しながら答えた。
「それは『裏山のしぃ先生』だよ。『山奥』は読み終わってるけど、『裏山』はまだなんだ」
「ふーん…今は何の本読んでるんだ?」
「これ」
ジエンがスタンドの明かりに本の表紙を照らし出す。
「ああ、『STANDARD MAD HERO』か」
「ギコも知ってるでしょ? 『STANDARD MAD』っていう犯罪グループの話を書いた本だよ」
「勿論だ。この物語は有名だからな。本嫌いの俺でも流石に読んだことはあるぜ」
ジエンはページから目を逸らさず、声だけでギコと会話していた。
ギコは懐かしそうにその手元を覗き込む。
「確かこの本の1巻が出たのが3年前だったか?」
「そうだよ。これは3巻目」
「俺は1巻だけ読んで、あまりの話の難しさに読むのを諦めちまったなぁ」
「1巻で断念って…あ、そうだ。ボク思ったんだけどさ」
ジエンが前のページをめくり出す。
ギコもいつしか彼の話に吸い寄せられるように聞き入っていた。
やがて彼の手が止まる。
「この挿絵見て」
彼が指さしたページには、頭部を蛇に似た魔物に変形させてAAを喰らう、モナー族の男の挿絵が描かれていた。
「これは…」
「3巻で、モナーがフサを喰らうシーンだよ」
「こんなシーンがあるのか…」
「うん。でもそんなことより、ボクが言いたいのはさ」
ジエンは不機嫌な顔をして尋ねた。
その変わりように、ギコは少しだけ表情を硬くする。
「…モナー、読んだんでしょ? この本」
「ああ…恐らくは」
「いや、絶対に読んでるよ。ボクにこの本をくれたのはモナーだ。本はあまり読まない主義だって言ってたけど、それは嘘だと思う」
「なぜそんなことが言える?」
「ギコこそ、どうしてそんなことが言えるの?!」
ジエンが声を荒げて言う。
「モナーの刻印の能力は、一度見たものになら何でも変身出来るというものだよね。
そしてこの物語に出てくるモナー。彼も根本的なところは違うけど似たような能力を持っている」
「それがどうかしたのか?」
「昨日、モララーが言ってた。モナーの変身能力は物凄いスピードで伸びているって。
…それに他にも、モナーは『醜いHERO』や『虐待専用キャラ・ぽろろです。好きに虐めて下さい』とかも読んでた。
どれも残酷な描写やアクションシーンを含む作品ばかり」
「…どういうことだ、それは」
小難しい顔をするギコに、ジエンは断言した。
「本を読むこと…いや、挿絵を見ることによって、彼は自分の変身能力を高め続けている。
これ以上彼の能力が高まり続けたら…いずれ大変なことになるよ」
ギコは何も言い返せなかった。
モナーは危険な香具師なんかじゃない。
そう言い返せるほど、彼に対する信頼感がなかったのだ。
今は味方…そういった程度の意識しか。
「…このことは誰にも言うなよ。お前の胸の中にでもしまっておけ」
「ギコ!!」
「今日は乙カレーでいいよな。俺がまともに作れるのそれぐらいのもんだからよ。
それじゃ、おとなしく本の続きでも読んでろ。邪魔したな」
ずぶり、と粘着質な音を立てながら、ギコは部屋から出て行った。
真っ暗な部屋に残されたのは、ジエンと大量の本の山だけ。
「…あの人が言ってたことなんだ。間違いなんかじゃないんだよ…」
ジエンは悲しそうな目でギコが消えた扉を見つめていた。
第21話:「フラッシュバック」
何だ?
何だ、これは?
僕の視界に浮かんでは消える、見覚えのある映像。
ああ…何だか、懐かしい。
でも、
コノ、胸ヲ貫クヨウナ哀シミハ何ナンダ?
視界が晴れた。
目の前には、燃える街。
知らない街。
そして、「僕」がそこに立っていた。
…ひとりきりで。
顔に、沢山の血の跡をつけて。
目の前の「僕」は、燃える街を見下ろしながら笑っていた。
―――ああ、これで何もかもおしまいじゃないか。
「僕」が言う。
―――僕が今までしてきたことも無駄だったんだ。なんて可笑しいんだ。
「僕」は笑う。
―――何のために、僕は生きてきたんだろう。もう、生きる価値もないな。
目から涙を零しながら、「僕」は笑っていた。
その目に、生気はない。
まるで、魂の抜け殻のようだ。
―――なぁ、キミなら知ってるんだろ? 教えてくれよ。
祈るように、叫ぶように。
「僕」は言葉を紡ぐ。
―――僕はキミのために生きてきたのに。
―――返して、返してよ。
―――僕の全てを返して。
すると、目の前に一人の女性が現れた。
だが彼女は「僕」の方へは行かず、僕の目の前に立って。
恐ろしい形相で、こう言った。
――――お前のせいだよ。お前の力のせいでこうなったんだ。
その言葉は僕の心に重くのしかかってくる。
彼女の言葉は止まらない。
―――嘘だと思うなら、目の前の街を見ろ。あれがお前の行く末だ。
吐き気がする。
身体の底から沸き上がってくる何かが、僕をどうしようもない気持ちにさせていた。
第一、何だ。
僕の力があの街を壊滅させたって?
何の攻撃能力も持たない僕が?
―――愚かな。自分の所業もわからないとは。
―――ならば見せてやろう。お前が何をしたのかを、しっかりと胸に刻んでおけ。
女性の瞳孔が、開いた。
途端、世界は再び真っ白になった。
そこで見たものは、とても言葉では言い表せないものだった。
ただ、見た後に残ったものは、何とも言えない空虚感。
そして、絶望感。
「う…うわぁぁぁぁぁっぁああああああ!!!!!!!!」
もう、叫ぶしかなかった。
自分がどうにかなってしまいそうだった。
「…嘘だ、嘘だ嘘だ嘘だ嘘だぁぁぁぁぁ!!!!」
頭を掻きむしりながら、雷に打たれたように。
僕は転がり、悶え、叫び続けた。
無情にも、女性の声が続く。
―――そうだ、狂え。狂ってしまえ。お前に安息などないのだ。
―――今、見せたのは…ほんの断片。ほんの一欠片に過ぎない。
―――お前の過去を失わせたのは、誰だったかな?
嘲笑う口調で、声は余韻を残して消えた。
僕は涙を流しながら、ただひたすらに叫び続けた。
『少しは思い出して貰えたかな?』
僕が我に返った時には、あの忌まわしい映像はどこにもなかった。
あの真っ暗な空間に立って、ダウト・レイジが僕を静かに見下ろしている。
顔に貼り付いた涙の跡が痛く感じた。
「…あれは…何なん…ですか…?」
辛うじてそれだけ訊くと、ダウト・レイジはあっさりと答えた。
『あれは、キミの残した過去の一部だ』
「あんな…あんなものが僕の過去だとでも言うんですか?!」
『そうとしか言いようがないんだ、仕方ないだろう』
「嘘だ…僕は認めない!!!」
頭を抱えながら断固として拒否する僕に、彼はため息をついた。
『…まぁ、信じるも信じないもキミの自由だ。ボクがどうこう言うことじゃないしね。
さて、約束通り…キミの封印されかかっている意識を外に帰してあげよう』
彼がそう言った途端、全身を浮遊感が包み込んだ。
例えるなら、プールの底から静かに浮かび上がっていくような…そんな感じ。
「ま、待って下さい!!」
僕は慌てて叫んだ。
最後にこれだけは訊いておきたいことがある。
『ん? 何だい?』
「…貴方は、僕の過去を知っているんですか?」
それを聞いた彼は何か言おうとして、口ごもった。
だがすぐに再び口を開く。
『…知っていると言えば嘘になるが、知らないと言っても嘘になるね。
これはボクが元々知っていたものではない。ボクが目覚めた時から既にボクの中にあった。
誰かに、これを持っているように命令されたのかもしれない。でもそれはわからない。
だからボクは、キミにこれを見せたんだ。これはボクの独断でやったことだよ』
…よくわからない。
そうこうしているうちに、ダウト・レイジが指をくん、と上に向けて動かした。
その動きに合わせるように、僕は外界へと意識を押し上げられていく。
『…今は、現在の状況に流されていればいいんじゃないかな。そのうち変化は来るよ』
彼の声が耳元で聞こえ、弾けて消えた。
空間同士のうねりに呑まれるように、僕は再び意識を失った。
第22話:「Dream is Over」
「…いつのことでしたかねぇ…」
タカラはぼんやりと窓の外を眺めながら、誰に言うでもなくぽつりと呟いた。
それを聞いたでぃが、問い返す。
「何デスカ?」
「ああ、でぃさんには話していませんでしたか」
「話シテイルモイナイモ、ソレダケノセリフデハ何モワカリマセン」
「…それもそうですね。じゃあ…でぃさんには特別に教えましょう」
下の階からはほとんど戦闘音が聞こえなくなっていた。
だがそのことを別に気に留める様子もなく、タカラは口を開く。
「僕が昔、神々の刻印の研究者をやっていたってことは知ってますよね?」
「ハイ。前ニ聞カサレマシタ。確カ…神ノ復活ヲ望ンデ研究ヲシテイタトカ何トカ…」
「ええ、その通りです。世界征服をするにあたり、『刻印』の創造主である神を復活させようと、
神の遺産である刻印に何かヒントはないかと思って研究していたんですよ」
「ソノ方向性ガ、ドウシテスリ替ワッタンデスカ?」
でぃはタカラを真っ直ぐな目で見つめて問う。
光のない、その白い瞳の無言の圧力に気圧される者は数多く居るが、彼女の主であるタカラだけは、
どうやってもその瞳に屈することはなかった。
「…何のことですか?」
「トボケナイデ下サイ。神ヲ復活サセル目的デ『偽リノ刻印』ヲ作リ出シタ訳デハナイデショウ?
恐ラク何ラカノ心境ノ変化ガアッテ、『神復活』ヲシナイデ世界征服ヲ成シ遂ゲルトイウ方向ニスリ替ワッテイッタハズデス」
タカラはふうとため息をつくと、両手を軽く上げて降参のポーズを取った。
だが表情の笑みは消えない。
恐らく、心底屈服した訳ではないのだろう。
そういった意味でも、でぃは彼を打ち負かすことが出来ずにいた。
「…参りましたね…このことはモナーさんぐらいしか知らなかったはずなんですけど」
「敵ガコノコトヲ知ッテイルノニ、何デ秘書ノ私ガ知ラナインデスカ。今マデノタカラサンノ行動ヲ見テイレバ大体読メテキマスヨ」
「僕、そんなにわかりやすいAAじゃないと思ったんですが…まぁいいでしょう。さっき『特別に教える』と約束しましたしね。
僕が構想を練っている段階のことは全てお教えします」
その時だった。
ドォン…
下の階の方で、微かな爆発音のような音がした。
音自体はそれほど大きなものではなかったが、部屋全体が少しきしむように揺れた。
「…マタ、アノ二人デスカ」
「ええ…羽が散るからあまり戦闘には行って貰いたくないんですけど…」
「私ハソレヨリモムシロ、柱ヤ壁ヲ腐ラセテシマウ方ガ困リマス」
「そうですね…それも困りますけど仕方ないでしょう」
タカラは椅子から立ち上がった。
「でぃさん。申し訳ないんですが、先程のお話の続きは後でもいいですか?」
「ハイ、構イマセン。タカラサンガ話シタイ時ニ話シテクレレバ良イデス」
「ありがとうございます。それでは…行きますか」
音もなく、部屋の扉が開く。
タカラとでぃは揃って部屋を出て歩き出した。
「…お客様のお迎えに」
遠のいていた意識が、蘇ってくる。
ほどけていた紐が、また結び直されていくように。
視界が、繋がる。
かちり。
「ポジ君っ!!」
目が覚めたのは、レモナさんの声だった。
ゆっくりと目を開けると、建物の群れに切り取られた空が映った。
もう、日は半分傾いている。
「…僕は…」
「ポジ君大丈夫?!」
「レモナさん…僕は…一体…」
むっくりと起きあがり、辺りを見渡す。
手には愛用の小型拳銃。
足下には巨大な鍵。
「全く驚いたな…」
フーンさんが呟く。
「俺が能力を発動させるまでもなく、鍵は見事に固定されていた。
しかも、封印を無理矢理塞き止めておいて、さらに強引に封印解除させるとはな」
「大耳ノ封印能力ハ本物ダカラナ! 鍵ガ刺サッタ状態カラ封印回避出来タ香具師ナンテ、オレモ聞イタコトガナイゼ」
つーさんも半ば唖然とした顔でこちらを見ている。
大耳はというと、もう唖然呆然のようだ。
「…鍵がひとりでに回って…勝手に解除しやがった…」
「…ひとりでに?」
「そうよ、ポジ君に刺さってた鍵が勝手に回り出して、封印解除されたの。
持ち主である大耳君がどんなに強い力で回しても駄目だったのに」
「…ひとりでに解除された…」
僕は先程のダウトとの会話を思い出していた。
もしかして、これもダウトがやったことなのだろうか。
「おおゆうしゃよ、のうりょくがつうじなかったとはなさけない」
そんなことを考える僕を尻目に、妙なニュアンスを含んだ言い方で、フーンさんが大耳に近づいていく。
大耳はもう目の前が真っ白になってしまっているらしく、フーンさんが近づいてきても身構えようともしない。
ただ、うわごとを呟きながら全身をがたがたと震わせているだけ。
それは、大耳がどれだけ自身の能力に自信を持っていたか、そしてどれだけその能力に頼り切っていたのかを表していた。
「…さて、ここまで時間がかかってしまったのは正直予想外だ。一番手っ取り早い方法で、この任務を終わらせるとするか」
フーンさんが目を開けた。
彼の後ろ姿しか見えない僕は直接見たわけではないけれど、大耳の動きが止まったのを見て確信した。
――――止めたのだ。大耳の「速度」を。
「残念だが、大耳。ここでDream is Overだ」
彼は呟いて、大耳の額に銃を押しつけた。
「その哀れな泣きっ面をフッ飛ばしてやる」
何の躊躇いもなく、引き金が引かれる。
乾いた音が、Vip区域に響いた。
第23話:「暗黒四重奏」
フーンさんが引き金を引く直前。
ごとん、と瓶が地面に落ちるような音がしたのは気のせいではなかった。
「…もう許してやったらどうだい、フーン君」
ばしぃっ!!
乾いた音が響いたかと思うと、フーンさんの手に握られていた拳銃は、その手を離れて地面に落ちていた。
僕はそれで、彼が撃つ瞬間に何者かの手によって叩き落とされたのだと悟った。
でも一体誰が…。
「…アンタの考えることは本当わからねぇな…」
フーンさんがため息混じりに相手を見やる。
「…マスター・ノマ」
彼の視線の先には、ノマさんが立っていた。
その手に、一振りの木刀を握って。
モナーは心底楽しそうな笑みを浮かべていた。
腕の魔物は奇妙に変態し、異臭を放つ唾液を口からだらしなく零している。
「…モナ達はタカラ君に話があって来たモナ。通してくれないのなら…」
魔物が巨大化する。
「容赦しないモナよ?」
そんな彼を見て、モララーが声をかける。
「モナー。今日は話に来ただけだろう? 下っ端はともかく、幹部まで頃すのは…」
「予定変更もあり得る、とも言ったはずモナ」
「それなら……ん?」
モララーの耳がぴくりと動いた。
「どうしたモナ?」
「何か来る」
しゅぴぴぴぴっ!!
彼が呟いた途端、二人の背後から沢山の羽が飛んできた。
羽とはいっても高速で飛んできているそれは、弾丸のようなものだ。
刺さったらただごとでは済まない。
ぶわっ!!
モララーは咄嗟に全身から風を巻き起こし、羽を吹き散らした。
モナーはもう片方の手を後ろに回し、手のひらを巨大な盾に変化させて受け止める。
「…あー、やっぱりかわされちゃったかぁ」
「まだまだ殺傷力が低いYO。やっぱこうしないとNE♪」
二人分の声がして、すぐに何かが飛んできた。
死角の方向から飛んできたそれは、ただの塊のような物体に見える。
だが、その周辺を不気味なオーラが包んでいるのは明らかだった。
「モナー、あの塊が何かわかる?」
「ちょっと確かめるモナ」
モナーは盾を引っ込め、モララーを下がらせると一歩前に出た。
そして、飛んできた塊を素手で掴む。
じゅわっ!!
途端、モナーの手が変な音を立てて溶けた。
だが彼は少し眉をしかめただけで、別段動じることはない。
そして、モララーに溶けた手をぶらぶらさせながら見せた。
「溶けたモナ」
「うわ、こりゃ派手に溶けたね。熱くなかった?」
モナーの手は手首から先が溶けていて、どろどろとした白い液体が床に落ちている。
わかりやすく言うなら、溶けたアイスクリームが手首から流れ落ちているような感じだ。
「んー、ちょっと熱かったモナけど…溶けたっていうより、一瞬で腐った感じモナね。
だから溶けたように見えたのかもしれないモナよ。それにしては中途半端モナ」
「…なるほどね。腐りすぎて、個体としての原型を留めなくなってしまったと」
「そうモナ。ま…モナにやってもあまり意味はないモナよ」
モナーがそう言うと同時に、手首からこぼれ落ちていた「手だったもの」が手首に吸い寄せられ始めた。
それらはあっという間に手首に集まり、変形して再び元の形に成る。
彼は元に戻った手を握ったり開いたりして感覚を確かめた後、不敵に微笑んだ。
「居るなら出てきていいモナよ。残りの幹部モナね?」
この空間を包んでいる、新たな殺気。
モナーもモララーも、とっくにそれに感づいていたのだ。
「やれやれ…参ったNA。僕の能力を軽く受け流すとはNE」
「だから頭狙えば良かったのに。楽しむ余裕がない相手なのは知ってるでしょ?」
「わかってるYO。アヒャとシーンがここまで苦戦する相手なんだしNE♪」
二人が現れたのは、モナー達の背後からだった。
足音ひとつ立てずに現れるところは、やはり戦闘慣れしている証拠だろう。
「初めましてだNE、僕はぼるじょあ。宜しくだYO」
「ぼるじょあ共々、お初にお目にかかりますね。私はエーと申します」
ぼるじょあの手からは淀んだ色のオーラが溢れ出していた。
それは先程モナーがつかみ取った塊の色と同じだ。
「さっきモナの手を腐らせたのはキミモナね」
「そうSA。僕の刻印は『Rot』って言ってNE、僕の放つオーラに触れたものは腐るんDA。
そのオーラを集めて塊にして、さっきみたいに飛び道具としても使えるんだYO」
そう言うとぼるじょあは手に持ったオーラをひゅっ、とおもむろに投げた。
先程は掴み取ったモナーだったが、今度はかわす。
「最初の羽の弾丸は…キミかい?」
「ええ、そうです。私の刻印は『Wing』…。私の身体からは自由に翼を生やすことができ、
さらにその翼を変形させたり、羽を弾丸のように扱ったりと様々なことに応用が可能です」
言い終わった彼女の背から、巨大な翼が生える。
その美しい姿に、モララーは苦笑いした。
エーは続けて言う。
「間もなく、私達の主君はここへ現れるでしょう。貴方達にはおとなしく待っていて頂きたいところなのですが…
それでは納得いかないだろうと思いまして。結果として私達が参りました所存です」
「タカラ君も結構な暇潰しを用意してくれたモナね。…モナ達は今、ちょっと退屈モナ。
楽しませてくれるのなら、付き合ってあげてもいいモナよ」
「主君から、お客様を退屈させてはならないとの指示がありました。
今、お二方が退屈してしまっていらっしゃるのは私達の配慮の至らなさが原因です。ですから…」
エーとぼるじょあがアヒャとシーンの前に立つ。
残る二人も立ち上がった。
「…『Fakers』幹部…『七人の嘘吐き 』所属……アヒャ、シーン、ぼるじょあ、エー。
我ら『暗黒四重奏 』…謹んでお相手させて頂きます」
「…僕はもう正直うんざりなんだよ」
ノマは木刀を手に握ったまま、大耳の狂った横顔を見た。
「今まで、沢山のAAが頃される様を見てきた。これも、自分の宿命なら仕方ないと思った時もあったさ。
でも…決して見ていて気持ちのいいものではない。…だから、僕の前では出来る限りの頃しは控えて貰いたいんだ」
「フーン、相変わらずの自分勝手だな。モナーがどうしてアンタを構うのか、未だに理解できねぇぜ。…戦闘能力は認めるが」
フーンが吐き捨てるように言う。
大耳はもう失神直前のところまで来ているようだ。
それを見たノマはすっ、と大耳の背後に回り、木刀を振り上げた。
ぼごっ!!
鈍い音がして、大耳が地に沈む。
彼がすっかりノビてしまったのを確認すると、ノマは木刀を下ろした。
「…あまりにも哀れだからね。おとなしくさせたよ」
「アヒャー…マスター、チョット機嫌悪ソウダナ」
つーさんが呟いたのを聞いて、僕は尋ねた。
「今の…フーンさんの拳銃を叩き落としたのって、ノマさん…ですか?」
「ソウダ。マスターハ、剣術ノ達人ナンダゼ。確カ…『ノマノマ流』トカ言ッタカ」
「でもAAを斬るのは性に合わないって言って、代わりに木刀を持ち歩いてるの。
そのままでも十分強いけど…米酒を飲んでからだと異様に強くなるわね」
「そうだったんですか…」
僕は先程の彼の早業を思い出して、息を呑んだ。
本来守られる立場のノマさんが、フーンさん達と対等…
いや、それ以上かもしれない程の戦闘能力を持っているだなんて思いもしなかったからだ。
「ここは僕に免じて…彼を見逃してやってくれないかな。モナー君に何か言われたら、僕が責任を取るよ。
それに、頼まれていたボルジョア・ヌーボーも2本に増やすからさ。キミもあの酒は好きだろう? フーン君」
「…納得いかねぇが…アンタが責任取ってくれるのなら、俺はそれ以上何も言わん。
ただ、あいつを怒らせると色々と面倒だからな。頃すのが好きな香具師だけに」
ふぅ、とフーンさんが初めて息をついた。
銃を納め、ふと大耳を見やる。
「…で、このろくでなしはどうするつもりだ?」
「放っておくさ。そのうち、向こうからお迎えが来るだろうし。それより、早いところ店に来るといい。今日は沢山の酒をご馳走するよ」
「やったぁー!! マスターってば、太っ腹♪」
レモナさんが飛び跳ねて喜び、つーさんも楽しそうに笑う。
ノマさんは苦笑いを浮かべ、僕に視線を向けて言った。
「それに…新しく入ったっていうキミのことも聞きたいしね」
第24話:「接触」
「『暗黒四重奏 』だって?」
モララーの疑問に、エーが答える。
「はい。私達はFakersの幹部グループである『七人の嘘吐き 』に所属する幹部です。
その中で、私達4人を特別に指していう呼び名…まぁ、異名みたいなものでしょうか。
それが『暗黒四重奏 』なのです」
「何とまぁ、小綺麗な異名だこと」
「でも」
呆れるモララーにモナーが言う。
「名前の美しさと強さは、必ずしも比例しないモナ」
「そうかNA? だったら試してみてもいいけDO?」
「タカラ君がせっかく用意してくれた暇潰し…使わせて貰わないのは失礼だしね」
「アヒャ! 暇潰シデハ終ワラナイコトヲ思イ知ラセテヤルヨ!!」
「…御託はそれまでにして…さっさと始めるモナ」
ぼごっ、とモナーの片腕が蠢く。
さっきまで魔物だったその腕は、巨大なハンマーに変化した。
「モナー…それ、『ガッハンマー』じゃん」
「そうモナ。一人でもぬるぽする香具師が居たら…ガッしてやるモナ」
「だったら、言わない方が良いNE!」
言うと同時にぼるじょあが地を蹴り、一気に間合いを詰めて来た。
手には、先程の腐食のオーラ。
モナーも走って間合いを詰め、速度の勢いに任せてそのままハンマーを振り下ろす。
ドォン…
だが、ハンマーが捕らえたのは床だけ。
モナーはむ、と眉をしかめた。
背後からぼるじょあの声が響く。
「そのハンマー、当たったら痛そうだけDO…大振りになるから小回りは利かないよNE」
オーラを纏ったぼるじょあの手が、モナーに伸びる。
狙いは、頭。
「そうはさせないからな!!」
ぼわっ!!
モララーが叫ぶと同時に、モナーとぼるじょあの間に炎の壁が出来た。
ぼるじょあが慌てて数歩退く。
「おっと、危ないじゃないKA。そちらさんもなかなか厄介な能力をお持ちのようDE」
「モナーばかり構って貰うのは狡いからな。僕も楽しませておくれよ」
「なら…」
エーが前に進み出た。
「私がお相手致しましょう。アヒャとシーンは後ろで私達の援護をおながいします」
「援護カァ、オレハアマリ得意ジャナインダガナ」
「…わかった。その代わり、急に僕の能力が発動しても驚かないでくれよ」
モララーは視線をエーに向けた。
彼女の翼は淡く発光しており、今にも攻撃を放ってきそうな雰囲気だ。
今まで多くの敵と戦ってきたが、流石は「Fakers」の幹部ともなると、かなりの殺気が全身から溢れ出している。
久々に感じる「大物」の空気に、モララーはひゅうと口笛を吹いた。
「なかなか良い殺気を放つんだね。モナーほどじゃないけど」
「あの方は別格なのでしょう? 貴方の組織の中でも」
「そうだね。確かにそれは合ってる。氏なないし、殺人狂だしさ」
エーはモララーの目をじっと見て、訊いた。
「…貴方はご存じなのですか?」
「ご存じって…何を?」
「あの方がなぜ不死なのか、その理由です」
モララーは少し躊躇うように俯いたあと、答えた。
「…知っているはずがないからな。本人だってよくわかっていないのに」
「そうですか。なら良いんです、始めましょう」
エーの両の翼が、巨大な拳に変形する。
低い体勢で地を蹴り、拳の片方を後ろへ引き絞ると一直線に打撃を放った。
だが、モララーも読んでいる。
サイドステップで横に飛び、一撃をかわすと片手に冷気を宿らせる。
「その翼、動かなくしてあげるよ」
冷気を帯びた手が、伸びきったエーの拳を掴む。
かきぃぃぃぃん!!
途端に強い冷気が吹き出し、エーの拳の先から一気に翼の根元までを凍らせた。
エー本人までは凍っていないものの、相当の痛手となったことは確かだ。
「どうだい? これでキミの拳は片方封じた。残るはもう一つだね」
だが、エーは表情を変えない。
「…だから、どうしたというのですか?」
ぴしり。
彼女がそう言うと同時に、翼の動きを止めていたはずの氷にひびが入った。
「なんて力だ…並じゃないね。でも…」
モララーは舌打ちしつつも、今度は両手に再び冷気を宿らせる。
今度の冷気は、さっきよりも勢いが強い。
握りしめた手の中から零れてくるドライアイスのような煙が床に触れる度、そこを次々と凍らせていく。
「今度はそう簡単に壊せない強度で凍らせてあげるまでさ」
片方の翼と両足が生きている以上、遠隔攻撃は効かないだろう。
そう判断した彼は、冷気を逃がさないようにしっかりと両手を握りしめ、間合いを詰めるべく走り出した。
「…あら、貴方は近距離戦が不得意だと聞いていましたが」
「その通りだよ。でも、別に駄目な訳じゃないからな!」
本来は近距離戦を苦手と自負するモララーだが、決して戦えない訳ではない。
近距離派のつーやレモナ、オールラウンダーのギコやフーンの戦法を見て、常に努力はしてきているのだ。
彼はそのまま前に飛び、敢えて正面から突っ込んだ。
「ぼるじょあが言っていたのを思い出してね。大きな翼では、小回りが利かないだろ?」
モララーがにや、と笑う。
だが、エーは冷静にその視線を受け止め、答えた。
「…小回りなら、いくらでも利きますよ」
「あー、美味しい!! やっぱりマスターのカクテルは最高ね!!」
「アヒャ! マスター、今度ハ『カンパリオレンジ』飲ミテェゾ!!」
「マスター、私も! 『キス・イン・ザ・ダーク』おながい!」
「はいはい、ちょっとお待ち下さいね…」
一仕事終えた僕達はギコさんに連絡を入れた後、ノマさんのお店「BARマイヤヒ」に来ていた。
モナーさんからの頼まれものがあるから、ここに来るのも一応仕事のうちではある。
でも、つーさんやレモナさんはすっかりマターリモードになっていた。
「えーっと、ポジ君だったかな? キミも何か飲むかい?」
「あ、でも…僕、自分がお酒に強いか弱いか、はっきりとはわからないんです。
何回か飲んだことはあるんですけど…小さいビール缶ぐらいですから…」
「そうか、じゃあノンアルコールカクテルから試してみたらどうかな? ちょっと待っててね、ちょうどいいのがあるから」
「はい…ありがとうございます」
ノマさんはニコニコしながら、シェイカーにお酒を注ぎ始めた。
「フーン君は何か飲む? さっきのこともあるし、サービスしておくよ」
「ふーん…じゃあ、『ジン・ビターズ』くれ」
「かしこまりました~」
彼はとても手際が良い。
4人からほぼ同時に受けた注文を、たった一人で次々にこなしていっている。
僕だったら、作っている間にきっとお客さんから遅いという苦情を浴びてしまうだろう。
「はい、お待たせ。レモナちゃんは『キス・イン・ザ・ダーク』。
つーちゃんは『カンパリオレンジ』。フーン君は『ジン・ビターズ』だったね。それから、ポジ君のは…と」
ノマさんは3人にそれぞれのカクテルを出した後、僕のカクテルを出してきた。
「はい、ノンアルコールカクテルの『シンデレラ』だよ」
そのカクテルは、ややオレンジがかった黄色をしていた。
見た目は普通のジュースのようにしか見えない。
正直、普通にスーパーとかで売られていそうだ。
「…これって、何だかカクテルっぽくないですね」
「そうだね、ノンアルコールカクテルにはそういった感じのものが多いんだ。どうだい? 試しに飲んでみなよ」
ノマさんに言われて、僕はグラスを口に運ぶと傾けた。
口に広がるのはレモンとオレンジの風味、そしてパイナップルの華やかなフレーバー。
まぁ、一言で言うと…甘い。
まさにジュースそのものだ。
「…これ、本当にカクテルですか?」
「うん。れっきとしたカクテルさ。ノンアルコールだから、お酒は入ってないけどね。
オレンジ・レモン・パイナップルの3種類のジュースをステアしただけのものだよ」
「ああ、だからこんなに甘いんですね」
ノマさんは頷くと、カウンターの下から米酒の瓶を取り出した。
それを見たレモナさんが、思わず尋ねる。
「ねぇ、マスター…。相変わらず米酒が好きみたいだけど…。どうしてなの?」
「どうして、って…僕はこの酒と共に生まれて来たようなものだよ。人生の相方でもあるこの酒を捨てられるわけがないじゃないか」
そう言うノマさんの米酒を見る目は、とても穏やかだった。
「キミにとってのモナー君と同じだよ。なぜキミがモナー君を愛しているのか。
キミはその質問に対する、ちゃんとした答えを持っているかい?」
レモナさんがはっ、と言葉に詰まる。
ノマさんは苦笑いして、瓶のフタを開けた。
「…ごめん。今のは僕の八つ当たりだった。キミの愛に理由なんて要らなかったね」
「いえ…それは…」
「いいんだよ、忘れてくれ」
ノマさんの手にしたグラスに、米酒が注がれる。
透明なその色は、どこかノマさんの瞳に似ていた。
プルルルル…
途端、フーンさんの携帯が鳴った。
彼は傾けていたグラスを置くと、すぐに電話に出る。
「…俺だが。ああ、ギコか。 モナーとモララーはまだ帰ってないのか?
あの二人にしては遅いんだな。…わかってるよ、酒はちゃんと持って帰る」
どうやら、電話の相手はギコさんのようだ。
「…あ? ああ…わかった。次の任務はそういうことになるな。つーとレモナに伝えとく。
ポジは明日どうするんだ? …そうか。まぁ…まずはモナーが帰ってからだな。
じゃあ、なるべく早く本部に戻るようにする。わかった、また後でな」
フーンさんはそう言って電話を切った。
同時につーさんがグラスを置いて尋ねる。
「フーン、ギコガ何カ言ッテ来タノカ?」
「次の任務の話だ。詳しくは後で正式発表があるらしい。その下準備もあるから、早く本部に戻るようにとの指示だ」
「でも、モナー君はまだ帰ってないんでしょ? 心配だわ」
「あいつのことだ、どうせまた楽しんでるんだろ」
そう言うとフーンさんは一気にカクテルを飲み干し立ち上がった。
「話は聞いてたろ? マスター。ボルジョア・ヌーボーの瓶をくれ」
「わかった。どうやらキミ達も相当忙しいようだね」
ノマさんはカウンターの下からやや大きめのボトル二つを取り出した。
「これだよ。落とさないように気を付けて」
「マスター…オレ達ハ子供ジャナインダゼ?」
つーさんが呆れながら、一本を持つ。
残りの一本はレモナさんが持った。
「じゃ、そろそろ帰りますね」
「マタ飲ミニ来ルカラナ!」
「今度はツケじゃなくてちゃんと現金で支払い頼むよー」
さりげなく痛いノマさんの一言に押されて、僕らは店を出た。
外はもうすっかり夜が更けてしまっていて、視界も悪い。
ぽつりぽつりと灯っている街灯を頼りに歩き出す。
「…疲れた…」
僕は3人より少し後ろを俯き加減に歩きながら、ぽつりと呟いた。
昨日もそうだったが、今日はもっと色々なことがあった。
躊躇っていたはずの殺人をしてしまいそうになり。
自分の意識が封印されそうにもなって。
でも、あのダウト・レイジとか言う変なモナー族に救われたんだっけ。
「…何だかなぁ…」
ため息をついて、ふっと顔を上げる。
その時、ちょうど向かい側から歩いてきていた誰かとぶつかりそうになった。
「あ、すいません」
「あ…いえ、こっちこそぼんやりしてて…すいません」
街灯に照らされた相手は、片耳のモララー族だった。
モララー族にしては珍しく、残された片耳だけが白い。
フードつきのマントという、今時流行らないファッションスタイルだ。
「そ、それじゃ…失礼します」
何だか気まずくなって、僕が逃げるように歩き出した時だった。
「…キミには、もう一つの刻印の器があるね。それはいずれ手にするよ」
「っ?!」
僕は思わず振り向いてしまった。
相手の声が、あの時のモナー族…ダウト・レイジのものにそっくりだったからだ。
だが、さっきの人物はもうそこには居なかった。
「オーイ! ポジ! 何ヤッテンダー!! 置イテクゾー!!」
つーさんの声で我に返った僕は、慌てて3人の後を追いかけて行った。
第25話:「対談」
「その辺になさったらどうですか?」
その場に居た全員が聞き覚えのあるテノールが、突然響き渡った
http://town.s96.xrea.com/cgi-bin/long/anthologys.cgi?action=html2&key=20051011232803
【保管庫】
小説板のログ置き場(ログ丸ごと)→http://omaemona.flop.jp/mona/long/30.html
持知の自サイト(編集済みログ)→http://kugatu.fc2web.com/septemberalbum/index/index.html(ページ未完成…スマソ)
自サイトの過去ログ保管ページはまだ出来てないです…出来るまで小説板のログ置き場の方を利用して下さい。
【関連スレ】
「銀の街と黒の空」→http://town.s96.xrea.com/cgi-bin/long/anthologys.cgi?action=html2&key=20060101230038
遂に2スレ目。これからもよろしくですよ。
以下何事もなかったかのように再開↓
第19話:「暗闇の光」
暗闇に、誰かが立っている。
…誰だろう?
――――キミか。
ああ、僕はこの人を知っている。
でも…誰だっけ?
――――とは言っても、キミはボクのことを覚えていないと思うけどね。
足下からゆっくりと、光が差していく。
その人の、姿を照らし出す。
―――――まぁ、そんなことは今のキミにとったらどうでもいいことなのかな。
闇が、晴れた。
目の前に立っていたのは、
『とりあえず…久しぶりだね、ポジビリティ君』
黒いマントに身を包んだ、片耳のモナー族だった。
左耳はもげてなくなっており、唯一残っている右耳には包帯が乱雑に巻かれている。
「…貴方は…誰ですか…?」
僕は辛うじてそれだけ聞くことが出来た。
この質問に、彼は変に言葉を濁すことなく簡潔に答えた。
『ん? それは名前のことかい? 名前なら、一応ダウト・レイジという立派な名前があるよ』
彼はやけに誇らしげだった。
それだけ、このダウト・レイジという名前を気に入っているのだろうか。
『他に何か聞きたいことは?』
「あ、ええと…ここはどこなんですか…?」
『ここ? ここはキミの意識の深淵だ』
「意識…?」
僕の意識は、こんなに不確かで真っ暗な存在だっただろうか?
『そうだ。今のキミは、大耳の鍵の力によって意識を永遠に封印される途中なんだよ。
本来ならそのままキミは意識の暗闇に溺れて氏んでいくところなんだろうけども、
それは困るから、ボクがキミの沈みかけの意識を一時的に止めた。今が、その「止まっている」状態なんだ』
ダウト・レイジは大真面目な顔でそう言った。
僕は、ただ目を瞬かせるしかなかった。
「…氏ねない、ですって?」
シーンが問い返す。
モナーは自分の頭から引っこ抜いたナイフを手の上で弄びながら、笑顔で頷いた。
「そうモナ。モナはこう見えても、結構危険なことをしてきたモナ。
そりゃもう、普通のAAだったら軽く氏ぬぐらいの危ないことを色々と」
その頃を思い出しているのか、懐かしむような顔でモナーは語る。
「…でも、モナは氏ななかった。いや、氏ぬことが出来なかったんだモナ。
それが最初は自分にとって都合のいいことだと思っていたモナ」
弄んでいた手の中のナイフは、いつの間にか綺麗さっぱり消えていた。
その跡すら、残さずに。
それでもモナーは、まるで空気を掴んで転がしているかのように弄ぶ手を止めなかった。
「氏ねば、もう何もすることは出来なくなる。だから、モナは氏ぬことを恐れていたモナ。
だから、この『氏なない肉体』というものはとても有り難いものだ…そう思ったモナ」
「…モナー、もうそれ以上は言うな」
モララーがモナーの弄ぶ手を掴んで制するが、モナーはその手を振り払うと続けた。
「だけど、それは氏ぬことよりも恐ろしいことだったモナ。
永遠に生き続けなければならないというのは、今だかつてない孤独を味わうことと同じモナ」
「孤独? ソレガ何デ怖インダヨ?」
不思議そうに問うアヒャに、モナーは酷く哀れむような視線を向けた。
「…仲の良い友人が出来ても、大好きな妹が生まれても、いずれはモナより先に氏んでしまう運命モナ。
例え世界が滅んでも、モナは氏ぬことが出来ない。それは…とても悲しいことだし、同時に寂しいことでもあるモナ」
「なるほど、独りきりになるのを恐れていると言うことですね」
「そうモナ。だからモナは…自分があまり好きじゃないモナ」
モナーは左腕を大きく振った。
すると、腕が一瞬のうちに変形し、恐ろしい魔物が腕に住み着いたような格好になった。
「…独りにならないために、モナは生きている。そう考えながらじゃないと、とてもやっていけるような状態ではないモナよ。
…キミ達にはわからないと思うモナけど」
モナーの声は、とても悲しそうだった。
今まで見たこともない彼の姿に、誰もが息を呑んだ…その瞬間。
「…だから、モナはキミ達を頃すモナ」
先程までの切なげな表情はどこへ消えたのか。
モナーの口の両端が一気に吊り上がり、醜悪な笑みへと変わる。
同時に腕の魔物が牙を剥いて伸び上がり、二人に襲いかかった。
「おっと…」
「…フェイントカヨ! マッタク、姑息ナ手ヲ使ウモンダナ!」
二人は魔物の攻撃を後ろに飛んでかわすと、アヒャがシーンを庇うような形で前に立ち、ナイフを無数に出現させて放つ。
どすどすどすっ、と鈍い音がしてナイフが魔物に突き刺さり、モナーにも刺さる。
だが、彼の表情は変わらない。
「さて…そろそろ飽きてきたから、一気に始末するモナ」
モナーがにやり、と歪んだ笑みを浮かべた。
「…ちょ、ちょっと待って下さいよ。要するに今、僕はビデオでいう一時停止みたいな状態になってるってことですか?」
『うん、まぁ平たく言えばそんな感じだね。とは言っても「一時停止」だから、出来れば早いところキミに決めて貰わないといけないんだ』
「何をですか?」
混乱する中、僕が尋ねるとダウト・レイジは答えた。
『勿論、キミはこの後どうするかだ。このまま暗闇に墜ちて氏ぬのがいいならそうする。
ボクとしては困るけど、キミが望むなら仕方のないことだと思って諦める。
でも氏にたくないなら、それなりの対処はしてあげようと思ってるんだが』
「氏にたくなんかないですよ!! 何言ってるんですか!!」
僕は即答していた。
記憶のないまま氏ぬなんて、僕は絶対に嫌だった。
それに…組織の皆さんに、まだ満足に恩返しも出来ていないのに。
『…そうか、わかった。でも、これには条件がある』
「何ですか? 僕に出来る範囲のことでなら何でも…」
『なに、別に難しいことじゃないさ。ちょっと、キミに昔のことを見て貰いたいだけだよ』
「昔のこと…?」
ダウト・レイジは不思議な微笑みを浮かべた。
『そう、昔の…思い出みたいなものさ。キミにとってはほんの一瞬に過ぎないけどね』
つい、と彼が指を動かす。
すると、真っ暗だった空間の一部が何かに引っ張られるようにして、抜け落ちた。
丸く空いた穴からは、暖かな光が漏れ出している。
『今からここで見たことを、忘れるも思い出すもキミ次第だ。じゃあ、また後で』
「え?! あ、ちょっと!!!」
叫んだ時にはもう遅く、僕の視界は光に塞がれて真っ白になってしまった。
「…どうなってんだ…?」
大耳は目の前の「ありえない」状況を見つめて、ぽつりと呟いた。
「何で、これ以上鍵が回らねぇんだよ…!?」
ポジの後頭部には、しっかりとマスター・キーの先端部分が埋め込まれている。
あとは、それを音がするまで回せば「封印完了」となるはずであった。
だが、途中まで回したところで突然鍵が回らなくなってしまったのだ。
いくら力を入れて回しても、鍵はうんともすんとも言わない。
「何だこいつ…?! 何しやがったんだ…?!」
「そんな乱暴に振り回したりしてっから、言うこと聞かなくなっちまったんじゃねぇか?」
「んなわけねーだろ!! 今までもちゃんとメンテは頻繁にしてたんだぜ!!」
「デモヨ…」
つーが指さして言った。
「ポジノ意識モ、無イミタイダゼ…?」
鍵の先端が差し込まれたままのポジは、目を見開いたままぴくりとも動かない。
だが鍵が完全に回されていない以上、少なくとも意識を封印されてはいないだろう。
それが唯一の救いだった。
「きっとポジ君も頑張ってるのよ…。封印されまいと、必死になってるのよ…!!」
レモナが鋼鉄の拳をさらに硬いものにして叫ぶ。
「なら、ここで俺達が何とかしてやるってのが筋ってところか?」
「ソウダナ。ソウデモシネェト、オレ達ノメンツガネェモンナ」
フーンもつーも頷いた。
焦ったのは大耳だ。
自分が予測していた展開が、多少ではあるが狂ったのだ。
「くそ…!! 一旦ここは解除するしかねぇのか…!!」
大耳は仕方なく鍵を解除方向に回そうとして…
「…あれ」
「今度は何だよ」
「…封印が解除出来なくなってる…」
鍵は中途半端に回されたまま、完全に固定されていたのだった。
第20話:「昇り詰める者の恐怖」
Sevence Sign本部。
一人留守番を任されたギコは、今日の夕飯のことをぼんやりと考えながら、虚ろな目でテレビを見ていた。
「…今日はレモナが出ちまってるからな…。かといって俺は料理苦手だし…」
メンバーが早く帰って来るのは稀だ。
モナーはいつも割と早い方だが、今日は行くところが行くところだけに、遅れることは確実であろうとギコは踏んでいた。
「それにしてもモララーから聞いた時は驚いたぜ…。まさかいきなり『Fakers』の本部に乗り込むなんてな。
話をしに行くだけだとは言っていたが…タカラのことだ、そう簡単に自分のもとまで通させはしないだろう。…さて…」
ギコはテレビのスイッチを切り、立ち上がって奥の部屋へと向かった。
一番奥にある扉を開けると、その先にはやや長い廊下がある。
その廊下をしばらく歩き、見えて来たのはまた扉。
重い鉄で出来たその扉には、いくつも厳重に鍵がかけられている。
「…全く、モナーもここまですることないだろうによ」
言いながら、刻印の刻まれた片手を扉に押し当てる。
すると、刻印が音もなく輝き…その手が扉にずぶりと吸い込まれた。
「刻印所有者はどっちにしろこの扉抜けられるし…しぃの存在がある今になって、こいつを狙う香具師なんているとは思えねぇな」
そのままどんどん身体も吸い込まれていき…やがて彼は扉を『通り抜けた』。
通り抜けた先は、真っ暗な部屋。
常人なら目が慣れるまでかなりの時間を要するだろう。
ギコは部屋の真ん中に灯っている電気スタンドの僅かな明かりを見つけると、そこに向けて声をかけた。
「おい、ジエン。今晩は何が食いたい?」
明かりの下で、一匹のAAが本を読んでいた。
よく見ると、彼の周りには沢山の本が散らばっており、足の踏み場もない程だ。
ジエンと呼ばれたそのAAは、ギコの声に顔を上げた。
「…その様子じゃ、レモナは仕事で居ないんだ?」
「ああ。ポジを任務に連れて行くようにモナーから言われてな。つーとフーンも一緒に出払っちまってるよ。
今、本部に残ってるのは俺とお前だけだ」
「モナーまで居ないって珍しいね」
ジエンは読んでいた本にしおりを挟んで閉じると、ギコを手招きした。
ギコはそれに従い、本を踏まないよう、器用に歩いて近寄って行く。
「ところで、ボクはまだその『ポジ君』に会ってないんだけど」
「ああ、悪いな。モナーがなかなか許可を出さなくてよ」
「そんなにお気に入りなの?」
「お気に入りかどうかは知らんが…いや…まぁ、気に入られてはいるだろうな」
ギコはモララーに次ぐ組織のナンバー3と言われているが、それは正直ほとんど飾りのようなもので、
組織のトップであるモナーのことをそれほど知っているわけではない。
そのことは当然、ギコもわかっている。
それでいてナンバー2の座を狙っているものだから、いつもモララーにからかわれているのだ。
「それよりジエン…お前本ばかり読んで疲れないのか?」
「疲れる? 冗談はよしてよ。こんな面白いもの、読んでいて疲れるわけないじゃん」
「いや、面白いって言ったらそうなんだろうが…」
ジエンは、この真っ暗な部屋で一日中本を読み続けている。
それ以外にすることがないと言ってしまえばおしまいだが、何よりもジエンは本を読むことが大好きなのだった。
その影響だろうか、彼はいつの間にか全角で会話をすることが出来るようになっていた。
彼は特に物語が大好きで、沢山の愛読書を持っているほどだ。
よく見ると、床に散らばっている本には皆、しおりが挟まっている。
「ん? お前『山奥のしぃ先生』は前に読み終わったんじゃなかったか?」
足下に落ちていた本を拾い上げギコが言うと、ジエンは本へと再び目を戻しながら答えた。
「それは『裏山のしぃ先生』だよ。『山奥』は読み終わってるけど、『裏山』はまだなんだ」
「ふーん…今は何の本読んでるんだ?」
「これ」
ジエンがスタンドの明かりに本の表紙を照らし出す。
「ああ、『STANDARD MAD HERO』か」
「ギコも知ってるでしょ? 『STANDARD MAD』っていう犯罪グループの話を書いた本だよ」
「勿論だ。この物語は有名だからな。本嫌いの俺でも流石に読んだことはあるぜ」
ジエンはページから目を逸らさず、声だけでギコと会話していた。
ギコは懐かしそうにその手元を覗き込む。
「確かこの本の1巻が出たのが3年前だったか?」
「そうだよ。これは3巻目」
「俺は1巻だけ読んで、あまりの話の難しさに読むのを諦めちまったなぁ」
「1巻で断念って…あ、そうだ。ボク思ったんだけどさ」
ジエンが前のページをめくり出す。
ギコもいつしか彼の話に吸い寄せられるように聞き入っていた。
やがて彼の手が止まる。
「この挿絵見て」
彼が指さしたページには、頭部を蛇に似た魔物に変形させてAAを喰らう、モナー族の男の挿絵が描かれていた。
「これは…」
「3巻で、モナーがフサを喰らうシーンだよ」
「こんなシーンがあるのか…」
「うん。でもそんなことより、ボクが言いたいのはさ」
ジエンは不機嫌な顔をして尋ねた。
その変わりように、ギコは少しだけ表情を硬くする。
「…モナー、読んだんでしょ? この本」
「ああ…恐らくは」
「いや、絶対に読んでるよ。ボクにこの本をくれたのはモナーだ。本はあまり読まない主義だって言ってたけど、それは嘘だと思う」
「なぜそんなことが言える?」
「ギコこそ、どうしてそんなことが言えるの?!」
ジエンが声を荒げて言う。
「モナーの刻印の能力は、一度見たものになら何でも変身出来るというものだよね。
そしてこの物語に出てくるモナー。彼も根本的なところは違うけど似たような能力を持っている」
「それがどうかしたのか?」
「昨日、モララーが言ってた。モナーの変身能力は物凄いスピードで伸びているって。
…それに他にも、モナーは『醜いHERO』や『虐待専用キャラ・ぽろろです。好きに虐めて下さい』とかも読んでた。
どれも残酷な描写やアクションシーンを含む作品ばかり」
「…どういうことだ、それは」
小難しい顔をするギコに、ジエンは断言した。
「本を読むこと…いや、挿絵を見ることによって、彼は自分の変身能力を高め続けている。
これ以上彼の能力が高まり続けたら…いずれ大変なことになるよ」
ギコは何も言い返せなかった。
モナーは危険な香具師なんかじゃない。
そう言い返せるほど、彼に対する信頼感がなかったのだ。
今は味方…そういった程度の意識しか。
「…このことは誰にも言うなよ。お前の胸の中にでもしまっておけ」
「ギコ!!」
「今日は乙カレーでいいよな。俺がまともに作れるのそれぐらいのもんだからよ。
それじゃ、おとなしく本の続きでも読んでろ。邪魔したな」
ずぶり、と粘着質な音を立てながら、ギコは部屋から出て行った。
真っ暗な部屋に残されたのは、ジエンと大量の本の山だけ。
「…あの人が言ってたことなんだ。間違いなんかじゃないんだよ…」
ジエンは悲しそうな目でギコが消えた扉を見つめていた。
第21話:「フラッシュバック」
何だ?
何だ、これは?
僕の視界に浮かんでは消える、見覚えのある映像。
ああ…何だか、懐かしい。
でも、
コノ、胸ヲ貫クヨウナ哀シミハ何ナンダ?
視界が晴れた。
目の前には、燃える街。
知らない街。
そして、「僕」がそこに立っていた。
…ひとりきりで。
顔に、沢山の血の跡をつけて。
目の前の「僕」は、燃える街を見下ろしながら笑っていた。
―――ああ、これで何もかもおしまいじゃないか。
「僕」が言う。
―――僕が今までしてきたことも無駄だったんだ。なんて可笑しいんだ。
「僕」は笑う。
―――何のために、僕は生きてきたんだろう。もう、生きる価値もないな。
目から涙を零しながら、「僕」は笑っていた。
その目に、生気はない。
まるで、魂の抜け殻のようだ。
―――なぁ、キミなら知ってるんだろ? 教えてくれよ。
祈るように、叫ぶように。
「僕」は言葉を紡ぐ。
―――僕はキミのために生きてきたのに。
―――返して、返してよ。
―――僕の全てを返して。
すると、目の前に一人の女性が現れた。
だが彼女は「僕」の方へは行かず、僕の目の前に立って。
恐ろしい形相で、こう言った。
――――お前のせいだよ。お前の力のせいでこうなったんだ。
その言葉は僕の心に重くのしかかってくる。
彼女の言葉は止まらない。
―――嘘だと思うなら、目の前の街を見ろ。あれがお前の行く末だ。
吐き気がする。
身体の底から沸き上がってくる何かが、僕をどうしようもない気持ちにさせていた。
第一、何だ。
僕の力があの街を壊滅させたって?
何の攻撃能力も持たない僕が?
―――愚かな。自分の所業もわからないとは。
―――ならば見せてやろう。お前が何をしたのかを、しっかりと胸に刻んでおけ。
女性の瞳孔が、開いた。
途端、世界は再び真っ白になった。
そこで見たものは、とても言葉では言い表せないものだった。
ただ、見た後に残ったものは、何とも言えない空虚感。
そして、絶望感。
「う…うわぁぁぁぁぁっぁああああああ!!!!!!!!」
もう、叫ぶしかなかった。
自分がどうにかなってしまいそうだった。
「…嘘だ、嘘だ嘘だ嘘だ嘘だぁぁぁぁぁ!!!!」
頭を掻きむしりながら、雷に打たれたように。
僕は転がり、悶え、叫び続けた。
無情にも、女性の声が続く。
―――そうだ、狂え。狂ってしまえ。お前に安息などないのだ。
―――今、見せたのは…ほんの断片。ほんの一欠片に過ぎない。
―――お前の過去を失わせたのは、誰だったかな?
嘲笑う口調で、声は余韻を残して消えた。
僕は涙を流しながら、ただひたすらに叫び続けた。
『少しは思い出して貰えたかな?』
僕が我に返った時には、あの忌まわしい映像はどこにもなかった。
あの真っ暗な空間に立って、ダウト・レイジが僕を静かに見下ろしている。
顔に貼り付いた涙の跡が痛く感じた。
「…あれは…何なん…ですか…?」
辛うじてそれだけ訊くと、ダウト・レイジはあっさりと答えた。
『あれは、キミの残した過去の一部だ』
「あんな…あんなものが僕の過去だとでも言うんですか?!」
『そうとしか言いようがないんだ、仕方ないだろう』
「嘘だ…僕は認めない!!!」
頭を抱えながら断固として拒否する僕に、彼はため息をついた。
『…まぁ、信じるも信じないもキミの自由だ。ボクがどうこう言うことじゃないしね。
さて、約束通り…キミの封印されかかっている意識を外に帰してあげよう』
彼がそう言った途端、全身を浮遊感が包み込んだ。
例えるなら、プールの底から静かに浮かび上がっていくような…そんな感じ。
「ま、待って下さい!!」
僕は慌てて叫んだ。
最後にこれだけは訊いておきたいことがある。
『ん? 何だい?』
「…貴方は、僕の過去を知っているんですか?」
それを聞いた彼は何か言おうとして、口ごもった。
だがすぐに再び口を開く。
『…知っていると言えば嘘になるが、知らないと言っても嘘になるね。
これはボクが元々知っていたものではない。ボクが目覚めた時から既にボクの中にあった。
誰かに、これを持っているように命令されたのかもしれない。でもそれはわからない。
だからボクは、キミにこれを見せたんだ。これはボクの独断でやったことだよ』
…よくわからない。
そうこうしているうちに、ダウト・レイジが指をくん、と上に向けて動かした。
その動きに合わせるように、僕は外界へと意識を押し上げられていく。
『…今は、現在の状況に流されていればいいんじゃないかな。そのうち変化は来るよ』
彼の声が耳元で聞こえ、弾けて消えた。
空間同士のうねりに呑まれるように、僕は再び意識を失った。
第22話:「Dream is Over」
「…いつのことでしたかねぇ…」
タカラはぼんやりと窓の外を眺めながら、誰に言うでもなくぽつりと呟いた。
それを聞いたでぃが、問い返す。
「何デスカ?」
「ああ、でぃさんには話していませんでしたか」
「話シテイルモイナイモ、ソレダケノセリフデハ何モワカリマセン」
「…それもそうですね。じゃあ…でぃさんには特別に教えましょう」
下の階からはほとんど戦闘音が聞こえなくなっていた。
だがそのことを別に気に留める様子もなく、タカラは口を開く。
「僕が昔、神々の刻印の研究者をやっていたってことは知ってますよね?」
「ハイ。前ニ聞カサレマシタ。確カ…神ノ復活ヲ望ンデ研究ヲシテイタトカ何トカ…」
「ええ、その通りです。世界征服をするにあたり、『刻印』の創造主である神を復活させようと、
神の遺産である刻印に何かヒントはないかと思って研究していたんですよ」
「ソノ方向性ガ、ドウシテスリ替ワッタンデスカ?」
でぃはタカラを真っ直ぐな目で見つめて問う。
光のない、その白い瞳の無言の圧力に気圧される者は数多く居るが、彼女の主であるタカラだけは、
どうやってもその瞳に屈することはなかった。
「…何のことですか?」
「トボケナイデ下サイ。神ヲ復活サセル目的デ『偽リノ刻印』ヲ作リ出シタ訳デハナイデショウ?
恐ラク何ラカノ心境ノ変化ガアッテ、『神復活』ヲシナイデ世界征服ヲ成シ遂ゲルトイウ方向ニスリ替ワッテイッタハズデス」
タカラはふうとため息をつくと、両手を軽く上げて降参のポーズを取った。
だが表情の笑みは消えない。
恐らく、心底屈服した訳ではないのだろう。
そういった意味でも、でぃは彼を打ち負かすことが出来ずにいた。
「…参りましたね…このことはモナーさんぐらいしか知らなかったはずなんですけど」
「敵ガコノコトヲ知ッテイルノニ、何デ秘書ノ私ガ知ラナインデスカ。今マデノタカラサンノ行動ヲ見テイレバ大体読メテキマスヨ」
「僕、そんなにわかりやすいAAじゃないと思ったんですが…まぁいいでしょう。さっき『特別に教える』と約束しましたしね。
僕が構想を練っている段階のことは全てお教えします」
その時だった。
ドォン…
下の階の方で、微かな爆発音のような音がした。
音自体はそれほど大きなものではなかったが、部屋全体が少しきしむように揺れた。
「…マタ、アノ二人デスカ」
「ええ…羽が散るからあまり戦闘には行って貰いたくないんですけど…」
「私ハソレヨリモムシロ、柱ヤ壁ヲ腐ラセテシマウ方ガ困リマス」
「そうですね…それも困りますけど仕方ないでしょう」
タカラは椅子から立ち上がった。
「でぃさん。申し訳ないんですが、先程のお話の続きは後でもいいですか?」
「ハイ、構イマセン。タカラサンガ話シタイ時ニ話シテクレレバ良イデス」
「ありがとうございます。それでは…行きますか」
音もなく、部屋の扉が開く。
タカラとでぃは揃って部屋を出て歩き出した。
「…お客様のお迎えに」
遠のいていた意識が、蘇ってくる。
ほどけていた紐が、また結び直されていくように。
視界が、繋がる。
かちり。
「ポジ君っ!!」
目が覚めたのは、レモナさんの声だった。
ゆっくりと目を開けると、建物の群れに切り取られた空が映った。
もう、日は半分傾いている。
「…僕は…」
「ポジ君大丈夫?!」
「レモナさん…僕は…一体…」
むっくりと起きあがり、辺りを見渡す。
手には愛用の小型拳銃。
足下には巨大な鍵。
「全く驚いたな…」
フーンさんが呟く。
「俺が能力を発動させるまでもなく、鍵は見事に固定されていた。
しかも、封印を無理矢理塞き止めておいて、さらに強引に封印解除させるとはな」
「大耳ノ封印能力ハ本物ダカラナ! 鍵ガ刺サッタ状態カラ封印回避出来タ香具師ナンテ、オレモ聞イタコトガナイゼ」
つーさんも半ば唖然とした顔でこちらを見ている。
大耳はというと、もう唖然呆然のようだ。
「…鍵がひとりでに回って…勝手に解除しやがった…」
「…ひとりでに?」
「そうよ、ポジ君に刺さってた鍵が勝手に回り出して、封印解除されたの。
持ち主である大耳君がどんなに強い力で回しても駄目だったのに」
「…ひとりでに解除された…」
僕は先程のダウトとの会話を思い出していた。
もしかして、これもダウトがやったことなのだろうか。
「おおゆうしゃよ、のうりょくがつうじなかったとはなさけない」
そんなことを考える僕を尻目に、妙なニュアンスを含んだ言い方で、フーンさんが大耳に近づいていく。
大耳はもう目の前が真っ白になってしまっているらしく、フーンさんが近づいてきても身構えようともしない。
ただ、うわごとを呟きながら全身をがたがたと震わせているだけ。
それは、大耳がどれだけ自身の能力に自信を持っていたか、そしてどれだけその能力に頼り切っていたのかを表していた。
「…さて、ここまで時間がかかってしまったのは正直予想外だ。一番手っ取り早い方法で、この任務を終わらせるとするか」
フーンさんが目を開けた。
彼の後ろ姿しか見えない僕は直接見たわけではないけれど、大耳の動きが止まったのを見て確信した。
――――止めたのだ。大耳の「速度」を。
「残念だが、大耳。ここでDream is Overだ」
彼は呟いて、大耳の額に銃を押しつけた。
「その哀れな泣きっ面をフッ飛ばしてやる」
何の躊躇いもなく、引き金が引かれる。
乾いた音が、Vip区域に響いた。
第23話:「暗黒四重奏」
フーンさんが引き金を引く直前。
ごとん、と瓶が地面に落ちるような音がしたのは気のせいではなかった。
「…もう許してやったらどうだい、フーン君」
ばしぃっ!!
乾いた音が響いたかと思うと、フーンさんの手に握られていた拳銃は、その手を離れて地面に落ちていた。
僕はそれで、彼が撃つ瞬間に何者かの手によって叩き落とされたのだと悟った。
でも一体誰が…。
「…アンタの考えることは本当わからねぇな…」
フーンさんがため息混じりに相手を見やる。
「…マスター・ノマ」
彼の視線の先には、ノマさんが立っていた。
その手に、一振りの木刀を握って。
モナーは心底楽しそうな笑みを浮かべていた。
腕の魔物は奇妙に変態し、異臭を放つ唾液を口からだらしなく零している。
「…モナ達はタカラ君に話があって来たモナ。通してくれないのなら…」
魔物が巨大化する。
「容赦しないモナよ?」
そんな彼を見て、モララーが声をかける。
「モナー。今日は話に来ただけだろう? 下っ端はともかく、幹部まで頃すのは…」
「予定変更もあり得る、とも言ったはずモナ」
「それなら……ん?」
モララーの耳がぴくりと動いた。
「どうしたモナ?」
「何か来る」
しゅぴぴぴぴっ!!
彼が呟いた途端、二人の背後から沢山の羽が飛んできた。
羽とはいっても高速で飛んできているそれは、弾丸のようなものだ。
刺さったらただごとでは済まない。
ぶわっ!!
モララーは咄嗟に全身から風を巻き起こし、羽を吹き散らした。
モナーはもう片方の手を後ろに回し、手のひらを巨大な盾に変化させて受け止める。
「…あー、やっぱりかわされちゃったかぁ」
「まだまだ殺傷力が低いYO。やっぱこうしないとNE♪」
二人分の声がして、すぐに何かが飛んできた。
死角の方向から飛んできたそれは、ただの塊のような物体に見える。
だが、その周辺を不気味なオーラが包んでいるのは明らかだった。
「モナー、あの塊が何かわかる?」
「ちょっと確かめるモナ」
モナーは盾を引っ込め、モララーを下がらせると一歩前に出た。
そして、飛んできた塊を素手で掴む。
じゅわっ!!
途端、モナーの手が変な音を立てて溶けた。
だが彼は少し眉をしかめただけで、別段動じることはない。
そして、モララーに溶けた手をぶらぶらさせながら見せた。
「溶けたモナ」
「うわ、こりゃ派手に溶けたね。熱くなかった?」
モナーの手は手首から先が溶けていて、どろどろとした白い液体が床に落ちている。
わかりやすく言うなら、溶けたアイスクリームが手首から流れ落ちているような感じだ。
「んー、ちょっと熱かったモナけど…溶けたっていうより、一瞬で腐った感じモナね。
だから溶けたように見えたのかもしれないモナよ。それにしては中途半端モナ」
「…なるほどね。腐りすぎて、個体としての原型を留めなくなってしまったと」
「そうモナ。ま…モナにやってもあまり意味はないモナよ」
モナーがそう言うと同時に、手首からこぼれ落ちていた「手だったもの」が手首に吸い寄せられ始めた。
それらはあっという間に手首に集まり、変形して再び元の形に成る。
彼は元に戻った手を握ったり開いたりして感覚を確かめた後、不敵に微笑んだ。
「居るなら出てきていいモナよ。残りの幹部モナね?」
この空間を包んでいる、新たな殺気。
モナーもモララーも、とっくにそれに感づいていたのだ。
「やれやれ…参ったNA。僕の能力を軽く受け流すとはNE」
「だから頭狙えば良かったのに。楽しむ余裕がない相手なのは知ってるでしょ?」
「わかってるYO。アヒャとシーンがここまで苦戦する相手なんだしNE♪」
二人が現れたのは、モナー達の背後からだった。
足音ひとつ立てずに現れるところは、やはり戦闘慣れしている証拠だろう。
「初めましてだNE、僕はぼるじょあ。宜しくだYO」
「ぼるじょあ共々、お初にお目にかかりますね。私はエーと申します」
ぼるじょあの手からは淀んだ色のオーラが溢れ出していた。
それは先程モナーがつかみ取った塊の色と同じだ。
「さっきモナの手を腐らせたのはキミモナね」
「そうSA。僕の刻印は『Rot』って言ってNE、僕の放つオーラに触れたものは腐るんDA。
そのオーラを集めて塊にして、さっきみたいに飛び道具としても使えるんだYO」
そう言うとぼるじょあは手に持ったオーラをひゅっ、とおもむろに投げた。
先程は掴み取ったモナーだったが、今度はかわす。
「最初の羽の弾丸は…キミかい?」
「ええ、そうです。私の刻印は『Wing』…。私の身体からは自由に翼を生やすことができ、
さらにその翼を変形させたり、羽を弾丸のように扱ったりと様々なことに応用が可能です」
言い終わった彼女の背から、巨大な翼が生える。
その美しい姿に、モララーは苦笑いした。
エーは続けて言う。
「間もなく、私達の主君はここへ現れるでしょう。貴方達にはおとなしく待っていて頂きたいところなのですが…
それでは納得いかないだろうと思いまして。結果として私達が参りました所存です」
「タカラ君も結構な暇潰しを用意してくれたモナね。…モナ達は今、ちょっと退屈モナ。
楽しませてくれるのなら、付き合ってあげてもいいモナよ」
「主君から、お客様を退屈させてはならないとの指示がありました。
今、お二方が退屈してしまっていらっしゃるのは私達の配慮の至らなさが原因です。ですから…」
エーとぼるじょあがアヒャとシーンの前に立つ。
残る二人も立ち上がった。
「…『Fakers』幹部…『
我ら『
「…僕はもう正直うんざりなんだよ」
ノマは木刀を手に握ったまま、大耳の狂った横顔を見た。
「今まで、沢山のAAが頃される様を見てきた。これも、自分の宿命なら仕方ないと思った時もあったさ。
でも…決して見ていて気持ちのいいものではない。…だから、僕の前では出来る限りの頃しは控えて貰いたいんだ」
「フーン、相変わらずの自分勝手だな。モナーがどうしてアンタを構うのか、未だに理解できねぇぜ。…戦闘能力は認めるが」
フーンが吐き捨てるように言う。
大耳はもう失神直前のところまで来ているようだ。
それを見たノマはすっ、と大耳の背後に回り、木刀を振り上げた。
ぼごっ!!
鈍い音がして、大耳が地に沈む。
彼がすっかりノビてしまったのを確認すると、ノマは木刀を下ろした。
「…あまりにも哀れだからね。おとなしくさせたよ」
「アヒャー…マスター、チョット機嫌悪ソウダナ」
つーさんが呟いたのを聞いて、僕は尋ねた。
「今の…フーンさんの拳銃を叩き落としたのって、ノマさん…ですか?」
「ソウダ。マスターハ、剣術ノ達人ナンダゼ。確カ…『ノマノマ流』トカ言ッタカ」
「でもAAを斬るのは性に合わないって言って、代わりに木刀を持ち歩いてるの。
そのままでも十分強いけど…米酒を飲んでからだと異様に強くなるわね」
「そうだったんですか…」
僕は先程の彼の早業を思い出して、息を呑んだ。
本来守られる立場のノマさんが、フーンさん達と対等…
いや、それ以上かもしれない程の戦闘能力を持っているだなんて思いもしなかったからだ。
「ここは僕に免じて…彼を見逃してやってくれないかな。モナー君に何か言われたら、僕が責任を取るよ。
それに、頼まれていたボルジョア・ヌーボーも2本に増やすからさ。キミもあの酒は好きだろう? フーン君」
「…納得いかねぇが…アンタが責任取ってくれるのなら、俺はそれ以上何も言わん。
ただ、あいつを怒らせると色々と面倒だからな。頃すのが好きな香具師だけに」
ふぅ、とフーンさんが初めて息をついた。
銃を納め、ふと大耳を見やる。
「…で、このろくでなしはどうするつもりだ?」
「放っておくさ。そのうち、向こうからお迎えが来るだろうし。それより、早いところ店に来るといい。今日は沢山の酒をご馳走するよ」
「やったぁー!! マスターってば、太っ腹♪」
レモナさんが飛び跳ねて喜び、つーさんも楽しそうに笑う。
ノマさんは苦笑いを浮かべ、僕に視線を向けて言った。
「それに…新しく入ったっていうキミのことも聞きたいしね」
第24話:「接触」
「『
モララーの疑問に、エーが答える。
「はい。私達はFakersの幹部グループである『
その中で、私達4人を特別に指していう呼び名…まぁ、異名みたいなものでしょうか。
それが『
「何とまぁ、小綺麗な異名だこと」
「でも」
呆れるモララーにモナーが言う。
「名前の美しさと強さは、必ずしも比例しないモナ」
「そうかNA? だったら試してみてもいいけDO?」
「タカラ君がせっかく用意してくれた暇潰し…使わせて貰わないのは失礼だしね」
「アヒャ! 暇潰シデハ終ワラナイコトヲ思イ知ラセテヤルヨ!!」
「…御託はそれまでにして…さっさと始めるモナ」
ぼごっ、とモナーの片腕が蠢く。
さっきまで魔物だったその腕は、巨大なハンマーに変化した。
「モナー…それ、『ガッハンマー』じゃん」
「そうモナ。一人でもぬるぽする香具師が居たら…ガッしてやるモナ」
「だったら、言わない方が良いNE!」
言うと同時にぼるじょあが地を蹴り、一気に間合いを詰めて来た。
手には、先程の腐食のオーラ。
モナーも走って間合いを詰め、速度の勢いに任せてそのままハンマーを振り下ろす。
ドォン…
だが、ハンマーが捕らえたのは床だけ。
モナーはむ、と眉をしかめた。
背後からぼるじょあの声が響く。
「そのハンマー、当たったら痛そうだけDO…大振りになるから小回りは利かないよNE」
オーラを纏ったぼるじょあの手が、モナーに伸びる。
狙いは、頭。
「そうはさせないからな!!」
ぼわっ!!
モララーが叫ぶと同時に、モナーとぼるじょあの間に炎の壁が出来た。
ぼるじょあが慌てて数歩退く。
「おっと、危ないじゃないKA。そちらさんもなかなか厄介な能力をお持ちのようDE」
「モナーばかり構って貰うのは狡いからな。僕も楽しませておくれよ」
「なら…」
エーが前に進み出た。
「私がお相手致しましょう。アヒャとシーンは後ろで私達の援護をおながいします」
「援護カァ、オレハアマリ得意ジャナインダガナ」
「…わかった。その代わり、急に僕の能力が発動しても驚かないでくれよ」
モララーは視線をエーに向けた。
彼女の翼は淡く発光しており、今にも攻撃を放ってきそうな雰囲気だ。
今まで多くの敵と戦ってきたが、流石は「Fakers」の幹部ともなると、かなりの殺気が全身から溢れ出している。
久々に感じる「大物」の空気に、モララーはひゅうと口笛を吹いた。
「なかなか良い殺気を放つんだね。モナーほどじゃないけど」
「あの方は別格なのでしょう? 貴方の組織の中でも」
「そうだね。確かにそれは合ってる。氏なないし、殺人狂だしさ」
エーはモララーの目をじっと見て、訊いた。
「…貴方はご存じなのですか?」
「ご存じって…何を?」
「あの方がなぜ不死なのか、その理由です」
モララーは少し躊躇うように俯いたあと、答えた。
「…知っているはずがないからな。本人だってよくわかっていないのに」
「そうですか。なら良いんです、始めましょう」
エーの両の翼が、巨大な拳に変形する。
低い体勢で地を蹴り、拳の片方を後ろへ引き絞ると一直線に打撃を放った。
だが、モララーも読んでいる。
サイドステップで横に飛び、一撃をかわすと片手に冷気を宿らせる。
「その翼、動かなくしてあげるよ」
冷気を帯びた手が、伸びきったエーの拳を掴む。
かきぃぃぃぃん!!
途端に強い冷気が吹き出し、エーの拳の先から一気に翼の根元までを凍らせた。
エー本人までは凍っていないものの、相当の痛手となったことは確かだ。
「どうだい? これでキミの拳は片方封じた。残るはもう一つだね」
だが、エーは表情を変えない。
「…だから、どうしたというのですか?」
ぴしり。
彼女がそう言うと同時に、翼の動きを止めていたはずの氷にひびが入った。
「なんて力だ…並じゃないね。でも…」
モララーは舌打ちしつつも、今度は両手に再び冷気を宿らせる。
今度の冷気は、さっきよりも勢いが強い。
握りしめた手の中から零れてくるドライアイスのような煙が床に触れる度、そこを次々と凍らせていく。
「今度はそう簡単に壊せない強度で凍らせてあげるまでさ」
片方の翼と両足が生きている以上、遠隔攻撃は効かないだろう。
そう判断した彼は、冷気を逃がさないようにしっかりと両手を握りしめ、間合いを詰めるべく走り出した。
「…あら、貴方は近距離戦が不得意だと聞いていましたが」
「その通りだよ。でも、別に駄目な訳じゃないからな!」
本来は近距離戦を苦手と自負するモララーだが、決して戦えない訳ではない。
近距離派のつーやレモナ、オールラウンダーのギコやフーンの戦法を見て、常に努力はしてきているのだ。
彼はそのまま前に飛び、敢えて正面から突っ込んだ。
「ぼるじょあが言っていたのを思い出してね。大きな翼では、小回りが利かないだろ?」
モララーがにや、と笑う。
だが、エーは冷静にその視線を受け止め、答えた。
「…小回りなら、いくらでも利きますよ」
「あー、美味しい!! やっぱりマスターのカクテルは最高ね!!」
「アヒャ! マスター、今度ハ『カンパリオレンジ』飲ミテェゾ!!」
「マスター、私も! 『キス・イン・ザ・ダーク』おながい!」
「はいはい、ちょっとお待ち下さいね…」
一仕事終えた僕達はギコさんに連絡を入れた後、ノマさんのお店「BARマイヤヒ」に来ていた。
モナーさんからの頼まれものがあるから、ここに来るのも一応仕事のうちではある。
でも、つーさんやレモナさんはすっかりマターリモードになっていた。
「えーっと、ポジ君だったかな? キミも何か飲むかい?」
「あ、でも…僕、自分がお酒に強いか弱いか、はっきりとはわからないんです。
何回か飲んだことはあるんですけど…小さいビール缶ぐらいですから…」
「そうか、じゃあノンアルコールカクテルから試してみたらどうかな? ちょっと待っててね、ちょうどいいのがあるから」
「はい…ありがとうございます」
ノマさんはニコニコしながら、シェイカーにお酒を注ぎ始めた。
「フーン君は何か飲む? さっきのこともあるし、サービスしておくよ」
「ふーん…じゃあ、『ジン・ビターズ』くれ」
「かしこまりました~」
彼はとても手際が良い。
4人からほぼ同時に受けた注文を、たった一人で次々にこなしていっている。
僕だったら、作っている間にきっとお客さんから遅いという苦情を浴びてしまうだろう。
「はい、お待たせ。レモナちゃんは『キス・イン・ザ・ダーク』。
つーちゃんは『カンパリオレンジ』。フーン君は『ジン・ビターズ』だったね。それから、ポジ君のは…と」
ノマさんは3人にそれぞれのカクテルを出した後、僕のカクテルを出してきた。
「はい、ノンアルコールカクテルの『シンデレラ』だよ」
そのカクテルは、ややオレンジがかった黄色をしていた。
見た目は普通のジュースのようにしか見えない。
正直、普通にスーパーとかで売られていそうだ。
「…これって、何だかカクテルっぽくないですね」
「そうだね、ノンアルコールカクテルにはそういった感じのものが多いんだ。どうだい? 試しに飲んでみなよ」
ノマさんに言われて、僕はグラスを口に運ぶと傾けた。
口に広がるのはレモンとオレンジの風味、そしてパイナップルの華やかなフレーバー。
まぁ、一言で言うと…甘い。
まさにジュースそのものだ。
「…これ、本当にカクテルですか?」
「うん。れっきとしたカクテルさ。ノンアルコールだから、お酒は入ってないけどね。
オレンジ・レモン・パイナップルの3種類のジュースをステアしただけのものだよ」
「ああ、だからこんなに甘いんですね」
ノマさんは頷くと、カウンターの下から米酒の瓶を取り出した。
それを見たレモナさんが、思わず尋ねる。
「ねぇ、マスター…。相変わらず米酒が好きみたいだけど…。どうしてなの?」
「どうして、って…僕はこの酒と共に生まれて来たようなものだよ。人生の相方でもあるこの酒を捨てられるわけがないじゃないか」
そう言うノマさんの米酒を見る目は、とても穏やかだった。
「キミにとってのモナー君と同じだよ。なぜキミがモナー君を愛しているのか。
キミはその質問に対する、ちゃんとした答えを持っているかい?」
レモナさんがはっ、と言葉に詰まる。
ノマさんは苦笑いして、瓶のフタを開けた。
「…ごめん。今のは僕の八つ当たりだった。キミの愛に理由なんて要らなかったね」
「いえ…それは…」
「いいんだよ、忘れてくれ」
ノマさんの手にしたグラスに、米酒が注がれる。
透明なその色は、どこかノマさんの瞳に似ていた。
プルルルル…
途端、フーンさんの携帯が鳴った。
彼は傾けていたグラスを置くと、すぐに電話に出る。
「…俺だが。ああ、ギコか。 モナーとモララーはまだ帰ってないのか?
あの二人にしては遅いんだな。…わかってるよ、酒はちゃんと持って帰る」
どうやら、電話の相手はギコさんのようだ。
「…あ? ああ…わかった。次の任務はそういうことになるな。つーとレモナに伝えとく。
ポジは明日どうするんだ? …そうか。まぁ…まずはモナーが帰ってからだな。
じゃあ、なるべく早く本部に戻るようにする。わかった、また後でな」
フーンさんはそう言って電話を切った。
同時につーさんがグラスを置いて尋ねる。
「フーン、ギコガ何カ言ッテ来タノカ?」
「次の任務の話だ。詳しくは後で正式発表があるらしい。その下準備もあるから、早く本部に戻るようにとの指示だ」
「でも、モナー君はまだ帰ってないんでしょ? 心配だわ」
「あいつのことだ、どうせまた楽しんでるんだろ」
そう言うとフーンさんは一気にカクテルを飲み干し立ち上がった。
「話は聞いてたろ? マスター。ボルジョア・ヌーボーの瓶をくれ」
「わかった。どうやらキミ達も相当忙しいようだね」
ノマさんはカウンターの下からやや大きめのボトル二つを取り出した。
「これだよ。落とさないように気を付けて」
「マスター…オレ達ハ子供ジャナインダゼ?」
つーさんが呆れながら、一本を持つ。
残りの一本はレモナさんが持った。
「じゃ、そろそろ帰りますね」
「マタ飲ミニ来ルカラナ!」
「今度はツケじゃなくてちゃんと現金で支払い頼むよー」
さりげなく痛いノマさんの一言に押されて、僕らは店を出た。
外はもうすっかり夜が更けてしまっていて、視界も悪い。
ぽつりぽつりと灯っている街灯を頼りに歩き出す。
「…疲れた…」
僕は3人より少し後ろを俯き加減に歩きながら、ぽつりと呟いた。
昨日もそうだったが、今日はもっと色々なことがあった。
躊躇っていたはずの殺人をしてしまいそうになり。
自分の意識が封印されそうにもなって。
でも、あのダウト・レイジとか言う変なモナー族に救われたんだっけ。
「…何だかなぁ…」
ため息をついて、ふっと顔を上げる。
その時、ちょうど向かい側から歩いてきていた誰かとぶつかりそうになった。
「あ、すいません」
「あ…いえ、こっちこそぼんやりしてて…すいません」
街灯に照らされた相手は、片耳のモララー族だった。
モララー族にしては珍しく、残された片耳だけが白い。
フードつきのマントという、今時流行らないファッションスタイルだ。
「そ、それじゃ…失礼します」
何だか気まずくなって、僕が逃げるように歩き出した時だった。
「…キミには、もう一つの刻印の器があるね。それはいずれ手にするよ」
「っ?!」
僕は思わず振り向いてしまった。
相手の声が、あの時のモナー族…ダウト・レイジのものにそっくりだったからだ。
だが、さっきの人物はもうそこには居なかった。
「オーイ! ポジ! 何ヤッテンダー!! 置イテクゾー!!」
つーさんの声で我に返った僕は、慌てて3人の後を追いかけて行った。
第25話:「対談」
「その辺になさったらどうですか?」
その場に居た全員が聞き覚えのあるテノールが、突然響き渡った