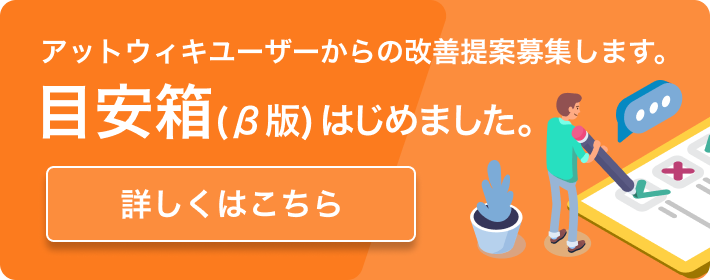学校の門を出て少し歩くと小さなアイスクリーム屋がある。
店に寄り道するのは殆どが女子だ。白とピンクに彩られた店のケースの中には彩りの豊かなアイスクリームが並び、それを眺めながらどれにしようか迷う姿が穏やかな放課後を物語っている。
ところが。
「今ヒマ? ちょっと付き合えよ」
浮かれたアイスクリーム屋の前に今日は異変が起きている。
(何やってんだ? アイツ)
ギコは立ち止まると、アイスクリーム屋に出入りする女子に片っ端から声をかけているモララーを眺めた。
この学校の生徒ではない。
自分達よりも少し年上のように見える。高校生…くらいだろうか?
暇をもてあました卒業生がナンパでもしに来たのだろうか。それにしては…彼は遊んでいる風貌には見えない。
モララーは行き交う生徒たちに完全無視をされている。無視ではない。“完全無視”だ。
中には遊び好きそうな女子もいる。逆にナンパなど嫌いそうな硬い女子もいる。
何人かに一人くらいは立ち止まって目を合わせても良さそうなものだし、逆に“ウザい”と睨まれても良さそうだ。
が、誰一人として反応無しなのだ。こんな虚しいナンパ風景は初めて見る。
「ギコ!」
つい、立ち止まっておかしな風景に目を奪われていたギコは背中をポン、と押されて我に返った。
「一緒に来る?」
「あ?」
ぱっちりとした目のガナーはそう言うと隣に立つしぃとクスクス笑い合った。
「さっきからずっと見てるんだもん。男子一人じゃ入りにくい?」
「ねぇ、行こうよ。ここのアイス美味しいよ」
そう言われてギコは初めて自分が“アイスクリームに見とれている”と誤解されていることに気づいた。
「ばっ…違っ! そうじゃねーよ!」
別にアイスクリームは嫌いではない。が、ボケッとつっ立って食べ物に見とれているなんてみっともない誤解をされたくはない。
「俺はただ、アイツの事が気になって……!」
こうしている間にも物凄い勢いで完全無視の記録を更新中のモララーを指差した。
今もまた店から出てきた上級生に声をかけ…無視をされている。
「……ふーん」
ガナーはチラリとアイスクリーム屋に目を向け、そう言うとしぃの腕を掴んだ。
「行こ」
「?」
何故か突然態度が冷たくなったような気がする。
一方、腕を引かれたしぃは少しだけギコの方を振り向き、すぐに店の方へ視線を戻し、心持ち俯いた。
二人はそのまま真っ直ぐに店の入り口に向かった。
ドアを開ける直前、顔をあげたしぃが連敗中のモララーをチラリと見る。モララーもしぃの顔をじっと覗き込んでいる。そして例によって─────
「ねえ、君さぁ…」
と声をかけた。
よもやナンパが成功するとは思ってはいないが、心配になる。
二人ともクラスの中でも感じの良い女子グループに入っているのだ。いくら知らないナンパ男とは言え、視線を合わせて話しかけてくる者に完全無視を見舞うなど、ありえないような気がした。
ヘタをすると立ち止まってしまうかもしれない。いや、それはそれで彼女達の自由なのだが。
「今こっち見たよね?」
“目があった”なんて陳腐なナンパの言葉だ……
ギコは他人事ながら頭を抱えそうになった。そりゃあ勿論、自分にはナンパなどという真似はできない。できないが、高校生にもなってその程度か? と問い詰めたくなってくる。
(うちのクラスのモララーの方が上手いぞ……)
まあ、あの二人の事だからここまで陳腐なナンパにも「すみません」と言って通り抜けるぐらいはしてくれるだろう。そう思った。
(え?)
肩にかけていたカバンがずるり、と落ちる。予想は見事に外れた。。
面と向かって視線を合わせた相手に二人は“完全無視”をしたのだ。
“当然だろう”という気持ちと“嘘だろう?”という気持ちが複雑に交じり合う。
呆然としているギコの目の前で二人は店の中に姿を消した。
「おい、そこのお前!」
店の前からモララーが声をあげる。
ギコはキョロキョロと辺りを見回した。ちょうど下校途中の生徒の流れが途絶えていて誰もいない。
「お前だよ」
モララーが真っ直ぐにこちらに向かってくる。
「お前、ずっと俺の事見てたよな?」
ヤバい。ナンパがうまく行かずに当り散らしに来るつもりだろうか?
「とぼけたって判るからな! お前、ずっとこっち見てただろ?」
ナンパよりはむしろケンカの方が自信がある。だからと言って学校の目の前でケンカ沙汰は…望まない。
「別に。何か文句でもあるのか?」
心と口の裏腹な連携プレーに少し呆れる。これは一層ヤバい。そうこうしている間にモララーとの距離はどんどん縮まる。
「お前、ヒマなら俺に付き合え!」
「ハァ?!」
臨戦態勢だったしっぽがだらんと垂れ下がる。
無理もない。放課後、ピンクと白の愛くるしいアイスクリーム屋の前で甘い香りに包まれながら…モララーにナンパされてしまったのだ。
「お前に会えて良かったよ」
全身に不快感が走る。ここに鏡があったなら間違いなく「脳天からつま先まで全て鳥肌が立った自分の姿」を見られただろう。
「お、俺は男だ! ゴルァ!」
握り締めた拳がわなわなと震える。
「見りゃ判る」
モララーは全く気にしないらしい。彼は非常に嬉しそうな表情でそう返した。
目の前で見るモララーはギコより20センチ程度視線が上にある。離れて見るよりも大きい。
「俺にそんな趣味は無え!」
「お前の趣味なんて聞いちゃいないさ。ヒマなんだろ? 行こうぜ」
(行こうぜって……何処にだよ?)
うっかりそう考えてから相手のペースに乗せられかけている自分に気付く。このままでは駄目だ。
ギコは先程から沢山の女子達が見せてくれた手本を思い出した。
“完全無視”だ。
もはやこの変態モララーから逃れる手立てはこの手一つしか無い。早く逃げろ、ヤバい相手に関わるな。
本能がそう叫んでいる。そして幸いな事にギコの足はその本能の叫びに忠実に従い、歩き出した。
「お前じゃなきゃ駄目なんだからな!」
モララーは再度鳥肌モノのセリフを言いながら追いかける。足は速いようで、彼は難無くギコの前に回りこむと後ろ向きに歩きながらギコの顔を覗き込んだ。
「うぶっ……」
突然、現れた黒い影に真正面からぶつかる。
「あらヤダ、気を付けなさいよ!」
ギコを跳ね飛ばし、微動だにしなかった買い物途中の主婦は不快な声でそう言うとフン、と鼻息を残して立ち去った。
「大丈夫か?」
諸悪の根源であるモララーが、立ち去った主婦の後ろから現れる。
「うるせぇ!」
その声に周囲が驚いて振り返る。
背後からぶつかった主婦が「悪態だけは一人前だよ」と聞こえよがしに言い放った。
“お前のせいだぞ!”
そう言おうと開いた口が凍りつく。ギコの目にはとても恐ろしい光景が映っていたからだ。
「大丈夫? 目が悪いのならちゃんとメガネかけなきゃダメよ?」
優しそうな“お姉さん”が手を差し出している。
それだけ言うと「とても良い光景」なのだが……問題が一つだけ。
その“お姉さん”の顔はモララーの腹の辺りからニョッキリと出ているのだ。手は…右膝より少し上辺りから。
程無く、その“お姉さん”は完全にモララーの体から分離し、こちらに出てきた。
「……お前以外、誰も俺の事“見えない”んだよな」
いやあ、参った参った。そんな表情で笑うモララーの体を通りすがりの爺さんがスルリと通り抜けてゆく。
「─────」
どうやらホモのナンパ男よりもヤバいヤツが自分だけに見えるらしい。
レンガ敷きの歩道の上に座り込んだまま、ギコは軽い目眩に襲われた。
----------------------------------------------------------------------
2
「……成仏しろ」
ギコは歩きながらボソリと言った。
今まで霊感は強い方ではなかった。だから“他人には見えない者”が自分にだけ見える、などという夏向きな現象に出会ってもそう言ってやるしかない。
「?」
言われた本人はギコの言葉の意味が解らなかったのか、相変わらず道行く人々を通り抜けながら歩いている。
(幽霊って本当に居るんだな)
不思議と怖い気がしないのは、昼間のせいかもしれない。いや、ハッキリと見え過ぎる姿のせいか。
ギコは数年前、祖父が他界した直後の妹の言動を思い出した。確かあの時、妹は暫くの間「おじいちゃんがソファーに居た」だの、家族で乗った車に「乗ってきた」だのと言っていた。
幼い妹が「死」を理解できずに“そんな気”になっているのだろうと思っていた。母親がその都度「じーじはもう居ないのよ」と優しく膝の上に抱きながら言い聞かせていた。
今思えばあの時、本当に祖父はそこに居たのかもしれない。いや、「居たのかもしれない」ではなく「居たのだ」だろう。
ここまでハッキリと証明する人物が目の前に居るのだから……
「お前さぁ、何でここに居るわけ?」
幽霊というものは、大抵の場合はこの世に恨みや未練があって存在する。夏休みにテレビで見たオカルト特集で霊能者がそう言っていた。
だとしたらこのモララーにもこの世に留まっている原因がある筈だ。
「人探し」
「人探し?」
幽霊というものは行きたい所に瞬間的に移動ができる、という噂を聞いた事がある。残念ながらそれは嘘らしい。現に今、行き所(相手)を探して彷徨っている奴がここに居る。
ギコの足は知らず知らず公園に向かっていた。
このまま自宅に霊を連れ帰るのに抵抗があったからかもしれない。
「だから成仏できないのか? 会えれば成仏できるのか?」
「お前さっきから何言ってんだ? 俺は死んだ覚えなんか無いからな」
「それだ!」
よく「天国からのメール」なんて番組でもそんな話が出ている。霊能者が霊と話しをして、「あっという間の出来事で、自分が死んだと理解できていない。これから事故現場に行きましょう」なんて言って霊を背負って行く。
このモララーもその類なのかもしれない。
「お前、死んでんだよ。それが解ってねえから成仏できねえんだ」
ゴキッ!
モララーの右ストレートがギコの顔面に綺麗に決まった。
(何でだよ?)
相手は幽霊だ。確かに、殴ろうとしているのは見えていた。が、通り抜けるのだから問題無い。そう思って避けずにいたらこのザマだ。
鼻の頭が熱い。気付いたら鼻血がパタパタと音をたてて地面に滴った。
「し…信じらんねえ」
幽霊というものは見える者には触れる事ができる。また一つ、知識が豊富になった。他人に話した所で信じてはもらえない、トリビア中のトリビアだが。
もう何が何だか解らない頭の中に“へぇ”という音がこだましてぐるぐると回っているような気がしてきた。
「俺は死んでなんかいないからな!」
これで解っただろ? とモララーは拳を解くとギコの腕を引っつかんで近くのベンチに座らせた。
「おーい! ギコ!」
ティッシュなど持っていなかったので、下を向いて小鼻をつまむ。暫くこのままでいれば止まるだろう。そう思っていた矢先、聞きなれた声に呼ばれた。
「アヒャヒャ! お前、何興奮してんだよ?」
小学生の時にいつもつるんで遊んでいた仲間の一人、つーが鼻血まみれのギコを指差しながら笑っている。学校には結構な数のつー族が居る。性別不詳のため好きな方の制服を着て良い事になっている友人は、先週は男子用のブレザーだったが、今週はセーラーを着ている。
「おい、お前ティッシュ持ってねぇ?」
腹を抱えて笑い続けるつーの隣でフサが訊く。つーはポケットを探ることもせずに“そんなもん、持ってるかよ!”と即答した。
「いい、すぐ止まるだろ」
真正面からのパンチで大きな血管が切れたらしい。鼻血は結構な勢いで出ている。が、先程よりは治まってきたようだ。
「ちょっと待ってろ!」
ひとしきり笑うと満足したのか、つーは公園の公衆トイレに走って行き、女子トイレからトイレットペーパーを1個丸ごと持って来た。
「使え!」
安物のゴワゴワしたトイレットペーパーをダンゴ状にして鼻に押し当てる。
ティッシュはすぐに真っ赤な水分を含んでしんなりとし始めた。
「で? どうしたんだよ?」
まさか本当に興奮して鼻血が止まらないわけではあるまい、とフサは訊いた。ギコの顔面の中心が赤味を帯び、衝撃を加えられた形跡がある事は一目瞭然だ。
“そこに居る幽霊モララーに殴られました”
(……って言っても信じられないだろうしな)
ギコは相変わらずフサやつーを通り抜けさせているモララーを横目で見ながら考えた。
二人とも通り抜けているという事は、“見えない”という事だ。
そこを「信じてくれ、ここにモララーの幽霊が居る。そいつに殴られた」と言ったら……頭を打ったと勘違いされて自宅か学校に連絡されるのがオチだ。
ギコは適当に通りすがりの人にぶつかって殴られた、と説明する事にした。大した怪我ではないし、それが一番無難だろう。
「実は……」
ドッ、ガシャン!!
適当に頭の中で話を組み立てながらギコが口を開いた瞬間、大きな衝撃音がすぐ近くの交差点から響いた。
やにわに騒がしくなってゆく周囲に、嫌でも大きな事故が起きたのだと解る。
「事故かよ」
フサとつーが立ち上がり、交差点の方を伺う。
「見に行こうぜ!」
派手に潰れた車が見られるかもしれない、と走り出したつーを二人が追いかける。ギコはトイレットペーパーを抱えたままだ。
事故現場にはすでに人だかりができ始めていた。大型ダンプが交差点に斜めに止まり、対向車線で小さな乗用車と衝突している。ワゴン車が乗用車を避けるようにダンプが進むはずだった車線へとはみ出し、その前輪と後輪の間に……人らしき体が倒れ、夥しい血液が広がっている。
飛び出してきた者に気づいたダンプが避けようとしてハンドルを切ったが間に合わず、撥ねた直後に対向車線にはみ出し、乗用車と衝突。その衝突された車の後ろを走っていたワゴン車が追突を防ぐためにハンドルを切り、飛ばされた者を轢いて停止。そんな状況が見てとれた。
「うわ……ひでぇな」
フサが思った以上の悲惨な状況に顔をしかめる。
大喜びで走っていったつーも凍りついたように動かない。血溜まりの現場から目を逸らせずにいる。
そんな中、ギコは一人の人物に目を奪われた。
モララーだ。
先程知り合った幽霊モララーではない。彼は黒いのでウララーなのかもしれない。
黒モララーは現場の真ん中をウロウロと歩き回り、ダンプでグシャグシャになった乗用車の運転席を覗き込んでいる。そして何かを取り出し、運転席にいる者にそっと手渡した。
それからくるりと振り向き、ワゴン車の下に仰向けに寝転がっている者を覗き込み、先程と同じように黒い塊を胸の上にそっと置いた。
塊は程無く体に吸い込まれ、それ以上何も起きない。
彼の行為を周囲の誰もが咎めない。それどころかあの幽霊モララーと同じように“完全無視”をしているようだ。
(まさか……)
ギコは嫌な予感と共に彼を目で追った。
黒モララーは幽霊モララーと同じように涼しい顔で人の体を通り抜け、ギコの傍まで来るとニヤニヤしながら言った。
「こっち見んな」
「!」
誰一人、彼を追うものは居ない。
「やあ、お疲れ」
事故現場から離れてゆく彼に声をかける者が現れた。
あの幽霊モララーだ。
ギコはフサとつーを振り返った。二人ともまだ人だかりの中で背伸びをしながら釘付けになっている。現場はサイレン音が鳴り響き、救急車の到着を知らせていた。
「アイツ何?」
「見えるらしい」
「へー」
二人は知り合いらしく、並んで腕組みをしながらこちらを眺めている。
「お前、さっき何やってたんだ?」
もう驚くのは飽きた。それよりもこの不思議な二人の正体が気になる。ただの幽霊ではなさそうだ。
「何って……卵をあげただけ」
黒モララーはそう言ってニヤリと笑った。
----------------------------------------------------------------------
3
「たまご?」
先程の光景には不釣合いな食品名にギコは抑揚無く呟いた。
「卵」
黒モララーは涼しい顔で再び言うと、真っ黒な塊の乗った掌をギコに向かって差し出した。“見る?”と言わんばかりに。
非常に危険な予感がするものの、その黒い卵から目が離れない。ギコはふらふらと歩み寄ると漆黒の卵に手をのばした。
「やめろよ。クロ」
「冗談だよ」
ギコの指があと数センチで卵に触れる、といった所で彼はオモチャを取り上げるいじめっ子のようにヒラリと腕をかわした。
「俺は忙しいんだからな」
クロと呼ばれたモララーはそう言うと左右の肩を2,3度コキコキと鳴らした。その音に合わせているのか、背中が異常に変形して盛り上がる。
何が起きるのかと思って見ていると、その盛り上がった背中を突き破るように黒い翼が現れてばさりと音をたてた。同時に風が足元から巻き起こり、たった一度の瞬きの間に“クロ”の姿は消えて無くなった。
救急車のサイレンが再び鳴り始める。
ギコは妙な興奮を覚えている自分に気付いた。胸がドキドキと高鳴り、冷たく、ぺったりとした汗を足の裏や掌に感じる。
鼻血はいつのまにか止まっていた。手に持っていた筈のティッシュを落とした事にも気付かなかった。
「……お前ら、何者だ?」
幽霊ではない。幽霊は自在に翼を出したりひっこめたりなどという芸はしない。
「配達屋」
「何の?」
「卵の」
先刻の“クロ”もそう言っていた。あの掌の上に乗せられた漆黒の塊。
形は確かに卵に似ている。が、あんな真っ黒な卵は見た事が無い。濃淡に差はあるが茶色いものならば店でパック詰めになっているものをいつも見る。
母親がそれを目の前で割って調理したものを食べた事も数え切れないくらいある。
百歩譲って普通の卵を真っ黒に染めたものだとしても……あの時感じた衝動は何だったのだろう?
目を逸らす事ができなかった。
体が勝手に吸い寄せられ、手に取って握りたいと思った。
それが何であるのか、本能は知っているような気がする。しかし、言葉にして認識してしまったら引き返せないような気もする。
「何の卵なんだ?」
(言うな!)
ギコは心のどこかで目の前のモララーが答を告げずに去って行く事を望んだ。
自分は何の変哲も無い、普通の中学生の筈だ。
退屈な授業にあくびを噛み殺し、友達とバカ笑いをしながら放課後を過ごし、自分の将来を考えるのはもう少し先になってから……と漠然と考えている、ただの中学生の筈だ。
ならば何故訊いてしまったのだろう? 訊かずに逃げ出してしまえば良かったのに。
モララーはその答を知っているかのような顔でじっとギコを見据え、期待を大きく裏切った。
「さっきのは“死卵”」
「…………」
「クロは“死”を配達してる。運命に従って、逝く者の左手に握らせれば配達完了」
ギコは最後まで聞く前に吐き気を覚えた。
ならばあの時、この手に卵を握っていたのならば……
「あの卵に惹きつけられたのはお前が生きているから。生と死は必ず一対だからな」
“左手に握らせれば配達完了”
まだ嫌な感触の汗が残る左手を見る。そう言えば利き手は右手の筈なのにあの時伸ばしていたのは左手だった。
「死神……なのか?」
もし、そうだとしたならば……それが見える自分はとても危機的な状態にあるのではないか?
「神様じゃない。ただの配達屋だ」
「…………」
「そんな顔するなよ」
モララーは公園の中に戻りながら呟いた。
ギコは彼の後に付いて行くべきか否か迷った。のこのこと付いていってあの黒い卵の餌食になるわけにはいかない。
が、何故か彼らが自分を騙して命を奪おうとしているようには思えない。
それはついさっき、あの黒い卵を自分が握ろうとしていたのを止めてくれたからなのかもしれない。餌食にするつもりならばあの時点でできていた筈だ。
“運命に従って、逝く者の左手に握らせれば……”
「運命は……」
ギコはフェンスの内側に植え込まれているベニカナメの葉の向こうに消えたモララーに訊いた。
「運命は誰が決めるんだ?」
「知らない。たぶん、神様なんじゃないか?」
「たぶん?」
「俺達も知らない。どうして受け取る相手が決まっているのか。どうして俺達は配達するのか。いつからそうだったのか」
「決まっているって?」
「卵にはちゃんと受け取るべき相手が決まっている」
「じゃあ、さっき俺があの卵を握っていたら?」
「握れない。弾かれるだけだよ。まあ、悪くすれば体調崩すくらいの事はあるけど」
一人一人、全員に必ず一対。
確かに不死の者など世界中を探しても一人も居ない。
「クロはあの卵のせいで人々に忌み嫌われている。死は必ずしも“奪う”だけではないのに」
今この瞬間も、彼は“死”を配達し続けている。
「お前は? お前も握らせるのか? あの黒い……」
「俺が配達するのは違う色の卵だよ」
その言葉にギコは安堵した。足元を見ると影が少しだけ長くなっている。陽が翳り始めたのだ。
植え込みの向こうで風が巻き起こった。ギコはモララーが“クロ”のように翼を出したことを悟った。
「在庫がダメになっちまうからな。俺はもう行かなくちゃならない」
葉の隙間から薄い黄色の羽根が零れ落ちる。彼の体と同じ色の羽根だ。
「探して欲しい人が居る。あいつは飛べないからたぶん、この辺りをウロウロしている筈なんだ」
「おい、待てよ!」
小さな竜巻のように風が渦巻く。彼がここを去ろうとしている。
ギコは慌ててフェンスをよじ登り、植え込みを飛び越えた。
「シィを探してくれ。緑色の目をしたヤツだ。あいつが居ないとマズい」
「探すってったって……そんなに簡単に見つかるのかよ?」
返事は返って来なかった。
モララーは鼻の頭の痛みと理解に苦しむ話を残して去ってしまったのだ。
「わけ解んねぇよ! 何だってんだよ、チクショーッ!!」
----------------------------------------------------------------------
4
目印は“緑色の目”名前は「シィ」
その他の特徴は……他の人には見えない。多分。
(それでどうやって探せと?)
窓から見える通りを眺めながら考え込む。通りはまっすぐこの建物に向かっており、沢山の人が行き来している。タクシーが数台ロータリーに停まり、送り迎えのための車が邪魔そうに避けてゆく。
ごくたまに救急車がサイレンを鳴らしながら入って来て救急受付に車尾を付けている。
ギコは窓から視線を戻すと、眠っている妹の左手をそっと握らせて毛布の下に隠した。
妹が原因不明の昏睡で入院したのは先週末の朝だった。
前日の夕方、ソファーの上で眠り始めた時には「疲れているのだろう」と笑って父親がベッドに運んでいた。しかし翌朝、激しく揺り動かしても目覚めない様子に異常を感じた両親が大慌てで病院へ運んだのだ。
甘えん坊で5つ年が離れている。ギコが帰るといつも部屋から飛び出してきて家中付いて歩く、兄にベッタリな妹だった。
様々な検査を経て医者が出した結論は「原因不明」
悪いところは全く見つからない。
昏睡というには語弊があるかもしれない。たまに彼女は寝返りを打つ。本当に普通に眠っているようにしか思えない、と医者は首を振っていた。
時々、閉じた瞼の上から眼球が動いているのが判る。まるでレム睡眠の只中、夢を見ているような状態なのだ。
食事を摂る事ができず、衰弱してゆく心配があるため、幼い腕に点滴の太い針が固定されている。
そんな姿を見ていると嫌でもあの黒い卵を思い出した。
もし、このまま目覚める日が来なかったら……あの卵を渡しに“クロ”はここへ来るのだろうか?
左手を握らせて隠した所で無駄だという事は百も承知だ。けれど開いている左手を見ると居てもたってもいられなくなる。
あんな光景見なければ良かった。そうすれば廊下をよぎる黒い人影に必要以上に神経質にならなくて済んだ筈だ。
(何で俺なんだよ?)
街には沢山の人が溢れ返っているというのに、どうして彼らに出会ってしまったのが自分だったのだろう。昨夜からずっと考えているのだが勿論答はみつからない。
病室の扉が静かに開いた。
「ごめんね、遅くなって。夕飯、テーブルの上に置いてきたからチンして食べてね」
母親はそう言うと真っ先にベッドを覗き込み、彼女に良く似たフサフサの毛並みを撫でた。今日は週末なのでここに泊り込むつもりで来たのだろう。いつもより荷物が多い。
「ああ……」
下手な慰めはもう出てこない。先週は皆口々に「明日にでも起きるかもしれない」と言い合っては縋り合っていた。
「今日は帰るよ」
毛布の下に手をそっと入れ、妹の手を握る。小さな手は先程してあげたまま握られていた。
病室を出るとすぐ前にエレベーターがある。
一階上に止まっているのが点灯している数字で判ったのだが、そこを素通りして階段への扉を開いた。
何だか自分でも辛気臭い表情をしているのが判る。だから誰にも会わずに病院を出てしまいたかった。
誰もいない階段に自分の足音だけが響いている。病院内で人の気配が無い場所というのは気味が悪い。真っ白な壁に蛍光灯の青白さが目立ち、どこからか聞こえる空調の低い音が余計にそう感じさせるのかもしれない。
手すりを片手で辿りながら巻くように折り重なっている階段をゆっくりと降りてゆく。
何を考えても何処を見ても、非力な自分が悔しい。気持ちが焦るばかりで何をしたら良いのか分からない。
階段を降りきり、1階の受付前を通ると沢山の長椅子が並んでいる。診療受付はとっくに終わっているのでそこには会計待ちをしている人達がまばらに座っていた。
大きな病院なので随分待たされたのだろう。中には待ちくたびれたのか、長椅子に横になって眠っている子供がいる。
出入り口の自動ドアはひっきりなしに開閉し、多くの人が出入りしている。こんな場所で眠り込んでは風邪をひきそうだ。
妹よりは大きい子のように見えるが、自分に比べるとかなり小さい。
親はどこにいるのだろう? 子供の周囲を見たが、それらしい者は見当たらない。このご時勢に随分と無用心だ。そう思いながらカウンターを見ると自分の母親よりは若そうな女性が支払いをしている。あれが母親に違いない。
「ギコくん?」
正面のガラスの扉が左右に開き、外の風が入り込んで来たのと同時に懐かしい声が自分を呼んだ。
振り返ると見覚えのある中年の女性が小さな花かごを持ってこちらを見ている。
「先生?」
5年生の時に担任をしてくれた先生だった。そこそこのキャリアを持つ、穏やかな彼女は保護者の受けも良く、今年は妹の担任になったと聞いている。週末の放課後なので見舞いに来てくれたのだろう。
状態の詳しい説明は母親にしてもらった方が良い。それにあまり顔を見られたくない。そう思い、病室の場所と礼を言うと、彼女はギコの気持ちを敏感に感じ取ったのか、肩口に手を添えて「大丈夫よ」と囁いた。
エレベーターの扉の向こうに彼女が見えなくなるのと同時にギコは足元に置かれているカゴに気付いた。出口に向かおうとしてうっかりつま先を引っ掛けてしまったのだ。
カゴの中には薄灰色になった石がぎっしりと詰まっている。
「?」
位置的に見て忘れ物か、傍で寝ている子供のもののような気がする。
受付カウンターを見ると、先程まで支払いをしていた筈の母親らしき女性の姿が無い。
先生と話しているちょっとした間にどこかへ行ってしまったようだ。
「……返して」
キョロキョロしていると下から声が聞こえ、石詰めのカゴが手から消えた。
「私のよ」
サーモンピンクのワンピースに白いエプロンを着けた子供はギコの手から取り上げたカゴを片手に持ちながら大あくびをし、眠そうに目をこすった。
----------------------------------------------------------------------
5
子供はカゴを抱えたまま鼻をひくひくとさせ、あちこちを向いて匂いを嗅いでいる。
「……なぁ」
「…………」
ギコは声をかけるべきかどうか迷った末に口を開いた。
あからさまな疑いの目つきが見上げる。まるで“自分に声をかける者など信用できない”と言わんばかりだ。
しかし、聞いておかなければならない。昨日のおかしな奴に頼まれた「探し人」に該当する条件を持つ者になど滅多に出逢いはしない。
エメラルドのような深い緑の目と体を覆う淡いピンク。補色どうしが共存する少女の顔色は不安定な雰囲気を湛えている。
同じ名の知っている少女にどことなく似ているような気がする。この子が微笑みさえすれば、の話だが。
不安定に見えるのは色合いだけの話ではない。この子には同じ姿を持つ種族の表情に見る特徴─微笑─が無い。口元が無表情なのだ。
「お前、シィ?」
「…………」
目の前の少女に警戒心が満ちてゆくのが判る。
彼女は暫くの間何か考えているのか、質問に答えなかった。ただ無表情に緑色の瞳だけがギコを隅々まで見上げている。
「…………」
そろり、と一歩後ずさる。どうするのだろうかと見ていると、目の前で身を翻した少女は一目散に走り出した。行く先には厚いガラスの自動ドアがある。
もし、彼女が例の「探し人」ならばあのドアをすり抜けて外へ逃げる事ができる筈だ。
ごんっ
低く、鈍い音がロビーに響く。
少女は予想に反し、透明のガラスに突進して弾き返された。顔面からぶつかったらしく、両手で顔をくしゅくしゅと擦っている。
「風……?」
居合わせた老婦人が大きな音をたてた自動ドアを見ながら呟いている。足元に座り込んでいる少女が見えないようだ。
老婦人はそれ以上気にする様子も無く、ゆっくりと歩き出した。
ガラス扉を通り抜けられないということは、「探し人」ではないのかもしれない。しかし、不可解な少女は床に散らばったカゴの石を拾い集めながら老婆の足を通り抜けた。昨日のモララーのように。
呆然と見守るギコの目の前で石をカゴに戻し終えた少女は再び立ち上がった。
「……おい」
少女は耳をピンと立て、小さく搾り出したギコの声を捕らえた。
「お前シィなのか?」
尋ねる声と走り出すのは同時だった。今度は病院の中を目指している。先程ギコが降りてきた階段へのドアが大きく開き、沢山のカルテを抱えた看護婦と事務員が出てくる。
開いている扉ならばどこでも良いのだろう。道に迷った動物が警戒心と恐怖故にやみくもに走り回る姿に似ている。
「待てよ」
少女は閉じかけていた金属ドアの隙間からスルリと階段スペースに入った。
階段への扉は防火扉になっていてわりと重い。その扉を開くと、先程の不気味な雰囲気の階段が上にも下にものびている。
「逃げるな!」
少女は階段を降りてゆく。病院の地下と言ったら何があるかは決まっている。この階段よりも一段と寒気のする場所だ。
降りてゆくとその先の扉を開けられない少女は行き止まりになってしまった階段にオロオロと周囲を見回し、追跡者の顔を見上げた。
「俺、お前を探してくれって頼まれてんだよ」
なるべく怖がらせないように、わざと数段残して立ち止まる。
「お前、シィだろ? 昨日、モララーに“探してくれ”って頼まれたんだ」
「……モラに?」
少女は初めて声を発した。
なるほど、昨日のあいつの名は“モラ”なのか。そう思いながら頷く。
「“緑の目のシィを探してくれ”って。それだけ言って飛んでっちまった。俺としちゃあ、探す義理は無いんだが……まあ、何だ。一応、他の奴には見えないし、頼まれちまった上に会っちまったから一応、な」
「モラはどこ?」
「知らねぇよ。俺が聞きたい」
大体、探したというか偶然出会ったわけだが、この先どうしたら良いのかはさっぱりわからない。見ず知らずのヤツに言われたからといって他人に見えない少女を拉致るつもりも無い。
行き先を知っているのならば送って行かぬでもないが、この中途半端な能力を持つ少女も昨日の“モラ”も、自分が行けるような世界の住人ではないような気がする。
ギコは階段に腰を下ろすとドアの前でつっ立っている少女を見ながらため息をついた。また中途半端だ。この先何をどうしようか。
「き…………」
少女の小さな唇が微かに開く。
「きゃぁぁぁぁぁぁぁぁぁっ!」
防火扉とコンクリートで密閉された空洞に甲高い声が響く。そのキン、と刺さるような声に一瞬両手で耳を塞ぐ。
ギコがそうして悲鳴にひるんでいる隙をつき、少女は傍を通り抜けると降りてきた階段を駆け上がり始めた。
「あっ、こらっ……!」
観念したかと思っていたが、逃亡を諦めたわけではなかったようだ。
----------------------------------------------------------------------
6
少女は真っ白な階段をひたすら上った。大きめで石の詰まったカゴがとても邪魔そうだが、そんな事にはお構いなしに力一杯走ってゆく。
(全く……)
いくら力一杯走った所で所詮子供だ。体格差のある、しかも結構足が速い自分から逃げ切れる筈が無い。しかも壁や扉を通り抜けられない上に扉を開ける事もできないのだ。屋上まで上った所で先程と同じ状況になるだけなのは目に見えている。
「いい加減に諦めろ!」
一段飛ばしで階段を駆け上がるギコとの距離が段々小さくなってゆく。それに伴って呪文のように唱える少女の声がはっきりと聞こえ始める。
「嫌…来ないでっ」
別に取って食おうというわけではないのだから話ぐらい聞いても良さそうなものだ。しかし、ひたすら接触を拒み逃げ続ける。“探してくれ”と言われたので相手はすんなり付いて来るものだと思っていたのだが、何かがおかしい。
(アイツに引き渡されるのが嫌なのか?)
実は“モラ”から逃げようとしているのに自分が邪魔をしている……と考えてみる。それならば逃げ回るのには納得がいく。捕まるわけにはいかないだろう。
「おい、お前……」
3階と4階の間でギコは少女に追い付くと腕を掴んだ。
「離して!」
少女は掴まれた腕を見ると尻尾の先まで毛を逆立てて怯えた。
「別に俺は……」
「きゃぁぁぁぁっ! きゃぁぁぁぁっ! ろりこん! へんたい!……えーっと、えーっと、ろりこん! ろりこん!」
自動ドア激突時に証明済みなので、他人に聞かれないのは解っている。解ってはいるのだが……数歳下の少女にやみくもに“ロリコン”“変態”呼ばわりされるのを余裕で流せるほどギコは大人ではない。
いや、大人ならばその言葉も状況的に正しいのかもしれない、と思う。逆に年が近いだけに“ロリコン”などと言われるのは我慢がならない。
「うるせぇっ!」
どうせ誰にも聞かれはしないだろう。鉄製の扉は音も密封してくれる筈だ。ギコは遠慮無く怒鳴った。
「別に取って食ったりしねぇから! 嫌なら誰にも引渡したりしねぇし!」
だから暴れるのを止めて話しに応じろ、とジタバタ暴れる少女にゲンコツを落とす。
「ただし、“ロリコン”と“変態”は訂正しろ」
そのまま少女をひょい、と抱える。見た目よりも痩せているのか、軽い体は簡単に小脇に納まった。
「………本当?」
「何が?」
「食べない?」
「あのなぁ……食うわきゃねーだろが」
いくら何でも子供を取って食う奴がこの世にいるのか? と呆れる。
「だってモラが……」
「あいつが?」
少女は小脇に抱えられたまま、ギコを見上げた。
「こっちでは“ろりこん”っていう人が居て、見つかると“食べられちゃう”って」
「…………」
(アイツ、子供に何を教えてんだ!)
返答に困ったのは言うまでも無い。意味は違えど「そういう事」もたまにはあるだろう。自分の妹だって学校帰りに不審な男に声をかけられたことがあるのだ。最初にこの子を見つけた時に“無用心”と思ったのはそんな背景があったからだ。
しかし、どうせ皆には見えないのだから、そんな心配は要らないのではないだろうか?
「おーい、その子抱えたまま屋上まで上って来い!」
ドアが開く小さな音と共に頭の上から聞き覚えのある声が聞こえてきた。誰かがここに自分達が居る事を知っているようだ。
「?」
もの凄く聞き覚えがある声なのに誰のものなのか思い出せない。少なくとも昨日出会ったモラのものではない。階段を上る足が止まる。ここに誰もいないのに「多くの者に見えない筈の少女を抱えている」事を知っているなんて怪しい。
「お前、誰かから逃げてんのか?」
少女は無言でギコを指差した。
「だぁからっ! 食わねぇって!」
「じゃあ逃げていないわ」
「あそ」
ならば頭上から降りてきた不審な声の主に出会ってしまっても構わないかもしれない。どのみちこの先どうしたら良いのか判らなかったのだから丁度良い。
ギコは再び階段を上り始めた。
少女は寝起きにそうしていたように、鼻をひくひくとさせると大きく息を吸った。柔らかいお腹がそれに合わせて動くのが抱えた腕ごしに伝わる。
「気持ちいい……ここは臭くて頭が痛かったの」
ギコには微妙な匂いの変化は判らなかった。確かにここは病院なので薬の匂いはしている。
しかし、そういうものだと思っているし、頭が痛くなるほど強い匂いとは思わない。随分と鼻が利く子なのだろうか。
「ジエンの匂い!」
少女はさらにひくひくと匂いを嗅ぎ続け、嬉しそうな声をあげた。
「あと……あなたの匂いもする」
「悪かったな、汗臭くて」
汗ばむ季節ではないのだが、走ったりしたので汗臭くなったのだろうか。
「違うわ。上からあなたの匂いがするの」
「俺の匂い?」
「そう。声だってしたじゃない?」
「俺の声?」
言われてみればさっきの声は自分の声に似ている。しかし常識から考えるとそれはありえない。
7階を越えるとさすがに屋上から吹き込む風を感じた。もう1度踊り場を折り返すと屋上へのドアがある筈だ。
「ありえないだろ。俺はここに居る」
上階から声をかける事などできるわけが無い。
「でもするわ。あなたの匂い」
----------------------------------------------------------------------
7
踊り場を曲がると、白い壁に薄い象牙色の扉があった。それは予想していたとおり、大きく開け放され、そこだけ青い空が四角く見えている。
屋上で待っているのは何なのか。
少女は鼻で感じているらしい。あのドアの先には新鮮な空気とジエンとギコ本人が待っているのだという。
「でも…遠ざかってる」
彼女はそう言うと何回もそうしたように鼻をひくひくさせ、自分を抱えているギコの脇腹辺りの匂いを嗅いだ。
「確かにあなたの匂いがするわ」
彼女は確信したらしい。抱えられたまま待ちきれなさそうに伸び上がっている。
しかし無表情は変わらない。彼女は愛想の無い口元をキュッと結び、キラキラとした緑の瞳で青い空を見上げた。
7階建ての大きな病院の屋上は風が強い。
数人の入院患者らしい者が寝巻き姿のまま、柵越しに街の風景を眺めながら飲み物を口にしたり煙草をふかしたりしている。見舞い客と談笑する者もいれば一人でぼーっとしている者もいる。
杖をつくもの、車椅子に座って点滴のフックを持っている者、色々だ。
その中に一台の荷車が置いてある。木でできた古臭いもので、病院の屋上なんかで何に使うのか見当もつかなかったが、点滴柱を引っ張った女性がすり抜けて通り過ぎるのを見て“ああ、またか”と悟る。
明らかに病院のものではないと判るものは他にもあった。ドア口から柵の淵までのあちこちにジエンが飛び跳ねたり集まったりしている。彼等もきっと“そう”に違いない。病院でジエンを飼育するなんて聞いた事が無いからだ。
「お前の鼻って正確だな」
ギコはそう言いながら少女を下ろした。
「シィ!」
一匹のジエンがこちらを見るなり声をあげた。
それを聞きつけた他のジエン達も一斉にこちらを向いた。
「来タ!」
「帰ル!」
少女の姿を見つけたジエン達は全部で6匹。皆真っ白で柔らかな、餅のような弾力を帯びた体で跳ね回っている。
「乗せてね」
少女は自分の周りを跳ね回るジエンのうちの1匹に抱きつくと頬を押し当てた。少し声が嬉しそうだが、やはり無表情なままだ。
「シロは?」
擦り寄ってくるジエンに次々と頬を押し当てながらシィは訊いた。
「配達!」
「ジエン、卵取リニ帰ル!」
「そう」
シィは手に下げていたカゴを荷車に乗せると、そこによじ登った。
周囲に居る者達には当然、ジエンや荷車やシィは見えていない。だから驚く者など誰もいない。ギコは同調してくれる者が居ない寂しさに晒されながらただ呆然とジエンと荷車とシィを見ていた。
(でけぇ!)
遠目に見ている時には気付かなかったが、6匹のジエン達は大きい。普通のジエンの3倍ほどの大きさはある。シィに引っ付いている姿で初めてその大きさの比がはっきり判ったのだ。
彼らはシィが荷車に乗ったのを確認すると、そこから伸びている引き棒に設置された革製のベルトを体に着けた。
「乗レ!」
先頭の列のジエンがギコに向かって言った。
「へ?」
俺? と聞き返す代わりに自分を指差す。
ジエン達は一斉に頷いた。
「モラガソウシロッテ」
「あいつが?」
「どうして?」
シィも不思議そうに訊ねた。
「知ラナイ!」
「ソウシロッテ」
シィはジエン達とギコを交互に見比べ、心配そうに小首を傾げた。
「落っこちない?」
「知ラナイ!」
何だか会話の内容に不安を感じずにはいられない。下手をすると生命が危機に晒されるような気がしてならない。
が、不思議と“嫌だ”という気はしなかった。興味の方が勝ったせいだろうか。
「乗ってみて」
シィはこの荷車に乗る事ができるのならば大丈夫だと思っているようだ。確かに、人の体は通り抜けてしまうのだからこれに乗れないのなら話にならない。
ギコはささくれ立った木肌の荷車にそっと片足をかけた。
ミシッという音がする。が、大丈夫なようだ。そのまま足で踏みしめると、荷車の床はドンドン、という音でそれに答えた。
「行けそうだな……」
よっ、ともう片足を乗せると、思ったよりも高さのある荷車の上に立てた。
「大丈夫そうだな……ガッ!」
床に腰を下ろして胡坐をかこうと屈んだ拍子に荷車は暴走を始めた。
ジエンは高速で移動する。それは知っていた。が、せめて座るのぐらいは待っていてくれるものだと思っていた。が、彼等は遠慮無く急に走り始めたのだ。
荷台の上でギコは足をすくわれたかのようにひっくり返り、へりに頭をぶつけた。
「ってーな……ちょ、待て! オイ!」
ギコの声は走るジエンには全く追い付かない。
猛ダッシュで走り始めたジエンの引く荷車は、制止の声を聞く前に事故防止用に設置してある二重の柵を飛び越えると屋上から空に向けてジャンプをした。
慌てて荷車のへりにしがみ付く。
「止まるまで掴まっててね」
今ごろ遅い、と怒鳴りたくなるようなシィの声が風の音に混じって聞こえる。
体中に電気のようにビリビリとした感じが走る。7階建ての病院の屋上からダイブしたら、間違いなく死ぬ。
一瞬、頭の中であの“クロ”が黒い卵を差し出しながら笑った。
荷車は風を切って進んだ。
尋常ではないスピードに、落ちているのかと錯覚するぐらいだったのだが、恐々下を覗くと街がどんどん遠ざかって行き、小さくなったので上昇している事が解った。
「オイ!」
風の音がばばばばっ、とうるさいので大声をあげる。
「どこに行くんだ?」
既に下は雲に覆われていてどこの上空を飛んでいるかも判らない。いや、見えた所でかなり上昇しているのだから判らないかもしれない。
「帰るのよ!」
「帰る?」
「お家に帰るの!」
「お家ぃ~?!」
周囲が薄暗くなってくる。やがて空の一点に小さな黒い穴が現れた。
荷車が加速する。今まで切っていた筈の風が背後から強く吹き付ける。まるであの穴に向かって吸い込まれてゆくような感じだ。
しかし、穴は一匹のジエンがやっと通れる程度の大きさだ。
一体どうなってしまうのだろうと思っていると、先頭のジエンが光り始めた。
彼等は前から順に次々と光り始め、やがて荷車自体も光り始めた。荷車前方にしがみついていたシィの体もぼんやりと光り始める。
と、いう事は……
ギコはチラリとしっぽの先に目をやった。
しっぽの先は案の定、光りを帯びている。そしてすぐに光はしっぽの先からギコの体全体に広がり始めた。
自分の体に気を取られているうちに周囲は一変していた。
気付くと、真っ暗な中をおそらく、自分達であろう光の塊が走っているのが見える。何かに反射するような動きを繰り返しながらうねるように高速の光は進んだ。
(穴に入ったのか?)
自分の実体を感じる事ができない。が、確かに自分はここに居る。
前方に光が見えた。
----------------------------------------------------------------------
8
感覚などは無い。が、前方に見えた光に吸収されたような気がした。
眩しさに目を閉じる。光は瞼の存在などには構わずギコの眼球へ入り込んできた。
無意識に腕を目の前にかざして覆う。と、幾分の薄暗さが訪れ、ギコは再び自分の実体を感じることができた事に気付き目を開いた。
薄い水色の空が広がっている。
秋のように高く、青く感じる空ではなく、どことなく霞がかった春の空のような感じの色だ。
「…………」
ギコは光の塊になっていた筈の自分の身体をまじまじと見つめた。手も、足も、しっぽの先も元通りの青い色をしている。
先程までもの凄いスピードで走っていた荷車は停止しているようだ。風を感じない。
(どこだ? ここ…)
周囲を見渡す。が、青い空以外に見えるものは無い。
「降リルヨ!」
ジエンの声がした。
水平を保っていた荷車は前触れも無く傾き、最初ゆっくりと動き出したかと思うと程無く加速した。強い風圧が呼吸を邪魔する。
急角度に傾いた荷車の前方に景色が見えた。
深緑色の森が広がっている。そして明るい黄緑色の草原に美しい色を筆先で置いていったように散らばる花畑、だろうか。遠くに真っ白な雪が積もった小高い山がそびえ立っている。
その山からは美しく澄んだ水の流れが伸び、大きく蛇行しながら森へ入り込んでいる。
家が何軒か建っているのが見える。森の入り口や草原のはずれ、山の中腹。
とんでもない田舎にやってきたようだ。
ビルも、学校らしき建物も鉄道も見当たらない。そして今飛んでいる所は先程ほど高度はない。
(しかし……)
真正面を向いていると風圧で呼吸がしにくい。もの凄いスピードのせいなのか、上昇気流に向かって下降しているのか、とにかくやたらに風を受ける。
息苦しさに後ろを向こうと試みるが、あまりの圧力に身体が荷車に押し付けられたような感じになり、身動きが取れない。
寄りかかった荷車のへりがミシミシと音をたてて軋んでいる。
(こんなボロ車で耐えられるのか?)
そう思った矢先、突如ガクン、とへりが外れた。
「あ?」
押し付けられていた壁を失ったギコは仰け反るような姿勢で空中に放り出された。
向こうとして向けなかった後ろの風景が逆さまに目に映る。
深緑の森が延々と続いた先に空が灰色になっている部分がある。まるで雷雲がひしめくようなその灰色の部分は段々に濃さを増し、地上の真っ黒な部分と接触している。
同時に呼吸がとても楽になった。前方からの風圧が無いからだ。が、そんな事をのほほんと喜んでいる暇は無い。
風圧から開放された身体は重力に縛られ、落下を始めている。
「危ない!」
シィの声が聞こえた。
先程の荷車が“ジェットコースター”だとしたら、今の状態は“スカイダイビング”だ。
自分の身体の周囲に何も無いというのは何と心もとないことか。あるのは下方からの空気抵抗のみだ。
しかも、このスカイダイビングは最悪な事に“パラシュートが無いスカイダイビング”だ。
(嘘だろ?)
このまま続行すれば迫り来る森の木々の先端に串刺しになってしまうか、運良く地面まで辿り着いた所でグチャリと潰れるか、二つに一つの結末が待っている。
とりあえず、手足をバタバタとさせてみる。これがマンガならば泳ぐような仕草で数メートルでも上昇できるのだろうが、生憎そんな現象は起きなかった。
「助けてぇっ!」
離れた所でシィの悲鳴が聞こえる。
どうする事もできないのは解っているが、策は無いかと頭を回転させる。が、当たり前だが妙案など一つも浮かばない。
その内、意識が薄れてきた。
飛び降り自殺を図る者が「途中で意識を失うらしい」と聞いた事がある。
(本当だったのか……まぁその方が怖くも痛くもないからな)
危険が迫りすぎると思考は雑多な作業ばかりを繰り返し、恐怖からの開放を図るらしい。下らないことが次々に頭の中を駆け巡る。が、思い出は浮かんで来ない。
そして周囲は完全に真っ暗になって五感は全て閉じた。
お腹が空いた。
美味しそうな料理の匂いに刺激されて思い出した。
そういえば昼を食べた後、何も口にはしていない。4時ごろ、空腹を感じてパンを買い食いしようと思っていたのにサイフを忘れ、仕方なく真っ直ぐ病院に寄ったのだ。
未練が残るのならばそこだ。
学校からの帰り道、商店街の中に一軒の肉屋がある。
そこのコロッケが安くて美味い。よくフサ達とそこに寄っては揚げたてのコロッケを挟んだコロッケパンを買い食いしていた。
(死ぬ前にもう一度食っておけばよかったな)
死んでまで空腹を味わうとは何とも切ない話だ。第一、こんな美味そうな料理の匂いだけ嗅いでも食べる口がもう無いのだ。こんなに悔しい事は無い。
「………腹減ったぁ」
幽霊がじっとりとした声で「恨めしや」と言うのはきっと空腹も手伝っているからに違いない。そう思いながらギコは恨みがましい声で呟いた。
部屋の中にテーブルがある。
そのテーブルに誰かが座っている。ぼんやりとしか見えないのは、辺りが薄暗く、灯したランプのみが照明だからだろうか。
「お、起きた」
右手にスプーンを持ったまま、左手に持ったパンを齧るモラがのん気に呟いた。
「本当?」
シィの声がする。が、姿が見えない。
やがて美味しそうな匂いは先程よりも強くなり、湯気のあがる皿を持ったシィがテーブルの向こうから現れた。あの向こうには台所があるようだ。
シィは大きな皿をモラの前に置くと、急いでギコの枕元にやってきて覗き込んだ。
「大丈夫?」
「平気だろ?」
モラは湯気のあがる皿にスプーンを突っ込んでは口に運びながらギコの代わりに答えた。時々、左手に持ったパンを皿の中に浸して齧っている。
ギコは横になったままモゾモゾと身体を動かしてみた。両手を握り、足を伸ばし、伸びをしてみる。
柔らかな毛布が肌に触れ、横たわっている場所はベッドの上だという事が解った。
ゆっくりと起き上がってみる。
見下ろすと身体は無傷なようだ。腹のどこにも串刺しになった痕跡は無いし、身体の隅々までグチャグチャに潰れている場所も無い。
「何で?」
どう考えても無事でいるのが納得できない。普通は死んでいる筈だ。
「モラが助けてくれたのよ」
「…………」
当の本人はギコの視線が注がれているのに気にならないようだ。先程と変わらない様子で食事を続けている。
やがて彼は満腹になったのか、食事の手を止めるとギコを振り返り、おもむろに言った。
「ありがとうは?」
「……ありがとうございました」
彼に関ったが為に遭ってしまったような災難だったので不条理を感じるものの、命の恩人なのだから仕方が無い。
ギコは猫背のような姿勢でペコリと頭を下げた。
モラは「フン」と鼻を鳴らすとスプーンを置き、カップに入った飲み物を一気に飲み干した。
そして使い終えた食器をガチャガチャと積みあげ、シィが入ってきた所から出ていった。
----------------------------------------------------------------------
続き
1~10
11~20
21~30
31~40
41~49
最新のものは新板(AA小説掲示板)の連載に投稿中。