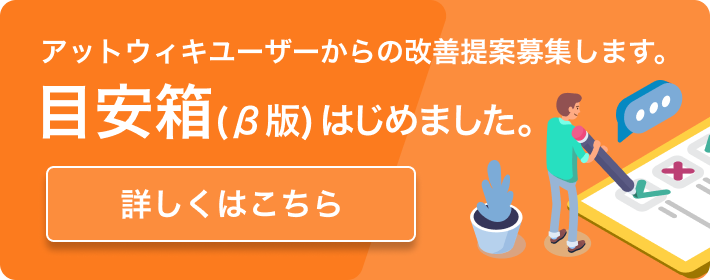~プロローグ~
カランカラン…
荒野にひっそりと佇む寂れた街の小さなバーに、夕暮れ時の入り日と共に一人の男のAAが入って来た。
男は目深に帽子を被ってはいるが、何か独特の雰囲気を放っていた。鋭く、でもどこか穏やかな。
周りの客の目は自然と男に集まるが、男は別段気にする様子もなくゆっくりと歩みを進め、カウンターに腰掛ける。
「…マスター、ウォッカを一つ」
「はいモナ」
気さくなマスターのモナーは明るく答えたが、酒を出そうとして彼の帽子につけられた“*”を象ったようなバッジが目に止まり、首を傾げる。
「お客さん、そのバッジ…」
その声に気付いた男は、ん、と少し帽子をあげた。
男は、白い肌に、右は黒、左は金色の瞳といった風貌だった。30代ほどだろうか。
何でもないようにああ、と答える。
「安心しな。こいつは確かに隣国のゼセルドの国章だが、オレはクレスト・フォル・クレスの者だ」
「…とすると、それは戦利品モナ?なるほど、お客さん元兵士モナか。道理で…」
―ダンッ!!!―
雰囲気が違う、と言おうとしたモナーの言葉を、男がグラスを乱暴に置く音が遮った。
「―こいつは戦利品なんかじゃない。もっと悲しくて、ちっぽけなもんだ…」
「…ほう?」
モナーは心外そうな顔をすると、男の正面にイスを持って来て座った。
「丁度退屈してたとこモナ。良ければ話を詳しく聞かせてくれないモナ?」
男は、眉を顰める。「…何故、興味を持つ?」
モナーは少し寂しそうに微笑んだ。
「モナは10年前の戦争で家族も知人も皆亡くしたモナ。あの戦争の意味を、モナは知りたい。だからこうして、兵士さんに話を聞くモナ…」
「……」
しばしの沈黙のあと、男は一気に酒を飲み干し、口を開いた。
「“アイツ”がいなければ俺は今ココにはいないだろうし、意味を持って生きていることなどなかったんだろう……――」
*******************************
今でも瞳を閉じれば蘇る、アイツの瞳と、背中に燃える紅い炎の華…
*******************************
第一話:邂逅/rencounter
―それは、ある冬のこと。
木枯らしが吹き荒び、木々は立ち枯れた季節。
「…ハァ、ハァ…」
誰の声かと思ったら、洞窟に反響した自分の声だった。
彼は、冷たく暗い洞窟の壁に体を預け、座り込んでいる。
ひどく眠い。けれど、このまま眠ったらこの洞窟の闇に呑まれて自分が消えてしまいそうだった。
(落ち着け…!落ち着くんだ…!)
心の中で、何度も自分に語りかける。自分を見失わぬように。
この洞窟は全く日が当たらない上、水脈があるのか底辺には水が溜まっており、容赦なく彼の体温を奪う。
(グリモナ…)
自分ではない、誰かの声が聞こえたような気がした。
(グリモナ…)
声に応え目を瞑ると、自分の名を呼ぶ恋人の姿が見えた。
桜色の美しい肌、緋色の瞳。暖かい日差しのような微笑み。
けれども彼―グリモナが手を伸ばすと、彼女の姿は闇へと掻き消えた。
目を開く。そこには目を閉じていたときとさして変わらない闇が広がっていた。
(そうだ、俺は…グリモナ・フェルブルク…)
小さく呟き、心を保つ。
(俺は、クレスト・フォル・クレスの兵士で…今は戦場にいる…)
耳を澄ますと、遠くに爆撃の音が聞こえる。
(…何でオレは逃げている?)
グリモナの部隊は敵の奇襲に遭い、彼は成す術も無くこの洞窟に逃げて来たのだ。
(…アイツは…恋人は、もう死んだじゃないか…)
グリモナは、自ら進んで兵士となった志願兵だ。
彼は小さな村で育ち、やがて幼馴染みの娘と恋に落ちた。しかし彼が19になった時、戦争が始まった。
科学大国、ゼセルド。
宗教大国、クレスト・フォル・クレス。
隣り合う2つの国の境には、巨大なエネルギー鉱石の結晶体があった。それはAA達が誕生する遥か前に、宇宙より飛来したといわれている。
全高10mほどもあるその石を、クレスト・フォル・クレスは神の意思の宿る石として信仰の対象として来た。
しかしここ数年でゼセルドの科学技術は大幅に発達し、ついに鉱石のもつエネルギーに着目し、クレスト・フォル・クレスと交渉に出た。
あの石を譲ってくれれば、必ずその恩恵をクレスト・フォル・クレスにも平等に分け与える、と。
しかし彼らの答えはNOだった。
あの石はAAが手を出していいモノではない。強引に奪うのであれば、こちらも手段は選ばない、と。
しかしゼセルドはあくまでも自国側の鉱石の所有権を主張した。
この鉱石は自然の一部であり、我々が大地を分かつように、この石も分ければよいではないか。
そしてゼセルドが独断で自国側の鉱石を掘削し始めたのが戦争の火蓋となった。
もちろんクレスト・フォル・クレスにしてみれば、信仰の対象である石が半分でいい訳が無い。
ある夜、クレスト・フォル・クレスの政府直属の兵士がゼセルドの掘削隊に奇襲をかけた。そしてそれは本格的な戦場へと発展していくこととなる。
クレスト・フォル・クレスのグリモナも、愛する者を守るため兵士に志願した。彼はかなりの田舎に生まれ育ったため、正直神だとか石だとか、どちらが正しいとか正しくないとか、そんなことはどうでも良かった。
ただ、彼女の笑顔を守ることができれば。―もう半年もしたら生まれる、新たな命を守ることができれば。それだけだった。
グリモナが戦場に赴いてから8ヶ月。彼はある作戦で左目を失う。
クレスト・フォル・クレスは、この時点では兵役は強制ではなく、基本的に志願兵だけだった。この宗教大国の国民は非常に愛国心が強く、強制などしなくともある程度は兵士が集まったからだ。ただ、少々の戦力不足は否めなかった。
それ故、負傷した兵士は本国にて治療されるケースが多い。彼もその内の一人だった。彼はすぐさま本国に帰され、角膜の移植手術を受けた。お陰で視力は奇跡的に回復した。
彼は再び戦地に赴く数日前の晩、病院を密かに抜け出した。
――…一目、見るだけで良かったのだ。
愛する者と、愛の結晶であるわが子を。
会って話をしなくても良い。
触れられなくても良い。
ただ、見たかった。
決して贅沢な願いでは無い。しかし彼らが崇めるところの神は、それさえも許さなかったようだ。
森を抜けた彼の眼前に現れたのは、懐かしい村ではなく、
ただの、荒野、だった。
茶色い乾いた土と、石ころと、平坦な大地。ところどころに立ち並ぶ、少し大きめの石。
彼が幼い頃虫捕りをした緑の森も、友達と泳いだ美しい川も、恋人と語らった大きな木も。建物も。村人も、家族も、恋人も。
―何も、無かった。
訳が分からずただただ立ち尽くす彼の視界に、一人の男が映る。
男は、親しかった村人たちを弔った墓堀人だった。グリモナに気づき、やあ、と軽く挨拶をして近寄ってくる。
―あんた、この村に親しい人でもいたのかい?この村なんてとうの2ヶ月以上も前に消えたよ。跡形もなくね。
聞いた話では、1時間も掛からなかったそうだよ。何がって、全てが消えるのが。
ここに何も無いのは私が片付けたからじゃない。…本当に何も残らなかったんだ…―
男はそんなことを話しながら小さな墓石らしき物に手を合わせた後、彼を尻目に去って行った。
―嘘だ…―
彼はしばし呆然とした。
―俺は一体何の為に戦って来たんだ…―
遺言も無い。遺品さえも無い。
彼が拠り所とする物は、何もなかった。
結局彼は心配した同僚によって見つけられ、病院に連れ戻された。
抜け殻のようだった彼は、一週間後には何事も無かったかのように再び戦地へ繰り出された。
そして今。彼は戦う意味も、生きる意味さえも分からず、ただ毎日戦っている。
遠くに聞こえる銃弾戦の音。
闇にこだまする、自分の、息。
(…そうだ、何故オレは逃げている?)
彼は閉じていた目を開いた。
(―行けばいいじゃないか…)
疲れ切った老人のように、ゆっくりと立ち上がる。
(―彼女のところへ…)
死ぬことは怖くないはずだ。
何故今までこうしなかったのだろう?
一歩一歩、確かめるように歩みだす。
そして外の光が見えた、その時。
(―……?)
グリモナは、違和感を覚えた。
――シン…――
先ほどまでの戦争の音が、全く持って消えていた。変わりに彼の耳に届いたのは、
(―歌?)
確かに女性のものと思わしきソプラノの歌声が、微かに聞こえた。
彼は外の眩しさに目を細めながらも、また一歩踏み出す。すると彼の前に、唐突に一つの小さな影が立ち塞がる。
それは、
1、2歳程度の子供、だった。
逆光でよく見えないが、彼と同じ白い肌に、真紅の瞳。こちらを見て微笑んでいる。それはまるで――
(―俺と、アイツの…?)
生きていたのか?
彼は淡い希望を持ち、その子供を目を凝らして見つめる。
しかし彼が何度も瞬きすると、その姿はチラチラと、映りの悪いテレビのように揺らいだ。
(もしかして…これは…)
彼は元からあった右目を閉じ、移植された金色の左目のみを開く。
その瞳に写ったのは、ただの岩だった。
幻か、はたまた催眠か。
原因は分からないが、どちらにしろその子供は、彼の幻想に過ぎなかった。
(―…そうだよな、あるわけないよな…)
そう、彼が移植された瞳は、敵国の兵士のものだった(らしい。噂では。)どうやらそれには偽りを見破り、真実を見透かす能力があるようなのだ。
例えば彼は視覚的な催眠を見破ることができるし、隠れている伏兵を見つけることもできる。どういうことかは良く分からないが、普段彼はあまりこの力を使わないようにしていた。――命が永らえてしまうし、得体の知れないモノだったからだ。
しかし今は使わずにはいられなかった。
今この状況は、どんな激しい戦場にいる時よりも死を間近に感じるような気がするから。
そして彼は気付く。
何てことだ、俺はまだ死を恐れているのか?
それとも死を求めているから歩みを進めているのか。彼にはよく分からなかった。
「~、~♪」
立ち止まって耳を澄ます。冬の風の音に掻き消されて良く分からないが、それは少なくともグリモナの国の言葉ではなかった。とすれば…。
グリモナは左目を見開き、声のする方に慎重に歩みだす。
―そして、一際高い茂みを乗り越えた先に見えたモノは。
背の高い枯れ木に座って歌を歌う、少女のAAだった。
それは、先ほどのような幻などではない。
なぜなら、グリモナの左目にも彼女の姿ははっきりと鮮明に写ったからだ。
桜色の透き通った肌、緋色の瞳。その姿はまるで―
「―アリア!!」
考えるより先に、彼の口は恋人の名を叫んでいた。そしてすぐさま後悔する。
彼女がここにいるわけないじゃないか―…!!!
彼の声に気付き、少女は歌うのをやめた。
目と目が、合う。
少女は、グリモナの恋人とは似ても似つかない、とても冷徹な表情をしていた。
―すると、
「―何故、アナタは動いているの?」
少女が先ほどの澄んだ歌声とは全く違う、沈んだ声で喋る。
「アナタは―…隣国の兵士でしょう?なのに何故…」
黙っているわけにもいかず、
「さあ、な…」
とグリモナも答える。
彼女の顔を良く見て、彼は更に後悔した。彼女の左頬には、“*”のようなマーク…つまり、ゼセルドの国章の刺青が掘られている。さらに、両耳にもぐるりと一周刺青。
(―この子も、ゼセルドの兵士―…)
しかし、少女は全くの丸腰で、彼を警戒する雰囲気もない。
(―…なのか?)
おかしい。さっきから何もかも不自然過ぎる。しかし彼の目はこれは真実だとしか告げてくれない。
―こんな現実があるのだろうか?この子が、兵士?
「…我々の軍事機密が、クレスト・フォル・クレスに漏れたとでもいうの?」
少女は静かに問い質す。
「…そうかもな。俺は分からんが」
グリモナも、馬鹿みたいに冷静に答える。何だってこんな落ち着いているんだ、俺は。…なんだか笑えてきた。
何故か笑うグリモナに、少女の雰囲気が一変する。
「…それなら、アナタも私の攻撃対象になる。」
少女の紅い瞳が一際輝いたかと思うと、急に強い突風が吹き、グリモナは一瞬だが反射的に目を瞑る。
そして慌てて目を見開いたグリモナが見たものは、
少女の背に燃え盛る炎――
否、瞳と同じ緋色の、1対の巨大な翼だった。
第2話:異形/dreadful
「すぐ終わらせるわ」
少女は誰ともなく呟くと、その身の丈程もある翼をすぼめ、彼の元に急降下した。
――“背に炎を抱く、戦場の桜”――
彼は、不意にこんな言葉を思い出した。
―おい、グリモナ。お前のような若いもんは向こう見ずなところが長所ってもんだ。
そう、それは確か、向こう見ずで一本気なグリモナが左目を失った作戦の直後。
彼は、入隊してから何度か世話になったベテランの軍医にたっぷりと説教を受けた。軍医はちょうど他の軍医と交代の時期で、彼と一緒に本国に戻り、彼に治療を施したのだ。
―けどな、ものには限度ってもんがある。世の中にはお前が知らない兵器なんかも多く存在するんだぞ。
彼は、はぁ、と生返事を返す。
軍医は彼が全く反省の色を見せないのに眉をひそめた。
―お前、もしあの敵の軍隊の中にアイツがいたらどうするつもりだったんだ?
―アイツ…ですか?
グリモナは左右違う色の瞳で、軍医を見た。
―何だ、知らないのか。道理で向こう見ずなわけだな。
軍医は軽く笑って付け足す。
―“背に炎を抱く、戦場の桜”。
―は?桜、っすか…?
桜といえば、クレスト・フォル・クレスではメジャーな植物だ。春に薄桃色の花を咲かせる木。彼らの国で知らない者は居ないだろう。
しかしそれと兵器とがどんな関係がある?
訝しむ彼を横目に、軍医は話を続ける。
―こいつを見たらその部隊は必ず負ける。
―負ける?
彼は軍医の言葉に違和感を覚えた。
―戦場で負けるということは、全滅ということですか?
軍医は首を横に振る。
―全員死んでたら、証言する奴はいないだろう?私が診た中には実際証言する奴もいるんだ。だから一層、現実味が強い。まあ上層部が口止めしてるのか、あまりはっきりとは分からないが…
(桜?)
結局、彼の話からはソレが何なのか分からなかった。
(植物が?炎を抱く?そんなもんで部隊が負ける?)
それから何度か考えを巡らせたことはあったが、やめた。形の見えないモノを想像するのは容易な事ではないし、疲れる。
ただ、ぼんやりと思ったのは―…
(ソイツは、俺を殺してくれるだろうか―…?)
そしてソイツは今、正にグリモナの目の前に迫ってきている。
彼女は急降下しながら、音階でいう“ラ”の音で、鋭く口笛を吹いた。
―すると、不可解な出来事が起こった。
彼女の進路の邪魔となる枝や葉が、木っ端微塵に砕けたのだ。ほぼ、跡形も無く。
(―な…)
彼は言葉を失う。
常識外れの翼でさえ驚いているというのに、なんだアレは―…
―いや、常識外れというなら、俺だって同じじゃないか…
アレも彼女の何らかの能力なのか?
俺の左目と同じ―…
そんなことを考えている内に、彼女は彼の眼前に音もなく降り立った。
(―やられる…?)
彼は反射的に体を強張らせる。
さっきの枝のように、自分も粉々に砕かれて死ぬのだろうか?だったら本望じゃないか。
―それなのに―…
どうしてオレは恐れている?
しかし、彼女は、
何もしなかった。
否、何もしなかった訳ではない。ただ、その緋色の瞳で彼の瞳を真っ直ぐに見つめていた。
目を反らすことができず、グリモナは彼女の瞳に写し出される自分を凝視させられる。
瞳の中の自分は、血塗れで笑っている。
笑いながら顔が歪み、だんだん溶けてゆく。
やがて骨だけになるが、それでもカタカタと笑って―…
(ヤバい!)
彼は唐突に我に帰り、右目を閉じる。左目だけで見ると、元の少女の顔が眼前にあった。
「―え」
そこで少女は初めて不思議そうな顔をした。
「アナタ、その左目―?隣国にもその技術はあるの…?」
少女は彼の目を見る。今度は幻術をかけるのでなく、探るような瞳で。
純粋に瞳を覗き込まれて、彼は思わずのけ反る。
「…いや、っ、多分…これはそっちの技術だろ?」
「…どういうこと…?」
「オレは2ヶ月程前に左目を失って、移植手術を受けたんだ。…その後人伝てに聞いたんだよ、コレは向こうの兵士のものだって、な」
「……何てこと…遺体から移植したということ…?」
彼女はしどろもどろ説明する彼の言葉を聞いて、僅かに顔を曇らせた。
しかし彼女は怒り狂うでもなく泣き叫ぶでもなく、ただ少し何かを考えるような面持ちで俯いているだけだった。
堪り兼ねて、冷や汗を滴らせながらも彼は聞く。
「―オレを、殺さないのか?」
すると、彼女は目線は戻さず、小さく小さく、消えそうな声で呟いた。
「―殺す、ですって?…そんなこと…」
見ると、彼女は僅かに震えていた。
「できるわけない…」
第3話:涙/teardrop
何てことだ。
戦場で最も恐れられている彼女が、人を殺せない?
グリモナでさえ、何人もの敵国の兵士をその手にかけてきたのに。
なのに彼女は―…
「殺すのが、怖いのか?」
気がつけば、グリモナは目の前に居るのが敵だということも忘れて訊いていた。
彼女は目を伏せたまま、ほんの少し頷く。
「…私はただ、一般市民として、穏やかに生きて、誰にも知られず死ねば良い
―…だけど…」
いくら戦場で恐れられているとはいえ、彼女も年相応(あくまで外見上だが)の少女なのだろう。それに彼女が兵器と成り果ててからは、まともに会話したのはグリモナが初めてだったのかもしれない。
やがて殆ど感情を見せなかった彼女が、小さく嗚咽を漏らし始めた。
(…うわわ…!)
始めは突然のことに慌てふためいたグリモナだったが、やがて手に余る彼女の体をそっと抱き寄せた。
なぜだろう。なぜ自分は敵国の兵士を抱いている?
どういうわけか。彼女も彼の胸に縋って泣いた。
彼女が泣き止んだのは、それから数十分後の日が暮れる頃だった。
桜色の肌が夕日に照らされ、ほんのり赤く染まるのを見て、彼は素直に“美しい”と思う。彼女の瞳や翼のようなぞっとする美しさでなく、純粋な美しさ。
彼と彼女は並んで枯れた倒木に座っている。彼女はさっきの涙はどこへ行ったのやら、平然な顔をしていた。元々瞳が紅いので、充血しているかどうかも分からない。けれども時折鼻を啜る音が、先ほどの出来事を思い出させる。
「―私、」
なんとなく気まずい雰囲気の中、突然、静かな声で彼女が口を開いた。
「―気付いた時には、戦場にいたの…」
ぽつり、ぽつりと話し始める。
「それより前の事は覚えてなくて。ただ、敵の存在と、自分の任務だけを知っていた。だから私は戦ってきた。」
彼は何も言わなかったが、微動だにせずに意識を集中して聞いていた。
「最初のうちは良かったの。クレスト・フォル・クレスの兵士達は私の特異な姿を見るだけで逃げて行った。けれど、すぐに状況は変わった」
彼女の瞳に宿る、悲しみの色。
「アナタ達の国は、とても信心深いのね―…国のため、残してきた者のため、私に命懸けで挑む兵士たちが現れた。―私は疑問を抱いたの。彼らを殺して何になるの?守るべき者すら忘れてしまった私に、彼らを殺す資格があるのか、と―…」
「だから君は、殺さないのか…」
彼も彼女の声のトーンに合わせるように、深く静かな声で語る。
「殺さないのではない。殺せないの」彼女は呟き、そして付け加えた。「あんな――悪魔の石の為に―…」
「石…?」グリモナは訝しむ。「それはあの御身体とかいう鉱石のことか?俺は田舎の出身だからあまり良く知らないのだが…」
「そうだったわね、アナタ達の国では―…」
彼女は自嘲するように、顔を歪めた。
「君達の国でもあの石を有効活用しようとしていたんじゃないのか?」
「有効活用、されたわ。少なくとも上の連中にとっては、ね…」
「それは―…」
まさか、と思った彼の心を、彼女はそのまま言葉にする。
「そう、あの鉱石は既に戦争に利用されている。――私のような兵士を産みだす為に…」
突然知った真実に、彼は言葉を失った。
第4話:名前/denomination
気がつけば、すっかり日は暮れていた。夜の闇が辺りを支配している。今宵は三日月らしく、弱々しい月明かりが二人の輪郭を辛うじて照らしていた。
「…そろそろ戻らなきゃ…」
「…そうだな…」
彼女の告げた真実に驚き、考えを巡らせていた彼だったが、腰を上げて辺りを見回す。
「ねえ…」
彼女は腰を下ろしたまま、彼のマフラーを引っ張った。
「
ん?」
「その…私に出会った事は…」
「ああ、もちろん。誰にも話さない」
彼が微笑むと、彼女は安堵の表情を見せた。
「ありがとう…それと…」
まだ何かあるのか?と思った彼は、黙って次の言葉を待つ。
するとみるみるうちに彼女の顔は赤くなり、肩をすくめ、今にも消え入りそうな声で囁いた。
「アナタ…名前は…」
「ああ、」敵国の兵士にそんなにたやすく名前を教えてもいいものかと思ったが、教えてどうなる訳でもない。それに彼女の懇願するような雰囲気を裏切ることは出来なかった。
―これが彼女の策略であったとしても、構わない。
ただ、彼女の悲しい顔は見たくなかった。
「俺は、グリモナ。グリモナ・フェルブルク。―君は?」
グリモナが聞くと、彼女は少し困惑したような顔をする。
「私は…“A”…」
「A?それが君の名か?」
「…分からない。覚えてないの。けれど皆私をそう呼ぶわ。だから私はAなの」
彼女はとても寂しげな顔をしていた。
(―しまったな…)
彼は困り、考える。
名前とは、誰かがそう呼ぶから決まるものだ。
彼女だって、周りがAと呼ぶから自分はAなのだと認識したのだろう。
だったら、自分が新しく呼べばいいではないか。
…彼女の名を。
「―なあ、君は桜を見たことがあるか?」
彼の突然の問いかけに、彼女はきょとんとした表情を見せる。
「サクラ?それは…何?」
言葉から察するに、彼女は自分が戦場の桜などと呼ばれていることを知らないようだ。
「綺麗な花が咲く木の一種だ。君達の国は確か、文明が進んでいてあまりそういったものは見掛けないんだな」
彼が説明すると、彼女は興味深々といった様子で、
「へえ…見てみたい」
と、薄く笑った。
ああ…やっぱり彼女は、美しい。この笑顔を、守りたい。
例え彼女が敵であっても―…
「俺は君をサクラと呼ぶ。これから、ずっと」
「…え」
「名前は、誰かが呼ぶから決まるものだ。だから俺は、君にサクラという名を与える。だから―」
後ろを見ずに、彼女の手を握る。
「いつか。俺が君の名前を呼んだら、振り向いてくれないか?」
彼がそう言うと、彼女が手を握り返してきた。
「―うん、ありがとう…」
そしてグリモナは彼女―サクラの立ち上がる気配を感じ、やがてサクラは微かな羽音を残して去った。
振向いて月を仰いだ彼の元に残ったのは、一片の紅い羽。
彼はそれを拾い上げ、思う。
隣国では、一体何が起きているのか。
また、彼女に会えるだろうか。
そして。
サクラという名前は、俺と彼女を結んでくれるだろうか…
私は今日、変わった兵士に出会った。―敵国の。
あろうことか、私は彼に思いを全て打ち明け、感情のまま泣いてしまった。
感情をこんなに表に出すのは久しぶりで、よくよく考えたら恥ずかしい話なのだけど―…
だって、私の気持ちを理解してくれたのは彼が初めてだったから…
私は、A。
悪魔の石の加護を受けた、ゼセルドの機密兵士。
けれど私は、サクラでもある。
サクラというのは、一人のAAであり、一人の女。
彼は私を、サクラと呼ぶ。
―また、彼に会えるだろうか。
―サクラという名前は、彼と私を結んでくれるだろうか―…
―何だろう、この気持ち。
これが―…
シアワセ、ということ?
第5話:再会/reunion
「おい…グリモナ、どうしたんだ?左目。」
作戦待機中、同期に突然尋ねられて、グリモナは左目につけた眼帯を手でなぞりながら、
「いや、別に。ちょっと疼くだけ」と答えた。
「そっか、お前一回怪我したんだよな…結構重傷で、一旦本国に帰ったし。
あんなにひどい怪我がよく治ったもんだ。神のお力だな」
信心深い彼は感心する。
彼の左目が彼のものでは無いことを、誰も知らない。
これほどの信仰の国で敵兵の体の一部を移植したとなったら、彼はどんな扱いを受けるだろうか?まずは軍には居られないだろう。
「ま、あんま無理はすんなよ」
「ああ…」
グリモナは同期に生返事を返す。
彼女…サクラに出会って以来、度々左目が疼くことがあった。
共鳴―というやつだろうか?
やはりこの左目は得体が知れない。こんなものを産みだすゼセルドとは、一体どれほどの技術力があるのだろうか…
(やっぱり、もう一度彼女に会わなくては―…)
兵士としてではなく、彼女と同じくあの石の加護を受けた者として、謎を解明する為に。
そして――
彼女の笑顔を、もう一度見る為に。
―このへんか…
その日の夜、グリモナは敵陣の真っ直中の切り立った崖に立っていた。
今宵は満月。
彼の輪郭は青白い燐光にはっきりと映し出されている。
もちろん、常人であったら危険極まりない行為だ。しかし彼は、その左目で敵国の兵士が擬態したり隠れているのを、レントゲンで透過するように見抜く事ができる。
どうやら今は安全なようだ。近くに敵兵が潜伏している様子はない。
グリモナはそっと眼帯を外すと、その瞳で辺りを見渡した。
彼の左目のもう一つの力。それは―千里眼というべきものか。
彼はその左目を用いて、常人の数十倍の視力を発揮できる(透視などと併用は出来ないのだが)。もちろん彼には原理は良く分かっていない。
別に原理を知らなくても不自由は無いしな。―今のところ。
そして彼はその金色の瞳に、桜色の少女を認めた。その距離は、1キロも離れていない。
―サクラ…
どうやら彼女は、また歌を歌っているようだ。
彼女の周りには、ちょうど円状に兵士が倒れていた。―勿論、グリモナの仲間たちだ。
彼女を包囲したつもりなのだろう。しかし仲間であるグリモナが思うのも少し問題だが、そんなことをしたって彼女にとっては何ら意味の無いことだ。
彼は複雑な心境に顔を歪めながらも、踵を返して彼女のもとへ向かった。
最後の兵士が、ドサッと音を立てて頽れた。
この部隊の兵士は、全員気を失った。1週間ほどは目覚めず、後遺症は残るが、命を奪う程のモノではない。
無論、彼女は人を殺す術も知っている。武器を使わなくとも、そういう歌を歌うだけ―でも。
(―やっぱり、無理…)
溜め息。
(分かっている。コレは戦争。敵は、生かしてはおけない。分かってるけど…)
彼女にはどうしても命を奪うことは出来ない。
頭では分かっていても、実行には移せなかった。
(あまり長くも居られないわ…)
さっきから敵兵の無線機からは、「おい、どうした!?」という怒号が漏れてきている。応援部隊もじきに駆け付けるだろう。敵の不意を突かなければ、彼女の方が危うい。
彼女がその場を去ろうと、紅い羽を大きく広げたその時。
「―サクラ!!!」
(―!!)
木々の間の闇から、彼―グリモナの声がした。
こちらからは彼の姿は見えない。しかし、彼には見えているだろう。彼の左目にそういう能力があることを、彼女は知っている。
「―ぁ…」
彼女は、子供が悪戯しているのを見つかったような顔をした。
『オレが呼んだら、振り向いてくれ…』
彼の言葉が脳裏に過る。
けど―
「…見ないで―!!!」
心とは裏腹に、彼女の口を突いて出たのはそんな言葉だった。
「―私を、見ないで…
醜い、から―…」
縋るように、言い放つ。
あれ?何故だろう。
私は、彼に会いたかったのに――
彼に名前を呼んで欲しかったのに――…
けれど、見られたくない。
人智を超えた、背の翼と、魔の歌声を用いて戦う、
まさに兵器そのもの、いやそれ以上に相手に畏怖の念を抱かせる自分の姿を。
「―…」
彼には、言葉が見つからなかった。
しかし、何故だか彼女に近付いてはいけない事は分かった。
俯き、目を閉じる。
(君は、醜くなんか、ないのに―…)
彼女は、グリモナの祖国――クレスト・フォル・クレスの部隊を退けた。
誰一人、殺すことなく。
彼女は、戦場で散るはずの彼らの命を助けたのだ。少なくともグリモナはそう思う。
(―君は―…!!)
サクラは、彼に自分の姿を見られたくないが故か。そっとその場を飛び去る。
微かに、彼女の羽音がした。
「―君は…」
思いが、言葉を紡ぐ。
「オレの瞳に映る君は、紛れもなく―…」
サクラは、遠ざかる森の木々の合間から、彼の呟く声を聞いた気がした。
―天使なのに、と。
第6話:光明/torch
それから1週間。
グリモナはその晩、野営のテントで寝袋に包まれ、眠れずに仄暗い天井を見つめていた。
オレは―
まだ、死にたくないんだろうか。
真実を見透かす瞳でも、自分の心までは分からない。
けれど、もし死ぬのなら―
彼女の顔が、思い浮かんだ。
しかし彼は、即座にその考えを否定する。
――人殺しを恐れる彼女にオレを殺させるのか?
彼が取り留めも無い考えを終わらせて眠ろうとしたその時。
―ドサ。
そんなに遠くは無い場所から、誰かの倒れる音がした。
グリモナの全身に緊張が走る。
(敵…!?)
音を立てずに身を起こし、左目で音のした方向をテントの壁越しに“凝視”する。
思わずあっと声を出しそうになった。
野営をしている開けた場所と、森の境目。
夜の闇に紛れて現れたのは―
(サクラ…!)
彼女が、彼の左目の視界の先に佇んでいた。彼女の両脇には、見張りの兵士が倒れている。
『グリモナ…』
彼女の唇が動く。
『お願い、“見えて”いたら…外に来て…』
彼は一瞬躊躇った。
左目が疼く。
体は彼女の元へ行きたがっている。
けれど―
自分は、彼女を傷つけないだろうか…それだけが怖かった。
彼女は彼が見ていることが分かって居るかのように、こちらをじっと見て居る。
彼女も共鳴しているのだろうか、俺の左目に。
(―彼女は、望んでここに来たんだ―…)
彼は腹を括った。
サクラは、俺に何か伝えたいことがある―とても、重要なことだ。
寝袋から這い出し、仲間の兵士に見つからぬよう足音を立てずにテントから出る。一度小枝を踏んでパキッと音を立ててしまったが、誰も気付かずにすやすやと寝息を立てている。最近徹夜続きだったとはいえ、呑気な奴等だ。
外に出たグリモナを、サクラは柔らかい笑顔で迎える。初めて出会ったときと同じ、笑顔。
「ごめんなさい…彼らには少し眠ってもらったけど、朝になれば起きるから…
ついて来て」
彼女は背を向けると、倒れている兵士の間を抜け足早に森の奥へと消えた。
彼は大きく深呼吸してから、小走りで彼女の後を追った。
しばらく2人は、グリモナがサクラを追う形で、無言で木々を縫って歩いた。
足場は悪いが、2人にとってそれほど問題でもない。
「―知りたい?」
「え…?」
10分ほど歩いたところで唐突にサクラが言葉を発し、彼は驚いて立ち止まる。
彼女も立ち止まり、彼を振り返った。
「私の翼と、力のこと。あなたの…左目のこと。私の国のこと。」
彼は彼女の目線を受け止め、頷く。
「俺は、知りたい。けど、戦いの為じゃない。俺の国の為じゃない。
ただ、真実を知りたい。知ってどうなるかは分からないが、このままじゃ死ねない。そんな気がする。それに、」
彼は心の底から、本音を吐きだす。
「君の事を、もっと知りたいから―」
彼女はしばしあっけにとられていた。まさか自分のことを彼が考えていたなんて。
しかしその顔はすぐに微笑みに変わった。
「…ありがとう」
第7話:星空/starry heaven
さらに数分後。二人は木の上にいた。
それはグリモナが1週間前にサクラを見つけるために上った崖に、たった1本だけある、巨大な大木。
それは冬の寒さに枯れ、寒々しい枝を夜空に晒していた。
空には無数の星が瞬いている。新月なのか、月は見当たらない。
「私の国―ゼセルドは、この戦争が始まる前からあの鉱石のエネルギーに着目していたの。エネルギーというのが何なのか、私はよく分からないけど…
戦争の20年ほど前はゼセルドもクレスト・フォル・クレスも問わず、有能な研究者を集って石について研究していたらしいわ。もちろん、―あなたの前で言うのもなんだけど、クレスト・フォル・クレスの技術はこっちに比べたら遅れているから、研究者はごく少数だったけど…」
サクラは枝に腰掛け、足をぶらぶらさせながら語る。
その仕草は、見た目の年相応、いやそれ以上に幼く見える。
しかグリモナは、彼女の次の言葉で、彼女の壮絶な過去を知った。
「私も本当はどこかの辺境の村で生まれたみたい。といっても覚えてないんだけど。
けど戦争が始まってから研究所に連れて行かれて、何かの実験を受けて…そして気づいたときには戦場に居たの。
記憶はなかったけど、戦い方は知っていた。けれどそれと同時に、誰かを殺すことが恐ろしくてたまらなかった…」
彼女の体が小さく震えていることに、彼は気づく。
思わず手を伸ばそうとするが、彼女は気丈に「大丈夫」と言った。
「ごめんなさい、この話は関係なかったわね…それよりも、あの石を用いた実験のことだけど―」
そういった彼女は目を閉じ、彼が瞬きをする一瞬に、背に巨大な翼を広げた。
「さっきも言ったけど、私は実験の内容についてはよく分からない。けれど自分の能力ならもちろん知っているわ。―あなたの左目のことも。」
彼は思わず彼女の顔を見た。
鼓動が高鳴る。
―求めていた答えが、ここに…
サクラは彼の懇願するような瞳を柔らかい表情で受け止めた。
全てを受け入れる聖母のように。
「私の能力。それは“空気の振動”、すなわち“音”を操ること。この翼は、その実験で偶然生まれた副産物よ。
私は音を操って相手を催眠状態に陥れることが出来る。それだけでなく、空気の振動を使って物質を破壊することもできる。
―その気になれば、AAもね。」
そう言ってサクラは自虐的な笑みを浮かべた。
「けれどあなたには催眠が通じなかったでしょう?それがあなたの左目の能力よ。分かっているとは思うけど」
グリモナは、思わず息を呑んだ。
「私の催眠は聴覚を介して、ほとんどは視覚に現れるの。もちろん音は体に直接作用してはいるんだけど、視覚に作用しなければ効果はないのよ。面倒だけど。
あなたの左目は、催眠を見破り、そして物質を透過して見る事が出来る。さらに数キロ先まで見渡せる千里眼の能力がある。…そうでしょ?」
彼は冷や汗を掻きながら、「ああ」と頷いた。
「訓練すれば、常人が目で追えないものを追ったり、視野が広がったり。兎角“視覚”に関しては、はるかに常人を卓越したことが出来るようになるはずよ。
その瞳の元の持ち主は、私の知り合いだったから―」
目の前が真っ暗になったような気がした。
この目の持ち主が、彼女の知り合いだって―?
だったら彼女は、俺を恨んでいるんじゃないか…!?
けれど彼女はグリモナの不安を裏切り、首を振って微笑する。
「彼は亡くなったと聞いていたけど…ちゃんと生きていた。あなたと共に。
それは、とても嬉しいこと―そう思う。」
彼女は翼をたたみ、彼のすぐ隣に腰を下ろした。
グリモナは、夜空を仰いだ。心の中で、彼女の言葉を反芻しながら。
―それは、とても嬉しいこと―
(―彼女は、俺を恨んでいなかった)
それは彼にとって、何よりの救いであった。
彼女を傷つけることを恐れる彼にとっては。
相変わらず星たちは、我こそは、とその身を輝かせている。
彼女の存在は、そんな星たちとは違い、控え目で。
でも、無数の星よりもキレイだ。
グリモナが見上げている夜空を、サクラも彼に倣って見上げ、ぽつりと呟いた。
「空は、キレイね…私たちAAと違って。」
グリモナは空を見たまま、黙って彼女の次の言葉を待つ。
「でもあなたの心も、キレイ。今は底の見えない深い沼のようだけど、光が差し込めばきっと澄んだ湖だとわかるはずよ」
「―そんなこと―…」
即座に否定しようとした彼の口を、サクラがそっと塞ぐ。
「私には分かる。アナタは今まで見た他のAAとは違う。だって私を…」
彼女は口ごもってしまった。
「…?」
空から目線を彼女に移すと、彼女もその緋の瞳に彼の姿を映した。
「天使、だなんて…初めて言われたわ…」
「き、聞こえてたのか!?」
こんどはグリモナが恥らう番だった。なんて耳だ。流石だな…
「…私は、自分が人に不幸しかもたらさないと思ってた。だから、戦場でしか生切られなかったの。敵を退けることで、私にも価値が生まれれば良かった。
でも今は違うの―…」
サクラの薄桃色の瞼が、ゆっくりと緋色の瞳を隠す。
「アナタもきっと辛い過去があるのね。その左目――」
指が、そっとグリモナの顔を撫でる。
「アナタが私利私欲のために奪ったものではないはず。そうだとしたら、アナタはここにはいないでしょう?こんな所で、一介の兵士として、命を危険に晒していないはず…」
「――!」
グリモナは息を呑んだ。
「今は―…私は、ただ…」
彼女はその体を、そっと彼の胸に預ける。
柔らかな温もりが伝わってくる。
「アナタの“濁った湖”を照らす…光になりたい…」
しばらく二人はそのまま、星々の瞬きを眺めた。
寒さで凍えた体に、お互いの温もりが心地よかった。
「―俺、大切な人を守れなかったんだ…」
夜が明けようと、東の空が白んで来た頃。
グリモナは、彼女に語りだした。
「戦争行けばさ、みんな守れると思ってた。国も、村も、家族も、恋人も。けど俺はどこの誰だか知らない兵士たちをちまちま殺すだけで、何にもならなかったんだ…」
「……」
「だから、この左目を手に入れた気持ちは正直複雑だった。俺が選んだんじゃなく、勝手に移植されたんだが。
この左目があれば、守るべきものを守れるかもしれない。けど――
もう守るべきものは消えた。恋人は、死んだんだ…」
「……!」
彼女が息を呑む気配が伝わって来る。
彼は構わず続けた。
「俺は、死にたいと思っていた。けれど、心のどこかには死を恐れる気持ちもあった。どっちの気持ちが正しいのか俺は分からない。ただ、確かなのは、」
「……?」
「君なら、俺を殺してくれるんじゃないか。初めて君を見た時、そう思った…」
「…!!っ…」
ビクン、と彼女の体が強張る。
「けど。君の涙は…初めて会った時の君の涙は、俺のそんな濁った考えを消し去った。
彼女は涙しながら戦場で生きているじゃないか。大嫌いな戦場に――それに、」
一度だけ。彼女の頭を軽く撫でる。
「世界にはまだ、こんなに美しいものがあったんだ―…
そう、思った」
彼女が体を起こし、彼の顔を見た。
真紅のルビーのような瞳に彼の姿を湛える。
「私は、美しくなんか―…」
そう言いかけたが、サクラは目を閉じて首を振った。
「ううん、貴方がそう言ってくれて、とても嬉しい。私にも、生きる意味が出来た…」
グリモナも珍しく微笑み、片手で彼女を抱き寄せる。
「俺も、生きようと思う。君の命が続く限り、生きよう。
この戦場を生き抜いてみせる。約束するよ。」
そして彼は気づく。
「死にたい」などと思っていたのは、所詮俺のエゴだったんだ。
彼の恋人―アリアは、別れ際に言っていた。
生きて、生きて。必ず生きて。何があっても―
俺はカッコつけて死のうと思っていたんだな。
けれどどこかで死にきれなかったのはきっと―
きっと、彼女の言葉が心のどこかで引っかかっていたんだ…
俺は、生きる。
アリアの為にも。
―サクラの為にも―
アリアも、きっとそれを望んでいるはずだ。
そう、信じたい。
生きて生きて生き抜いて、その先はどうなるんだろう?
分からない。
分からなくていい。
今はただ、彼女と共に生きていたい。
第8話:疑惑/dubiety
「朝日だ…」
グリモナは小さく呟いた。
遥か遠く。白く霞んだ山々の際から、黄金色の朝日が顔を出し、二人を同じ色に染める。
「またしばらく、離れ離れね…」
「ああ、でも…」
彼の気持ちは、揺るがなかった。
「もう、大丈夫だ。俺も、君も。約束、しただろ?生きるって。」
「…うん、そうよね」
サクラの表情から不安の色が消える。
そう、俺達は大丈夫。
俺は、もう死にたいと思わない。
それは恐れではなく、揺るぎない信念。
その後二人は別れを告げ、グリモナは野営地へと戻っていった。
(…そういえば、倒れてた見張りは大丈夫か…?サクラは、朝になれば起きる、と言っていたが…)
彼が深く生い茂る木々の枝をくぐり、野営地へと出ると、案の定と言うべきか、兵士達は慌しく動き回っていた。
その内の一人が、その様子を傍観しているグリモナに気づき、驚いて叫ぶ。
「グリモナ!!お前、どこ行ってたんだ!!」
すると兵士達の目が全てこちらに集まり、口々に叫ぶ。
「おい、グリモナが生きてたぞ!!しかも無傷だ!!(多分)」
「先輩!!心配したんすよ!!」
「何してんだ、早く隊長のところに行かないか!!」
「てっきり捕虜になったかと。」
「ああもう、馬鹿野郎!!余計な手間掛けさせやがって!!」
どうやら彼らの話を総括するに、朝目覚めた兵士が見張りが倒れていることに気づき報告に行ったところ、グリモナが行方不明になっており、敵兵に捕らえられたものと思い捜索していたのだという。
ちなみに見張りの兵士は、「何故か眠くなって寝てしまった」と言っており、隊長にこっぴどく怒られていた。今は処罰として腕立て500回(本当にできるのか?)をしている。さすがサクラだ。
(う~ん…さすがに今回は少しヤバいかな…)
グリモナも彼らと同じ処罰を覚悟しながらも、隊長のテントに向かった。
「だからうちの兵士が一人行方不明なんだ!!あ!?そんなこたぁどうでもいい!!とにかく捜索隊を組むのに少し人を貸してくれ!!」
テントの中では、隊長の怒号が響き渡っていた。
どうやら他の隊に応援を求めているらしい。
グリモナは今更事の重大さを実感しながらも、恐る恐る彼に声を掛ける。
「た、隊長…?」
「うるさい!!今取り込んでいるんだゴルァ!!後にしろ!!で、どうなんだ!?いつになる!?」
「…。隊長!!」
「あ!?」
グリモナに耳元で叫ばれ、隊長は不機嫌そうに振り向き、そこで初めてグリモナの存在を確認する。
「!!グリモナ!!馬鹿野郎!!」
無事を確認した隊長が真っ先にお見舞いしたのは、強烈な往復ビンタだった。
「い、いて…」
数分後。興奮が収まった隊長から解放されたグリモナの頬は、両方とも真っ赤に腫れ上がっていた。
「いや、ちょっとやりすぎたか。すまんな。
しかしお前のやったことはそれだけで済まされることではないぞ。本来はな。」
「はい…すみませんでした…」
「で、どこに行っていたんだ?」
隊長の質問にグリモナは一瞬口ごもりそうになるが、野営地に戻ってきてから密かに考えていた言い訳が、淀みなく口から出た。
とはいっても、それは
「朝方、ちょっとトイレに行ってただけです。そしたら道に迷ってしまって」
といった単純なものだったが。
「あれほど単独行動はするなと口をすっぱくして言っただろうがゴルァ!!」
隊長が再び青筋を浮き出させる。
やばい。
何で単独行動をしたかとか、倒れている見張りの兵士を見なかったのかとか、どうして道に迷うほど遠くに行ったんだとか、そういうことを聞かれたら非常に不味い。頭の回る彼とて完璧に弁明する自信は無かった。
そして、
「そもそも…」
と、隊長による追求が今にも始まらんとしたその時。
「まあまあ。ギコ隊長。そんなに怒りなさんな」
グリモナの後ろから誰かがテントに入ってきて、穏やかに隊長をなだめる。
グリモナは、その声に聞き覚えがあった。
「こいつは向こう見ずな馬鹿だから仕方ないんだよ。でもそこがこいつのいいところだろ?」
そういってグリモナの方に手を置いたのは。
「…先生!?」
それは、かつて彼の左目を手術した軍医、茶色の長毛を持つAAのフサインだった。
「久しぶりだな、グリモナ。どうだ?調子は」
怒る隊長をよそに、彼はゆったりとした動作でグリモナの前に歩み出る。
「は、はあ…」
グリモナは予想外の人物の登場に、すっかり肝を抜かれた。
「返答がはっきりしないのは相変わらずだな」
そういって彼は微笑み、グリモナの頭をぐしゃぐしゃと撫でる。
「先生は、また軍医としてこちらに?」
「ああ、そんなとこだ。全く、年寄りをこき使いやがって」
言いつつもフサインは、嫌そうな顔を見せない。むしろ嬉しそうにも見える。
(そうか、先生ももう50近いのか…それにしては若々しいけど)
「ん?なんだその物言いたげな目は?」
フサインがグリモナの晴れ上がった頬をつねる。
気づいたらグリモナはフサインの顔を凝視していたようだ。
「い、痛ぇ…」
そんな二人のやり取りに、ギコ隊長もすっかり毒気を抜かれたようで、無線を持ったままぽかんと二人を見つめている。
フサインはグリモナの頬をつねりながら、そんなギコ隊長をちらっと横目で見た。
「ギコ隊長。すまんな、久々の再会だ。こいつをちょっと借りてもいいか?」
「…ん?あ、ああ…お前さんの頼みなら仕方ないな。好きなだけ借りてくれ」
ギコ隊長でさえもどうやらフサインには頭が上がらないところがあるらしく、素直にグリモナを引き渡す。
「ありがとよ」
フサインはグリモナに向き直り、出口に向かって歩き出す。
「じゃあ、第7テントで待ってるからな。体、洗って来い。お前――」
彼がすれ違い様に言葉を放つ。
「臭う、ぞ。」
グリモナは驚き、バッと振り返った。
フサインは何事もなかったかのように、「じゃあな、隊長」と右手を上げてテントを出て行く。
体の芯が凍りつくような感覚。
普段であったら、ただ単にグリモナの体が汗臭いとか、そういう冗談で済んだだろう。
しかし、フサインの顔は全く笑っていなかった。
『臭う、ぞ。』
脳に直接響くような、冷たい声が蘇る。
(―先生、貴方は一体――?)
グリモナは、嫌な予感が湧き出てくるのを止めることが出来なかった。
第9話:真実/veracity
「よお、グリモナ。」
30分後。第7テントに入ってきたグリモナを、フサインは簡素な折りたたみ式の椅子に座って迎えた。
彼は休む間もなく手を動かしている。
「悪いな。こっちから呼んでおいて何だが、ちょっと手が離せないんだ。そこらへんに適当に座ってくれ」
言われてグリモナは、手近にあった折りたたみ椅子に座る。
テントは小さく、薄暗い。これまた簡素で低いテーブルの上には、なにかの資料と思わしき紙束がうず高く積まれている。
「先生、まだ研究のほうは続けているんですか?軍医の仕事と並行して。」
「ん?ああ、まあな。」
フサインは、グリモナのほうを見ずに答えた。
「遺伝子学の研究、でしたっけ」
「そうだ。よく覚えているな。」
実を言うと、彼は隣国に比べれば医学が進んでいないクレスト・フォル・クレスにて、唯一隣国と同等の知識を持っているとも謳われるほどの名医だ。
しかし彼はそれほど自分の知識をひけらかしたがらない。
それ故、このような小さな部隊の専属の軍医として働いているのだ。
「先生は、元気でしたか?」
グリモナは、仕事を続けるフサインに構わず質問した。
久しぶりに出会った嬉しさが、彼の質問を留めることが出来なかった。
「そうだな。ま、ちょっとハゲてきたくらいかな」
「それは奥さんに刈られたからじゃないですか?」
「いや。昔は刈られてもちゃんと生えたんだよ。」
フサインが苦笑いしながら話す。
それを見てグリモナにも自然と笑顔が浮かんだ。
「さて。仕事ばかりしていても何だしな。ちょっとひと段落つけるか…」
フサインはポケットからステープラーを取り出し、紙束を綴じて封筒に入れた。
「それでだ、グリモナ…」
フサインの瞳が、テーブル越しにグリモナを見据える。
「お前、昨日どこへ行っていたんだ?」
グリモナの額には、冷や汗が滲み出た。
彼に、嘘が通用するようには思えない。
彼の瞳は、グリモナの心の奥底までもを見透かしているようだった。
しかし、本当の事は言えない。
例え、それがグリモナの信頼する名医であっても。
「隠さなくて
カランカラン…
荒野にひっそりと佇む寂れた街の小さなバーに、夕暮れ時の入り日と共に一人の男のAAが入って来た。
男は目深に帽子を被ってはいるが、何か独特の雰囲気を放っていた。鋭く、でもどこか穏やかな。
周りの客の目は自然と男に集まるが、男は別段気にする様子もなくゆっくりと歩みを進め、カウンターに腰掛ける。
「…マスター、ウォッカを一つ」
「はいモナ」
気さくなマスターのモナーは明るく答えたが、酒を出そうとして彼の帽子につけられた“*”を象ったようなバッジが目に止まり、首を傾げる。
「お客さん、そのバッジ…」
その声に気付いた男は、ん、と少し帽子をあげた。
男は、白い肌に、右は黒、左は金色の瞳といった風貌だった。30代ほどだろうか。
何でもないようにああ、と答える。
「安心しな。こいつは確かに隣国のゼセルドの国章だが、オレはクレスト・フォル・クレスの者だ」
「…とすると、それは戦利品モナ?なるほど、お客さん元兵士モナか。道理で…」
―ダンッ!!!―
雰囲気が違う、と言おうとしたモナーの言葉を、男がグラスを乱暴に置く音が遮った。
「―こいつは戦利品なんかじゃない。もっと悲しくて、ちっぽけなもんだ…」
「…ほう?」
モナーは心外そうな顔をすると、男の正面にイスを持って来て座った。
「丁度退屈してたとこモナ。良ければ話を詳しく聞かせてくれないモナ?」
男は、眉を顰める。「…何故、興味を持つ?」
モナーは少し寂しそうに微笑んだ。
「モナは10年前の戦争で家族も知人も皆亡くしたモナ。あの戦争の意味を、モナは知りたい。だからこうして、兵士さんに話を聞くモナ…」
「……」
しばしの沈黙のあと、男は一気に酒を飲み干し、口を開いた。
「“アイツ”がいなければ俺は今ココにはいないだろうし、意味を持って生きていることなどなかったんだろう……――」
*******************************
今でも瞳を閉じれば蘇る、アイツの瞳と、背中に燃える紅い炎の華…
*******************************
第一話:邂逅/rencounter
―それは、ある冬のこと。
木枯らしが吹き荒び、木々は立ち枯れた季節。
「…ハァ、ハァ…」
誰の声かと思ったら、洞窟に反響した自分の声だった。
彼は、冷たく暗い洞窟の壁に体を預け、座り込んでいる。
ひどく眠い。けれど、このまま眠ったらこの洞窟の闇に呑まれて自分が消えてしまいそうだった。
(落ち着け…!落ち着くんだ…!)
心の中で、何度も自分に語りかける。自分を見失わぬように。
この洞窟は全く日が当たらない上、水脈があるのか底辺には水が溜まっており、容赦なく彼の体温を奪う。
(グリモナ…)
自分ではない、誰かの声が聞こえたような気がした。
(グリモナ…)
声に応え目を瞑ると、自分の名を呼ぶ恋人の姿が見えた。
桜色の美しい肌、緋色の瞳。暖かい日差しのような微笑み。
けれども彼―グリモナが手を伸ばすと、彼女の姿は闇へと掻き消えた。
目を開く。そこには目を閉じていたときとさして変わらない闇が広がっていた。
(そうだ、俺は…グリモナ・フェルブルク…)
小さく呟き、心を保つ。
(俺は、クレスト・フォル・クレスの兵士で…今は戦場にいる…)
耳を澄ますと、遠くに爆撃の音が聞こえる。
(…何でオレは逃げている?)
グリモナの部隊は敵の奇襲に遭い、彼は成す術も無くこの洞窟に逃げて来たのだ。
(…アイツは…恋人は、もう死んだじゃないか…)
グリモナは、自ら進んで兵士となった志願兵だ。
彼は小さな村で育ち、やがて幼馴染みの娘と恋に落ちた。しかし彼が19になった時、戦争が始まった。
科学大国、ゼセルド。
宗教大国、クレスト・フォル・クレス。
隣り合う2つの国の境には、巨大なエネルギー鉱石の結晶体があった。それはAA達が誕生する遥か前に、宇宙より飛来したといわれている。
全高10mほどもあるその石を、クレスト・フォル・クレスは神の意思の宿る石として信仰の対象として来た。
しかしここ数年でゼセルドの科学技術は大幅に発達し、ついに鉱石のもつエネルギーに着目し、クレスト・フォル・クレスと交渉に出た。
あの石を譲ってくれれば、必ずその恩恵をクレスト・フォル・クレスにも平等に分け与える、と。
しかし彼らの答えはNOだった。
あの石はAAが手を出していいモノではない。強引に奪うのであれば、こちらも手段は選ばない、と。
しかしゼセルドはあくまでも自国側の鉱石の所有権を主張した。
この鉱石は自然の一部であり、我々が大地を分かつように、この石も分ければよいではないか。
そしてゼセルドが独断で自国側の鉱石を掘削し始めたのが戦争の火蓋となった。
もちろんクレスト・フォル・クレスにしてみれば、信仰の対象である石が半分でいい訳が無い。
ある夜、クレスト・フォル・クレスの政府直属の兵士がゼセルドの掘削隊に奇襲をかけた。そしてそれは本格的な戦場へと発展していくこととなる。
クレスト・フォル・クレスのグリモナも、愛する者を守るため兵士に志願した。彼はかなりの田舎に生まれ育ったため、正直神だとか石だとか、どちらが正しいとか正しくないとか、そんなことはどうでも良かった。
ただ、彼女の笑顔を守ることができれば。―もう半年もしたら生まれる、新たな命を守ることができれば。それだけだった。
グリモナが戦場に赴いてから8ヶ月。彼はある作戦で左目を失う。
クレスト・フォル・クレスは、この時点では兵役は強制ではなく、基本的に志願兵だけだった。この宗教大国の国民は非常に愛国心が強く、強制などしなくともある程度は兵士が集まったからだ。ただ、少々の戦力不足は否めなかった。
それ故、負傷した兵士は本国にて治療されるケースが多い。彼もその内の一人だった。彼はすぐさま本国に帰され、角膜の移植手術を受けた。お陰で視力は奇跡的に回復した。
彼は再び戦地に赴く数日前の晩、病院を密かに抜け出した。
――…一目、見るだけで良かったのだ。
愛する者と、愛の結晶であるわが子を。
会って話をしなくても良い。
触れられなくても良い。
ただ、見たかった。
決して贅沢な願いでは無い。しかし彼らが崇めるところの神は、それさえも許さなかったようだ。
森を抜けた彼の眼前に現れたのは、懐かしい村ではなく、
ただの、荒野、だった。
茶色い乾いた土と、石ころと、平坦な大地。ところどころに立ち並ぶ、少し大きめの石。
彼が幼い頃虫捕りをした緑の森も、友達と泳いだ美しい川も、恋人と語らった大きな木も。建物も。村人も、家族も、恋人も。
―何も、無かった。
訳が分からずただただ立ち尽くす彼の視界に、一人の男が映る。
男は、親しかった村人たちを弔った墓堀人だった。グリモナに気づき、やあ、と軽く挨拶をして近寄ってくる。
―あんた、この村に親しい人でもいたのかい?この村なんてとうの2ヶ月以上も前に消えたよ。跡形もなくね。
聞いた話では、1時間も掛からなかったそうだよ。何がって、全てが消えるのが。
ここに何も無いのは私が片付けたからじゃない。…本当に何も残らなかったんだ…―
男はそんなことを話しながら小さな墓石らしき物に手を合わせた後、彼を尻目に去って行った。
―嘘だ…―
彼はしばし呆然とした。
―俺は一体何の為に戦って来たんだ…―
遺言も無い。遺品さえも無い。
彼が拠り所とする物は、何もなかった。
結局彼は心配した同僚によって見つけられ、病院に連れ戻された。
抜け殻のようだった彼は、一週間後には何事も無かったかのように再び戦地へ繰り出された。
そして今。彼は戦う意味も、生きる意味さえも分からず、ただ毎日戦っている。
遠くに聞こえる銃弾戦の音。
闇にこだまする、自分の、息。
(…そうだ、何故オレは逃げている?)
彼は閉じていた目を開いた。
(―行けばいいじゃないか…)
疲れ切った老人のように、ゆっくりと立ち上がる。
(―彼女のところへ…)
死ぬことは怖くないはずだ。
何故今までこうしなかったのだろう?
一歩一歩、確かめるように歩みだす。
そして外の光が見えた、その時。
(―……?)
グリモナは、違和感を覚えた。
――シン…――
先ほどまでの戦争の音が、全く持って消えていた。変わりに彼の耳に届いたのは、
(―歌?)
確かに女性のものと思わしきソプラノの歌声が、微かに聞こえた。
彼は外の眩しさに目を細めながらも、また一歩踏み出す。すると彼の前に、唐突に一つの小さな影が立ち塞がる。
それは、
1、2歳程度の子供、だった。
逆光でよく見えないが、彼と同じ白い肌に、真紅の瞳。こちらを見て微笑んでいる。それはまるで――
(―俺と、アイツの…?)
生きていたのか?
彼は淡い希望を持ち、その子供を目を凝らして見つめる。
しかし彼が何度も瞬きすると、その姿はチラチラと、映りの悪いテレビのように揺らいだ。
(もしかして…これは…)
彼は元からあった右目を閉じ、移植された金色の左目のみを開く。
その瞳に写ったのは、ただの岩だった。
幻か、はたまた催眠か。
原因は分からないが、どちらにしろその子供は、彼の幻想に過ぎなかった。
(―…そうだよな、あるわけないよな…)
そう、彼が移植された瞳は、敵国の兵士のものだった(らしい。噂では。)どうやらそれには偽りを見破り、真実を見透かす能力があるようなのだ。
例えば彼は視覚的な催眠を見破ることができるし、隠れている伏兵を見つけることもできる。どういうことかは良く分からないが、普段彼はあまりこの力を使わないようにしていた。――命が永らえてしまうし、得体の知れないモノだったからだ。
しかし今は使わずにはいられなかった。
今この状況は、どんな激しい戦場にいる時よりも死を間近に感じるような気がするから。
そして彼は気付く。
何てことだ、俺はまだ死を恐れているのか?
それとも死を求めているから歩みを進めているのか。彼にはよく分からなかった。
「~、~♪」
立ち止まって耳を澄ます。冬の風の音に掻き消されて良く分からないが、それは少なくともグリモナの国の言葉ではなかった。とすれば…。
グリモナは左目を見開き、声のする方に慎重に歩みだす。
―そして、一際高い茂みを乗り越えた先に見えたモノは。
背の高い枯れ木に座って歌を歌う、少女のAAだった。
それは、先ほどのような幻などではない。
なぜなら、グリモナの左目にも彼女の姿ははっきりと鮮明に写ったからだ。
桜色の透き通った肌、緋色の瞳。その姿はまるで―
「―アリア!!」
考えるより先に、彼の口は恋人の名を叫んでいた。そしてすぐさま後悔する。
彼女がここにいるわけないじゃないか―…!!!
彼の声に気付き、少女は歌うのをやめた。
目と目が、合う。
少女は、グリモナの恋人とは似ても似つかない、とても冷徹な表情をしていた。
―すると、
「―何故、アナタは動いているの?」
少女が先ほどの澄んだ歌声とは全く違う、沈んだ声で喋る。
「アナタは―…隣国の兵士でしょう?なのに何故…」
黙っているわけにもいかず、
「さあ、な…」
とグリモナも答える。
彼女の顔を良く見て、彼は更に後悔した。彼女の左頬には、“*”のようなマーク…つまり、ゼセルドの国章の刺青が掘られている。さらに、両耳にもぐるりと一周刺青。
(―この子も、ゼセルドの兵士―…)
しかし、少女は全くの丸腰で、彼を警戒する雰囲気もない。
(―…なのか?)
おかしい。さっきから何もかも不自然過ぎる。しかし彼の目はこれは真実だとしか告げてくれない。
―こんな現実があるのだろうか?この子が、兵士?
「…我々の軍事機密が、クレスト・フォル・クレスに漏れたとでもいうの?」
少女は静かに問い質す。
「…そうかもな。俺は分からんが」
グリモナも、馬鹿みたいに冷静に答える。何だってこんな落ち着いているんだ、俺は。…なんだか笑えてきた。
何故か笑うグリモナに、少女の雰囲気が一変する。
「…それなら、アナタも私の攻撃対象になる。」
少女の紅い瞳が一際輝いたかと思うと、急に強い突風が吹き、グリモナは一瞬だが反射的に目を瞑る。
そして慌てて目を見開いたグリモナが見たものは、
少女の背に燃え盛る炎――
否、瞳と同じ緋色の、1対の巨大な翼だった。
第2話:異形/dreadful
「すぐ終わらせるわ」
少女は誰ともなく呟くと、その身の丈程もある翼をすぼめ、彼の元に急降下した。
――“背に炎を抱く、戦場の桜”――
彼は、不意にこんな言葉を思い出した。
―おい、グリモナ。お前のような若いもんは向こう見ずなところが長所ってもんだ。
そう、それは確か、向こう見ずで一本気なグリモナが左目を失った作戦の直後。
彼は、入隊してから何度か世話になったベテランの軍医にたっぷりと説教を受けた。軍医はちょうど他の軍医と交代の時期で、彼と一緒に本国に戻り、彼に治療を施したのだ。
―けどな、ものには限度ってもんがある。世の中にはお前が知らない兵器なんかも多く存在するんだぞ。
彼は、はぁ、と生返事を返す。
軍医は彼が全く反省の色を見せないのに眉をひそめた。
―お前、もしあの敵の軍隊の中にアイツがいたらどうするつもりだったんだ?
―アイツ…ですか?
グリモナは左右違う色の瞳で、軍医を見た。
―何だ、知らないのか。道理で向こう見ずなわけだな。
軍医は軽く笑って付け足す。
―“背に炎を抱く、戦場の桜”。
―は?桜、っすか…?
桜といえば、クレスト・フォル・クレスではメジャーな植物だ。春に薄桃色の花を咲かせる木。彼らの国で知らない者は居ないだろう。
しかしそれと兵器とがどんな関係がある?
訝しむ彼を横目に、軍医は話を続ける。
―こいつを見たらその部隊は必ず負ける。
―負ける?
彼は軍医の言葉に違和感を覚えた。
―戦場で負けるということは、全滅ということですか?
軍医は首を横に振る。
―全員死んでたら、証言する奴はいないだろう?私が診た中には実際証言する奴もいるんだ。だから一層、現実味が強い。まあ上層部が口止めしてるのか、あまりはっきりとは分からないが…
(桜?)
結局、彼の話からはソレが何なのか分からなかった。
(植物が?炎を抱く?そんなもんで部隊が負ける?)
それから何度か考えを巡らせたことはあったが、やめた。形の見えないモノを想像するのは容易な事ではないし、疲れる。
ただ、ぼんやりと思ったのは―…
(ソイツは、俺を殺してくれるだろうか―…?)
そしてソイツは今、正にグリモナの目の前に迫ってきている。
彼女は急降下しながら、音階でいう“ラ”の音で、鋭く口笛を吹いた。
―すると、不可解な出来事が起こった。
彼女の進路の邪魔となる枝や葉が、木っ端微塵に砕けたのだ。ほぼ、跡形も無く。
(―な…)
彼は言葉を失う。
常識外れの翼でさえ驚いているというのに、なんだアレは―…
―いや、常識外れというなら、俺だって同じじゃないか…
アレも彼女の何らかの能力なのか?
俺の左目と同じ―…
そんなことを考えている内に、彼女は彼の眼前に音もなく降り立った。
(―やられる…?)
彼は反射的に体を強張らせる。
さっきの枝のように、自分も粉々に砕かれて死ぬのだろうか?だったら本望じゃないか。
―それなのに―…
どうしてオレは恐れている?
しかし、彼女は、
何もしなかった。
否、何もしなかった訳ではない。ただ、その緋色の瞳で彼の瞳を真っ直ぐに見つめていた。
目を反らすことができず、グリモナは彼女の瞳に写し出される自分を凝視させられる。
瞳の中の自分は、血塗れで笑っている。
笑いながら顔が歪み、だんだん溶けてゆく。
やがて骨だけになるが、それでもカタカタと笑って―…
(ヤバい!)
彼は唐突に我に帰り、右目を閉じる。左目だけで見ると、元の少女の顔が眼前にあった。
「―え」
そこで少女は初めて不思議そうな顔をした。
「アナタ、その左目―?隣国にもその技術はあるの…?」
少女は彼の目を見る。今度は幻術をかけるのでなく、探るような瞳で。
純粋に瞳を覗き込まれて、彼は思わずのけ反る。
「…いや、っ、多分…これはそっちの技術だろ?」
「…どういうこと…?」
「オレは2ヶ月程前に左目を失って、移植手術を受けたんだ。…その後人伝てに聞いたんだよ、コレは向こうの兵士のものだって、な」
「……何てこと…遺体から移植したということ…?」
彼女はしどろもどろ説明する彼の言葉を聞いて、僅かに顔を曇らせた。
しかし彼女は怒り狂うでもなく泣き叫ぶでもなく、ただ少し何かを考えるような面持ちで俯いているだけだった。
堪り兼ねて、冷や汗を滴らせながらも彼は聞く。
「―オレを、殺さないのか?」
すると、彼女は目線は戻さず、小さく小さく、消えそうな声で呟いた。
「―殺す、ですって?…そんなこと…」
見ると、彼女は僅かに震えていた。
「できるわけない…」
第3話:涙/teardrop
何てことだ。
戦場で最も恐れられている彼女が、人を殺せない?
グリモナでさえ、何人もの敵国の兵士をその手にかけてきたのに。
なのに彼女は―…
「殺すのが、怖いのか?」
気がつけば、グリモナは目の前に居るのが敵だということも忘れて訊いていた。
彼女は目を伏せたまま、ほんの少し頷く。
「…私はただ、一般市民として、穏やかに生きて、誰にも知られず死ねば良い
―…だけど…」
いくら戦場で恐れられているとはいえ、彼女も年相応(あくまで外見上だが)の少女なのだろう。それに彼女が兵器と成り果ててからは、まともに会話したのはグリモナが初めてだったのかもしれない。
やがて殆ど感情を見せなかった彼女が、小さく嗚咽を漏らし始めた。
(…うわわ…!)
始めは突然のことに慌てふためいたグリモナだったが、やがて手に余る彼女の体をそっと抱き寄せた。
なぜだろう。なぜ自分は敵国の兵士を抱いている?
どういうわけか。彼女も彼の胸に縋って泣いた。
彼女が泣き止んだのは、それから数十分後の日が暮れる頃だった。
桜色の肌が夕日に照らされ、ほんのり赤く染まるのを見て、彼は素直に“美しい”と思う。彼女の瞳や翼のようなぞっとする美しさでなく、純粋な美しさ。
彼と彼女は並んで枯れた倒木に座っている。彼女はさっきの涙はどこへ行ったのやら、平然な顔をしていた。元々瞳が紅いので、充血しているかどうかも分からない。けれども時折鼻を啜る音が、先ほどの出来事を思い出させる。
「―私、」
なんとなく気まずい雰囲気の中、突然、静かな声で彼女が口を開いた。
「―気付いた時には、戦場にいたの…」
ぽつり、ぽつりと話し始める。
「それより前の事は覚えてなくて。ただ、敵の存在と、自分の任務だけを知っていた。だから私は戦ってきた。」
彼は何も言わなかったが、微動だにせずに意識を集中して聞いていた。
「最初のうちは良かったの。クレスト・フォル・クレスの兵士達は私の特異な姿を見るだけで逃げて行った。けれど、すぐに状況は変わった」
彼女の瞳に宿る、悲しみの色。
「アナタ達の国は、とても信心深いのね―…国のため、残してきた者のため、私に命懸けで挑む兵士たちが現れた。―私は疑問を抱いたの。彼らを殺して何になるの?守るべき者すら忘れてしまった私に、彼らを殺す資格があるのか、と―…」
「だから君は、殺さないのか…」
彼も彼女の声のトーンに合わせるように、深く静かな声で語る。
「殺さないのではない。殺せないの」彼女は呟き、そして付け加えた。「あんな――悪魔の石の為に―…」
「石…?」グリモナは訝しむ。「それはあの御身体とかいう鉱石のことか?俺は田舎の出身だからあまり良く知らないのだが…」
「そうだったわね、アナタ達の国では―…」
彼女は自嘲するように、顔を歪めた。
「君達の国でもあの石を有効活用しようとしていたんじゃないのか?」
「有効活用、されたわ。少なくとも上の連中にとっては、ね…」
「それは―…」
まさか、と思った彼の心を、彼女はそのまま言葉にする。
「そう、あの鉱石は既に戦争に利用されている。――私のような兵士を産みだす為に…」
突然知った真実に、彼は言葉を失った。
第4話:名前/denomination
気がつけば、すっかり日は暮れていた。夜の闇が辺りを支配している。今宵は三日月らしく、弱々しい月明かりが二人の輪郭を辛うじて照らしていた。
「…そろそろ戻らなきゃ…」
「…そうだな…」
彼女の告げた真実に驚き、考えを巡らせていた彼だったが、腰を上げて辺りを見回す。
「ねえ…」
彼女は腰を下ろしたまま、彼のマフラーを引っ張った。
「
ん?」
「その…私に出会った事は…」
「ああ、もちろん。誰にも話さない」
彼が微笑むと、彼女は安堵の表情を見せた。
「ありがとう…それと…」
まだ何かあるのか?と思った彼は、黙って次の言葉を待つ。
するとみるみるうちに彼女の顔は赤くなり、肩をすくめ、今にも消え入りそうな声で囁いた。
「アナタ…名前は…」
「ああ、」敵国の兵士にそんなにたやすく名前を教えてもいいものかと思ったが、教えてどうなる訳でもない。それに彼女の懇願するような雰囲気を裏切ることは出来なかった。
―これが彼女の策略であったとしても、構わない。
ただ、彼女の悲しい顔は見たくなかった。
「俺は、グリモナ。グリモナ・フェルブルク。―君は?」
グリモナが聞くと、彼女は少し困惑したような顔をする。
「私は…“A”…」
「A?それが君の名か?」
「…分からない。覚えてないの。けれど皆私をそう呼ぶわ。だから私はAなの」
彼女はとても寂しげな顔をしていた。
(―しまったな…)
彼は困り、考える。
名前とは、誰かがそう呼ぶから決まるものだ。
彼女だって、周りがAと呼ぶから自分はAなのだと認識したのだろう。
だったら、自分が新しく呼べばいいではないか。
…彼女の名を。
「―なあ、君は桜を見たことがあるか?」
彼の突然の問いかけに、彼女はきょとんとした表情を見せる。
「サクラ?それは…何?」
言葉から察するに、彼女は自分が戦場の桜などと呼ばれていることを知らないようだ。
「綺麗な花が咲く木の一種だ。君達の国は確か、文明が進んでいてあまりそういったものは見掛けないんだな」
彼が説明すると、彼女は興味深々といった様子で、
「へえ…見てみたい」
と、薄く笑った。
ああ…やっぱり彼女は、美しい。この笑顔を、守りたい。
例え彼女が敵であっても―…
「俺は君をサクラと呼ぶ。これから、ずっと」
「…え」
「名前は、誰かが呼ぶから決まるものだ。だから俺は、君にサクラという名を与える。だから―」
後ろを見ずに、彼女の手を握る。
「いつか。俺が君の名前を呼んだら、振り向いてくれないか?」
彼がそう言うと、彼女が手を握り返してきた。
「―うん、ありがとう…」
そしてグリモナは彼女―サクラの立ち上がる気配を感じ、やがてサクラは微かな羽音を残して去った。
振向いて月を仰いだ彼の元に残ったのは、一片の紅い羽。
彼はそれを拾い上げ、思う。
隣国では、一体何が起きているのか。
また、彼女に会えるだろうか。
そして。
サクラという名前は、俺と彼女を結んでくれるだろうか…
私は今日、変わった兵士に出会った。―敵国の。
あろうことか、私は彼に思いを全て打ち明け、感情のまま泣いてしまった。
感情をこんなに表に出すのは久しぶりで、よくよく考えたら恥ずかしい話なのだけど―…
だって、私の気持ちを理解してくれたのは彼が初めてだったから…
私は、A。
悪魔の石の加護を受けた、ゼセルドの機密兵士。
けれど私は、サクラでもある。
サクラというのは、一人のAAであり、一人の女。
彼は私を、サクラと呼ぶ。
―また、彼に会えるだろうか。
―サクラという名前は、彼と私を結んでくれるだろうか―…
―何だろう、この気持ち。
これが―…
シアワセ、ということ?
第5話:再会/reunion
「おい…グリモナ、どうしたんだ?左目。」
作戦待機中、同期に突然尋ねられて、グリモナは左目につけた眼帯を手でなぞりながら、
「いや、別に。ちょっと疼くだけ」と答えた。
「そっか、お前一回怪我したんだよな…結構重傷で、一旦本国に帰ったし。
あんなにひどい怪我がよく治ったもんだ。神のお力だな」
信心深い彼は感心する。
彼の左目が彼のものでは無いことを、誰も知らない。
これほどの信仰の国で敵兵の体の一部を移植したとなったら、彼はどんな扱いを受けるだろうか?まずは軍には居られないだろう。
「ま、あんま無理はすんなよ」
「ああ…」
グリモナは同期に生返事を返す。
彼女…サクラに出会って以来、度々左目が疼くことがあった。
共鳴―というやつだろうか?
やはりこの左目は得体が知れない。こんなものを産みだすゼセルドとは、一体どれほどの技術力があるのだろうか…
(やっぱり、もう一度彼女に会わなくては―…)
兵士としてではなく、彼女と同じくあの石の加護を受けた者として、謎を解明する為に。
そして――
彼女の笑顔を、もう一度見る為に。
―このへんか…
その日の夜、グリモナは敵陣の真っ直中の切り立った崖に立っていた。
今宵は満月。
彼の輪郭は青白い燐光にはっきりと映し出されている。
もちろん、常人であったら危険極まりない行為だ。しかし彼は、その左目で敵国の兵士が擬態したり隠れているのを、レントゲンで透過するように見抜く事ができる。
どうやら今は安全なようだ。近くに敵兵が潜伏している様子はない。
グリモナはそっと眼帯を外すと、その瞳で辺りを見渡した。
彼の左目のもう一つの力。それは―千里眼というべきものか。
彼はその左目を用いて、常人の数十倍の視力を発揮できる(透視などと併用は出来ないのだが)。もちろん彼には原理は良く分かっていない。
別に原理を知らなくても不自由は無いしな。―今のところ。
そして彼はその金色の瞳に、桜色の少女を認めた。その距離は、1キロも離れていない。
―サクラ…
どうやら彼女は、また歌を歌っているようだ。
彼女の周りには、ちょうど円状に兵士が倒れていた。―勿論、グリモナの仲間たちだ。
彼女を包囲したつもりなのだろう。しかし仲間であるグリモナが思うのも少し問題だが、そんなことをしたって彼女にとっては何ら意味の無いことだ。
彼は複雑な心境に顔を歪めながらも、踵を返して彼女のもとへ向かった。
最後の兵士が、ドサッと音を立てて頽れた。
この部隊の兵士は、全員気を失った。1週間ほどは目覚めず、後遺症は残るが、命を奪う程のモノではない。
無論、彼女は人を殺す術も知っている。武器を使わなくとも、そういう歌を歌うだけ―でも。
(―やっぱり、無理…)
溜め息。
(分かっている。コレは戦争。敵は、生かしてはおけない。分かってるけど…)
彼女にはどうしても命を奪うことは出来ない。
頭では分かっていても、実行には移せなかった。
(あまり長くも居られないわ…)
さっきから敵兵の無線機からは、「おい、どうした!?」という怒号が漏れてきている。応援部隊もじきに駆け付けるだろう。敵の不意を突かなければ、彼女の方が危うい。
彼女がその場を去ろうと、紅い羽を大きく広げたその時。
「―サクラ!!!」
(―!!)
木々の間の闇から、彼―グリモナの声がした。
こちらからは彼の姿は見えない。しかし、彼には見えているだろう。彼の左目にそういう能力があることを、彼女は知っている。
「―ぁ…」
彼女は、子供が悪戯しているのを見つかったような顔をした。
『オレが呼んだら、振り向いてくれ…』
彼の言葉が脳裏に過る。
けど―
「…見ないで―!!!」
心とは裏腹に、彼女の口を突いて出たのはそんな言葉だった。
「―私を、見ないで…
醜い、から―…」
縋るように、言い放つ。
あれ?何故だろう。
私は、彼に会いたかったのに――
彼に名前を呼んで欲しかったのに――…
けれど、見られたくない。
人智を超えた、背の翼と、魔の歌声を用いて戦う、
まさに兵器そのもの、いやそれ以上に相手に畏怖の念を抱かせる自分の姿を。
「―…」
彼には、言葉が見つからなかった。
しかし、何故だか彼女に近付いてはいけない事は分かった。
俯き、目を閉じる。
(君は、醜くなんか、ないのに―…)
彼女は、グリモナの祖国――クレスト・フォル・クレスの部隊を退けた。
誰一人、殺すことなく。
彼女は、戦場で散るはずの彼らの命を助けたのだ。少なくともグリモナはそう思う。
(―君は―…!!)
サクラは、彼に自分の姿を見られたくないが故か。そっとその場を飛び去る。
微かに、彼女の羽音がした。
「―君は…」
思いが、言葉を紡ぐ。
「オレの瞳に映る君は、紛れもなく―…」
サクラは、遠ざかる森の木々の合間から、彼の呟く声を聞いた気がした。
―天使なのに、と。
第6話:光明/torch
それから1週間。
グリモナはその晩、野営のテントで寝袋に包まれ、眠れずに仄暗い天井を見つめていた。
オレは―
まだ、死にたくないんだろうか。
真実を見透かす瞳でも、自分の心までは分からない。
けれど、もし死ぬのなら―
彼女の顔が、思い浮かんだ。
しかし彼は、即座にその考えを否定する。
――人殺しを恐れる彼女にオレを殺させるのか?
彼が取り留めも無い考えを終わらせて眠ろうとしたその時。
―ドサ。
そんなに遠くは無い場所から、誰かの倒れる音がした。
グリモナの全身に緊張が走る。
(敵…!?)
音を立てずに身を起こし、左目で音のした方向をテントの壁越しに“凝視”する。
思わずあっと声を出しそうになった。
野営をしている開けた場所と、森の境目。
夜の闇に紛れて現れたのは―
(サクラ…!)
彼女が、彼の左目の視界の先に佇んでいた。彼女の両脇には、見張りの兵士が倒れている。
『グリモナ…』
彼女の唇が動く。
『お願い、“見えて”いたら…外に来て…』
彼は一瞬躊躇った。
左目が疼く。
体は彼女の元へ行きたがっている。
けれど―
自分は、彼女を傷つけないだろうか…それだけが怖かった。
彼女は彼が見ていることが分かって居るかのように、こちらをじっと見て居る。
彼女も共鳴しているのだろうか、俺の左目に。
(―彼女は、望んでここに来たんだ―…)
彼は腹を括った。
サクラは、俺に何か伝えたいことがある―とても、重要なことだ。
寝袋から這い出し、仲間の兵士に見つからぬよう足音を立てずにテントから出る。一度小枝を踏んでパキッと音を立ててしまったが、誰も気付かずにすやすやと寝息を立てている。最近徹夜続きだったとはいえ、呑気な奴等だ。
外に出たグリモナを、サクラは柔らかい笑顔で迎える。初めて出会ったときと同じ、笑顔。
「ごめんなさい…彼らには少し眠ってもらったけど、朝になれば起きるから…
ついて来て」
彼女は背を向けると、倒れている兵士の間を抜け足早に森の奥へと消えた。
彼は大きく深呼吸してから、小走りで彼女の後を追った。
しばらく2人は、グリモナがサクラを追う形で、無言で木々を縫って歩いた。
足場は悪いが、2人にとってそれほど問題でもない。
「―知りたい?」
「え…?」
10分ほど歩いたところで唐突にサクラが言葉を発し、彼は驚いて立ち止まる。
彼女も立ち止まり、彼を振り返った。
「私の翼と、力のこと。あなたの…左目のこと。私の国のこと。」
彼は彼女の目線を受け止め、頷く。
「俺は、知りたい。けど、戦いの為じゃない。俺の国の為じゃない。
ただ、真実を知りたい。知ってどうなるかは分からないが、このままじゃ死ねない。そんな気がする。それに、」
彼は心の底から、本音を吐きだす。
「君の事を、もっと知りたいから―」
彼女はしばしあっけにとられていた。まさか自分のことを彼が考えていたなんて。
しかしその顔はすぐに微笑みに変わった。
「…ありがとう」
第7話:星空/starry heaven
さらに数分後。二人は木の上にいた。
それはグリモナが1週間前にサクラを見つけるために上った崖に、たった1本だけある、巨大な大木。
それは冬の寒さに枯れ、寒々しい枝を夜空に晒していた。
空には無数の星が瞬いている。新月なのか、月は見当たらない。
「私の国―ゼセルドは、この戦争が始まる前からあの鉱石のエネルギーに着目していたの。エネルギーというのが何なのか、私はよく分からないけど…
戦争の20年ほど前はゼセルドもクレスト・フォル・クレスも問わず、有能な研究者を集って石について研究していたらしいわ。もちろん、―あなたの前で言うのもなんだけど、クレスト・フォル・クレスの技術はこっちに比べたら遅れているから、研究者はごく少数だったけど…」
サクラは枝に腰掛け、足をぶらぶらさせながら語る。
その仕草は、見た目の年相応、いやそれ以上に幼く見える。
しかグリモナは、彼女の次の言葉で、彼女の壮絶な過去を知った。
「私も本当はどこかの辺境の村で生まれたみたい。といっても覚えてないんだけど。
けど戦争が始まってから研究所に連れて行かれて、何かの実験を受けて…そして気づいたときには戦場に居たの。
記憶はなかったけど、戦い方は知っていた。けれどそれと同時に、誰かを殺すことが恐ろしくてたまらなかった…」
彼女の体が小さく震えていることに、彼は気づく。
思わず手を伸ばそうとするが、彼女は気丈に「大丈夫」と言った。
「ごめんなさい、この話は関係なかったわね…それよりも、あの石を用いた実験のことだけど―」
そういった彼女は目を閉じ、彼が瞬きをする一瞬に、背に巨大な翼を広げた。
「さっきも言ったけど、私は実験の内容についてはよく分からない。けれど自分の能力ならもちろん知っているわ。―あなたの左目のことも。」
彼は思わず彼女の顔を見た。
鼓動が高鳴る。
―求めていた答えが、ここに…
サクラは彼の懇願するような瞳を柔らかい表情で受け止めた。
全てを受け入れる聖母のように。
「私の能力。それは“空気の振動”、すなわち“音”を操ること。この翼は、その実験で偶然生まれた副産物よ。
私は音を操って相手を催眠状態に陥れることが出来る。それだけでなく、空気の振動を使って物質を破壊することもできる。
―その気になれば、AAもね。」
そう言ってサクラは自虐的な笑みを浮かべた。
「けれどあなたには催眠が通じなかったでしょう?それがあなたの左目の能力よ。分かっているとは思うけど」
グリモナは、思わず息を呑んだ。
「私の催眠は聴覚を介して、ほとんどは視覚に現れるの。もちろん音は体に直接作用してはいるんだけど、視覚に作用しなければ効果はないのよ。面倒だけど。
あなたの左目は、催眠を見破り、そして物質を透過して見る事が出来る。さらに数キロ先まで見渡せる千里眼の能力がある。…そうでしょ?」
彼は冷や汗を掻きながら、「ああ」と頷いた。
「訓練すれば、常人が目で追えないものを追ったり、視野が広がったり。兎角“視覚”に関しては、はるかに常人を卓越したことが出来るようになるはずよ。
その瞳の元の持ち主は、私の知り合いだったから―」
目の前が真っ暗になったような気がした。
この目の持ち主が、彼女の知り合いだって―?
だったら彼女は、俺を恨んでいるんじゃないか…!?
けれど彼女はグリモナの不安を裏切り、首を振って微笑する。
「彼は亡くなったと聞いていたけど…ちゃんと生きていた。あなたと共に。
それは、とても嬉しいこと―そう思う。」
彼女は翼をたたみ、彼のすぐ隣に腰を下ろした。
グリモナは、夜空を仰いだ。心の中で、彼女の言葉を反芻しながら。
―それは、とても嬉しいこと―
(―彼女は、俺を恨んでいなかった)
それは彼にとって、何よりの救いであった。
彼女を傷つけることを恐れる彼にとっては。
相変わらず星たちは、我こそは、とその身を輝かせている。
彼女の存在は、そんな星たちとは違い、控え目で。
でも、無数の星よりもキレイだ。
グリモナが見上げている夜空を、サクラも彼に倣って見上げ、ぽつりと呟いた。
「空は、キレイね…私たちAAと違って。」
グリモナは空を見たまま、黙って彼女の次の言葉を待つ。
「でもあなたの心も、キレイ。今は底の見えない深い沼のようだけど、光が差し込めばきっと澄んだ湖だとわかるはずよ」
「―そんなこと―…」
即座に否定しようとした彼の口を、サクラがそっと塞ぐ。
「私には分かる。アナタは今まで見た他のAAとは違う。だって私を…」
彼女は口ごもってしまった。
「…?」
空から目線を彼女に移すと、彼女もその緋の瞳に彼の姿を映した。
「天使、だなんて…初めて言われたわ…」
「き、聞こえてたのか!?」
こんどはグリモナが恥らう番だった。なんて耳だ。流石だな…
「…私は、自分が人に不幸しかもたらさないと思ってた。だから、戦場でしか生切られなかったの。敵を退けることで、私にも価値が生まれれば良かった。
でも今は違うの―…」
サクラの薄桃色の瞼が、ゆっくりと緋色の瞳を隠す。
「アナタもきっと辛い過去があるのね。その左目――」
指が、そっとグリモナの顔を撫でる。
「アナタが私利私欲のために奪ったものではないはず。そうだとしたら、アナタはここにはいないでしょう?こんな所で、一介の兵士として、命を危険に晒していないはず…」
「――!」
グリモナは息を呑んだ。
「今は―…私は、ただ…」
彼女はその体を、そっと彼の胸に預ける。
柔らかな温もりが伝わってくる。
「アナタの“濁った湖”を照らす…光になりたい…」
しばらく二人はそのまま、星々の瞬きを眺めた。
寒さで凍えた体に、お互いの温もりが心地よかった。
「―俺、大切な人を守れなかったんだ…」
夜が明けようと、東の空が白んで来た頃。
グリモナは、彼女に語りだした。
「戦争行けばさ、みんな守れると思ってた。国も、村も、家族も、恋人も。けど俺はどこの誰だか知らない兵士たちをちまちま殺すだけで、何にもならなかったんだ…」
「……」
「だから、この左目を手に入れた気持ちは正直複雑だった。俺が選んだんじゃなく、勝手に移植されたんだが。
この左目があれば、守るべきものを守れるかもしれない。けど――
もう守るべきものは消えた。恋人は、死んだんだ…」
「……!」
彼女が息を呑む気配が伝わって来る。
彼は構わず続けた。
「俺は、死にたいと思っていた。けれど、心のどこかには死を恐れる気持ちもあった。どっちの気持ちが正しいのか俺は分からない。ただ、確かなのは、」
「……?」
「君なら、俺を殺してくれるんじゃないか。初めて君を見た時、そう思った…」
「…!!っ…」
ビクン、と彼女の体が強張る。
「けど。君の涙は…初めて会った時の君の涙は、俺のそんな濁った考えを消し去った。
彼女は涙しながら戦場で生きているじゃないか。大嫌いな戦場に――それに、」
一度だけ。彼女の頭を軽く撫でる。
「世界にはまだ、こんなに美しいものがあったんだ―…
そう、思った」
彼女が体を起こし、彼の顔を見た。
真紅のルビーのような瞳に彼の姿を湛える。
「私は、美しくなんか―…」
そう言いかけたが、サクラは目を閉じて首を振った。
「ううん、貴方がそう言ってくれて、とても嬉しい。私にも、生きる意味が出来た…」
グリモナも珍しく微笑み、片手で彼女を抱き寄せる。
「俺も、生きようと思う。君の命が続く限り、生きよう。
この戦場を生き抜いてみせる。約束するよ。」
そして彼は気づく。
「死にたい」などと思っていたのは、所詮俺のエゴだったんだ。
彼の恋人―アリアは、別れ際に言っていた。
生きて、生きて。必ず生きて。何があっても―
俺はカッコつけて死のうと思っていたんだな。
けれどどこかで死にきれなかったのはきっと―
きっと、彼女の言葉が心のどこかで引っかかっていたんだ…
俺は、生きる。
アリアの為にも。
―サクラの為にも―
アリアも、きっとそれを望んでいるはずだ。
そう、信じたい。
生きて生きて生き抜いて、その先はどうなるんだろう?
分からない。
分からなくていい。
今はただ、彼女と共に生きていたい。
第8話:疑惑/dubiety
「朝日だ…」
グリモナは小さく呟いた。
遥か遠く。白く霞んだ山々の際から、黄金色の朝日が顔を出し、二人を同じ色に染める。
「またしばらく、離れ離れね…」
「ああ、でも…」
彼の気持ちは、揺るがなかった。
「もう、大丈夫だ。俺も、君も。約束、しただろ?生きるって。」
「…うん、そうよね」
サクラの表情から不安の色が消える。
そう、俺達は大丈夫。
俺は、もう死にたいと思わない。
それは恐れではなく、揺るぎない信念。
その後二人は別れを告げ、グリモナは野営地へと戻っていった。
(…そういえば、倒れてた見張りは大丈夫か…?サクラは、朝になれば起きる、と言っていたが…)
彼が深く生い茂る木々の枝をくぐり、野営地へと出ると、案の定と言うべきか、兵士達は慌しく動き回っていた。
その内の一人が、その様子を傍観しているグリモナに気づき、驚いて叫ぶ。
「グリモナ!!お前、どこ行ってたんだ!!」
すると兵士達の目が全てこちらに集まり、口々に叫ぶ。
「おい、グリモナが生きてたぞ!!しかも無傷だ!!(多分)」
「先輩!!心配したんすよ!!」
「何してんだ、早く隊長のところに行かないか!!」
「てっきり捕虜になったかと。」
「ああもう、馬鹿野郎!!余計な手間掛けさせやがって!!」
どうやら彼らの話を総括するに、朝目覚めた兵士が見張りが倒れていることに気づき報告に行ったところ、グリモナが行方不明になっており、敵兵に捕らえられたものと思い捜索していたのだという。
ちなみに見張りの兵士は、「何故か眠くなって寝てしまった」と言っており、隊長にこっぴどく怒られていた。今は処罰として腕立て500回(本当にできるのか?)をしている。さすがサクラだ。
(う~ん…さすがに今回は少しヤバいかな…)
グリモナも彼らと同じ処罰を覚悟しながらも、隊長のテントに向かった。
「だからうちの兵士が一人行方不明なんだ!!あ!?そんなこたぁどうでもいい!!とにかく捜索隊を組むのに少し人を貸してくれ!!」
テントの中では、隊長の怒号が響き渡っていた。
どうやら他の隊に応援を求めているらしい。
グリモナは今更事の重大さを実感しながらも、恐る恐る彼に声を掛ける。
「た、隊長…?」
「うるさい!!今取り込んでいるんだゴルァ!!後にしろ!!で、どうなんだ!?いつになる!?」
「…。隊長!!」
「あ!?」
グリモナに耳元で叫ばれ、隊長は不機嫌そうに振り向き、そこで初めてグリモナの存在を確認する。
「!!グリモナ!!馬鹿野郎!!」
無事を確認した隊長が真っ先にお見舞いしたのは、強烈な往復ビンタだった。
「い、いて…」
数分後。興奮が収まった隊長から解放されたグリモナの頬は、両方とも真っ赤に腫れ上がっていた。
「いや、ちょっとやりすぎたか。すまんな。
しかしお前のやったことはそれだけで済まされることではないぞ。本来はな。」
「はい…すみませんでした…」
「で、どこに行っていたんだ?」
隊長の質問にグリモナは一瞬口ごもりそうになるが、野営地に戻ってきてから密かに考えていた言い訳が、淀みなく口から出た。
とはいっても、それは
「朝方、ちょっとトイレに行ってただけです。そしたら道に迷ってしまって」
といった単純なものだったが。
「あれほど単独行動はするなと口をすっぱくして言っただろうがゴルァ!!」
隊長が再び青筋を浮き出させる。
やばい。
何で単独行動をしたかとか、倒れている見張りの兵士を見なかったのかとか、どうして道に迷うほど遠くに行ったんだとか、そういうことを聞かれたら非常に不味い。頭の回る彼とて完璧に弁明する自信は無かった。
そして、
「そもそも…」
と、隊長による追求が今にも始まらんとしたその時。
「まあまあ。ギコ隊長。そんなに怒りなさんな」
グリモナの後ろから誰かがテントに入ってきて、穏やかに隊長をなだめる。
グリモナは、その声に聞き覚えがあった。
「こいつは向こう見ずな馬鹿だから仕方ないんだよ。でもそこがこいつのいいところだろ?」
そういってグリモナの方に手を置いたのは。
「…先生!?」
それは、かつて彼の左目を手術した軍医、茶色の長毛を持つAAのフサインだった。
「久しぶりだな、グリモナ。どうだ?調子は」
怒る隊長をよそに、彼はゆったりとした動作でグリモナの前に歩み出る。
「は、はあ…」
グリモナは予想外の人物の登場に、すっかり肝を抜かれた。
「返答がはっきりしないのは相変わらずだな」
そういって彼は微笑み、グリモナの頭をぐしゃぐしゃと撫でる。
「先生は、また軍医としてこちらに?」
「ああ、そんなとこだ。全く、年寄りをこき使いやがって」
言いつつもフサインは、嫌そうな顔を見せない。むしろ嬉しそうにも見える。
(そうか、先生ももう50近いのか…それにしては若々しいけど)
「ん?なんだその物言いたげな目は?」
フサインがグリモナの晴れ上がった頬をつねる。
気づいたらグリモナはフサインの顔を凝視していたようだ。
「い、痛ぇ…」
そんな二人のやり取りに、ギコ隊長もすっかり毒気を抜かれたようで、無線を持ったままぽかんと二人を見つめている。
フサインはグリモナの頬をつねりながら、そんなギコ隊長をちらっと横目で見た。
「ギコ隊長。すまんな、久々の再会だ。こいつをちょっと借りてもいいか?」
「…ん?あ、ああ…お前さんの頼みなら仕方ないな。好きなだけ借りてくれ」
ギコ隊長でさえもどうやらフサインには頭が上がらないところがあるらしく、素直にグリモナを引き渡す。
「ありがとよ」
フサインはグリモナに向き直り、出口に向かって歩き出す。
「じゃあ、第7テントで待ってるからな。体、洗って来い。お前――」
彼がすれ違い様に言葉を放つ。
「臭う、ぞ。」
グリモナは驚き、バッと振り返った。
フサインは何事もなかったかのように、「じゃあな、隊長」と右手を上げてテントを出て行く。
体の芯が凍りつくような感覚。
普段であったら、ただ単にグリモナの体が汗臭いとか、そういう冗談で済んだだろう。
しかし、フサインの顔は全く笑っていなかった。
『臭う、ぞ。』
脳に直接響くような、冷たい声が蘇る。
(―先生、貴方は一体――?)
グリモナは、嫌な予感が湧き出てくるのを止めることが出来なかった。
第9話:真実/veracity
「よお、グリモナ。」
30分後。第7テントに入ってきたグリモナを、フサインは簡素な折りたたみ式の椅子に座って迎えた。
彼は休む間もなく手を動かしている。
「悪いな。こっちから呼んでおいて何だが、ちょっと手が離せないんだ。そこらへんに適当に座ってくれ」
言われてグリモナは、手近にあった折りたたみ椅子に座る。
テントは小さく、薄暗い。これまた簡素で低いテーブルの上には、なにかの資料と思わしき紙束がうず高く積まれている。
「先生、まだ研究のほうは続けているんですか?軍医の仕事と並行して。」
「ん?ああ、まあな。」
フサインは、グリモナのほうを見ずに答えた。
「遺伝子学の研究、でしたっけ」
「そうだ。よく覚えているな。」
実を言うと、彼は隣国に比べれば医学が進んでいないクレスト・フォル・クレスにて、唯一隣国と同等の知識を持っているとも謳われるほどの名医だ。
しかし彼はそれほど自分の知識をひけらかしたがらない。
それ故、このような小さな部隊の専属の軍医として働いているのだ。
「先生は、元気でしたか?」
グリモナは、仕事を続けるフサインに構わず質問した。
久しぶりに出会った嬉しさが、彼の質問を留めることが出来なかった。
「そうだな。ま、ちょっとハゲてきたくらいかな」
「それは奥さんに刈られたからじゃないですか?」
「いや。昔は刈られてもちゃんと生えたんだよ。」
フサインが苦笑いしながら話す。
それを見てグリモナにも自然と笑顔が浮かんだ。
「さて。仕事ばかりしていても何だしな。ちょっとひと段落つけるか…」
フサインはポケットからステープラーを取り出し、紙束を綴じて封筒に入れた。
「それでだ、グリモナ…」
フサインの瞳が、テーブル越しにグリモナを見据える。
「お前、昨日どこへ行っていたんだ?」
グリモナの額には、冷や汗が滲み出た。
彼に、嘘が通用するようには思えない。
彼の瞳は、グリモナの心の奥底までもを見透かしているようだった。
しかし、本当の事は言えない。
例え、それがグリモナの信頼する名医であっても。
「隠さなくて