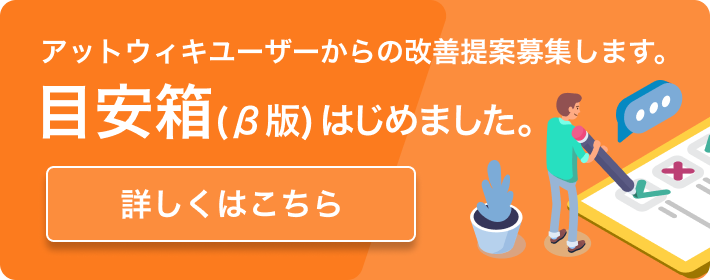芸術の民は詩歌藩国の民です。
日常生活を送る傍らで芸術を愛し、創造する。
音楽に限らず芸術全般に秀でた人々です。
日常生活を送る傍らで芸術を愛し、創造する。
音楽に限らず芸術全般に秀でた人々です。
L:芸術の民 = {
t:名称 = 芸術の民(人)
t:要点 = 詩人,エレキギター,ギリシア風
t:周辺環境 = この世の終わり
t:評価 = 体格2,筋力2,耐久力2,外見4,敏捷2,器用3,感覚3,知識4,幸運1
t:特殊 = {
*芸術の民の人カテゴリ = 高位人アイドレスとして扱う。
*芸術の民は一般行為判定を伴うイベントに出るたびに食料2万tを消費する。
*芸術の民は芸術に関して+8修正を得る。
}
t:→次のアイドレス = ゴシックメード(職業),絨毯職人(職業),ゴシックバード(職業),ゴシックナイト(職業)
}
三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三

三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三
『Art with life.』
芸術とは、なんらかの作品や表現などによって、自身と相手が相互に影響し合うことで、互いの心に変化を与えることを指す。
それはつまり、一人では芸術は完成しないことを示している。
それはつまり、一人では芸術は完成しないことを示している。
どれほど優れた芸術家であっても、作品を見る者がいなければ、それは芸術たりえない。
逆をいえば、作品を生みだす者、鑑賞する者が一人づついるのであれば、生んだ者、表現者は芸術家たりえると言える。
一方で、現実には本質とかけ離れた一面も、ままある。
絵画、彫刻、詩歌、建築、歌劇。
芸術と呼ばれるものには様々なカタチがある。
それらすべてを総称して、芸術と呼ぶ。
絵画、彫刻、詩歌、建築、歌劇。
芸術と呼ばれるものには様々なカタチがある。
それらすべてを総称して、芸術と呼ぶ。
芸術というものには、優劣がつけられることがある。
それは日々努力を続け、高みを目指す場合には必然と言っても良いほどに当たり前のことだ。
あらゆるものは、競争の中でこそたくましく育つ。
それは日々努力を続け、高みを目指す場合には必然と言っても良いほどに当たり前のことだ。
あらゆるものは、競争の中でこそたくましく育つ。
だが、はたしてそれは正しく芸術と言えるのだろうか?
もしくは、既存のカタチとは異なる道もありうるのではないか?
そも我々が芸術と呼ぶものに、貨幣的価値など必要ないのではないか?
もしくは、既存のカタチとは異なる道もありうるのではないか?
そも我々が芸術と呼ぶものに、貨幣的価値など必要ないのではないか?
ニューワールド中からあらゆる芸術が集う国、詩歌藩国のなかで、そんな考え方をする一派が台頭してきたのは、つい最近のことだ。
みずからを芸術の民と名乗る、のちの歴史に<新芸術派>と呼ばれることになる芸術家たちの総称である。
彼らの主張は、とてもとても単純で明快なものであった。
すなわち「すべては芸術である」
すなわち「すべては芸術である」
/*/
『Art with life.』
芸術は生活とともにある、と彼らはいう。
たとえば、一組の若い男女がいたとする。
青年は少女に好意を持って接するが、彼女はまったく気づかない。
二人はとても仲が良いが、ただそれだけだった。
そこで彼は、三日三晩かけて恋文をしたためた。便箋にぎっしりと愛の言葉が詰め込まれた、力作である。
その手紙はきっと少女の胸を打つだろう。
その恋は、言葉は、便箋は。まぎれもなく芸術である。
二人はとても仲が良いが、ただそれだけだった。
そこで彼は、三日三晩かけて恋文をしたためた。便箋にぎっしりと愛の言葉が詰め込まれた、力作である。
その手紙はきっと少女の胸を打つだろう。
その恋は、言葉は、便箋は。まぎれもなく芸術である。
たとえば、閉店間際の深夜のバーで、客がひとり、くだを巻いている。
仕事でくたびれきった男は、まるで終わらぬ夜を歩いているようだと、愚痴をこぼす。
そう言った男に、バーテンダーは注文にないカクテルを差し出した。
黄色く色づいた酒のなかに、真っ赤なサクランボがひとつだけ浮いている。
それは夜明けというカクテルだと、バーテンダーが説明した。 どんな夜にも終わりはきますよ、と。
男が夜明けの酒をくちに運ぶと、それはとてもきつい酒の味がした。
明日を歩むその厳しさを、教えてくれているような気がした。
仕事でくたびれきった男は、まるで終わらぬ夜を歩いているようだと、愚痴をこぼす。
そう言った男に、バーテンダーは注文にないカクテルを差し出した。
黄色く色づいた酒のなかに、真っ赤なサクランボがひとつだけ浮いている。
それは夜明けというカクテルだと、バーテンダーが説明した。 どんな夜にも終わりはきますよ、と。
男が夜明けの酒をくちに運ぶと、それはとてもきつい酒の味がした。
明日を歩むその厳しさを、教えてくれているような気がした。
その言葉と、カクテルと、気遣いは、まぎれもなく芸術である。
男はすこしだけ、胸を張って明日を進むだろう。
男はすこしだけ、胸を張って明日を進むだろう。
家で、母の帰りを待つ娘がいる。
まだ幼い少女は、色とりどりのクレヨンを手に取って、画用紙へと塗り広げていく。
彼女は自分がいちばん好きなものを書き上げた。 それは、母親の笑顔であった。
少女が母親にその傑作を手渡したとき、それは母親にとって生涯の宝物となるだろう。
少女は間違いなく、偉大な芸術家である。
まだ幼い少女は、色とりどりのクレヨンを手に取って、画用紙へと塗り広げていく。
彼女は自分がいちばん好きなものを書き上げた。 それは、母親の笑顔であった。
少女が母親にその傑作を手渡したとき、それは母親にとって生涯の宝物となるだろう。
少女は間違いなく、偉大な芸術家である。
それが芸術の民にとっての芸術であり、ある意味では誇りとも呼べるもの。
芸術の全肯定がそこにあった。
芸術の全肯定がそこにあった。
人はすべからく芸術である。
そして人生とは、芸術の連続である。
そして人生とは、芸術の連続である。
芸術を極めようと努力する者がいる。それは良いことだ。
しかし、それだけが芸術ではないはずだ。
子供が、大人が、老人が、男が、女が、犬が、猫が、北国が、南国が、東国が、西国が、はてない国が、森国が、生きとし生けるものすべては芸術であり、創造し、鑑賞することも同じく尊ぶべきことだと、彼らは言った。
しかし、それだけが芸術ではないはずだ。
子供が、大人が、老人が、男が、女が、犬が、猫が、北国が、南国が、東国が、西国が、はてない国が、森国が、生きとし生けるものすべては芸術であり、創造し、鑑賞することも同じく尊ぶべきことだと、彼らは言った。
それは、ある人にとっては当たり前のことかもしれない。
だが、それを当たり前のこととは思わない者もいるかもしれない。
彼らは声を大にして叫んだ。
だが、それを当たり前のこととは思わない者もいるかもしれない。
彼らは声を大にして叫んだ。
芸術の民風に言えば、それもまた芸術である、と言えるのかもしれない。
/*/
芸術の民とはいうが、基本的な部分はこれまで詩歌藩国を支えてきた国民となんら変わらない。
当然のことだが見た目にはまったく変わらず、ひとつだけ違うのは、芸術というものをとても身近に置いて生活しているという点だ。
これまで詩歌藩には音楽院が象徴として存在したが、学ぶには厳しい選定試験があり、悪い言い方をすれば、その他大勢を切り捨てる形で質を向上させてきた。
<新芸術派>と呼ばれる人々が、これを変えられないかと唱えはじめたのがきっかけだった。
国をあげての産業育成もあり、この思想は一気に広がりを見せた。
<新芸術派>と呼ばれる人々が、これを変えられないかと唱えはじめたのがきっかけだった。
国をあげての産業育成もあり、この思想は一気に広がりを見せた。
すべての人々に音楽を、そして芸術のすばらしさを。
そういった思いが行動へと結びついた。
そういった思いが行動へと結びついた。
現在の詩歌藩国では、国のどこにいたとしても音楽が聞こえてくる。
それは音楽家や吟遊詩人たちが演奏しているものでもあったが、国中の人々が、仕事の合間に楽器を演奏していることが大きい。
芸術振興による効果である部分ももちろんあったが、それ以上に彼ら芸術の民による普及活動の成果だった。
もともと音楽院や美術院の出身者である彼らは、乞われれば誰にでも自身の技術を教え広めた。
すべての人々に音楽を、そして芸術のすばらしさを。
その活動はいつしか国中に広まり、親から子へ、子から孫へと伝えられ、いつしか国の誰もが楽器を扱い、絵筆を握るようになった。
それは音楽家や吟遊詩人たちが演奏しているものでもあったが、国中の人々が、仕事の合間に楽器を演奏していることが大きい。
芸術振興による効果である部分ももちろんあったが、それ以上に彼ら芸術の民による普及活動の成果だった。
もともと音楽院や美術院の出身者である彼らは、乞われれば誰にでも自身の技術を教え広めた。
すべての人々に音楽を、そして芸術のすばらしさを。
その活動はいつしか国中に広まり、親から子へ、子から孫へと伝えられ、いつしか国の誰もが楽器を扱い、絵筆を握るようになった。
それはまるで、国というひとつの楽器が奏でるオーケストラのようだった。
人々が紡ぎ出す様々な旋律が、風に乗って吹き抜けていく。
もしかすると、詩歌藩国という巨大な楽器を創り上げることこそが、芸術の民が最初に手がけた芸術作品なのかもしれない。
人々が紡ぎ出す様々な旋律が、風に乗って吹き抜けていく。
もしかすると、詩歌藩国という巨大な楽器を創り上げることこそが、芸術の民が最初に手がけた芸術作品なのかもしれない。
/*/
詩歌藩国の冬は長い。
わんわん帝國の最南端に位置するこの国は、ニューワールドのなかでも極寒の地として知られている。
わんわん帝國の最南端に位置するこの国は、ニューワールドのなかでも極寒の地として知られている。
都市部は地熱利用によってある程度の積雪には対応できるものの、真冬になれば地上は数メートル単位での積雪によって、屋外活動が著しく制限される。
地下通路などの利用で外出には支障がないものの、過去からの慣習で、国民の多くは長い冬のほとんどを自宅の中ですごしている。
地下通路などの利用で外出には支障がないものの、過去からの慣習で、国民の多くは長い冬のほとんどを自宅の中ですごしている。
多量の食料を備蓄し、風邪を引かぬよう暖炉で部屋を暖める。
刺繍や機織りなど、外に出られなくともできることはたくさんある。
この頃、子供たちは老人たちの昔語りを日々の楽しみとして育つ。
もちろん詩や歌を教え込まれることもある。
コンピュータ技術や電化製品など、世界中からさまざまなものが国内へとやってきたが、それでもこの国は昔からあまり変わっていない。
刺繍や機織りなど、外に出られなくともできることはたくさんある。
この頃、子供たちは老人たちの昔語りを日々の楽しみとして育つ。
もちろん詩や歌を教え込まれることもある。
コンピュータ技術や電化製品など、世界中からさまざまなものが国内へとやってきたが、それでもこの国は昔からあまり変わっていない。
そんな中、芸術の民は冬のあいだどうしているのか。
もちろん決まっている。 芸術のために全力を注いでいるのだ。
もちろん決まっている。 芸術のために全力を注いでいるのだ。
長い冬期休暇の中で、彼らはキャンバスに向かい、詩を書き、金細工を彫り、歌を作ってすごす。
気兼ねなく創作に没頭できるためか、毎年、冬明けになると多くの芸術家が作品を発表する。
それはまるで春に咲く花のように、多くの芸術たちが一斉に芽吹き出すのだ。
気兼ねなく創作に没頭できるためか、毎年、冬明けになると多くの芸術家が作品を発表する。
それはまるで春に咲く花のように、多くの芸術たちが一斉に芽吹き出すのだ。
また、作品制作とは別に、冬季期間の芸術の民にはある種の傾向がある。
それは、冬の間、彼らの服装がとても前衛的になるということだ。
それは、冬の間、彼らの服装がとても前衛的になるということだ。
本来、詩歌藩国において服装とは凍死しないための防寒具という側面が大きい。
なによりもまず求められるのは寒さを防ぐ機能性であり、見た目などについては二の次に考えられることが多かった。
しかし昨今、他国との聯合などによって文化が流入し、美意識の向上などがはかられたためか、服装のおしゃれについて意識する者が増えていた。
高位北国人の要点からもわかるように、薄着の文化は確実に根付いてきていたのだ。
なによりもまず求められるのは寒さを防ぐ機能性であり、見た目などについては二の次に考えられることが多かった。
しかし昨今、他国との聯合などによって文化が流入し、美意識の向上などがはかられたためか、服装のおしゃれについて意識する者が増えていた。
高位北国人の要点からもわかるように、薄着の文化は確実に根付いてきていたのだ。
もちろん屋外では昔からある厚手の服を着るのが一般的だが、暖かい屋内に長くいる冬の間は、さまざまなオシャレを楽しむ者が若者を中心に増加していた。
なかでも人気なのは、東国にあるゆったりとした和装や、南国の布地が少ない袖なし服などである。
普段は着ることのできない服を身につけるという行為が、ある種の非日常を感じさせるのかもしれない。
そして、この非日常という部分が芸術家にとってはとても重要な意味をもつことがある。
人の姿形は、その人となりを表しているという。
であれば、服を変えることは人が変わるということでもある。
人の姿形は、その人となりを表しているという。
であれば、服を変えることは人が変わるということでもある。
芸術は心を表現するものだという。
服を変えることで自身に変化を与えることは、新たな作品を生み出すことにもつながると考えたのだ。
服を変えることで自身に変化を与えることは、新たな作品を生み出すことにもつながると考えたのだ。
画家のオズワルド・アマデウスもまた服装に気を使った一人だ。
ある雑誌のインタビューで彼は、冬のあいだはよく東国の紋付き袴を愛用していると答えている。
黒を基調としたその装いを身につけると、身が引き締まるように感じるという。
黒を基調としたその装いを身につけると、身が引き締まるように感じるという。

三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三
『紡がれるは人生、繋がるは縁。それもまた芸術』
詩歌藩国は芸術の国であるが、最も有名なのは音楽である。
始まりは吟遊詩人。詩歌藩がその色をNWに示した最初の職業。
念願の音楽院。その教育力は想像をはるかに超える評価であった。
そして音楽系最終到達地点、音楽家。この国は音楽だけで絶技に匹敵する力を得た。
始まりは吟遊詩人。詩歌藩がその色をNWに示した最初の職業。
念願の音楽院。その教育力は想像をはるかに超える評価であった。
そして音楽系最終到達地点、音楽家。この国は音楽だけで絶技に匹敵する力を得た。
ではほかの芸術は?
絵画、彫刻、建築、工芸など数え上げればきりがない。
そもそもこの国は大洋にぽつんと浮かぶ島国。
必要な物は自分達で創り、伝え、改良を加える。
結果、独自の文化が発達を続けた。
革新的な技術の発達は望めないが、着実に文化が洗練を重ねる。
絵画、彫刻、建築、工芸など数え上げればきりがない。
そもそもこの国は大洋にぽつんと浮かぶ島国。
必要な物は自分達で創り、伝え、改良を加える。
結果、独自の文化が発達を続けた。
革新的な技術の発達は望めないが、着実に文化が洗練を重ねる。
その様は、冬に耐える芽であった。
いつか来る春に備え、日々力を蓄え、そして厚い雪を破る。
その一瞬がついに来た。
いつか来る春に備え、日々力を蓄え、そして厚い雪を破る。
その一瞬がついに来た。
作品達はNWで目が飛び出る程の値段で取引されている。
帝国の精強、星鋼京の博物館には詩歌の名品が集められた。
皇帝陛下の御髪に輝く黄金の髪飾りは詩歌、星鋼京、後ほねっこ男爵領の職人たちが生んだ傑作である。
帝国貴族の間で詩歌の宝飾を身に付けぬ者はいないであろう。
帝国の精強、星鋼京の博物館には詩歌の名品が集められた。
皇帝陛下の御髪に輝く黄金の髪飾りは詩歌、星鋼京、後ほねっこ男爵領の職人たちが生んだ傑作である。
帝国貴族の間で詩歌の宝飾を身に付けぬ者はいないであろう。
そして、この国は芸術家の研鑽に報いた。
それが、産業育成である。
それが、産業育成である。
産業育成においてまず中心に据えられたのは絵画である。
イリューシア美術院の設立。
長く絵筆を執る芸術家を招き、教育の担い手という生き方を示した。
若き芸術家の卵には生きる指針と同胞、そして自分の知らない芸術を与えた。
イリューシア美術院の設立。
長く絵筆を執る芸術家を招き、教育の担い手という生き方を示した。
若き芸術家の卵には生きる指針と同胞、そして自分の知らない芸術を与えた。
電子美術という全く未知の芸術体系。
絵具ではなかなか表現できない電子の魔術に学生は目を奪われた。
絵具ではなかなか表現できない電子の魔術に学生は目を奪われた。
陶芸、彫刻など絵画とは違う身に迫るリアリティ。
それに憑かれた芸術家は多かった。
この産業育成の後、巨大な女神像を訪れる若者が随分増えたのがその証左であろう。
それに憑かれた芸術家は多かった。
この産業育成の後、巨大な女神像を訪れる若者が随分増えたのがその証左であろう。
また、芸術の保護というこれまでにない取組も行われた。
美術品国家補償制度、文化財保護法、文化財関係の税優遇。
これまで野放しだった芸術作品への制度による支援が行われたのは大きな進歩である。
この取組は星鋼京の協力がなくては為し得なかったであろう。
美術品国家補償制度、文化財保護法、文化財関係の税優遇。
これまで野放しだった芸術作品への制度による支援が行われたのは大きな進歩である。
この取組は星鋼京の協力がなくては為し得なかったであろう。
芸術保護の最前線基地、それは美術館。
ここに勤める学芸員は、芸術の守護者である。
国のそこかしこにある文化財がいかなる歴史的経緯を経てその存在を希求され、生み出されたのか。
その美しさを見る人にどうすれば最もダイレクトに伝えられるのか。
彼らの苦悩は尽きず、喜びもまた涸れることはない。
詩歌藩国で初めて開催された芸術祭での学芸員達の縦横無尽の活躍は国民の記憶にも新しい。
ここに勤める学芸員は、芸術の守護者である。
国のそこかしこにある文化財がいかなる歴史的経緯を経てその存在を希求され、生み出されたのか。
その美しさを見る人にどうすれば最もダイレクトに伝えられるのか。
彼らの苦悩は尽きず、喜びもまた涸れることはない。
詩歌藩国で初めて開催された芸術祭での学芸員達の縦横無尽の活躍は国民の記憶にも新しい。
この国に根付く芸術は、長い冬を超えた。
華が開く。
芸術の民が掴んだ、栄光の華が。
華が開く。
芸術の民が掴んだ、栄光の華が。
_ _ _ _ _ ___________________________ _ _ _ _ _
農夫オズワルドは一枚の絵を描いた。
描いたのはオーロラである。
詩歌の国をすっぽり覆いつくす程の巨大で見事な円環、さながらエメラルドの王冠であった。
彼はケチであったので普段はデッサンしかしない。
しかし、この絵は水彩画である。
空の紺碧、オーロラの深緑は単色では出せない深みがあった。
多くの色が混じり合い、溶け込んでいる。
描いたのはオーロラである。
詩歌の国をすっぽり覆いつくす程の巨大で見事な円環、さながらエメラルドの王冠であった。
彼はケチであったので普段はデッサンしかしない。
しかし、この絵は水彩画である。
空の紺碧、オーロラの深緑は単色では出せない深みがあった。
多くの色が混じり合い、溶け込んでいる。
この一枚が描かれるのにどれほどの苦悩があったのか。
見た者の多くはそう考えるであろう。
ところが、驚いたことにこの絵は一晩で描かれたという。
この絵がいかにして生まれたのか、当人の話をたどる事にしよう。
農夫オズワルドはケチで勤勉である。
人里離れた山奥で気ままに独り暮らしている。
朝霜が露に溶け出す頃に寝所を出、夕暮れを眺めながら畑から家に帰る。
月が家の窓から見えなくなる頃眠りにつく。
毎日がその繰り返しである。
人里離れた山奥で気ままに独り暮らしている。
朝霜が露に溶け出す頃に寝所を出、夕暮れを眺めながら畑から家に帰る。
月が家の窓から見えなくなる頃眠りにつく。
毎日がその繰り返しである。
その日、詩歌の長い冬が終わって例年通り硬い土を鍬で掘り起こした。
掘り起こす度にむせ返るような土の匂いがする。
涸れた土には決して出せない命の匂いであった。
この国の冬は過酷である。
だから命の温かさには敏感になるのは当然のことであろう。
橡色の土から揚がる白い湯気を見て、冬に吐いた白い息を思い出した。
掘り起こす度にむせ返るような土の匂いがする。
涸れた土には決して出せない命の匂いであった。
この国の冬は過酷である。
だから命の温かさには敏感になるのは当然のことであろう。
橡色の土から揚がる白い湯気を見て、冬に吐いた白い息を思い出した。
畑の半分を耕したあと、作業小屋の中で昼御飯を食べるのだが、そこで懐かしいものを見つけた。
水彩絵の具と画材である。
王都できままな絵描きをやっていた頃の商売道具であった。
最近は気が向いたときに落書き程度のデッサンしかしないのですっかり忘れていた。
家に持ち帰ろうかと思ったが、使うあてもない。
結局そのままにして、小屋を出た。
最近は気が向いたときに落書き程度のデッサンしかしないのですっかり忘れていた。
家に持ち帰ろうかと思ったが、使うあてもない。
結局そのままにして、小屋を出た。
夕暮れが眩しいので帰路に就いた。
自分で草刈をして作った道を歩きながら、久しぶりに何か描いてみようかなとぼんやり考える。
何を描こうかと考えてみたが、考えなきゃ描けないのなら描かなくてもいいかと思いやめた。
あぁ、早く風呂に入りたいなぁ。
風呂から上がったら晩御飯を作ろう。
ジャガバターとビールがいいな。
自分で草刈をして作った道を歩きながら、久しぶりに何か描いてみようかなとぼんやり考える。
何を描こうかと考えてみたが、考えなきゃ描けないのなら描かなくてもいいかと思いやめた。
あぁ、早く風呂に入りたいなぁ。
風呂から上がったら晩御飯を作ろう。
ジャガバターとビールがいいな。
ビールのゲップが5回を迎えた頃。
そろそろ月が窓から見えなくなるだろう。
いつも通りベットに潜り込んで目を閉じたのだが、さっぱり睡魔がやってこない。
どうしたものかと目を開けて気が付いた。
そろそろ月が窓から見えなくなるだろう。
いつも通りベットに潜り込んで目を閉じたのだが、さっぱり睡魔がやってこない。
どうしたものかと目を開けて気が付いた。
窓からの光がやけに強い。
どうしたのかと訝しんで外に出てみると、空一面を覆うオーロラである。
詩歌で生まれ育ったが、これほど巨大なものを見たことがなかった。
しばしぽかんと口を開け空を眺めていたのだが、ふとあの古ぼけた画材を思い出した。
久しぶりに絵具を溶いてみたい。
筆を整え色を混ぜ、絵を描いてみたい。
オズワルドは走った。
肺が痛い。
足が重い。
息を切らせるなど何年振りだろう。
肺が痛い。
足が重い。
息を切らせるなど何年振りだろう。
その夜が世界にとって一番長い夜だった。
そして詩歌の音楽家がその力をNWに示した初めての夜だった。
あの巨大なオーロラは数多くの音楽家が生んだ奇跡だったのかもしれない。
暁の円卓から伝わる歌が、世界の糸を紡ぐように。
オーロラを貫く光の束が、その絵には確かに描かれていた。
これが芸術界に彗星の如く現れた画家、オズワルド・アマデウスの処女作となる。
_ _ _ _ _ ___________________________ _ _ _ _ _
はぁ、ちょっと休憩。
万年筆が机をたたく。
ぐっと体を伸ばすと、関節が鳴った。
盛大である。
久々の書き物は楽しいなぁ。
そんな感慨と共に息が漏れた。
ぐっと体を伸ばすと、関節が鳴った。
盛大である。
久々の書き物は楽しいなぁ。
そんな感慨と共に息が漏れた。
学芸員グスタフ・サンダールは詩歌藩国で暮らしている。
今年で30の半ばを超える。
筋骨隆々の体躯に厳つい顔。
名前も相まって、軍人のようである。
けれど、人間見た目はあてにはならないものだ。
殊この男の性格はおよそ軍人向きではない。
今年で30の半ばを超える。
筋骨隆々の体躯に厳つい顔。
名前も相まって、軍人のようである。
けれど、人間見た目はあてにはならないものだ。
殊この男の性格はおよそ軍人向きではない。
この国の在り様が気に入って、住み着き始めて早6年たった。
当初、自前の収集癖からこの国の骨董屋で働いていたのだが、そこで一人の老人と知り合う。
目の利き、知識、物への敬意、骨董屋が頭を垂れるに足る人物であった。
2年後、偶然この御仁が探している一つの箱を見つけ出し、届けた所いたく気に入られ親交を持つようになる。
種々様々な名品悪品珍品凡品を見せ、触らせ、教えられた。
その後この御仁が亡くなり、彼のコレクションを受け継ぐ。
そして、藩国政府からの要請でこのコレクションの展示を始めた。
これが、グスタフ・サンダールという異邦人がこの国で学芸員として生きていくことになる事情である。
当初、自前の収集癖からこの国の骨董屋で働いていたのだが、そこで一人の老人と知り合う。
目の利き、知識、物への敬意、骨董屋が頭を垂れるに足る人物であった。
2年後、偶然この御仁が探している一つの箱を見つけ出し、届けた所いたく気に入られ親交を持つようになる。
種々様々な名品悪品珍品凡品を見せ、触らせ、教えられた。
その後この御仁が亡くなり、彼のコレクションを受け継ぐ。
そして、藩国政府からの要請でこのコレクションの展示を始めた。
これが、グスタフ・サンダールという異邦人がこの国で学芸員として生きていくことになる事情である。
えーっと、あとやらなきゃいかんのは修復1、研究2、教育2か。
とりあえず修復からかかるか。
とりあえず修復からかかるか。
椅子から立ち上がり、首を鳴らす。
部屋に並ぶ作品修復に必要な機材を避け、ドアへと向かう。
四方の壁には天井まで届く本棚。
無数の背表紙が並ぶ。
すべてが一つの作品を理解するために必要な資料である。
その作品が生まれるに至った歴史的社会的背景を知る。
学芸員にとっての基礎である。
しかし、ここに注力することは極めて地味で困難である。
並ぶ背表紙の大半は一見何の共通点も見いだせない。
歴史書の横には家庭料理の指南書、小学校の教科書に劇場のポスター集。
無論作者の自叙伝や概論・注釈書や作品集も揃っている。
だが、それだけでは駄目なのだと師匠は言った。
この本棚に並ぶ物達が繋がっていく。
その時、初めてお前はこの作品を理解できるだろうと。
部屋に並ぶ作品修復に必要な機材を避け、ドアへと向かう。
四方の壁には天井まで届く本棚。
無数の背表紙が並ぶ。
すべてが一つの作品を理解するために必要な資料である。
その作品が生まれるに至った歴史的社会的背景を知る。
学芸員にとっての基礎である。
しかし、ここに注力することは極めて地味で困難である。
並ぶ背表紙の大半は一見何の共通点も見いだせない。
歴史書の横には家庭料理の指南書、小学校の教科書に劇場のポスター集。
無論作者の自叙伝や概論・注釈書や作品集も揃っている。
だが、それだけでは駄目なのだと師匠は言った。
この本棚に並ぶ物達が繋がっていく。
その時、初めてお前はこの作品を理解できるだろうと。
部屋から出た。
壁には無数の木製扉と灯りが等間隔に並んでいる。
細く長い廊下を歩いていく。
高い天井は闇に閉ざされ梁一本見えない。
それぞれの扉にはナンバーが打たれており、各々には文化財と研究に必要な全ての物が収められている。
つまり恐ろしい数の仕事場があるということである。
学芸員になって初めての仕事はナンバーと研究対象の組み合わせを暗記することであった。
お目当てのナンバーにたどり着き、ドアノブを捻る。
さて、やるか。
壁には無数の木製扉と灯りが等間隔に並んでいる。
細く長い廊下を歩いていく。
高い天井は闇に閉ざされ梁一本見えない。
それぞれの扉にはナンバーが打たれており、各々には文化財と研究に必要な全ての物が収められている。
つまり恐ろしい数の仕事場があるということである。
学芸員になって初めての仕事はナンバーと研究対象の組み合わせを暗記することであった。
お目当てのナンバーにたどり着き、ドアノブを捻る。
さて、やるか。
芸術作品の修復作業は、一時的な精神改造を要する。
それが師匠の言葉である。
随分修復もこなしたが、未だこの真意を知ることはできていない。
作業を終え、自室に戻り、蜂蜜入りホットミルクを飲みながら、胡乱な頭で考える。
スプーンで底に溜まった蜂蜜を掬い、口に入れる。
ミルクを啜り、思う。
それが師匠の言葉である。
随分修復もこなしたが、未だこの真意を知ることはできていない。
作業を終え、自室に戻り、蜂蜜入りホットミルクを飲みながら、胡乱な頭で考える。
スプーンで底に溜まった蜂蜜を掬い、口に入れる。
ミルクを啜り、思う。
はぁ、この一杯の為に働いてる。
「グスタフさーーーーーーーーん!実習生のソフィアですーーーーー!」
あぁ、そうだ。今日はあの子が来る日だった。あぁ、そうだった。
重い重い腰を上げる。
自室を出て、長い長い廊下を歩き、たった一つしかない鋼鉄のドアを開ける。
重い重い腰を上げる。
自室を出て、長い長い廊下を歩き、たった一つしかない鋼鉄のドアを開ける。
「おーう。よく来た、今日もよろしく」
それじゃ、教育2 始めるか。
_ _ _ _ _ ___________________________ _ _ _ _ _
「畜生、なんで見つからんのだ」
調香師ソフィア・フォルシウスはぼやいた。
美術館の蔵に潜り始めて30回になる。
あの無限と思える数の扉はしばらく見たくない。
グスタフさんの引きつった笑顔も見るに忍びない。
調香師ソフィア・フォルシウスはぼやいた。
美術館の蔵に潜り始めて30回になる。
あの無限と思える数の扉はしばらく見たくない。
グスタフさんの引きつった笑顔も見るに忍びない。
蔵から出て、通った回数30回目の喫茶店に入ったのは30分前。
2杯目のアイスレモンティーは中程まで減っている。
天井を眺める目は遠い。
ソファは相変わらず硬い。
華奢な手足が重く感じる。
長い銀髪を纏めた香匙を抜いた。
バサバサと派手な音を立てて髪が散らばる。
完全なスイッチオフ、今日の探索終了。
2杯目のアイスレモンティーは中程まで減っている。
天井を眺める目は遠い。
ソファは相変わらず硬い。
華奢な手足が重く感じる。
長い銀髪を纏めた香匙を抜いた。
バサバサと派手な音を立てて髪が散らばる。
完全なスイッチオフ、今日の探索終了。
店を出ると、青かった空がすっかり赤い。
丸い雲に夕日が射して、熟れたトマトのようだった。
丸い雲に夕日が射して、熟れたトマトのようだった。
調香師ソフィア・フォルシウスのお目当ては太古の香を記したレシピである。
詩歌という国は薬草に恵まれた。
厚い雪が草花の香を強めている。
彼女の実家は香料を扱う大家。
幼少より慣れ親しんだ無数の香。
実家には秘伝の調香書が伝わっており、それら全てを自らの物としたのは18の春。
だが、彼女は出会ってしまう。
未知の香に。
わずか3ヶ月後のことだった。
詩歌という国は薬草に恵まれた。
厚い雪が草花の香を強めている。
彼女の実家は香料を扱う大家。
幼少より慣れ親しんだ無数の香。
実家には秘伝の調香書が伝わっており、それら全てを自らの物としたのは18の春。
だが、彼女は出会ってしまう。
未知の香に。
わずか3ヶ月後のことだった。
歩き続けて海岸に出た。
森から海に香の光景が変わる。
近くのパン屋から漏れる芳ばしさ。
嗅ぎ続けて30回になる匂いだと思った。
(明日で31回目になるのかなぁ)
そんなことを考えていると、ふと嗅ぎなれない香が鼻をかすめた。
形の良い眉が歪む。
森から海に香の光景が変わる。
近くのパン屋から漏れる芳ばしさ。
嗅ぎ続けて30回になる匂いだと思った。
(明日で31回目になるのかなぁ)
そんなことを考えていると、ふと嗅ぎなれない香が鼻をかすめた。
形の良い眉が歪む。
なんだこれ。
胡乱が一瞬で吹き飛ぶ。
目つきが鷹のように鋭くなった。
犬妖精にも劣らない嗅覚が研ぎ澄まされる。
そして、見つけたのは一匹の犬。
赤いマフラーに黒い毛並。
胡乱が一瞬で吹き飛ぶ。
目つきが鷹のように鋭くなった。
犬妖精にも劣らない嗅覚が研ぎ澄まされる。
そして、見つけたのは一匹の犬。
赤いマフラーに黒い毛並。
王犬シィ?あんな香り、いったいどこで?
かくして、彼女の日課に王犬追跡が加わった。
この後、調香師ソフィア・フォルシウスは新たな香を生み出した。
類する物はNWのどこにもなく、その材料・配合すら誰にも分かっていない。
この後、調香師ソフィア・フォルシウスは新たな香を生み出した。
類する物はNWのどこにもなく、その材料・配合すら誰にも分かっていない。
名を月光の雫といった。

三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三///三
『犬士達と芸術』
詩歌藩国の犬士は寡黙で実直な勤勉家である。
それは街の巡回をする銃士隊のきびきびとした動作、整備士達の確かな仕事を見れば明らかだ。
しかし、彼らが芸術というものを解さないわけではない。
それは街の巡回をする銃士隊のきびきびとした動作、整備士達の確かな仕事を見れば明らかだ。
しかし、彼らが芸術というものを解さないわけではない。
振り返ってみればこの国に響き渡った最初の歌は、犬士達の遠吠えではなかったか。
遠く離れた地に住まう同胞を想うそれは、切々とした感情の込められたものだ。
遠く離れた地に住まう同胞を想うそれは、切々とした感情の込められたものだ。
それに銃士隊は制服着用が義務だが、その帽子は隊員個人が選ぶ事ができる。
注意してみれば、彼らの細やかなおしゃれに気づくはずだ。
それは色のあわせであったり、わずかな折れ目であったりする。
声高な自己主張ではなく、己の心を飾り立てるものだ。
だがともすれば人間よりも強いこだわりと誇りを持っている。
注意してみれば、彼らの細やかなおしゃれに気づくはずだ。
それは色のあわせであったり、わずかな折れ目であったりする。
声高な自己主張ではなく、己の心を飾り立てるものだ。
だがともすれば人間よりも強いこだわりと誇りを持っている。
かつて犬妖精と呼ばれた彼らに倣い、詩歌の民はその仕事に敬意を払った。
神は細部に宿る──犬妖精の務めた仕事を人間が行う時、犬耳と尻尾をつけるのはその名残である。
神は細部に宿る──犬妖精の務めた仕事を人間が行う時、犬耳と尻尾をつけるのはその名残である。
人と犬にはそれぞれの領分がある。
だが、共に働く時。共に歌う時。共に絵画を見る時。
その心が同じことを想っても、いいのではないだろうか。
だが、共に働く時。共に歌う時。共に絵画を見る時。
その心が同じことを想っても、いいのではないだろうか。
__________________________________________
スタッフリスト
文
鈴藤 瑞樹
士具馬 鶏鶴
九音・詩歌
文
鈴藤 瑞樹
士具馬 鶏鶴
九音・詩歌
絵
岩崎経
星月 典子
岩崎経
星月 典子
編集
竜宮・司・ヒメリアス・ドラグゥーン
__________________________________________
竜宮・司・ヒメリアス・ドラグゥーン
__________________________________________