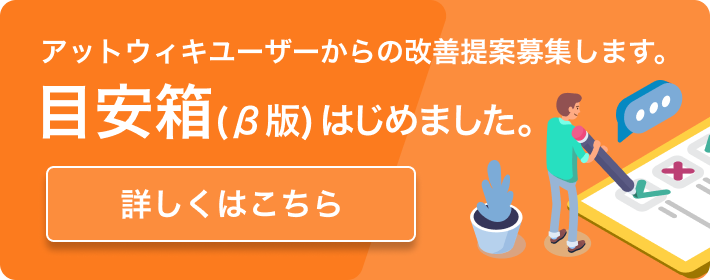プロローグ
はるか昔。今から約1000年前の出来事。
各自が勝手気ままに暮らす、自由にあふれた世界。
そんな中で、AA達は憎しみや悲しみ、苦しみや嫉妬を知らずに育っていた。
ある日、一つの新しい命が世界に誕生した。
誰もがそれを笑いながら、自分達の世界に受け入れるはずだった。
だが、生まれた子供は他のものとはどこか違っていた。
子供の背中には小さな、ほんの小さな翼が生えていたのだ。
それは、本当に小さな翼だったのだが、大きな厄災を引き起こした。
多くの者が、初めて他者との違いから来る不快感を感じた。
多くの者が、その不快感から逃げるように子供を拒絶した。
子供は戸惑い、悲しみ、苦しんだ。誰からも受け入れてもらえず、その存在すら認めてもらうことができなかった。
子供は、人々に何度も問いかけた。どうして誰も、自分のことを同じAAとして扱ってくれないのかと。
だが、返ってくる答えはいつも同じだった。
「お前のような化け物が、私たちと同じアスキーアートであるはずがないだろう。とっととどこへでも消えてしまえ!」
ある日、子供は姿を消した。煙がその身を消すかのごとく、ひっそりといなくなった。
あるものは喜び、またある者は子供を嘲り、気づかなかったもの達は普段どおりの日常を行った。
三日もすれば、子供のことなど忘れて、また普通の生活を楽しみあった。
いつしか、子供のことなど、まるでなかったことのように扱われた。
そして、時が流れた。
しかし、話はそこで終わらなかった。
突然、翼を生やした多数のAA達が、村という村を襲い、多くのAAを殺した。
ついに、子供を追い出した村までもが襲われた。
昔、子供を嘲り、蔑み、差別していたもの達は、皆口をそろえて言った。
「同じAAじゃないか!どうしてこんなことをするんだ!」
翼を持つAA達は皆、口をそろえて言った。
「俺達はお前らを同じアスキーアートだとは思っていない。俺達で、自分達だけの世界を作るんだ」
村を襲ったAA達は、昔に村を追われ、AAのとても住めないような場所に追いやられていた者たちだった。
子供が最初の一人ではなかった。もっと多くの被害者がいたのだ。
人々の記憶から抹消された、いないものとして扱われていたものたちが。
そしてかつての子供が、村の者を集めて言った。
「俺には仲間がいる。みんな俺が探し出して、助け出した。俺達には強い絆がある。
お前らには何がある? 毎日を堕落して過ごしてきたお前らに。
自分の幸せのためには、他人を蹴落としてもよいと思っているお前らに」
村のAA達は何も言い返せなかった。
「俺は自分で理想の世界を作る。その世界に、お前らは必要ない。
だから最後に、お前らに聞かせてやろう。
これからは、俺は創造者と名乗る。理想の世界を、作っていく者だ!」
残されたAA達は、集まって話し合った。翼を持つ者に対抗する手段を考えあい、ともに知恵を出し合った。
長い長い戦いが始まった。翼を持つものも、そうでないものも、多くのAAが犠牲になった。たくさんの美しい大地や自然が失われた。
多くの犠牲の末、翼のないAA達は勝利をおさめた。
彼らは話し合い、二度と同じ過ちを犯さないように、この話を天地戦争と名づけ、ずっと言い伝えていくことにした。
すると、驚いたことに、もう翼の生えたAAは生まれなくなった。
AA達は、また生活を楽しみ始めた。今度は、他人と共有する楽しみも知ることができた。
おかげで科学技術の分野の研究などが進み、その結果、世界はゆっくりと近代化していった。
時は流れた。
便利が浸透していくにつれて、事態はゆっくりと巻き戻り始めた。
差別が生まれ、戦争が始まり、おなじ種族同士のものまでもが、いがみ合い始めた。
だが、翼を持つAA達は二度と現れなかった。無論、創造者も。
天地戦争は、もはや教科書の中にある、歴史の一部でしかなくなったいた。
誰もが個人のことを考え、他人との付き合いはうわべだけになっていった。
事態はどんどん悪化していた。まるで火のついた車輪のように、加速ばかりしてとまらなくなった。
誰もがその現実から目を背け、自分だけは幸せだと思い込むことで強引に納得していた。
天地戦争から1000年。
時計の針のように、まったく同じことが今繰り返されようとしている。
第一章
「起きなさい!」
ある平凡な一日の朝。
快活そうなしぃ族の女性が、布団にもぐりこみ抵抗を続ける彼の息子を叱り付けていた。
「ほら、早く起きないと学校に遅れるでしょ!」
「……まだ五時ちょっとすぎだよ。あと一時間は眠れる……ふあぁ……」
「何言ってんの! あんた今日から寮生活でしょうが! 早く行かないと初日から遅刻して恥かくわよ!」
「だいじょぶ……だよ。だからもう十分だけ……」
弁解の後半は口の奥へと落ちて、もはや言葉にもなっていない。
母親はそんな息子の様子を見て、嘆息した。
「あんた言ったわよね? 明日遅刻しないように、どんな手段つかっても起こしてくれって」
息子の返事はない。もっとも、母親も返事は期待していない。単なる確認である。
軽い舌打ちとともに服の裾を肩まで捲り上げ、布団の端に手を伸ばす。
その白く細い腕は、いとも簡単にねぼすけを布団ごと持ち上げた。
そして。
「うおりゃあぁぁぁぁぁぁっ!」
気合一閃。
静かな朝の街中に、近所迷惑な音が響き渡った。
結局、激しい頭痛とともに少年が夢から引っ張り出された時には、もう彼の母親の姿はなかった。
高校生にしては少し小柄、小学生にしては育ちすぎといった風貌のギコ族の少年は、穏やかな目をいかにも眠そうに半開きにし頭をかいた。
体には下着の他に、胸部に包帯をまとっている。かなり使い込まれたものなのか、本来真っ白のはずのそれは灰色に汚れていた。
彼はゆっくりと布団から這い出し、寒さに軽く身を震わせてから時計を見る。
時計は五時をゆっくりと過ぎようとしているところだった。
少し肌寒い温度がゆっくりと思考を整えていき、彼はようやく立ち上がった。
いつものように着替えをタンスから取り出す。だが、タンスの中に今日の分の着替えを除いて、他に何も入っていない。
他の衣類は、窓の下の方に転がっている大きめのボストンバッグの中に昨夜入れておいた。
普段着の中では一番立派に見える服を着て、ともに犠牲になった布団を元のようにたたんで床に置く。
すべての動作を手早く終え、彼は満足そうに部屋を見渡した。
そこには、バッグにつめられたいくつかのものを除けば、毎日見ていた部屋があった。
だが今日はどこか、とてもさびしそうに見えた。
ゆっくりとボストンバッグを担ぎ上げ、十数年世話になった部屋に背を向ける。
いつも何気なくやってることだったが、今日だけは違和感を感じずにはいられなかった。
「いままでどうもありがとう。また、帰ってくるから」
彼は親類にでもかけるような言葉を静まり返った部屋の中に残し、ゆっくりと扉を閉めた。
少年の名前はルー。
ルーは中学生だった。
そして今日、多くの同級生とともに高校生となる。
しかし、彼の行く高校は近場の都立高校でも、進学校で有名な名門私立高校でもない。
聖モナー学園。
ここから電車で一時間はかかる、都会に位置する寮制の私立高校だ。
つい最近できたにもかかわらず、完備された環境、洗練された授業でおおくのエリートを世に送り出している。
おまけに、費用が都立高校並みに安い。
高校の創設者が、並外れた財産の持ち主で、自分の息子を入れるためにちゃくちゃくと準備を進めていたらしい。
毎年募集人員は一般でも三~四倍をゆうに超し、厳選された難問題に毎年熾烈な争いが繰り広げられる。
ではなぜ、これといった特徴もない市立中学出身のルーが入学することになったのか?
話は、去年の冬にさかのぼる。
去年の冬、十二月も半ばを過ぎ、学校も終わったころだった。
世間一般の子供達はクリスマスプレゼントに胸をときめかせたり、雪の積もる量に一喜一憂する時期である。
だが、なかにはそんな悠長なことを言っていられない人たちがいる。
年明けの二月に、まさに運命の分かれ道とも言える受験を控えた、受験生達である。
ルーも例に漏れず、このグループに属していた。
目標の近場の都立高校に受かるには十分な学力はあったが、家の財政の関係で私立を受けさせてもらえない以上
ルーにとっては、絶対に失敗できない大一番の勝負である。
最後の追い込みにうってつけの十二月を、悠長に過ごすわけにはいかないのだった。
早起きして机に向かい、不得意な歴史の苦手つぶしをしていたが、思ったより勉強ははかどってくれない。
暖房による生暖かい空気が、ぬるま湯に使っているような気だるい気分にさせてくれる。
そこに早起きの産物の眠気までがまとわりついてきて、いつしかまぶたが揺れ始めた。
ルーは一旦立ち上がり、リビングに気分転換に行くことにした。
廊下は冷気に支配され、足の先から顔までを一気に冷やしていく。
予想外の攻撃に身を大きく震わせ、ルーは体を精一杯ちぢこませると、早足でリビングへと向かった。
「おはよ、お兄ちゃん。遅かったね」
「おはよう。別に寝坊したわけじゃないぞ」
リビングの先客と軽く挨拶を交わし、近場のあいてるいすに腰掛けると、一つしかないストーブを自分の近くに引き寄せた。
感覚がなくなり始めていた指先が、氷が解けるような感覚に襲われる。
「お兄ちゃんズルい~! 一つしかストーブないんだから譲り合って使ってよー」
「さっきまで独り占めしてた奴が何いってんだよ。だいたい、寒いならアイス食わなきゃいいだろうが」
「な~に言ってんの。アイスっていうのは、冬に食べるものなんだよ?」
「それはない。大体、お前は年がら年中アイス食ってるだろうが」
妹の手に握られているのは、ガツンとみかんというアイス。
彼女はこのアイスが大の好物で、冷凍庫に欠かさずストックが入っているほどである。
妹はガナー族で、現在は中学一年生だ。
ガナー族らしいふっくらとした体つきで、整った顔立ちをしている。
小六の時まではよく一緒に遊んでいたが、体が成長し始めてから、女子から女性になり始めたため
最近はなんだか気恥ずかしくて、ルーのほうが少し避けているという感じだ。
そんな兄の苦悩に、妹のほうはどこ吹く風で、今日のような寒い朝でもだらしなくパジャマを着て、
いすの上に無防備な姿をさらしながら、お気に入りのアイスを食べている。
(家でも少しぐらい気をつかえよな……)
心の中では愚痴っていても、目線はどうしても小さめのパジャマが窮屈そうな胸の隆起物に向かってしまうのは男の性であった。
「おはよ~……ぅははあぁ~」
新たにリビングに現れた人物は、勝手にルー達の場所からストーブを持ち去り、自分の座るいすの近くに寄せて暖をとり始める。
「母さん、一個しかないんだから譲り合って使おうよ……」
「ガナー、新聞取ってきて」
ため息混じりに抗議する息子を無視して、母親は机の上につっぷして丸くなった。
ガナーは少し困ったような顔をしていたが、すぐに顔を明るくさせ、
「お母さん、私朝ごはんにトースト焼いてあげる! ちょっと待っててね」
と言い残し、台所へと早足でかけていった。
「あ~、ありがとう。ガナーは優しいわね。じゃあルーでいいや。新聞」
「なんだよ、その扱いの差。大体、俺は受験生。普通の母親だったら、早起きして朝飯ぐらい作っててくれても――」
「うちはそんなことで、わが自慢の息子を差別したりしないわ。ほら、はやくしんぶ~ん」
「そんな差別ならしてくれたほうがいいよ……」
愚痴をこぼしつつも立ち上がる。ただでさえ受験勉強で疲れている頭を、母との無謀な会話で浪費させたくはない。
足を置いた床は、少しあったまってしまったせいか、なおさら冷たく感じた。
つま先歩きで、玄関へと走る。
ドアを開けると、外は完全に寒さの支配下であった。
風も吹いていないのに、体の芯まで一気に冷やされ、まるで冷水に飛び込んだ気分だ。
ガナーが率先して朝食作ってまで、避けたい理由が良くわかった。
妹や母親に対する愚痴を口の中で転がしながら、かかとを踏んだままの靴で郵便受けに近寄り、中の新聞を乱暴に引っ張り出した。
それと同時に、茶色の封筒が隅からこぼれ落ちる。母親宛のものだろうか。
たいした確認もせず封筒を新聞の間に挟むと、暖かいリビングまで一直線にかけ戻った。
リビングでは、ちょうどガナーが母親に焼きたてのトーストを出していたところだった。
ガナーは母親にお茶を入れ終わると、睨む兄に気づき、小さく舌を出して台所へと逃げていった。
暖かい部屋に安堵感を覚えつつ、ルーは母親の後頭部にまだ冷たいままの新聞を叩きつけた。
「遅いわよ」
「ありがとうの一言もないのかよ……」
「はいはい、ありがとうありがとう。ルーちゃんはほんっといい子ねぇ……ってあれ?
ちょっとルー、これ何よ?」
母親が先ほどの封筒を突きつけてきた。
どうやら開いたときに滑り落ちたらしい。
妹の持ってきてくれたお茶をすすり、一泊おいてから答える。
「新聞と一緒に入ってた。どうせ母さんのだろ?」
「でも、あんたの名前が書かれてるけど?」
「は?」
「だから、あんたの名前がしっかりと書かれてるわよ」
母親が示すところを見れば、確かに自分の名前が明記されている。
封筒をひったくるように取ると、すばやく中身を確認してみる。なかには、三枚の紙が入っていた。
「これは……推薦状?」
「どうしたの、お兄ちゃん?」
「ちょっと、私にも見せなさい」
「おい、押すなって」
両脇から、野次馬二人が文字通り首を突っ込んできた。
押し返すようにして自分の居場所を確保、手紙の内容を簡潔に説明する。
「これは推薦状みたい。内容を要約すると、あなたに是非、我が高校の推薦試験を受けてもらいたい、ってこと」
「ええ――っ! 嘘ぉ!」
「なんだよ。俺のところに来るのが、おかしいみたいじゃんか」
「おかしいもなにも、この封筒に聖モナー学園って書いてあるじゃん!」
「まぁな。そこってすごいのか?」
「お兄ちゃん、馬鹿でしょ! 聖モナー学園知らないなんて、ほんとに受験生なの?」
「あのな……」
「聖モナー学園といえば、大学で言えばモナ大ぐらいの超有名校だよ!
私の友達の兄弟がそこ受けてみたって言ってたけど、問題がものすんごく難しいんだって。
なんかね、三教科で合計が三桁いかなかったんだって」
「……そんなにすごいのか?」
「ちなみに、その兄弟の人はお兄ちゃんの志望校の2ランク上の高校に合格しました」
「黙っとれ」
まるで自分のことのように自慢げに話すガナー。
言葉に偽りがあるように思えなかった。
有名大学の名も引き合いに出されるほどだ、流石にルーも顔色を失う。
「母さん、どうしよ……」
母親は、机の上に推薦書を置いたまま、じっとそれらを眺めていた。
ゆっくりとルーのほうに向き直ると、諭すように語り掛ける。
「ルー。昔、中国かどっかでこんな話があったわ。
矢を放つときは、矢を二本以上持つなかれ。
そうじゃないと、一本目を外しても、二本目があるんだって思っちゃうでしょ?
まさに二兎追うものは一兎も得ずよ。
せっかく自分の決めた志望校があるんだから、今はそっちだけに集中しなさい。わかったわね?」
「でも、母さん……」
「いいから。何も言わずに回れ右して部屋帰りなさい」
「……。でも……」
「ルー」
ゆっくりと立ち上がった母親は、ルーの肩に両手を置き、顔を見据えるようにゆっくりと見た。
母親の様子に、思わず顔がこわばる。
「ルー。私はあなたのことを思って言ってるのよ?
人生の先輩の言うことは、黙って聞いておくものよ」
「じゃあさ、母さん。俺のこと思ってるなら、なんで受けさせてくれないのさ」
母親は視線を逸らし、数秒虚空を睨んでから言葉を吐き出した。
「それは……。望みのない試験のための試験料なんて、払いたくないからよ!」
「本音が出やがったな、この野郎! だいたい、なんで受けてもいないのに望みのないなんて言えるんだよ!」
「ない! 断じてないわ! あんたを十数年ずっと見守ってきたんだから、それぐらいわかるわ!」
「わかるな! それが実の息子に対して言う言葉か! こんちくしょう!」
「たとえ受かったとしても、家には私立に行かせるお金なんてない! 断言してもいいわ!」
「だから、断言するな!」
言うが早いか、ルーは母親に飛びかかっていった。
この家での、もう何回目になるかすらわからない、不毛な喧嘩の火蓋が切られた。
もっとも、怒声が悲鳴に変わるのに、数秒を要しなかったが。
まったく学習能力のない兄を遠目で見つめながら、ガナーは呆れたようにため息を一つはいた。
こうなってしまったときの仲裁役は、もっぱらガナーの仕事であった。
喧騒の巻き添えを食らって机から落ちた紙を拾い上げると、息子にがっちり四の字固めをかけている母親の前に広げる。
「お母さん、ここ見て。もし試験を受けていただけるなら、試験料は免除しますって書いてあるよ」
「えっ? あら、ホントだわ」
「そういう大事なところは、ちゃんと読んでから発言しぐふぇっ!?」
後頭部に綺麗なかかと落としが決まって、ルーは床に伸びた。第一ラウンド終了。
「それにね、お母さん。聖モナー学園って、実は都立高校よりずっと学費が安いんだよ?」
「……。ちょっと、どれくらいなのか教えて?」
ガナーが母親に耳打ちすると、母親はルーを優しく抱き上げ、服のほこりを手で払った。
一連の騒動からは想像もできないような優しい声で、母親はルーに話した。
「ルー。せっかくこんな名門校から御誘いが来ているの。受けなければ失礼というものでしょう?」
「なんだよ、その変わりようは……」
「しょうがないわね、ルーは。一人じゃ心細いんでしょう?」
「いや、そんなこと誰も言ってねえし」
「仕方がないわね。特別に母さんが試験会場まで一緒に行ってあげるわ。
ルーのためなら、昼ドラの一つや二つ、苦じゃないの。
なんてったって、私の自慢の息子だもの!」
「……もういいよ。じゃあ、受けてもいいんだね?」
「絶対受かるのよ!」
「へいへい」
「でもさ、お兄ちゃんがもし受かったら、私なんか友達にすっごく自慢できちゃうよね!」
「ルーが寮に行ってくれれば食事も作んなくて済むし、洗濯物も減っていいことだらけね!」
「お兄ちゃんでもいけるんなら、来年は私が行けちゃったりして!」
「ルーがエリート道走ってくれれば、定年後には左団扇ね!」
勝手なことを言い出す家族達を尻目に、ルーはさっさと家族の輪から抜け出した。
ルーとしては受かれる自信などまったくない。
ただ、推薦してくれるならなんとなく受けないと悪いような気がしたから、一応受けてみるだけなのだ。
あまりに過度な期待は、少し胸に響いた。
「こんな朝から、何の騒ぎだい?」
突然の言葉に顔を上げると、目をこすりながらこちらへと近づいてくる男性を見つけた。
普段から眠たそうに見えるその目をこすりながら、ゆったりとしたパジャマにその身を包まれているモナー族。
あまり家では会わないが、絶対に忘れることはない人物だ。
「おはよう、父さん。遅くまで仕事してたの?」
「あぁ。私は仕事が遅いから、こつこつとやっておかないとな。
ルーも受験勉強、がんばってるか?」
「父さん、そのことなんだけど……」
推薦状を渡し、先ほどまでのいきさつを説明する。後ろの、妄想に浸っている二人はとりあえず無視した。
父親はルーの話を聞き終えると、逆にルーに問い返した。
「ルーはどうしたいんだ?」
「一応、受けてみようかな……と思ってる」
「ふむ。行きたい理由とかはないのか?」
「だって、名前も知らないような高校だし。寮制っていうのは、すこし気になるけど……」
「そうか。だが、今いる友達とは別れてしまうことになるな。勉強も難しいだろう。上手くやっていけるのか?」
「それは……うーん……」
「母さんはどう言ってるんだ?」
「母さんは俺のことなんかどうでもいいみたい。学費が安いから、行けって言ってる……」
「それはないだろう。母さんなりに、はっぱをかけようとしてくれているんだよ」
「そうかなぁ……。父さんは、どう思うの?」
父親は手をあごに回し、一度ルーから視点をそらした。表情こそ変わらないものの、真剣に思案してくれていることがわかる。
そのまま部屋を見渡し、母親、ガナー、そしてルーを最後にもう一度見てから口を開いた。
「父さんは受験に賛成だ。ルーにもそろそろ、転機が訪れてもいいはずだからな」
「転機?」
「人が変わるときの、きっかけのようなものだ。
転機とは、必ずしもいいことばかりとは限らない。
失敗や挫折、努力をしても報われなかったり、悲しい思いをすることによっても、人間は成長する。
見つけるものやスピードも、人によってそれぞれだがな」
「父さんも、転機があったの?」
「あったとも。誰にだってあるものなんだ。
ルーがもしその高校に行くのなら、家族からも離れなくてはならないし、知り合いも一から作らなくてはならない。
勉強も、今まで以上に大変になるだろうな。
そんな中でなら、きっとルーにも転機が訪れるだろう」
「もし、受かんなかったら?」
「そうなら、まだ転機が来るには早すぎる、ということだろう。
転機はすぐ来れば良い物ではない。遅くても良いというわけでもない。
大事なのは、転機が訪れたときに、自分の中で何を見つけるかということだ。
すこし、説教くさくなってしまったかな?」
「ううん、そんなことないよ。どうもありがとう」
照れくさそうに鼻の頭を書く父親に、ルーは心からの感謝の言葉を述べた。
すると、唐突に父親の手がルーの頭へと置かれた。
「私は、ルーなら難なく受かることができると信じているよ。
ルーのことを育ててきた私が言うんだ。間違いない」
「……。ありがとう。俺受けてみることにするよ」
もう一度礼をのべ、照れくささを隠すかのようにルーはその場から走り去った。
残された父親は推薦書に目を落とし、そっと呟いた。
「しかし、妙だな……」
残念ながら、その声は誰の耳に届くこともなかったのだが。
「まさか、本当に合格するなんてな」
ボストンバックを背負ったままリビングに向かっている時、ついそんな言葉が口をついて出た。
実際、今でもまだ夢のようなのだ。
簡単な面接と、筆記試験をやっただけで、翌週にはもう合格通知が届いて、年内のうちに、ルーは高校生になれたのだから。
「あの時の母さんとガナーの顔ったら、なかったな」
鳩が豆鉄砲食らったかのような顔で立ち尽くす家族二人を思い出し、おもわず笑みがこぼれる。
だが、ふとあることが頭をよぎり、ルーはすぐにまじめな顔へと戻った。
「でも……。そんな二人にも、しばらく会えなくなるんだよな」
聖モナー学園は全寮制だ。
そのうえ門限が厳しく定められているので、家に帰ってこられるのは、早くて次の長期休業になってしまう。
長年付き合ってきた家族と別れるのは、まだ若いルーにとって、苦痛だった。
自分は新しい学校でうまくやっていけるのだろうか。
勉強はついていけるだろうか。
友達はできるだろうか。
いじめにあったりしないだろうか。
深刻な悩みが、頭の中にちらついては、消えてゆく。
それに、ルーにはもう一つ、心配の種があった。
この胸に巻かれている包帯の下に隠された、家族共通の秘密。
万が一ばれれば、普段どおりの生活を送ることさえ難しくなる。
家族にも、多大な迷惑をかけることになってしまう。
すでにこの件で何度も苦い経験をしているルーにとって、最大の不安要素であった。
「まぁ、何とかなるよな。今までも何とかなってきたんだし」
自分に言い聞かせるように呟いたルーの耳に、別の音が飛び込んできた。
朝のやわらかい光に包まれた居間から、台所で母親がゆっくりと寝息を立てているのが見えた。
朝食を作っていた最中だったのか、コンロの上には作りかけのおかずが所々に置かれている。
(俺のこと、待っててくれたのかな)
ルーはそっと母親に近寄り、やさしく肩を揺さぶった。
「母さん、母さん!」
「う……うん、起きてる、起きてるわよ」
「別に眠いなら寝ててもいいよ?」
「ん……、大丈夫よ。いいから、机のほういってなさい」
母親に背中を押されて机につくと、すぐに朝食を持ってきてくれた。
別段豪華な朝食というわけではなかったが、やはり母親の作ってくれた朝食はどんなものよりもおいしかった。
なにげなく卵焼きをほおばっていると、母親がじっと、ルーを見つめていた。
「母さん、俺の顔になんかついてる?」
「ううん、別に。ただ……あんたもすこしの間に大きくなったなぁって、思ったのよ」
「そうかなぁ。俺はあんまし、実感ないんだけど」
「時が流れるのは早いわね。もうすぐガナーも、こんな風に巣立っていくのかしら」
「母さん、俺は別に巣立つわけじゃなくて、ただ全寮制の学校行くだけだから。
夏休みになれば、またすぐ会えるってば」
「ふふ、そうだったわね」
母親はそう言って笑い、またルーの顔を名残惜しそうに眺めていた。
相手は母親とはいえ、なんだか気恥ずかしい。
目の前の食事をとっとと胃に押し込んで、その場を離れようと席を立った時だった。
背を向けたルーの背中を、暖かい感触が包み込んだ。
「か、母さん!?」
母親がルーに寄りかかるように、後ろから抱きついていた。
思わず赤くなった頬に、母親の顔が隣から擦り寄ってきた。
それと同時に、甘ったるいにおいが鼻腔をくすぐる。
嫌な予感がして振り返ってみると、台所の床にゴミ箱から落ちた空き缶が散乱していた。
「母さん、朝っぱらから酒飲んだのかよ!?」
「うるさいわね……。酒なんてもんは、いつ飲んでも同じよ……」
「よりによって、息子が高校生になる大事な日に飲むか!?」
ぐっと、ルーの腹に回されていた両手に力がこもった。
首筋に熱いものがつたったかと思うと、後ろから嗚咽が聞こえてきた。
「母さん……泣いてるの?」
「……泣いてなんかないわよ。目にごみが入ったの……」
酒、涙、母親の下手な嘘のすべての原因が、自分にあることを知った。
ルーが母親のほうに向き直ると、相対的に母親は顔を逃がした。
別に覗き込まなくても、その顔がどうなっているかは容易に想像がついた。
「母さん」
「……」
返事の代わりに、光るしずくが床に落ちて、小さな音をたてた。
「俺は大丈夫だよ。一人でもしっかりやっていける。だって」
もったいぶるように一度大きく間を空けて、母親が聞いているのを確認してから言葉をつないだ。
「だって……俺は母さんの息子だろ? 自慢の母さんのさ」
くっ、と息を呑む音が母親の喉から漏れた。
「……あんたのことなんか、これっぽっちも心配しちゃいないわよ。
とにかく……っ、あのことだけは注意しなさいよ……。
あんたは昔っから、そそっかしいんだから……」
母親は肩を小刻みに震わせながら、とても力なく、しかし強い調子で反論する。
言葉はぼろぼろで、今にも本音が零れ落ちそうなほどだった。
ルーはなにも言わずにそっと手を伸ばすと、母親の目から伸びる涙の線を指でたどった。
「わかってるってば。俺ももう高校生なんだし。
……じゃあ、そろそろ行くね。
ガナーと父さんにも、さよなら言っといてね」
ルーは母に背を向けるとボストンバッグをつかみあげ、一目散に部屋の外へ飛び出した。
ドアを閉めた時の乱暴な音がリビングに、そして家中に響き渡った。
「こんな朝から何の騒ぎだい?」
先ほどの騒動からすこし経ってから、寝室から出てきた父親がいつもののんびりした調子で尋ねた。
母親はドアの前に立ち尽くし、子供のように泣きじゃくりながら、両目からあふれる出る涙を必死でぬぐっていた。
父親はそんな母親の肩に、優しく手を置く。
「まったく。そんなにさびしいなら、なんで受験のときに反対しなかったんだい?」
母親は胸の中に顔をうずめ、小さな声でうるさい、とだけ返した。
「やれやれ、まったく昔から変わらないな。もっと素直になればいいじゃないか。
そんなことでは、ルーに嫌われてしまうよ。
さぁ、もう一寝入りしてきなさい」
父親は子供をあやすかのような口調で、母親の頭を優しくなでながら寝室へと連れて行った。
母親も、時折嗚咽を漏らしながら、文句も言わずそれに従った。
父親に言われるがままにベッドにいれられると、母親は顔を隠すかのように布団を深くかぶった。
そんな様子を眺めながら、父親もベッドの隣に腰掛ける。
「君がそんな調子では、ルーも分かれるとき辛かっただろうに」
「……」
「まぁ、それも君らしいということか」
「うるさい」
子供がすねるかのような調子で、布団の奥からが返事がきた。
父親はそれを見て、すこし顔をほころばせた。
「ルーなら大丈夫さ。もう一人でも立派にやっていける。
それは君も分かっているんだろう?」
返事はない。しかし、父親は続けた。
「別れはさびしいものだ。だが、それはルーも同じことなんだ。
私達も、すこし変わらなければいけないよ」
「わかってる……」
布団の中からの声は、とても深い悲しみに包まれていた。
父親は、布団の上からゆっくりと背中をさすっていった。
やがて嗚咽は消え、規則正しい呼吸音だけが部屋に響き始めた。
父親は布団を下ろし、すこし顔を眺めてから部屋の外へ出て行った。
部屋の中に、暗闇と静寂だけが残された。
「ちょっとは、寂しがりなさいよ……」
寝言か、はたまた本音が、暗闇の部屋の中に浮かび、そして消えた。
以降、こちらに続きます。↓
http://town.s96.xrea.com/cgi-bin/long/anthologys.cgi?action=html2&key=20060102232225