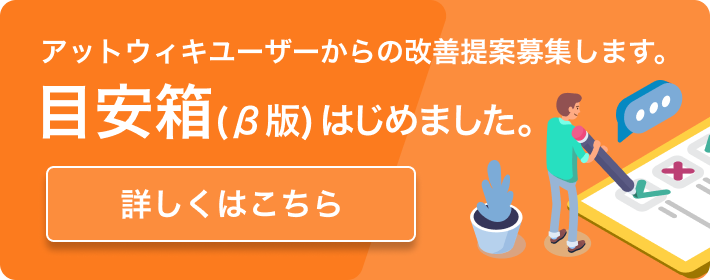強くなった自分とそう見えていただけのワタシ
人には、慣れと言うものがある。
様々な事にそれは当てはまる。例えばそれは勉学であっても。例えばそれは夢の為の努力であっても。
数をこなせば、人は自然とその行為に慣れというものを抱き、容易くそれを実行出来るようになる。
そうして手に入れる力。努力した末に手に入る慣れもあれば、生きて行く内に自然と手にする慣れもある。
そう。どんな事も慣れてしまえば簡単に実行できてしまうのだ。
それが例え「人を殺める」事ですら・・・。
プロローグ
ワタシは、気付いたらここに居た。
一面真っ白で、部屋の隅っこにはワタシが遊ぶ為に用意されたオモチャや道具があった。
時々真っ白い部屋の壁が割れて、そこから色々な人が出てくる。
良く分からない事を言ってる人達や、変なモノを持った白衣を着ている人達とか。
ワタシは、良く分からないけどその人達が好きだった。遊んでくれるし、お腹が減ったら御飯を持って来てくれる。
だからワタシはその人達の言う事を聞いたんだ。初めてお外に出して貰えた時は、嬉しかった。
お外に出る時、どうしてか分からないけど「目を閉じてて」。そう言われてその人達と一緒に何処かへ行った。
「目を開けて」。そう言われるとすぐワタシは目を開ける。一面、真っ赤だった。
広くて、天井が高くて、それから誰かが中で見てる変な所が上にあって。
その中では色んな人が、ワタシが大好きなケチャップみたいなもので汚れて倒れてた。でもケチャップと違うのは、臭い。
でも、ワタシは笑った。だって皆遊んでると思ったから。
その真っ赤な中で、倒れてない何人かの人達が遊んでた。ワタシの知らないピカピカのオモチャで。そのオモチャは、その中の誰かに当たるとケチャップみたいなものを浴びてもっと綺麗になった。
ワタシは何故かすごくワクワクした。ワタシもアレで遊びたい。あのピカピカの何かがすごく欲しい。
だからワタシは隣に立ってる人に言った。「ワタシもアレで遊びたい!」
そう言うと、その人はニッコリ笑って同じものをワタシにくれた。すごく嬉しい!
「行って一緒に遊んで来なさい」。ワタシは言われてすぐに遊んでる人達に混ぜてもらった。
ピカピカのそれで触れたり、叩いたりすると、遊んでる人達はうるさくなった。だからワタシは止める為にもっともっとやった。
しばらくして皆動かなくなっちゃった。静かになって、それでピカピカはすごく綺麗になって。ワタシは嬉しかった。
もっと遊びたいな。そう思って、ワタシは隣で倒れてる人にピカピカを刺した。
動かなかった。何故か嫌な気分になって、ワタシはその人を刺し続けた。赤いのがいっぱい出たけど、どうでも良かった。
気付いたら、白衣を着ている人達に止められて、ワタシはいつの間にかあの真っ白な部屋に戻されてた。白いのがすごく眩しくて、気持ち悪くなった。
つまんないから寝転がってたら、白衣を着た人達が入ってきてこう言った。
「おめでとう。君は最初で最後の『成功者』だ」
何を言ってるのか分からなかった。だけど嬉しかった。そして、どうしてか怖かった。
でもいいんだ。ワタシは、この人たちが大好きだから。
ワタシは、何度もあの真っ赤で広い所で遊んだ。始めは楽しかったのに、ワタシは赤と、ピカピカと、嫌いになってきた。
すごく怖い。だけど、同じ事をずっとずっと繰り返した。
刺された人達は皆苦しそうだった。ワタシもああなったら嫌だな。だから、ワタシは嫌だけどずっと遊び続けてた。
そしたらね、どうしてだろう。
何も感じなくなっちゃったんだ。
第一話
「自業自得・・・って奴だから、多分」
ぽつりと一つ呟き。そして、その呟きの持ち主は今まで読んでいた新聞を畳み、自らの座るベンチに置く。
彼は顔を上げ、自分の目の前に聳える巨大なビルを見上げた。暖かく吹く風に、茶色のフサ毛がのどかに揺れる。
物憂げにビルを見上げている彼の名は、ルドルフ・フッサール。長毛種の猫型AAである。そしてこのビルは彼の勤める大企業、「マルディアス」の本社である。つい最近社長が何者かに殺害され、社内も含め内外が大騒ぎになっている。
「あんな社長だったしな・・・そりゃ恨まれるか」
ルドルフは思い出せる限りに社長の顔を思い出す。ルドルフは単なる平社員ではあるが、社長の顔くらいは知っていた。名は「マニール・ワード」だったか。経済界では相当悪名名高い人物であったらしい。
凄まじい勢いで企業を成長させたマニールであったが、そこに恨みを買われる要因を作ったのだろう。気付けば彼は殺され、今では社内の平社員達に仕事は無く、上層部やらのお偉方にばかり責任や重圧が回っているのであった。
「お陰で俺等平社員は仕事無しの上連日休日、と・・・」
つまらなそうにルドルフは大きく欠伸をし、目から漏れた涙を拭う。仕事ばかりで忙しかったはずの日常に唐突に暇が出来ても、やる事などそうすぐに出来るものではない。
「・・・久々にギコル達と遊・・・ぶっつってもアイツらもこの時間は仕事・・・か」
同年代の友人は勿論皆仕事である。普段ならこの時間帯はルドルフとてデスクワークであり、やれる事は本来無いのだ。
「・・・腹減ったな」
いつもは忙しいからと言って朝は何も食べないルドルフであったが、暇が出来た途端体が空腹を認識し始めた。やる事も無いし、丁度良いから。ルドルフはベンチを後にし、マルディアスの正面玄関の巨大な自動ドアをくぐり、食堂に向かう。
だだっ広い社の正面玄関内。誰も居なければ、これほどに無駄な空間は無いと言えよう。
そしてやはり皆騒ぎの収拾を図ろうとしているのであろう。食堂に居る者はまばらで、むしろここまで来る時にすれ違った様々な表情のAAの方が断然多かった。エレベーターは引っ切り無しに動き、非常階段を使っている者も少なくはなかった。
正面に見えるエレベーターから脇にそれた場所に位置する食堂。その内部は広く、大抵何処でも空いていた。が、ルドルフは奥まった所に居るある人物を見、その人物が座るテーブルに向かう。
「よっ。タカラ。上の方が忙しそうだな」
タカラと呼ばれた青い猫型AAは読んでいた新聞から目を離し、顔を上げる。笑ったような目をしているが、彼はいつもこれで普通だ。
「あ・・・先輩。どうしたんですか?今日は休みのはずじゃ?」
タカラは眉をひそめて訝しげな顔をする。ちなみに彼はルドルフより立場が上。多少ではあるのだが、そのせいで彼もまた社長死後の尻拭いをさせられているのだ。
「ああ・・・色々あってな。それとその先輩ってのやめて欲しいから。ここじゃお前の方が上だろ?」
ルドルフは苦笑いしながらそう言う。タカラはルドルフと同じ学校出身で、一つ年下の後輩。だが実力で勝っているのはタカラだったらしく、短期間で彼は上層部に食い込んだ。タカラはその事を気にしているのであろうか、常にルドルフを先輩と呼ぶ。
勿論、そう呼ばれているルドルフはそんな事どうでも良いのではあるのだが。
「いえ・・・でも何か悪い気がして。それはそうと、結局何故ここに居るんです?」
ルドルフはため息をつきながらタカラの向かいの椅子に座る。
「いや、何だか知らんが連絡があるんでとりあえず今日も来いって事で。来てみたら連絡事項の一つ二つだけ。勘弁して欲しいから」
「大変ですね・・・僕も今休憩時間ですよ。全く、社長も嫌な時期に死んでくれたもんです」
何気に黒いなコイツ。そんな事を思いながらルドルフは注文を取りに来たウェイターに「カレーライスで」と一言注文を入れる。
「朝から良くそんな重いもの食べようと思えますね・・・」
そうか? と首を傾げるルドルフ。それに対しブラックコーヒーとトースト一枚のタカラ。言ってしまえばどちらも不健康なのだが。
「・・・先輩は知ってますか?社長が殺された理由」
唐突に何を・・・ルドルフはそう思ったが、聞かれたのだから答えないという訳にも行くまい。
「知っちゃいないけど、予想はつくから。大方ここを成長させすぎた、そんなモンだろ?」
タカラはそれを聞くと、口元にニヤリと笑みを浮かべた。
「まあ世間一般にはそういう風な噂が流れてますね」
違うんかい。予想が外れた事に顔を顰めるルドルフを横目に、タカラはメモ帳らしき物を胸ポケットから出し、その文面を読み始める。
「えー・・・と、ハイ。『サンプル関連に関して邪魔な取締役の殺害に成功。しかしその際サンプル-2は暴走。しかし予定通り、内部崩壊の第一ステップ成功。重要なサンプルは失ったが、天秤にかければ重さは同等と言った所だろう。なお、サンプルは火急的速やかに破棄すr・・・』」
ルドルフは目を見開いていた。予想と180度違う。いや、と言うより予想だにしなかった事実が飛んできたのだから。
「・・・何処で手に入れたんだ、それ」
タカラの持つメモ帳を指差し。ルドルフは恐怖の入り混じる声で質問する。
「これですか? たまたま資料探ししていたら大会議室の前に落ちていたんです。で、こんな風に書かれていて」タカラはルドルフに手帳のオモテ表紙を見せる。まるで子供の遊戯の代物のように、大きく『丸秘』と印が押されていた。
「誰だって気にしますよね、アハハ」
笑っている場合なのだろうか。もしかしたら自らの身とて危うくするのかもしれないというのに、タカラは軽い調子で笑っている。
「・・・いや、もしかしたらそれだって悪戯かも・・・」
「残念。今度は裏です」
今度は裏表紙。流石にルドルフも「これは間違いなく重要なものだ」そう思ったが、それと同時に吹き出してしまった。
「なっ・・・ちょっ・・・名・・・前・・・・・アハハハハハ」
空笑いだか何だか分からない声をルドルフは上げる。背表紙にはご丁寧に名前。そして記された名は副社長のもの、『ニドルァー・チョンニーダ』。どう見ても副社長の所有物であった。
「どう見ても副社長の物です。本当にありがとうございました。アハハー」
タカラはケラケラ笑いながら手帳を胸ポケットに戻し、ブラックコーヒーを一息に飲み干す。
「ね、分かったでしょう。社長はどうやらこの『サンプル』とやらの関係で殺害されたようです。とりあえず、このメモ帳が更に上層部に食い込む切っ掛けに成り得るかもしれません」
タカラはいつに無く強い意志を語調に含めていた。ルドルフも見た事の無いその意志が感じられる顔。その意志の裏には、隠された何かがあるのだろうか。
「・・・タカラ。まさか、『アイツ』の事まだ・・・」ルドルフは思い付いたかのように言う。
「ええ、諦めてません。僕は簡単にチャンスを手放すほど弱い復讐心なんて抱きませんよ。勿論」
タカラは振り返り、ルドルフを真っ直ぐに睨む。感じられるのは、鋭く研ぎ澄まされた憎悪。
ルドルフは睨みに対峙しながらも。いつの間にか届いていたカレーライスを平然と口に運んでいた。ルドルフ以外が睨まれれば、大抵の者は臆し、目を逸らさずにはおれないであろう。
「例え、いかに親しい人物が『あの人』の事に関わっていたとしても・・・僕は・・・・・・」
そこまで言うと、タカラはパッといつもの明るい笑顔に戻った。
「まあ、随分前から貴方の疑いは晴れてますけどね、アハハ」
だったら睨むな。そう言った感じの睨みを返しながら、ルドルフはカレーを次々口へ運んで行く。
「あ、それとこの話。内外含め誰にも話しちゃダメですからね?」
分かってるから。ルドルフは最後の一口を口に含みながらそう言ったが、言葉になっていなかった。
「アハハ。では僕はこれで。先輩もお気をつけて。いつ誰が自分を狙っているか分かりませんからね」
「ああ。こんな平社員を狙うような奴も居ないだろうけど、一応気をつけるから。と言うより、その忠告そのまんまオマエガナー」
地位も立場もタカラの方が上。おまけにその手の内には手帳に記された秘密の数々。狙われる危険性はタカラの方が断然に高い。
「ええ、殺るのはこちらなんですからね・・・ハハ」
ルドルフは涼しい顔をしてタカラを見つめる。奴は本気だ。だが、止める権利が自分に無いのは分かっている。それに、止めたって止まらない奴なのも知っている。
「とにかく・・・お互い気をつけましょう。命あっての今ですからね」
「おう。気をつけろよ」
と、ルドルフはタカラが立ち去ろうとすると同時に立ち上がる。皿は既に綺麗に真っ白だ。
「・・・相も変わらず早食いですね、先輩。流石いn」そう言いかけた瞬間ゴツンという鈍い音。
「・・・・・・狼だから」
口元には笑みがあったが、確かに青筋が入った顔に、タカラは殴られたのにも関わらずヘラヘラと笑うのであった。
「・・・あー・・・明日は土曜・・・・・・か。明日位なら暇な奴も居るだろ・・・・・・しかし寒い」
小さなその声は、暗闇に満ちる静寂に飲まれ、すぐ消えて行く。響くのは、土の上を歩く靴の音だけ。
無機質な街頭の照る公園を歩くルドルフ。春先ではあるが、冬の余韻残る夜風は冷たく、毛の合間をぬって地肌に直接冷気を送る。早く暖かくなって欲しいから。ルドルフは、薄い雲に覆われる霞んだ月を見上げながらそう思っていた。
結局やる事も無く、タカラと別れた後は夕方過ぎまで適当な施設を巡り、ビデオを借りたり、或いは図書館で本を借りたり。全く以って暇人全開だ。車を持たぬルドルフであるから、歩き回る内にすぐ陽は沈んでしまった。
そして現在が帰路、と言う訳だ。誰も居ない暗い公園を一人歩く青年。格好によっては変質者と間違われてしまいそうだ。
「独り身は辛いから・・・うぅ」
家に帰っても、待っているのは前以って沸かしておくタイマー式の風呂と炊飯器の米達。そんな温もりじゃない。俺が欲しいのは人肌、そう、俺を想う彼女の・・・・・・と、訴えたくなるルドルフであったが、訴える相手も周りには居ない。
とっとと帰ろう。泣けてくる考えを頭の隅に追いやり、ルドルフは見上げていた月から視線を下ろす。
直後、ルドルフは数メートル先に人影がある事に気付いた。
こんな所に居るとすれば、家を持たぬホームレスか、皆の寝静まった頃に出てくるアベック位のものであろう。警戒一つせず、ルドルフはそのまま脇を通り過ぎようとする。
が、その足は人影がはっきりと認識できる距離に近づいた時点でストップした。
「・・・・・・女・・・の子?」
人影は予想していたいずれとも異なっていた。ルドルフの瞳に映るのは、か細い少女、小さな赤いAAの姿。
少女は身動き一つせず、身を切る夜風にその素肌を、何と裸で晒している。ルドルフは微妙に頬を赤らめながら、顔を落とし、自らの膝に顔を埋める少女の肩に手をやった。体温は確かにあった。だが、冷たい。
「おい・・・・・・こんな所で何やってるんだ? 寒くないか?」
肩に手が触れてしばらくすると、少女はゆっくり顔を上げた。ルドルフはたじろぐ事無くその少女の目を見返す。こういう時、挙動不審になる方がかえって失礼だと思ったからだ。
少女は、まるで意志を持たぬかの如く虚ろな瞳をしていた。歳はルドルフより少し下くらいであろうか(ちなみにルドルフは19である。優秀であれば彼の勤める社に歳など関係ないのだ)、幼さの残る顔。それに反すように、目に意志が宿れば強い光になるであろう蒼い瞳。そしてその蒼い瞳に双鉾を成すかのような紅き肌を蒼白に近い桃に染め、彼女もまたルドルフを真っ直ぐに見返していた。
「・・・何があったんだ?」
ルドルフは怯えさせぬよう、優しげな語調で聞く。何も感じていないのか、少女は震えてすらいなかった。
「・・・・・・貴方は・・・違う・・・・・・貴方じゃない・・・・・・私・・・やらなきゃ・・・・・・」
全く以って意味不明な事を言うと、少女は急に立ち上がる。無垢な体が露わになったが、少女は意にすら介しておらぬようだ。
「ちょっ・・・・・・ちょっと待て! そんな格好で何処に・・・じゃなくてとにかく・・・ああもう!」
ルドルフは顔を真っ赤にしながらも自らのコートを素早く脱ぎ、歩き出そうとしていた少女の肩にかけるように着せる。唐突に、少女は動きを止め、自らの羽織るコートを不思議そうに触った。
「・・・・・・暖かい」
「そりゃそうだろ。俺が着てたんだk・・・じゃなくて。君は一体何者なんだ? どうしてこんな所にそんな格好で・・・・・・」
隙、と言うか丁度動きを止めた少女の前に回り、ルドルフは早速質問をぶつける。
「私・・・私は・・・・・・やらなきゃ・・・・・・ぁ!」
ルドルフの手を押しやり、少女はまた歩き出そうとする。が、お決まりの如く少女はバランスを崩し、倒れそうになる。
「いきなり動くから・・・と」
ルドルフは予見していたかのように少女を素早く支える。少女の体はやはり冷え切っている。相当長時間野外で冷たい風を受けていたのだろう。
「わた・・・し・・・・・・」
一人称を呟くか呟かないか。少女は静かに意識を失ってしまった。一瞬ルドルフは焦ったが、このままにして置く訳にも行くまい。その意志が、次に取るべき行動をルドルフに思い出させていた。
「・・・・・・とりあえず、体暖めてやんないとな」
向かうは家。待ち受けるは暖かい風呂と食されるのを待つ白米達。疲れた体には持って来い、そして冷たい体を温めるのにも。
「・・・給料良くて良かった。ホント」
平でも給料の良い所に勤めていて良かった。これが貧乏会社であったらどうなった事か。普段は考えぬような事を切実に思うルドルフなのであった。
私は、生まれてこの方生温い温もりしか知らなかった。
その温もりとすら呼びがたい温もりを身に受け、何か感じていたのはその温もりを知った頃くらいだった。
生温さから伝わる何かは、どうしようもない苦しみと悲しみみたいなもの。
でも、分からなかった。何がその生温さに秘められているのか。何の意味があるのか。
もう感じたくない、その生温さ。感じていた全てを否定したら、私は何も感じなくなった。
人の死をまともに直視しても、私は何も感じなくなった。
何故なら、私は・・・・・・。
頭の中に、声が響く。
近くに居る、その声の持ち主達。目を開けると霞んだ視界が開け、次第にはっきりしてくる。
「もう。いくら女の子が私しか居ないからって・・・・・・」
「ごめんごめん。ガナールくらいしかこの時間帯に暇そうな娘居そうに無かったから・・・・・・」
誰だろう。節々痛む体を起こし、自分の置かれる状態を確認する。今居るのはベッドの上、そしていつの間にか着せられているサイズ違いの淡い桃色をした服。ここは・・・何処?
「ん。気が付いたみたいよ、彼女」
体を起こした目線の先には、二人のAAが居た。ルドルフと、オレンジの体色をし、大きな黒い目に特徴的なまつ毛を生やした少女。
「・・・ここは・・・?」
彼女の口を突いて出た第一声であった。
「安心して欲しいから。ここは俺の家。あ、ちなみに名前はルドルフ・フッサール」
「そして私はガナール・モナル。このワンちゃんの友達よ」
一瞬ルドルフが笑顔でガナールの方を睨もうとしたが、逆にガナールの笑顔に気圧され、表情を戻す。
「私・・・は、ツィーナ・メルティ。・・・・・・それ以外、覚えてない」ツィーナはそこまで言うと目を細め、顔を軽く落とす。
「記憶が無いのか・・・・・・?」
ルドルフは更に質問しようと口を開きかけたが、それはガナールの手に遮られる。
「ダメ。休ませてあげようよ。・・・・・・ツィーナ、ね。分かった。・・・とりあえず、ここでゆっくり体を治して、それから自分が何をすべきで、一体何者なのか、じっくり考えると良いよ。無理したら体に悪いから、ね?」
ガナールの優しい言葉に、ツィーナは少し安心したような表情をし、ゆっくりと頷いた。
「・・・意外とこういう事慣れてる感じだから、ガナール。あんな兄貴と違って」意外そうにルドルフは言う。
「あら、お兄ちゃんと私は違うわよ。それに、これでも看護学校生なんだから」
意外に俺よりしっかりしてそうだな。そう思ったルドルフであるが、第三者から見ればガナールの方が間違いなくしっかりしている。
「私・・・・・・」
何か言いかけるツィーナだったが、探し出したつもりの言葉が空回りしたらしい。言葉に詰まり、ツィーナはまた顔を落とす。
「慌てなくてもいいから、ね。今は休む方が大事」
ガナールに促され、ツィーナはまたベッドに横になる。数分後、聴こえて来たのは小さな寝息。
「・・・よし、と。一通り私がやるべき世話は終わったかね、ワンちゃん?」
ルドルフが反論出来ないのを分かって、ニヤニヤしながらガナールはからかい混じりの質問をする。
「だから狼・・・・・・ああ、まあ大体は終わったと思うから・・・」
「ん、よろしいっ」
ガナールはニッコリすると、ベッドの脇に置いてあるカバンから色々引っ張り出す。その大半は服、そして残りは生活用品等々。
「ハイ。コレ全部あの娘用。私のだからサイズがちょっと・・・じゃなくて結構違うかな。とりあえず、何かあった時は私に。それから足りない物があったらちゃんと買い足して行ってあげてね。そ・れ・とっ!」
適当に頷きながら各々の物を受け取り、早速何処かに収納しようとしていたルドルフをガナールが止める。
「あの娘に手なんか出したら、同じ女として私が制・裁するからね」
またまたニッコリするガナール。だがその笑顔に何が隠されているかルドルフはしっかり知っている。タカラの時とはまるで違い、縮こまりながらルドルフはこくこく頷いた。
「分かればよろしいっ。それじゃあ、私は帰るからね。お兄ちゃんが帰って来る前に帰らないと、あの人心配するから」
あのシスコン野郎め。ルドルフはガナールの兄、モナスの顔を思い浮かべながらニヤリと笑う。
ガナールはまさしく元気印の女の子だ。それに反して、心配性すぎるのがたまに傷のモナスという兄を持っている。近い兄妹の為か、仲も良いのではあるが、どう見ても妹の方がしっかり者の上、心配される玉でも無い。
「あ、ガナール」帰りかけていたガナールをルドルフは寸前で止める。
「わざわざ来てくれてありがとうだから。それと、モナスにはこの事言わないで欲しいから。アイツまたうるさくしそうだから」
モナスの優しさを十分に知っているルドルフだからこそ、また心配させたくない。以前ルドルフが事故で骨折した時、ほとんど毎日と言って良いほど見舞いに来ていたからだ。
「心配しすぎると自分が体壊すから」
「うん分かった。ルドルフも結構心配性だと思うけどねー」
ルドルフの言葉にガナールは頷き、踵を返してまた玄関に向かって行く。家を出る直前、ガナールは一言残し帰って行った。
「それが良い所なんだけどね」
ガナールが去った後、ルドルフは誰も聞いていないのに一言呟く。
「そりゃどうも・・・・・・だから」
彼自身、相当な心配性である事ははっきりしているのであった。
人には、慣れと言うものがある。
様々な事にそれは当てはまる。例えばそれは勉学であっても。例えばそれは夢の為の努力であっても。
数をこなせば、人は自然とその行為に慣れというものを抱き、容易くそれを実行出来るようになる。
そうして手に入れる力。努力した末に手に入る慣れもあれば、生きて行く内に自然と手にする慣れもある。
そう。どんな事も慣れてしまえば簡単に実行できてしまうのだ。
それが例え「人を殺める」事ですら・・・。
プロローグ
ワタシは、気付いたらここに居た。
一面真っ白で、部屋の隅っこにはワタシが遊ぶ為に用意されたオモチャや道具があった。
時々真っ白い部屋の壁が割れて、そこから色々な人が出てくる。
良く分からない事を言ってる人達や、変なモノを持った白衣を着ている人達とか。
ワタシは、良く分からないけどその人達が好きだった。遊んでくれるし、お腹が減ったら御飯を持って来てくれる。
だからワタシはその人達の言う事を聞いたんだ。初めてお外に出して貰えた時は、嬉しかった。
お外に出る時、どうしてか分からないけど「目を閉じてて」。そう言われてその人達と一緒に何処かへ行った。
「目を開けて」。そう言われるとすぐワタシは目を開ける。一面、真っ赤だった。
広くて、天井が高くて、それから誰かが中で見てる変な所が上にあって。
その中では色んな人が、ワタシが大好きなケチャップみたいなもので汚れて倒れてた。でもケチャップと違うのは、臭い。
でも、ワタシは笑った。だって皆遊んでると思ったから。
その真っ赤な中で、倒れてない何人かの人達が遊んでた。ワタシの知らないピカピカのオモチャで。そのオモチャは、その中の誰かに当たるとケチャップみたいなものを浴びてもっと綺麗になった。
ワタシは何故かすごくワクワクした。ワタシもアレで遊びたい。あのピカピカの何かがすごく欲しい。
だからワタシは隣に立ってる人に言った。「ワタシもアレで遊びたい!」
そう言うと、その人はニッコリ笑って同じものをワタシにくれた。すごく嬉しい!
「行って一緒に遊んで来なさい」。ワタシは言われてすぐに遊んでる人達に混ぜてもらった。
ピカピカのそれで触れたり、叩いたりすると、遊んでる人達はうるさくなった。だからワタシは止める為にもっともっとやった。
しばらくして皆動かなくなっちゃった。静かになって、それでピカピカはすごく綺麗になって。ワタシは嬉しかった。
もっと遊びたいな。そう思って、ワタシは隣で倒れてる人にピカピカを刺した。
動かなかった。何故か嫌な気分になって、ワタシはその人を刺し続けた。赤いのがいっぱい出たけど、どうでも良かった。
気付いたら、白衣を着ている人達に止められて、ワタシはいつの間にかあの真っ白な部屋に戻されてた。白いのがすごく眩しくて、気持ち悪くなった。
つまんないから寝転がってたら、白衣を着た人達が入ってきてこう言った。
「おめでとう。君は最初で最後の『成功者』だ」
何を言ってるのか分からなかった。だけど嬉しかった。そして、どうしてか怖かった。
でもいいんだ。ワタシは、この人たちが大好きだから。
ワタシは、何度もあの真っ赤で広い所で遊んだ。始めは楽しかったのに、ワタシは赤と、ピカピカと、嫌いになってきた。
すごく怖い。だけど、同じ事をずっとずっと繰り返した。
刺された人達は皆苦しそうだった。ワタシもああなったら嫌だな。だから、ワタシは嫌だけどずっと遊び続けてた。
そしたらね、どうしてだろう。
何も感じなくなっちゃったんだ。
第一話
「自業自得・・・って奴だから、多分」
ぽつりと一つ呟き。そして、その呟きの持ち主は今まで読んでいた新聞を畳み、自らの座るベンチに置く。
彼は顔を上げ、自分の目の前に聳える巨大なビルを見上げた。暖かく吹く風に、茶色のフサ毛がのどかに揺れる。
物憂げにビルを見上げている彼の名は、ルドルフ・フッサール。長毛種の猫型AAである。そしてこのビルは彼の勤める大企業、「マルディアス」の本社である。つい最近社長が何者かに殺害され、社内も含め内外が大騒ぎになっている。
「あんな社長だったしな・・・そりゃ恨まれるか」
ルドルフは思い出せる限りに社長の顔を思い出す。ルドルフは単なる平社員ではあるが、社長の顔くらいは知っていた。名は「マニール・ワード」だったか。経済界では相当悪名名高い人物であったらしい。
凄まじい勢いで企業を成長させたマニールであったが、そこに恨みを買われる要因を作ったのだろう。気付けば彼は殺され、今では社内の平社員達に仕事は無く、上層部やらのお偉方にばかり責任や重圧が回っているのであった。
「お陰で俺等平社員は仕事無しの上連日休日、と・・・」
つまらなそうにルドルフは大きく欠伸をし、目から漏れた涙を拭う。仕事ばかりで忙しかったはずの日常に唐突に暇が出来ても、やる事などそうすぐに出来るものではない。
「・・・久々にギコル達と遊・・・ぶっつってもアイツらもこの時間は仕事・・・か」
同年代の友人は勿論皆仕事である。普段ならこの時間帯はルドルフとてデスクワークであり、やれる事は本来無いのだ。
「・・・腹減ったな」
いつもは忙しいからと言って朝は何も食べないルドルフであったが、暇が出来た途端体が空腹を認識し始めた。やる事も無いし、丁度良いから。ルドルフはベンチを後にし、マルディアスの正面玄関の巨大な自動ドアをくぐり、食堂に向かう。
だだっ広い社の正面玄関内。誰も居なければ、これほどに無駄な空間は無いと言えよう。
そしてやはり皆騒ぎの収拾を図ろうとしているのであろう。食堂に居る者はまばらで、むしろここまで来る時にすれ違った様々な表情のAAの方が断然多かった。エレベーターは引っ切り無しに動き、非常階段を使っている者も少なくはなかった。
正面に見えるエレベーターから脇にそれた場所に位置する食堂。その内部は広く、大抵何処でも空いていた。が、ルドルフは奥まった所に居るある人物を見、その人物が座るテーブルに向かう。
「よっ。タカラ。上の方が忙しそうだな」
タカラと呼ばれた青い猫型AAは読んでいた新聞から目を離し、顔を上げる。笑ったような目をしているが、彼はいつもこれで普通だ。
「あ・・・先輩。どうしたんですか?今日は休みのはずじゃ?」
タカラは眉をひそめて訝しげな顔をする。ちなみに彼はルドルフより立場が上。多少ではあるのだが、そのせいで彼もまた社長死後の尻拭いをさせられているのだ。
「ああ・・・色々あってな。それとその先輩ってのやめて欲しいから。ここじゃお前の方が上だろ?」
ルドルフは苦笑いしながらそう言う。タカラはルドルフと同じ学校出身で、一つ年下の後輩。だが実力で勝っているのはタカラだったらしく、短期間で彼は上層部に食い込んだ。タカラはその事を気にしているのであろうか、常にルドルフを先輩と呼ぶ。
勿論、そう呼ばれているルドルフはそんな事どうでも良いのではあるのだが。
「いえ・・・でも何か悪い気がして。それはそうと、結局何故ここに居るんです?」
ルドルフはため息をつきながらタカラの向かいの椅子に座る。
「いや、何だか知らんが連絡があるんでとりあえず今日も来いって事で。来てみたら連絡事項の一つ二つだけ。勘弁して欲しいから」
「大変ですね・・・僕も今休憩時間ですよ。全く、社長も嫌な時期に死んでくれたもんです」
何気に黒いなコイツ。そんな事を思いながらルドルフは注文を取りに来たウェイターに「カレーライスで」と一言注文を入れる。
「朝から良くそんな重いもの食べようと思えますね・・・」
そうか? と首を傾げるルドルフ。それに対しブラックコーヒーとトースト一枚のタカラ。言ってしまえばどちらも不健康なのだが。
「・・・先輩は知ってますか?社長が殺された理由」
唐突に何を・・・ルドルフはそう思ったが、聞かれたのだから答えないという訳にも行くまい。
「知っちゃいないけど、予想はつくから。大方ここを成長させすぎた、そんなモンだろ?」
タカラはそれを聞くと、口元にニヤリと笑みを浮かべた。
「まあ世間一般にはそういう風な噂が流れてますね」
違うんかい。予想が外れた事に顔を顰めるルドルフを横目に、タカラはメモ帳らしき物を胸ポケットから出し、その文面を読み始める。
「えー・・・と、ハイ。『サンプル関連に関して邪魔な取締役の殺害に成功。しかしその際サンプル-2は暴走。しかし予定通り、内部崩壊の第一ステップ成功。重要なサンプルは失ったが、天秤にかければ重さは同等と言った所だろう。なお、サンプルは火急的速やかに破棄すr・・・』」
ルドルフは目を見開いていた。予想と180度違う。いや、と言うより予想だにしなかった事実が飛んできたのだから。
「・・・何処で手に入れたんだ、それ」
タカラの持つメモ帳を指差し。ルドルフは恐怖の入り混じる声で質問する。
「これですか? たまたま資料探ししていたら大会議室の前に落ちていたんです。で、こんな風に書かれていて」タカラはルドルフに手帳のオモテ表紙を見せる。まるで子供の遊戯の代物のように、大きく『丸秘』と印が押されていた。
「誰だって気にしますよね、アハハ」
笑っている場合なのだろうか。もしかしたら自らの身とて危うくするのかもしれないというのに、タカラは軽い調子で笑っている。
「・・・いや、もしかしたらそれだって悪戯かも・・・」
「残念。今度は裏です」
今度は裏表紙。流石にルドルフも「これは間違いなく重要なものだ」そう思ったが、それと同時に吹き出してしまった。
「なっ・・・ちょっ・・・名・・・前・・・・・アハハハハハ」
空笑いだか何だか分からない声をルドルフは上げる。背表紙にはご丁寧に名前。そして記された名は副社長のもの、『ニドルァー・チョンニーダ』。どう見ても副社長の所有物であった。
「どう見ても副社長の物です。本当にありがとうございました。アハハー」
タカラはケラケラ笑いながら手帳を胸ポケットに戻し、ブラックコーヒーを一息に飲み干す。
「ね、分かったでしょう。社長はどうやらこの『サンプル』とやらの関係で殺害されたようです。とりあえず、このメモ帳が更に上層部に食い込む切っ掛けに成り得るかもしれません」
タカラはいつに無く強い意志を語調に含めていた。ルドルフも見た事の無いその意志が感じられる顔。その意志の裏には、隠された何かがあるのだろうか。
「・・・タカラ。まさか、『アイツ』の事まだ・・・」ルドルフは思い付いたかのように言う。
「ええ、諦めてません。僕は簡単にチャンスを手放すほど弱い復讐心なんて抱きませんよ。勿論」
タカラは振り返り、ルドルフを真っ直ぐに睨む。感じられるのは、鋭く研ぎ澄まされた憎悪。
ルドルフは睨みに対峙しながらも。いつの間にか届いていたカレーライスを平然と口に運んでいた。ルドルフ以外が睨まれれば、大抵の者は臆し、目を逸らさずにはおれないであろう。
「例え、いかに親しい人物が『あの人』の事に関わっていたとしても・・・僕は・・・・・・」
そこまで言うと、タカラはパッといつもの明るい笑顔に戻った。
「まあ、随分前から貴方の疑いは晴れてますけどね、アハハ」
だったら睨むな。そう言った感じの睨みを返しながら、ルドルフはカレーを次々口へ運んで行く。
「あ、それとこの話。内外含め誰にも話しちゃダメですからね?」
分かってるから。ルドルフは最後の一口を口に含みながらそう言ったが、言葉になっていなかった。
「アハハ。では僕はこれで。先輩もお気をつけて。いつ誰が自分を狙っているか分かりませんからね」
「ああ。こんな平社員を狙うような奴も居ないだろうけど、一応気をつけるから。と言うより、その忠告そのまんまオマエガナー」
地位も立場もタカラの方が上。おまけにその手の内には手帳に記された秘密の数々。狙われる危険性はタカラの方が断然に高い。
「ええ、殺るのはこちらなんですからね・・・ハハ」
ルドルフは涼しい顔をしてタカラを見つめる。奴は本気だ。だが、止める権利が自分に無いのは分かっている。それに、止めたって止まらない奴なのも知っている。
「とにかく・・・お互い気をつけましょう。命あっての今ですからね」
「おう。気をつけろよ」
と、ルドルフはタカラが立ち去ろうとすると同時に立ち上がる。皿は既に綺麗に真っ白だ。
「・・・相も変わらず早食いですね、先輩。流石いn」そう言いかけた瞬間ゴツンという鈍い音。
「・・・・・・狼だから」
口元には笑みがあったが、確かに青筋が入った顔に、タカラは殴られたのにも関わらずヘラヘラと笑うのであった。
「・・・あー・・・明日は土曜・・・・・・か。明日位なら暇な奴も居るだろ・・・・・・しかし寒い」
小さなその声は、暗闇に満ちる静寂に飲まれ、すぐ消えて行く。響くのは、土の上を歩く靴の音だけ。
無機質な街頭の照る公園を歩くルドルフ。春先ではあるが、冬の余韻残る夜風は冷たく、毛の合間をぬって地肌に直接冷気を送る。早く暖かくなって欲しいから。ルドルフは、薄い雲に覆われる霞んだ月を見上げながらそう思っていた。
結局やる事も無く、タカラと別れた後は夕方過ぎまで適当な施設を巡り、ビデオを借りたり、或いは図書館で本を借りたり。全く以って暇人全開だ。車を持たぬルドルフであるから、歩き回る内にすぐ陽は沈んでしまった。
そして現在が帰路、と言う訳だ。誰も居ない暗い公園を一人歩く青年。格好によっては変質者と間違われてしまいそうだ。
「独り身は辛いから・・・うぅ」
家に帰っても、待っているのは前以って沸かしておくタイマー式の風呂と炊飯器の米達。そんな温もりじゃない。俺が欲しいのは人肌、そう、俺を想う彼女の・・・・・・と、訴えたくなるルドルフであったが、訴える相手も周りには居ない。
とっとと帰ろう。泣けてくる考えを頭の隅に追いやり、ルドルフは見上げていた月から視線を下ろす。
直後、ルドルフは数メートル先に人影がある事に気付いた。
こんな所に居るとすれば、家を持たぬホームレスか、皆の寝静まった頃に出てくるアベック位のものであろう。警戒一つせず、ルドルフはそのまま脇を通り過ぎようとする。
が、その足は人影がはっきりと認識できる距離に近づいた時点でストップした。
「・・・・・・女・・・の子?」
人影は予想していたいずれとも異なっていた。ルドルフの瞳に映るのは、か細い少女、小さな赤いAAの姿。
少女は身動き一つせず、身を切る夜風にその素肌を、何と裸で晒している。ルドルフは微妙に頬を赤らめながら、顔を落とし、自らの膝に顔を埋める少女の肩に手をやった。体温は確かにあった。だが、冷たい。
「おい・・・・・・こんな所で何やってるんだ? 寒くないか?」
肩に手が触れてしばらくすると、少女はゆっくり顔を上げた。ルドルフはたじろぐ事無くその少女の目を見返す。こういう時、挙動不審になる方がかえって失礼だと思ったからだ。
少女は、まるで意志を持たぬかの如く虚ろな瞳をしていた。歳はルドルフより少し下くらいであろうか(ちなみにルドルフは19である。優秀であれば彼の勤める社に歳など関係ないのだ)、幼さの残る顔。それに反すように、目に意志が宿れば強い光になるであろう蒼い瞳。そしてその蒼い瞳に双鉾を成すかのような紅き肌を蒼白に近い桃に染め、彼女もまたルドルフを真っ直ぐに見返していた。
「・・・何があったんだ?」
ルドルフは怯えさせぬよう、優しげな語調で聞く。何も感じていないのか、少女は震えてすらいなかった。
「・・・・・・貴方は・・・違う・・・・・・貴方じゃない・・・・・・私・・・やらなきゃ・・・・・・」
全く以って意味不明な事を言うと、少女は急に立ち上がる。無垢な体が露わになったが、少女は意にすら介しておらぬようだ。
「ちょっ・・・・・・ちょっと待て! そんな格好で何処に・・・じゃなくてとにかく・・・ああもう!」
ルドルフは顔を真っ赤にしながらも自らのコートを素早く脱ぎ、歩き出そうとしていた少女の肩にかけるように着せる。唐突に、少女は動きを止め、自らの羽織るコートを不思議そうに触った。
「・・・・・・暖かい」
「そりゃそうだろ。俺が着てたんだk・・・じゃなくて。君は一体何者なんだ? どうしてこんな所にそんな格好で・・・・・・」
隙、と言うか丁度動きを止めた少女の前に回り、ルドルフは早速質問をぶつける。
「私・・・私は・・・・・・やらなきゃ・・・・・・ぁ!」
ルドルフの手を押しやり、少女はまた歩き出そうとする。が、お決まりの如く少女はバランスを崩し、倒れそうになる。
「いきなり動くから・・・と」
ルドルフは予見していたかのように少女を素早く支える。少女の体はやはり冷え切っている。相当長時間野外で冷たい風を受けていたのだろう。
「わた・・・し・・・・・・」
一人称を呟くか呟かないか。少女は静かに意識を失ってしまった。一瞬ルドルフは焦ったが、このままにして置く訳にも行くまい。その意志が、次に取るべき行動をルドルフに思い出させていた。
「・・・・・・とりあえず、体暖めてやんないとな」
向かうは家。待ち受けるは暖かい風呂と食されるのを待つ白米達。疲れた体には持って来い、そして冷たい体を温めるのにも。
「・・・給料良くて良かった。ホント」
平でも給料の良い所に勤めていて良かった。これが貧乏会社であったらどうなった事か。普段は考えぬような事を切実に思うルドルフなのであった。
私は、生まれてこの方生温い温もりしか知らなかった。
その温もりとすら呼びがたい温もりを身に受け、何か感じていたのはその温もりを知った頃くらいだった。
生温さから伝わる何かは、どうしようもない苦しみと悲しみみたいなもの。
でも、分からなかった。何がその生温さに秘められているのか。何の意味があるのか。
もう感じたくない、その生温さ。感じていた全てを否定したら、私は何も感じなくなった。
人の死をまともに直視しても、私は何も感じなくなった。
何故なら、私は・・・・・・。
頭の中に、声が響く。
近くに居る、その声の持ち主達。目を開けると霞んだ視界が開け、次第にはっきりしてくる。
「もう。いくら女の子が私しか居ないからって・・・・・・」
「ごめんごめん。ガナールくらいしかこの時間帯に暇そうな娘居そうに無かったから・・・・・・」
誰だろう。節々痛む体を起こし、自分の置かれる状態を確認する。今居るのはベッドの上、そしていつの間にか着せられているサイズ違いの淡い桃色をした服。ここは・・・何処?
「ん。気が付いたみたいよ、彼女」
体を起こした目線の先には、二人のAAが居た。ルドルフと、オレンジの体色をし、大きな黒い目に特徴的なまつ毛を生やした少女。
「・・・ここは・・・?」
彼女の口を突いて出た第一声であった。
「安心して欲しいから。ここは俺の家。あ、ちなみに名前はルドルフ・フッサール」
「そして私はガナール・モナル。このワンちゃんの友達よ」
一瞬ルドルフが笑顔でガナールの方を睨もうとしたが、逆にガナールの笑顔に気圧され、表情を戻す。
「私・・・は、ツィーナ・メルティ。・・・・・・それ以外、覚えてない」ツィーナはそこまで言うと目を細め、顔を軽く落とす。
「記憶が無いのか・・・・・・?」
ルドルフは更に質問しようと口を開きかけたが、それはガナールの手に遮られる。
「ダメ。休ませてあげようよ。・・・・・・ツィーナ、ね。分かった。・・・とりあえず、ここでゆっくり体を治して、それから自分が何をすべきで、一体何者なのか、じっくり考えると良いよ。無理したら体に悪いから、ね?」
ガナールの優しい言葉に、ツィーナは少し安心したような表情をし、ゆっくりと頷いた。
「・・・意外とこういう事慣れてる感じだから、ガナール。あんな兄貴と違って」意外そうにルドルフは言う。
「あら、お兄ちゃんと私は違うわよ。それに、これでも看護学校生なんだから」
意外に俺よりしっかりしてそうだな。そう思ったルドルフであるが、第三者から見ればガナールの方が間違いなくしっかりしている。
「私・・・・・・」
何か言いかけるツィーナだったが、探し出したつもりの言葉が空回りしたらしい。言葉に詰まり、ツィーナはまた顔を落とす。
「慌てなくてもいいから、ね。今は休む方が大事」
ガナールに促され、ツィーナはまたベッドに横になる。数分後、聴こえて来たのは小さな寝息。
「・・・よし、と。一通り私がやるべき世話は終わったかね、ワンちゃん?」
ルドルフが反論出来ないのを分かって、ニヤニヤしながらガナールはからかい混じりの質問をする。
「だから狼・・・・・・ああ、まあ大体は終わったと思うから・・・」
「ん、よろしいっ」
ガナールはニッコリすると、ベッドの脇に置いてあるカバンから色々引っ張り出す。その大半は服、そして残りは生活用品等々。
「ハイ。コレ全部あの娘用。私のだからサイズがちょっと・・・じゃなくて結構違うかな。とりあえず、何かあった時は私に。それから足りない物があったらちゃんと買い足して行ってあげてね。そ・れ・とっ!」
適当に頷きながら各々の物を受け取り、早速何処かに収納しようとしていたルドルフをガナールが止める。
「あの娘に手なんか出したら、同じ女として私が制・裁するからね」
またまたニッコリするガナール。だがその笑顔に何が隠されているかルドルフはしっかり知っている。タカラの時とはまるで違い、縮こまりながらルドルフはこくこく頷いた。
「分かればよろしいっ。それじゃあ、私は帰るからね。お兄ちゃんが帰って来る前に帰らないと、あの人心配するから」
あのシスコン野郎め。ルドルフはガナールの兄、モナスの顔を思い浮かべながらニヤリと笑う。
ガナールはまさしく元気印の女の子だ。それに反して、心配性すぎるのがたまに傷のモナスという兄を持っている。近い兄妹の為か、仲も良いのではあるが、どう見ても妹の方がしっかり者の上、心配される玉でも無い。
「あ、ガナール」帰りかけていたガナールをルドルフは寸前で止める。
「わざわざ来てくれてありがとうだから。それと、モナスにはこの事言わないで欲しいから。アイツまたうるさくしそうだから」
モナスの優しさを十分に知っているルドルフだからこそ、また心配させたくない。以前ルドルフが事故で骨折した時、ほとんど毎日と言って良いほど見舞いに来ていたからだ。
「心配しすぎると自分が体壊すから」
「うん分かった。ルドルフも結構心配性だと思うけどねー」
ルドルフの言葉にガナールは頷き、踵を返してまた玄関に向かって行く。家を出る直前、ガナールは一言残し帰って行った。
「それが良い所なんだけどね」
ガナールが去った後、ルドルフは誰も聞いていないのに一言呟く。
「そりゃどうも・・・・・・だから」
彼自身、相当な心配性である事ははっきりしているのであった。