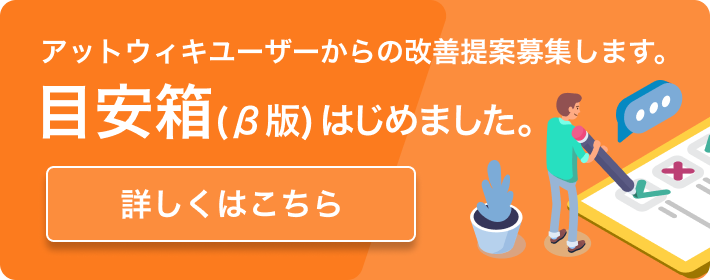月が美しい夜の事だった。
一人の男が悲しそうに微笑んでいた。
「僕の予想は外れてはいなかったのですね」
男の視線の先には、同じく悲しそうに微笑んだ顔をした女がいた。
体中には沢山の傷があり、そして美しい瞳を持った妙齢の彼女。
「タカラ、貴方にはまだやるべき事があるでしょう?
見逃してあげるから早くここから逃げなさい」
タカラと呼ばれた男は無視して女に近づいていく。
彼らの距離は後僅か数歩だった。
「貴方は死にたいの!? 私は殺人鬼なのよっ!! わかる? 私は人殺しよ!!?」
女の手には鋭いナイフが握られてあった。
すでにそのナイフは赤黒い血に染められてあった。
「あはは、スイマセン…。貴方は僕を殺さないという確信があったので」
手を伸ばせば届く距離ぐらいで立ち止まり、男は言う。
男はそれだけ言うと、じっと女の目を見つめた。
女はそんな視線を拒絶するかのようにナイフを構えた。
「あっは! 馬鹿じゃないの? この血、誰のだか分かる?
私の母親の血よ? ……私は貴方も殺せるわ」
女は視線を逸らしまるで自分に言い聞かせるように言った。
「………ならばどうせいつか僕は死ぬから、貴方の手で殺して欲しいです」
男は切なそうに顔を歪め、女の血で濡れた手を取った。
そして祈るような目で彼女を見つめた。
それは彼が初めて彼女に求めた事だったのだ。
「………」
女は男が何を言っているのか理解できなかった。
「お願いです。愛する貴方であれば死も恐くない気がするのです。
僕は貴方を愛してます。凄く酷い我侭だとは分かってますけど……」
男のその言葉がどれ程彼女に重く圧し掛かった事か。
男はそれまで女に愛の言葉を囁いた事がなかった。
それなのに今、愛すると言う言葉を使った男が女は憎かった。
気づかぬうちに流れてきた涙が頬を濡らす。
言葉だけが全てじゃないとは女にも分かっていた。
けれども一度は言葉に表して欲しかった。
女は人生一番の幸福の中で人生最悪の絶望を感じていた。
涙を拭き、無理に微笑んで女は言った。
「私たち、誰もいない所に逃げられればいいのに」
‐‐‐
二人が出会ったのは5年前、雪が降る寒い夜だった。
タカラは昔から心臓が悪かった。
もうそんなに長く持たないだろうと言う事も聞かされていた。
小さい頃から病院の中で暮らしていたタカラは外の世界に憧れていた。
自分と同じ年の子はもう中学に行っているであろう。
しかし自分は小学校さえも満足に通えなかった。
家こそは裕福だが、親はこんな自分を荷物扱い。
「……最後に外に出て見たのはいつでしたっけ」、とポツリと呟いてみた。
その言葉を口に出した瞬間、外に出て見たいと言う気持ちが強くなった。
しかし、自分の体じゃあ寒い外でずっといたら大変な事になるだろう。
タカラにはそれが分かっていた。
だが、一生ここから出られないかも…という想像をしたら、
堪らなく恐くなったのだ。
苦い薬を我慢して飲み、苦痛だらけの治療を受け続ける。
「………いやだ、僕は!」
今のタカラの頭には「ここから逃げ出したい」と言う事しかなかった。
今は深夜。多分出てもばれないだろう。
もし見つかっても何とか誤魔化せばいい。
タカラは服を暖かく着込み逃げるようにして病室を後にした。
…外は雪が積もっていた。
これだけ着込んでもまだ寒さが身を刺す。
乱れた呼吸を整え、タカラは辺りを見回した。
「綺麗…ですね」
白い雪で覆われた世界。
タカラは久しぶり過ぎるこの景色に感動を覚えた。
出来れば病院という狭い世界から逃げ出して、
この美しい世界の中でずっと居たかった。
しかし、外に出てほんの少ししか経ってないのにタカラは
自分の体が可笑しい事に気づく。
「っはぁ、はっ……心臓が………っ」
冷たい空気を吸い過ぎたのだろうか?
段々と目が霞んできた。
嗚呼、自分の体はここまで弱っていたのか。
「…くっ、はぁ……あはは、どうせ病院にいたって治りはしないんだ」
こんな時間帯。周りに助けてくれる人など居ない。
ほんのちょっと長く生きてあんな窮屈な所で死ぬくらいなら、
今この広くて美しい所で死にたい。
タカラは適当なベンチに座りこみ、小さく乱れる息を吐く。
(――――ああ、段々と眠くなってきちゃいましたねぇ。
このまま寝ちゃえば僕も楽になれるでしょうか?)
体温が奪われてるのが分かる。
頭もくらくらするし、心臓も破裂しそうに痛い。
しかしタカラはそんな事はどうでもよかった。
タカラはそっと目を閉じ、襲い掛かる睡魔に身を預けた。
‐‐‐
「……今年も結構寒いわね」
一人の女が呟く。
見た目は童顔なのだが妙に落ち着いた雰囲気を持った女性だった。
寒いのが苦手なのだろうか、ぶつぶつと文句を言いながら歩いている。
彼女は今、深夜の仕事帰りに急いで母の家に行っている途中だった。
母親がまた、泣いているらしい。
彼女の家は母子家庭だった。
今は彼女も大人になって一人暮らしをしているが。
ある日の事である。
父親は他の女と金を持って逃げて、幼い彼女とその母親は取り残された。
その日を境目に彼女の母親は欝病に罹ってしまった。
一人でいると不安らしい。
ちょっとした事で泣き出したり、イライラしたりする母親を彼女は必死で支えている。
玄関の鍵を開けようとしてふ、と思う。
自分はいつまでこんな事をしなければいけないのだろうか。
彼女は勉強が好きだった。
しかし、金銭問題や母親の状態などで大学までは行けなかった。
医者とゆう自分の夢も追えなかった。
高校を卒業した後はすぐに就職した。
必死で働いて、必死で母親を支えた。
嗚呼、これは違う。 自分が望んだのは-…
飾り気のない部屋に入るとそこに母親はいた。
目は虚ろで生気のない顔をしている。
彼女は小さくため息をつき、肩にかけていたバックを下ろす。
「お母さん、どうしたの? 今日はなんでまた元気がないの?」
母親は顔を横に振るだけで返事をしてくれない。
「…お母さん?」
徐徐に母の目に涙が溜まっていくのがわかる。
嗚咽をしつつ、肩を小さく震わせる母親を見て、
彼女は優しく抱きしめるしかなかった。
どれだけ時間が流れたのだろうか、母や落ち着きを取り戻していた。
「……お母さん、ね。お父さんの夢を見ちゃったの。あの人幸せそうだった」
母はそれだけを言うと儚く笑い部屋を後にした。
彼女はその母の笑顔を見て、少し泣いた。
最近目に見えて痩せてしまった母の為に手料理を作って家を出る。
もうこんなに遅い時間だ。
人気の無い道を小走りで進む。
そして道のベンチに人が寝そべっている事に気づく。
可笑しい。
こんな寒い冬の日に外で寝たらどうなるか馬鹿でもわかるのに。
女は怪訝そうな顔をしてベンチに近づく。
そこには少年がいた。
年は14か15ぐらいだろうか。
服を暖かく着込んでいるが、やはりそれでも相当な寒さを感じるだろう。
とりあえず、その少年を起こしてみる事にする。
「おーい、君! そんな所で寝てたら凍え死んじゃうよ?」
肩を揺さぶってみるが反応がない。
「聞こえてるー? ……ったく、最近の若い子は」
呆れてそのまま立ち去ろうとしたが、
もしも死んだりなんかしたら…と思うと置いていけなかった。
しかし、いくら少年とは言え女の彼女よりは体が大きい。
「うー重いー。ああ、もう!! こんな所で凍え死にさせはしないわよ!! …たぶん」
彼女は必死に少年を担いで家まで歩いていった。
一人の男が悲しそうに微笑んでいた。
「僕の予想は外れてはいなかったのですね」
男の視線の先には、同じく悲しそうに微笑んだ顔をした女がいた。
体中には沢山の傷があり、そして美しい瞳を持った妙齢の彼女。
「タカラ、貴方にはまだやるべき事があるでしょう?
見逃してあげるから早くここから逃げなさい」
タカラと呼ばれた男は無視して女に近づいていく。
彼らの距離は後僅か数歩だった。
「貴方は死にたいの!? 私は殺人鬼なのよっ!! わかる? 私は人殺しよ!!?」
女の手には鋭いナイフが握られてあった。
すでにそのナイフは赤黒い血に染められてあった。
「あはは、スイマセン…。貴方は僕を殺さないという確信があったので」
手を伸ばせば届く距離ぐらいで立ち止まり、男は言う。
男はそれだけ言うと、じっと女の目を見つめた。
女はそんな視線を拒絶するかのようにナイフを構えた。
「あっは! 馬鹿じゃないの? この血、誰のだか分かる?
私の母親の血よ? ……私は貴方も殺せるわ」
女は視線を逸らしまるで自分に言い聞かせるように言った。
「………ならばどうせいつか僕は死ぬから、貴方の手で殺して欲しいです」
男は切なそうに顔を歪め、女の血で濡れた手を取った。
そして祈るような目で彼女を見つめた。
それは彼が初めて彼女に求めた事だったのだ。
「………」
女は男が何を言っているのか理解できなかった。
「お願いです。愛する貴方であれば死も恐くない気がするのです。
僕は貴方を愛してます。凄く酷い我侭だとは分かってますけど……」
男のその言葉がどれ程彼女に重く圧し掛かった事か。
男はそれまで女に愛の言葉を囁いた事がなかった。
それなのに今、愛すると言う言葉を使った男が女は憎かった。
気づかぬうちに流れてきた涙が頬を濡らす。
言葉だけが全てじゃないとは女にも分かっていた。
けれども一度は言葉に表して欲しかった。
女は人生一番の幸福の中で人生最悪の絶望を感じていた。
涙を拭き、無理に微笑んで女は言った。
「私たち、誰もいない所に逃げられればいいのに」
‐‐‐
二人が出会ったのは5年前、雪が降る寒い夜だった。
タカラは昔から心臓が悪かった。
もうそんなに長く持たないだろうと言う事も聞かされていた。
小さい頃から病院の中で暮らしていたタカラは外の世界に憧れていた。
自分と同じ年の子はもう中学に行っているであろう。
しかし自分は小学校さえも満足に通えなかった。
家こそは裕福だが、親はこんな自分を荷物扱い。
「……最後に外に出て見たのはいつでしたっけ」、とポツリと呟いてみた。
その言葉を口に出した瞬間、外に出て見たいと言う気持ちが強くなった。
しかし、自分の体じゃあ寒い外でずっといたら大変な事になるだろう。
タカラにはそれが分かっていた。
だが、一生ここから出られないかも…という想像をしたら、
堪らなく恐くなったのだ。
苦い薬を我慢して飲み、苦痛だらけの治療を受け続ける。
「………いやだ、僕は!」
今のタカラの頭には「ここから逃げ出したい」と言う事しかなかった。
今は深夜。多分出てもばれないだろう。
もし見つかっても何とか誤魔化せばいい。
タカラは服を暖かく着込み逃げるようにして病室を後にした。
…外は雪が積もっていた。
これだけ着込んでもまだ寒さが身を刺す。
乱れた呼吸を整え、タカラは辺りを見回した。
「綺麗…ですね」
白い雪で覆われた世界。
タカラは久しぶり過ぎるこの景色に感動を覚えた。
出来れば病院という狭い世界から逃げ出して、
この美しい世界の中でずっと居たかった。
しかし、外に出てほんの少ししか経ってないのにタカラは
自分の体が可笑しい事に気づく。
「っはぁ、はっ……心臓が………っ」
冷たい空気を吸い過ぎたのだろうか?
段々と目が霞んできた。
嗚呼、自分の体はここまで弱っていたのか。
「…くっ、はぁ……あはは、どうせ病院にいたって治りはしないんだ」
こんな時間帯。周りに助けてくれる人など居ない。
ほんのちょっと長く生きてあんな窮屈な所で死ぬくらいなら、
今この広くて美しい所で死にたい。
タカラは適当なベンチに座りこみ、小さく乱れる息を吐く。
(――――ああ、段々と眠くなってきちゃいましたねぇ。
このまま寝ちゃえば僕も楽になれるでしょうか?)
体温が奪われてるのが分かる。
頭もくらくらするし、心臓も破裂しそうに痛い。
しかしタカラはそんな事はどうでもよかった。
タカラはそっと目を閉じ、襲い掛かる睡魔に身を預けた。
‐‐‐
「……今年も結構寒いわね」
一人の女が呟く。
見た目は童顔なのだが妙に落ち着いた雰囲気を持った女性だった。
寒いのが苦手なのだろうか、ぶつぶつと文句を言いながら歩いている。
彼女は今、深夜の仕事帰りに急いで母の家に行っている途中だった。
母親がまた、泣いているらしい。
彼女の家は母子家庭だった。
今は彼女も大人になって一人暮らしをしているが。
ある日の事である。
父親は他の女と金を持って逃げて、幼い彼女とその母親は取り残された。
その日を境目に彼女の母親は欝病に罹ってしまった。
一人でいると不安らしい。
ちょっとした事で泣き出したり、イライラしたりする母親を彼女は必死で支えている。
玄関の鍵を開けようとしてふ、と思う。
自分はいつまでこんな事をしなければいけないのだろうか。
彼女は勉強が好きだった。
しかし、金銭問題や母親の状態などで大学までは行けなかった。
医者とゆう自分の夢も追えなかった。
高校を卒業した後はすぐに就職した。
必死で働いて、必死で母親を支えた。
嗚呼、これは違う。 自分が望んだのは-…
飾り気のない部屋に入るとそこに母親はいた。
目は虚ろで生気のない顔をしている。
彼女は小さくため息をつき、肩にかけていたバックを下ろす。
「お母さん、どうしたの? 今日はなんでまた元気がないの?」
母親は顔を横に振るだけで返事をしてくれない。
「…お母さん?」
徐徐に母の目に涙が溜まっていくのがわかる。
嗚咽をしつつ、肩を小さく震わせる母親を見て、
彼女は優しく抱きしめるしかなかった。
どれだけ時間が流れたのだろうか、母や落ち着きを取り戻していた。
「……お母さん、ね。お父さんの夢を見ちゃったの。あの人幸せそうだった」
母はそれだけを言うと儚く笑い部屋を後にした。
彼女はその母の笑顔を見て、少し泣いた。
最近目に見えて痩せてしまった母の為に手料理を作って家を出る。
もうこんなに遅い時間だ。
人気の無い道を小走りで進む。
そして道のベンチに人が寝そべっている事に気づく。
可笑しい。
こんな寒い冬の日に外で寝たらどうなるか馬鹿でもわかるのに。
女は怪訝そうな顔をしてベンチに近づく。
そこには少年がいた。
年は14か15ぐらいだろうか。
服を暖かく着込んでいるが、やはりそれでも相当な寒さを感じるだろう。
とりあえず、その少年を起こしてみる事にする。
「おーい、君! そんな所で寝てたら凍え死んじゃうよ?」
肩を揺さぶってみるが反応がない。
「聞こえてるー? ……ったく、最近の若い子は」
呆れてそのまま立ち去ろうとしたが、
もしも死んだりなんかしたら…と思うと置いていけなかった。
しかし、いくら少年とは言え女の彼女よりは体が大きい。
「うー重いー。ああ、もう!! こんな所で凍え死にさせはしないわよ!! …たぶん」
彼女は必死に少年を担いで家まで歩いていった。