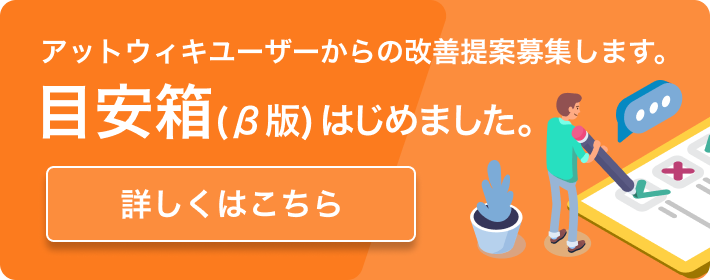・イントロダクション・
僕の名前はタンデム=ジェネシス。
モララー族とモナー族のハーフだが、僕はどちらかといえばモララー族の血が濃い。
モナー族の面影が残っているところはせいぜい右耳が白いことぐらいだろうか。
もう一つあったはずの耳は、生まれつきちぎれていて存在しない。
タンデムって、バイクの二人乗りのこととかを言うらしいけど、
僕の名前が今起こっていることを予め予測した上でつけられたものだとすると、何とも気味の悪い話だ。
今となってはそのことを恨もうにも恨めないし、恨んだところでどうしようもない。
…それに…「あいつ」にも悪気があるわけではないし、むしろ…「あいつ」の存在意義とかを考えると、
自分の方まで何だか…胸がいっぱいになるというか、そんな感じになる。
だから、僕は今の状況を決して悲観的には考えていない。
「あいつ」はとても変わった奴だ。
いつも一人で心の中に閉じこもっているようで、外の世界のことをよく知っている。
知っているかと思えば、逆に知りすぎて何かを悟ってしまっている。
まぁ、そういう奴でもないとあんな仕事は出来ないのかもしれないが。
…さて、こんなことをぐだぐだと話していてもしょうがない。
まずは僕と「あいつ」が出会ったところから話そうか。
第1話:「白い部屋の真ん中で」
そいつと出会ったのは数年前になる。
僕はいつものように街をプラプラと歩いていた。
世間的にいえば僕はいわゆるニートみたいなもので、一応アルバイトなどで食い繋いではいるのだが、みんな長続きはしなかった。
「…何でだろうなぁ…」
どうして自分がこんな退屈な世界に生まれてきてしまったのか、自分でもわからない。
そのことを思い起こす度に、僕はため息を漏らす。
考えるのも嫌だが、考えずにはいられないのだ。
「何言ってんの。退屈退屈って言ってる暇あるなら、少しはまともな職に就いたら?」
僕の隣に並んで一緒に歩いているのは、幼馴染みのサドネス。
「悲哀」の名に似合わず、彼女はいつもさばさばしていて、僕を引っ張っていってくれる。
どうしようもない僕にとって、それが唯一の救いみたいなものだった。
「んー、まぁ気が向けばそのうち」
「そんなこと言って…いつ気が向くかわからないでしょ? いいバイト紹介しよっか?」
「いや…今はまだいいや」
彼女は僕のためにと、よくバイトを探してきてくれるのだが、僕はそんな彼女の期待にいつも応えてあげることが出来ていない。
でも、そのことに関して彼女は文句ひとつ言わなかった。
僕としては、何か言って貰った方がいいのかもしれないけど。
「あ、そういえばさぁ。あんた『Sevence・Sign』って知ってる?」
「…何それ」
「知らないの? 裏の世界じゃあ有名な組織よ」
「僕は裏社会の人間じゃないからね。…また、じぃちゃんに聞いたの?」
「まぁね♪ そんなに詳しくは教えてくれなかったけどさー」
サドネスは、噂話がとにかく大好きだ。
どんなに小さな噂でも、例えそれがガセネタであっても、必死で飛びついていく。
そして、噂の真相を確かめるのが彼女の趣味であった。
「で? その『Sevence・Sign』って何?」
「詳細はわからないけど、『神々の刻印』っていう変な印を持っている人しか入れない組織なんだって。
活動内容は闇に包まれていて、探ろうとする者は一人残らずあぼーんされるとかいう話よ」
「へぇ、なかなか恐ろしい組織のようで」
「でしょ? 知りたいわぁ、謎の組織の秘密」
「…あぼーんされるかもしれないのに?」
「だから面白いんじゃない」
彼女はくすんだ色の空を見上げて、高らかに叫んだ。
「今もこの街のどこかで…組織の面々が活動しているのかもしれないのよ? 想像するだけでドキがムネムネしてくるわ!」
「はいはいわろすわろす…」
そんな当たり前のようで、でもどこか退屈な毎日。
それが僕の日常だった。
変化が訪れたのは、その日の夜からだった。
時々、軽い頭痛がするようになったのだ。
馬鹿は風邪をひかないというが、僕は一応自分が馬鹿じゃないと思っているので、翌日とりあえず病院に行ってみた。
だが病院のどの科を回っても、返って来る答えは「原因不明」ばかり。
なんてこった、と僕は思ったね。
原因がわかっていれば、多少は救いようがあるんだろうけど、僕にはそれがないのだ。
まるで、僕のどうしようもない毎日と同じだった。
僕が見る夢はいつも同じものだ。
どこまでも広がっている白い世界を、一人でひたすら歩き続けている夢。
周りには当然誰もいないし、道もなければ空もない。
歩いて行く先に何があるのかも知らない。
でもその日の夢は違った。
白い世界に、いつものように一人で放り出されて。
歩こうと腰を上げたその時、僕の前に初めて人影が立った。
「やあ」
そいつは、モナー族の男だった。
僕と同じように左耳はちぎれ、残った黄色い右耳には、包帯が乱雑に巻かれている。
三月ウサギが着ていそうな黒いマントを着込み、金色の金具で留めている。
金具の下からは意味もなく長いリボンが下がっていた。
「…お前は…?」
突然の来客に驚く僕に、彼は答えた。
「そうか、自己紹介もしていなかったね。ボクはダウト・レイジという。
ちなみにこの名前は自分でつけてみたんだ。どう? 格好いいかな?」
そう言って、彼は複雑な笑みを浮かべた。
これが、僕と「あいつ」の初めての出会いだった。
第2話:「前奏曲」
変な香具師だな、と思った。
今まで、コスプレイヤー以外でそんな変わったファッションをしているAAを見たことがなかったし、
単に三月ウサギの真似事をしているようには見えない。
それは、彼…ダウト・レイジの目線が真剣みを帯びているものだったからだ。
「…お前、どうやってここに来たんだ?」
「来たも何も、ボクは随分前からここに居た」
「え? だって今までは誰も…」
「それは、キミがボクを見ようとしなかったからじゃないのか?」
見ようとしなかったとか言う前に、誰も居なかったって。
そう言おうとした僕に、ダウト・レイジは大真面目な顔で言った。
「真っ白な世界だからって、何も見えない世界だからって、何もない世界と決めつけてしまうからそんなことになるんだ。
キミはそのことを忘れている。ボクが「居る」ということを想定しないでいたから、ボクの姿を見つけることが出来なかったのさ」
…よくわからない。
僕が呆気にとられていると、彼はため息をついて「別にわからなくてもいいよ」と言った。
「さて、キミは知りたいだろう?」
「何をだよ」
「ボクがどうしてここに居るのか、そしてキミの中にいつから居るのかを」
「…僕の中って…お前、もしかして僕の心の中にいる香具師なのか?」
「そう。なかなか察しがいいね」
ダウト・レイジはあっさりと頷いた。
突然夢の中に現れたと思いきや、僕の心に住む香具師だって?
…もう、何が何だかわからないことが多すぎる。
とりあえず、この状況になるまでの経緯を説明して貰うことにした。
「…OK、わからないことだらけだ。とにかく説明して貰えないかな」
「うん。まず大まかなことから説明しようか」
そう言って、ダウト・レイジはどっこいしょ、とその場に腰を下ろした。
「まず、ボクがどうしてキミの心に現れたかだ。正直言うと、ボクにも詳しいことはあまりわからない。
ただ、わかっているのはボクが『神々の刻印』の力を制御するために生み出された存在だということだ」
聞き覚えのある言葉に、僕は眉をひそめる。
「…『神々の刻印』って…『Sevence・Sign』のメンバーが持っているって噂の…?」
「そうだよ。よく知ってるね。あ、サドネス=エイデンに聞いたのか」
「何で僕がサドネスから聞いたって知ってるんだ?」
「さっき、キミの記憶を読んだばかりでね。最近の記憶だけしか読んでいないから、かなり昔のことについてはわからないが」
ダウト・レイジは話を続けた。
「キミは知らないだろうが、『神々の刻印』には神が残した強大な力が秘められている。
その力を全て手にすれば、世界を我がものに出来るくらいらしいんだけどね」
「…何か、かなり大層なものなんだな」
「うん。だから神はその力が悪しき者の手に渡ることを恐れて、刻印を七人の『守人』と呼ばれる
ガーディアン達に託し、守人達は何百年にも渡って刻印を守り続けた」
「ふーん……ん? 待てよ」
僕は彼の言ったことを頭の中で反復しながら、逆に尋ねた。
「そんなに強大な力があるなら、ガーディアン達が結束して、逆に世界を征服することぐらい簡単なんじゃないのか?」
「ふむ、それはなかなか的確なご意見だね。確かにその可能性はある。刻印の力を行使出来るのは、
基本的にガーディアン達だけだと言われているからね。あとは、刻印を作り出した神ぐらいのものだ」
「…それってヤバいんじゃ…」
「いいや。そのためにボクが居るんだよ」
ダウト・レイジはとんとん、と自分の胸元を軽く叩いた。
「具体的にどうするのかまでは言えないけど。とにかく、そのためにボクは肉体を得る必要があった。
だから、こうしてキミの中に居るわけだ」
「…えーと…要するにお前は…」
僕が何とか話をまとめようとすると、ダウト・レイジは薄く微笑った。
「ただの居候みたいなものだと思って貰えればいい」
「いや…流石にそこまでは…えーっと、ダウト・レイジ?」
「ダウトでいいよ。長いし、言いづらいみたいだから」
彼は立ち上がり、ぱちんと指を鳴らす。
すると今まで真っ白だった世界に、道が出来始めた。
「頼み事があるんだ。2つ」
「え? ああ…何?」
「ボクは自分の肉体がない。だから、時々でいいからキミの身体を貸して貰いたい。
キミの心から出て、仕事をしなくてはならない時もあるんだ」
「…それってもしかして、『よーしパパ身体乗っ取っちゃうぞー』って奴?」
「乗っ取る…のとはちょっと違う。貸して貰う時にはキミに一言声をかける。あとはボクが何とかするから」
道は伸びて伸びて、やがて一つの扉の前で止まった。
「それと、ボクがキミの身体を借りて仕事をする際に、少々手荒な真似をするかもしれない。
もしそれを誰かに見られて、キミがやっていると勘違いされたら、キミもこの街に居づらくなる。そうするとキミは困るし、ボクも困る」
「手荒な真似って…殺人とか?」
「出来ればしたくはないが…やるかもわからない。だから、ボクの今着ているマント。
これを適当でいいから見繕って来て貰いたいんだ。仕事の時だけ今の格好をすれば、キミが誤解を受けることもないだろう」
ダウトは言うだけ言って歩き出す。
行く先は扉。
僕も慌ててその後をついて行く。
その扉は真っ白に染まっていて、周りの空気に溶け込んでいた。
だが、その輪郭線だけは不気味なほどにはっきりと浮かび上がっている。
「さぁ、ここから外に帰れる。今日はもう帰りたまえ」
ダウトが扉を開ける。
途端、視界が白で塗り潰された。
さて、ここまでが僕とダウトが出会った日の話だ。
信じないのなら、それでもいい。
少なくとも僕が信じていればいいと思っているから。
次は…そうだな、初仕事の時のことでも話す?
とは言っても、あまり僕は覚えていないんだけど。
第3話:「裏路地の占い師」
最初はただの幻だと思っていたさ。
あの夢も、そのためだけにあったもので。
でも、そうではなかった。
「…サドネスが洋裁得意で良かったよ」
『おかげで買わなくて済んだね』
「そうだけど…『何に使うの?』って聞かれた時はマジでどうしようかと」
『でも納得してくれたじゃないか。「コスプレショーのバイトする」で』
「…それであっさり納得されるのもなぁ…」
僕は、ダウトから頼まれた衣装の制作をサドネスに頼んだ。
彼女は洋裁が大の得意で、頼まれれば何でも作ってくれるのだ。
そこで早速ダウトが夢の中で着ていた衣装を絵にして持って行ったというわけで。
が、何しろあの奇抜な衣装だ。
案の定「何に使うの?」と聞かれ、僕は咄嗟に「コスプレショーのバイト」と答えたのだ。
そんな苦し紛れな僕の答えにも、彼女は疑問一つ浮かべることなくあっさり納得した。
それは…ラッキーなのかもしれないけどさ。
『まぁ、いいんじゃないかな。結果オーライだよ』
「言い出したのはお前だろ…」
『ところで、彼女の腕は確かなのかい?』
「ああ、サドネスは裁縫と銃の腕は一流なんだ。料理は下手だけど」
『出来るだけ早めがいいな。今、この場で仕事に行かなくちゃならなくなった時に困る』
僕の隣でそんなことを言いながら、ダウトはぼんやりと宙を眺めた。
今、彼は上半身だけ半透明になって(僕以外のAAには見えないけど)表に出ている。
僕の身体を使わないで現実世界に干渉するのはこれが精一杯らしい。
「…あのさ」
『ん?』
「お前、僕の心に住んでる香具師だって言ったよな。じゃあ、僕の心そのものから生まれて、そのまま心の中に居たのか?」
『いいや、それは違う。ボクは誰かの手によってキミの心へ植え付けられた』
ダウトはあっさりと答えた。
だが僕はその答えに納得するどころか、さらなる疑問を抱いてしまう。
「…植え付けられた?」
『うん。言い方は悪いけど、寄生虫みたいな感じだね』
「それはちょっと言い過ぎじゃないのか?」
『そうかい? 似たようなものじゃないのかな。ボクの身勝手で、キミの命を危険に晒すことになるかもしれないんだから』
…何で、こういうことを真顔で言うかな。
ちっとも悲しそうな顔とかしないし。
「…それより、その植え付けたって香具師は誰なんだよ」
『それが思い出せないんだ。記憶が切り取られていてね』
「…切り取られてる?」
『多分、植え付けた側の処置だと思うよ。植え付けた側が誰なのかわからなくするための』
「でも…何でそんなことする必要があったんだ?」
『ボクに訊くなよ。ボクが知りたいぐらいなんだから』
はぁ、とダウトはため息をついた。
察してくれよ、とでも言いたいのか。
でも僕は彼のことをほとんど知らないのだから、許して貰いたい。
ダウトはしばらくまた虚空をぼんやりと眺めていたが、急にこちらを見て言った。
『…そうだな、ボクの知り合いにそのことを知っていそうな香具師が居るんだが、ちょっと行ってみようか』
街の裏路地にはほとんど入ったことがなかった。
今見てみると、結構色々な店や露店がある。
ここならバイトも簡単に見つかるかもしれないな、と僕はろくでもないことを考えた。
「ダウトに知り合いなんているんだ?」
『うん。ボクの覚えている範囲で、知り合いは数人居る。まともな人じゃないけどね』
「…まともな人じゃないって…」
『ああ、殺し屋とかそんなんじゃないよ。Vipperほどじゃないけど、世間からちょっとズレてる人達さ。あ、そこの角曲がって』
言われた通りにしばらく歩くと、一軒の寂れた店が見えて来た。
その道は行き止まりになっていて、その店以外は周りに何もない。
入り口の古ぼけた扉には、『占い』と書かれた看板がかかっている。
「…なんか、RPGとかに出てきそうな店だな」
『「モーラス伝」の「ソル・コーテフ」がやってる店に雰囲気が似てるとか、よく言われるらしいよ。
断じてインスパイヤはしていないって店主は言い張ってるけどね』
「ふーん…で、ここなのか?」
『うん。まぁ、入ってみてくれよ。入ればわかるからさ』
言われて、僕は恐る恐る扉を開けた。
ぎぃぃぃ…と独特の扉のきしむ音がして、薄暗い店内に光が差し込む。
店内には沢山の棚があり、難しそうな書物やヤバそうな占いグッズなどが置かれている。
僕はごくり、と息を呑み、中に入ると後ろ手に扉を閉めた。
再び店内に暗さが戻る。
その時、奥から関西弁口調で誰かの声が聞こえた。
「…いらっしゃいまし」
僕が辺りを見回すと、店の奥に一人の女性が座っているのが見えた。
高そうな着物を身に纏い、ヴェールのような薄い布を頭に被っている。
彼女の周りには寒色系の色の照明が灯っており、そこだけ妙に明るかった。
椅子はなく、彼女は座布団の上に座っている。
「よう来たな。何か用でっか?」
「あ、えーと…あの…用って言えば用なんですけど…」
彼女は言い淀む僕の顔をひとしきり眺めてから、もう一度尋ねてきた。
「…ほな、質問変えよか。兄ちゃん、『刻印殺し』背中にしょって何の用や?」
女性が布越しににやり、と笑った。
僕の隣で、ダウトが困ったような笑みを浮かべる。
『…相変わらずだね、のー』
「そりゃこっちのセリフやで、ダウト。久々に『目覚めた』割には…」
『いやいや、こっちにも結構な事情があるんだよ。前に会った時より、遙かに状況は変わっている。
キミなら既にわかっているだろうけどね』
「無論や。ウチにわからんことなんか無いで。アンタの未来も全部わかっとる。でも、今はアンタよりも…」
のーさんは、僕を指さして言った。
「…兄ちゃん、こっち来いや。アンタの運命占ったるわ」
第4話:「絶望を視る」
僕はあっけに取られた。
てっきりダウトの方を占うか何かすると思ったのに。
「…え? 何で僕を?」
「アンタの方が重要なんや。そこに立ってる香具師なんかより、数倍な」
『酷いなぁ。ボクだって結構重要な立場に居ると思うんだけど』
「よう言うわ。ま、間違ってはおらんけどな。アンタも後で一応見てやるから待っとれ」
のーさんはそう言うと、僕の手を引っ張って無理矢理座らせた。
彼女の目の前には、埃を被った水晶玉が置かれている。
これで運命とやらを見るのだろうか。
すると僕の心を見抜いたかのようなタイミングで、のーさんが答えた。
「ああ、水晶玉が気になるんか? これはただのおもちゃみたいなもんや。置いておくと、使わなくても占い師っぽく見えるやろ?」
「…ダミーってことですか?」
「そやな。ただのお飾り。店の棚とかに置いてある変なもんも、みんなそうやで。
ウチの占いは水晶玉も変な札も文字盤みたいなのも使わんからな。
何も使わんで占いなんか出来るんかいなって、信頼してくれる人がそんな多くないねん。だから、一応形だけでもそうしてるんや」
のーさんはそう言うと、僕の額に人差し指を押しつけた。
ぐいっ、と強い力で額を押して来る。
「倒れたらあかんで。辛抱や。今、アンタの未来を抽出しとるからな」
「未来を抽出…?」
「そや。ま、黙って辛抱しとれ」
言われた通り、僕は両手を床について踏ん張った。
のーさんが押して来る力は相当のものだったが、不思議と痛みは感じない。
5分ほど踏ん張っていると、のーさんの声がした。
「よし、終わりや。力抜いてええぞ」
指が離され、僕も全身の力を抜く。
ただ踏ん張っていただけなのに、何だか体力を相当消耗した気分だ。
「…疲れた…」
「ああ、ウチの占いを受け終わった香具師はみんなそう言うで。ダウトとあのひと以外は」
のーさんは離した指を親指と擦り合わせ、ぴんっと上に何かを弾くような仕草をした。
それと同時に、握り拳程度の光の塊が宙にぷかりと浮かび上がる。
「お、出よったな。どれどれ…アンタの未来は、と………………っ!!」
彼女はその塊をしばらくじっと見ていたが、急に顔色を変えると塊を掴んだ。
そしてそのまま塊を手の中で握り潰してしまった。
それがまるで僕の未来ごと潰されたように思えて、僕はのーさんの肩を掴むと揺さぶった。
「ちょ、な、何するんですか?!」
「…あかん…アンタの未来にはあかんことが待っとる…」
「あかんことって…悪いことですか…?」
「そや…。こんな未来は今まで視たことがない」
のーさんは少し、いや…かなり驚いているようだ。
額には脂汗が浮いていて、口から零れる息も荒い。
僕は彼女から手を離し、改めて尋ねた。
「…何を視たんですか?」
「駄目や。今言うたら、アンタはアンタで居られなくなってまう」
「何ですかそれ…僕が僕で居られなくなる?」
「そや。アンタの未来はある意味ダウトより残酷なもんでな。
今、その内容を教えたらアンタはきっと自分自身の運命を呪うようになってしまう。それはあかんのや」
のーさんの顔は真剣そのものだ。
彼女が占い師という職業だけに、狂言だと言ってしまえばおしまいかもしれない。
でも、僕はなぜか彼女の言葉を否定することが出来なかった。
むしろ、その「悪い未来」に興味すら湧いてきていた。
「じゃあ、全部じゃなくてもいいです。ヒントみたいなものでいいですから、僕の未来…教えて貰えませんか? おながいします」
自然と口をついて、僕はそんなことを言っていた。
それを見たダウトが付け加えるように呟く。
『ヒントぐらいならいいんじゃないかな。その未来…ボクにも大体予測はついている』
「アンタにとったら何でもないことなのかもしれへんよ。
でも、この兄ちゃんにとったらいずれこの未来は絶望的なものへと変わるんや。…兄ちゃん、名前は?」
のーさんの声が急に優しいものへと変わる。
それにつられるように、僕は自分の名を答えた。
「…タンデム。タンデム=ジェネシスです」
「タンデム…アンタの未来、どうしても知りたいか?」
優しく、でも深みを帯びた声。
その見えない威圧感に押されて、僕は少したじろいだ。
耳元でダウトが囁く。
『ここで引いたら、彼女は二度と未来を言わないよ』
そうして貰った方が幸せなのかもしれない。
でも、僕はそれが嫌だった。
いずれわかることなのに、今隠される必要なんてないじゃないか。
僕はずい、と身体を前に押し出してはっきりと言った。
「構いません。言って下さい。どんなことでもいいです」
真っ直ぐ、相手の目を見て。
真剣に彼女を見据える。
のーさんはしばし僕の目をじっと見つめていたが、やがてふぅっと息を吐いた。
「…わかった。全部を言うことは出来へんが…ヒント程度のものなら話すわ」
「ありがとうございます」
僕は礼を言うと、改めて彼女に顔を向けた。
その横で、ダウトが少し満足そうな微笑みを浮かべたのが見えた。
「…アンタは、いずれ壮絶な哀しみに打ちひしがれることになるんや」
「壮絶な哀しみ…? それが僕を襲うことになると?」
「それが何なのかは言うことは出来ん。だがそれだけは確かやで。
あと…神々の刻印。アンタのこれからの運命は、これらと絡んで行くことになるな」
神々の刻印…?
それは確か、夢の中でダウトが言っていたあのヤバそうな刻印だ。
そんなものと関わっていかなくちゃならないだって?
内心冗談であって欲しいと思いながら、僕はダウトに声をかけた。
「…ダウト、『神々の刻印』ってやっぱり…」
『うん、以前キミに話した刻印のことだ。7人の守人が守る神の遺産だよ』
「そうだよなぁ…それしかないよなぁ…」
『おや? 不満そうだね』
「だって、使い方によっては世界征服も出来るヤバいものなんだろ? そんなものと正直関わり持ちたくないっつーの…」
第一、そんな危ない刻印と関わり持ちたいAAなんて居るんだろうか。
その刻印を守ってるとかいう守人はともかく、あとはダウトぐらいのものだろうと思う。
僕はため息をついて、のーさんに尋ねた。
「…それって、『Sevence・Sign』とも関わりを持たなくてはいけなくなりますか?」
「ほう、あの組織のことを知っとるんかいな」
「いや、ちょっと噂好きの友人が居まして…彼女に聞いたんですけど。のーさんも『Sevence・Sign』について、何か知ってるんですか?」
彼女は少し考えて、答えた。
「知っとるも何も、ウチはあそこの頭領と長い付き合いやからな」
第5話:「久しぶり」
「…え?」
驚いた。
のーさんが「Sevence・Sign」のトップと知り合いだなんて。
「そんなに驚くことでもないで。ウチとあそこの頭領は幼馴染みでな。もともとウチらはしぃ族の多く住んどる、田舎の村におったんや」
「へぇ…何でまた、こんな都会に?」
「それは秘密や。…おっと、そんなことよりダウトを占ってやらんとな」
のーさんがそう言った時だった。
ざわっ…
外の空気が、動いたような気がして。
ダウトがふと顔を外へと向ける。
『…どうやら、仕事のようだね』
「えっ? 仕事? もう?!」
「せやな。残念やけど…占いはまた今度や」
のーさんの言葉と共に、扉がひとりでに開く。
ダウトが耳元で囁いた。
『…身体、借りてもいいかな?』
「え、あ…うん。傷つけないって約束するなら」
『難しいな。まぁ、それなりに善処するよ』
「善処するって…頼むよ、本当に…」
僕が縋るように呟くと、意識がふわりと浮いたような感覚がした。
『ははっ、わかった。保証は出来ないが…努力はする』
「僕を氏ぬ手前ぐらいまで追い込んだら許さないからな…」
『それはないよ、多分。さ、キミはひとまず寝て待っててくれたまえ…』
ダウトの声が段々と遠ざかっていき…僕は意識を失った。
「…ダウト」
「ん? 何だい?」
「アンタ、そのナリで仕事したらタンデムに迷惑かけるで」
「うん、それはわかってるんだ。でも生憎コスチュームが完成していなくてね」
ダウトはタンデムの姿で、困ったような表情を浮かべた。
姿形はタンデムそのものだが、顔はモナー族…ダウトのものに変化している。
「ったく…しゃーないな。ほれっ」
のーは近くにあった棚を漁ると、少し大きめの布らしきものをダウトに投げて寄越した。
「うちに置いてある占い師用のフード付きマントや。でも所詮は飾り物やから、棚にしまい込んどるだけで全然使っとらん。
アンタのコスチュームが完成するまでのその場しのぎにでもしいや」
「これは有り難い。礼を言うよ」
「礼なんかいらんわ。それよりさっさと仕事に向かった方がええで」
「そうだね、そうさせて貰うよ。じゃ」
ダウトはさっさと手際よくマントを着込むと、開け放たれていたドアから飛び出し、あっという間に見えなくなってしまった。
それと同時に閉まる店の扉。
再び闇に包まれた店内で、のーはぽつりと呟いた。
「…またのお越しをお待ちしておりますでな…」
ダウトはフードを頭まですっぽりと被り、完全に目元を隠して走っていた。
こういう被り方をしてしまうと、ダウト自身も視界が悪くなるはずなのだが、
彼はそんなことお構いなしといった風に物凄いスピードで走っている。
こんなことをいうと大袈裟かもしれないが、タクシーを追い抜けるかもしれないほどだ。
「…刻印の力関係が崩れかかってるな。やはり『七番目』が原因か…」
昼下がりの街は人通りも多い。
ダウトはその間をすいすいと通り抜けていくが、それでも多少のタイムロスは免れない。
大分走ったところで、彼は建物沿いに身体を寄せると足を止めた。
ふと、真上を見上げる。
「上から行こうかな」
彼はそう呟き、片手を空へと掲げた。
すると、彼の手の中に光の糸が一本生まれ、一気に伸び上がった。
伸び上がった糸は建物の屋上に自然と貼り付き、固定される。
とん、とダウトが地を蹴ると、ふわりと浮いた身体はそのまま糸に吸い寄せられるように上空へと舞い上がって行った。
「…おや?」
建物の屋上に舞い降りたダウトは、ふと一点の方向に目を留める。
その視線の先には、宙を舞う天使とその上に乗るAAを模したような人影が見えていた。
「反応を感じていたから何となく予想はついていたが…まさか本当に来ているとはね」
ダウトはくすりと微笑み、糸をしまうとその人影に向かってぴょんぴょんと建物の上を飛び越えて行った。
「…予定変更もあり得るって…お前は毎回そんな感じだよな」
「それがモナのスタイルモナ。時と場合に応じて作戦を変更する。基本モナよ?」
「…お前のは作戦というより、ただの気まぐれだし」
「Fakers」の本部へ向かう道すがら、モナーとモララーはそんなことを話していた。
刻印の能力で背から翼を生やしたモナーの上に、モララーが乗っている格好で、二人は優雅に空の旅を楽しんでいる。
「あまり深みに入りすぎるとヤバいからな。またレモナに怒られるしさ」
「…レモナのことなら心配しなくてもモナが………ん?」
モララーの忠告を笑顔で流していたモナーが、急に会話を止めた。
その様子にモララーも会話を切り、辺りに視線を巡らせる。
「…何が来た?」
「…忌まわしい香具師が現れたモナ」
モナーは吐き捨てるように言って、その名を呼んだ。
「居るのはわかってるモナ。出てくるモナ、『刻印殺し』ダウト・レイジ」
すると、その名に引き寄せられるかのように二人のすぐ近くから声が聞こえた。
「その通り名で呼ばれるのは心外だね。ボクはあまり気に入っていないものだから」
「何を言っているモナ。お前のやっていることは『刻印殺し』以外の何ものでもないモナ」
「そうかな? それはキミ達から見るとそう見えるだけであって、本当はそうじゃないかもしれないじゃないか。
何事も決めつけるのは良くないことだよ、モナー」
モナーはすい、と建物の一角に降り立つと、モララーを下ろして虚空を見上げた。
「隠れんぼが好きなのは昔からモナね。出てくるモナ」
モナーが少し強く言うと、空間の一部に切り取られたようにぽっかりと穴が空いた。
「いや、失敬。この癖は昔からのものでね。なかなか直ってくれないのさ」
切り取られた空間の穴から出てきたダウトは、含み笑いをしながらそう言った。
モナーはさっきからずっと不機嫌そうな顔をしている。
「お前の顔を見ていると落ち着かないモナ。…その様子だと、また目覚めたモナね」
「うん。恐らく『七番目』が覚醒したことにより、ボクが起動したんだろう。
今まで機能していなかった刻印が覚醒を遂げた…これによって、力のバランスが乱れてしまってきているようだからね」
その言葉に対して、モナーはため息をついた。
「毎回、余計なお節介モナ」
「仕方ないさ。これがボクの仕事、ボクの存在意義なんだから。
ボクが消える時があるとするなら…それは『刻印』が全てこの世から消滅した時だろう」
「それだから困るモナよ。お前はいらないけど、刻印が無くなるのは嫌モナからね」
「ははは、残念。…ところで」
ダウトは不敵な笑いを口元に浮かべて、尋ねた。
「『Fakers』へ乗り込むみたいだね?」
「そうモナ。モララーと二人、タカラ君と話をしに行くモナ」
「……そうか。やはりそれは…妹さんの件かな?」
途端、モナーの顔色が変わった。
すぐさま気づいたモララーが、モナーを宥めようと手をかける。
モナーも何かを言いかけたが頷き、勤めて自然に答えた。
「ガナーのことは…もう関係ないモナよ。お前も、本当は今ここで道草食ってる場合じゃないモナ?」
「その通りさ。今回はほんの挨拶。たまたま見かけたものだから」
「…なら、さっさと行けばいいモナ。モナ達も急いでるモナからね」
「そうかい? ならお言葉に甘えて。くれぐれも自分を見失わないように頼むよ」
ダウトはそう言うと、再び空間の中に飛び込んで消えた。
「…はぁ…嫌な香具師と会っちゃったモナ」
「モナー…今のが前に言ってた?」
モナーは静かに頷いて、答える。
「あいつが刻印の力のバランスを保つ者…『刻印殺し』の異名を持つ存在…『ダウト・レイジ』モナ。
刻印のバランスが乱れたり崩れたりした時に現れて、再び均衡を取り戻すために『仕事』をするという謎の存在と言われているモナ。
数年前に刻印の乱れが解消されて眠りについたはずモナけど…」
「…『七番目』の覚醒による起動、と彼は言っていたね。それってやっぱり…」
モララーの言葉に、モナーは頷く。
「『七番目』っていうのは、間違いなくポジ君のことモナ」
「彼はポジ君を狙っているのか…? それとも…」
「今のところはモナにもはっきりしたことは言えないモナ。いずれわかるモナよ。とにかく今はこれからの任務に集中するモナ」
モナーはそう言うと再び翼を広げ、モララーを背に乗せて飛び立った。
だが話を強引に終わらせておきながらも、モナーは心の中で動揺を隠せなかった。
(…あいつが動き出したのは正直マズいモナ。ちょっと対策が必要モナね…)
心の中で舌打ちしつつ、モナーはスピードを上げた。
第6話:「核の中へ」
彼はとても身軽だった。
タンデム自身は走ったりすることが苦手なのだが、ダウトはその身体を借りているにもかかわらず、十分なくらいに素早く動いていた。
ふわりふわりとビルの上を飛んでいくその姿は、まるで舞っているようにも見える。
「あれか」
足を止め、ダウトは地上を見下ろした。
そこはこの大きな街の中でも極めて異端と騒がれる区域。
「しかし、Vip区域とは思わなかったな…さて」
ダウトは片耳をぴんと立てて、気配を探った。
刻印所持者独特の気配が、片耳を通して彼に伝わる。
…その気配は、弱々しいものだった。
「…どうやら、厄介なことになってるみたいだね。彼も」
ため息をついて、彼はコンクリートの床を軽く蹴った。
投げ出された身体は一旦ふわりと宙に浮き、すぐに重力にならって落ち始める。
しかし、彼に焦る様子は微塵もなかった。
すっ、と手を天に向けて差し出すと、手の中から先程の光の糸が伸びて天へと向かう。
伸びた糸は遙か天へと伸びていき、その先端はやがて見えなくなる。
「…モナーの能力、ボクも欲しかったな」
ぽつりとダウトが呟いた途端、物凄いスピードで落ちていた身体が糸に引っ張られるようにして、急に止まった。
どこかに糸が辛うじて引っかかっているかのような不自然さである。
「そうすれば、こんな危なっかしい真似しなくて済むんだけど」
彼の身体は、地面から数センチのところで止まっていた。
あと数秒遅ければ、地に激突してしまい…重傷では済まなかっただろう。
だが彼の顔は人形のように無表情だった。
動揺しているようには見えない。
「…さて、仕事だ」
ダウトは再び地を蹴り、先程の落下速度に負けないくらいのスピードで走り出した。
静まりかえった部屋に、携帯の着信音が鳴り響く。
部屋にはベッドが一つと小さな窓、そして小さな箪笥。
ベッドの中には少女が一人、布団を被って横たわっている。
やがて少女は布団から顔を出し、忌々しそうに携帯を睨み付けると、渋々手に取り通話ボタンを押した。
「…はい? ああ…サドネスか。何か用?」
相手は少女の友人だった。
それほど親しい訳ではないが、元々友人の少ない彼女にとっては数少ない友人の一人だ。
「え? また『Sevence・Sign』の話するの? …面倒臭いなぁ…今、寝てたのに。
…わかった、わかったから…じゃあ、今からそっち行く…うん、また後で…」
電話を切ると、彼女は舌打ちをして布団から出た。
箪笥の上に置かれた小さな鏡を見ながら適当に髪をセットすると、枕元に置かれた帽子をひっ掴み、乱暴に被る。
「あー、もう…満足に寝ることすら許されてないんですか、あたしには…」
ぶつぶつ言っていると、部屋の扉が細く開いた。
「珍しい、じぃ姉が早起きしてるのだ。今日はきっとあられが降るのだ」
「五月蠅いわね、づー。あたしだってこんなに早く起きるつもりはなかったの」
「早く…って、もうお昼とっくに過ぎてるのだ」
じぃは自分と似た容姿を持つ妹を睨み付けた。
だが、その眼差しに真の殺気や嫌悪感は込められていない。
それを見越してか、づーは涼しい顔でその視線を受け流す。
「その様子だと、またサドネスさんに呼ばれたみたいなのだ」
「そうなの、Sevence・Signの話をして欲しいって。ここのところ、毎日よ…」
「よっぽど気に入ってるのだ」
「気に入るのは構わないけど…あまり深入りしないで貰いたいわね」
じぃは立ち上がり、カーテンを開けて窓の外を見た。
外は曇っているせいか、少し薄暗い。
「ぬーは居るの?」
「居るのだ。ぬーちゃんに頼んで、じぃ姉のご飯作って貰ってあるから、食べてから行った方がいいのだ」
「そうね…」
箪笥の引き出しを開け、一丁の小型拳銃を取り出す。
それを右腿のホルスターにしまうと、じぃはづーと共に部屋を出た。
「…今日も、この銃を使わないことを願うばかりね…」
その「核」を見つけるのに、それほど時間はかからなかった。
状況も大体呑み込めた。
あとは、どうやってこの危機を回避するかだ。
ダウトは今にも後頭部に鍵を差し込まれそうになっている青年を見つめて考えた。
「やっぱりこの方法が一番手っ取り早いだろうね」
彼の手からするりと光の糸が伸びる。
伸びた糸は青年の頭によじ登り、そのまま先端を埋め込んだ。
青年の周りにいるAA達は糸に気づいていないようだ。
…見えていないのだろうか。
「…よし、これで接続した。あとは同調すればいい」
ダウトはそう言って両目を閉じた。
すぅ、と深く大きく息を吸い、そのまま身体を停止させる。
肉体から何かが抜けていく感覚。
タンデムがダウトと入れ替わる時に感じていた感覚を、ダウトは感じていた。
瞼の裏には、何かの強い光が輝き続けている。
「そろそろいいかな?」
目を開けると、そこは真っ暗な世界だった。
彼の手から伸びている糸だけが、辺りを照らし出している。
道はなければ地面すらない。
空間にぼんやりと立っているだけだ。
ふと見ると、黒に覆われていた世界が段々とその色を失ってきている。
「さて、彼の意識を塞き止めておこう。彼が封印されてしまっては、意味がないからね」
手の中の糸がふわりと宙に浮き、空間の中を走って止まる。
ぎしりと軋んだ音がして、空間の蠢きが止まった。
それと同時に、すぐ傍に現れた青年の姿。
ダウトは、微かな声で呼びかけた。
「…キミか。とは言っても、キミはボクのことを覚えていないと思うけどね」
やがて青年はむっくりと起きあがり、しばらくぼんやりと虚空を見つめた後、ダウトをまじまじと見つめた。
足下から、光がせり上がるように差してくる。
「…まぁ、そんなことは今のキミにとったらどうでもいいことなのかな」
まるでスポットライトを浴びているかのように、ダウトの身体は光の真下にあった。
真っ暗な空間の中で、唯一彼だけが光の下に立っている。
驚愕の視線を向けられ、少し苦笑いを浮かべながらダウトは挨拶した。
「…とりあえず、久しぶりだね。ポジビリティ君」
「…?!」
あっけに取られたような相手のリアクションに、ダウトはまた苦笑いを浮かべた。
第7話:「時が来るまでは」
気まずくも思える沈黙に似た静寂が、場を包み込む。
やがて、ポジビリティはおずおずと口を開いた。
「貴方は…誰ですか…?」
「ん? それは名前のことかい? 名前なら、一応ダウト・レイジという立派な名前があるよ」
彼の質問にそう答えたダウトは、心の中でため息をついた。
やっぱり…何も覚えていないんだね、と。
「…他に何か聞きたいことは?」
「あ…ええと…ここはどこなんですか…?」
「ここ? ここはキミの意識の深淵だ」
「意識…?」
真っ暗な空間。
ダウトの立っているところ以外、一筋の光すら見えない世界。
それが、彼…ポジビリティの意識だった。
恐らく…意識を封印されかけていることで、この世界が半分消えかかっているのだろう。
世界が真っ暗になってしまったのは、その前兆のようなもの。
しかしすぐに変化は現れ、現に世界は消滅しようとしていた。
それを繋ぎ止めるため、ダウトは糸を走らせたのだ。
「そうだ。今のキミは、大耳の鍵の力によって意識を永遠に封印される途中なんだよ。
本来ならそのままキミは意識の暗闇に溺れて氏んでいくところなんだろうけども、
それは困るから、ボクがキミの沈みかけの意識を一時的に止めた。今が、その『止まっている』状態なんだ」
目の前の彼は、文字通りぽかんとして話を聞いていた。
もしかしたらダウトの話なんて半分近く耳に入っていないかもしれない。
それほど、彼はこの状況を理解するのに苦しんでいた。
「ちょ、ちょっと待って下さいよ。要するに今、僕はビデオでいう一時停止みたいな状態になってるってことですか?」
彼は回らない舌を必死に動かし、尋ねる。
その質問を否定することなく、ダウトはさくさくと話を進めていく。
「うん、まぁ平たく言えばそんな感じだね。とは言っても『一時停止』だから、出来れば早いところキミに決めて貰わないといけないんだ」
「何をですか?」
そんなこと、わかりきっているじゃないか。
ダウトは内心呆れながら、その先を続けた。
「勿論、キミはこの後どうするかだ。このまま暗闇に落ちて氏ぬのがいいならそうする。
ボクとしては困るけど、キミが望むなら仕方のないことだと思って諦める。
でも氏にたくないなら、それなりの対処はしてあげようと思ってるんだが」
正直、こんな質問は彼にとって愚問だろう。
今の彼は…
「氏にたくなんかないですよ!! 何言ってるんですか!!」
以前に比べて、とても強く安定した心を持っているからだ。
それを知っているダウトは、表情を変えぬまま、淡々と相槌を打った。
「…そうか、わかった。でも、これには条件がある」
目の前の彼が一瞬不安そうな表情になって、しかしすぐに表情を戻す。
「何ですか? 僕に出来る範囲のことでなら何でも…」
「なに、別に難しいことじゃないさ。ちょっと、キミに昔のことを見て貰いたいだけだよ」
「昔のこと…?」
彼の望みを叶えるには、彼に味わって貰う必要がある。
数年前、彼の記憶が消される少し前…彼に起こったことを。
「そう…昔の…思い出みたいなものさ。キミにとってはほんの一瞬に過ぎないけどね」
今は、全てを彼に伝えることは出来ない。
その時ではないからだ。
だが、例え信じなくてもいいから…欠片だけでも渡しておきたい。
ダウトはつい、と指を指揮者のように軽く振った。
指にかかる、やや重い感覚。
それに構わず、ダウトは指を振り切る。
ずこん。
彼の指に巻き付いた光の糸に引っ張られて、空間の一部が抜け落ちる。
丸く開いた穴からは、青年が求めていた暖かい光が漏れ出す。
ダウトは青年をその穴へと導くように、手をかざしてみせた。
「今からここで見たことを、忘れるも思い出すもキミ次第だ。じゃあ、また後で」
漏れ出す光が強さを増す。
あっという間にその場を覆い尽くした光は、ポジビリティの姿を瞬時に飲み込み。
「え?! あ、ちょっと!!」
彼の声さえも無視して全てを飲み込んだ光は、やがて収束していった。
再び空間に闇が戻り、佇むのはダウト一人。
先程開けた穴も、今はすっかり無くなっていた。
「…思い出せないのなら、欠片だけでも持っていた方がいい。やがてそれは…キミを導き、道を作り出す光になっていくだろうからね」
何も映らない空を見上げ、彼は呟く。
音を立て軋む空間を再び縛り上げながら。
「さて、『彼女』は上手くやっている頃かな?」
視界に一瞬映っただけだ。
それが確信出来るものとは思えない。
でも、追わずには居られなかった。
「ちょっと! じぃってばどこ行くのよ!」
「知りたいんなら、ついて来ることね!」
後ろで文句を言いながらついて来ている友人に声だけで答えながら、じぃはある人物を追って走っていた。
それは、彼女が仕事で行く先々で何回も出会った、あの「片耳のモナー族」。
(全く…いつ目覚めたっていうのよ…ダウト…!!)
じぃは舌打ちをすると、段々遅れ始めている友人の手を掴んだ。
それと同時に、一気に走るスピードを上げる。
「わわっ、ちょっと…急に引っ張らないでよ!!」
息切れしていたところを急に引っ張られたものだから、彼女の身体はバランスを崩した。
しかしすぐに体勢を立て直し、必死にじぃの速度について行く。
「遅れるのが悪いの!! 詳細は後で話すから、今はとにかく走るわよサドネス!!」
言いながら、じぃは右腿のホルスターからそっと銃を抜いた。
過去を見せられて、動揺しない者などいない。
それは未来を視ることの出来る自分も同じことだ。
先程視た青年の未来は、自分にとっても苦痛な未来だった。
そして、自分は青年の過去も知っている。
「…タンデムはんの未来は絶望に満ちたもの…まるで救いようのないdatの海のようや。
だが…それは過去とて同じ…。ウチは…彼に未来を伝えるべきやったろうか…」
まだ、その時ではない。
そう思ってあの時は躊躇った。
しかし…もう時は動き出してしまっている。
絶望へのカウントダウンは始まっているのだ。
「…せめて…ダウトがあの子の哀しみと苦しみを癒してやれたらいいんやけど…
香具師は不器用やからな…逆にあの子に救われそうな気がしてならんわ…」
のーは、傍らの棚の上に乗っている写真立てを手に取った。
そこに映っているのは、幼い頃の自分とモナー…そして、今は敵地に身を置く友人。
「…ウチはどうしていくべきやろか…ニダやん…」
答えない写真に、のーはぽつりと声を漏らした。
待っていた時間はそれほど長いものではなかった。
強い光が再びその場を覆い、現れたポジビリティ。
彼の顔には、涙の跡が痛々しく貼り付いている。
「少しは思い出して貰えたかな?」
ダウトが問うと、彼は座り込んだまま顔を上げた。
この世に絶望したような、そんな表情で。
掠れた声で、彼は逆に尋ね返す。
「…あれは…何なん…ですか…?」
「あれは、キミの残した過去の一部だ」
「あんな…あんなものが、僕の過去とでも言うんですか?!」
今までになく声を荒げて、彼は問う。
だがダウトは驚く様子もなく、淡々と答えた。
「そうとしか言いようがないんだ、仕方ないだろう」
「嘘だ…僕は認めない!!」
彼は頭を抱え、断固として拒否している。
拒否したいのもわからないではないが…彼にはこの事実を呑んで貰わないといけない。
しかし、今の彼がとてもそんな精神状態でないことは誰の目から見ても明らかだった。
「…まぁ、信じる信じないはキミの自由だ。ボクがどうこう言うことじゃないしね。
さて、約束通り…キミの封印されかかっている意識を外に帰してあげよう」
今はまだ呑み込めなくても仕方ないだろう。
いずれは認めて、受け入れて貰わなければならないけれど。
ダウトは内心でそう思いながら、ポジビリティの意識に神経を集中させ、外界へと浮上させ始める。
その時、ポジビリティが慌てて叫んだ。
「ま、待って下さい!!」
その声に、意識の浮上を一旦止める。
元々細い目をさらに細めて、ダウトは言葉を投げた。
「ん? 何だい?」
「…貴方は、僕の過去を知っているんですか?」
「……」
ダウトの口がほんの少し動きかけて、止まる。
数秒の躊躇いがあった後、彼はややぎごちなく答えた。
「…知っていると言えば嘘になるが、知らないと言っても嘘になるね。
これはボクが元々知っていたものではない。ボクが目覚めた時から既にボクの中にあった。
誰かに、これを持っているように命令されたのかもしれない。でも、それはわからない。
だからボクは、キミにこれを見せたんだ。これはボクの独断でやったことだよ」
畳みかけるように、一気にダウトは言い切った。
勢いに呑まれた目の前の彼が、ぽかんとした顔でこちらを見つめる。
その隙を逃すまいと、ダウトは指を上に向けて動かした。
再び、彼の意識が外界へと昇り始める。
…知られては、ならな
僕の名前はタンデム=ジェネシス。
モララー族とモナー族のハーフだが、僕はどちらかといえばモララー族の血が濃い。
モナー族の面影が残っているところはせいぜい右耳が白いことぐらいだろうか。
もう一つあったはずの耳は、生まれつきちぎれていて存在しない。
タンデムって、バイクの二人乗りのこととかを言うらしいけど、
僕の名前が今起こっていることを予め予測した上でつけられたものだとすると、何とも気味の悪い話だ。
今となってはそのことを恨もうにも恨めないし、恨んだところでどうしようもない。
…それに…「あいつ」にも悪気があるわけではないし、むしろ…「あいつ」の存在意義とかを考えると、
自分の方まで何だか…胸がいっぱいになるというか、そんな感じになる。
だから、僕は今の状況を決して悲観的には考えていない。
「あいつ」はとても変わった奴だ。
いつも一人で心の中に閉じこもっているようで、外の世界のことをよく知っている。
知っているかと思えば、逆に知りすぎて何かを悟ってしまっている。
まぁ、そういう奴でもないとあんな仕事は出来ないのかもしれないが。
…さて、こんなことをぐだぐだと話していてもしょうがない。
まずは僕と「あいつ」が出会ったところから話そうか。
第1話:「白い部屋の真ん中で」
そいつと出会ったのは数年前になる。
僕はいつものように街をプラプラと歩いていた。
世間的にいえば僕はいわゆるニートみたいなもので、一応アルバイトなどで食い繋いではいるのだが、みんな長続きはしなかった。
「…何でだろうなぁ…」
どうして自分がこんな退屈な世界に生まれてきてしまったのか、自分でもわからない。
そのことを思い起こす度に、僕はため息を漏らす。
考えるのも嫌だが、考えずにはいられないのだ。
「何言ってんの。退屈退屈って言ってる暇あるなら、少しはまともな職に就いたら?」
僕の隣に並んで一緒に歩いているのは、幼馴染みのサドネス。
「悲哀」の名に似合わず、彼女はいつもさばさばしていて、僕を引っ張っていってくれる。
どうしようもない僕にとって、それが唯一の救いみたいなものだった。
「んー、まぁ気が向けばそのうち」
「そんなこと言って…いつ気が向くかわからないでしょ? いいバイト紹介しよっか?」
「いや…今はまだいいや」
彼女は僕のためにと、よくバイトを探してきてくれるのだが、僕はそんな彼女の期待にいつも応えてあげることが出来ていない。
でも、そのことに関して彼女は文句ひとつ言わなかった。
僕としては、何か言って貰った方がいいのかもしれないけど。
「あ、そういえばさぁ。あんた『Sevence・Sign』って知ってる?」
「…何それ」
「知らないの? 裏の世界じゃあ有名な組織よ」
「僕は裏社会の人間じゃないからね。…また、じぃちゃんに聞いたの?」
「まぁね♪ そんなに詳しくは教えてくれなかったけどさー」
サドネスは、噂話がとにかく大好きだ。
どんなに小さな噂でも、例えそれがガセネタであっても、必死で飛びついていく。
そして、噂の真相を確かめるのが彼女の趣味であった。
「で? その『Sevence・Sign』って何?」
「詳細はわからないけど、『神々の刻印』っていう変な印を持っている人しか入れない組織なんだって。
活動内容は闇に包まれていて、探ろうとする者は一人残らずあぼーんされるとかいう話よ」
「へぇ、なかなか恐ろしい組織のようで」
「でしょ? 知りたいわぁ、謎の組織の秘密」
「…あぼーんされるかもしれないのに?」
「だから面白いんじゃない」
彼女はくすんだ色の空を見上げて、高らかに叫んだ。
「今もこの街のどこかで…組織の面々が活動しているのかもしれないのよ? 想像するだけでドキがムネムネしてくるわ!」
「はいはいわろすわろす…」
そんな当たり前のようで、でもどこか退屈な毎日。
それが僕の日常だった。
変化が訪れたのは、その日の夜からだった。
時々、軽い頭痛がするようになったのだ。
馬鹿は風邪をひかないというが、僕は一応自分が馬鹿じゃないと思っているので、翌日とりあえず病院に行ってみた。
だが病院のどの科を回っても、返って来る答えは「原因不明」ばかり。
なんてこった、と僕は思ったね。
原因がわかっていれば、多少は救いようがあるんだろうけど、僕にはそれがないのだ。
まるで、僕のどうしようもない毎日と同じだった。
僕が見る夢はいつも同じものだ。
どこまでも広がっている白い世界を、一人でひたすら歩き続けている夢。
周りには当然誰もいないし、道もなければ空もない。
歩いて行く先に何があるのかも知らない。
でもその日の夢は違った。
白い世界に、いつものように一人で放り出されて。
歩こうと腰を上げたその時、僕の前に初めて人影が立った。
「やあ」
そいつは、モナー族の男だった。
僕と同じように左耳はちぎれ、残った黄色い右耳には、包帯が乱雑に巻かれている。
三月ウサギが着ていそうな黒いマントを着込み、金色の金具で留めている。
金具の下からは意味もなく長いリボンが下がっていた。
「…お前は…?」
突然の来客に驚く僕に、彼は答えた。
「そうか、自己紹介もしていなかったね。ボクはダウト・レイジという。
ちなみにこの名前は自分でつけてみたんだ。どう? 格好いいかな?」
そう言って、彼は複雑な笑みを浮かべた。
これが、僕と「あいつ」の初めての出会いだった。
第2話:「前奏曲」
変な香具師だな、と思った。
今まで、コスプレイヤー以外でそんな変わったファッションをしているAAを見たことがなかったし、
単に三月ウサギの真似事をしているようには見えない。
それは、彼…ダウト・レイジの目線が真剣みを帯びているものだったからだ。
「…お前、どうやってここに来たんだ?」
「来たも何も、ボクは随分前からここに居た」
「え? だって今までは誰も…」
「それは、キミがボクを見ようとしなかったからじゃないのか?」
見ようとしなかったとか言う前に、誰も居なかったって。
そう言おうとした僕に、ダウト・レイジは大真面目な顔で言った。
「真っ白な世界だからって、何も見えない世界だからって、何もない世界と決めつけてしまうからそんなことになるんだ。
キミはそのことを忘れている。ボクが「居る」ということを想定しないでいたから、ボクの姿を見つけることが出来なかったのさ」
…よくわからない。
僕が呆気にとられていると、彼はため息をついて「別にわからなくてもいいよ」と言った。
「さて、キミは知りたいだろう?」
「何をだよ」
「ボクがどうしてここに居るのか、そしてキミの中にいつから居るのかを」
「…僕の中って…お前、もしかして僕の心の中にいる香具師なのか?」
「そう。なかなか察しがいいね」
ダウト・レイジはあっさりと頷いた。
突然夢の中に現れたと思いきや、僕の心に住む香具師だって?
…もう、何が何だかわからないことが多すぎる。
とりあえず、この状況になるまでの経緯を説明して貰うことにした。
「…OK、わからないことだらけだ。とにかく説明して貰えないかな」
「うん。まず大まかなことから説明しようか」
そう言って、ダウト・レイジはどっこいしょ、とその場に腰を下ろした。
「まず、ボクがどうしてキミの心に現れたかだ。正直言うと、ボクにも詳しいことはあまりわからない。
ただ、わかっているのはボクが『神々の刻印』の力を制御するために生み出された存在だということだ」
聞き覚えのある言葉に、僕は眉をひそめる。
「…『神々の刻印』って…『Sevence・Sign』のメンバーが持っているって噂の…?」
「そうだよ。よく知ってるね。あ、サドネス=エイデンに聞いたのか」
「何で僕がサドネスから聞いたって知ってるんだ?」
「さっき、キミの記憶を読んだばかりでね。最近の記憶だけしか読んでいないから、かなり昔のことについてはわからないが」
ダウト・レイジは話を続けた。
「キミは知らないだろうが、『神々の刻印』には神が残した強大な力が秘められている。
その力を全て手にすれば、世界を我がものに出来るくらいらしいんだけどね」
「…何か、かなり大層なものなんだな」
「うん。だから神はその力が悪しき者の手に渡ることを恐れて、刻印を七人の『守人』と呼ばれる
ガーディアン達に託し、守人達は何百年にも渡って刻印を守り続けた」
「ふーん……ん? 待てよ」
僕は彼の言ったことを頭の中で反復しながら、逆に尋ねた。
「そんなに強大な力があるなら、ガーディアン達が結束して、逆に世界を征服することぐらい簡単なんじゃないのか?」
「ふむ、それはなかなか的確なご意見だね。確かにその可能性はある。刻印の力を行使出来るのは、
基本的にガーディアン達だけだと言われているからね。あとは、刻印を作り出した神ぐらいのものだ」
「…それってヤバいんじゃ…」
「いいや。そのためにボクが居るんだよ」
ダウト・レイジはとんとん、と自分の胸元を軽く叩いた。
「具体的にどうするのかまでは言えないけど。とにかく、そのためにボクは肉体を得る必要があった。
だから、こうしてキミの中に居るわけだ」
「…えーと…要するにお前は…」
僕が何とか話をまとめようとすると、ダウト・レイジは薄く微笑った。
「ただの居候みたいなものだと思って貰えればいい」
「いや…流石にそこまでは…えーっと、ダウト・レイジ?」
「ダウトでいいよ。長いし、言いづらいみたいだから」
彼は立ち上がり、ぱちんと指を鳴らす。
すると今まで真っ白だった世界に、道が出来始めた。
「頼み事があるんだ。2つ」
「え? ああ…何?」
「ボクは自分の肉体がない。だから、時々でいいからキミの身体を貸して貰いたい。
キミの心から出て、仕事をしなくてはならない時もあるんだ」
「…それってもしかして、『よーしパパ身体乗っ取っちゃうぞー』って奴?」
「乗っ取る…のとはちょっと違う。貸して貰う時にはキミに一言声をかける。あとはボクが何とかするから」
道は伸びて伸びて、やがて一つの扉の前で止まった。
「それと、ボクがキミの身体を借りて仕事をする際に、少々手荒な真似をするかもしれない。
もしそれを誰かに見られて、キミがやっていると勘違いされたら、キミもこの街に居づらくなる。そうするとキミは困るし、ボクも困る」
「手荒な真似って…殺人とか?」
「出来ればしたくはないが…やるかもわからない。だから、ボクの今着ているマント。
これを適当でいいから見繕って来て貰いたいんだ。仕事の時だけ今の格好をすれば、キミが誤解を受けることもないだろう」
ダウトは言うだけ言って歩き出す。
行く先は扉。
僕も慌ててその後をついて行く。
その扉は真っ白に染まっていて、周りの空気に溶け込んでいた。
だが、その輪郭線だけは不気味なほどにはっきりと浮かび上がっている。
「さぁ、ここから外に帰れる。今日はもう帰りたまえ」
ダウトが扉を開ける。
途端、視界が白で塗り潰された。
さて、ここまでが僕とダウトが出会った日の話だ。
信じないのなら、それでもいい。
少なくとも僕が信じていればいいと思っているから。
次は…そうだな、初仕事の時のことでも話す?
とは言っても、あまり僕は覚えていないんだけど。
第3話:「裏路地の占い師」
最初はただの幻だと思っていたさ。
あの夢も、そのためだけにあったもので。
でも、そうではなかった。
「…サドネスが洋裁得意で良かったよ」
『おかげで買わなくて済んだね』
「そうだけど…『何に使うの?』って聞かれた時はマジでどうしようかと」
『でも納得してくれたじゃないか。「コスプレショーのバイトする」で』
「…それであっさり納得されるのもなぁ…」
僕は、ダウトから頼まれた衣装の制作をサドネスに頼んだ。
彼女は洋裁が大の得意で、頼まれれば何でも作ってくれるのだ。
そこで早速ダウトが夢の中で着ていた衣装を絵にして持って行ったというわけで。
が、何しろあの奇抜な衣装だ。
案の定「何に使うの?」と聞かれ、僕は咄嗟に「コスプレショーのバイト」と答えたのだ。
そんな苦し紛れな僕の答えにも、彼女は疑問一つ浮かべることなくあっさり納得した。
それは…ラッキーなのかもしれないけどさ。
『まぁ、いいんじゃないかな。結果オーライだよ』
「言い出したのはお前だろ…」
『ところで、彼女の腕は確かなのかい?』
「ああ、サドネスは裁縫と銃の腕は一流なんだ。料理は下手だけど」
『出来るだけ早めがいいな。今、この場で仕事に行かなくちゃならなくなった時に困る』
僕の隣でそんなことを言いながら、ダウトはぼんやりと宙を眺めた。
今、彼は上半身だけ半透明になって(僕以外のAAには見えないけど)表に出ている。
僕の身体を使わないで現実世界に干渉するのはこれが精一杯らしい。
「…あのさ」
『ん?』
「お前、僕の心に住んでる香具師だって言ったよな。じゃあ、僕の心そのものから生まれて、そのまま心の中に居たのか?」
『いいや、それは違う。ボクは誰かの手によってキミの心へ植え付けられた』
ダウトはあっさりと答えた。
だが僕はその答えに納得するどころか、さらなる疑問を抱いてしまう。
「…植え付けられた?」
『うん。言い方は悪いけど、寄生虫みたいな感じだね』
「それはちょっと言い過ぎじゃないのか?」
『そうかい? 似たようなものじゃないのかな。ボクの身勝手で、キミの命を危険に晒すことになるかもしれないんだから』
…何で、こういうことを真顔で言うかな。
ちっとも悲しそうな顔とかしないし。
「…それより、その植え付けたって香具師は誰なんだよ」
『それが思い出せないんだ。記憶が切り取られていてね』
「…切り取られてる?」
『多分、植え付けた側の処置だと思うよ。植え付けた側が誰なのかわからなくするための』
「でも…何でそんなことする必要があったんだ?」
『ボクに訊くなよ。ボクが知りたいぐらいなんだから』
はぁ、とダウトはため息をついた。
察してくれよ、とでも言いたいのか。
でも僕は彼のことをほとんど知らないのだから、許して貰いたい。
ダウトはしばらくまた虚空をぼんやりと眺めていたが、急にこちらを見て言った。
『…そうだな、ボクの知り合いにそのことを知っていそうな香具師が居るんだが、ちょっと行ってみようか』
街の裏路地にはほとんど入ったことがなかった。
今見てみると、結構色々な店や露店がある。
ここならバイトも簡単に見つかるかもしれないな、と僕はろくでもないことを考えた。
「ダウトに知り合いなんているんだ?」
『うん。ボクの覚えている範囲で、知り合いは数人居る。まともな人じゃないけどね』
「…まともな人じゃないって…」
『ああ、殺し屋とかそんなんじゃないよ。Vipperほどじゃないけど、世間からちょっとズレてる人達さ。あ、そこの角曲がって』
言われた通りにしばらく歩くと、一軒の寂れた店が見えて来た。
その道は行き止まりになっていて、その店以外は周りに何もない。
入り口の古ぼけた扉には、『占い』と書かれた看板がかかっている。
「…なんか、RPGとかに出てきそうな店だな」
『「モーラス伝」の「ソル・コーテフ」がやってる店に雰囲気が似てるとか、よく言われるらしいよ。
断じてインスパイヤはしていないって店主は言い張ってるけどね』
「ふーん…で、ここなのか?」
『うん。まぁ、入ってみてくれよ。入ればわかるからさ』
言われて、僕は恐る恐る扉を開けた。
ぎぃぃぃ…と独特の扉のきしむ音がして、薄暗い店内に光が差し込む。
店内には沢山の棚があり、難しそうな書物やヤバそうな占いグッズなどが置かれている。
僕はごくり、と息を呑み、中に入ると後ろ手に扉を閉めた。
再び店内に暗さが戻る。
その時、奥から関西弁口調で誰かの声が聞こえた。
「…いらっしゃいまし」
僕が辺りを見回すと、店の奥に一人の女性が座っているのが見えた。
高そうな着物を身に纏い、ヴェールのような薄い布を頭に被っている。
彼女の周りには寒色系の色の照明が灯っており、そこだけ妙に明るかった。
椅子はなく、彼女は座布団の上に座っている。
「よう来たな。何か用でっか?」
「あ、えーと…あの…用って言えば用なんですけど…」
彼女は言い淀む僕の顔をひとしきり眺めてから、もう一度尋ねてきた。
「…ほな、質問変えよか。兄ちゃん、『刻印殺し』背中にしょって何の用や?」
女性が布越しににやり、と笑った。
僕の隣で、ダウトが困ったような笑みを浮かべる。
『…相変わらずだね、のー』
「そりゃこっちのセリフやで、ダウト。久々に『目覚めた』割には…」
『いやいや、こっちにも結構な事情があるんだよ。前に会った時より、遙かに状況は変わっている。
キミなら既にわかっているだろうけどね』
「無論や。ウチにわからんことなんか無いで。アンタの未来も全部わかっとる。でも、今はアンタよりも…」
のーさんは、僕を指さして言った。
「…兄ちゃん、こっち来いや。アンタの運命占ったるわ」
第4話:「絶望を視る」
僕はあっけに取られた。
てっきりダウトの方を占うか何かすると思ったのに。
「…え? 何で僕を?」
「アンタの方が重要なんや。そこに立ってる香具師なんかより、数倍な」
『酷いなぁ。ボクだって結構重要な立場に居ると思うんだけど』
「よう言うわ。ま、間違ってはおらんけどな。アンタも後で一応見てやるから待っとれ」
のーさんはそう言うと、僕の手を引っ張って無理矢理座らせた。
彼女の目の前には、埃を被った水晶玉が置かれている。
これで運命とやらを見るのだろうか。
すると僕の心を見抜いたかのようなタイミングで、のーさんが答えた。
「ああ、水晶玉が気になるんか? これはただのおもちゃみたいなもんや。置いておくと、使わなくても占い師っぽく見えるやろ?」
「…ダミーってことですか?」
「そやな。ただのお飾り。店の棚とかに置いてある変なもんも、みんなそうやで。
ウチの占いは水晶玉も変な札も文字盤みたいなのも使わんからな。
何も使わんで占いなんか出来るんかいなって、信頼してくれる人がそんな多くないねん。だから、一応形だけでもそうしてるんや」
のーさんはそう言うと、僕の額に人差し指を押しつけた。
ぐいっ、と強い力で額を押して来る。
「倒れたらあかんで。辛抱や。今、アンタの未来を抽出しとるからな」
「未来を抽出…?」
「そや。ま、黙って辛抱しとれ」
言われた通り、僕は両手を床について踏ん張った。
のーさんが押して来る力は相当のものだったが、不思議と痛みは感じない。
5分ほど踏ん張っていると、のーさんの声がした。
「よし、終わりや。力抜いてええぞ」
指が離され、僕も全身の力を抜く。
ただ踏ん張っていただけなのに、何だか体力を相当消耗した気分だ。
「…疲れた…」
「ああ、ウチの占いを受け終わった香具師はみんなそう言うで。ダウトとあのひと以外は」
のーさんは離した指を親指と擦り合わせ、ぴんっと上に何かを弾くような仕草をした。
それと同時に、握り拳程度の光の塊が宙にぷかりと浮かび上がる。
「お、出よったな。どれどれ…アンタの未来は、と………………っ!!」
彼女はその塊をしばらくじっと見ていたが、急に顔色を変えると塊を掴んだ。
そしてそのまま塊を手の中で握り潰してしまった。
それがまるで僕の未来ごと潰されたように思えて、僕はのーさんの肩を掴むと揺さぶった。
「ちょ、な、何するんですか?!」
「…あかん…アンタの未来にはあかんことが待っとる…」
「あかんことって…悪いことですか…?」
「そや…。こんな未来は今まで視たことがない」
のーさんは少し、いや…かなり驚いているようだ。
額には脂汗が浮いていて、口から零れる息も荒い。
僕は彼女から手を離し、改めて尋ねた。
「…何を視たんですか?」
「駄目や。今言うたら、アンタはアンタで居られなくなってまう」
「何ですかそれ…僕が僕で居られなくなる?」
「そや。アンタの未来はある意味ダウトより残酷なもんでな。
今、その内容を教えたらアンタはきっと自分自身の運命を呪うようになってしまう。それはあかんのや」
のーさんの顔は真剣そのものだ。
彼女が占い師という職業だけに、狂言だと言ってしまえばおしまいかもしれない。
でも、僕はなぜか彼女の言葉を否定することが出来なかった。
むしろ、その「悪い未来」に興味すら湧いてきていた。
「じゃあ、全部じゃなくてもいいです。ヒントみたいなものでいいですから、僕の未来…教えて貰えませんか? おながいします」
自然と口をついて、僕はそんなことを言っていた。
それを見たダウトが付け加えるように呟く。
『ヒントぐらいならいいんじゃないかな。その未来…ボクにも大体予測はついている』
「アンタにとったら何でもないことなのかもしれへんよ。
でも、この兄ちゃんにとったらいずれこの未来は絶望的なものへと変わるんや。…兄ちゃん、名前は?」
のーさんの声が急に優しいものへと変わる。
それにつられるように、僕は自分の名を答えた。
「…タンデム。タンデム=ジェネシスです」
「タンデム…アンタの未来、どうしても知りたいか?」
優しく、でも深みを帯びた声。
その見えない威圧感に押されて、僕は少したじろいだ。
耳元でダウトが囁く。
『ここで引いたら、彼女は二度と未来を言わないよ』
そうして貰った方が幸せなのかもしれない。
でも、僕はそれが嫌だった。
いずれわかることなのに、今隠される必要なんてないじゃないか。
僕はずい、と身体を前に押し出してはっきりと言った。
「構いません。言って下さい。どんなことでもいいです」
真っ直ぐ、相手の目を見て。
真剣に彼女を見据える。
のーさんはしばし僕の目をじっと見つめていたが、やがてふぅっと息を吐いた。
「…わかった。全部を言うことは出来へんが…ヒント程度のものなら話すわ」
「ありがとうございます」
僕は礼を言うと、改めて彼女に顔を向けた。
その横で、ダウトが少し満足そうな微笑みを浮かべたのが見えた。
「…アンタは、いずれ壮絶な哀しみに打ちひしがれることになるんや」
「壮絶な哀しみ…? それが僕を襲うことになると?」
「それが何なのかは言うことは出来ん。だがそれだけは確かやで。
あと…神々の刻印。アンタのこれからの運命は、これらと絡んで行くことになるな」
神々の刻印…?
それは確か、夢の中でダウトが言っていたあのヤバそうな刻印だ。
そんなものと関わっていかなくちゃならないだって?
内心冗談であって欲しいと思いながら、僕はダウトに声をかけた。
「…ダウト、『神々の刻印』ってやっぱり…」
『うん、以前キミに話した刻印のことだ。7人の守人が守る神の遺産だよ』
「そうだよなぁ…それしかないよなぁ…」
『おや? 不満そうだね』
「だって、使い方によっては世界征服も出来るヤバいものなんだろ? そんなものと正直関わり持ちたくないっつーの…」
第一、そんな危ない刻印と関わり持ちたいAAなんて居るんだろうか。
その刻印を守ってるとかいう守人はともかく、あとはダウトぐらいのものだろうと思う。
僕はため息をついて、のーさんに尋ねた。
「…それって、『Sevence・Sign』とも関わりを持たなくてはいけなくなりますか?」
「ほう、あの組織のことを知っとるんかいな」
「いや、ちょっと噂好きの友人が居まして…彼女に聞いたんですけど。のーさんも『Sevence・Sign』について、何か知ってるんですか?」
彼女は少し考えて、答えた。
「知っとるも何も、ウチはあそこの頭領と長い付き合いやからな」
第5話:「久しぶり」
「…え?」
驚いた。
のーさんが「Sevence・Sign」のトップと知り合いだなんて。
「そんなに驚くことでもないで。ウチとあそこの頭領は幼馴染みでな。もともとウチらはしぃ族の多く住んどる、田舎の村におったんや」
「へぇ…何でまた、こんな都会に?」
「それは秘密や。…おっと、そんなことよりダウトを占ってやらんとな」
のーさんがそう言った時だった。
ざわっ…
外の空気が、動いたような気がして。
ダウトがふと顔を外へと向ける。
『…どうやら、仕事のようだね』
「えっ? 仕事? もう?!」
「せやな。残念やけど…占いはまた今度や」
のーさんの言葉と共に、扉がひとりでに開く。
ダウトが耳元で囁いた。
『…身体、借りてもいいかな?』
「え、あ…うん。傷つけないって約束するなら」
『難しいな。まぁ、それなりに善処するよ』
「善処するって…頼むよ、本当に…」
僕が縋るように呟くと、意識がふわりと浮いたような感覚がした。
『ははっ、わかった。保証は出来ないが…努力はする』
「僕を氏ぬ手前ぐらいまで追い込んだら許さないからな…」
『それはないよ、多分。さ、キミはひとまず寝て待っててくれたまえ…』
ダウトの声が段々と遠ざかっていき…僕は意識を失った。
「…ダウト」
「ん? 何だい?」
「アンタ、そのナリで仕事したらタンデムに迷惑かけるで」
「うん、それはわかってるんだ。でも生憎コスチュームが完成していなくてね」
ダウトはタンデムの姿で、困ったような表情を浮かべた。
姿形はタンデムそのものだが、顔はモナー族…ダウトのものに変化している。
「ったく…しゃーないな。ほれっ」
のーは近くにあった棚を漁ると、少し大きめの布らしきものをダウトに投げて寄越した。
「うちに置いてある占い師用のフード付きマントや。でも所詮は飾り物やから、棚にしまい込んどるだけで全然使っとらん。
アンタのコスチュームが完成するまでのその場しのぎにでもしいや」
「これは有り難い。礼を言うよ」
「礼なんかいらんわ。それよりさっさと仕事に向かった方がええで」
「そうだね、そうさせて貰うよ。じゃ」
ダウトはさっさと手際よくマントを着込むと、開け放たれていたドアから飛び出し、あっという間に見えなくなってしまった。
それと同時に閉まる店の扉。
再び闇に包まれた店内で、のーはぽつりと呟いた。
「…またのお越しをお待ちしておりますでな…」
ダウトはフードを頭まですっぽりと被り、完全に目元を隠して走っていた。
こういう被り方をしてしまうと、ダウト自身も視界が悪くなるはずなのだが、
彼はそんなことお構いなしといった風に物凄いスピードで走っている。
こんなことをいうと大袈裟かもしれないが、タクシーを追い抜けるかもしれないほどだ。
「…刻印の力関係が崩れかかってるな。やはり『七番目』が原因か…」
昼下がりの街は人通りも多い。
ダウトはその間をすいすいと通り抜けていくが、それでも多少のタイムロスは免れない。
大分走ったところで、彼は建物沿いに身体を寄せると足を止めた。
ふと、真上を見上げる。
「上から行こうかな」
彼はそう呟き、片手を空へと掲げた。
すると、彼の手の中に光の糸が一本生まれ、一気に伸び上がった。
伸び上がった糸は建物の屋上に自然と貼り付き、固定される。
とん、とダウトが地を蹴ると、ふわりと浮いた身体はそのまま糸に吸い寄せられるように上空へと舞い上がって行った。
「…おや?」
建物の屋上に舞い降りたダウトは、ふと一点の方向に目を留める。
その視線の先には、宙を舞う天使とその上に乗るAAを模したような人影が見えていた。
「反応を感じていたから何となく予想はついていたが…まさか本当に来ているとはね」
ダウトはくすりと微笑み、糸をしまうとその人影に向かってぴょんぴょんと建物の上を飛び越えて行った。
「…予定変更もあり得るって…お前は毎回そんな感じだよな」
「それがモナのスタイルモナ。時と場合に応じて作戦を変更する。基本モナよ?」
「…お前のは作戦というより、ただの気まぐれだし」
「Fakers」の本部へ向かう道すがら、モナーとモララーはそんなことを話していた。
刻印の能力で背から翼を生やしたモナーの上に、モララーが乗っている格好で、二人は優雅に空の旅を楽しんでいる。
「あまり深みに入りすぎるとヤバいからな。またレモナに怒られるしさ」
「…レモナのことなら心配しなくてもモナが………ん?」
モララーの忠告を笑顔で流していたモナーが、急に会話を止めた。
その様子にモララーも会話を切り、辺りに視線を巡らせる。
「…何が来た?」
「…忌まわしい香具師が現れたモナ」
モナーは吐き捨てるように言って、その名を呼んだ。
「居るのはわかってるモナ。出てくるモナ、『刻印殺し』ダウト・レイジ」
すると、その名に引き寄せられるかのように二人のすぐ近くから声が聞こえた。
「その通り名で呼ばれるのは心外だね。ボクはあまり気に入っていないものだから」
「何を言っているモナ。お前のやっていることは『刻印殺し』以外の何ものでもないモナ」
「そうかな? それはキミ達から見るとそう見えるだけであって、本当はそうじゃないかもしれないじゃないか。
何事も決めつけるのは良くないことだよ、モナー」
モナーはすい、と建物の一角に降り立つと、モララーを下ろして虚空を見上げた。
「隠れんぼが好きなのは昔からモナね。出てくるモナ」
モナーが少し強く言うと、空間の一部に切り取られたようにぽっかりと穴が空いた。
「いや、失敬。この癖は昔からのものでね。なかなか直ってくれないのさ」
切り取られた空間の穴から出てきたダウトは、含み笑いをしながらそう言った。
モナーはさっきからずっと不機嫌そうな顔をしている。
「お前の顔を見ていると落ち着かないモナ。…その様子だと、また目覚めたモナね」
「うん。恐らく『七番目』が覚醒したことにより、ボクが起動したんだろう。
今まで機能していなかった刻印が覚醒を遂げた…これによって、力のバランスが乱れてしまってきているようだからね」
その言葉に対して、モナーはため息をついた。
「毎回、余計なお節介モナ」
「仕方ないさ。これがボクの仕事、ボクの存在意義なんだから。
ボクが消える時があるとするなら…それは『刻印』が全てこの世から消滅した時だろう」
「それだから困るモナよ。お前はいらないけど、刻印が無くなるのは嫌モナからね」
「ははは、残念。…ところで」
ダウトは不敵な笑いを口元に浮かべて、尋ねた。
「『Fakers』へ乗り込むみたいだね?」
「そうモナ。モララーと二人、タカラ君と話をしに行くモナ」
「……そうか。やはりそれは…妹さんの件かな?」
途端、モナーの顔色が変わった。
すぐさま気づいたモララーが、モナーを宥めようと手をかける。
モナーも何かを言いかけたが頷き、勤めて自然に答えた。
「ガナーのことは…もう関係ないモナよ。お前も、本当は今ここで道草食ってる場合じゃないモナ?」
「その通りさ。今回はほんの挨拶。たまたま見かけたものだから」
「…なら、さっさと行けばいいモナ。モナ達も急いでるモナからね」
「そうかい? ならお言葉に甘えて。くれぐれも自分を見失わないように頼むよ」
ダウトはそう言うと、再び空間の中に飛び込んで消えた。
「…はぁ…嫌な香具師と会っちゃったモナ」
「モナー…今のが前に言ってた?」
モナーは静かに頷いて、答える。
「あいつが刻印の力のバランスを保つ者…『刻印殺し』の異名を持つ存在…『ダウト・レイジ』モナ。
刻印のバランスが乱れたり崩れたりした時に現れて、再び均衡を取り戻すために『仕事』をするという謎の存在と言われているモナ。
数年前に刻印の乱れが解消されて眠りについたはずモナけど…」
「…『七番目』の覚醒による起動、と彼は言っていたね。それってやっぱり…」
モララーの言葉に、モナーは頷く。
「『七番目』っていうのは、間違いなくポジ君のことモナ」
「彼はポジ君を狙っているのか…? それとも…」
「今のところはモナにもはっきりしたことは言えないモナ。いずれわかるモナよ。とにかく今はこれからの任務に集中するモナ」
モナーはそう言うと再び翼を広げ、モララーを背に乗せて飛び立った。
だが話を強引に終わらせておきながらも、モナーは心の中で動揺を隠せなかった。
(…あいつが動き出したのは正直マズいモナ。ちょっと対策が必要モナね…)
心の中で舌打ちしつつ、モナーはスピードを上げた。
第6話:「核の中へ」
彼はとても身軽だった。
タンデム自身は走ったりすることが苦手なのだが、ダウトはその身体を借りているにもかかわらず、十分なくらいに素早く動いていた。
ふわりふわりとビルの上を飛んでいくその姿は、まるで舞っているようにも見える。
「あれか」
足を止め、ダウトは地上を見下ろした。
そこはこの大きな街の中でも極めて異端と騒がれる区域。
「しかし、Vip区域とは思わなかったな…さて」
ダウトは片耳をぴんと立てて、気配を探った。
刻印所持者独特の気配が、片耳を通して彼に伝わる。
…その気配は、弱々しいものだった。
「…どうやら、厄介なことになってるみたいだね。彼も」
ため息をついて、彼はコンクリートの床を軽く蹴った。
投げ出された身体は一旦ふわりと宙に浮き、すぐに重力にならって落ち始める。
しかし、彼に焦る様子は微塵もなかった。
すっ、と手を天に向けて差し出すと、手の中から先程の光の糸が伸びて天へと向かう。
伸びた糸は遙か天へと伸びていき、その先端はやがて見えなくなる。
「…モナーの能力、ボクも欲しかったな」
ぽつりとダウトが呟いた途端、物凄いスピードで落ちていた身体が糸に引っ張られるようにして、急に止まった。
どこかに糸が辛うじて引っかかっているかのような不自然さである。
「そうすれば、こんな危なっかしい真似しなくて済むんだけど」
彼の身体は、地面から数センチのところで止まっていた。
あと数秒遅ければ、地に激突してしまい…重傷では済まなかっただろう。
だが彼の顔は人形のように無表情だった。
動揺しているようには見えない。
「…さて、仕事だ」
ダウトは再び地を蹴り、先程の落下速度に負けないくらいのスピードで走り出した。
静まりかえった部屋に、携帯の着信音が鳴り響く。
部屋にはベッドが一つと小さな窓、そして小さな箪笥。
ベッドの中には少女が一人、布団を被って横たわっている。
やがて少女は布団から顔を出し、忌々しそうに携帯を睨み付けると、渋々手に取り通話ボタンを押した。
「…はい? ああ…サドネスか。何か用?」
相手は少女の友人だった。
それほど親しい訳ではないが、元々友人の少ない彼女にとっては数少ない友人の一人だ。
「え? また『Sevence・Sign』の話するの? …面倒臭いなぁ…今、寝てたのに。
…わかった、わかったから…じゃあ、今からそっち行く…うん、また後で…」
電話を切ると、彼女は舌打ちをして布団から出た。
箪笥の上に置かれた小さな鏡を見ながら適当に髪をセットすると、枕元に置かれた帽子をひっ掴み、乱暴に被る。
「あー、もう…満足に寝ることすら許されてないんですか、あたしには…」
ぶつぶつ言っていると、部屋の扉が細く開いた。
「珍しい、じぃ姉が早起きしてるのだ。今日はきっとあられが降るのだ」
「五月蠅いわね、づー。あたしだってこんなに早く起きるつもりはなかったの」
「早く…って、もうお昼とっくに過ぎてるのだ」
じぃは自分と似た容姿を持つ妹を睨み付けた。
だが、その眼差しに真の殺気や嫌悪感は込められていない。
それを見越してか、づーは涼しい顔でその視線を受け流す。
「その様子だと、またサドネスさんに呼ばれたみたいなのだ」
「そうなの、Sevence・Signの話をして欲しいって。ここのところ、毎日よ…」
「よっぽど気に入ってるのだ」
「気に入るのは構わないけど…あまり深入りしないで貰いたいわね」
じぃは立ち上がり、カーテンを開けて窓の外を見た。
外は曇っているせいか、少し薄暗い。
「ぬーは居るの?」
「居るのだ。ぬーちゃんに頼んで、じぃ姉のご飯作って貰ってあるから、食べてから行った方がいいのだ」
「そうね…」
箪笥の引き出しを開け、一丁の小型拳銃を取り出す。
それを右腿のホルスターにしまうと、じぃはづーと共に部屋を出た。
「…今日も、この銃を使わないことを願うばかりね…」
その「核」を見つけるのに、それほど時間はかからなかった。
状況も大体呑み込めた。
あとは、どうやってこの危機を回避するかだ。
ダウトは今にも後頭部に鍵を差し込まれそうになっている青年を見つめて考えた。
「やっぱりこの方法が一番手っ取り早いだろうね」
彼の手からするりと光の糸が伸びる。
伸びた糸は青年の頭によじ登り、そのまま先端を埋め込んだ。
青年の周りにいるAA達は糸に気づいていないようだ。
…見えていないのだろうか。
「…よし、これで接続した。あとは同調すればいい」
ダウトはそう言って両目を閉じた。
すぅ、と深く大きく息を吸い、そのまま身体を停止させる。
肉体から何かが抜けていく感覚。
タンデムがダウトと入れ替わる時に感じていた感覚を、ダウトは感じていた。
瞼の裏には、何かの強い光が輝き続けている。
「そろそろいいかな?」
目を開けると、そこは真っ暗な世界だった。
彼の手から伸びている糸だけが、辺りを照らし出している。
道はなければ地面すらない。
空間にぼんやりと立っているだけだ。
ふと見ると、黒に覆われていた世界が段々とその色を失ってきている。
「さて、彼の意識を塞き止めておこう。彼が封印されてしまっては、意味がないからね」
手の中の糸がふわりと宙に浮き、空間の中を走って止まる。
ぎしりと軋んだ音がして、空間の蠢きが止まった。
それと同時に、すぐ傍に現れた青年の姿。
ダウトは、微かな声で呼びかけた。
「…キミか。とは言っても、キミはボクのことを覚えていないと思うけどね」
やがて青年はむっくりと起きあがり、しばらくぼんやりと虚空を見つめた後、ダウトをまじまじと見つめた。
足下から、光がせり上がるように差してくる。
「…まぁ、そんなことは今のキミにとったらどうでもいいことなのかな」
まるでスポットライトを浴びているかのように、ダウトの身体は光の真下にあった。
真っ暗な空間の中で、唯一彼だけが光の下に立っている。
驚愕の視線を向けられ、少し苦笑いを浮かべながらダウトは挨拶した。
「…とりあえず、久しぶりだね。ポジビリティ君」
「…?!」
あっけに取られたような相手のリアクションに、ダウトはまた苦笑いを浮かべた。
第7話:「時が来るまでは」
気まずくも思える沈黙に似た静寂が、場を包み込む。
やがて、ポジビリティはおずおずと口を開いた。
「貴方は…誰ですか…?」
「ん? それは名前のことかい? 名前なら、一応ダウト・レイジという立派な名前があるよ」
彼の質問にそう答えたダウトは、心の中でため息をついた。
やっぱり…何も覚えていないんだね、と。
「…他に何か聞きたいことは?」
「あ…ええと…ここはどこなんですか…?」
「ここ? ここはキミの意識の深淵だ」
「意識…?」
真っ暗な空間。
ダウトの立っているところ以外、一筋の光すら見えない世界。
それが、彼…ポジビリティの意識だった。
恐らく…意識を封印されかけていることで、この世界が半分消えかかっているのだろう。
世界が真っ暗になってしまったのは、その前兆のようなもの。
しかしすぐに変化は現れ、現に世界は消滅しようとしていた。
それを繋ぎ止めるため、ダウトは糸を走らせたのだ。
「そうだ。今のキミは、大耳の鍵の力によって意識を永遠に封印される途中なんだよ。
本来ならそのままキミは意識の暗闇に溺れて氏んでいくところなんだろうけども、
それは困るから、ボクがキミの沈みかけの意識を一時的に止めた。今が、その『止まっている』状態なんだ」
目の前の彼は、文字通りぽかんとして話を聞いていた。
もしかしたらダウトの話なんて半分近く耳に入っていないかもしれない。
それほど、彼はこの状況を理解するのに苦しんでいた。
「ちょ、ちょっと待って下さいよ。要するに今、僕はビデオでいう一時停止みたいな状態になってるってことですか?」
彼は回らない舌を必死に動かし、尋ねる。
その質問を否定することなく、ダウトはさくさくと話を進めていく。
「うん、まぁ平たく言えばそんな感じだね。とは言っても『一時停止』だから、出来れば早いところキミに決めて貰わないといけないんだ」
「何をですか?」
そんなこと、わかりきっているじゃないか。
ダウトは内心呆れながら、その先を続けた。
「勿論、キミはこの後どうするかだ。このまま暗闇に落ちて氏ぬのがいいならそうする。
ボクとしては困るけど、キミが望むなら仕方のないことだと思って諦める。
でも氏にたくないなら、それなりの対処はしてあげようと思ってるんだが」
正直、こんな質問は彼にとって愚問だろう。
今の彼は…
「氏にたくなんかないですよ!! 何言ってるんですか!!」
以前に比べて、とても強く安定した心を持っているからだ。
それを知っているダウトは、表情を変えぬまま、淡々と相槌を打った。
「…そうか、わかった。でも、これには条件がある」
目の前の彼が一瞬不安そうな表情になって、しかしすぐに表情を戻す。
「何ですか? 僕に出来る範囲のことでなら何でも…」
「なに、別に難しいことじゃないさ。ちょっと、キミに昔のことを見て貰いたいだけだよ」
「昔のこと…?」
彼の望みを叶えるには、彼に味わって貰う必要がある。
数年前、彼の記憶が消される少し前…彼に起こったことを。
「そう…昔の…思い出みたいなものさ。キミにとってはほんの一瞬に過ぎないけどね」
今は、全てを彼に伝えることは出来ない。
その時ではないからだ。
だが、例え信じなくてもいいから…欠片だけでも渡しておきたい。
ダウトはつい、と指を指揮者のように軽く振った。
指にかかる、やや重い感覚。
それに構わず、ダウトは指を振り切る。
ずこん。
彼の指に巻き付いた光の糸に引っ張られて、空間の一部が抜け落ちる。
丸く開いた穴からは、青年が求めていた暖かい光が漏れ出す。
ダウトは青年をその穴へと導くように、手をかざしてみせた。
「今からここで見たことを、忘れるも思い出すもキミ次第だ。じゃあ、また後で」
漏れ出す光が強さを増す。
あっという間にその場を覆い尽くした光は、ポジビリティの姿を瞬時に飲み込み。
「え?! あ、ちょっと!!」
彼の声さえも無視して全てを飲み込んだ光は、やがて収束していった。
再び空間に闇が戻り、佇むのはダウト一人。
先程開けた穴も、今はすっかり無くなっていた。
「…思い出せないのなら、欠片だけでも持っていた方がいい。やがてそれは…キミを導き、道を作り出す光になっていくだろうからね」
何も映らない空を見上げ、彼は呟く。
音を立て軋む空間を再び縛り上げながら。
「さて、『彼女』は上手くやっている頃かな?」
視界に一瞬映っただけだ。
それが確信出来るものとは思えない。
でも、追わずには居られなかった。
「ちょっと! じぃってばどこ行くのよ!」
「知りたいんなら、ついて来ることね!」
後ろで文句を言いながらついて来ている友人に声だけで答えながら、じぃはある人物を追って走っていた。
それは、彼女が仕事で行く先々で何回も出会った、あの「片耳のモナー族」。
(全く…いつ目覚めたっていうのよ…ダウト…!!)
じぃは舌打ちをすると、段々遅れ始めている友人の手を掴んだ。
それと同時に、一気に走るスピードを上げる。
「わわっ、ちょっと…急に引っ張らないでよ!!」
息切れしていたところを急に引っ張られたものだから、彼女の身体はバランスを崩した。
しかしすぐに体勢を立て直し、必死にじぃの速度について行く。
「遅れるのが悪いの!! 詳細は後で話すから、今はとにかく走るわよサドネス!!」
言いながら、じぃは右腿のホルスターからそっと銃を抜いた。
過去を見せられて、動揺しない者などいない。
それは未来を視ることの出来る自分も同じことだ。
先程視た青年の未来は、自分にとっても苦痛な未来だった。
そして、自分は青年の過去も知っている。
「…タンデムはんの未来は絶望に満ちたもの…まるで救いようのないdatの海のようや。
だが…それは過去とて同じ…。ウチは…彼に未来を伝えるべきやったろうか…」
まだ、その時ではない。
そう思ってあの時は躊躇った。
しかし…もう時は動き出してしまっている。
絶望へのカウントダウンは始まっているのだ。
「…せめて…ダウトがあの子の哀しみと苦しみを癒してやれたらいいんやけど…
香具師は不器用やからな…逆にあの子に救われそうな気がしてならんわ…」
のーは、傍らの棚の上に乗っている写真立てを手に取った。
そこに映っているのは、幼い頃の自分とモナー…そして、今は敵地に身を置く友人。
「…ウチはどうしていくべきやろか…ニダやん…」
答えない写真に、のーはぽつりと声を漏らした。
待っていた時間はそれほど長いものではなかった。
強い光が再びその場を覆い、現れたポジビリティ。
彼の顔には、涙の跡が痛々しく貼り付いている。
「少しは思い出して貰えたかな?」
ダウトが問うと、彼は座り込んだまま顔を上げた。
この世に絶望したような、そんな表情で。
掠れた声で、彼は逆に尋ね返す。
「…あれは…何なん…ですか…?」
「あれは、キミの残した過去の一部だ」
「あんな…あんなものが、僕の過去とでも言うんですか?!」
今までになく声を荒げて、彼は問う。
だがダウトは驚く様子もなく、淡々と答えた。
「そうとしか言いようがないんだ、仕方ないだろう」
「嘘だ…僕は認めない!!」
彼は頭を抱え、断固として拒否している。
拒否したいのもわからないではないが…彼にはこの事実を呑んで貰わないといけない。
しかし、今の彼がとてもそんな精神状態でないことは誰の目から見ても明らかだった。
「…まぁ、信じる信じないはキミの自由だ。ボクがどうこう言うことじゃないしね。
さて、約束通り…キミの封印されかかっている意識を外に帰してあげよう」
今はまだ呑み込めなくても仕方ないだろう。
いずれは認めて、受け入れて貰わなければならないけれど。
ダウトは内心でそう思いながら、ポジビリティの意識に神経を集中させ、外界へと浮上させ始める。
その時、ポジビリティが慌てて叫んだ。
「ま、待って下さい!!」
その声に、意識の浮上を一旦止める。
元々細い目をさらに細めて、ダウトは言葉を投げた。
「ん? 何だい?」
「…貴方は、僕の過去を知っているんですか?」
「……」
ダウトの口がほんの少し動きかけて、止まる。
数秒の躊躇いがあった後、彼はややぎごちなく答えた。
「…知っていると言えば嘘になるが、知らないと言っても嘘になるね。
これはボクが元々知っていたものではない。ボクが目覚めた時から既にボクの中にあった。
誰かに、これを持っているように命令されたのかもしれない。でも、それはわからない。
だからボクは、キミにこれを見せたんだ。これはボクの独断でやったことだよ」
畳みかけるように、一気にダウトは言い切った。
勢いに呑まれた目の前の彼が、ぽかんとした顔でこちらを見つめる。
その隙を逃すまいと、ダウトは指を上に向けて動かした。
再び、彼の意識が外界へと昇り始める。
…知られては、ならな